フェルミ推定のやり方と攻略法|評価ポイントと頻出例題を総まとめ
「フェルミ推定のやり方って、どう進めればいいのだろう…」
就活やコンサル面接で頻出するフェルミ推定は、一見すると難しそうに見えますが、論理的な思考プロセスを身につければ誰でも攻略できます。面接の合否に直結することもあるため、早めに慣れておくことが大切です。
そこで本記事では、フェルミ推定の評価ポイントやステップごとの進め方、攻略のコツをわかりやすく解説しつつ、実際に出題された頻出例題や回答例文も紹介します。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。
フェルミ推定とは?就活で頻出する理由と基礎知識

フェルミ推定とは、すぐには答えが分からない問題を論理的に分解し、推測を重ねて答えを導く思考法のことです。
たとえば「東京にあるコンビニの数は?」という問いに対して、人口や利用頻度などを前提として見積もっていきます。
就活の面接でよく出題される理由は、正解を当てる力ではなく、限られた情報をもとに筋道を立てて考える力や、仮定を根拠として相手を納得させる力を測るのに適しているためです。
企業が重視しているのは「正確さ」ではなく「思考の過程」でしょう。そのため答えが多少ずれていても、前提や説明がしっかりしていれば評価されます。
多くの学生は「正解できなければ不合格」と誤解しがちですが、実際は論理の一貫性や伝え方が試されているのです。この点を理解しておけば、不安を減らして落ち着いて取り組めるはずです。
企業がフェルミ推定で見ている4つの評価ポイント

フェルミ推定は単なる計算力を問うものではなく、面接官が「どのように考え、筋道を立てて答えを導くか」を見極めるための課題です。
特にコンサルティングや総合商社のような難関企業では、答えの正確さよりも思考プロセスそのものが評価されるでしょう。
ここでは、企業が注目する4つのポイントを紹介します。
- 仮説思考力
- フレームワーク思考力
- 数値の根拠を示す論理性
- 面接官に伝える説明力
①仮説思考力
フェルミ推定で最初に見られるのは、問いに対して仮説を立てられるかどうかです。細かい計算に入る前に大枠の答えを想定し、それを検証する形で進めることが大切といえます。
仮説を持つことで思考の方向性が定まり、限られた時間でも無駄なく答えに近づけるでしょう。
就活生が陥りがちなのは「正確な数値を出さなければならない」という思い込みです。実際には誤差があっても仮説に基づいた一貫性が評価されます。
例えば「この規模感だと考えるので、おおよそこの程度になる」と示すだけでも説得力があります。仮説を立てる姿勢は柔軟さと問題解決力を伝える有効な手段です。
②フレームワーク思考力
仮説を立てたあとは、それをどう検証するかが問われます。ここで重視されるのがフレームワーク思考力です。
たとえば「人口 × 利用率 × 単価」といった形で要素を分けると、問題を段階的に整理できます。体系立てた進め方は面接官に安心感を与えるはずです。
ただし、型にはめるだけでは十分ではありません。重要なのは、問いに応じた切り口を選べる柔軟さです。例えば「コンビニ市場の規模」を推定するときに、店舗数から考えるのか、利用者数から計算するのかです。
その選択理由を論理的に語ることで、戦略的な思考力を示すことができるでしょう。
③数値の根拠を示す論理性
フェルミ推定で扱う数値には、根拠が求められます。理由なく置いた数字では説得力がなく、評価も下がってしまいます。そこで重要なのが日常的な知識や常識をもとにした推定です。
例えば「日本の世帯数」を推測するなら、人口を約1億2,000万人と置き、1世帯を平均3人と仮定すれば約4,000万世帯と導けます。
このように手順と背景を明確に説明すれば、多少の誤差があっても論理的な答えとして受け止められるでしょう。
感覚的に数字を決めてしまうのではなく、必ず「なぜそう考えるのか」を添えることが信頼につながります。
④面接官に伝える説明力
思考の質が高くても、相手に伝わらなければ意味がありません。フェルミ推定は面接の場で出題されるため、短い時間でわかりやすく説明する力が評価されます。
特に大切なのは、考えた手順を声に出して伝えることです。頭の中で計算していても、相手には見えません。
結論を先に述べ、そのあとに根拠や手順を説明するPREP法を意識すると理解されやすいでしょう。説明力はすぐに身につくものではないため、普段から人に話す練習を積み重ねておくことが効果的です。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
フェルミ推定のやり方をステップ別に解説

フェルミ推定は、限られた情報から論理的に数値を導き出す思考法です。就活の面接やケース面接で頻繁に出題されるため、やり方を具体的に理解しておくことが重要でしょう。
ここでは、ステップごとに流れを整理し、実際に活用できる形で解説します。
- 前提条件の確認
- アプローチ方法の設定
- モデル化による構造化
- 数値の代入と計算
- 解答の評価と検証
①前提条件の確認
フェルミ推定では、最初に前提条件を明確にすることが成功の第一歩です。与えられる情報が限られているため、出発点があいまいだと途中で計算が崩れてしまいます。
例えば「日本にあるコンビニの数」を推定する場合、対象を大手3社に絞るのか、小規模店舗まで含めるのかで結果は大きく変わるでしょう。
ここで曖昧さを残さないことが、面接官に対して論理的な思考力を示すポイントです。また、前提条件を言葉にして面接官に共有することは、自分の思考の透明性を高める効果もあります。
例えば「全国規模で展開している企業のみを対象とします」と伝えれば、前提が共有され、結果の数値にズレが生じても納得してもらいやすくなります。
条件を確認せずに進めると、答えが現実からかけ離れ、説得力を失うだけでなく、論理性に欠ける印象も与えてしまうでしょう。
問題を受け取ったら、まず「範囲」「単位」「対象」を定義し、整理したうえで次に進むことが必須といえます。
②アプローチ方法の設定
前提条件を確認したあとは、解法の方向性を決める必要があります。大きく分けると、大きな数値から割り算していく「トップダウン型」と小さな要素を積み上げて全体を導く「ボトムアップ型」があります。
例えば「東京にある美容室の数」を推定する場合、人口を基準に1店舗あたりの顧客数から割り出すのはトップダウン型、地域ごとの店舗数を積み上げるのはボトムアップ型です。
どちらを選んでも構いませんが、アプローチ方法の選び方によって答えの精度や説得力が変わるため、注意が必要です。トップダウンは短時間で答えにたどり着けますが、仮定がずれると全体に大きな誤差が出やすい傾向があります。
一方でボトムアップは情報を細かく分解するため現実に近づきやすい反面、要素を拾い漏らすと結果が小さく出すぎる危険もあるでしょう。
就活の場面では、限られた時間で筋道を示すことが求められるため、2つの方法を柔軟に組み合わせるのも有効です。
③モデル化による構造化
アプローチ方法が決まったら、次はモデル化を通じて問題を整理します。モデル化とは、複雑な現象を単純な数式やフレームに置き換える作業です。
例えば「駅を利用する人の数」を推定する場合、通勤客・学生・観光客に分けて考えると現実に近づきます。構造を整理することで、面接官に「問題を分解する力」を示せるのが強みです。
さらに、モデル化には「抜け漏れを防ぐ」役割もあります。問題をいくつかの要素に分けることで、思考が一本道に偏らず、多角的な検討が可能になります。
例えば「レストランの年間売上」を推定するとき、座席数×回転率×客単価という形に分けると、計算の根拠が明確になり、面接官に納得感を与えられるでしょう。
このように、現実の状況を適切に抽象化してモデルに落とし込むことで、論理性と再現性を両立できます。構造化を怠れば、場当たり的な推定に見えてしまい、評価を下げかねません。
④数値の代入と計算
モデルが完成したら、次に数値を代入して計算を進めます。このときは必ず根拠を添えることが大切です。
例えば「日本の人口は1億2000万人」といった基本情報や、「都市部の世帯あたり平均人数は2.3人」といった統計的知識を使うと説得力が増します。計算の際には数値を丸めて扱うとシンプルでしょう。
また、数値を選ぶときには「なぜその値を採用したのか」を必ず説明してください。面接官は結果よりもプロセスを見ているため、根拠があれば多少の誤差は問題視されません。
途中で迷った場合は「仮にこの値を用いると…」と前置きし、常識的な範囲に収まるよう調整する姿勢を見せましょう。
プロセスを軽視すると答えが極端にずれ、信頼性を失うリスクがありますが、筋道を示せば納得感を持たせられるのです。
⑤解答の評価と検証
最後に必要なのは、導き出した答えの評価と検証です。計算結果が現実感を持っているかを常識と照らし合わせて確認しましょう。
例えば「日本のコンビニの数」を計算して30万店となった場合、実際は約5万店であるため違和感に気づけます。そのうえで「対象範囲を広く取りすぎた」といった修正点を述べると、柔軟な思考力を示せます。
さらに重要なのは、検証の姿勢を相手に示すことです。誤差を認めつつ改善点を提示できれば、論理的かつ実務的な思考力が評価されます。
例えば「都市部と地方を区別しなかったため差が出た」と指摘すれば、単なる計算者ではなく問題解決志向を持つ人物として印象づけられるでしょう。
就活では正解を出すことよりも、仮説を立てて検証し、改善策を提示できることが重視されます。この最終ステップを踏むことで、数値だけでなく姿勢そのものが高く評価されるはずです。
フェルミ推定を攻略するためのコツ

就活の面接やケース面接で出題されるフェルミ推定は、正解を出すことよりも「論理的に考える姿勢」が評価されます。
しかし初めて取り組むと、何から手をつけていいのか迷う学生も多いでしょう。
ここでは、フェルミ推定を効率的に解くための実践的なコツと注意点を紹介します。
- 日本や世界の基礎知識の活用
- 要素分解
- MECEの意識
- 概算によるシンプルな計算
- 制限時間と時間配分の工夫
- 完璧を求めず論理性を重視する姿勢
①日本や世界の基礎知識の活用
フェルミ推定では、基礎知識をどれだけ持っているかで考え方の幅が大きく変わります。人口や世帯数、都市の規模などを知っていれば、計算の出発点を現実に近い形で設定できるからです。
例えば「日本の人口は約1億2000万人」「東京都は約1400万人」と把握しておけば、曖昧な想像に頼らず答えを導けます。
さらに知識の幅が広いほど、問題に応じて適切な切り口を選びやすくなるのです。「世帯あたりの人数」「平均寿命」「主要都市の割合」といった情報を知っておくと、さまざまな推定に応用できるでしょう。
知識が不足していると、極端に現実離れした答えになりやすいため、信頼性も下がってしまいます。
事前に総務省の統計や経済白書などを見ておくと、基礎的な数値が自然に頭に入り、面接本番でも落ち着いて推定できます。暗記するより「大まかな数値の感覚」を持つことを意識すると効果的です。
②要素分解
複雑に思える問いでも、要素に分けて考えることで解きやすくなります。
例えば「日本にあるコンビニの数」を推定するなら、「人口あたりの店舗数」「都市部と地方の違い」「大手チェーンのシェア」と分けると、無理のない形で計算できます。
要素分解の利点は、答えがぶれにくくなることです。大きな問題をそのまま扱うと精度が落ちますが、小さな要素に分ければ精度が上がります。
また、分けた要素ごとに「どの情報を使うか」を選択できるため、考えの道筋を相手に分かりやすく説明できるのもメリットです。
ただし細かく分けすぎると混乱するため、適度なレベルで整理することが重要です。例えば「地域別」や「業種別」といった大きな単位で考え、計算の流れを保つようにしてください。
③MECEの意識
MECEとは「漏れなく、重複なく」を意味し、フェルミ推定では特に役立つ考え方です。論理を整理する枠組みを持つことで、答えを導く過程が明快になり、面接官からも評価されやすくなります。
例えば「飲食店の売上」を推定する場合、「客数×客単価」と分解するのはシンプルでMECEな考え方です。これなら重複も漏れもなく、誰が見ても納得しやすい構造になります。
一方で「客層×時間帯×メニュー別売上」と細かく切り分けると、重複や抜けが出やすく、論理が不安定になる危険があるのです。
MECEを意識すると「答えに至る思考の筋道」が整うため、答えが多少ずれても説得力が増します。また、話しながら解答する場面では、聞き手にわかりやすく伝えられることも大きな強みです。
日常生活でもニュースや身近な出来事を「MECEで考える」習慣を持つと、練習効果が高まるでしょう。
④概算によるシンプルな計算
フェルミ推定で重視されるのは正確さではなく、妥当性や合理性のため、細かい数字を追うよりも、概算でシンプルに進める方が有効です。
例えば「1人が年間に使うボールペンの数」を求めるとき、正確なデータは不要で「平均2〜3本」と仮定すれば十分でしょう。
概算を使うことで、時間の節約にもなります。限られた時間内に答えを導く必要があるため、細部にとらわれると全体をまとめる余裕がなくなるのです。
また「ざっくりと仮定します」と前置きすれば、相手に論理的に考えていることが伝わりますし、さらに概算を組み合わせることで、大きな誤差を避けつつも現実に近い推定が可能になります。
大事なのは「この数字なら不自然ではない」と面接官が納得できる根拠を示すことです。潔く大枠を捉える姿勢が、評価につながるでしょう。
⑤制限時間と時間配分の工夫
面接でのフェルミ推定は、多くの場合5〜10分程度しかありません。この時間内で問題の理解から計算、結論までを終えるには、あらかじめ時間配分を意識して練習する必要があります。
最初の2分を前提条件の整理に使い、次の3分で要素分解と計算を進め、最後の数分で結論をまとめる流れにするとバランスが良いでしょう。
途中で迷ったときも、全体を完了させることを優先すれば、論理が途切れずに済みます。
また、声に出して考えを伝えることも重要です。面接官は思考の透明性を見ているため、過程を説明しながら進めることで評価されやすくなります。
普段からストップウォッチを使って練習すれば、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。実戦的な練習が自信につながります。
⑥完璧を求めず論理性を重視する姿勢
企業が見ているのは正確さよりも「論理的に考えたかどうか」です。そのため、完璧を求めると、時間切れや説明不足につながるリスクがあります。
大切なのは、自分なりに仮定を置き、その前提で合理的に推論することです。たとえ結論が実際の数値と外れていても、過程が一貫していれば評価は十分に得られます。
特に「どういう仮定を置き、なぜそう考えたのか」を説明することで、論理性が伝わりやすくなるでしょう。
完璧主義ではなく、論理的な一貫性を意識してください。面接官は「数字の正解」よりも「筋道のある思考プロセス」に注目しています。
結論が多少違っていても、誠実に過程を説明できれば大きな武器になるはずです。
よくあるフェルミ推定の例題と回答例文

フェルミ推定の実際の使い方を理解するには、具体的な例題を見ることが最も効果的です。
ここでは、日常的なテーマから面接で頻出する内容まで幅広く取り上げて、紹介します。思考プロセスの流れを確認しましょう。
市場規模の推定例と回答例文
ここでは、日常的なサービスを題材にしながら、市場規模を推定する流れを紹介します。フェルミ推定は一見難しそうに見えますが、身近なテーマを使うことで誰でも取り組みやすくなります。
特に大学生が普段利用するようなお店やサービスを題材にすると、数字の根拠を自分の経験から導けるため、理解が深まりやすくなります。
以下に実際の問題例とその回答例を示しますので、考え方の流れをイメージしてみてください。
| 《問題例》 あなたの街にあるカフェ全体の月間売上を推定してください。 《回答例》 まず、駅前から大学までの道にあるカフェを数えると、ざっと20店舗ほどあります。そこから、1店舗あたり1日の来客数を平均100人と仮定しました。 1人あたりの平均利用額を500円とすると、1日の売上は5万円。これを20店舗にかけると100万円になります。さらに、月30日営業するとして3000万円程度が街全体の月間売上になると見積もれます。 |
この例では「店舗数×来客数×客単価」のシンプルな掛け算で市場規模を算出しています。
同じテーマを書くときは、前提条件を明確に示し、数字の根拠をできるだけ身近な体験に結びつけると読者に伝わりやすくなります。
人口や世帯数を利用した例と回答例文
ここでは、街の人口や世帯数を手がかりにして規模を推定する流れを紹介します。普段の生活で目にする数字をもとに考えると、難しそうに思えるフェルミ推定も取り組みやすくなります。
大学生でも自分の住んでいる地域を題材にして練習できるため、実感を持ちながら学べる点が大きな特徴です。
| 《問題例》 あなたの街にあるコンビニ全体の1日の利用者数を推定してください。 《回答例》 まず、この街の人口を10万人と仮定しました。次に、1世帯あたり3人暮らしだとすると、約3万3千世帯になります。そのうち半分の世帯が1日に1回はコンビニを利用すると考えると、1万6千世帯です。 さらに、1回の利用で平均2人が訪れると仮定すると、1日の利用者数はおよそ3万2千人と推定できます。 |
この例では「人口→世帯数→利用割合→人数」という流れで段階的に推定しています。
同じテーマで書くときは、推定の根拠となる前提を小さなステップに分け、誰が見ても納得できる数値の組み立て方を意識しましょう。
売上や消費量の推定例と回答例文
ここでは、日常生活でよく目にする商品の売上や消費量を推定する流れを紹介します。身近な題材を選ぶことで、フェルミ推定の考え方を自然に理解でき、数値を組み立てる練習にもなります。
大学生の日常の中でも「これってどのくらい売れているのだろう?」と感じる場面をきっかけにすると、推定の面白さを実感しやすいです。
| 《問題例》 大学の購買で売られているペットボトル飲料の1か月あたりの売上本数を推定してください。 《回答例》 まず、購買に来る学生は1日でだいたい2000人と仮定しました。そのうち3割の学生が飲み物を買うとすると600人です。 1人が1本ずつ購入すると、1日あたり600本が売れる計算になります。さらに1か月を20日営業日とすると、600本×20日で1万2000本が売れると推定できます。 |
この例では「来店人数×購入率×本数」という流れで計算しています。同じテーマを書くときは、来店者数や購入割合などを自分の体験から導き、根拠を明確に示すと信頼性が高まります。
実際の面接で頻出する例題と回答例文
ここでは、就職活動の面接でよく出されるフェルミ推定の問題を取り上げます。実際の面接では、正確な数値よりも論理的な思考の流れが重視されます。
大学生であれば一度は体験する場面を想定しておくことで、本番でも落ち着いて答えやすくなります。
| 《問題例》 日本国内にあるピアノの台数を推定してください。 《回答例》 私はまず日本の人口を1億2千万人と仮定しました。次に、1世帯あたりの平均人数を3人とすると、約4000万世帯です。そのうち、音楽に関心がありピアノを所有している世帯は全体の1割程度と考えました。 すると400万世帯がピアノを持っている計算になります。さらに学校や音楽教室などの施設にもピアノがあると仮定し、追加で100万台ほどを加えると、日本全体でおよそ500万台と推定できると考えました。 |
この例では「人口→世帯数→所有割合→施設分加算」という流れで推定しています。同じテーマを書くときは、段階的に前提を置き、面接官にわかりやすく伝えることを意識しましょう。
実際の選考で出題されたフェルミ推定の問題例と回答例文5選

実際の選考ではどのようなフェルミ推定が出題されるのか気になる方も多いはずです。
ここでは、企業ごとの出題傾向や回答例を取り上げ、面接対策に役立てられるように整理しました。
コンサルティングファームの出題例と回答例文
ここでは、実際にコンサルティングファームで出題されやすいフェルミ推定の問題を取り上げます。
難しく感じるかもしれませんが、身近な前提を組み合わせることで論理的に答えられることを理解していただけるはずです。
| 《問題例》 日本国内にあるガソリンスタンドの数を推定してください。 《回答例》 私はまず日本の人口を1億2千万人と仮定しました。次に、1世帯あたりの平均人数を3人とすると、約4000万世帯になります。 そのうち、車を所有している世帯は全体の6割程度と考え、約2400万世帯が対象となります。 1つのガソリンスタンドが平均2000世帯をカバーしていると仮定すると、2400万世帯÷2000で約1万2000か所という推定値を出すことができました。 |
この例では「人口→世帯数→車の所有率→カバー世帯数」という流れで分解しています。同じテーマを書くときは、前提条件を段階的に示し、推定に至る思考の筋道を丁寧に伝えることが重要です。
総合系ファームの出題例と回答例文
ここでは、幅広い業界を担当する総合系ファームでよく出題されるフェルミ推定の問題を紹介します。普段の生活に関連するテーマをもとに考えると、面接の場面でも落ち着いて答えることができます。
| 《問題例》 日本国内で1年間に消費されるカップラーメンの数を推定してください。 《回答例》 まず、日本の人口を1億2千万人と仮定しました。そのうち、月に1回カップラーメンを食べる人は半分の6000万人と考えました。すると1か月で6000万食になります。 これを12か月に換算すると、年間で7億2000万食という数字が出せます。さらに、学生や一人暮らし世帯がもう少し多く食べると考えると、実際には年間10億食前後と推定できると考えました。 |
この例では「人口→食べる人の割合→頻度」というシンプルな流れで推定しています。同じテーマを書くときは、生活習慣に基づいた前提を置くことで説得力を高められます。
外資系企業の出題例と回答例文
ここでは、外資系企業の面接で出題されやすいフェルミ推定の問題を紹介します。
グローバル企業ではユニークな視点や大胆な仮定が求められることも多く、普段から幅広いテーマで練習しておくことが大切です。
| 《問題例》 日本国内にあるスマートフォンの台数を推定してください。 《回答例》 私はまず日本の人口を1億2千万人と仮定しました。そのうちスマートフォンを持つ割合は8割程度と考え、約1億人が利用していると推定しました。 さらに、一人が2台持っている場合もあると考え、平均保有数を1.2台と仮定しました。すると1億人×1.2台で、全国にはおよそ1億2千万台のスマートフォンが存在すると答えました。 この推定は普段大学の周りで友人が複数台を使っている様子を見た体験から発想しました。 |
この例では「人口→利用率→平均保有数」という段階的な流れで計算しています。同じテーマを書くときは、身近な観察を取り入れることで推定の説得力を高めることができます。
日系大手企業の出題例と回答例文
ここでは、日系大手企業の面接でよく出題されるフェルミ推定の問題を紹介します。普段の生活に結びつけて考えることができるテーマが多く、論理的な思考力と実行力を試される傾向があります。
| 《問題例》 日本国内で1年間に消費される卵の数を推定してください。 《回答例》 まず、日本の人口を1億2千万人と仮定しました。1人が1週間に平均2個食べると考えると、年間で約100個になります。これを人口にかけると、1億2千万人×100個でおよそ120億個となります。 さらに、家庭以外でも飲食店や給食などで使われることを考慮し、2割ほど上乗せすると、年間で約144億個が消費されると推定できます。 |
この例では「人口→1人あたりの年間消費量→外食分加算」という流れで組み立てています。同じテーマを書くときは、家庭と外食の両方を意識して数字を組み合わせると、より現実味のある推定になります。
ケース面接との関連例題と回答例文
ここでは、ケース面接でよく出題されるフェルミ推定の問題を紹介します。実際のビジネス課題に近いテーマが多く、論理的な考え方を問われる点が特徴です。
事前に練習しておくことで、本番でも安心して取り組めるようになります。
| 《問題例》 東京ディズニーランドの1日の来場者数を推定してください。 《回答例》 まず、ディズニーランドの年間来場者数を3000万人と仮定しました。次に、年間営業日数をおよそ300日とすると、1日あたりの平均来場者数は10万人となります。 さらに、土日や長期休暇は混雑しやすく平日の2倍近く入場すると考え、休日は15万人、平日は7万人程度と補足しました。このように条件を分けて考えることで、現実的な推定値を出せると考えました。 |
この例では「年間来場者数→営業日数→平日・休日の差」という流れで分解しています。同じテーマを書くときは、平均値だけでなく条件ごとの違いを考慮すると説得力が増します。
フェルミ推定に関するよくある質問(Q&A)

就活生がフェルミ推定について調べるとき、多くの人が「初心者でもできるのか」「どんな数値を覚えるべきか」「スピードと正確性はどちらが重要か」などの疑問を持っています。
ここでは、よくある質問とその回答を整理し、安心して準備を進められるように解説します。
- 初心者でもフェルミ推定は解けるのか?
- どんな基礎数値を暗記しておくべきか?
- 計算に自信がない場合はどう対応すべきか?
- 解答を面接官にわかりやすく説明するにはどうすればよいか?
- ケース面接とフェルミ推定は何が違うのか?
- 正確性とスピードはどちらを重視すべきか?
- 独学で練習するにはどんな方法があるのか?
- 受験生が陥りやすい失敗は何か?
①初心者でもフェルミ推定は解けるのか?
多くの学生が「数学が得意でなければ難しいのでは」と心配しますが、その必要はありません。初心者でも十分対応できるので安心してください。
フェルミ推定で重要なのは正しい答えではなく、論理的な考え方と筋道を立てた説明です。
たとえば「東京にあるコンビニの数」を推定する場合も、人口や生活圏の広さから段階的に考えれば誰でも答えに近づけます。
つまり、必要なのは特別な知識ではなく、常識をもとに組み立てる力でしょう。
②どんな基礎数値を暗記しておくべきか?
フェルミ推定は「基準となる数値」を知っているとスムーズに進みます。代表的なものは、日本の人口約1億2000万、東京の人口約1400万、成人男性の平均体重60キロなどです。
これらは計算の出発点になり、暗記しておけば解答の精度が上がります。完璧に覚えなくても、おおよその数を押さえていれば十分でしょう。そこから合理的に近似する力を見せれば評価されやすくなります。
③計算に自信がない場合はどう対応すべきか?
フェルミ推定で問われるのは正確な計算力ではなく、筋道の立った考え方です。暗算に自信がなくても、紙に書き出して整理すれば問題ありません。大切なのは概算で大きく外れないことです。
誤差が多少あっても論理がしっかりしていれば評価は下がらないでしょう。むしろ、計算を簡単にする工夫を見せることで、柔軟な思考力が伝わります。計算力よりも工夫する姿勢が重視されます。
④解答を面接官にわかりやすく説明するにはどうすればよいか?
解答の伝え方で意識したいのは「結論から述べる」ことです。まず推定した数値を提示し、その後に根拠を順序立てて説明しましょう。加えて、数値の理由を短く添えると説得力が増します。
たとえば「日本の人口は約1億2000万なので、東京の人口はその1割の1200万と仮定しました」と説明すると理解されやすいです。順序立てた話し方を意識することが評価につながります。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
⑤ケース面接とフェルミ推定は何が違うのか?
ケース面接はビジネス課題全般を扱う広い試験で、フェルミ推定はその中の「数値を使った推定」に特化しています。
ケース面接では市場規模や戦略の立案など幅広い思考が必要ですが、フェルミ推定では限られた情報から合理的に数を出す力が問われます。
位置づけとしてはフェルミ推定がケース面接の一部であることが多く、数値感覚を磨く練習に最適です。両者の違いを知っておくと安心でしょう。
⑥正確性とスピードはどちらを重視すべきか?
面接で見られるのは「考え方の筋道」です。多少時間がかかっても論理が明確なら評価は高いでしょう。ただし、面接は時間制限があるため、スピードも無視できません。
最適なのは「正確さ7割、スピード3割」を意識することです。大まかな精度を保ちつつ、簡潔に説明する練習を重ねることで両立が可能になります。
⑦独学で練習するにはどんな方法があるのか?
独学で取り組むなら、日常の疑問を数値化してみるのが効果的です。たとえば「大学の食堂で1日に使われるお椀の数」などを推定すると、自然に数値感覚が鍛えられます。
また、市販のケース問題集やネット上の例題を活用して繰り返し練習するのもおすすめです。さらに、他人に解答を説明する練習をすると、本番での表現力も磨かれるでしょう。
⑧受験生が陥りやすい失敗は何か?
よくある失敗は「数字にこだわりすぎる」ことです。正確さを求めすぎて時間を費やすと、論理の流れが伝わらなくなります。また、根拠を省いて数字だけを並べるのも評価が下がる原因です。
面接官は「なぜその数値を仮定したのか」を重視しているため、前提の根拠を簡潔に示す必要があります。数字に振り回されず「考え方」を大切にすれば失敗を防げるでしょう。
着実なステップでフェルミ推定を攻略しよう
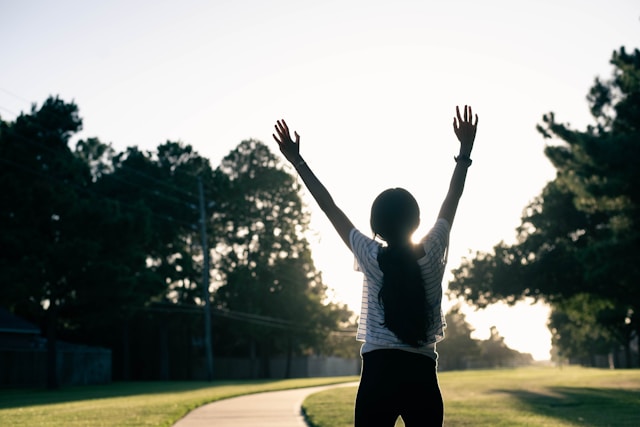
フェルミ推定は就活で頻出する課題ですが、論理的に進めれば誰でも対応できます。結論として重要なのは、完璧な正解ではなく「仮説を立てて構造的に説明できるか」という点です。
その理由は、企業が重視するのは数値の正しさよりも、前提条件の整理、要素分解、そして筋道の通った思考プロセスだからです。
実際、前提を明確にし、シンプルな計算で概算を導き、制限時間内に論理的な説明ができれば十分評価につながります。
したがって、基礎知識を活用しつつ、練習を通じて思考を言語化する習慣をつけることが、フェルミ推定攻略の最短ルートといえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













