履歴書の「卒業見込み」とは?正しい意味と書き方を解説
就職活動で履歴書を書くときに、「卒業見込み」とどう書けばいいのか迷った経験はありませんか?
「在学中」や「卒業予定」との違いがよく分からず、どれを使えば正しいのか不安になる方も多いでしょう。
特に就活では正しい記載が求められるため、表現の使い分けを理解しておくことが大切です。
この記事では、「卒業見込み」の意味や他の表記との違い、履歴書での正しい書き方、証明書の種類や注意点までわかりやすく解説します。迷わず履歴書が書けるように、一緒に確認していきましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
卒業見込みの意味は?

卒業見込みとは、大学や専門学校などで必要な単位を修得し、卒業要件を満たす見通しが立っている状態を指します。
採用担当者は「まだ学生なのか」「卒業は確実なのか」という点を重視するため、表現を誤ると誤解を招きかねません。例えば「卒業予定」と書くと、学校が正式に保証しているニュアンスに近くなります。
一方で「在学中」と記すと、卒業できるかどうか不透明な印象を与えてしまうのです。そのため、履歴書に「卒業見込み」と記入することは、自分の立場を正しく示すうえで大切な要素になりますよ。
履歴書の学歴欄における「卒業見込み」「在学中」「卒業予定」の違い
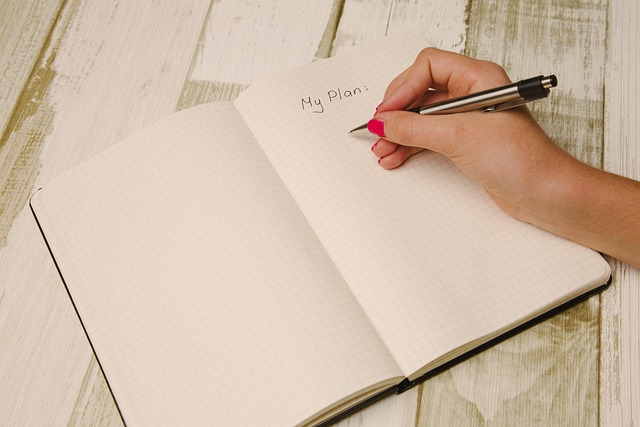
履歴書を作成するときに迷いやすいのが「卒業見込み」「在学中」「卒業予定」の使い分けです。どれも似たように見えますが、実際には意味が異なり、書き方を間違えると誤解を招く恐れがあります。
採用担当者に正確な状況を伝えるために、それぞれの違いを理解しておきましょう。
- 卒業見込み
- 在学中
- 卒業予定
①卒業見込み
「卒業見込み」は、卒業に必須な単位をすでに修得している、または履修計画上確実に取得できる状態を示します。新卒の就活生がもっとも多く用いる表現で、採用担当者に安心感を与えやすい言葉です。
まだすべての単位を取り終えていなくても、カリキュラムどおりに進めば卒業できると判断できる場合は問題なく記載できます。
ただし、要件を満たしていないのに「卒業見込み」と記すのは不適切で、信頼を損なう原因になります。
大学が発行する「卒業見込み証明書」を確認しておけば、事実に基づいた正しい記載ができ、安心して提出できるでしょう。
②在学中
「在学中」とは、学校に所属しているが卒業要件をまだ満たしていない段階を意味します。大学2年生や3年生でインターンや早期の採用選考を受ける場合によく使われます。
4年生であっても、必要な単位を修得しきれていない場合は「在学中」と表記する方が正確です。この点を理解せずに「卒業見込み」と書いてしまうと、後の面接で事実との矛盾が生じる恐れがあります。
「在学中」と記載しても、それ自体がマイナス評価になるわけではありません。むしろ正直に書いたうえで、卒業に向けてどう取り組んでいるかを説明すれば、誠実さを評価される場合もあります。
状況を正しく伝える姿勢が、信頼につながります。
③卒業予定
「卒業予定」は、卒業に必須な単位を取得し、卒業が確定している状態を指します。卒業式を待つだけという段階で使う表現です。
一般的な新卒採用で用いることは少ないですが、大学院への進学や社会人経験を経た人が再び進学し、その後転職活動を行う場合などに使用されます。
「卒業見込み」との違いは、条件を満たしているかどうかにあります。「卒業見込み」は卒業要件を満たす見通しがある状態、「卒業予定」はすでに要件を達成している状態です。
履歴書にこの言葉を記載するときは、大学から正式な確認を受けていることが前提になります。不確定な段階で使うと誤解を招くため、状況に応じて慎重に表現を選んでください。
履歴書に「卒業見込み」と記入するために必要な条件

ただ単に在学しているだけでは、卒業見込みの条件には当てはまりません。採用担当者に信頼してもらうためには、以下の4つの条件を満たしていることが重要です。
- 最終学年であること
- 卒業要件となる単位を修得済み、または取得できる見込みがあること
- 休学や留年の予定がないこと
- 入社時点で確実に卒業していることが保証されていること
①最終学年であること
「卒業見込み」と書けるのは、大学や専門学校の最終学年に進級している人に限られます。
3年生以前では、卒業に必要な要件や研究、実習の進捗が不確かであるため、信頼性に欠ける印象を与えるかもしれません。
それに対し、4年生になっていれば、卒業に向けた準備状況がはっきりしているため、納得感をもって「卒業見込み」と記せます。
履歴書の学歴欄は企業が最初に目にする部分だからこそ、学年に応じた正確な表記が信頼につながります。
②卒業に必要な単位の修得または見込みがあること
「卒業見込み」と書くには、単位の取得状況が鍵となります。必修科目が多く残っていたり、再履修が必要な教科があると不安材料となります。
その点、卒業までの単位取得が明確に見通せる状況なら、「卒業見込み」と表記して差し支えないでしょう。
就活前には、履修状況を整理し、卒業に必要な要件をクリアできるかどうかを確認しておくと安心です。背後に根拠がある表現だからこそ、採用担当者にも誠実さが伝わります。
③休学や留年の予定がないこと
「卒業見込み」と表記するには、入社予定時までに在籍が安定していることも重要です。休学や留年の可能性がある場合、採用担当者からは「入社時期に影響が出るかも」と不安を抱かれる恐れがあります。
たとえ状況に不安があったとしても、それを隠して「卒業見込み」と記すより、「在学中」と明記しておく方が誠実さが伝わる場合も。
信頼を築くには、むしろ未確定な要素は正直に示す姿勢が評価されることもあります。
④入社時に卒業していることが確実であること
最も重要なのは、入社時点で確実に卒業していることです。
多くの企業は卒業証明書や卒業見込証明書の提出を求めるため、卒業が保証されていない段階で「卒業見込み」と書くと、後にトラブルになる恐れがあります。
卒論や試験の結果が未定でも、大学側から「卒業要件は満たしている」との確認が取れていれば、記載してかまいません。しかし、まだ要件に不安がある状態であれば、「卒業見込み」は避けた方が安心です。
履歴書に書くのは、採用担当者が安心して目を通せる内容であることが前提です。
履歴書の「卒業見込み」の書き方
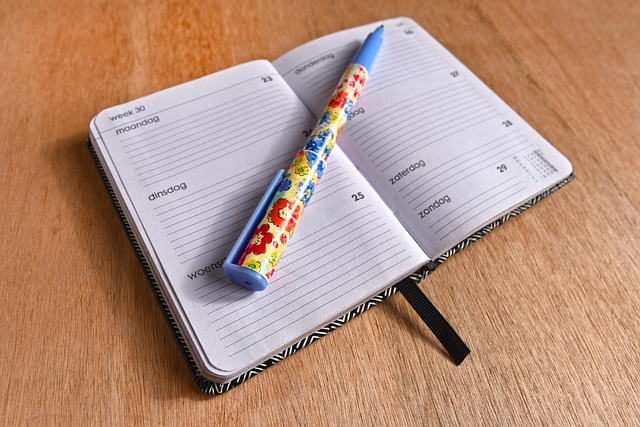
就職活動で履歴書を書くとき、「卒業見込み」の記載は避けて通れません。正しく書けなければ不信感を与え、選考に不利になることもあります。
ここでは、卒業見込みを記載するときの基本的なルールと注意点を整理しました。
- 卒業見込みの日付は卒業予定年月を書く
- 「卒業見込み」と正しく表記する
- 卒業見込みは学歴欄の最終行に記入する
- 学校名・学部・学科は略さず正式名称で書く
- 大学院の場合は「修了見込み」と記入する
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①卒業見込みの日付は卒業予定年月を書く
履歴書の学歴欄には、必ず卒業予定の年月を入れましょう。例えば「2026年3月 卒業見込み」と書くのが正しい形式です。
「卒業見込み」とだけ記すと卒業時期がわからず、採用担当者に不安を与えてしまいます。年月を明示することで、入社時期との整合性を確認しやすくなります。
特に新卒採用では4月入社が前提となることが多いため、年月を正しく記載することは欠かせません。また、卒業予定年月を記載することで、自分自身も学業の進捗を客観的に整理できます。
履修漏れや単位不足の有無を再確認する良い機会になるでしょう。企業に正確さを示すだけでなく、自身の計画管理の意味でも卒業予定年月は必ず記しておくべきです。
細部まで配慮した記載は、履歴書全体の信頼性を高めます。
②「卒業見込み」と正しく表記する
履歴書に書くときは、必ず「卒業見込み」と正しい言葉を選んでください。「卒業予定」と混同して使う人もいますが、意味は異なります。
「卒業見込み」は卒業要件を満たせる見通しがある状態を指し、「卒業予定」はすでに卒業が確定している場合に用いられる表現です。この違いを理解せずに誤記すると、面接で説明に困る可能性があります。
履歴書は公式な書類であるため、言葉の使い方ひとつが信頼性に直結します。省略や自己流の表現は避け、大学や公的機関で使われている表記を参考にしてください。
正しい言葉を使うことで誠実さが伝わり、採用担当者に安心してもらえるでしょう。小さな違いでも軽視せず、正確に「卒業見込み」と書くことが大切です。
③卒業見込みは学歴欄の最終行に記入する
「卒業見込み」は必ず学歴欄の最後に書きます。最終行に記すことで、応募者の現在の状況が一目で理解できるからです。
例えば「2022年4月 ○○大学△△学部◇◇学科 入学」と記載し、最後に「2026年3月 ○○大学△△学部◇◇学科 卒業見込み」とまとめるのが正しい書き方です。
途中の行に記入してしまうと学歴の流れが不自然になり、読みにくい履歴書になってしまいます。
採用担当者は数多くの履歴書を短時間で確認するため、情報が整理されているかどうかは重要な評価ポイントです。最終行に記載するだけで履歴書全体が見やすく整い、信頼感も高まります。
読みやすさと正確さを兼ね備えることが、選考での印象を良くする近道です。
④学校名・学部・学科は略さず正式名称で書く
履歴書では、学校名や学部・学科を略さずに正式名称で書くことが必要です。「○○大」や「△△学部経済」といった略記は形式が崩れ、雑な印象を与えてしまいます。
正しくは「○○大学 △△学部 経済学科」と書きます。丁寧に正式名称を記すことで、信頼性や誠実さを示せるでしょう。採用担当者は大量の履歴書を確認するため、略称や不正確な表記はすぐに目につきます。
大学院や専門課程に在籍している場合は、研究科や専攻まできちんと記載することが重要です。細部にまで気を配れるかどうかは、社会人としての姿勢を評価する基準にもなります。
小さな表記の違いが大きな印象の差につながるため、必ず正式名称で統一してください。
⑤大学院の場合は「修了見込み」と記入する
大学院に通っている場合は、「卒業見込み」ではなく「修了見込み」と書くのが正しい表現です。大学院では「修了」という言葉が公式に使われており、「卒業」と区別されています。
例えば「2026年3月 ○○大学大学院 △△研究科□□専攻 修了見込み」と書きましょう。これが正式な記載方法です。「卒業見込み」と誤って記すと、学問への理解不足と受け取られる可能性があります。
採用担当者は細かな点まで確認するため、こうした表記の違いも見逃しません。正しい表現を使うことは、研究や専門性に真剣に取り組んでいる姿勢を示すことにもつながります。
特に大学院生の場合は研究内容や専門分野が評価されるため、誤記による印象の低下を避けることが大切です。細部まで意識を払った正確な表現が、安心感を与える履歴書につながります。
履歴書の学歴欄の書き方

履歴書の学歴欄は採用担当者が最初に目を通す重要な部分です。ここで誤りがあると、内容以前に基本的なマナーを守れていないと判断されかねません。
正しく書けているかどうかが第一印象を左右するため、注意が必要です。ここでは学歴欄を正しく記載するために押さえておきたい4つのルールを解説します。
- 学歴欄は中学校卒業から記載する
- 学校名・学部・学科は略さず正式名称で書く
- 西暦か和暦かは統一して使用する
- 一行目中央に「学歴」と記載する
①学歴欄は中学校卒業から記載する
学歴欄は中学校卒業から始めるのが一般的です。義務教育を終えた段階を基準とすることで、学歴としての区切りが明確になります。小学校の記載は必要なく、書くとむしろ冗長に感じられるでしょう。
記載例としては「○○中学校 卒業」とし、その後に「△△高等学校 入学」「△△高等学校 卒業」「□□大学 △△学部 △△学科 入学」という形で続けます。年月は正確に書くことが大切です。
転校や編入があった場合でも、基本は最終的に卒業した学校を中心に書き、必要に応じて補足してください。
履歴書は正確さと簡潔さが評価されるため、余計な情報を増やさず中学校卒業から始めることが適切です。
②学校名・学部・学科は略さず正式名称で書く
学校名や学部・学科を略して記載すると誤解を招くおそれがあります。正式名称を用いることで誠実さが伝わり、読み手に安心感を与えられるでしょう。
例えば「○○大」「経済学科」と略さず、「○○大学 経済学部 経済学科」と記載するのが正しい形です。大学院に進学している場合も「○○大学大学院 △△研究科 □□専攻」と省略せずに記載してください。
採用担当者は学歴欄から応募者がどの分野を学んできたのかを把握するため、曖昧な表記は避けるべきです。細かい部分まで丁寧に記載する姿勢は、社会人としての基本的なマナーにも直結します。
こうした配慮は小さなことですが、履歴書全体の印象を大きく左右するでしょう。
③西暦か和暦かは統一して使用する
学歴欄に記載する年月は、西暦でも和暦でも問題ありません。ただし途中で混在させるのは避けましょう。例えば「2020年4月 入学」「令和5年3月 卒業」と混ぜると、不自然さを与えてしまいます。
書類には一貫性が求められるため、最初に選んだ形式を最後まで統一してください。一般的には西暦を使う人が多いですが、企業から和暦を指定される場合は指示に従うのが適切です。
統一感を持たせることで履歴書全体がすっきり整い、読み手にとってわかりやすい内容になります。
採用担当者は限られた時間で多くの書類を確認するため、細部まで配慮された書き方が好印象につながるでしょう。
④一行目中央に「学歴」と記載する
学歴欄を始めるときは、一行目の中央に「学歴」と記載します。これによって採用担当者は学歴情報をすぐに把握でき、視認性も高まるのです。
いきなり「○○中学校 卒業」と書き始めると、整っていない印象を与えてしまうでしょう。正しい形式は、一行目中央に「学歴」と記載し、その下に学校名と年月を順に並べる方法です。
このルールを守ることで履歴書全体に統一感が生まれ、完成度も高まります。読みやすく整理された履歴書は、それだけで応募者の印象を良くする効果があるでしょう。
小さな部分まで丁寧に整える姿勢が、就活生の誠実さを伝えることになるのです。
卒業条件を満たしていることを証明する書類
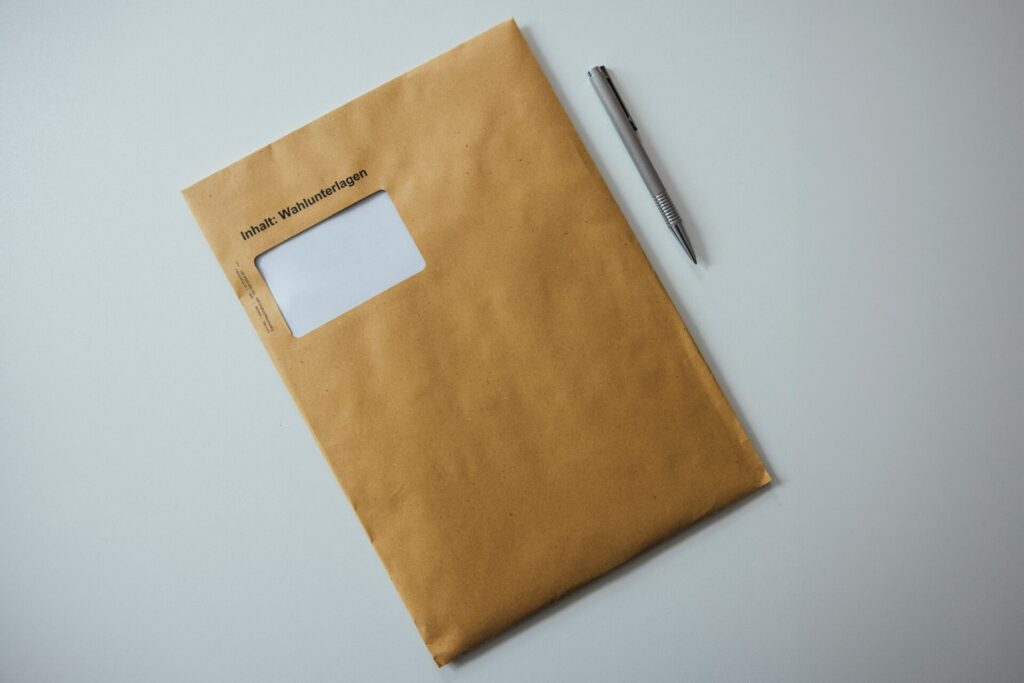
就活では、履歴書に「卒業見込み」と書くだけでなく、それを裏づける書類の提出を求められる場合があります。
採用担当者に安心感を与えるためにも、どの書類が必要になるのかを理解しておくことが大切でしょう。ここでは代表的な証明書の内容と役割を整理しました。
- 卒業見込み証明書
- 成績証明書
- 在学証明書
- 単位修得証明書
- 推薦書・調査書
①卒業見込み証明書
卒業見込み証明書は、大学が「必要な単位を修得すれば卒業できる見込みがある」と公式に証明する書類です。就活で最も提出を求められることが多く、企業にとって信頼できる根拠になります。
履歴書に「卒業見込み」と書いただけでは本当に卒業できるのか判断できませんが、この証明書を添えることで大学からの保証を示せるのです。
特に4年生の春には申請が集中するため、必要な時期を見据えて早めに準備してください。学務課や教務課で発行されるので、余裕を持った手続きが安心につながります。
さらに、企業によっては内定後に提出を必須とするケースも。そのため、就活が本格化する前に発行方法を確認し、複数部を用意しておくと良いでしょう。
証明書の有効期限が限られている場合もあるので、提出先ごとに新しく取得する必要があるかを把握しておくことも重要です。計画的に準備を進めれば、提出を求められたときに慌てる心配はありません。
②成績証明書
成績証明書は、履修した科目や取得単位、成績評価を一覧で示す書類です。大学生活でどのような学習を積み重ねてきたかがわかり、企業が学業への取り組み姿勢を確認する材料になります。
特に推薦選考や公務員試験では提出が必須となることが多いです。履歴書の内容と矛盾がないかを確認するためにも利用されるでしょう。
成績が突出していなくても、継続して学習を進めている点は評価される場合があります。自動発行機や窓口の利用方法を事前に把握しておけば、必要なときにすぐ取得できて安心です。
また、成績証明書は学生の努力の過程を示す資料でもあります。特定の分野で成績が良ければ、その分野に関心や得意分野があることをアピールするきっかけにもなるでしょう。
企業側も履歴書だけでは判断できない点を成績証明書から読み取ります。事前に取得方法と発行にかかる日数を確認し、複数社に応募する場合は必要部数を揃えておくと安心です。
③在学証明書
在学証明書は、現在その学校に正式に在籍していることを示す書類です。奨学金の申請や資格試験で必要になるほか、就活でも提出を求められることがあります。
特に留学生や編入学を経た学生は、在籍状況を明確にする目的で提出を指示される場合があるでしょう。
「卒業見込み証明書」と混同しがちですが、在学証明書はあくまで籍があることを示すだけで、卒業要件の進捗までは証明しません。
就活で求められる可能性があることを踏まえて、発行方法を把握しておくと安心です。さらに、在学証明書は大学が公式に発行する書類のため、信頼性が高いのも特徴です。
例えば途中で休学や復学をしている場合、その記録も反映されることがあります。
採用担当者にとっては学生の在籍状況を正確に把握する材料となるため、指示があったときにすぐ提出できるよう準備しておきましょう。
余裕を持って手続きを進めておくことで、書類不備によるトラブルを避けられます。
④単位修得証明書
単位修得証明書は、取得した単位数や科目を示す書類です。企業が卒業要件の達成度を確認する目的で提出を求めることがあります。
理系学部や専門性の高い学科では、履修状況が採用に直結することもあるため重要です。「卒業見込み証明書」が総合的な見通しを示すのに対し、単位修得証明書は具体的な数値で裏づける役割を持ちます。
発行には数日かかることもあるため、必要になったときに備えて事前に教務課の手続き方法を確認しておくと良いでしょう。
さらに、卒業研究や専門課程を控えている学生にとっては、単位修得証明書が学業の進行度を示す重要な資料になります。
採用担当者が「卒業に必要な条件を満たせるか」を判断する材料にもなるため、提出を求められた場合は正確に準備してください。提出までの余裕を持つことで、安心して就活を進められるでしょう。
⑤推薦書・調査書
推薦書や調査書は、教授や大学が学生の人物像や学業態度を保証するために作成する書類です。
すべての就活で必須ではありませんが、推薦応募や特定の企業、または教員採用試験などで提出を求められることがあります。
内容には成績だけでなく、研究への姿勢や人柄も含まれるため、採用担当者が応募者を総合的に判断する材料になるでしょう。
依頼から作成まで時間がかかる場合が多いため、必要になりそうなときは早めに指導教員へ相談してください。準備を怠らなければ、スムーズに対応できて安心です。
加えて、推薦書や調査書は学生と教員の関係性を反映するものでもあります。普段から授業や研究に真剣に取り組んでいれば、その姿勢が文章に表れるでしょう。
提出を求められたときに慌てないためにも、日頃から教員とのコミュニケーションを大切にしてください。信頼関係が築けていれば、推薦内容にも説得力が増し、採用担当者に強い印象を与えられるはずです。
卒業見込みを履歴書に書く際の注意点

履歴書に「卒業見込み」と記入するのは就活で基本的なマナーです。ただし細かな点で間違えると、信頼を損ねる原因になるでしょう。ここでは特に気をつけたい5つの注意点を解説します。
- 「卒業見込み」の誤表記に注意する
- 「在学中」を不用意に使わない
- 卒業年度や年月を間違えない
- 西暦・和暦を混在させない
- 記載ミスや誤字脱字を避ける
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①「卒業見込み」の誤表記に注意する
履歴書でありがちな失敗の1つは、「卒業見込み」を正しく書けていないことです。「卒業予定」と混同したり、「卒見」と略してしまうのは誤りで、正式な表現ではありません。
採用担当者は短時間で履歴書を確認するため、こうした小さな誤表記でもすぐに目に留まり、基本的な注意力が欠けていると判断される恐れがあります。
正しい表現は「〇〇大学 △△学部 △△学科 卒業見込み」です。省略せず丁寧に書くことで誠実さが伝わり、信頼を得やすくなるでしょう。
また、表記の正確さは応募者の姿勢を映すものでもあります。たとえ内容が優れていても、書き方に不備があれば印象は下がるでしょう。
履歴書は公式な文書であると意識し、細部まで正確さを優先してください。誤記や省略を避ける習慣を持つことで、社会人として必要な細やかな配慮を示すことにもつながります。
小さな気遣いの積み重ねが、選考での評価を高めるポイントになるのです。
②「在学中」を不用意に使わない
履歴書に「在学中」と記載する場合もありますが、適切に使い分けなければ採用担当者に誤解を与えることがあります。
特に最終学年の学生が「在学中」と書くと、卒業できるかどうかが不明確に見え、採用側に不安を抱かせてしまうでしょう。この場合は必ず「卒業見込み」と記載するのが正しい方法です。
一方で3年生や卒業がまだ先の学年であれば「在学中」と書くのが適切。状況に応じた正しい表現を選ぶことが大切になります。誤った表記をすると、面接で説明を求められた際に不利に働く可能性があります。
採用担当者は、応募者が自分の立場を理解し正しく伝えられるかを見ているでしょう。曖昧な表現を避け、明確に「卒業見込み」と「在学中」を区別して使うことが重要です。
立場に応じて表現を選ぶ力は、就職後にも役立つ社会人基礎力の一部でもあります。就活の第一歩として、履歴書の記載から正確さを心がけてください。
③卒業年度や年月を間違えない
学歴欄で卒業年度や年月を誤ると、採用担当者に不信感を持たれる恐れがあります。
例えば「2025年3月 卒業見込み」と書くべきところを「2026年」と記載してしまうと、学年との整合性が崩れて信頼を失うでしょう。
企業は入社時期の計画を立てる際に履歴書の情報を基に判断するため、日付の誤りは大きな影響を与えかねません。卒業見込証明書や履修計画表を確認して、必ず正しい年度を記載してください。
さらに、年月の記載ミスは履歴書全体の信頼性を下げる原因にもなります。小さな誤りでも「細部を軽視している」と見なされるでしょう。
提出前には必ず再確認を行い、できれば第三者に見てもらうと安心です。こうした慎重さは就活だけでなく、社会人になってからの文書作成でも求められる力。
細かな部分を正しく書けることが、選考での評価を高める大事な要素になります。
④西暦・和暦を混在させない
履歴書の年月は、西暦か和暦かを必ず統一して記載してください。「2022年4月 入学」「令和7年3月 卒業見込み」といった混在は不自然で、読み手に違和感を与えます。
統一感のない履歴書は、整理整頓が苦手だという印象を持たれる可能性があるのです。最初に選んだ形式を最後まで一貫して使うことを徹底しましょう。
一般的には西暦が多く使われていますが、企業から指定があればそれに従ってください。また、統一された書き方は履歴書全体の見やすさを高めます。
採用担当者は限られた時間で多数の履歴書を確認するため、わかりやすさや整合性が評価に直結するのです。
⑤記載ミスや誤字脱字を避ける
履歴書に誤字脱字や記載ミスがあると、注意力が不足していると判断される危険があります。誤字脱字は一度提出してしまうと訂正が難しいため、取り返しのつかない印象を残すことになるでしょう。
特に学校名や学部名を誤ると、応募者の誠意が伝わらず評価を落とす要因に。
提出前には必ず内容を確認し、第三者に見てもらうのも有効です。パソコンで作成する場合は変換ミスに注意し、手書きの場合は読みやすい字を書くよう心がけてください。
履歴書に卒業見込みを書くときに意識すべきこと

履歴書に「卒業見込み」と記入する際は、正しい意味や条件を理解し、学歴欄での表現を適切にすることが重要です。なぜなら誤った書き方や「在学中」との混同は、採用担当者に不信感を与えかねないから。
最終学年で卒業要件を満たす見通しがある場合のみ「卒業見込み」と書き、日付や正式名称を正確に記載しましょう。また、卒業見込み証明書などの裏づけ書類を用意することで信頼性が高まります。
結論として、卒業見込みを履歴書に正しく記載することは、就活をスムーズに進めるための必須条件といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












