懲戒免職とは?懲戒解雇との違いや退職金・再就職まで徹底解説
懲戒免職について聞いたことはあっても、懲戒解雇との違いや退職金・再就職への影響まで詳しく知っている人は多くありません。懲戒免職はキャリアや生活に大きな影響を及ぼす重要な制度です。
この記事では、「懲戒免職とは」何かをわかりやすく解説し、懲戒解雇との違い、退職金・年金・失業保険への影響、さらには再就職の可能性まで徹底的に整理して紹介します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
懲戒免職とは

懲戒免職とは、企業や組織が従業員の重大な不正や規律違反に対して科す最も重い処分のひとつです。一般的に「クビ」と表現されることもありますが、通常の解雇とは意味が異なります。
結論から言うと、懲戒免職は「働く権利を失うだけでなく、その後の生活にも強い影響を与える」処分です。たとえば横領や背任、重大なハラスメントなど、組織の秩序を大きく乱す行為が対象になります。
通常の解雇と違って、懲戒免職では退職金が大きく制限される場合もあり、社会的信用を著しく失ってしまう点が特徴です。
懲戒免職はキャリア形成に大きな影響を及ぼすリスクであり、知識として理解しておくことで社会人としての意識を高められるはずです。
懲戒免職と懲戒解雇の違い

就活生にとって「懲戒免職」と「懲戒解雇」はなじみが薄い言葉かもしれませんが、社会に出て働くうえで必ず押さえておきたい知識です。
両者は似ているようで、制度や対象となる職種、退職後の扱いに明確な違いがあります。誤解したままだと、ニュースや社会問題に触れたときに正しく理解できない可能性があるのです。
ここでは代表的なポイントを整理し、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
- 制度
- 対象となる主な職種
- 退職後の扱い
- 社会的影響
- 再就職への影響
①制度
懲戒免職は国家公務員法や地方公務員法に基づいて行われる公務員特有の処分であり、最も重い懲戒処分の一つです。
公務員は国民全体に奉仕する立場であるため、社会からの信頼が求められ、その期待を裏切る重大な非違行為があった場合に適用されます。
一方、懲戒解雇は民間企業の従業員に対して行われる処分で、労働基準法や会社の就業規則を根拠とするもの。
どちらも重大な違反行為に対して下されますが、懲戒免職は公的制度に基づくものであり、懲戒解雇は契約上の問題に基づくものという違いがあります。
このように背景となる法的根拠や制度の性質を理解しておくと、両者を区別して捉えやすくなるでしょう。
②対象となる主な職種
懲戒免職の対象は国家公務員や地方公務員に限られています。公務員は行政の公平性と透明性を保つ立場にあるため、服務規律違反や収賄、職権乱用といった行為には厳格に対処されるでしょう。
例えば、税務署職員が納税者の情報を不正に利用した場合や、地方自治体の職員が公金を横領した場合などは懲戒免職の対象となります。一方で懲戒解雇は、民間企業で働く正社員や契約社員に適用。
勤務態度の著しい悪化、横領、顧客への不正対応など企業活動に悪影響を及ぼす行為が理由です。
このように、対象となる職種や立場が異なることで、同じ「懲戒」という言葉でも持つ意味や重みは大きく変わるでしょう。
③退職後の扱い
懲戒免職を受けた公務員は退職金を受け取れない場合が多く、さらに加算年金の一部に制限がかかるケースもあります。これは、公務員という立場が社会的責任と密接に結びついているからです。
つまり、信頼を裏切る行為には経済的にも重い代償が伴います。一方で懲戒解雇を受けた従業員も退職金を失う場合がありますが、それは各企業の就業規則によって異なるのです。
また、懲戒解雇であっても年金や社会保険の資格自体は維持されるのが一般的。この点が懲戒免職との大きな違いであり、退職後の生活への影響の度合いを大きく左右します。
退職後の扱いを比較することで、それぞれの処分が個人の将来にどのように響くかを理解できるでしょう。
④社会的影響
懲戒免職は、行政機関から公式に発表されることが多く、新聞やインターネット上で名前が公開される場合もあります。
そのため社会的信用は著しく失われ、公務員としての再任用や関連業務への復帰はほぼ不可能です。家族や地域社会にも影響が及ぶことも少なくありません。
懲戒解雇の場合は企業内で処理され、公表されないケースもありますが、経歴に大きな傷を残すことに変わりはありません。転職活動では必ず理由を問われ、面接で説明を求められる場面も多いでしょう。
つまり、懲戒免職と懲戒解雇では社会的影響の広がり方に違いがあるものの、どちらもその後の人生設計に大きなダメージを与える点では共通しているのです。
⑤再就職への影響
懲戒免職を受けた場合、公務員として再度採用される道は閉ざされるだけでなく、民間企業でも信頼の喪失から就職は極めて困難になります。
履歴書や職務経歴に記録が残り、面接で不利益を受けることも避けられません。
懲戒解雇についても再就職のハードルは高いですが、場合によっては事情を正直に説明し、誠意ある態度を見せることで再スタートの道を開ける可能性があります。
懲戒免職は事実上キャリアの大きな断絶を意味しますが、懲戒解雇は改善や努力によって克服できる余地が残されているでしょう。
両者の違いを理解しておくことは、将来のキャリア形成やリスク回避のために欠かせない知識といえます。
懲戒免職に当たる行為の具体例

懲戒免職は社会的にも重い処分であり、どのような行為が対象になるのかを知っておくことが大切です。ここでは代表的な事例を取り上げ、それぞれがなぜ懲戒免職につながるのかを解説します。
具体的な内容を理解することで、働くうえでのリスクを予防できるでしょう。
- 無断欠勤や職務放棄に該当する行為
- セクハラ・パワハラなどハラスメントに当たる行為
- 経歴詐称や虚偽報告にあたる行為
- 公金や物品の不正使用に関わる行為
- 飲酒運転や重大な交通事故に関わる行為
①無断欠勤や職務放棄に該当する行為
無断欠勤や職務放棄は組織への信頼を大きく損なう行為であり、懲戒免職の対象になることがあります。業務に重大な支障を与え、同僚や顧客に大きな迷惑をかけるためです。
特に長期間にわたる無断欠勤や繰り返される遅刻・欠勤は「雇用契約を守る意思がない」とみなされやすいでしょう。
最初は注意や配置転換で済んでも改善が見られない場合、最終的に免職に至ることがあります。学生にとってもインターンやアルバイトでの無断欠勤は信用を大きく下げる行為です。
小さな習慣から規律を守る姿勢を大切にすることが、社会人としての第一歩になります。
②セクハラ・パワハラなどハラスメントに当たる行為
セクハラやパワハラなどのハラスメント行為は、人間関係を壊すだけでなく組織全体の信頼を失わせます。被害者が安心して働けない環境をつくるため、企業は近年特に厳しい態度で臨んでいるのです。
行為が認められれば懲戒免職に直結するケースも多く、加害者本人だけでなく組織の評判や社会的評価も大きく傷つけてしまうでしょう。
学生の段階でも「冗談のつもり」で発した言葉や態度がハラスメントと受け取られることは少なくありません。相手の立場を尊重し、日頃から思いやりを持った言動を心がけることが重要です。
これが将来のキャリア形成に直結する信頼関係を築く基盤になります。
③経歴詐称や虚偽報告にあたる行為
履歴書での経歴詐称や業務上の虚偽報告は、信頼関係を根本から壊す行為です。企業は従業員を信用して仕事を任せるため、虚偽は組織の秩序を乱し、重大な損害を招く恐れがあります。
経歴詐称が発覚すれば雇用契約の前提が崩れるため、免職処分に直結する可能性が高いです。また、虚偽報告は上司や組織の判断を誤らせ、経済的・社会的損失につながります。
学生にとっても「自己PRを盛る」ことは同じリスクを抱える行為です。小さな嘘が後々の信用を失う原因となるため、誠実に情報を伝える姿勢が長期的なキャリアの安定を支えるでしょう。
④公金や物品の不正使用に関わる行為
会社の経費や備品を私的に利用する行為は、横領や背任にあたり重大な違反です。金銭に関する不正は信用を一瞬で失わせ、懲戒免職に直結することが多いでしょう。
特に金額が大きい場合や組織ぐるみと疑われる場合は刑事責任にまで発展します。学生にとっては実感が湧きにくいかもしれませんが、アルバイトでのレジ金の管理や備品の扱いも同様です。
「少しなら」と考えること自体が信用を裏切る行為になります。小さな不正でも重大な処分につながることを理解し、日々誠実に行動する意識を持ち続けることが大切です。
⑤飲酒運転や重大な交通事故に関わる行為
飲酒運転や重大な交通事故は業務外の出来事であっても、懲戒免職の対象となることがあります。社会的影響が大きく、会社の信用を失わせるからです。
特に報道で広く知られると組織全体の信頼が揺らぎ、取引や採用にも影響が及ぶでしょう。
交通法規を守らない姿勢は社会人としての基本的資質に欠けるとみなされやすく、厳しい処分が下されるのは当然です。
学生のうちから交通マナーを守る意識を持ち、安全を最優先に行動する習慣を身につけることが求められます。ルールを徹底して守る姿勢が、社会に出てからの信頼や評価を高める近道となるのです。
懲戒免職の判断基準

懲戒免職は最も重い懲戒処分であり、安易に決めるべきものではありません。誤った判断をすれば不当処分とみなされ、裁判や不服申し立てに発展する可能性があります。
そのため法的根拠や社会的妥当性を十分に踏まえ、慎重かつ厳格に判断する必要があるのです。ここでは懲戒免職を決める際に重視される5つの観点について詳しく解説します。
- 罪刑法定主義に基づく
- 個人責任に基づく
- 二重処分の禁止を踏まえる
- 社会通念上の相当性を踏まえる
- 適正手続きの有無を確認する
①罪刑法定主義に基づく
懲戒免職を決定する際には、必ず明確な法的根拠が存在しなければなりません。
罪刑法定主義とは「何が違反行為にあたり、どのような処分が下されるのかをあらかじめ規則で定めておく」という基本的な考え方を指します。
この原則があることで、恣意的で不公平な処分を防げるのです。公務員の場合は国家公務員法や地方公務員法が根拠となり、民間企業では就業規則や労働契約が基準になります。
もし事前に規定のない理由で免職を行った場合、不当処分とされる可能性が極めて高いでしょう。
処分は必ず既存の規則や契約に沿って行われなければならず、この原則を無視すると組織の信頼そのものを失いかねません。
②個人責任に基づく
懲戒免職を行う場合は、組織全体の不祥事であっても個人の責任を明確にする必要があります。誰の行為が直接的な原因になったのかを特定しなければ、公平な処分は成立しません。
例えば部署単位で不正が発覚したとしても、各人の関与度や故意性によって処分の重さは大きく変わります。
責任をあいまいにしたまま処分を進めれば、不服申し立てや裁判で争われるリスクが高まるでしょう。正当性を確保するためには、個人の行為とその結果の関係を客観的に検証することが欠かせません。
関係者全員を一律で処分するのではなく、誰がどこまで関与したのかを丁寧に調査する姿勢が組織の公正さを保つ鍵となります。
③二重処分の禁止を踏まえる
同じ違反行為に対して複数の懲戒処分を課すことは許されません。これを二重処分の禁止と呼びます。たとえばすでに減給や停職の処分を受けているのに、同じ理由でさらに懲戒免職を追加するのは不当です。
この原則を守ることで処分の適正さが維持され、本人の権利も保障されます。懲戒免職を検討する際には、過去に同じ行為に対して処分が行われていないかを確認することが重要です。
二重処分を避けることは単なる形式的な手続きではなく、公平性や信頼性を守るために欠かせない視点。
もしこの原則を無視した場合、処分そのものが無効になる可能性もあるため、特に注意が求められます。
④社会通念上の相当性を踏まえる
懲戒免職は法律上は正しくても、社会常識から見て過度であれば妥当とは認められません。社会通念上の相当性とは「一般的な社会の目から見て処分が適切かどうか」という観点を意味します。
例えば軽微な規律違反でいきなり免職にするのは、行き過ぎと判断される可能性が高いでしょう。
処分は社会的な感覚や常識に照らして適切である必要があり、この視点を欠くと世間からの批判を招き、裁判でも無効とされる恐れがあります。
懲戒免職の判断は単に規則の条文を適用するだけではなく、社会全体の価値観や常識との整合性を考慮することが不可欠。組織の評判を守るためにも、この観点は極めて重要です。
⑤適正手続きの有無を確認する
懲戒免職を行う際には、正しい手続きを踏んでいるかどうかも欠かせない条件です。事前に弁明の機会を与えたり、事実関係を十分に調査したりすることは必須といえます。
こうしたプロセスを怠れば、処分そのものが違法とみなされる可能性があります。例えば事情聴取を行わずに免職を決定すれば、裁判で処分が取り消されるリスクが高まるでしょう。
公正で透明性のある手続きを進めることは、本人の権利を守るだけでなく、組織全体の信頼性を保つことにもつながります。
適正手続きを経てこそ懲戒免職の正当性は確保されるものであり、このプロセスを軽視すれば処分の正当性は大きく揺らぐことになるのです。
懲戒免職において最後の砦となるのが、この適正手続きの確保だといえるでしょう。
懲戒免職は不服申し立てできるのか

懲戒免職は非常に重い処分ですが、必ずしも受け入れるしかないわけではありません。不当だと思う場合には、不服申し立てを行える仕組みがあります。
公務員であれば人事院や地方公務員委員会に申し立てが可能ですし、民間企業であれば労働審判や裁判で処分の妥当性を争うこともできるでしょう。
不服を申し立てるには「処分に合理的な理由がない」「手続きが適切でなかった」といった根拠が必要です。
そのため、処分通知を受け取った際には内容を丁寧に確認し、関連する記録を残しておくことが欠かせません。さらに専門の弁護士に相談すれば、手続きを有利に進められる可能性が高まります。
安易にあきらめず、利用できる制度を知り冷静に対応することが、自分を守るための大切な行動になるはずです。
懲戒免職を行う際の注意点

懲戒免職は従業員の人生に大きな影響を与える重い処分であり、企業にとっても慎重さが求められる決定です。
手続きに不備があれば裁判で無効とされるリスクもあるため、法的根拠や社会的妥当性を踏まえて進めることが必要。ここでは懲戒免職を行う際に注意すべき5つの観点を解説します。
- 就業規則に懲戒免職の根拠が明記されているか確認する
- 従業員に弁明の機会を与えることを徹底する
- 懲戒免職の理由を具体的に示す
- 懲戒免職の内容が社会的に妥当か確認する
- 懲戒免職の手続きを適切に進める
①就業規則に懲戒免職の根拠が明記されているか確認する
懲戒免職を有効に行うためには、必ず就業規則に根拠が明記されている必要があります。
例えば「横領や重大な服務違反があった場合は懲戒免職とする」といった条文がなければ、処分自体が違法と判断されるおそれがあるのです。
事前に労働基準監督署へ届け出が済んでいるかも確認しなければなりません。根拠が不十分なまま処分を行えば、従業員からの不服申し立てや裁判で無効とされる可能性が高まります。
企業は処分前に必ず就業規則を確認し、適用できる条文があるかを把握しておくことが欠かせないでしょう。
②従業員に弁明の機会を与えることを徹底する
懲戒免職を進める際には、従業員本人に必ず弁明の機会を与える必要があります。これは適正手続きの一部であり、無視して処分を決めれば不当とされるリスクが高いです。
従業員が自らの立場や言い分を説明できる場を設け、その内容をしっかり検討することが重要でしょう。形式的に聞くだけではなく、証拠や主張を踏まえて判断することが公正さにつながります。
弁明の機会を確保することで、企業側も「公正な手続きを踏んだ」と主張でき、トラブル防止に役立つでしょう。
③懲戒免職の理由を具体的に示す
懲戒免職は従業員のキャリアや生活に大きな影響を与えるため、その理由を曖昧にしてはいけません。
「勤務態度が悪い」といった抽象的な説明ではなく、「顧客情報を無断で持ち出した」「職場で金銭を横領した」といった具体的な事実を明示する必要があります。
理由を明確にすることで従業員が納得しやすくなり、裁判になった場合でも企業側の正当性が認められる可能性が高まるでしょう。
証拠や経緯を示しながら説明することは、処分の妥当性を裏付けるうえで不可欠です。
④懲戒免職の内容が社会的に妥当か確認する
懲戒免職を行う際は、その内容が社会的に見て妥当かどうかを慎重に判断する必要があります。軽微な違反で免職処分を下せば「過度な処分」と見なされ、後に無効とされる可能性が高いでしょう。
例えば一度の遅刻や小さな規律違反で免職とするのは社会通念に照らして不相当とされます。社会的に受け入れられる水準かどうかを考えることは、裁判リスクを避けるうえで重要です。
懲戒免職は最終手段であることを意識し、処分の重さが行為に見合っているかを必ず確認してください。
⑤懲戒免職の手続きを適切に進める
懲戒免職は、理由や内容が正当であっても、手続きに誤りがあれば無効とされる場合があります。
例えば就業規則に定められた手続きを省略したり、労働基準監督署への報告を怠ったりすると、処分全体が不適正と判断されるでしょう。
手続きの各段階を丁寧に進めることが、処分の有効性を支える大前提です。具体的には、証拠の収集、弁明の聴取、処分決定の通知までを順序立てて行う必要があります。
適正な手続きを踏むことは、企業と従業員双方にとって公正な結果を導く基盤となるはずです。
懲戒免職で退職金はどうなる?

懲戒免職を受けた場合、退職金の扱いは一律ではなく、行為の内容や就業規則によって異なります。
特に重い非違行為では全額が支給されないこともありますが、状況によっては一部、または満額を受け取れる場合も。ここでは代表的な3つのパターンを整理します。
- 全額不支給:横領・背任・重大な非違行為の場合
- 一部支給:勤務態度不良や軽度の服務違反の場合
- 満額支給:非違の程度が軽く規程の不適用となる場合
①全額不支給:横領・背任・重大な非違行為の場合
横領や背任といった重大な非違行為に該当する場合、退職金は全額支給されないのが一般的。これは社会的な信用を大きく損なうためであり、職場や組織に深刻な損害を与えたと判断されるからです。
例えば、公金横領や機密情報の持ち出しなどが典型例といえるでしょう。また、規程に「特定の行為をした場合は退職金を不支給とする」と定められていれば、情状が考慮されても支給は認められません。
退職金は長年の功労に対する性格を持ちますが、重大な背信行為があれば権利を失うリスクが高いのです。就活生にとっても、信頼を失えば将来設計に大きな影響が及ぶことを理解しておくとよいでしょう。
②一部支給:勤務態度不良や軽度の服務違反の場合
横領のような重大な行為ではなく、勤務態度の悪化や軽度の服務違反が繰り返され懲戒免職に至った場合は、退職金が一部支給されることがあります。
例えば、無断欠勤が続いて業務に支障を与えた場合や、改善されない軽度のハラスメント行為などです。このようなケースでは組織に与える影響は比較的小さいものの、懲戒免職相当と判断されます。
そのため、功労部分を考慮して退職金の一部が残る場合があるのです。ただし、どの程度支給されるかは組織の規程次第であり、同じ行為でも企業ごとに処分が異なる点には注意が必要でしょう。
③満額支給:非違の程度が軽く規程の不適用となる場合
懲戒免職を受けても、必ずしも退職金が減額されるとは限りません。非違の程度が軽く、不支給規程に該当しない場合には満額支給される可能性があります。
例えば、軽微な違反で懲戒免職相当とされたが、長年の勤務実績や真摯な反省が考慮されたケースなどです。ただし、これは例外的な取り扱いであり、判断は組織ごとに大きく変わります。
規程に不支給要件がない場合に限られるため、実際にはまれなケースでしょう。
学生にとっては、退職金の有無が生活設計に直結する現実を知るきっかけとなり、社会に出てからの働き方を意識する材料になるはずです。
懲戒免職で年金はどうなる?
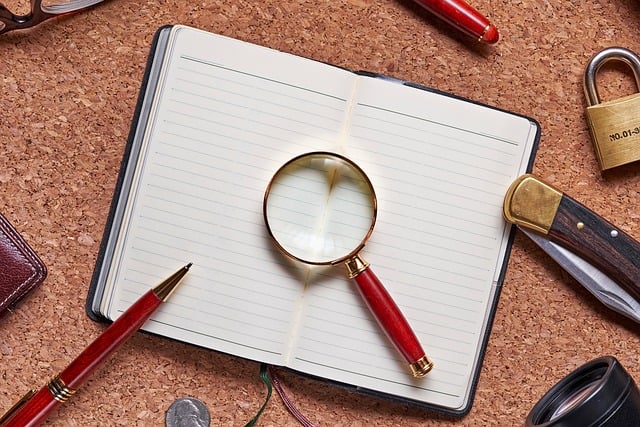
懲戒免職になると退職金や再就職だけでなく、老後の生活に関わる年金への影響も気になります。
年金は保険料を納めていれば原則として受給資格がありますが、処分の内容によって一部が制限されることがあるでしょう。ここでは懲戒免職後に年金がどう扱われるのかを解説します。
- 年金を受給できる
- 一部加算部分が減額される
①年金を受給できる
懲戒免職を受けても、基本的に年金は受給できます。年金は労働の対価ではなく、保険料を支払ったことによる権利だからです。
厚生年金や国民年金は、処分の有無に関わらず、受給資格期間を満たしていれば将来支給されます。そのため懲戒免職になったからといって、年金が全額なくなることはありません。
退職直後は「年金まで消えるのでは」と不安に思いがちですが、制度上そうした心配は不要です。年金の基本部分が守られていると理解できれば、安心して生活設計を考えられるでしょう。
②一部加算部分が減額される
一方で影響を受けるのは年金の加算部分です。特に公務員や大企業の一部職員に支給される「職域加算」や共済年金の上乗せ部分は、懲戒免職になると減額や支給停止となることがあります。
これは基礎的な年金とは異なり、職務に従事したことに対する加算だからです。例えば勤続年数に応じた加算額や役職手当的な性格を持つ部分は、処分の影響を強く受けやすいといえます。
こうした加算部分は退職金の減額と同じく生活に直結するため注意が必要です。制度を理解し、自分の将来の収入にどのように反映されるかを把握しておくことが大切でしょう。
懲戒免職を受けると失業保険はもらえる?
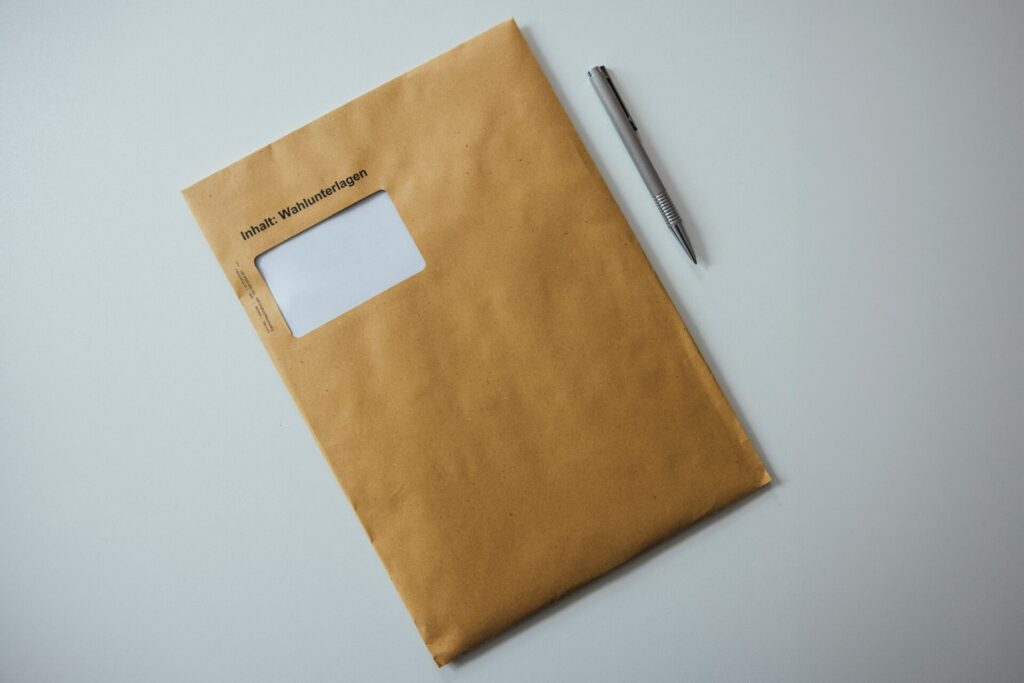
懲戒免職になっても、必ずしも失業保険を全く受けられないわけではありません。ただし、一般的な自己都合退職や会社都合退職とは違い、給付条件や期間に厳しい制限が設けられる場合があります。
ここでは受給資格や制限内容を整理して確認しておきましょう。
- 失業保険を受給できる
- 給付制限期間が長くなる
- 審査が厳格化される
①失業保険を受給できる
懲戒免職であっても、失業状態にあると認められれば失業保険を受け取れる可能性があります。雇用保険に一定期間加入していれば基本的な資格は残るため、完全に権利を失うことはありません。
ただし、会社都合退職と違って「自己に責任がある離職」とみなされるため、通常より不利な扱いになるでしょう。すぐに支給されるわけではなく、待機期間や制限が加わるのが一般的です。
誤解して「もらえない」と決めつけず、条件を確認してからハローワークに相談してください。正しく理解して行動することが大切です。
②給付制限期間が長くなる
懲戒免職の場合、失業保険の給付制限期間は通常の自己都合退職よりも長くなる傾向があります。
一般的なケースでは2〜3か月の制限ですが、重大な違反と判断されればさらに長期化する可能性も否定できません。これは就業規則に反した重大な理由で離職したとみなされるためです。
その結果、退職から実際に支給が始まるまでの期間が延び、生活の安定に影響しやすくなります。こうした事態に備えて、あらかじめ貯蓄や支出の見直しを行うことが現実的な対策になるでしょう。
③審査が厳格化される
懲戒免職後に失業保険を申請すると、ハローワークでの審査が他のケースより厳しくなる傾向があります。
離職理由や処分の内容について詳細な確認が行われ、追加で書類提出を求められることも少なくありません。これは不正受給を防ぐためであり、審査に時間がかかることもあります。
また、担当者の判断によっては給付が遅れる場合も考えられるのです。正直に事実を伝え、必要書類を揃えて対応することが円滑な受給につながります。
こうした仕組みを知っておけば、社会人になった後に備えやすくなるはずです。
懲戒免職後に再就職できる?

懲戒免職を受けると、退職金や年金と並んで「再就職は可能なのか」という不安を抱く人は少なくありません。結論として、懲戒免職後でも再就職はできます。
ただし処分の内容や社会的影響によっては、選択肢が限られる場合があるため注意が必要です。懲戒免職後でも再就職が禁止されるわけではありません。
法律上、職業選択の自由は認められているので、活動自体は可能です。ただし採用担当者から過去の処分について問われることもあり、経歴への信頼性に影響する場面があるでしょう。
懲戒免職後の再就職は簡単ではありませんが、適切な準備と誠実な姿勢があれば、新しいキャリアを築くことは十分可能です。
懲戒免職に関する理解を深めておく重要性
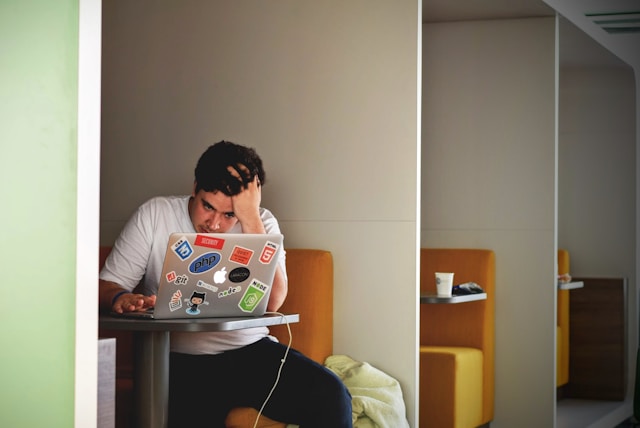
懲戒免職とは、重大な規律違反に対して適用される厳しい処分であり、懲戒解雇との違いや対象職種、退職後の影響を正しく理解することが大切です。
例えば、無断欠勤や経歴詐称、公金の不正使用などは典型的な例であり、判断基準には社会的妥当性や適正手続きが求められます。
さらに、不服申し立てが可能な点や、退職金・年金・失業保険といった生活に直結する制度の扱いも無視できません。
懲戒免職は再就職にも大きな影響を及ぼすため、仕組みを知りリスクを理解することが将来のキャリアを守るうえで欠かせないでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














