社員と従業員の違いとは?定義・雇用形態・必要手続きを解説
「社員と従業員の違いって、実際にはどう定義されているのだろう?」
企業で働く際によく耳にする言葉ですが、その意味を正しく理解している人は意外と少ないものです。雇用形態や加入する保険、手続きの内容によって呼び方や扱いが変わるため、混同しやすい用語でもあります。
そこで本記事では、社員と従業員の違いを軸に、それぞれの定義や雇用形態の種類、正規雇用・非正規雇用のメリット、さらに雇用に必要な手続きまでを詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
社員とは

社員とは、会社に属して働く人を指す言葉ですが、その意味は文脈によって変わります。多くの人は「社員=正社員」と考えがちでしょう。
しかし法律上の「社員」は、会社法において出資して会社を構成する人、つまり株主や出資者を示します。この点を理解していないと、雇用契約や採用活動で誤解を招くおそれがあるのです。
求人票や契約書で「社員」と書かれている場合、一般的には正社員を意味します。ただし社内での呼称として、契約社員や派遣社員もまとめて「社員」と表現されることがあるのです。
大切なのは、社員という言葉を法律上の定義と実務上の使い方の両面から理解することです。実務では雇用形態を区別する呼び方として使われますが、法律的には会社を構成する立場を意味します。
このギャップを意識することで、説明会や契約締結時に正確な情報を提供でき、応募者からの信頼も得やすくなるはずです。その結果、誤解のない健全な雇用関係を築けるでしょう。
従業員とは

従業員とは、企業や組織に雇用されて働く人を指す言葉です。一般的には正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パートタイマーも含まれるのが特徴でしょう。
つまり従業員とは、雇用形態にかかわらず賃金を受け取り、業務に従事する人すべてを対象とします。ここで重要なのは、「社員」とは定義が少し異なる点です。
社員は会社に籍を置く正規雇用者を指すことが多い一方で、従業員はより広い概念として使われています。この違いを正しく理解していないと、労務管理や契約書の作成時に誤解を招きかねません。
特に社会保険の加入義務や労働基準法の適用範囲を判断するときには、従業員に含まれる人の範囲を正確に認識しておくことが欠かせないでしょう。
実務においては、就業規則や雇用契約に記載される「従業員」の定義を明確にし、それをもとに制度運用を進めてください。そうすることで企業のリスクを避けられます。
従業員に該当する雇用形態

従業員にはさまざまな雇用形態があり、それぞれに特徴や役割があります。正社員だけでなく、契約社員、パートタイム、アルバイト、派遣社員なども含まれます。
ここでは、それぞれの働き方の違いを整理しました。
- 正社員
- 契約社員
- パートタイム
- アルバイト
- 派遣社員
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①正社員
正社員は、従業員の中でも最も安定した働き方です。企業と無期雇用契約を結び、長期的な就労を前提としているため、給与や賞与、福利厚生が整っているケースが多いでしょう。
キャリア形成の機会も多く、組織の中心的な役割を担う立場です。例えば、社会保険や厚生年金に加入でき、退職金制度の対象となる場合もあります。
そのため生活基盤を築きやすい反面、責任の大きな仕事を任されやすく、労働時間や業務量が増える傾向も。また、多くの企業では正社員に昇給や昇進の機会を与えるため、成果や姿勢が評価に直結します。
日々の努力を継続できるかどうかが重要になるでしょう。結論として、正社員は安定と責任を兼ね備えた働き方です。
人事担当者は長期的な人材育成やキャリアパスを意識して採用や配置を考える必要があります。
②契約社員
契約社員は、雇用期間をあらかじめ定めて働く従業員です。雇用契約は更新制で、正社員に比べると安定性は低めです。
しかし、仕事内容や労働条件が契約時に明確に決まっているため、働く側にとっては将来の見通しが立てやすい特徴があります。
具体的には、短期的なプロジェクトや専門性を必要とする業務に契約社員が採用されることが多いです。
企業によっては正社員登用制度を設けており、勤務態度や成果次第で正社員への道が開かれる場合もあります。
一方で、契約更新がなければ雇用が終了するため、働き続けるうえで不安を感じることも少なくありません。企業側も更新や待遇に関して丁寧に説明する姿勢が求められます。
結論として、契約社員は「期間限定で専門性を活かす働き方」です。企業はその特性を理解し、双方にとって納得できる契約条件を提示することが大切になります。
③パートタイム
パートタイムは、短時間勤務を基本とした雇用形態です。勤務時間や日数を調整しやすく、家庭や学業と両立したい人にとって働きやすい環境を提供します。
ただし、給与や福利厚生は正社員よりも制限される場合が多いでしょう。それでも「同一労働同一賃金」の流れによって、近年は待遇格差の是正が進んでいます。この点は働く側にとって大きな安心材料です。
企業にとっても、必要な人員を柔軟に配置できるメリットがありますが、教育や評価の仕組みが整っていないとモチベーションが下がるリスクがあります。
そのため、短時間勤務でもしっかりと貢献度を認める制度が不可欠です。結論として、パートタイムは柔軟性が高い働き方でしょう。
人事担当者は公平な評価制度や働きやすい環境づくりを意識することが求められます。
④アルバイト
アルバイトは、短期間やシフト制で柔軟に働ける雇用形態です。学生や副業を希望する人が多く、接客や販売、軽作業など未経験でも挑戦しやすい仕事が中心になります。
大きなメリットは、働く時間を自由に調整できる点です。学業やプライベートを優先しやすいため、学生や若年層から支持されています。
ただし、給与やキャリア形成の面では制約が多く、長期的な安定を求めるには不向きです。企業にとっては、人件費を抑えながら人材を確保できる利点があります。
しかし、アルバイトは入れ替わりが多く、教育コストや引き継ぎが負担になる可能性もあるでしょう。結論として、アルバイトは短期的かつ柔軟な働き方を希望する人に適しています。
企業は短期間でもやりがいを感じてもらえる環境を意識することが重要です。
⑤派遣社員
派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で働く従業員です。雇用契約は派遣会社とあり、実際の業務は派遣先で行うという点が大きな特徴です。
働く側のメリットとしては、派遣会社を通じて自分に合った仕事を見つけやすいことが挙げられます。また、多様な職場を経験できるため、幅広いスキルを身につけやすい点も魅力です。
一方で、安定性は派遣元の契約内容に左右されます。派遣先では意思決定に関わる機会が少なく、キャリアアップにつながりにくい課題もあるのです。
結論として、派遣社員は柔軟な働き方や多様な経験を求める人に適しています。企業は受け入れ体制を整え、派遣社員の役割を明確にすることがスムーズな業務遂行につながるでしょう。
正規雇用のメリット

正規雇用には、安定した働き方や制度面の安心感など、就活生が将来を考えるうえで大切な要素が多く含まれています。
ここでは正規雇用を選ぶことで得られる代表的な利点を整理しました。キャリア選択の参考にしてください。
- 安定した雇用が得られる
- 社会保険や福利厚生が充実している
- 昇給や昇進の機会が多い
- 長期的なキャリア形成が可能
- 会社に対して信頼を得やすい
「自分らしく働ける会社が、実はあなたのすぐそばにあるかもしれない」
就活を続ける中で、求人票を見て「これ、ちょっと興味あるかも」と思うことはあっても、なかなかピンとくる企業は少ないものです。そんなときに知ってほしいのが、一般のサイトには載っていない「非公開求人」。
①あなたの強みを見極め企業をマッチング
②ES添削から面接対策まですべて支援
③限定求人なので、競争率が低い
「ただ応募するだけじゃなく、自分にフィットする会社でスタートを切りたい」そんなあなたにぴったりのサービスです。まずは非公開求人に登録して、あなたらしい一歩を踏み出しましょう!
①安定した雇用が得られる
正規雇用の最大の特徴は、安定した雇用を得られる点です。非正規雇用と異なり契約期間に制限がなく、長期的に働ける安心感があります。この安定は生活の基盤を築くうえで欠かせないものでしょう。
例えば住宅ローンの審査や賃貸契約では、正規雇用であることが社会的信用として評価されやすいです。
さらに、経済状況が変化しても契約終了で職を失う心配が少なく、将来設計を立てやすい利点もあります。
ただし、安定に依存しすぎると成長の機会を逃すおそれもあるため、自ら学び続ける姿勢を持つことが重要です。
このように正規雇用は生活とキャリアに強い安定をもたらし、安心感を基盤に新たな挑戦へとつなげられる働き方だといえます。
②社会保険や福利厚生が充実している
正規雇用で働くと、健康保険や厚生年金といった社会保険に加入でき、福利厚生も整っているのが一般的です。これにより病気やけがをした際の医療費負担が軽くなり、将来の年金も安定します。
さらに住宅手当や交通費、育児休暇や研修制度など、生活を支える制度が利用できるでしょう。非正規雇用では制度が十分に整っていないことも多く、安心して働き続けるには不安が残りやすいです。
そのため、制度の充実度は就職先を選ぶ際の大きな判断材料になります。ただし、会社ごとに内容が異なるため、入社前に確認を怠らないことが大切です。
結果として、社会保険や福利厚生の充実は生活と将来を守る大きな支えとなり、働く人の安心感を高めてくれるでしょう。
③昇給や昇進の機会が多い
正規雇用では、昇給や昇進の機会が用意されている場合が多いです。長期雇用を前提に企業は人材育成に力を入れており、成果に応じて報酬や役職を上げる仕組みを整えています。
これは非正規雇用では得にくいメリットでしょう。昇給や昇進は努力が形として評価される経験になり、働く意欲を高めてくれます。
ただし、すべての企業が公平な評価制度を持つとは限らず、年功序列が強く残る職場もあるのです。その場合は成果を出してもすぐに報われないこともあるでしょう。
それでも正規雇用では挑戦できる場が多く与えられ、キャリアを積み重ねやすいのは確かです。正規雇用は努力が評価につながる仕組みを通じて、成長とやりがいを実感できる働き方といえます。
④長期的なキャリア形成が可能
正規雇用は、長期的なキャリア形成に適した環境を提供します。会社に継続的に在籍できるため、業務経験を積み重ね、専門性を高めながら成長できるのが特徴です。
数年ごとの異動や新規プロジェクトへの参加を通じて、多様なスキルを習得する機会が得られるでしょう。こうした経験は市場価値を高め、転職や独立を考える際にも強みになります。
ただし、同じ会社に長く勤めると環境に慣れすぎ、外の世界を知るきっかけを失う危険も。そのため、正規雇用で働きながらも社外の情報に触れ続ける姿勢が欠かせません。
結果的に、正規雇用はキャリアを計画的に築くための基盤となり、自分の可能性を広げる土台になるでしょう。
⑤会社に対して信頼を得やすい
正規雇用は、会社に対して信頼を得やすい働き方です。長期的に働く意思を示すことで、企業は安心して重要な業務や責任を任せやすくなります。
その結果、プロジェクトのリーダーや後輩の指導など責任ある役割を担う場面が増えるでしょう。さらに、信頼を得ることは職場での人間関係を円滑にし、働きやすさにもつながります。
ただし、信頼は自動的に得られるものではなく、日々の姿勢や成果の積み重ねが必要です。努力と誠実さを持ち続けることで信頼は強固なものとなり、評価も高まっていきます。
このように正規雇用は、会社との信頼関係を築きやすくし、キャリアの安定と発展を支える重要な働き方だといえるでしょう。
非正規雇用のメリット

非正規雇用は正規雇用に比べて安定性は劣りますが、生活スタイルに合わせて働きやすい点が大きな魅力です。
ここでは、非正規雇用ならではのメリットを整理し、人事担当者や求職者が理解しておくべきポイントを解説します。
- 働く時間や曜日を柔軟に選べる
- 学業や家庭と両立しやすい
- 副業との兼ね合いがしやすい
- 責任や業務負担が軽い
- 多様な職場を経験できる
①働く時間や曜日を柔軟に選べる
非正規雇用の大きな特徴は、勤務時間や曜日を自由に選べることです。子育て中の方や学業を優先したい学生にとって、シフトを調整できるのは安心につながります。
短時間勤務や週数日の出勤を選べるため、正規雇用に比べてワークライフバランスを取りやすいでしょう。ライフイベントが多い時期でもキャリアを継続できる点は大きな利点です。
一方で、シフトが安定しないと収入が不安定になる可能性があります。そのため、企業側は継続して働きやすい仕組みを整えておくことが大切です。
結論として、非正規雇用は自由度の高い働き方。働く人にとっても企業にとっても柔軟に対応できる体制を築くことが重要になるでしょう。
②学業や家庭と両立しやすい
非正規雇用は、学業や家庭との両立を考える人に向いています。学生であれば授業や試験に合わせて勤務日を調整でき、主婦や主夫であれば家事や育児の合間に働くことが可能です。
生活を優先しながら収入を得られるため、安心して働けるのが大きな強み。また、家庭や学業を大切にしながら社会とのつながりを保てるのも魅力でしょう。
ただし、長時間働けない分、収入は限定的になります。企業側も従業員が安心して続けられるよう、サポート体制を整えることが欠かせません。
結論として、非正規雇用は無理なく生活と仕事を両立させたい人に適した選択肢です。働く側も将来のキャリアを意識して経験を積むことが望ましいでしょう。
③副業との兼ね合いがしやすい
非正規雇用は副業を考えている人にとって働きやすい環境です。正規雇用のように勤務時間が固定されにくいため、別の仕事と両立しやすいでしょう。
たとえば、平日はパートとして働き、休日にフリーランスの仕事をする人も増えています。
副業で得た経験は新しいスキル習得につながり、長期的にはキャリアチェンジや正社員登用のチャンスを広げる可能性にもなるのです。
ただし、副業が本業に影響しないよう、企業側もルール作りを進める必要があるでしょう。結論として、非正規雇用は柔軟に働きたい人にとって副業との相性が良い働き方です。
働く人は複数の仕事を通してキャリアを広げる意識を持つことが大切でしょう。
④責任や業務負担が軽い
非正規雇用は正規雇用に比べて責任や業務負担が軽い傾向があります。重要な意思決定やマネジメントを任されることは少なく、決められた業務をこなす役割が中心です。
そのため、精神的なプレッシャーが少なく働けるのが魅力でしょう。特に未経験の分野に挑戦したい人や短期間だけ働きたい人にとっては安心できる環境です。
ただし、責任が軽い分、キャリアアップの機会は限られやすいです。働き手は自らスキルを磨き、成長を意識する必要があります。
結論として、非正規雇用は精神的負担を抑えたい人に適しているのです。安心感を得やすい一方で、将来に備えて自己成長を意識することが欠かせません。
⑤多様な職場を経験できる
非正規雇用は、多様な職場を経験できる点も魅力です。さまざまな業種や職場に関わることで、短期間でも幅広いスキルや知識を身につけやすいでしょう。
異なる職場を経験することで柔軟な考え方が養われ、将来のキャリア選択の幅を広げることができます。
例えば、接客や事務、製造など複数の現場を経験することで総合的な視点を持てるようになるでしょう。企業にとっても、多様な経験を持つ人材の存在は新しい発想を取り入れるきっかけになります。
結論として、非正規雇用は成長しながら幅広い経験を積みたい人にとって有益な選択肢です。働く側は積極的に挑戦を重ね、自分の強みを広げていくことが望まれます。
従業員が加入すべき保険の種類
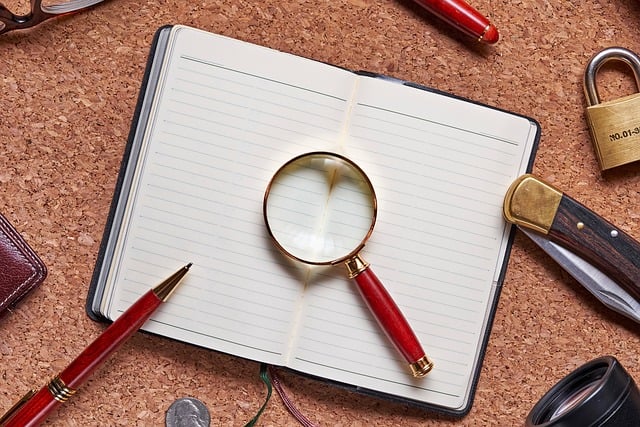
企業が従業員を雇うときには、社会保険や労働保険への加入が必要です。これらは従業員の生活を守ると同時に、会社の義務を果たすためにも欠かせません。
ここでは代表的な保険の種類を紹介し、それぞれの役割をわかりやすく解説します。
- 労災保険
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
①労災保険
労災保険は、従業員が仕事中や通勤中にけがや病気をしたときに補償を受けられる制度です。従業員を1人でも雇えば会社に加入義務があり、保険料は全額会社負担となります。
もし事故で治療費や休業補償を自費でまかなうことになれば、大きな負担になるでしょう。そのため労災保険は従業員にとって安心材料であり、企業にとっても信頼を得やすくなる仕組みです。
ただし私的な理由によるけがなどは対象外になるため、制度に頼りきらず事故防止に努める必要があります。
結果的に、労災保険は従業員の生活を支える基盤であり、企業が果たすべき大切な責任といえるでしょう。
②雇用保険
雇用保険は、従業員が失業したときや育児休業を取るときに給付を受けられる制度です。正規雇用だけでなく、条件を満たすパートやアルバイトも対象になります。
会社と従業員が保険料を分担し、安心して働ける環境を整える役割を持っているのです。特に失業時には基本手当が支給され、次の仕事を探すまでの生活を支えてくれるでしょう。
さらに育児や介護休業の給付もあり、ライフイベントに合わせた柔軟な働き方を後押しします。一方で、短時間労働など条件を満たさない場合は加入できません。
企業は対象となる従業員を正しく把握し、漏れなく手続きを進めることが欠かせないのです。結果として、雇用保険は働く人の生活を支えると同時に、会社の信頼性を高める制度といえるでしょう。
③健康保険
健康保険は、従業員が病気やけがで医療を受けるときに費用負担を軽くする制度です。正社員だけでなく、一定条件を満たす非正規雇用者も対象になります。
自己負担が3割に抑えられるため、医療費の不安を減らせる点が大きな利点でしょう。さらに扶養家族も対象になるため、家庭全体の安心につながります。
保険料は会社と従業員で折半し、協会けんぽや健康保険組合に加入して運用します。ただし、組合ごとに給付内容が異なることもあるため、詳細を理解しておくことが大切です。
もし加入がなければ高額な医療費を自己負担しなければならず、生活への影響は大きいでしょう。健康保険は従業員の安心と会社の責任を支える中心的な制度といえます。
④厚生年金保険
厚生年金保険は、老後や障害を抱えたときに年金を受け取れる制度です。国民年金に上乗せされる形で支給されるため、将来の生活安定に直結します。
保険料は会社と従業員で折半し、長く加入するほど将来の受給額も増えていく仕組みです。正社員だけでなく、週20時間以上働くなど一定条件を満たす非正規雇用者も対象となります。
厚生年金に加入していれば、老後の生活だけでなく、病気やけがで働けなくなった場合や遺族の生活を支える保障も受けられるでしょう。
ただし、企業が適切に手続きを行わないと従業員が不利益を受けるおそれがあります。人事担当者は加入条件を正しく判断し、確実に対応してください。
厚生年金保険は将来設計に直結する重要な制度であり、従業員と企業双方に欠かせない仕組みです。
⑤介護保険
介護保険は、40歳以上の従業員が加入する制度で、要介護状態になったときにサービスを利用できるようにするものです。介護費用の一部を公的に補助し、本人や家族の負担を軽減します。
健康保険や厚生年金と一体で運用され、保険料は従業員と会社で分担します。少子高齢化が進む今の社会では、介護保険の役割はますます大きいでしょう。
従業員にとっては将来の介護リスクに備える安心となり、家族の負担を減らす助けにもなります。ただし40歳未満では対象外となるため、制度の存在を知らない若手社員も少なくありません。
人事担当者は制度の内容を丁寧に伝え、理解を深めてもらうことが大切です。介護保険は高齢化社会を支え、従業員の安心を守る不可欠な制度といえるでしょう。
社員・従業員を雇用する際に必要な手続き

社員や従業員を雇うときには、必ず行うべき手続きがあります。これを正しく理解していないと法令違反やトラブルにつながりかねません。
ここでは雇用開始時に必要となる代表的な手続きを整理します。
- 労働契約書を作成・締結
- 労働保険への加入
- 雇用保険の資格取得
- 社会保険の資格取得
- 従業員名簿や賃金台帳の整備
①労働契約書を作成・締結
雇用の基本となるのが労働契約書です。労働条件や業務内容を明確に記載し、会社と従業員双方が確認して署名することで契約が成立します。
これを省略すると、条件を巡るトラブルが起きやすいでしょう。
勤務時間や休日、給与の額や支払い方法、試用期間の有無などを必ず明示する必要があります。口頭の約束だけでは誤解を招きやすいため、必ず書面にしてください。
労働契約書を整備しておけば、従業員も安心して働ける環境を得られます。信頼関係が築かれ、定着率の向上にもつながるでしょう。
②労働保険への加入
次に必要なのが労働保険の加入手続きです。労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼びます。労災保険は業務中や通勤中の事故に備える制度で、従業員を雇う以上は必ず加入が求められるのです。
未加入のまま事故が起きれば、企業は大きな責任を負うことになります。さらに、加入を怠れば罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
労働保険の加入は労働基準監督署や公共職業安定所で行います。正しく手続きを済ませることが、従業員の安全と企業の信頼を守る第一歩になるでしょう。
③雇用保険の資格取得
従業員を新しく雇った場合は、雇用保険の資格取得手続きを行う必要があります。雇用保険は失業時に給付を受けられる制度で、従業員の生活を支える重要な仕組みです。
手続きは雇用開始から10日以内に行わなければなりません。期限を過ぎると遡って処理する必要があり、企業にとっても余計な手間や信用低下につながるでしょう。
雇用保険をきちんと整備しておくことは、従業員にとって安心できる環境を提供することにつながります。企業にとっても信頼性の向上に役立つでしょう。
④社会保険の資格取得
正社員や一定の条件を満たすパートタイム労働者は、社会保険への加入が義務付けられています。社会保険には健康保険や厚生年金保険が含まれており、従業員の生活を守る基盤となるのです。
加入手続きは年金事務所で行います。もし加入を怠れば、従業員に不利益を与えるだけでなく、企業側も法的な責任を問われる可能性があるでしょう。
社会保険をきちんと整備しておくことは、福利厚生の充実や採用力の向上にもつながります。従業員が安心して働ける環境を提供するためにも、迅速に手続きを進めてください。
⑤従業員名簿や賃金台帳の整備
最後に、従業員名簿や賃金台帳の整備も欠かせません。従業員名簿には住所や生年月日、雇用開始日などを記録し、賃金台帳には給与の支払い状況を明確に残す必要があります。
これらの書類は労働基準法で作成と保存が義務付けられており、監査の際には提出を求められることも。不備があれば法令違反とみなされるでしょう。
正確な台帳を整備しておくことは、管理の効率化や透明性の確保につながります。信頼される組織運営を実現するためにも、必ず整えてください。
社員と従業員の違いを理解する意義

社員と従業員の違いを正しく理解することは、欠かせません。社員は一般的に正規雇用の人を指す一方、従業員は契約社員やアルバイト、派遣社員まで含む広い概念です。
この違いを把握することで、雇用形態ごとのメリットやリスクを正しく認識でき、労務管理や制度設計の精度が高まります。
さらに、社会保険や労働保険の加入義務、手続きの流れを理解することは企業にとって法的リスクを回避するうえでも重要です。
結論として、社員と従業員の区別を押さえたうえで雇用制度を整えることが、企業と働く人双方の安心と信頼を築く第一歩となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














