大学を卒業できない時の対処法|内定や再就活の選択肢を解説
大学を卒業できないかもしれない不安を抱えたとき、将来への影響を強く心配する人は少なくありません。実際、卒業要件を満たせないケースは珍しくなく、適切な対処を取れば進路の選択肢は残されています。
この記事では、大学が卒業できない場合に考えられる原因や解決策を整理し、内定や再就活に向けて取るべき行動を具体的に解説します。焦らず冷静に判断するための参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
大学が卒業できないと諦める前にできることを考えよう

大学の単位が足りない、進級が難しいと感じると、就職活動にも大きな不安を抱えてしまうものです。しかし「卒業できないかもしれない」と思った時点で諦めてしまうのは早いでしょう。
実際には、大学側の制度や教授との相談、履修計画の見直しによって解決できるケースも少なくありません。大切なのは、問題を先送りにせず現実的な対応策を冷静に考えることです。
まず、卒業に必要な条件を確認し、不足している点を明確にしてください。その上で、追加履修や集中講義の活用を検討すると道が開ける場合もあります。
卒業できるか不安を感じたときほど、一人で抱え込まない姿勢が重要です。早めの情報収集と行動が未来を守る鍵となります。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
大学を卒業できないときの対処法

大学を卒業できないと気づいたとき、多くの学生は不安や焦りを抱くでしょう。ただ、冷静に状況を整理して、できることを一つずつ行えば道は残されています。
ここでは、取るべき具体的な手段や相談先を紹介するので、今すぐ実行に移してください。
- 追加の単位取得や再試験の可能性を確認する
- 教授や学生課に相談しサポートを受ける
- 成績不服申し立てや救済制度を調べる
- 資格やインターンで単位に代替できないか確認する
- 卒業できないと確定した場合は企業に早めに連絡する
①追加の単位取得や再試験の可能性を確認する
卒業が危ういと分かったとき、まず調べるべきは追加の単位や再試験の可否です。大学によっては補講や再試験の申請期間があり、担当教員に相談すると救済措置を受けられる場合があります。
諦める前にシラバスや掲示板を確認し、学部事務に問い合わせてみてください。再試験は締め切りが短いため、早い行動が結果を左右します。
また、集中講義や他学部の科目を履修できることもあり、足りない単位を補える可能性があるでしょう。
就活中で気持ちが不安定になることもありますが、卒業判定は直前まで変わるため、取れる手段をすべて試す姿勢が安心につながるはずです。
②教授や学生課に相談しサポートを受ける
自分の判断だけで動くよりも、教授や学生課に相談する方が解決の道が見えることが多いです。教授は授業態度や課題提出の状況を把握しており、追加レポートや課題で成績を改善できることがあります。
学生課は制度や履修の調整方法に詳しく、学生本人では思いつかない選択肢を示してくれるかもしれません。大学には学生を卒業に導く仕組みがあるので、相談をためらう必要はないのです。
就活中の学生にとっては、問題を抱え込むよりもサポートを受ける方が気持ちの整理もしやすく、前に進むきっかけになるでしょう。
③成績不服申し立てや救済制度を調べる
成績に納得できない場合や、理不尽な理由で単位を落とした場合は、成績不服申し立て制度を利用できる可能性があります。
多くの大学では一定期間内に申請すれば、試験内容や評価基準の確認を求められるのです。必ず変更されるわけではありませんが、正当な理由があれば見直されることもあります。
また、病気や家庭の事情がある学生を対象にした救済制度がある大学もあり、不利な状況に置かれていた場合は認められることも。
自分が対象となる制度があるかを調べることで、単位取得の最後の望みをつなげることができるでしょう。
④資格やインターンで単位に代替できないか確認する
一部の大学では資格試験の合格やインターン経験を単位として認めています。
英語検定や簿記、IT関連資格などが授業と同等の扱いになることがありますし、長期インターンやボランティア活動が実習科目として単位換算される場合も。
こうした仕組みを利用すれば、不足した単位を補う手段になります。特に就活中の学生にとっては、インターン経験そのものが企業から評価されるため有利に働くでしょう。
ただし制度の有無は大学や学部で異なるため、履修要項や学生課で必ず確認してください。
⑤卒業できないと確定した場合は企業に早めに連絡する
最終的に卒業ができないと決まった場合は、内定先や応募企業に早めに連絡してください。
卒業を前提とした内定は取り消しになることが多いため、放置すると信頼を失うだけでなく、再就活にも悪影響を与えます。
正直に状況を伝える姿勢が大切であり、企業によっては再応募や翌年の採用を案内してくれることも。誠実に報告すれば、信頼を残すことにつながり、次のステップへ進む準備も早めに整うはずです。
勇気を出して伝えることで、将来に向けて一歩を踏み出せるでしょう。
大学を卒業できないときに避けたいNG行動

大学を卒業できない可能性が見えてきたとき、焦りから誤った行動を取ってしまう学生は少なくありません。
ここでは、就活生が陥りやすいNG行動を整理し、それぞれの問題点と適切な対応について解説します。冷静に状況を整理することで、内定や今後の進路に悪影響を及ぼさないようにしましょう。
- 卒業できない事実を隠してしまう
- 企業への連絡を遅らせる
- 安易に内定を辞退してしまう
- 中退して無理に入社しようとする
- 卒業要件の確認を怠る
①卒業できない事実を隠してしまう
卒業できない可能性を隠して就職活動を続けることは、最も避けたい行動です。なぜなら、最終的に企業へ事実が伝わったとき「誠実さに欠ける」と判断され、信頼を失ってしまうからです。
たとえ一時的に採用が進んでも、入社手続きで学歴確認が行われれば必ず発覚します。その場合、内定取り消しだけでなく再就活にも不利に働くでしょう。
正しい対応は、事実を隠さず早めに相談することです。企業側も学生の状況を理解し、柔軟に対応してくれる場合があります。正直に伝えることで「誠実な人」と評価される可能性もあるでしょう。
隠すのではなく伝える姿勢こそが、自分を守る方法になります。
②企業への連絡を遅らせる
卒業できない可能性が高くなったとき、企業への連絡を後回しにするのは大きなリスクです。時間が経つほど企業側の選択肢が減り、混乱を招くからです。
入社直前に告げても、代替要員を用意できず企業に迷惑をかけてしまい、学生への印象も悪化します。その結果、今後の採用選考にも響くかもしれません。
これを防ぐには、状況がわかった時点で速やかに伝えることが大切です。たとえ確定でなくても「卒業要件の一部に不安がある」と報告すれば誠意は伝わります。
早めに行動すれば入社時期の調整や内定保留など、選択肢が広がるでしょう。連絡を遅らせるのは、自分の可能性を狭める行為と心得てください。
③安易に内定を辞退してしまう
卒業が難しいと感じた途端に、深く考えず内定を辞退するのも避けたい行動です。なぜなら、実際には大学の救済措置や追加履修で卒業が可能な場合があるからです。
せっかく得た内定を手放すと、再就活でゼロからやり直さなければならず、精神的にも負担が大きくなります。まずは大学の教務課や教授に相談し、卒業できる可能性を正しく把握してください。
そのうえで企業に状況を伝えれば、留年して翌年入社という選択肢を提案される場合もあります。辞退は最後の手段であり、他の可能性をすべて確認してから判断するのが賢明です。
軽率に辞退するのは避けるべきでしょう。
④中退して無理に入社しようとする
大学を中退してでも内定先に入社しようとするのは、一見すると責任感のある選択に見えるかもしれませんが、実際には危険な判断です。
中退は将来のキャリア全体に影響し、学歴面で不利になることがあります。さらに、企業によっては「大卒」が条件のため、中退では入社できない可能性も高いでしょう。
中退するよりも、留年して卒業を目指す方が長期的に有利です。卒業できれば「やり遂げた」と評価され、信頼度も高まります。
短期的に入社を急ぐあまり中退を選ぶと、結果的に将来の選択肢を狭めることになりかねません。焦らず、長い目で判断してください。
⑤卒業要件の確認を怠る
卒業できない原因の多くは、単位や要件の確認不足にあります。必要な単位数や必修科目を正しく把握していなければ、知らないうちに卒業が難しくなるのです。
特に、専門科目や必修の取りこぼしは後から挽回しにくく、最終学年で気づく学生も少なくありません。こうした落とし穴を避けるには、早めから卒業要件を定期的に確認することが必要です。
履修計画を立てる際は、学期ごとに教務課で相談し、進捗をチェックしてください。疑問があれば教授や先輩に聞くことも有効です。確認を怠ることは卒業できない直接の原因になります。
普段から意識して行動することが重要です。
大学を卒業できないときに使える企業への連絡方法

大学を卒業できないと分かったとき、内定先や応募中の企業にどう伝えるか迷う人は多いでしょう。誠実さを示しながら冷静に対応することが、信頼を保つために大切です。
ここでは3つの連絡方法を取り上げ、それぞれの利点と注意点を整理します。
- 電話で直接伝える
- メールで要点を整理して伝える
- 面談を依頼する
①電話で直接伝える
卒業できないことを企業へ伝える際、最も誠意が伝わりやすいのは電話です。声で直接伝えることで、文字では表現しにくい真剣さや誠実さを示せます。特に内定先には電話での連絡が望ましいでしょう。
企業は採用計画に影響を受けるため、迅速で明確な情報共有が必要だからです。電話をかける前に、伝える内容を簡潔に整理しておくことが重要。
卒業が難しくなった経緯を短く説明し、そのうえで今後の進路について相談する姿勢を示してください。冷静なトーンで話すと、相手にも誠意が伝わりやすいでしょう。
②メールで要点を整理して伝える
電話に加えて、状況を整理して残したい場合はメールも有効です。相手の時間を拘束せず伝えられるので、採用担当者が確認しやすい方法といえます。
メールでは「卒業できない事実」「理由」「今後の対応」の3点を明確に記載してください。
例えば「必要単位が不足し卒業が困難になった」と冒頭で伝え、その後に簡潔な経緯、最後に「今後について相談したい」と締めるのが適切です。長文を避け、簡潔にまとめることが大切。
送信後に電話で補足すると、より誠意が伝わりやすくなるでしょう。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
③面談を依頼する
丁寧に説明したい場合は、企業に面談を依頼して直接会って伝える方法もあります。電話やメールでは十分に伝えられない思いを、対面で誠実に話すことができるでしょう。
特に内定先に再応募を希望する場合や、関係を良好に保ちたいと考えるときに有効。ただし、面談は相手の時間をいただくものなので「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と配慮を示してください。
対面であれば、相手の反応を確かめながら説明でき、誤解も減らせます。厳しい事実を伝える場面ですが、真摯な対応が結果的に今後の就職活動にも良い影響を与えるはずです。
大学を卒業できない場合に企業が取る対応方法

大学を卒業できないことがわかったとき、就活生にとって最も気になるのは「企業がどう対応するのか」という点でしょう。
実際には、企業ごとに対応は異なり、有利になる場合もあれば厳しい判断をされることも。ここでは代表的な対応を整理し、それぞれの意味や注意点をわかりやすく解説します。
- 入社時期を半年遅らせる
- 翌年度の採用試験を勧める
- 卒業できなくても入社を認める
- 条件次第で内定を継続する
- 内定を取り消す
①入社時期を半年遅らせる
企業が柔軟に対応する方法の1つが、入社時期を半年遅らせる措置です。これは秋卒業や留年に合わせて入社をずらす方法で、学生にとって大きな救済策になります。
企業側も採用した人材を確保できるため、前向きに採用される場合があるでしょう。ただし可能かどうかは人員計画や事業の都合によって変わります。
早めに状況を伝えれば「半年後に入社を調整しよう」という判断を得やすいでしょう。反対に報告が遅れると準備ができず、選択肢が限られてしまいます。誠実に相談する姿勢が、解決への近道です。
②翌年度の採用試験を勧める
卒業が1年以上先になる場合、企業から翌年度の採用試験を受け直すように勧められることがあります。これは内定を保留にするよりも、新卒枠で再挑戦してもらう方が合理的だと判断されるからです。
学生にとって厳しく感じるかもしれませんが、「内定を取り消すのではなく再挑戦の機会をくれる」と考えれば前向きに捉えられるでしょう。
過去の評価がプラスに働き、再選考がスムーズになる場合もあります。大切なのは誠実に説明し、翌年度の挑戦に前向きな姿勢を示すことです。
③卒業できなくても入社を認める
一部の企業では、学歴よりもスキルや適性を重視し、卒業できなくても入社を認めるケースがあります。
特にベンチャー企業や専門性の高い業界では、実力が評価されれば学歴要件にこだわらないこともあるのです。ただし多くの企業は「大卒」を条件にしているため、これは例外的な対応に過ぎません。
安易に期待するのではなく、自分の能力や経験がどの程度評価されるかを冷静に見極める必要があります。ごく一部のケースであることを理解しておくことが大切です。
④条件次第で内定を継続する
企業によっては「条件付きで内定を継続する」という方法を取ることがあります。
例えば「次年度に卒業見込みであること」「一定の単位を取得していること」といった条件を満たせば、内定が維持される仕組みです。
企業は人材を確保しつつリスクを減らし、学生にとっても可能性を残せる制度といえるでしょう。ただし条件を満たせなければ取り消しとなるため、履修計画を確実に進めなければなりません。
条件付き内定を得た場合は、勉強を最優先にして必ず達成してください。
⑤内定を取り消す
残念ながら、卒業できない場合には内定を取り消される可能性もあります。特に「大卒」を必須とする企業では、この対応が一般的です。企業側にとって採用条件を満たさないため、例外を設けにくいのです。
内定取消は厳しい現実ですが、その後の行動次第で新たな道を開くことができます。再就活を始める、既卒採用に挑戦する、資格取得で専門性を高めるなど選択肢はあります。
大切なのは取り消しを恐れて事実を隠すのではなく、誠実に対応することです。その姿勢が次のステップを有利に進める力になるでしょう。
大学を卒業できないときに使える企業への連絡例文
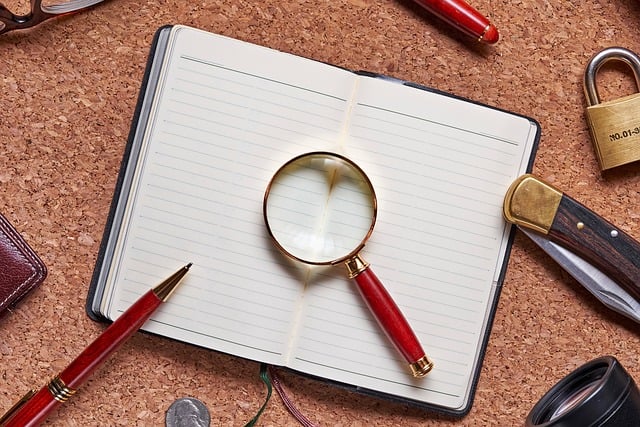
卒業が難しい状況では、企業への連絡の仕方に迷う人も多いでしょう。ここでは、実際に使える例文を通じて誠実に伝える方法をまとめました。
入社時期を延ばしてもらえるか相談する例文
大学の単位を取りこぼしてしまい、予定通りに卒業が難しくなるケースは珍しくありません。そのようなとき、企業に対して誠実に事情を伝え、入社時期を相談することは大切です。
ここでは、そのような状況で使える例文を紹介します。
《例文》
| このたびは内定をいただき誠にありがとうございます。大変心苦しいご連絡となりますが、必修科目の単位が不足しており、今年度中に卒業できない可能性がございます。 現在、追加履修や再試験の申請を行っており、卒業は半年後になる見込みです。つきましては、もし可能であれば入社時期を半年延ばしていただけないかご相談させていただきたく存じます。 ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんが、今後も御社で働く強い意志に変わりはございません。どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
《解説》
この例文は、不安な気持ちを抱えながらも誠実に状況を伝える姿勢を示しています。相談文を書く際は「事実」「見込み」「意志」の3点を明確に入れることを意識してください。
卒業が遅れる事情を正直に伝える例文
卒業が予定通りにできないとわかったとき、企業への連絡で大切なのは正直さです。
特に、家庭の事情や体調不良など身近な理由で単位が不足してしまった場合、隠さず説明することが信頼につながるでしょう。ここでは、卒業が遅れる理由を誠実に伝えるための例文を紹介します。
《例文》
| 内定をいただき誠にありがとうございます。このたびは大切なお時間をいただきながら、心苦しいご報告をすることになり申し訳ございません。 実は、昨年度に体調を崩してしまい出席が足りず、必修科目の単位を落としてしまいました。そのため、今年度の卒業が難しくなり、来年度の春に卒業予定となります。 現在は体調も安定し、学業にも問題なく取り組めております。御社で働く気持ちは変わらず強く持っておりますので、もし可能であれば状況を踏まえたうえでご相談させていただければ幸いです。 |
《解説》
この例文では、事情を具体的に伝えつつ「今は改善していること」を明記しています。同じテーマで書く場合は「理由」と「現状改善」をセットで示すことが効果的です。
内定辞退を伝える例文
卒業が難しくなったとき、どうしても内定を維持できない場合があります。その際は、感謝の気持ちをしっかり伝えたうえで、誠実に辞退の意思を示すことが重要です。
ここでは、そのような場面で活用できる例文を紹介します。
《例文》
| このたびは内定をいただき、心より御礼申し上げます。大変申し訳ございませんが、必修科目の単位を落としてしまい、卒業が予定通りにできない状況となりました。 大学とも相談しましたが、来年度に履修を重ねる必要があるため、御社の入社時期に間に合わせることができません。このような事情から、内定を辞退せざるを得ない結論に至りました。 せっかくのご縁をいただきながら、このようなご連絡となり本当に心苦しく思っております。御社のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
《解説》
この例文では「感謝」「理由」「謝罪」を順序立てて伝えています。内定辞退を伝えるときは、一方的な断り方ではなく誠意を込めることが信頼維持につながるのです。
卒業の目処を説明し協力をお願いする例文
卒業が遅れると確定した場合でも、その見通しをきちんと伝えれば企業に理解を得られることがあります。
特に、卒業時期が明確に見えている場合は、その計画を説明しつつ協力をお願いすることが大切です。ここでは、そのような場面で活用できる例文を紹介します。
《例文》
| このたびは内定をいただき、誠にありがとうございます。大変恐縮ではございますが、必修科目の履修が遅れており、当初の予定どおり今年度内の卒業ができなくなりました。 現在は教務課と相談のうえ、必要な単位をすでに履修登録しており、来年3月には必ず卒業できる見込みです。御社で働く意欲に変わりはなく、これまで以上に努力を重ねております。 つきましては、卒業時期の変更を踏まえ、入社に関してご相談させていただければ幸いです。ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。 |
《解説》
この例文では「卒業の見通し」を具体的に示してから協力をお願いしています。同じテーマで書く場合は、曖昧な表現を避け、確定したスケジュールを明記することが効果的です。
謝罪と今後の行動方針を伝える例文
卒業が予定どおりに進まないとき、企業へはまず誠意を持って謝罪し、そのうえで今後の行動を明確に伝えることが重要です。ここでは、そのような状況に適した例文を紹介します。
《例文》
| このたびは内定をいただき、誠にありがとうございます。心苦しいご報告となりますが、必修科目の単位を落としてしまい、今年度中の卒業が難しくなってしまいました。 大変なご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。現在は追加履修や再試験に向けて準備を進めており、来年3月には卒業できる見込みです。 今後は学業を最優先に取り組み、再発防止のため計画的な学習を徹底いたします。御社で働く強い意志は変わりませんので、どうか状況をご理解いただき、ご相談の機会をいただければ幸いです。 |
《解説》
この例文では「謝罪」「状況説明」「今後の行動」の順に整理しています。同じテーマを書くときは、謝罪だけで終わらせず改善策を添えることで信頼感を高められます。
大学を卒業できずに内定取り消しになった場合の選択肢

大学を卒業できず内定を失ったとき、大きな不安や焦りを抱く人は少なくありません。しかし就職の道はひとつではなく、複数の選択肢が存在するのです。
ここでは考えられる進路を整理し、それぞれの特徴や注意点を紹介します。
- 就職留年を選ぶ
- 就職浪人として翌年の採用を目指す
- 資格取得やスキルアップに専念する
- フリーランスとして働く
- 起業に挑戦する
①就職留年を選ぶ
卒業できなかった場合、最も一般的なのが就職留年です。大学に在籍し続けることで翌年の新卒採用に挑戦でき、学生という立場を維持できるのが大きな利点でしょう。
多くの企業は新卒枠を前提にしているため、この方法なら応募条件を満たしやすくなります。また留年中に足りなかった単位を取り、卒業を確実にできる点も魅力です。
ただし学費や生活費の負担が増えるため、家族との相談や資金計画が欠かせません。準備期間と捉えて過ごせば、次の就職活動を有利に進められるでしょう。
②就職浪人として翌年の採用を目指す
大学を卒業後に進学せず、翌年の採用を目指す方法が就職浪人です。学生という肩書きはなくなりますが、自由に時間を使えるため、自己分析や業界研究を深める良い機会になります。
前回の就活で準備不足を感じた人にとっては、力を磨き直す時間になるでしょう。ただし浪人期間は経歴に空白が生まれるため、面接で理由を問われることがあります。
その場合は「卒業に専念した」「資格取得に挑戦した」など前向きな説明を用意してください。不安は伴いますが、戦略的に過ごせば次の就職活動をより強固なものにできるはずです。
③資格取得やスキルアップに専念する
内定が取り消された時間を、資格取得やスキル習得に充てる選択も有効です。語学やIT、簿記といった資格は評価されやすく、就職活動で強みとして活かせます。
専門スキルを磨けば正社員以外にも契約社員や派遣社員の道が広がり、働き方の幅が広がるでしょう。さらに「学び続ける姿勢」は企業にとって成長意欲のある人材と映ります。
ただ資格を取るだけで満足せず、実際のキャリアにどう結びつけるかを考えることが重要です。目的を明確にして取り組めば、次の就活で自信を持ってアピールできるでしょう。
④フリーランスとして働く
卒業後にフリーランスとして働く道もあります。プログラミングやデザイン、ライティングなど特定のスキルがあれば、仕事を得ることは可能です。
自分の裁量で働ける点や収入に上限がない点は魅力でしょう。ただし安定性に欠け、生活を整えるまでに時間がかかることも少なくありません。
さらに実績がないと仕事を得にくく、最初は小さな案件から積み上げる必要があります。その一方で、就職活動に戻る際には「実務経験」や「自己管理能力」として評価されることもあります。
挑戦心がある人にとっては成長の機会となるでしょう。
⑤起業に挑戦する
大きな挑戦になりますが、起業という選択肢も存在します。学生時代の研究や活動を基盤に事業を立ち上げるケースもあり、自由な発想を活かせるでしょう。
成功すれば早い段階で経営経験を積めるのは大きな強みです。ただしリスクは高く、資金や人脈、ビジネスモデルの検証など多くの課題が待ち受けます。
失敗した場合の再就職も見据えておく必要があるでしょう。それでも起業経験は「挑戦心」や「行動力」として評価されることがあり、将来のキャリアにプラスに働く可能性があります。
計画的に取り組めば、大きな成長のきっかけになるはずです。
大学を卒業できないときの再就活ステップ

卒業できないと分かったとき、落ち込む気持ちにとらわれる人も多いでしょう。しかし冷静に行動を立て直せば、新しい道を開くことは可能です。再就活では計画性と行動力が鍵となります。
ここでは具体的なステップを紹介します。
- 不足単位数を確認しスケジュールを立て直す
- キャリアの方向性を整理し企業を絞る
- 資格取得やインターンで経験を積む
- 再就活の情報収集を行う
- 就活エージェントやキャリアセンターに相談する
①不足単位数を確認しスケジュールを立て直す
再就活を始める前に、まず不足している単位数を確認してください。卒業要件を満たさないまま動いても、同じ問題に直面するだけです。
必要な単位を把握したら、履修可能な授業や再試験の有無を確認し、卒業時期を前提に計画を組み直しましょう。この段階で無理のある予定を立ててしまうと、勉強と就活の両立が困難になります。
現実的な計画を作れば、気持ちの余裕を持ちながら活動できるはずです。計画を調整することが、安定した再就活の第一歩といえるでしょう。
②キャリアの方向性を整理し企業を絞る
次に、自分のキャリアの方向性を整理することが大切です。やみくもに応募を繰り返しても、納得できる内定につながる可能性は低いでしょう。
どの業界や職種で働きたいのかを改めて考え、優先順位をつけてください。そのうえで企業を絞れば、限られた時間を有効に使えます。
また、自己PRや志望理由に一貫性が出て、面接でも説得力を持って話せるでしょう。焦って数多く受けるよりも、方向性を定めた方が結果的に成功への近道になります。
③資格取得やインターンで経験を積む
再就活の期間を有効に活かすには、資格取得やインターンへの参加がおすすめです。資格はスキルを証明する材料となり、採用の場面で評価を高めます。
英語やIT、簿記といった資格は多くの企業で評価されやすいでしょう。インターンシップでは実務経験を得られるだけでなく、志望動機を裏付けるエピソードとしても活用できます。
さらに「ただ待っていたのではなく、行動した」という姿勢を示せることも大きな強みです。単位取得と並行して取り組めば、次の就活で自信を持って挑めるでしょう。
④再就活の情報収集を行う
再就活を成功させるには、正確な情報の把握が欠かせません。新卒採用とはスケジュールや選考方法が異なる場合もあるため、採用時期や応募方法を事前に確認してください。
求人サイトだけでなく、大学の掲示板や就職課の情報も参考になります。また、再就活を経験した先輩や友人の体験談は具体的で役立つでしょう。
情報を集めておけば、準備不足による失敗を防げます。十分な情報量は安心感にもつながり、自信を持って行動できるはずです。
⑤就活エージェントやキャリアセンターに相談する
最後に、専門的なサポートを受けることも重要です。就活エージェントを利用すれば、非公開求人の紹介や選考対策を受けられるため、効率的に活動を進められます。
大学のキャリアセンターでは履歴書の添削や模擬面接など、学生に特化した支援を提供している点も魅力です。自分だけでは気づけない改善点を教えてもらえるのは大きな強みでしょう。
相談することで不安も軽くなり、新しい可能性を見いだせます。一人で抱え込まず、支援を活用してください。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
大学を卒業できないときの行動指針

大学を卒業できない状況は就活生にとって大きな不安ですが、正しい行動を取れば進路を切り開くことは可能です。
まずは追加履修や再試験などで卒業の可能性を探り、教授や学生課に相談して支援を受けることが重要です。
そのうえで、卒業できないと確定した場合には、事実を隠さず企業へ早めに連絡する姿勢が信頼につながります。
企業側も入社時期を延期したり翌年度の採用を勧めるなど柔軟に対応してくれる場合があるため、誠実な対応が大切です。
大学を卒業できない事態に直面しても、冷静に現状を把握し、次の一歩を計画的に進めることが成功への近道です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













