公務員が休職するとどうなる?制度・待遇・社会の声まで網羅
「公務員が休職すると、その後の待遇や制度はどうなるのだろう…」と休職期間や給料の有無について気になりますよね。
安定した職業のイメージが強い公務員ですが、病気や育児、介護、さらには自己啓発など、さまざまな理由で休職するケースがあります。
そこで本記事では、公務員の休職に関する基本制度から理由別の条件、給料・ボーナス・公的給付の詳細、さらには社会の声まで網羅的に解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員の休職とは?制度の基本を解説

公務員の休職制度は、体調不良や家庭の事情などによって一定期間職務から離れる必要があるときに利用される制度です。
ただ、「休職」と聞いてもその内容を正しく理解できていない就活生は多いかもしれません。特に、病気休暇との違いや、国家公務員と地方公務員で制度に違いがある点は見落とされがちです。
ここでは、国家公務員と地方公務員がどのようなルールのもとで休職できるのか、その違いを分かりやすく解説します。
- 国家公務員の休職制度
- 地方公務員の休職制度
①国家公務員の休職制度
国家公務員の休職制度は、「国家公務員法」や「人事院規則」によって運用されています。病気や私事、懲戒処分など複数の理由が想定されており、特に病気による休職は最長で3年間まで認められています。
制度上、休職中も身分は維持され、復職の道も確保されています。そのため、安心して療養や問題の解決に専念できる環境が整っていると言えるでしょう。
ただし、実際に休職が認められるかどうかは医師の診断書や職場の判断によって異なり、必ずしも希望通りになるとは限りません。
また、給与やボーナスなどの待遇面にも影響があるため、事前に制度を確認しておくことが大切です。
とくに、「休職しても給料が出る」と思い込んでいた人が、実際には無給になるケースもあるため注意が必要です。
②地方公務員の休職制度
地方公務員の休職制度は、各自治体ごとに定められた条例や規則に基づいて運用されています。基本的な枠組みは国家公務員と似ていますが、詳細な条件や運用方法には違いがあります。
たとえば、病気による休職期間の上限は、ある自治体では1年、別の自治体では3年といった具合にバラつきがあります。また、給与の支給条件や復職の可否についても、自治体によって判断基準が異なります。
こうした違いを知らずに公務員を目指すと、後から「こんなはずじゃなかった」と感じることもあるかもしれません。志望先が決まっているなら、事前にその自治体の休職制度を調べておくと安心です。
公務員が休職する主な理由とは?公務員の休職制度の種類と条件について
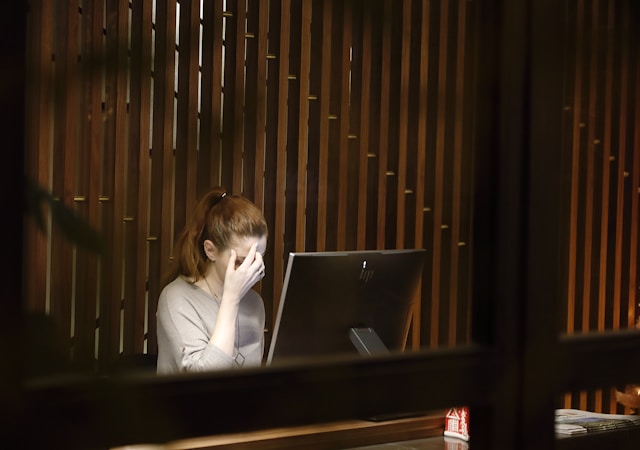
公務員が休職する理由は、体調不良だけではありません。育児や介護、家族の事情など、多様なケースが存在します。
それぞれの理由によって制度の内容や条件が異なり、給料の支給可否や休職期間にも差があるため、あらかじめ理解しておくことが大切です。
ここでは、代表的な休職理由について、具体的に解説します。
- 病気・精神疾患による休職
- 出産・育児による休職
- 介護による休職
- 私事(自己都合)による休職
- 配偶者の海外赴任等に伴う同伴休職(私的理由)
- 自己啓発(留学・研修)目的での休職
- 事故や災害などによる突発的なやむを得ない事情による休職
- 懲戒処分による休職
- 起訴・刑事事件関与による起訴休職
①病気・精神疾患による休職
最も多いのは、体調不良や精神的な不調による休職です。近年では、うつ病や適応障害などのメンタルヘルスの問題が増加しています。
心身の状態が長く回復しないときは、医師の診断をもとに休職が認められることがあります。通常はまず病気休暇を取り、長引く場合に休職へ移行する仕組みです。
ただし、休職中は無給になることもあるため、経済的な備えが求められます。悪化する前に、制度を理解して上手に活用しましょう。
②出産・育児による休職
出産や育児にともなう休職は、性別を問わず利用できます。産前産後休暇のあと、育児休業を取得する形が一般的です。
多くの自治体では育児休業中に手当が支給されるため、収入が完全に途絶えるわけではありません。また、復職を柔軟に延長できる制度もあり、家庭と仕事の両立を後押ししています。
子育てを視野に入れている方にとって、公務員の職場環境は恵まれているといえるでしょう。
③介護による休職
家族の介護が必要になったときも、休職が可能です。介護休暇で短期間対応し、それでも難しい場合は休職を申請することになります。
条件を満たせば給付金を受け取れる場合もあり、金銭面での負担を軽減できるでしょう。介護は突然訪れることが多いため、今は関係ないと思っていても安心できません。
制度を知っておくだけでも、いざというときの行動が変わります。
④私事(自己都合)による休職
家庭の事情や配偶者の転勤など、自分自身の都合で休職を希望するケースもあります。こうした「私事による休職」は認められることがありますが、職場の判断に大きく左右されます。
また、無給扱いになることがほとんどです。将来的にライフイベントに合わせてキャリアを中断する可能性があるなら、制度の有無や申請条件をあらかじめ確認しておくことが望ましいでしょう。
⑤配偶者の海外赴任等に伴う同伴休職(私的理由)
配偶者の海外赴任などに同行するために、休職を選ぶ方もいます。この場合も私的理由として申請が可能で、自治体によっては復職の道が確保されている制度もあります。
ただし、給与やボーナスの支給は基本的に停止されると考えておいたほうがよいでしょう。将来のキャリアに影響が出る可能性もあるため、制度の内容をよく確認し、慎重に判断してください。
⑥自己啓発(留学・研修)目的での休職
スキルアップやキャリアの再設計を目的として、留学や研修のために休職することもできます。条件を満たせば、自治体によっては制度として認められる場合がありますが、こちらも無給となるのが一般的です。
専門性を高めたいという明確な目標があるなら、有意義な制度といえるでしょう。ただし、復職後のポジションや人事評価にどのような影響があるかは、事前に把握しておくことが大切です。
⑦事故や災害などによる突発的なやむを得ない事情による休職
不慮の事故や自然災害によって出勤できない場合にも、特例的に休職が認められることがあります。こうしたケースでは、速やかな報告と申請が求められます。
制度の存在を知らずに自己判断で休んでしまうと、無断欠勤と見なされるおそれもあるため注意が必要です。非常時こそ、冷静に制度を活用する姿勢が重要になります。
⑧懲戒処分による休職
違法行為や不正が発覚した場合には、懲戒処分の一環として休職となることがあります。これは制裁の一種であり、一般的な休職とは意味合いが異なります。
原則として給与は支払われず、復職の可否にも厳しい基準が設けられることが多いです。職務中の行動や倫理意識が将来に影響を及ぼすことを理解し、日ごろから慎重な行動を心がけてください。
⑨起訴・刑事事件関与による起訴休職
刑事事件に関与して起訴された場合、「起訴休職」という形で職務を離れることになります。無罪が確定するまでは職務に戻れないため、身分は保持される一方で給与やボーナスは支給停止となります。
信頼回復には長い時間がかかる可能性があるため、法令順守の意識を常に持ち、軽率な行動を避けるようにしましょう。
病気休暇と休職の違いを理解しよう

まず病気休暇とは、病気やけがなどで一時的に勤務が困難になった場合に取得できる短期的な休暇です。原則として90日間を上限としており、給与が全額支給される点が特徴です。
この期間内での回復が見込まれる場合は、休職に切り替えることなく業務に復帰するケースが一般的です。
一方、90日を超えても回復が難しいと判断された場合に適用されるのが「休職」です。休職期間は最長で3年まで認められますが、給与の支給は制限されるか停止となります。
また、復職には医師の診断や人事上の審査が必要となるため、制度上のハードルも上がります。
病気休暇と休職では、取得条件・期間・給与などが大きく異なります。制度を混同してしまうと、後々トラブルにつながるおそれもあります。あらかじめ違いを正しく理解しておきましょう。
公務員の休職期間はどのくらい?最長で3年のケースも

公務員の休職には上限期間が設けられており、多くの場合、病気などの理由による休職は最長で3年まで認められています。症状や診断内容によっては短縮されることもあります。
公務員が病気を理由に休職する場合、まず90日以内で回復が難しいと判断された場合、「病気休暇」から「休職」へと移行します。
また、3年を過ぎても回復の見込みが立たない場合、退職を勧められるケースもあります。
見落とされがちですが、休職を「繰り返す」場合、通算で制度の上限を超えてしまい、再度の休職が認められなかったり、分限処分となるおそれもあります。
そのため、制度の限度や回復後の職場復帰計画をよく考え、慎重に対応することが求められます。
休職中の公務員の給料はどうなる?

公務員として働く上で、もしも体調を崩して長期間休まざるを得なくなった場合、最も気になるのが「休職中も給料は支給されるのか?」という点ではないでしょうか。
ここでは、休職中の給与に関する条件や影響について具体的に解説します。
- 支給される条件
- 退職手当や昇給への影響
①支給される条件
休職中の給料が支給されるかどうかは、休職の理由と期間によって変わります。たとえば病気による休職では、最初の90日間は「病気休暇」として全額支給されるのが一般的です。
しかし、それを超えて「休職」扱いとなった場合、多くの自治体では給与が減額されるか、完全に支給停止となることがあります。
精神疾患など、長期的な治療が必要なケースでは、収入が大幅に減る可能性もあります。
ただし、自治体によっては部分的な支給制度や傷病手当金の対象になる場合もあるため、所属先の制度をしっかり確認しておくことが大切です。
②退職手当や昇給への影響
休職が長引くと、将来的な退職手当や昇給への影響も見過ごせません。まず、休職期間中は原則として「勤務年数」にカウントされないため、退職金の算定対象から外れることがあります。
また、昇給の評価対象にもならない場合が多く、同世代の職員と比べて給与面で差が生じることも考えられます。仮に復職しても、昇進のタイミングがずれるなどキャリアに響くこともあるでしょう。
制度上は復帰の道が確保されていますが、収入や待遇面ではマイナスが生じる可能性もあるため、休職を選ぶ前には中長期的な視点で判断する必要があります。
休職中の公務員にボーナスは支給されるのか?

公務員を志す就活生にとって、休職中にボーナスがもらえるかどうかは気になるポイントの一つですよね。結論から言えば、休職中であっても一定の条件を満たせばボーナスが支給される場合があります。
多くの自治体や官公庁では、ボーナス(期末・勤勉手当)は支給日の直前6か月間の勤務実績をもとに計算されるため、休職前に十分な勤務期間があれば、その分についてはボーナスの一部が支給される可能性が高いです。
ただし、休職期間が長期に及んでいたり、支給基準日の直近でほとんど勤務していなかったりする場合は、支給額が大きく減額されたり、ゼロになることもあります。
特に病気や精神的な理由での長期休職では、制度上は支給対象であっても実際の額がほとんどないケースも少なくありません。
また、支給の有無や計算方式は自治体によって若干異なるため、自分の配属先となる機関の規定をあらかじめ確認しておくと安心です。
休職中の公務員がもらえる公的給付とは?

公務員が休職した場合、給料が減額または支給停止になることがあります。そんなときに頼りになるのが「公的給付制度」です。
ここでは、公務員でも対象となる主な給付について、種類と受給条件を分かりやすく紹介します。
- 傷病手当金
- 労災保険(労働者災害補償保険)
- 出産手当金・育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 雇用保険の基本手当
①傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがで働けなくなったときに支給される制度ですが、原則として健康保険の被保険者が対象となるため、公務員の場合は多くが対象外となります。
ただし、共済組合などが独自に同様の給付を行っている場合があるため、所属先の制度を確認することが重要です。
②労災保険(労働者災害補償保険)
業務中の事故や通勤中のけがによって休職することになった場合ことがあります。治療費や休業補償が給付されるため、申請することで経済的な負担を軽減できます。
公務員も労災対象となるケースがあるため、該当する場合は速やかに申請の手続きを進めてください。
③出産手当金・育児休業給付金
出産や育児を理由に休職する際には、出産手当金や育児休業給付金が支給されます。これらの給付金は共済組合や雇用保険制度から支給され、一定の条件を満たせば支給対象になります。
収入がゼロになることを避けるためにも、事前に必要書類や申請期限を把握しておくことが大切です。
④介護休業給付金
家族の介護を理由に休職する場合には、介護休業給付金が支給されることがあります。こちらも雇用保険に加入していることが前提となるため、公務員の場合は対象外となるケースが多いです。
ただし、一部の自治体では補完的な制度が設けられていることもあるため、自身が属する組織の制度を確認しておきましょう。
⑤雇用保険の基本手当
一般的に公務員は雇用保険に加入していないため、失業時に支給される「基本手当」(いわゆる失業手当)の対象外となることがほとんどです。
そのため、退職後に備えたい場合には、早めに再就職活動を始める必要があります。将来の転職を見据えた備えとして、制度の対象外であることを理解しておくことが大切です。
公務員の休職に対するバッシング

公務員の休職制度は整備されており、比較的手厚いサポートがある反面、世間からの批判や誤解されることも少なくありません。批判の背景には「公務員=安定」というイメージが強く根付いていることが挙げられます。
そのため、民間企業よりも休職制度が優遇されているように見えたり、長期間の病気休職でも職を失わない点が「甘い」「ずるい」と捉えられてしまうことがあります。
とくに、税金で運営されている立場上、一般の市民から厳しい視線が向けられる傾向にあるのも事実です。
しかし、実際に公務員として働いている人たちも、休職を簡単に選んでいるわけではありません。また、給与やボーナスの制限など、決して無条件に守られているわけでもないのです。
公務員を目指す就活生にとっては、こうした制度面と社会的イメージのギャップを理解しておくことが重要です。
公務員の休職制度を正しく理解して備えよう

公務員の休職制度は、病気・育児・介護など多様な理由に対応しており、国家公務員と地方公務員で規定に違いがあります。
特に、病気休暇との違いや最長3年の休職期間、給与・ボーナスの取り扱いなど、制度の内容を正確に知ることが重要です。
さらに、休職中に支給される公的給付や、バッシングなど社会的な視線にも触れておくと、不安のないキャリア設計につながります。
公務員を目指す就活生にとって、休職制度は「万が一」の安心を支える大切な仕組みです。
知らずに選ぶのではなく、制度の全体像を理解したうえで進路を決めることが、将来後悔しないための第一歩になるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










