内定お礼状の封筒の書き方|表面・裏面の正しい記載方法とは
「お礼状の封筒はどう書けばよいのか…」と不安がある方も多いでしょう。内定のお礼状を送る際、封筒の書き方に気を使うことが重要です。正しいマナーを守ることで、感謝の気持ちをより丁寧に伝えることができます。
本記事では、内定お礼状の封筒の表面・裏面の正しい記載方法について、詳しく解説します。封筒の選び方や書き方のポイントを押さえ、内定のお礼状をきちんと送るためのマナーを身につけましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
内定のお礼状を入れる封筒にもマナーがある

内定のお礼状を送る際、文面だけでなく封筒の扱いにも気を配る必要があります。封筒の選び方や書き方を間違えると、せっかくの丁寧な手紙も台無しになってしまうかもしれません。
たとえば、カラフルなデザインや柄のある封筒はカジュアルな印象を与えてしまい、ビジネスには不向きです。おすすめは、白無地の長形4号封筒です。
これはA4サイズの便箋を三つ折りにするとぴったり収まり、見た目も整いやすいため好印象を与えます。また、封筒は中身が透けないタイプを選ぶことも大切です。
文面がうっすら見えると、配慮が足りないと受け取られる可能性があるため注意してください。こうした細かい部分にも気を配ることで、相手に対する思いやりが伝わります。
さらに、封筒の表や裏の書き方、手紙の折り方や封の仕方などにもマナーがあるのです。就職活動では、小さなことでも丁寧に対応する姿勢が評価されやすいため、封筒の扱いにも十分注意してください。
内定のお礼状に適した封筒の選び方
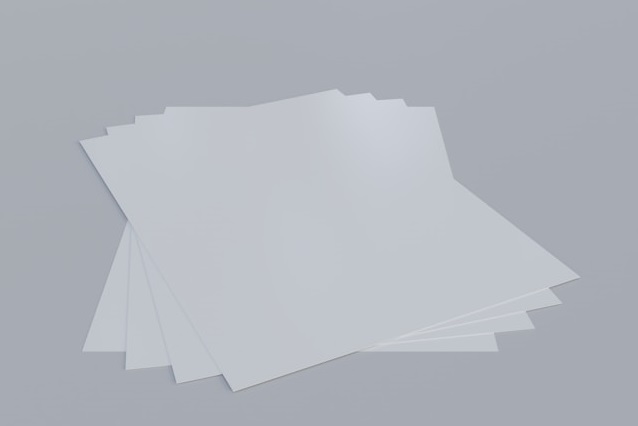
内定のお礼状を送るとき、どんな封筒を選ぶかは意外と見落とされがちですが、企業側の印象に大きく関わる大切なポイントです。
ここでは、返信用封筒がある場合の対応や、封筒の色・サイズ・素材・向きについて、正しい選び方をわかりやすく紹介します。
- 返信用封筒がある場合はそれを使用
- 封筒の色は白が基本
- 封筒のサイズは長形3号か角形2号
- 封筒の素材は無地・無装飾
- 封筒は横型ではなく縦型
①返信用封筒がある場合はそれを使用
企業から届いた内定通知に返信用の封筒が同封されている場合は、必ずそれを使用してください。
返信用封筒は、企業が「この封筒で返信してください」という意図を持って同封しているものであり、サイズや仕様が指定されているケースも少なくありません。
たとえ自分がもっと質の良い封筒を持っていたとしても、指定されたものを使うのが正解です。
仮に自分で封筒を用意して送ってしまうと、「ルールを守れない人」「細かい指示を読み飛ばす人」という印象を持たれることもあります。たった一通の手紙で評価を下げてしまうのは避けたいところです。
就職活動という正式なやり取りの中で、企業の指示に丁寧に応じることが、誠実な対応として高く評価されます。
②封筒の色は白が基本
封筒の色は、ビジネス文書の基本である「白」を選ぶのがもっとも無難で安全です。白は清潔感・誠実さ・フォーマルな印象を与える色であり、どんな企業にも違和感なく受け入れてもらえる色です。
たとえば、ベージュやクリーム色、パステルカラーの封筒を使った場合、「非常識」とまでは言わなくても「この人は少しビジネスマナーに疎いのかな」と感じられてしまう可能性があるでしょう。
特に人事担当者は、多くの応募者とやり取りしており、細かい点までよく見ているものです。柄や装飾の入ったものはもちろんNGです。
例え控えめな模様であっても、フォーマルな文書にはふさわしくありません。安全に、印象よく送りたい場合は、装飾のない純白の無地を選んでください。第一印象は封筒から始まります。
迷ったら「白」一択、それがビジネス文書における正しい選択です。
③封筒のサイズは長形3号か角形2号
お礼状に適した封筒のサイズは「長形3号」または「角形2号」のどちらかです。どちらもビジネス文書でよく使われるサイズであり、マナー違反になることはありません。
選ぶ際の基準は、便箋のサイズと折り方です。長形3号は、A4用紙を三つ折りにして入れられる細長いタイプで、履歴書の送付や企業との連絡でもよく使用されます。
比較的スリムな形状であり、持ち運びにも便利なので、手元に常備しておくと安心です。一方、角形2号はA4サイズを折らずに入れられるため、より丁寧で格式高い印象を与えることができます。
折り目をつけたくない場合や、企業がそのサイズを希望しているときにはこちらを選ぶのが適しているでしょう。
就職活動の場面では、長形3号が主流ではありますが、提出する書類の内容やボリュームに応じて適切なサイズを選ぶことが求められます。
④封筒の素材は無地・無装飾
封筒の素材は、装飾のないシンプルなものが基本です。無地で厚みのあるしっかりした紙を選ぶと、封筒自体に安っぽさがなく、受け取った相手にも好印象を与えることができます。
逆に、模様の入った紙や光沢感のある素材は、ビジネスの場にはふさわしくありません。
たとえば、リボン柄や透かし模様の入った紙、ラメが入った紙などは、一般の手紙やお祝い事には適していても、就職活動ではNGです。
また、透け感のある紙も避けましょう。封筒の中の文面がうっすら見えてしまうようでは、個人情報保護の面でも問題があります。中身が透けない「透け防止加工済み」と書かれている封筒であれば安心です。
装飾に気を取られるより、基本を守ることに注力しましょう。シンプルであることが、もっとも誠実さを伝えられる手段だと考えてください。
⑤封筒は横型ではなく縦型
封筒の向きについても注意が必要です。ビジネス文書においては、縦型の封筒を使うのが基本です。
横型封筒は洋封筒とも呼ばれ、カジュアルでプライベートな手紙や、招待状などで使われることが多く、お礼状などのフォーマルなやり取りには不向きです。
特に、手紙の本文が縦書きの場合、横型封筒に入れると見た目のバランスが悪く、違和感が生まれます。縦書き文書は縦型封筒に入れてこそ、統一感と丁寧さが伝わるものです。
日本ではビジネス文書=縦書き・縦型封筒という文化が根強く残っているため、特別な理由がない限り、縦型を選ぶことが無難です。迷ったら、「縦型の白無地封筒」と覚えておくと安心でしょう。
内定のお礼状の封筒の表面の書き方
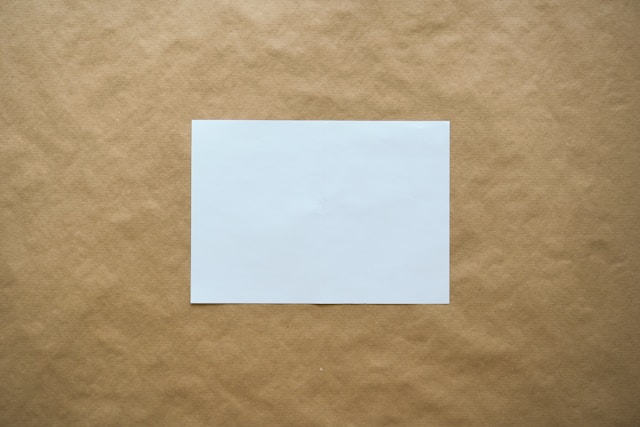
内定のお礼状を送る際、封筒の表面にもマナーがあります。宛名や住所の書き方を間違えると、せっかくのお礼状が台無しになるおそれもあるでしょう。
ここでは、封筒の表をきれいに仕上げるための書き方を、基本からわかりやすくまとめました。
- 住所は封筒の右上に正確に記載する
- 数字は漢数字で書く
- 宛名は中央にフルネームと敬称を忘れずに記載する
- 「行」や「宛」は二重線で消し「様」または「御中」にする
- 封筒の表に「内定承諾書 在中」と赤字で記載する
- 宛先の正式名称や部署名は略さずに記載する
①住所は封筒の右上に正確に記載する
封筒の表面に住所を記載する際は、右上から縦書きで正確に書くのが基本です。都道府県から順番に、建物名や部屋番号まで省略せず丁寧に記入してください。
手書きの場合は、はっきりと読みやすい楷書体で書くことが望ましく、にじみやかすれがないようペン選びにも気を配りましょう。
住所が長くなる場合でも文字を詰めすぎると読みにくくなってしまうため、適度な余白を保ちながらレイアウトを整えてください。また、住所欄と宛名欄のバランスも重要です。
企業名や部署名まで含めた宛先情報は、誤りがあると失礼になるので、改めて確認してから記入するようにしてください。特に郵便番号や番地は数字の間違いが起きやすいので注意しましょう。
②数字は漢数字で書く
封筒に記載する数字、特に住所や日付の部分では、アラビア数字ではなく漢数字を使うのが一般的なマナーです。「3丁目4番地5号」と表記したい場合には、「三丁目四番地五号」と記載してください。
この形式はやや古風に感じるかもしれませんが、ビジネスの文書では今も基本的な作法とされています。漢数字は手書きの文書において、視覚的な整いもよく、全体に落ち着いた雰囲気を与えてくれるでしょう。
また、日付や年号についても「2025年8月5日」とするのではなく、「令和七年八月五日」または「二〇二五年八月五日」のように漢数字を使うと、より丁寧です。
書き方を統一し、漢数字とアラビア数字が混在しないように注意してください。
③宛名は中央にフルネームと敬称を忘れずに記載する
封筒の中央には、送付先の宛名をフルネームで記入し、必ず敬称をつける必要があります。個人宛てであれば「様」、企業や部署宛ての場合は「御中」を使うのが正しいマナーです。
たとえば、「株式会社〇〇 人事部 御中」や「〇〇様」といった形になります。宛名は封筒の中央を基準に、上下左右のバランスをとって配置してください。
文字サイズはやや大きめに、他の記載よりも目立つようにすると、見た目も整って相手に丁寧な印象を与えられます。字の大きさや間隔にも気を配り、行間が詰まりすぎないよう注意しましょう。
敬称の使い方には特に注意が必要です。「御中」と「様」は同時に使ってはいけませんし、どちらを選ぶかによって相手との関係性が表現されます。
また、相手の氏名や部署名は略さず、正式な名称を使ってください。企業のホームページやメールの署名欄をもとに、正確な表記を確認することが大切です。
④「行」や「宛」は二重線で消し「様」または「御中」にする
就活中に企業から送られてきた封筒や案内に返信する際、あらかじめ「〇〇行」や「〇〇宛」と記載されているケースがありますが、「行」や「宛」に二重線を引き、その横に正しい敬称を記載してください。
「行」や「宛」は差出人より目下の相手に使う表現とされるため、そのまま使用すると失礼にあたるのです。
また、二重線を引くときは、黒のペンと定規を使って、まっすぐな線を引くと、より丁寧な印象になります。
形式的な手続きに見えるかもしれませんが、社会人としての基本的なマナーを身につけていることを示す大切な部分です。
⑤封筒の表に「内定承諾書 在中」と赤字で記載する
お礼状と一緒に内定承諾書を送る場合、封筒の表面左下に縦書きで「内定承諾書 在中」と赤字で明記するのがマナーです。この一文があることで、受け取る側は内容をすぐに把握でき、対応もしやすくなります。
赤ボールペンや朱肉の筆ペンを使うのが一般的です。市販のスタンプを使っても問題ありませんが、かすれやにじみがないかを確認してください。色が薄すぎると見落とされる可能性もあるため、しっかりと記入しましょう。
この表示は単なる形式ではなく、相手への配慮として非常に重要です。事務処理をスムーズにするだけでなく、「細かい気遣いができる人だ」と感じてもらえることもあります。
ビジネスマナーの一環として、こうしたひと工夫ができるかどうかは、印象を大きく左右するでしょう。
⑥宛先の正式名称や部署名は略さずに記載する
封筒に記載する企業名や部署名は、省略せず正式名称で記入することが基本です。「株式会社」を「(株)」と略したり、「人事部」を「人事」と書いたりすると、雑な印象を与えてしまう可能性があります。
たとえ略記が一般的な名称であっても、ビジネス文書ではきちんとした表記が求められるでしょう。重要なのは、相手に敬意を示す姿勢です。
名称の略記は、「手を抜いた」「調べていない」という印象を与えてしまうこともあります。企業の公式サイトや過去のやり取りのメールなどを見て、正式な表記を確認してから記入しましょう。
また、企業名の漢字や送り仮名を間違えると、相手に不快な思いをさせてしまうおそれがあります。特に似た名前の企業が複数ある場合は注意が必要です。
部署名も同様で、正確な表記を把握したうえで書くようにしてください。正式名称で書くことは、ビジネスマナーの基本中の基本です。
内定のお礼状の封筒の裏面の書き方

封筒の裏面はあまり目立たない部分ですが、マナーが問われる大切なポイントです。丁寧な印象を与えるためには、封の仕方や差出人情報の書き方を正しく理解しておく必要があるでしょう。
ここでは、封筒の裏面に記載すべき内容と、その正しい書き方をわかりやすく説明します。
- 封を閉じた部分には「〆」マークを記載する
- 左下に自分の郵便番号・住所・氏名を省略せず記載する
- 差出人の情報は読みやすく縦書きで記載する
- 住所の番地や建物名も省略せず記載する
①封を閉じた部分には「〆」マークを記載する
封筒の裏側を閉じた中央部分に「〆」マークを書きましょう。この記号には「封をしました」という意味があり、送付する文書が途中で開封されていないことを表す形式的なサインになります。
物理的に封を保護する機能はありませんが、受け取る相手に対して「封をきちんと行った」という意思表示になるのです。
記載する際は、封じ目の真ん中あたりに小さく、しかし読みやすく「〆」と書いてください。使う筆記具は黒のボールペンや万年筆が適しています。
このようなひと手間があるかどうかで、書類を受け取った際の印象は大きく変わります。形式だからと軽く考えず、誠実に対応することが、就活生としての評価につながるでしょう。
②左下に自分の郵便番号・住所・氏名を省略せず記載する
封筒の裏面左下には、必ず差出人の情報を省略せずにすべて明記しましょう。
たとえば、都道府県名やマンション名などを省いてしまうと、何かトラブルが起きたときに戻ってこない可能性もあるため注意が必要です。
また、差出人情報は、企業側が誰からの手紙かをすぐに判断するための手がかりにもなります。
特に就活中は、企業側も多くの応募者とやり取りをしているため、あなたの情報を明確に記しておくことが混乱を避ける手助けになるでしょう。
大学名や学部名を添えておくと、より分かりやすく親切です。たとえば「○○大学 経済学部 ○○ ○○」のように記入すれば、担当者が内容を把握しやすくなるでしょう。
③差出人の情報は読みやすく縦書きで記載する
封筒の裏面に記載する差出人情報は、縦書きが基本です。横書きでも間違いではありませんが、就活のようなフォーマルな場面では、やはり縦書きのほうが丁寧で落ち着いた印象を与えるでしょう。
郵便番号から順に、都道府県、市区町村、番地、建物名、氏名、大学名などを記載し、情報の順序をわかりやすく整理することが大切です。
手書きの場合は、定規やガイドを使ってまっすぐに書くことを意識してください。また、相手が読んだときにストレスなく読めるよう、文字を丁寧に書くことを心がけましょう。
④住所の番地や建物名も省略せず記載する
差出人の住所は、簡略化せず正式な表記で記載することがマナーです。
たとえば、「1-2-3」や「ハイツA-101」といった略記ではなく、「1丁目2番3号」「○○ハイツA棟101号室」のように、きちんと書いてください。
こうした正式な記載により、より丁寧で信頼のおける印象を与えることができます。特に就活の場では、相手企業もあなたがどれだけマナーを理解しているかを見ています。
また、マンションやアパートに住んでいる場合、建物名と部屋番号を記載することで、万が一の返送時にも確実に届くようになります。郵便物がきちんと戻るかどうかという点でも重要です。
手間に感じるかもしれませんが、こうした情報を正確に記載することは、相手への礼儀そのものです。就活というフォーマルな場面だからこそ、細かい部分まで丁寧に仕上げる意識を持っておきましょう。
内定のお礼状を封筒に入れる際のポイント
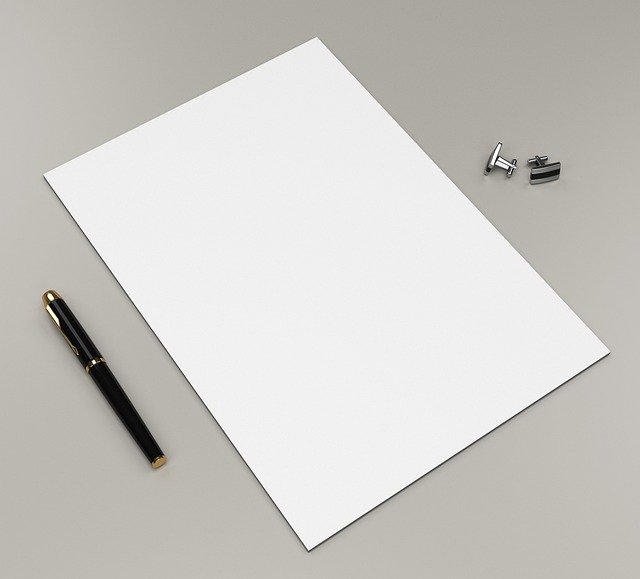
お礼状を封筒に入れるときは、見た目の丁寧さとミスのない対応が求められるでしょう。
ここでは、同封書類の扱い方や折り方、封筒内での収まり、確認事項、封入時の向きなど、基本だけれど見落としがちなポイントを解説します。
- 内定承諾書などの同封書類はクリアファイルに入れる
- お礼状のみの場合は三つ折りにして入れる
- 封筒の中で書類が折れたり動いたりしないようにする
- 封を閉じる前に内容や宛先を最終確認する
- 封筒の上下・表裏を間違えず正しい向きで入れる
①内定承諾書などの同封書類はクリアファイルに入れる
お礼状とあわせて内定承諾書や必要書類を同封する場合は、それらをクリアファイルにまとめてから封筒に入れるのが望ましいです。
配達中に書類が折れたり、雨や湿気で濡れたりするリスクを減らすことができます。特に複数枚を送る際には、バラバラにならないようひとまとめにしておくと、受け取る側にも配慮が伝わるでしょう。
また、しっかりとしたファイルに入っていることで、文書自体も折れや汚れから守られ、美しい状態で届きやすくなるのです。
透明なクリアファイルであれば、中身が一目でわかり、企業側が確認しやすいというメリットがあります。
安価なもので構いませんが、使い回しや汚れたものは使わず、清潔で新しいものを使用しましょう。こうした細やかな配慮が、「大切に扱っている」という姿勢として相手に伝わります。
②お礼状のみの場合は三つ折りにして入れる
お礼状のみを送る場合は、A4サイズの便箋を縦方向に三つ折りにして長形3号の封筒に入れるのが基本です。
三つ折りの際は「巻き三つ折り」と呼ばれる折り方を使い、封筒を開けたときに文面の冒頭がすぐ見えるようにしてください。これにより、読み手にとって読みやすく、礼儀正しい印象を与えることができます。
二つ折りや蛇腹折りは避けてください。封筒の中で収まりが悪くなり、書類が突き出たりシワが入ったりする可能性があるのです。
きれいな三つ折りにするためには、定規などを使って折り目を正確に付けるのがおすすめです。曲がっていたり、折り目がずれていたりすると、見た目の印象が損なわれてしまいます。
③封筒の中で書類が折れたり動いたりしないようにする
封筒に入れた書類が中で動いてしまうと、配達中の振動で端が折れたり角が傷んだりする可能性があります。
折り方が正しくても、中でズレたり揺れたりすれば、見た目が悪くなってしまうため、封筒のサイズと折り方のバランスを意識してください。
余白が多すぎる場合は、クリアファイルで挟むことである程度の安定感を保つことができます。
封筒のサイズが大きすぎると、せっかくの書類が中で暴れてしまい、結果として「雑に扱われた」という印象を与えるかもしれません。
逆に、封筒が小さすぎると無理に押し込むことになり、紙に折り目やヨレがついてしまう原因になります。封入前には、実際に入れてみて余裕とフィット感のバランスを確認しておきましょう。
④封を閉じる前に内容や宛先を最終確認する
封筒を閉じる前には、もう一度すべての内容を見直すことが非常に重要です。一度封をしてしまうと、内容を訂正するには開封が必要となり、封筒を使い直さなければならない場合もあります。
送付書類に不備がないか、お礼状の中身に誤字脱字がないか、企業名や担当者名が正しく記載されているかなど、丁寧に確認してください。
特に、名前の漢字の間違いや部署名の省略などは、相手に対する失礼にあたるため、念入りなチェックが必要です。
念のため、読み上げながらチェックする、第三者に見てもらうなど、複数の手段で確認するのがおすすめです。「大丈夫だろう」と思わず、最後のひと手間で信頼感は大きく変わります。
慎重すぎるくらいが、ちょうどよいと考えて行動してください。
⑤封筒の上下・表裏を間違えず正しい向きで入れる
封筒に書類を入れる際は、上下と表裏の向きに注意が必要です。開封口が上に来るようにし、封筒の裏側(のり付け部分)が上を向くように入れるのが正しい向きです。
また、書類の文字面が開封時にすぐ見えるよう、表を手前にして入れてください。
向きが逆だと、相手が手紙を取り出したときに文字が逆さになっていたり、裏面が先に見えてしまったりして、戸惑いや違和感を与えてしまいます。
封筒の上下や書類の方向は、自分ではわかっているつもりでも、慣れないうちはうっかり間違えることがあります。封を閉じる前に、もう一度確認しましょう。
丁寧に扱っているという印象は、こうした細部の積み重ねから生まれます。気を抜かず、最後までしっかり確認しましょう。
内定のお礼状を送る際の注意点

内定のお礼状は、感謝の気持ちを伝えるだけでなく、社会人としての基本的なマナーが試される場面でもあります。送付のタイミングや手段によって、受け取る側の印象は大きく変わるものです。
ここでは、送るときに気をつけたいポイントを3つ紹介します。
- なるべく早めに郵送する
- ポスト投函ではなく郵便局の窓口から送る
- 送付前に誤字脱字がないかを確認する
①なるべく早めに郵送する
内定のお礼状は、内定通知を受け取ってからできるだけ早く送るのが望ましいです。理想的なのは当日か、遅くとも翌日中の投函。
送るのが遅れると、「対応が遅い人」という印象を与えてしまうおそれがあります。早めに郵送することで、誠実な対応ができる人物だと感じてもらいやすくなります。
ただし、急いでいるからといって字が雑になったり内容が不十分になったりしては逆効果です。記入内容や封筒の書き方を丁寧に確認したうえで、落ち着いて投函してください。
タイミングだけでなく、丁寧さにも気を配ることで、あなたの印象はぐっと良くなるでしょう。
②ポスト投函ではなく郵便局の窓口から送る
内定のお礼状は普通郵便で問題ありませんが、確実に届けたい場合はポストではなく郵便局の窓口から出すのが安心です。
特に内定承諾書を同封する場合など、重要な書類を送る際は、郵便局の窓口を利用する方が安全でしょう。
窓口から出せば、切手の貼り方や重さのチェックもしてもらえますし、必要があれば簡易書留などで追跡も可能です。
ポスト投函より少し手間はかかりますが、それだけ丁寧な対応だと受け取ってもらえるはず。細やかな気配りができるかどうかは、社会人として重要な要素です。
送り方にも配慮があると、信頼につながりやすくなります。
③送付前に誤字脱字がないかを確認する
お礼状を送る前には、必ず内容を読み返して、誤字や脱字がないかをチェックしてください。特に人名や会社名を間違えるのは、相手に不快感を与える原因になります。
間違いを防ぐためにも、書き終えたら少し時間を置いて見直すことをおすすめします。できれば家族や友人など、第三者にも確認してもらいましょう。
自分では気づきにくい表現の不自然さや、敬語の使い方のミスに気づいてもらえることもあります。また、封筒の宛名や差出人の情報も忘れずに確認してください。
丁寧さがにじみ出る最終チェックで、好印象を残しましょう。
内定のお礼状を正しく送るために必要なこと
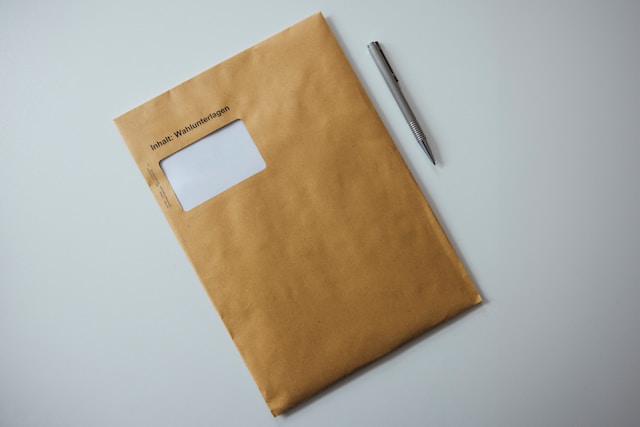
内定のお礼状を送る際、封筒の選び方や書き方、封入方法には細かなマナーが求められます。
適切な封筒を選ぶことはもちろん、宛名や差出人情報の記載、書類の折り方や封入時の向きまで気を配る必要があります。
封筒は白の縦型で長形3号が基本とされ、封の部分には「〆」マークを記すなど、見落としがちなルールも多いです。
しかし、これらのマナーを押さえておけば、相手企業に丁寧さや誠実さがしっかり伝わるでしょう。内定のお礼状 封筒に関する基本を理解しておくことで、就職活動の最後まで好印象を保つことができます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










