公務員面接は民間と何が違う?準備すべき質問例と答え方のコツ
「公務員の面接って、民間企業と何が違うの…?」
そう疑問に思いながらも、何となく同じように準備してしまっていませんか?
実は、公務員と民間の面接には“評価の視点”や“質問の傾向”に明確な違いがあります。特に公務員面接では、減点方式や公共性への理解といった独特のポイントが重視されるため、民間と同じ対策では通用しないケースも。
そこで本記事では、公務員面接の特徴や頻出質問、その答え方のコツまで、わかりやすく解説していきます。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る公務員と民間企業の面接の違いとは?

公務員面接は、民間企業の面接と比べて評価基準や質問内容に大きな違いがあります。
民間では加点方式で積極的な自己アピールが評価されますが、公務員では減点方式が主流で、ミスや不適切な発言を避ける慎重さが求められます。
また、公務員の面接は質問がマニュアル化されており、面接官も現場職員が多いため、的確に伝える力も重視されます。
民間と同じ対策では通用しないことを理解し、公務員に合った準備を進めることが大切ですよ。
公務員面接では、答え方のちょっとした癖や不用意な表現が減点につながることがあります。特に協調性や言葉遣いの丁寧さは、民間以上に重視される傾向にあるので意識しましょう。
一方で、熱意を伝えることはもちろんプラス評価になります。ただし、アピールを盛りすぎる必要はありません。質問に対して簡潔かつ誠実に答えることが大切ですよ。
そもそも公務員就活の流れがよく分からないという方は、まずは以下の記事を参考にしてみてください。公務員試験の内容や就活の進め方をはじめ、スケジュールの目安についても詳しく解説しています。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
公務員面接の特徴

公務員の面接には、民間企業の面接とは異なる特徴がいくつかあります。見た目は似ていても、質問のされ方や評価の方法、面接官のスタンスなどが大きく異なるため、民間の対策だけでは不十分です。
ここでは、公務員面接ならではのポイントを押さえながら、就活生がつまずきやすい注意点や心構えを解説していきます。
- 個別面接が基本である
- 不慣れな面接官が多い
- 減点方式が採用される
- 質問内容がマニュアル化されている
①個別面接が基本である
公務員面接の多くは、グループ面接ではなく個別面接で行われます。この形式では一人でじっくりと話す時間が取られるため、内容の一貫性や落ち着いた対応が重要になります。
民間企業のように集団の中で目立つ必要はありませんが、その分、一言ひとことがしっかり見られていることを意識してください。
緊張しやすい人は、模擬面接での練習を繰り返すことで自信をつけるとよいでしょう。
個別面接は一人の受験者に対して深く掘り下げられるため、回答の一貫性が特に重視されます。特に、志望理由は何度も聞かれることも。一度答えた内容を軸にぶれずに話すことが大切です。
また、公務員面接は評価基準が比較的明文化されており、面接官の印象一点で決まることは少ない傾向があります。そのため、想定質問への回答をしっかり準備して対策することが合格のために必要不可欠です。
集団面接には慣れているものの、個人面接に不安があるという方もいるでしょう。以下の記事では、個人面接の特徴から事前準備のポイント、基本的なマナー、頻出質問の答え方まで幅広く解説しているので、不安な方は面接前に一度目を通してみてください。
②不慣れな面接官が多い
公務員面接では、面接官が人事の専門職ではなく、現場の職員であることが一般的です。そのため、民間のように流れるような進行ではなく、質問や対応にぎこちなさを感じる場面もあるかもしれません。
ただし、だからこそ形式的な受け答えよりも、誠実で伝わりやすい表現が好まれます。面接官の反応にとらわれすぎず、自分の考えをしっかりと伝えることが大切ですよ。
③減点方式が採用される
民間企業では加点方式で評価されることが多いのに対し、公務員面接は減点方式が基本です。つまり、強くアピールすることよりも、「失点しないこと」が重視される傾向にあるのです。
無理に印象づけようとするのではなく、安定感のある態度や誠実な受け答えを心がけることが必要です。極端な意見や過度な自己主張は避け、バランスよく自分を表現することが評価につながります。
④質問内容がマニュアル化されている
公務員面接では、質問がある程度マニュアルに基づいて設定されているため、予想外の問いかけが来る可能性は低めです。
自治体や職種に関する質問、自分自身の性格や経験に関する質問が中心で、個性よりも一貫性や誠実さが重視されます。
そのため、想定される質問に対して事前にしっかりと準備しておくことが成功のカギです。回答例を自分の言葉に落とし込み、自然に話せるよう練習しておくと安心ですね。
面接質問事例集100選|聞かれる質問を網羅して選考突破を目指そう

「面接がもうすぐあるけど、どんな質問が飛んでくるかわからない……」
「対策はしてるつもりだけど、いつも予想外の質問が飛んでくる……」
面接前の就活生が抱える悩みとして「どんな質問をされるのか分からない」という問題は大きいですよね。頻出質問以外が予想しきれず、面接で答えに詰まってしまった人もいるでしょう。
また、面接経験がほとんどない人は、質問を予想することも難しいはず。そこでオススメしたいのが、就活マガジンが独自に収集した「面接質問事例集100選」です!
400社以上の企業の面接内容を厳選し、特に聞かれやすい100の質問を分かりやすく紹介。自分の回答を記入する欄もあるため、事前に用意した回答を面接直前に見返すことも可能ですよ。
面接で特に失敗しやすいのが「予想外の質問に答えられなかったパターン」です。よくある質問内容を知っておくだけでも、心の準備ができますよ。
また、志望動機などの頻出質問も、企業によってはひねった聞き方をしてくることも。質問集では特殊な例も網羅しているため、気になる人はぜひダウンロードしてくださいね。
\400社の質問を厳選/
公務員に求められる資質とは

公務員として働くうえでは、単に知識やスキルだけでなく、職務にふさわしい「資質」が重視されます。
民間企業のように個人の成果や利益を追求する姿勢とは異なり、公務員には住民や社会全体の利益を考えて行動する視点が必要です。ここでは、公務員に求められる代表的な4つの資質について解説します。
- 協調性|組織内外で良好な人間関係を築ける力
- 責任感|住民の生活を支える仕事への自覚
- 問題解決力|現場の課題に対して自ら考えて行動できる力
- 公共性|民間とは異なる“全体の奉仕者”としての視点
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①協調性|組織内外で良好な人間関係を築ける力
公務員の仕事では、多くの人と関わりながら業務を進めることが多いため、協調性がとても重要です。
特に部署間や住民との連携が欠かせない場面では、自分の意見を押し通すのではなく、相手の立場を理解しながら柔軟に対応する姿勢が求められます。
自己主張だけではなく、円滑な人間関係を築く努力ができるかどうかが評価のポイントになりますよ。
②責任感|住民の生活を支える仕事への自覚
公務員は、日々の業務が直接的に住民の暮らしに関わるため、一つひとつの仕事に対する責任感が不可欠です。
途中で投げ出したり、他人任せにしたりする態度は許されません。たとえ目立たない業務であっても、その一つが地域全体の安定に結びついているという意識を持つことが必要です。
このような姿勢は、面接でも確実に見られているのです。
③問題解決力|現場の課題に対して自ら考えて行動できる力
決まった手順通りに動くだけではなく、現場で発生する想定外の課題にどう対応するかが問われます。指示を待つのではなく、自ら状況を把握して動ける力があるかどうかが重要です。
特に災害時やトラブル対応の場面では、このような問題解決力が大きく役立ちます。正解がひとつではない場面でも冷静に対応できるかが、公務員としての評価につながりますよ。
④公共性|民間とは異なる“全体の奉仕者”としての視点
公務員は、「全体の奉仕者」という立場で行動することが求められます。民間企業のように売上や利益を最優先するのではなく、社会全体の利益や公平性を重視する視点が不可欠です。
そのため、自己中心的な発言や行動は敬遠される傾向にあります。自分が「なぜこの仕事に就きたいのか」を語る際にも、地域や住民のためという視点を忘れずに伝えることが大切ですね。
公務員の場合は、住民の安心や地域全体の幸福といった目に見えにくい部分をどう実現するかが求められます。そのような社会貢献の視点をどれだけ理解しているかが重視されていることを意識しましょう。
私たちも相談を受ける中で、「地域課題にどのように向き合いたいか」を具体的に話せる人は強く印象に残ると感じます。「人の役に立ちたい」だけでは弱く、自分の経験や関心と結びつけて話す工夫が必要です。
以下の記事では、逆に公務員の面接に落ちてしまう人の特徴を徹底解説しています。公務員に向いている人の特徴を理解できたら、あわせて注意すべきポイントも確認しておきましょう。
公務員の仕事内容

公務員と一口に言っても、その仕事内容は多岐にわたります。どの職種を志望するかによって、求められる知識やスキル、業務内容は大きく変わってきます。
ここでは代表的な「行政職」「技術職」「その他の職種」について、それぞれの役割や働き方の違いを詳しく見ていきましょう。
- 行政職の仕事内容
- 技術職の仕事内容
- その他の職種の仕事内容
また、公務員になりたいとは思っていても、どの職種が自分に向いているのかまだ決まっていない方もいますよね。その場合は、自己分析が足りていない可能性があります。以下の記事を参考に、自己分析をもう一度深めてみてください。
①行政職の仕事内容
行政職は、もっとも多くの就活生が目指す職種で、市役所や県庁などでの窓口業務、地域政策の立案、予算管理、福祉や子育て支援などの幅広い分野に関わります。
住民と直接接する場面も多いため、丁寧な対応や調整力が求められます。業務の種類は配属先によって異なるため、どの部署でも柔軟に対応できる姿勢が大切ですよ。
デスクワークだけでなく、現場に出て活動することもあるため、幅広い業務に対応できる意識を持ちましょう。
②技術職の仕事内容
技術職は、土木・建築・電気・機械・情報などの分野で専門性を活かして働く職種です。たとえば土木職なら道路や橋などのインフラ整備、建築職なら公共施設の設計・維持管理に携わります。
設計や調査の段階から完成まで一貫して関わることができる点が魅力です。
理系出身者向けの職種ではありますが、住民の安全や利便性を支えるという意味では、行政職と同じく社会的責任が伴います。計画性と実行力の両方が求められる分野なのです。
③その他の職種の仕事内容
公務員には行政職や技術職以外にも、消防官、警察官、学校事務、図書館司書、保健師、検査技師など、専門的なスキルを要する職種が多数あります。
これらの職種は、各分野の知識や資格が必要となることも多く、志望にあたっては事前の調査が欠かせません。
いずれの職種でも、住民に直接かかわるケースが多いため、対人対応力や冷静な判断力が問われます。職種の特性を理解したうえで、自分に合ったキャリアを選ぶことが重要ですね。
面接カードについて

面接カードとは、公務員試験の面接時に提出する書類で、応募者の人物像や志望動機、これまでの経験を把握するための重要な資料です。
まず、面接カードには、志望動機や自己PR、学生時代に力を入れたことなど、あなた自身の思いや経験が問われる項目が記載されています。
これらの内容は面接当日の質問のベースとなるため、面接官はカードを手元に置きながら質問を進めます。つまり、面接カードは単なる記入用紙ではなく、会話の出発点であり、評価の判断材料でもあります。
面接カードは、公務員試験における「あなたの自己紹介書」として、大きな意味を持つ存在なのです。
面接カードは、面接官が質問を考えるときの「手がかり」になります。書いた内容がそのまま面接での会話の起点になるため、曖昧な表現や筋の通っていない記述があると、結果的に質問に答えにくくなりますよ。
実際によくあるのは、自己PRと志望動機がうまく結びついていないケースです。面接官は内容のつながりや一貫性を重視するため、自身の経験や考えを矛盾なく整理することが大切ですよ。
以下の記事では、面接カードの書き方を徹底解説しています。面接カードの記載項目や入手方法に加え、評価されやすいポイントについても紹介しているので、ぜひ本記事とあわせて参考にしてみてください。
面接カードの注意点

面接カードは、公務員面接において質問内容や評価の基準になる非常に重要な書類です。内容に不備があると、面接全体の印象に大きく影響することもあります。
ここでは、就活生が見落としがちな面接カードの記入・活用時における注意点を3つの視点から解説します。
- 一貫性を持って自己PR・志望動機を記入する
- 提出前に書いた内容をしっかり覚えておく
- 想定質問に備えるための控えとして活用する
①一貫性を持って自己PR・志望動機を記入する
面接カードでは、志望動機や自己PRなどを問われますが、内容に一貫性がないと説得力が弱まってしまいます。
たとえば、「地域に貢献したい」と書きながら、別の欄で「安定志向」ばかりを強調すると、印象がちぐはぐになってしまいますよね。
すべての記入欄を通じて「何を伝えたいのか」を明確にし、一貫したメッセージになるよう意識しましょう。
面接カードは「質問のきっかけ」として活用されるため、内容に一貫性がないと突っ込まれやすく、答えに詰まるリスクが高まります。最初から「質問されてもしっかり答えられる構成」にすることが大切です。
アドバイスとして、自己PRと志望動機を声に出して一通り読んでみるのをおすすめします。どこかで違和感があるなら修正の必要がありますよ。書いたら終わりではなく、実際の面接を想定して確認しましょう。
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
②提出前に書いた内容をしっかり覚えておく
面接では、面接官がカードに書かれた内容をもとに質問を行います。
そのため、自分がどのような表現で記載したのかを正確に覚えておかないと、質問に対して的外れな答えになってしまうおそれがあります。
カードの提出後は、コピーを取り、何度も読み返して内容を頭に入れておくことが大切です。自分の言葉で自然に話せるよう練習しておくと安心ですね。
③想定質問に備えるための控えとして活用する
面接カードは、単に提出する書類ではなく、想定質問を考えるためのヒント集にもなります。
志望動機・自己PR・エピソードごとに、どのような質問がくるかを予想し、それに対する答えを準備しておくことで、面接本番での応答に余裕が生まれますよ。
事前にカードをもとにした模擬面接を行うと、実践力を高められるでしょう。準備段階から活用する意識が、合格への差を生むのです。
面接カードをもとに想定した質問にスムーズに答えられるようにするためにも、面接練習を重ねておきましょう。以下の記事では、面接の練習方法を多数紹介しているので、ぜひ自分に合った面接練習方法を見つけてみてください。
公務員面接で聞かれる内容は2つに分けられる

公務員面接では、質問の傾向が大きく「自治体に関するもの」と「自己に関するもの」の2種類に分かれます。
どちらも対策が必要ですが、それぞれ求められる視点や答え方が異なるため、事前にしっかり整理しておくことが大切です。ここでは、両方の質問にどのように向き合うべきかを一緒に見ていきましょう。
- 自治体に関する質問|地域課題や政策への理解が問われる
- 自己に関する質問|人物像や動機に関する問いかけが多い
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①自治体に関する質問|地域課題や政策への理解が問われる
公務員面接で自治体に関する質問は非常に頻出です。たとえば「この地域の課題は何だと思いますか?」や「今後のまちづくりに必要な施策は?」といった問いが代表的です。
これは、志望する自治体の現状をどれだけ理解しているか、そしてその中で自分がどのように貢献できるかを見極めるための質問です。
対策としては、自治体の公式ホームページや広報誌を読み、人口構成・産業・地域課題などの情報を押さえておくことが欠かせません。
さらに、自分の考えを交えながら答えることで、関心の深さをアピールできますよ。
公式情報だけでなく、地域ニュースや市議会の議事録なども参考にしましょう。その地域の課題の背景や住民の関心がより具体的に見えてきますよ。知識を得るのに加え、自分なりの視点を持ってくださいね。
また、回答を準備する際には「現状→課題→自分の貢献案」という流れを意識すると整理しやすいです。私たちも面接練習でこの順番を意識させることが多く、答えに一貫性が出やすくなります。
②自己に関する質問|人物像や動機に関する問いかけが多い
もう一つの軸となるのが、あなた自身に関する質問です。「志望動機は?」「長所と短所を教えてください」「学生時代に頑張ったことは?」といった質問が該当します。
これらの質問は、あなたの価値観や行動パターン、考え方が公務員として適しているかを見極めるためのものです。
大切なのは、ただ事実を並べるのではなく、そこに「なぜそう考えたのか」「どんな工夫をしたのか」など、あなたらしい視点や行動を交えて答えることです。
表面的なエピソードではなく、深堀りできる準備をしておくと安心ですね。
自己に関する質問は、受験者の「価値観の一貫性」や「動機の裏付け」を見極めるために特に重視されます。そのため、「なぜその考えに至ったのか」という背景を伝えることが大切です。
私たちも面接対策をサポートする際、深掘りされた質問に本人が答えられるかを確認します。話す際は、「結論→理由→具体例」の順で伝えると質問の意図に即した答えを言いやすいですよ。
自己分析を深めるために、マインドマップを活用するのもおすすめです。以下の記事では、マインドマップの書き方や活用方法などを詳しく解説します。ぜひ参考にしてくださいね。
公務員面接でよく聞かれる質問【自治体に関する質問編】

公務員面接では、志望する自治体に対する理解が問われる質問が多く出されます。とくに、地域の課題や施策、魅力への関心、時事的なテーマなどを踏まえた回答が求められます。
ここでは、よくある4つの質問パターンと、それぞれに対する考え方を整理しておきましょう。
- 自治体の課題と解決策
- 地域の魅力と特色
- 時事問題と政策
- 地域貢献への意欲
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①自治体の課題と解決策
「この自治体が直面している課題は何だと思いますか?」という質問では、地域の現状をどれだけ調べているかが見られます。
ただの批判にならないよう注意が必要で、「高齢化が進んでいる」という事実を挙げるだけでなく、「高齢者と若者が交流できる地域イベントの推進が必要」など、自分なりの解決案を具体的に述べることが重要です。
課題の把握と提案力のバランスが評価されるポイントですよ。
課題と解決策を問われたときには、国の統計データや自治体の公式発表を引き合いに出すと裏付けのある回答になります。根拠を示せると「理解している」と伝わりやすいです。
また、提案力を見せるには現実味が欠かせません。例えば「高齢化対策として地域イベント」と言うだけでなく、費用や人材面を意識した小規模案を示すと、実行可能性を考えられる人材と見なされやすくなりますよ。
②地域の魅力と特色
「この地域の魅力は何ですか?」という質問は、自治体への関心の深さを測る意図があります。
パンフレットに書かれている内容をそのまま答えるのではなく、自分自身の体験や調査を交えて語ると説得力が高まりますよ。
「農業体験を通じて地域の人とのつながりを感じた」など、実感を込めて伝えると印象に残りやすくなります。
地域の魅力を伝える際に効果的なのは、「暮らしやすさ」や「地域の人の価値観」に触れることです。自治体は住民サービスを重視しているので、生活者目線での気づきを盛り込むと納得感が増しますよ。
私たちも面接練習のサポートを通して、自分の経験と地域の特色をつなげられる人は説得力があると感じます。実体験ベースで感じたことや学んだことを話せるようにしましょう。
③時事問題と政策
「最近注目している政策はありますか?」という問いには、時事へのアンテナと政策理解の深さが求められます。
答える際は、単にニュースをなぞるのではなく、「なぜその政策に関心を持ったのか」「自治体でどのように活かせると考えるか」まで掘り下げて話すと、考える力をアピールできます。
日ごろから自治体の取り組みや予算資料に目を通しておくと対策しやすくなりますね。
時事問題や政策について問われた際は、政策の背景にある社会課題や国全体の流れを意識しながら話すことが大切になります。また、「自分なりの視点で解釈しているかどうか」が差をつけるポイントですよ。
私たちも面接準備をサポートする中で、自治体が公開している施策評価報告書や議会だよりをチェックしている就活生は強く印象に残ると感じます。一次情報にあたる資料を活用してくださいね。
とはいえ時事問題は「どこまで対策すればよいのか分からない」と感じている方も多いでしょう。以下の記事では、時事問題の出題理由や答え方、情報収集の方法まで分かりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
④地域貢献への意欲
「あなたが地域にどう貢献できると思いますか?」という質問では、抽象的な答えに終わらないように注意が必要です。
たとえば、「住民の声を丁寧に聞いて制度に反映する」といった具体的な姿勢を示すことで、自分が地域の一員としてどのような役割を担いたいのかを明確に伝えられます。
過去の経験と結びつけて語ると、より説得力が増すでしょう。
「役に立ちたい」という気持ちだけを伝えても評価は上がりません。自治体ごとに力を入れている政策が違うので、募集要項や自治体のホームページを見て、重点分野と自分の経験を結びつけることが大切です。
また、経験を紹介するだけで終わらせず、「その経験をどう行政の仕事に活かせるか」まで伝えるとより説得力があります。未来にどうつなげるのかを意識して答えると、面接官に響きやすいですよ。
公務員面接でよく聞かれる質問【自己に関する質問編】

公務員面接では、あなた自身の人となりを知るための「自己に関する質問」が多く出されます。
民間企業でも定番の質問ではありますが、公務員としての適性があるかどうかを見極める視点で問われる点が特徴です。ここでは、特によく聞かれる4つの質問内容について押さえておきましょう。
- 長所・短所
- 学生時代の経験
- 志望動機
- 人柄や価値観
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①長所・短所
「あなたの長所と短所は何ですか?」という質問では、自己理解の深さと誠実さが見られます。
単に「協調性があります」「慎重すぎるのが短所です」と答えるのではなく、具体的なエピソードを交えながら説明することが大切です。
また、短所については改善のための工夫や努力も添えることで、前向きな印象を与えれらますね。
②学生時代の経験
「学生時代に力を入れたことは何ですか?」という問いには、主体性や課題解決力、人との関わり方などが反映されるように答えると効果的です。
公務員には継続的に努力できる姿勢や周囲と連携する力が求められるため、部活やゼミ、アルバイトなどの経験を通じて得た学びを自分の言葉で伝えると良いでしょう。
学生時代の経験を伝える際には、自分がどんな役割を果たし、何を改善したのかを具体的に話す必要があります。成果だけでなく行動の過程も示しましょう。
私たちも面接練習を支援する中で、「自身の経験を公務員の資質に結び付ける」ことを意識するようにアドバイスしています。地域社会への貢献や協働の姿勢につなげて話してくださいね。
とはいえ、「ガクチカに書けるような経験がない…」と感じている方もいるでしょう。以下の記事では、ガクチカがない人必見のガクチカを見つける方法やおすすめのテーマ、例文まで紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
③志望動機
「なぜ公務員を志望したのですか?」という質問は、面接全体の中でも特に重要です。公務員という仕事の意義をどう捉えているか、そしてその自治体を選んだ理由が明確に語れるかが評価されます。
地域への貢献意欲や自分の経験との関連性を丁寧に説明し、「この人と一緒に働きたい」と思わせる動機に仕上げましょう。
志望動機は「なぜ公務員か」と「なぜその自治体か」を分けて整理しましょう。ここが曖昧なままだと志望動機の説得力が弱くなりやすいですよ。自治体固有の取り組みや政策に言及してください。
私たちも面接練習でよく指摘するのは、「地域に貢献したい」だけでは志望動機の説得力が弱いという点です。自分の経験や学びと結びつけて、地域に貢献したい根拠を明確にすることが大切になります。
④人柄や価値観
「あなたはどんな人ですか?」「大切にしていることは何ですか?」といった問いでは、職場や住民との関係づくりに適した性格かどうかを見られます。
誠実さ、柔軟さ、責任感など、公務員にふさわしい人物像を意識しつつ、実体験を交えて自分らしく語ることがポイントです。
抽象的にならず、他者との関わりの中で表れた性格を例にすると伝わりやすくなりますよ。
公務員の面接当日までにしておくべき対策4選

公務員面接は事前準備が結果を大きく左右します。本番で落ち着いて自分の考えを伝えるためには、単に内容を暗記するのではなく、自分の言葉で語れるようにしておくことが重要です。
ここでは面接日までにやっておくべき4つの具体的な準備について紹介します。
- 志望動機を明確にする
- 自治体研究で地域の特性を把握する
- 対策本を読み、よく出る質問への回答を準備する
- 模擬面接を活用し、練習を重ねる
①志望動機を明確にする
志望動機は、公務員を目指す理由と、その自治体を選んだ理由の両方を明確に伝える必要があります。
「安定しているから」だけでは不十分で、「なぜ公務員なのか」「なぜこの地域なのか」に自分の経験や価値観を結び付けて答えることが求められます。
面接官に納得感を与えるためには、根拠のあるストーリーが欠かせません。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
②自治体研究で地域の特性を把握する
面接では、その地域についての知識や関心も評価の対象になります。自治体の公式サイト、広報誌、地域ニュースなどをもとに、人口構成や課題、注力している政策などを調べておきましょう。
そのうえで、自分がどのように貢献できるかを考えておくと、説得力ある回答につながります。
自治体研究では、他地域と比べた強みや弱みを押さえることが重要です。私たちも面接指導をする際、比較がしっかりできているかどうかで回答の説得力が大きく変わると感じています。
また、統計データや行政資料だけでなく、地域イベントや現場の声に触れておくと理解度が一段と高まりますよ。自分の言葉で地域特性を伝えることが大切です。
③対策本を読み、よく出る質問への回答を準備する
質問内容はある程度パターン化されており、市販の公務員面接対策本にも豊富に紹介されています。
ただし、答えを丸暗記するのではなく、あくまで自分の経験や考えをもとにした回答を用意することが大切です。模範解答は参考程度にとどめ、自分らしさを出せる表現に言い換えておきましょう。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
④模擬面接を活用し、練習を重ねる
どれだけ準備しても、実際に口に出して話してみると、言葉に詰まることもあります。模擬面接を通じて質問に慣れておくことで、緊張を和らげられますよ。
大学のキャリアセンターや家族、友人に協力してもらい、フィードバックをもらいながら改善していくと安心感が得られます。
模擬面接は答え方の練習だけでなく、表情や声のトーン、姿勢といった非言語的な部分も意識することが大切です。実際には、第一印象が評価に影響することも少なくありません。
また、同じ相手に何度も見てもらうより、複数の人にフィードバックを受けた方が新しい気づきを得やすいですよ。友人やキャリアセンター、OB訪問などいろいろな立場の人に協力してもらいましょう。
模擬面接の進め方が分からず不安な方は、以下の記事を参考にしてみてください。模擬面接のやり方や注意点に加え、無料で利用できる練習サービスも紹介していますので、ぜひ活用しましょう。
面接時の回答のポイント

公務員面接では、内容の正確さだけでなく、伝え方そのものも評価対象になります。
どんなに優れた経験や考えを持っていても、伝わらなければ評価されません。ここでは、面接時に意識したい4つの回答のポイントを解説します。
- 質問の意図を正しく汲み取る
- 落ち着きのある丁寧な説明を心掛ける
- 結論ファーストで答える
- 具体的なエピソードを盛り込んで答える
①質問の意図を正しく汲み取る
面接では「何を聞かれているのか」を正確に理解する力がとても大切です。この力は、将来の市民対応においても求められる「傾聴力」に直結します。
たとえば「学生時代に頑張ったことは?」という一見シンプルな質問でも、面接官は主体性や協調性、問題解決力といった資質を見ようとしているのです。
ただ事実を話すだけでは不十分で、「なぜこの質問がされているのか」を考えながら、自分の強みや価値観を自然に伝えることが求められます。
公務員として住民の声を正確に受け止め、的確に対応する力を見られているという意識を持って臨みましょう。
意図を把握する力を高めるには、模擬面接後に「この質問は何を確認したかったのか?」を振り返る習慣をつけると効果的です。答えの精度も回数を重ねるごとに上がっていきますよ。
また、公務員面接では特に「市民の声を汲み取る力」も見られています。だからこそ「相手が期待する人物像」を意識しながら自分のエピソードを話すことが重要です。
②落ち着きのある丁寧な説明を心掛ける
焦って早口になったり、言い直しが多くなると、内容以前に印象が悪くなってしまいます。公務員に求められるのは、誠実で安定感のある対応です。
緊張してもいいので、ゆっくりとした口調で相手に伝わるよう心掛けることが大切です。口癖や語尾の癖にも注意しながら、日頃から練習しておくと安心です。
③結論ファーストで答える
公務員面接では限られた時間の中で簡潔に答える力も問われます。そのため、話の冒頭で「私は〇〇と考えます」と結論を伝えることが効果的ですよ。
その後に理由や背景、具体例を続けることで、論理的でわかりやすい回答になります。結論が後回しになると、話の趣旨が見えにくくなるので注意しましょう。
④具体的なエピソードを盛り込んで答える
説得力のある回答をするには、具体的な経験を交えることが不可欠です。
「責任感があります」だけで終わらせず、「ゼミの活動でリーダーを任され、期日までに全員の提出を取りまとめた経験があります」といった実例を添えると、印象がぐっと強くなります。
日頃からエピソードのストックを整理しておくと、本番でも落ち着いて話せますよ。
これらの回答のポイントを意識しながら、普段から練習を重ねて身につけていくことで、自然に話せるようになります。以下の記事では、就活面接に効果的な練習方法を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
面接時の回答の注意点
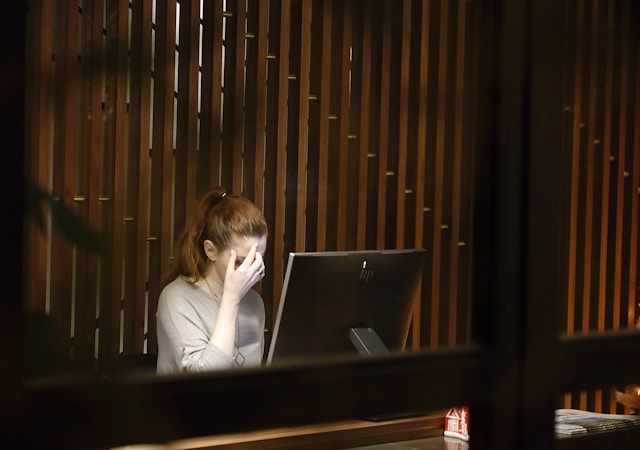
公務員面接では、回答内容そのものだけでなく、その伝え方や表現の仕方にも細かな評価が加えられます。
些細な一言がマイナス印象につながることもあるため、あらかじめよくある注意点を理解しておくことが大切です。ここでは特に気をつけたい3つのポイントを紹介します。
- 安定志向だけを強調しない
- 抽象的な表現は避ける
- 民間企業を否定する姿勢を出さない
①安定志向だけを強調しない
「安定しているから公務員を志望した」という動機は正直に思える一方で、それだけでは不十分です。
安定性は魅力の一つかもしれませんが、それだけを前面に出すと、受け身な姿勢や消極的な印象を与えてしまうことがあります。
大切なのは、「安定した環境の中でどんな仕事をしたいのか」「地域にどう貢献したいのか」という前向きな意欲を言葉にして伝えることです。
②抽象的な表現は避ける
「人の役に立ちたい」「地域を支えたい」といった言葉は一見好印象ですが、具体性がないと伝わりにくく、印象にも残りません。
面接官にあなたの考えや経験を正確に理解してもらうためには、「どんな経験を通してそう感じたのか」「どのような形で地域に貢献したいのか」をエピソードを交えて話すことが効果的です。
抽象的な表現は避け、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。
③民間企業を否定する姿勢を出さない
「民間ではなく公務員を選んだ理由」を説明する際、うっかり民間企業を批判するような言い回しになってしまうことがあります。
しかし、公務員面接では他の業界を否定する姿勢はマイナス評価につながりやすいため注意が必要です。
たとえば「ノルマが嫌だから民間は向いていない」という表現ではなく、「長期的な視点で地域に寄り添いたい」というポジティブな動機を軸に伝えると印象が良くなります。
もし上記の注意点を守れず、「失敗してしまった…」と感じている方も大丈夫です。以下の記事では、公務員就職に失敗する方の割合や気持ちの切り替え方、その後の進路について紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
公務員と民間の面接の違いを理解して対策を徹底しよう!

公務員面接と民間の面接では、評価の視点や重視される資質が大きく異なります。
たとえば公務員では「減点方式」や「マニュアル化された質問」が特徴で、個別面接を通じて協調性や公共性といった資質が問われます。
また、面接カードは単なる履歴書ではなく、自治体研究や志望動機を踏まえた一貫性ある準備が求められます。さらに、質問の意図を正確に読み取り、具体的なエピソードで自分を伝える技術も必要です。
民間とは異なるこの面接構造を理解し、適切な対策を積み重ねることが、公務員としての一歩を踏み出す鍵になるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











