食品業界の全体像を徹底解説|ビジネスモデルや動向・向いている人の特徴も紹介
「食品業界ってよく聞くけど、どんな仕組みで成り立っているの?」
そんな疑問を抱えながら、就活を進めている人も多いのではないでしょうか。
食品業界は、私たちの食卓に欠かせない“食”を支える産業でありながら、そのビジネスモデルは生産から販売まで多岐にわたります。そのため、業界全体を正しく把握するのが意外と難しいものです。
そこで本記事では、ビジネスモデルや現状、将来性から職種や志望動機の書き方までを徹底解説していきます。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
食品業界とは?

食品業界とは、人々の生活に欠かせない「食」に関する製品やサービスを提供する産業全体を指します。
製造から加工、流通、販売に至るまで幅広い工程が含まれており、企業ごとにビジネスモデルも多様です。
まずは業界全体の構造を把握し、それぞれの事業領域の違いを理解することが重要です。
「自分はどの立場から“食”に関わりたいのか」を明確にすることで、企業研究や志望動機の作成にも深みが出てくるでしょう。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
食品業界のビジネスモデルをわかりやすく解説

食品業界は、原材料の生産から加工、流通、販売に至るまで、さまざまな業態が連携して成り立っています。
どの業態もそれぞれに重要な役割を担っており、業界構造を理解することは、企業研究や志望動機の具体化に大いに役立つでしょう。以下では、代表的な4つの立場から食品業界のビジネスモデルを解説します。
- 農林水産業
- 仲介業
- 製造業
- 小売業
① 農林水産業
食品業界の原点となるのが、農業・漁業・畜産業などの農林水産業です。ここでは米や野菜、魚介類、畜産物など、食品の原料となる素材が生産されています。
自然環境の影響を強く受けるため、安定的な供給体制を確立するのは容易ではありません。
最近では、ITやデータを活用したスマート農業や持続可能な養殖技術など、新しい取り組みも進められており、将来性を感じさせる分野です。
② 仲介業
仲介業は、食品の生産現場と加工・販売の現場を結ぶ橋渡し役を担っています。国内外から食材を調達し、加工業者や小売業者に安定的に供給するのが主な役割です。
品質管理や価格交渉、物流の効率化など、多岐にわたる業務が求められます。輸出入に関わる機会も多いため、グローバルな視野と語学力が活かされるでしょう。
食品の安定供給を陰で支える、非常に重要なポジションといえます。
③ 製造業
原料となる素材を加工し、私たちの食卓に届く商品へと形づくる役割を担うのが製造業です。飲料、冷凍食品、お菓子など、身近な製品の多くがここで生まれます。
企業ごとに得意とする分野が異なるため、自分の興味と合う製品ジャンルを探すことが大切です。
市場のニーズに合わせて商品開発を進める力や、ブランド力を高めるマーケティング戦略が重視されており、創造性と論理的思考の両方が必要になります。
④ 小売業
小売業は、消費者と直接接する食品業界の最前線です。スーパーやコンビニなどで、商品を販売しながら顧客の声を受け取る役割。
仕入れ、陳列、接客、在庫管理といった現場での業務に加えて、近年ではECサイトやネットスーパーなど、オンラインと連携した取り組みも拡大しています。
マーケティング感覚と現場力の両立が求められる業態といえるでしょう。
「業界分析」はこれ1冊だけ!業界分析大全を受け取ろう!
就活で志望業界を説得力高く語るには、「なぜこの業界なのか」をデータやトレンドで裏づける業界分析が欠かせません。とはいえ、IR資料やニュースを一から読み解くのは時間も手間もかかり、表面的な理解で面接に臨んでしまう学生も少なくありません。
そこで就活マガジン編集部では、主要20業界を網羅し「市場規模・最新トレンド・主要企業比較」まで1冊で整理した『業界分析大全』を無料提供しています。業界研究に迷ったら、まずはLINEを登録で特典をダウンロードして「面接で差がつく業界知識」を最短で手に入れてみましょう。
業界知識の深さは選考官が必ずチェックするポイントです。志望度の高さもアピールできるのでおすすめですよ。
食品業界の現状

食品業界は私たちの食生活を支える一方で、深刻な課題を抱えています。食品業界の現状を理解することは、食品業界を志望する就活生にとって重要でしょう。
以下では3つのポイントから食品業界の現状を解説します。
- 人手が不足している
- 利益率が低い
- AIやIoTの導入が遅れている
① 人手が不足している
人手不足は業界全体が直面している大きな悩みです。製造現場や物流センターでは重労働にもかかわらず賃金が伸び悩み、高齢化と若年層の就業離れが進んでいます。
結果として作業効率の低下や品質管理のリスクが高まってしまうのが現状です。その対策として、外国人労働者の受け入れ拡大や再雇用制度の整備を進める企業も増えています。
就職先を選ぶ際は、こうした働きやすさへの取り組みをチェックしてみてください。
② 利益率が低い
利益率の低さも見逃せないポイントです。原材料価格の上昇や物流コスト増加、激しい価格競争により、企業は価格を簡単に引き上げられません。
その結果、売上は大きくても利益を確保しにくい構造にあります。こうした環境下では、高付加価値商品や健康志向の商品開発といった差別化戦略が必要とされます。
業界研究では、こうした取り組みに注力する企業に注目するとよいでしょう。
③ AIやIoTの導入が遅れている
AIやIoTといったDX(デジタル・トランスフォーメーション)の遅れも深刻です。中小企業が多い業界では資金やノウハウが不足し、衛生管理の厳しさから導入に慎重になるケースが散見されます。
しかし、人口減少や人手不足が続くなか、AIによる需要予測やIoTによる製造ラインの自動化は避けて通れません。
最近では大手企業を中心に導入が進みつつあるため、技術活用に積極的な企業を志望先の候補に加えてみてください。
食品業界の動向

食品業界は人々の暮らしに深く関わるため、社会や消費行動の変化に影響を受けやすい業界。最近では、生活スタイルの多様化や技術の進歩にともない、業界全体のビジネス構造も変化の途中です。
以下では、特に注目したい5つの動向を紹介します。
- インターネット販売が拡大している
- コロナ禍から回復している
- 健康志向が高まっている
- 利便性の高い食品の人気が高まっている
- 原材料費が高騰している
① インターネット販売が拡大している
食品業界でも、インターネット販売が拡大。生鮮食品や冷凍食品、加工食品に至るまで、幅広い商品がオンラインで購入されるようになっています。
企業側もこうした需要の変化に対応するべく、自社のECサイトの構築・改善に注力しています。
また、大手モール型EC(楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなど)への出店など、新たな販路の開拓にも積極的です。
デジタルを活用した販売戦略が、企業の成長を左右する重要な要素となりつつあります。
② コロナ禍から回復している
コロナ禍では外食や観光関連の食品需要が一時的に大きく落ち込みましたが、その後の回復を経て、現在は新たな消費スタイルが定着しつつあります。
業務用食品の出荷量は堅調に推移しており、観光や外食の需要も安定。さらに、コロナ禍で普及した冷凍食品や簡便調理品の人気は今なお続いており、日常生活に深く根づいた存在となっています。
企業には、こうした定着したニーズに対応した商品開発や、ライフスタイルの変化を見越した提案力が求められるでしょう。
③ 健康志向が高まっている
消費者の健康意識が高まっていることも、食品業界にとって重要な動きです。糖質オフ、高たんぱく、オーガニック、無添加などのニーズが増えており、各社がこうした志向に応えた商品開発を進めています。
とくに若者からシニア世代まで幅広い層が、健康と食を結びつけて意識するようになりました。
おいしさを維持しながら栄養価を高める工夫が必要とされ、開発やマーケティングの現場では、食と健康に関する知識を持つ人材が重宝されるでしょう。
④ 利便性の高い食品の人気が高まっている
調理の手間を省きたいという人が増え、すぐに食べられる食品のニーズが高まっています。冷凍弁当やレトルト商品、電子レンジでそのまま温められるパウチ食品などが代表例です。
忙しい共働き世帯や一人暮らしの若年層にとって、利便性は商品選びの大きなポイントになっています。食品メーカーにとっては、こうした需要にどう応えるかが大きな課題です。
時短でおいしい食品が、今後のヒット商品となる可能性を秘めています。
⑤ 原材料費が高騰している
近年は原材料費の上昇が業界全体の大きな課題となっています。小麦や油脂、肉類など、輸入に頼る素材の価格が国際情勢や物流の混乱によって大きく変動しているからです。
企業は製造コストの上昇に対処するため、価格設定の見直しやパッケージサイズの変更、原材料の代替などさまざまな手段を講じています。
しかし、価格を上げすぎれば消費者離れにつながるため、品質とコストのバランスを取る工夫が求められています。原材料費の動向は今後の経営戦略にも大きく影響するでしょう。
食品業界の今後はどうなる?将来性を解説

食品業界の将来性を見極めることは、志望先を選ぶ上で重要です。
とくに、人口減少や価値観の多様化が進む中で、業界がどのように変化するのかを理解しておくことで、志望動機に具体性を持たせることができるでしょう。
ここでは、今後の食品業界に関して予測されることを紹介します。
- 国内市場は縮小する可能性が高い
- 海外進出が加速する可能性が高い
① 国内市場は縮小する可能性が高い
日本では少子高齢化が急速に進んでおり、それにともなって食品の国内需要も減少していくと見込まれています。
とくに外食や中食といった分野では、従来のような大量販売の仕組みが通用しづらくなってきました。さらに、健康志向の高まりによって、消費者のニーズも多様化しています。
そのため、多くの企業が少人数向けの商品や高付加価値商品にシフトしながら、利益確保の道を模索しています。
こうした取り組みは、単なる生産量の調整にとどまらず、商品設計や流通戦略の見直しをともなうものです。今後の食品業界では、市場の変化に柔軟に対応できる企業が生き残っていくでしょう。
② 海外進出が加速する可能性が高い
成長のチャンスを海外に求める動きも加速しています。人口が増加している東南アジアや中東では、日本の食品に対する安心感や品質の高さが評価され、需要が拡大しています。
味の素やキッコーマンといった大手企業は、すでに海外展開を本格化。現地の食文化に合わせた商品開発や販売チャネルの整備を進めています。
リスクはあるものの、将来的な成長を考えると海外市場への挑戦は避けて通れません。
企業研究を行う際は、その企業がどの地域に注力しているのか、自分の語学力や異文化適応力がどのように活かせそうかといった視点で見てみると、より深い理解につながるでしょう。
【食品業界】企業の売上高ランキング

食品業界のなかでも、売上高の規模は企業の成長性や安定性を見極めるための重要な指標です。ここでは、食品業界の企業の売上高ランキング(2024年12月期または2025年3月期)を紹介します。
| 順位 | 企業名 | 売上 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2兆9,394億円 | 公式サイト |
| 2 | キリンホールディングス株式会社 | 2兆3,384億円 | 公式サイト |
| 3 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 1兆6,968億円 | 決算短信 |
| 4 | 味の素株式会社 | 1兆5,306億円 | 公式サイト |
| 5 | 日本ハム株式会社 | 1兆3,706億円 | 公式サイト |
| 6 | 明治ホールディングス株式会社 | 1兆1,541億円 | 公式サイト |
| 7 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 9,888億円 | 決算短信 |
| 8 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 8,927億円 | 公式サイト |
| 9 | 山崎製パン株式会社 | 8,570億円 | 公式サイト |
| 10 | 株式会社 日清製粉グループ本社 | 8,515億円 | 公式サイト |
食品業界の主な職種
食品業界には多様な職種があり、それぞれが連携して商品開発から販売までを支えています。ここでは、食品業界の代表的な職種を7つ紹介します。
- 研究開発職
- 生産管理職
- 品質管理職
- 企画職
- マーケティング職
- 営業職
- 事務職
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
① 研究開発職
研究開発職は、新商品を生み出したり、既存商品の味や保存性を改良したりする仕事です。
具体的には、原材料の配合や調理工程を工夫しながら、消費者に支持される味や品質を追求します。消費者の嗜好やトレンドは日々変化しており、商品力を高めることが必要です。
市場調査や試作の繰り返しを通じて、論理的思考力だけでなく実践力も必要とされます。理系出身者が多い職種ですが、食に対する強い関心があれば文系でも活躍できるでしょう。
② 生産管理職
生産管理職は、食品工場における生産工程全体を効率的に進める役割です。たとえば、原材料の調達状況やスタッフの人数を確認し、滞りなく製造が進むよう調整を行います。
計画どおりに生産が進まないと、納期の遅れやコストの増加につながるため、細やかなスケジュール管理とトラブル対応力が求められるでしょう。
また、衛生管理や安全対策も重要な業務の一部であり、責任の重さを感じながら取り組む仕事です。
③ 品質管理職
品質管理職は、製品の安全性や品質を確認し、一定の基準を保つ役割です。たとえば、原材料の受け入れ検査や製造後の微生物検査、異物混入防止策の点検などを行います。
万が一問題が発生すれば、企業全体の信用を失うリスクがあるため、細部まで気を配る姿勢が欠かせません。記録作業やマニュアル作成も多く、丁寧で正確な作業が得意な人に向いている職種でしょう。
④ 企画職
企画職は、新商品やキャンペーンなどの企画を立案し、実行までの流れを設計する仕事です。
たとえば、季節や流行を意識した商品を提案したり、ターゲット層に合わせたパッケージや販促企画を考えたりします。企画を実現するには、他部署との連携が欠かせず、調整力や柔軟な思考力が必要です。
消費者のニーズを汲み取り、アイデアをかたちにする楽しさが魅力の職種といえるでしょう。
⑤ マーケティング職
マーケティング職は、商品を「売れる状態」にするための戦略を立てる役割を担います。たとえば、購買データや市場調査をもとに、販売促進の方向性を検討し、効果的な広告や販促イベントを企画します。
消費者の行動を読み取る力が重要で、数字を扱う分析力と、伝える力の両方が求められる場面が多いでしょう。論理的な視点と感性のバランスが必要な職種です。
⑥ 営業職
営業職は、自社製品を小売店や卸業者に提案し、取り扱ってもらうための交渉や提案を行う仕事です。取引先にとって魅力的な売場づくりや販促案を提供することで、信頼関係を築いていきます。
売上データを活用して説得力のある提案をするには、論理的思考と対人スキルの両方が重要です。人とのやり取りが好きな人や、現場感覚を大切にするタイプに向いているでしょう。
⑦ 事務職
事務職は、受発注管理、請求業務、スケジュール調整など、社内の業務が円滑に進むよう支えるポジションです。
食品業界では特に賞味期限や在庫の管理が重要であるため、正確性とスピードの両方が求められます。
たとえば、発注ミスがあると生産ラインが止まる可能性もあり、見えないところで現場の安心を支える責任の大きな仕事といえるでしょう。コツコツと丁寧に作業するのが得意な人にぴったりです。
食品業界に向いている人の特徴

食品業界で活躍するには、食に対する興味だけでなく、社会の変化や地道な作業にも対応できる柔軟性が必要です。ここでは、食品業界に向いている人の特徴を具体的に5つ紹介します。
志望動機や自己PRを考える際のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
- 食への関心が強い人
- 世の中の変化に敏感な人
- 地道な努力を継続できる人
- チームで協働できる人
- 責任感が強い人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
① 食への関心が強い人
食品業界では、食に対する興味や愛着が大きな力になるでしょう。どの職種であっても、商品の開発や営業活動を通じて「おいしさ」や「安心・安全」を消費者に届ける姿勢が求められます。
たとえば、新商品の提案では、自分自身が本当に食に関心がなければ、説得力のある意見は出せません。
食に日頃から興味を持ち、味や素材への探究心がある人は、業務に対するモチベーションも維持しやすいでしょう。
② 世の中の変化に敏感な人
食品業界はトレンドや社会の変化に敏感な分野です。健康志向やサステナビリティへの関心が高まると、それに対応した商品づくりが求められます。
こうした背景から、普段から情報収集を行い、社会の動きを素早くキャッチできる力が重要です。日々のニュースや消費者の声に目を向け、柔軟に考えを変えられる人は、業界内での活躍が期待されます。
③ 地道な努力を継続できる人
食品関連の業務には、コツコツと進める作業が多くあります。たとえば、品質管理や検査、細かな仕様の調整といった仕事は、地味であっても非常に重要です。
目立つ成果がすぐに出るとは限りませんが、誠実に仕事を積み重ねていける人ほど、信頼される存在になれます。途中で投げ出さず、結果が出るまで丁寧に取り組む姿勢が求められるでしょう。
④ チームで協働できる人
食品業界では、複数の部門が連携して商品を形にしていきます。製造・営業・マーケティング・品質管理など、それぞれの立場を理解しながら動くことが必要です。
一人だけの判断で進めるよりも、仲間と意見を出し合い、全体としての成果を目指す姿勢が求められます。
適切なコミュニケーションを取りながら、協力して仕事を進められる人は、職場で信頼されやすいでしょう。
⑤ 責任感が強い人
食品は人の口に入るものであり、安全性は極めて重要です。アレルゲン表示の確認や衛生管理など、細心の注意が必要な場面も多くあります。
自分の仕事が消費者の健康に直結しているという意識を持ち、丁寧で責任ある行動ができる人が、現場では重宝されるでしょう。
食品業界の志望動機の書き方

食品業界を志望するには、「なぜその業界を選んだのか」「どのような経験が関係しているのか」「入社後どう貢献したいのか」といった軸を明確にすることが大切です。
企業は、学生がどれほど業界や会社を理解し、将来を見据えているかを志望動機から判断します。以下では、説得力のある志望動機を書くための3つのステップを紹介します。
- 志望した理由を書く
- 根拠となる経験を書く
- 今後どう貢献したいかを書く
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
① 志望した理由を書く
食品業界を志望する理由は、なぜ数ある業界の中からこの業界を選んだのかを説明する出発点です。「食を通じて人々の暮らしを豊かにしたい」といった一般的な表現だけでは差別化が難しくなります。
そこで、ありきたりな表現に終始せず、自分なりの視点や関心をもとに、簡潔かつオリジナリティのある理由を述べることが大切です。
自分の考えを明確に言語化することで、他の応募者との差が伝わりやすくなるでしょう。
② 根拠となる経験を書く
志望理由に説得力を持たせるためには、実際の経験に裏打ちされた話が必要です。
たとえば、食育イベントの企画に関わった経験や、食品ロス問題に関心を持ち大学で関連するゼミに参加したといった具体例があると、説得力が増します。
重要なのは、経験をただ羅列するのではなく、その経験を通じて自分が何を感じ、どのような考えを持つようになったかを明確にすることです。
企業が見ているのは、過去の行動から導かれる価値観や考え方。経験の内容だけでなく、自分自身の変化や気づきを丁寧に伝えましょう。
③ 今後どう貢献したいかを書く
志望動機の締めくくりでは、「入社後にどのように活躍したいか」を具体的に伝えることが求められます。ただ「貢献したい」だけではなく、企業の事業や方向性に合わせた提案があると好印象です。
たとえば、健康志向の商品開発に力を入れている企業であれば、「大学で学んだ栄養学の知識を活かし、新商品づくりに貢献したい」といった形で、自分の強みと企業の特徴を結びつけて話すとよいでしょう。
意欲だけでなく、将来のビジョンを持っていることが伝われば、評価にもつながりやすくなります。
食品業界の自己PRの書き方
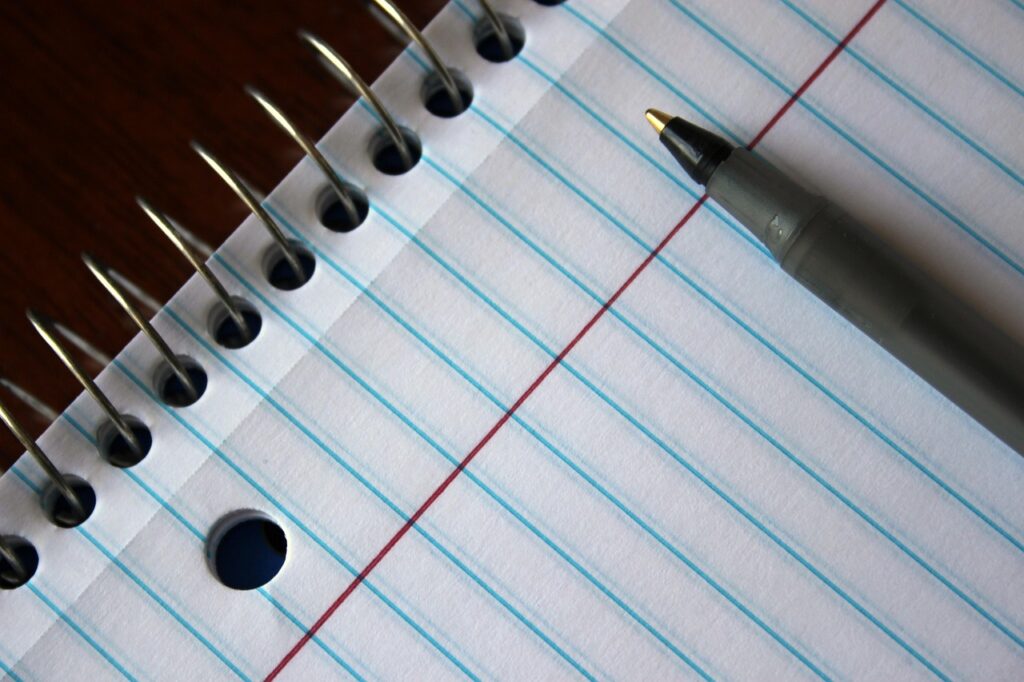
食品業界を志望する就活生にとって、自己PRは採用担当者に自分の強みを印象づける重要な要素です。単なるアピールにとどまらず、「企業にどう貢献できるか」をイメージさせることが重要。
ここでは、効果的な自己PRを作成するために意識したいポイントを3つに分けて紹介します。
- 強みを端的に書く
- 強みを活かしたエピソードを書く
- 今後どう活かすかを書く
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
① 強みを端的に書く
自己PRの冒頭では、まず自分の強みを一言で伝えることが重要です。
たとえば「ゼロから形にする推進力」「声にならないニーズを察知する観察力」「異なる立場をつなぐ調整力」といったように、自分の経験や価値観がにじむような表現を選ぶと印象に残りやすくなります。
採用担当者は多くのエントリーシートを読むため、冒頭の一文で「この人はちょっと違う」と思わせることができれば、読み進めてもらえる可能性が高まるでしょう。
後のエピソードと矛盾のない強みを設定することが大切です。
② 強みを活かしたエピソードを書く
強みを述べたあとは、それを実際に発揮した経験を具体的に示してください。
たとえば「行動力」を伝えたいなら、ゼミ活動で自ら提案をしてチームを動かした経験や、アルバイト先で新たな取り組みを提案して売上向上に貢献した話などが効果的です。
重要なのは、「どのように考え、どう行動したか」「その結果どうなったか」を時系列でわかりやすく説明することです。
また、自分だけでなく周囲への影響やチームへの貢献も意識して書くことで、組織の中で活躍できるイメージを与えられます。
③ 今後どう活かすかを書く
最後に、自分の強みを食品業界でどのように活かしていきたいかを明確にしましょう。
たとえば「傾聴力」が強みであれば、「消費者の声を丁寧に拾い、ニーズに合った商品づくりに貢献したい」といったように、具体的な業務と結びつけると説得力が増します。
企業が重視するのは、自分をどう売り込むか以上に「自社でどう活躍できるか」。そのため、企業研究を踏まえたうえで、自分の強みと企業の方向性がどのように重なるのかをしっかりと考えておきましょう。
食品業界の全体像を理解してから選考に進もう!

食品業界は、第一次産業から小売業まで多様なプレイヤーが関与し、人々の生活に深く根ざしたビジネスモデルが特徴的です。
さらに、売上高の高い大手企業が業界を牽引しており、志望動機や自己PRの作成にも豊富な題材が存在します。
つまり、食品業界を正しく理解し、自分の強みと重ね合わせることが、就職活動を成功に導く大きなポイントだといえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











