旅行業界を目指す就活生必見!仕事内容・企業・求められるスキルを徹底解説
「旅行が好き」「人に感動や思い出を届ける仕事がしたい」そんな思いから旅行業界に興味を持つ就活生も多いのではないでしょうか。
人々の非日常体験をサポートする旅行業界は、単に旅を売るだけでなく、顧客の人生に残る時間を一緒に創り上げるやりがいのある仕事です。
とはいえ、「旅行業界って実際どんな仕事があるの?」「英語は必須?」「将来性は大丈夫?」と不安や疑問を感じている方も少なくないでしょう。
本記事では、旅行業界の基本的な構造や動向、職種ごとの仕事内容・年収、主要企業の特徴、さらには就活で活かせるスキルまで、就活生に役立つ情報をわかりやすく解説します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
旅行業界とは?

ここでは、旅行業界の動向、今後の展望や課題を解説します。
業界理解を深めれば、説得力のある志望動機や自己PRを作成できるでしょう。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①旅行業界の動向
旅行業界は、社会情勢の影響を強く受けやすい「平和産業」と言われています。
新型コロナウイルスによって業界全体が大打撃を受けたことは記憶に新しいですが、実は2003年のSARSや2011年の東日本大震災など、旅行業界は過去にも何度か同様の危機に見舞われてきました。
しかし近年は、行動制限の解除や円安効果もあって、国内旅行・インバウンド(訪日外国人旅行)は急速に回復中です。
さらに、「ワーケーション」や「オンラインツアー」「MICE」などの新しい旅行の形が登場し、サービスの多様化が進んでいます。
②旅行業界の将来性
旅行業界は「不安定ながら可能性に満ちている」業界です。
国際情勢や感染症、物価上昇といった外的要因に左右されやすい反面、観光立国としての日本の政策的な後押しもあり、インバウンド需要は今後も高まると予想されています。
また、働き方改革による平日の旅行ニーズ、地方創生の一環としての観光資源の開発、デジタル技術によるサービスの進化など、旅行のあり方そのものが変わりつつありますよ。
学生からの業界人気も徐々に回復しており、語学力や異文化理解、ITリテラシーなどを持つ人材には大きなチャンスが広がるでしょう。
③旅行業界の今後の課題
一方で、旅行業界が抱える課題として、人手不足と労働環境の改善は見逃せません。
まず、コロナ禍による人員削減や離職の影響が長引き、需要回復に人材供給が追いついていない現状があります。
また、OTA(インターネット専業の旅行代理店)との競争も激化しており、リアル店舗型の旅行会社は新しい付加価値の提供が求められています。
さらに、アウトバウンド(海外旅行)は回復が遅く、円安や航空費の高騰がその足かせとなっています。こうした課題に向き合うためには、デジタル対応力や柔軟な発想を持つ若手人材の力が必要不可欠です。
業界が求めているのは、ただ旅行が好きな人ではなく、未来の旅行を一緒に創る意欲のある人だと言えるでしょう。
旅行業界の3つの業態と仕事内容

ここでは、旅行業界の3つの業態と仕事内容を解説します。
旅行業界は、一見するとどの会社も「旅行を扱っている」ように見えますが、業態によって担っている役割や仕事内容が大きく異なることを覚えておきましょう。
①旅行会社
旅行会社は、自社で旅行商品を企画・販売する企業で、旅行業界の中心的な存在です。
代表例としては、JTBや近畿日本ツーリスト、阪急交通社などがあり、これらの企業では企画・手配・販売・添乗といった旅行に関する一連の業務を担います。
旅行業登録の種類によって取り扱える旅行の範囲が決まっており、第1種旅行業者であれば海外旅行も含めて幅広いプランを提供可能です。
営業職や企画職だけでなく、添乗員や法人営業など多彩な職種があります。
②旅行代理店
旅行代理店は、旅行会社が企画・製作したツアーや商品を、旅行会社に代わって販売する役割を担う企業です。いわば旅行会社の商品を「販売窓口」として扱う存在で、自社で企画は行えません。
主な仕事は、店頭やWebでの接客・販売業務が中心です。自社の商品ではなく他社の商品を扱うため、プランの自由度は低く、接客や説明の丁寧さが求められます。
小田急トラベルやセントラル観光などが代表的な企業です。
③OTA
OTAは Online Travel Agency(オンライン・トラベル・エージェンシー) の略で、日本語では「オンライン旅行代理店」と訳されます。
インターネット上だけで旅行商品の予約・販売を行っており、楽天トラベル、じゃらんnet、一休.comなどが日本の代表的なOTAです。
実店舗を持たないため、店舗の運営費用や人件費を削減でき、ユーザーにとっても価格面や操作性でメリットがあります。
仕事内容としては、デジタルマーケティング、システム開発、カスタマーサポート、掲載施設との交渉などが中心で、旅行業×ITという分野で活躍したい人におすすめの業態です。
「業界分析」はこれ1冊だけ!業界分析大全を受け取ろう!
就活で志望業界を説得力高く語るには、「なぜこの業界なのか」をデータやトレンドで裏づける業界分析が欠かせません。とはいえ、IR資料やニュースを一から読み解くのは時間も手間もかかり、表面的な理解で面接に臨んでしまう学生も少なくありません。
そこで就活マガジン編集部では、主要20業界を網羅し「市場規模・最新トレンド・主要企業比較」まで1冊で整理した『業界分析大全』を無料提供しています。業界研究に迷ったら、まずはLINEを登録で特典をダウンロードして「面接で差がつく業界知識」を最短で手に入れてみましょう。
業界知識の深さは選考官が必ずチェックするポイントです。志望度の高さもアピールできるのでおすすめですよ。
旅行業界の3つの商品
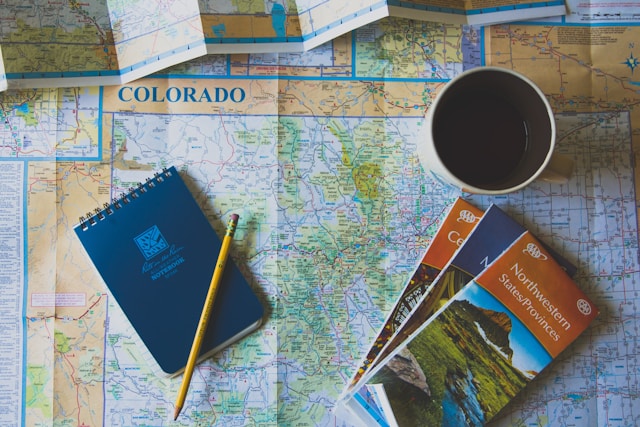
ここでは、旅行業界の3つの商品を紹介します。
それぞれの特徴を理解することで、自分に合った働き方や志望先を見つけるヒントになるでしょう。
①募集型企画旅行
募集型企画旅行とは、旅行会社があらかじめ旅行内容を企画し、広く一般の顧客に向けて販売するツアー商品のことです。
たとえば、「2泊3日で北海道の観光地を巡るプラン」や「東京発・沖縄ビーチリゾート満喫ツアー」などがこれに該当します。
旅行会社は、ホテルの宿泊枠や飛行機・新幹線の座席などをまとめて確保し、1つの商品としてパッケージ化。自社サイトやパンフレット、旅行代理店経由で販売するのが一般的です。
価格がわかりやすく、移動や宿泊も一括で手配されているため、初心者やシニア層、ファミリー層に人気があります。
旅行会社の企画職や販売スタッフ、マーケティング部門などが密接に関わる商品です。
②受注型企画旅行
受注型企画旅行は、顧客の要望をヒアリングしたうえで、旅行会社がそのニーズに合わせて企画・手配を行う旅行商品です。
例としては、「ある企業の社員旅行として、温泉地での研修+観光を組み合わせた2泊3日プラン」や「高校の修学旅行での歴史学習ツアー」などがあります。
顧客は個人の場合もありますが、団体旅行(企業・学校・地域グループなど)としてのニーズが多いのが特徴です。
受注型企画旅行では、企画力・交渉力・ネットワークが大いに発揮されるため、法人営業やプランナーといった提案型の職種に関心がある方にぴったりです。
③手配旅行
手配旅行とは、旅行者が行き先や日程を自由に決め、その内容に応じて旅行会社が個別に手配する旅行スタイルです。
たとえば、「来月、京都に1泊2日で行きたいので、新幹線とホテルをお願いできますか?」というような依頼が該当します。
あくまでも旅行者が主体で、旅行会社はその希望に合わせて宿泊施設や交通機関、チケットなどを予約・手配する位置づけです。
現在ではインターネット予約が普及し、個人でもある程度手配ができるようになっていますが、旅行会社を通じて安心感やサポートを得たい層には根強いニーズがあります。
旅行業界の4つの職種と仕事内容

ここでは、旅行業界の4つの職種と仕事内容を紹介します。
旅行業界には多様な職種が存在し、それぞれ役割ややりがいが異なるため、以下で詳しく見ていきましょう。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①商品開発・企画
旅行の目的地やテーマ、日程、価格などを組み立て、「季節限定の温泉ツアー」や「世界遺産を巡るプラン」のような魅力あるツアーをつくり上げるのが「商品開発・企画」の仕事です。
近年は、ECサイトでの販売やオンライン企画商品の需要も高まっており、トレンドに合わせた柔軟な発想力やスピード感が求められています。
旅行全体の流れや顧客のニーズを深く理解していることが強みとなるため、接客や添乗業務などの現場経験を積んだうえでステップアップするケースが多いでしょう。
②法人営業
法人営業は、企業の出張手配や社員旅行、官公庁の研修旅行、学校の修学旅行など、大口の顧客に対して旅行プランを提案・調整する仕事です。
契約金額が大きく、複数人・長期にわたるプランの提案になるケースが多いため、責任もやりがいも非常に大きい職種と言えるでしょう。
顧客の業種や目的に応じて、最適なプランを柔軟に構築していく力が求められるため、ヒアリング力や調整力、プレゼン力など幅広いビジネススキルが活かされます。
「大規模な案件を動かしたい」「社会との関わりを感じながら働きたい」という方におすすめです。
③個人・店頭営業
個人・店頭営業は、旅行会社や旅行代理店の店舗に立ち、顧客に対して旅行の提案・手配を行います。
主な仕事は、家族旅行や新婚旅行、一人旅など、旅行者の目的や希望に応じて最適なプランを紹介し、一緒に旅のかたちを考えることです。
初めての旅行で不安を抱える顧客もいるため、親身な対応や丁寧な説明が求められるシーンが多いでしょう。
「人と話すのが好き」「誰かの思い出づくりをサポートしたい」という想いを持つ方に向いています。
➃旅行添乗員
旅行添乗員は、ツアーに同行しながら、顧客が安全かつ快適に旅行を楽しめるようにサポートする仕事です。具体的には、スケジュール管理・観光地での案内や誘導・トラブル対応などを行います。
勤務先は旅行会社とは限りません。添乗員専門の派遣会社を通じて働くケースも多くあります。
全国や海外を飛び回ることも多いため、体力や柔軟な対応力が求められますが、「現場で人と関わりたい」「非日常を共に楽しみたい」と感じる方には大きな魅力のある職種です。
旅行業界の職種別平均年収ランキング

ここでは、旅行業界の職種別平均年収ランキングの一覧を紹介します。
| 順位 | 職種 | 年収 |
| 1位 | 客室乗務員 | 約534万円 |
| 2位 | 旅行会社カウンター係 | 約496万円 |
| 3位 | 観光バス運転手 | 約453万円 |
| 4位 | ツアーコンダクター | 約394万円 |
| 5位 | ホテル・旅館のフロント係 | 約330万円 |
最も高年収なのは「客室乗務員(約534万円)」です。語学力やホスピタリティなど、厳しい訓練を経て働くことが求められる分、待遇面でも比較的恵まれていることが分かります。
一方、「旅行会社カウンター係」や「ツアーコンダクター」などは400万円前後の水準ではありますが、勤務形態や地域によって差が出やすい職種です。
「ホテル・旅館のフロント係」は約330万円とやや低めであることから、安定した収入を重視する場合には、他の職種を考慮する必要があるでしょう。
旅行業界の代表的な7つの企業

ここでは、旅行業界を代表する7つの企業を紹介します。
旅行業界を志望するうえで、「どの企業が自分に合っているのか」「企業ごとにどんな特徴があるのか」を理解しておくことはとても大切ですよ。
①JTB
JTBは、1963年に創業された日本最大手の旅行会社です。国内外に広がるネットワークを基盤に、個人・団体旅行から法人向けの企画まで、幅広いニーズに応えてきました。
「エースJTB」や「ルックJTB」などの主力商品では、旅行先の選択肢や自由度の高さが特徴です。
また、会議や研修などのMICE事業、地域振興を目的とした官民連携プロジェクトにも積極的に参画するなど、単なる旅行販売にとどまらず、社会全体に新たな価値を提供している企業ですよ。
| 企業名 | JTB |
| 設立年 | 1963年11月12日 |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル |
| 代表者名 | 山北 栄二郎 (代表取締役 社長執行役員) |
| 公式サイト | https://www.jtbcorp.jp/ |
②KNT-CTホールディングス
KNT-CTホールディングスは、近畿日本ツーリストとクラブツーリズムを中核とする企業グループで、国内外に向けた旅行事業を軸に多様なサービスを展開しています。
なかでもクラブツーリズムでは、登山や歴史探訪といった趣味に特化したツアーを企画し、他社にはない独自性を打ち出してきました。
さらに、ネット予約の利便性向上やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にも注力しており、業務効率化や顧客体験の向上を図っています。
社内では、働き方改革や新たな事業分野への挑戦が進んでおり、変化を恐れない柔軟な企業文化が特徴だと言えるでしょう。
| 企業名 | KNT-CTホールディングス |
| 設立年 | 1947年5月26日 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル |
| 代表者名 | 小山 佳延(代表取締役社長) |
| 公式サイト | https://www.kntcthd.co.jp/ |
③日本旅行
日本旅行は1905年に創業した国内最古の旅行会社で、JR西日本の連結子会社という立場を活かし、鉄道を中心とした旅行商品に強みを持っています。
「赤い風船」シリーズでは、JRとのセットプランをはじめとした多彩な国内ツアーを提供しており、幅広い年代から支持を集めてきました。
また、教育旅行や企業・団体向けの企画にも対応しており、個人旅行にとどまらない事業展開を進めています。
地域創生やインバウンド振興といった社会的な課題にも積極的に取り組んでいるため、今後の更なる成長が期待されるでしょう。
| 企業名 | 日本旅行 |
| 設立年 | 1949年1月28日(創業:1905年11月) |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング12階 |
| 代表者名 | 小谷野 悦光 (代表取締役社長 兼 執行役員) |
| 公式サイト | https://nta-corporate.jp/ |
④阪急交通社
阪急交通社は1948年に創業された旅行会社です。「トラピックス」や「クリスタルハート」など複数のブランドを展開して、長年にわたり業界内で安定した存在感を維持してきました。
昨今は、訪日観光の需要拡大を見据えたサービス展開や、地方との連携による観光資源の開発にも力を入れており、旅行業を通じた地域貢献を重視しています。
堅実な経営姿勢を持ちつつ、新たな価値創出にも挑戦し続ける企業だと言えるでしょう。
| 企業名 | 阪急交通社 |
| 設立年 | 2007年10月1日 (創業:1948年2月22日) |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA |
| 代表者名 | 酒井 淳(代表取締役社長) |
| 公式サイト | https://www.hankyu-travel.co.jp/ |
⑤ジャルパック
ジャルパックは、日本航空(JAL)グループの旅行会社として、「JALダイナミックパッケージ」などの航空ネットワークを活かした旅行商品を多数取り揃えています。
国内・海外に展開するグローバルなネットワークを通じて、航空会社系ならではの信頼感やマイル付与といった付加価値を提供することで、顧客満足度の向上につとめてきました。
旅行と航空の融合によって、他社にはないユニークな価値を生み出している企業だと言えます。
| 企業名 | ジャルパック |
| 設立年 | 1978年4月1日 |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル |
| 代表者名 | 平井 登(代表取締役社長) |
| 公式サイト | https://jalpak.jp/ |
⑥リクルート(じゃらん)
リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」を中心に、ITと旅行を融合させたサービスを展開しています。
宿泊予約を主軸としつつ、交通機関やレジャー体験の予約機能も拡充しており、旅行の計画から手配までを一括で完結させられることが強みです。
口コミやレビュー機能を活用したユーザー視点のサービス設計がなされている点も、利用者から高く評価されています。
テクノロジーと観光の両方に関心がある人には、魅力的なフィールドだと言えるでしょう。
| 企業名 | リクルート |
| 設立年 | 2012年10月1日 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
| 代表者名 | 北村 吉弘(代表取締役社長) |
| 公式サイト | https://www.recruit.co.jp/ |
⑦HIS
HIS(エイチ・アイ・エス)は、1980年に設立された旅行会社で、海外旅行を中心に急成長を遂げてきました。
格安航空券の提供を出発点としながらも、自由度の高いツアーやユニークな商品展開によって、若年層を中心に強い支持を集めていますよ。
現在では、「変なホテル」などのホテル事業や、訪日旅行、地域創生、エネルギー事業など、旅行業の枠を超えた分野にも進出しています。
挑戦的で柔軟な企業文化が根づいており、新しいことに積極的にチャレンジしたい学生には、特に相性が良いかもしれません。
| 企業名 | HIS(エイチ・アイ・エス) |
| 設立年 | 1980年12月19日 |
| 本社所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
| 代表者名 | 矢田 素史(代表取締役社長 兼 CEO) |
| 公式サイト | https://www.his.co.jp/ |
旅行業界で働く4つのメリット

ここでは、旅行業界で働く4つのメリットを紹介します。
自分がこの業界で何を得られるのかを考える際の参考にしてください。
①観光地や旅行商品に自然と詳しくなれる
旅行業界で働くと、観光地や旅行商品に自然と詳しくなれます。
全国各地や世界の観光地に関する最新情報に日常的に触れることになり、人気のスポットだけでなく、まだあまり知られていない穴場やお得な交通・宿泊プランなども把握できますよ。
その知識は業務に活かせるだけでなく、自身のプライベート旅行もより充実させる際にも役立つでしょう。
②お客様の楽しい思い出づくりをサポートできる
旅行業界で働くと、お客様の楽しい思い出づくりをサポートできます。
旅行は、誕生日や結婚記念日、ハネムーンなど、大切な節目に活用されることも少なくありません。旅行業界では、そうした人生の特別な瞬間を一緒に計画できます。
「ありがとう」「またお願いしたい」といった言葉を直接もらえる場面も多く、モチベーションの維持につながるでしょう。
③自分の提案が直接売上や満足度につながる
旅行業界で働くと、自分の提案が売上や満足度に直結します。商品開発や営業の仕事では、自分が企画・提案したプランが実際に売れたり、顧客からの高評価を得られることもありますよ。
自分のアイデアが形になり、会社の業績や顧客満足に結びついたときは、大きな達成感を味わえるでしょう。
そのため、「人と接する力」と「企画力」を同時に活かしたい人にとっては、非常にやりがいのある業界だと言えます。
➃語学力やコミュニケーション能力が活かせる
旅行業界で働くと、語学力やコミュニケーション能力が活かせますよ。特に、訪日外国人を案内する場面や、海外旅行を手配する業務では、外国語でのコミュニケーションが求められます。
語学に自信がなくても、現場での実践を通してスキルを磨けるため、グローバルな舞台で活躍したい人にとって魅力的な業界と言えるでしょう。
また、旅行という「非日常」の体験を提供するには、相手の期待や感情をくみ取る力が重要です。業務を通じて、こうしたコミュニケーションスキルも自然と養われていくでしょう。
旅行業界で働く3つのデメリット

ここでは、旅行業界で働く3つのデメリットを紹介します。
どんなに魅力のある業界でも、必ず向き・不向きや大変な面は存在するため、あらかじめデメリットを知っておくことで、「思っていた仕事と違った」と後悔するリスクを減らせるでしょう。
①景気や災害・感染症など外的要因の影響を受けやすい
旅行業界は、景気や災害・感染症など外的要因の影響を受けやすい傾向にあります。
たとえば、新型コロナウイルスの流行時には国内外の移動が制限され、売上が急減した企業も少なくありませんでした。
この他、台風や地震といった自然災害、あるいは国際情勢の悪化によるツアー中止など、旅行業界は常にリスクがつきまとう業界だと頭に入れておきましょう。
②シーズンによって勤務が不規則になりがち
旅行業界は、シーズンによって勤務が不規則になりがちです。特に、旅行需要が高まる長期休暇シーズンや週末は、多くのスタッフが現場対応に追われます。
個人営業や添乗員業務に携わると、シフト勤務や早朝・深夜の出勤が必要になるケースもあるでしょう。
特に海外ツアーでは、現地の時差にあわせた勤務や現地滞在が求められることもあり、生活リズムが乱れやすい点には注意が必要です。
③精神的・体力的にハードな場面もある
旅行業界は、精神的・体力的にハードな場面もあります。顧客の期待が高い分、トラブルが起きたときの対応に大きなプレッシャーがかかるからです。
特に、天候による交通機関の乱れや、現地でトラブルが発生した際には、迅速かつ冷静に対応しなければなりません。
また、繁忙期の連勤や移動の多さによる体力面への負担も無視できないでしょう。
旅行業界への就職で有利に働くス6つのスキル

旅行業界に興味を持っていても、「どのような経験が評価されるのか分からない」「アピールできるスキルがない気がする」と悩む人は多いのではないのでしょうか。
ここでは、旅行業界への就職で有利に働く6つのスキルを紹介します。
- 旅先での体験や留学を通じた異文化理解
- 英語をはじめとする語学コミュニケーション能力
- 国内外の地理や観光地に関する知識
- 鉄道や交通機関に関する情報への理解と関心
- 接客業やサービス業での実務経験
- 応募先企業のサービスを実際に利用した経験
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①旅先での体験や留学を通じた異文化理解
旅行業界に就職する際は、旅先での体験や留学を通じた異文化理解が役立ちます。自身が異文化に触れた経験は、顧客に対するリアルなアドバイスや提案につながる強みになるからです。
そのため、志望動機や自己PRに「どんなことに驚いたか」「現地で何を学んだか」といった具体的なエピソードを盛りこめば、より説得力をもたせられるでしょう。
訪問国の数よりも、その体験をどう言語化できるかが評価の分かれ目になります。
②英語をはじめとする語学コミュニケーション能力
旅行業界に就職する際は、英語をはじめとする語学コミュニケーション能力が非常に重視されます。インバウンドの拡大や海外旅行商品の取扱いなどで、語学力を活かす場面が多くあるからです。
特に英語は、添乗員や法人営業の現場で頻繁に使われるため、基礎的な会話力があると評価されやすいでしょう。
TOEICのスコア提出が求められる企業だと、数値でアピールして他の応募者と差をつけられます。
③国内外の地理や観光地に関する知識
旅行業界では、国内外の地理や観光地に関する知識が深い人が求められます。
旅行商品を案内する際に、「〇〇に行きたい」という顧客の要望に対して、行き方や見どころをスムーズに案内できることは大きな信頼につながるからです。
そのため、観光地の知識を積極的に学んでおけば、面接でも具体的な提案力があるとみなされて就職に有利に働くでしょう。
④鉄道や交通機関に関する情報への理解と関心
旅行業界に就職するうえで、鉄道や交通機関に関する情報への理解と関心があることは有利に働きます。
国内旅行では、鉄道やバスを利用した移動が多く、主要駅や新幹線の種類、観光列車などの知識も業務上重要だからです。
特に鉄道に興味がある人は、自分の知識を武器に提案や企画に活かせる場面が多いでしょう。
駅名や路線図に詳しいことも十分アピールポイントになりえます。旅行業界にとって交通手段の理解は「商品知識の一部」であるため、見落とせないスキルです。
⑤接客業やサービス業での実務経験
旅行業界への就活においては、接客業やサービス業での実務経験は大きなアピールポイントになります。
旅行会社の顧客には高額商品を求める富裕層も多く、丁寧な接客態度や言葉遣いが求められるからです。
そのため、学生時代に飲食店やアパレルなどで接客を経験している方は、その経験を通して「どのような気配りを心がけていたか」「どんな顧客対応を評価されたか」などを伝えると良いでしょう。
特に「明るくはきはきと対応できること」は、旅行業界では重要な資質とされています。
⑥応募先企業のサービスを実際に利用した経験
旅行業界への就職を目指すうえで、応募先企業のサービスを実際に利用した経験は大きな武器になります。
自らパッケージツアーを予約して旅行を楽しんだり、カウンターで相談したりといった体験を通じて、その企業ならではの接客やサービスの特徴、魅力を肌で感じとれるからです。
こうした経験をエントリーシートや面接で活かす際は、「どこに魅力を感じたか」「どのような工夫が印象に残ったか」「逆に改善の余地があると感じた点」などを、自分の言葉で具体的に伝えると良いでしょう。
サービスの体験談から導き出した志望動機は説得力があるため、他の就活生と差をつけられます。
旅行業界を理解して自分の働き方を考えよう
旅行業界は、時代の変化に敏感でありながらも、人と人とのつながりや感動を大切にする、非常に魅力的な業界です。
本記事で紹介したように、仕事内容や企業、求められるスキルは多岐にわたりますが、自分の強みや価値観と向き合いながら業界研究を深めることで、「自分に合った働き方」が見えてくるでしょう。
「旅行が好き」「人と関わる仕事がしたい」といった思いは、旅行業界を目指すきっかけとして十分です。まずはその関心を出発点に、業界について理解を深めていきましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











