面接の録音は違法?マナーと注意点を就活生向けに解説
「面接って録音してもいいのかな?バレたらまずい?」
就活中、面接の振り返りや対策のために録音したいと思う人も多いはず。しかし、企業側の印象や法的な問題が気になって、なかなか踏み出せないのが本音ではないでしょうか。
そこで本記事では、「面接の録音はOKなのか?」「録音する際の注意点は?」といった疑問にお答えしつつ、実際の活用方法や代替手段についてもわかりやすく解説していきます。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者
記事の監修者
人事担当役員 小林
1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る面接での録音はマナーを守ろう

就職活動の面接で録音をしても大丈夫なのか、疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
結論から述べると、面接の録音は法律で明確に禁止されておらず、マナーを守れば可能です。
ただし、相手への配慮がないまま録音を行うと、思わぬトラブルを招いたり、印象を悪くしたりする可能性があります。
自分の都合だけでなく、相手の立場を思いやった行動が求められる点に注意しましょう。
録音以外にも、それぞれの場面で求められるマナーを正しく理解しておくことが重要です。以下の記事では、形式別の面接マナーを徹底解説しているので、面接前にぜひ確認しておきましょう。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
面接の録音が違法になる場合とならない場合の違い

面接の録音について不安を感じる就活生は少なくありません。特に、「勝手に録音してもいいのか」「トラブルにならないか」といった疑問を持つ方は多いでしょう。
ここでは、面接の録音が違法となる場合と、そうでない場合の違いについてわかりやすく解説します。
- 違法になるパターン
- 違法にならないパターン
① 違法になるパターン
面接で録音が違法になるのは、主に「相手に無断で録音した場合」です。
たとえ本人同士の会話であっても、相手の許可なく録音を行えば、プライバシーの侵害として民事上のトラブルに発展するおそれがあります。
また、面接官に無断で録音していたことが発覚すれば、不信感を招くだけでなく、採用選考にも影響を及ぼしかねません。
録音を希望する場合は、必ず事前に「記録のために録音してもよろしいですか」といった一言を添えて確認を取りましょう。マナーを守り、誠実な姿勢で臨むことが大切です。
無断録音が発覚すると「この人は信用できるか?」という疑念が一気に高まります。信頼関係を損ねる行為は、それだけで評価を大きく下げる原因になりかねません。
また、企業によっては社内規定で「面接内容の録音・録画を禁止」と明記している場合もあります。確認なく録音すると規則違反にもなり得るので、確認は必ず取りましょう。
録音が禁止されている場合でも、面接で話した内容を後から振り返りたいですよね。そこでおすすめなのが就活日記。以下の記事では、面接直後に就活日記として記録するメリットや始め方、書き方、継続のコツまで詳しく解説しているので、ぜひ実践してみましょう。
② 違法にならないパターン
録音が常に違法となるわけではありません。自分が当事者であり、面接の録音を個人的に保管するだけなら問題ないケースが多いです。
ただし、録音したデータを第三者に提供したり、インターネット上で公開したりすれば、名誉毀損やプライバシーの侵害として問題になる可能性があります。
重要なのは、録音の目的と使い方。内容を他人に見せたり拡散したりせず、自分の選考対策としてのみ活用するようにしましょう。
録音は、その場で気づけなかった質問の意図や回答の癖を後から振り返るのに有効です。ただ、無断での録音はやはりリスクも生じかねません。許可は必ず取りましょう。
また録音を残すなら、面接の冒頭や終了直後に要点を簡単にメモしておくと、振り返りやすくなります。特に自分の発言の順序などは、音声よりも目で確認できるとわかりやすいです。
面接を録音するメリット

面接を録音することには、就活生にとって多くの利点があります。ここでは、録音を通じて得られる5つのメリットを紹介します。
- 自分の回答を客観的に振り返ることができる
- 面接官の質問傾向を把握できる
- 就活仲間の受け答えを参考にできる
- ハラスメント発言の証拠として録音を残すことができる
- 内定後の選考過程を見直す際に活用できる
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
① 自分の回答を客観的に振り返ることができる
面接を録音することで、自分の話し方や回答内容を客観的に見直すことができます。面接中は緊張のあまり、自分が何を話したのかを正確に覚えていないことも珍しくありません。
しかし、録音を後から聞き返すことで、話していた内容やトーン、無意識の癖など、実際の様子を冷静に確認できるでしょう。
自分では気づかなかった話し方のクセや「えー」「あのー」といった無意識の口癖にも気づけるため、改善に大きく役立てることができます。
録音を振り返る際は、話の「構成」や「答えの順序」も意識すると改善につながりやすいです。特に、「結論から話せているかどうか」は評価に大きく関わるので重点的に見直してほしいポイントです。
また、早く改善するためには良い点と悪い点を第三者視点で分析することが欠かせません。「全体の流れ」「口癖や間の取り方」など、着眼点を変えて録音を聞くと修正スピードが上がりますよ。
② 面接官の質問傾向を把握できる
録音を活用すれば、企業ごとの質問の特徴や傾向を把握しやすくなります。
たとえば、ある企業ではチームワークに関する質問が多かったり、別の企業では自己分析の深さを重視していたりと、面接にはそれぞれのスタイルがあります。
複数の企業を同時に受ける就活生にとっては、質問内容が混同してしまうことも少なくありません。録音しておけば、過去のやり取りを確認しながら企業ごとの特徴を明確に記録できます。
こうした情報を積み重ねることで、自分の受け答えの精度が高まり、似たような質問に対しても落ち着いて対応できるようになります。
質問傾向を掴むことは、「面接対策の質」を大きく左右します。過去の質問を整理して「どのような切り口で深掘りされたか」で大きく分類しておくことで、対策の方向性が見えやすくなりますよ。
さらに、複数の面接でも繰り返し出てくる質問に気づくと、自分の回答が場当たり的になっていないかもチェックできます。事前にパターンを整理して、次の本番で落ち着いて対応できるよう準備しましょう。
③ 就活仲間の受け答えを参考にできる
大きな工夫を集団面接では、他の学生の発言内容も録音に含まれます。自分にはない視点や表現の工夫から、大きな学びを得られるでしょう。
特に、自己PRや志望動機の伝え方が上手な人の発言は参考になります。
また、自分と似た経験を持つ人がどのように話を組み立てているかを知ることで、表現のバリエーションを増やすことができるでしょう。
ただし、他人の発言をそのまま真似するのではなく、自分の言葉でアレンジすることが大切です。
④ ハラスメント発言の証拠として録音を残すことができる
もし面接中に不適切な発言や高圧的な態度を受けた場合、録音があればその内容を証拠として残すことができます。
就活生は立場が弱く、面接中に強く反論するのは難しい場面もあるかもしれません。録音を活用すれば、冷静に状況を整理し、あとから適切に対応しやすくなるでしょう。
場合によっては、大学のキャリアセンターや第三者機関へ相談する際の資料としても活用できるはずです。ただし、録音した内容をSNSなどで感情的に公開することは避けてください。
情報の取り扱いには十分注意し、必要に応じて正しい手順を踏んで活用することが重要です。
以下の記事では、圧迫面接で「意地悪な質問」をされた際の対応方法を紹介しています。中には、選考に進まないほうがよい企業もあるため、ハラスメント発言を受けたかもしれないと感じた方は、自分を守るためにも内容を理解しておきましょう。
⑤ 内定後の選考過程を見直す際に活用できる
面接の録音は、内定を獲得した後にも役立ちます。
どのような質問にどう答えたかを正確に振り返ることで、自分が評価されたポイントや強みを再確認することができるからです。
また、選考過程を体系的に振り返ることで、就職活動全体の流れを把握でき、次のキャリアステップや転職時にも応用できます。
さらに、後輩からアドバイスを求められた際にも、実体験に基づいた具体的なフィードバックができるでしょう。
面接質問事例集100選|聞かれる質問を網羅して選考突破を目指そう

「面接がもうすぐあるけど、どんな質問が飛んでくるかわからない……」
「対策はしてるつもりだけど、いつも予想外の質問が飛んでくる……」
面接前の就活生が抱える悩みとして「どんな質問をされるのか分からない」という問題は大きいですよね。頻出質問以外が予想しきれず、面接で答えに詰まってしまった人もいるでしょう。
また、面接経験がほとんどない人は、質問を予想することも難しいはず。そこでオススメしたいのが、就活マガジンが独自に収集した「面接質問事例集100選」です!
400社以上の企業の面接内容を厳選し、特に聞かれやすい100の質問を分かりやすく紹介。自分の回答を記入する欄もあるため、事前に用意した回答を面接直前に見返すことも可能ですよ。
面接で特に失敗しやすいのが「予想外の質問に答えられなかったパターン」です。よくある質問内容を知っておくだけでも、心の準備ができますよ。
また、志望動機などの頻出質問も、企業によってはひねった聞き方をしてくることも。質問集では特殊な例も網羅しているため、気になる人はぜひダウンロードしてくださいね。
\400社の質問を厳選/
面接で録音する方法

面接の内容を後から見返すために録音したいと考える就活生は多いでしょう。
ただし、録音の方法を誤ると、音がうまく記録されなかったり、デバイスが動作しなかったりすることもあるかもしれません。
ここでは、面接の形式ごとに適した録音の方法を紹介します。
- スマートフォンの録音機能やボイスレコーダーを使う
- Web面接ではパソコンの画面録画や録音ソフトを使う
① スマートフォンの録音機能やボイスレコーダーを使う
対面面接では、スマートフォンの録音アプリやICレコーダーを使うのが一般的です。
カバンやポケットの中に入れたままだと音がこもるため、机の上など声を拾いやすい位置に置いてください。
事前にアプリの使い方や録音状態を確認しておくと、安心して面接に臨めるでしょう。
以下の記事では、面接でメモを取る際の注意点やノートの選び方について解説しています。録音ができない場合でもメモなら残せることもあるので、今後の面接対策の参考にしてみてください。
② Web面接ではパソコンの画面録画や録音ソフトを使う
Web面接では、パソコンの内蔵マイクや録音ソフトを使って録音する方法が効果的です。音声だけでなく画面全体を記録できるソフトもあり、話し方や表情の振り返りにも役立ちます。
「OBS Studio」や「Bandicam」などの無料ソフトを使えば、操作も比較的かんたんです。録音前にはマイク設定や保存先を確認し、実際に短いテスト録音をしておくと安心でしょう。
また、通信環境が不安定だと音が途切れることがあります。できるだけ安定したWi-Fi環境を確保し、イヤホンマイクを使用することで音質の向上も期待できるでしょう。
面接で録音する際に守るべきマナー

面接を録音すること自体は違法ではありませんが、マナーを守らずに行うと企業側に不快感を与えたり、評価に悪影響を及ぼしたりする可能性があるでしょう。
ここでは、面接時に録音を行う際に意識しておくべき基本的なマナーを5つ紹介します。
- 録音の可否を面接官に事前に確認する
- 録音は私的利用にとどめる
- 録音機器は面接の妨げにならないようにセットする
- 録音をしていることを隠さないようにする
- 録音内容の取り扱いには注意をする
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
① 録音の可否を面接官に事前に確認する
録音を行う際は、必ず面接官に許可を取りましょう。無断で録音してしまうと、相手からの信頼を失い、不信感を抱かせる恐れがあります。
「復習のために録音させていただいてもよろしいでしょうか」と一言伝えるだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。
録音前のひと言が、トラブルを防ぎ円滑な面接につながります。
「無断録音により不採用」なんてことがないよう録音の際の確認は必須です。許可を取る際は、面接が始まる直前や雑談の流れで切り出すと、受け入れてもらいやすいですよ。
また、許可をもらった場合でも通知音などが鳴らないよう、スマホやICレコーダーはあらかじめマナーモードや機内モードに設定しておくと安心です。
マナーモードの設定以外にも、面接前にやるべき準備はたくさんあります。まだ不安という方は、以下の記事で面接の流れやマナー、面接前後にやるべきことを徹底解説しているので、ぜひ改めて確認してみてください。
② 録音は私的利用にとどめる
録音データはあくまで自分自身の学習や振り返りの目的で利用することが原則です。
特に企業側が話した内容には、社外秘の情報が含まれている場合もあります。無断で情報が拡散された場合、法的責任を問われるリスクも否定できません。
録音の使用範囲は自分の就活対策のみにとどめ、第三者への共有は控えましょう。
私たちも面接練習で録音を活用しますが、あくまで「聞き返して改善点を洗い出す」ためです。内容を外部と共有してしまうと相手の信頼を失いかねません。
企業は予想以上に情報管理に敏感です。面接官の言葉には今後の事業方針や採用戦略が含まれることがあります。それを外部に漏らす行為はリスクを伴うので、注意しましょう。
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
③ 録音機器は面接の妨げにならないようにセットする
録音機器の使い方や設置方法にも十分な配慮が必要です。
たとえば、面接の直前に録音アプリを操作したり、スマートフォンを目立つ場所に置いたりすると、相手に不快感を与える可能性があります。
録音が主目的ではなく、面接が円滑に進むことが第一です。録音する場合は、事前に機器のテストを行い、通知音をオフに設定しておくと安心でしょう。
また、面接の流れを止めないように、できるだけスムーズに準備を済ませておくことも忘れないでください。
④ 録音をしていることを隠さないようにする
録音の事実を面接官に伝えずに進行すると、思わぬ不信感を与える場合があります。たとえ法的に問題がなくても、「盗み録り」だと感じられてしまえば、その後の面接の空気が悪くなるおそれがあるのです。
録音の必要性を感じたら、面接の冒頭で「復習用に録音してもよろしいでしょうか」と、正直に伝えるようにしましょう。許可がもらえない場合は、その判断を尊重してください。
隠すよりも、オープンに丁寧に説明することのほうが、誠実な姿勢として相手に伝わるはずです。
⑤ 録音内容の取り扱いには注意をする
録音には面接のやりとりや企業の情報など、重要な内容が含まれています。そのため、録音データの取り扱いは慎重に行いましょう。
スマートフォンやパソコンに保存する際は、必ずロックやパスワードを設定し、不正アクセスを防いでください。クラウドに保存する場合も、アクセス権限の管理に気を付けましょう。
さらに、録音が不要になった場合には速やかに削除し、データの放置を避けるのが安心です。個人情報や企業情報を扱う意識を持って、データを安全に保管しましょう。
録音データは個人情報保護の観点だけでなく、企業側の知的財産にも直結します。特に面接中の発言には、非公開の情報が含まれることもあり、データ漏えいは違法にもなりかねません。
私たちも面談時に録音を扱う際は非常に慎重に管理しています。また、外出先のフリーWi-Fi経由でクラウドにアップロードするのは避けたほうが無難ですよ。
面接で録音する際の注意点

録音は面接内容を振り返るうえで役立ちますが、扱いを誤ると信頼を損なう原因にもなるでしょう。ここでは、面接中に録音を行う際の注意点を5つ紹介します。
- 録音に気を取られない
- 録音機器のトラブルへの備えを怠らない
- 録音データを流出させない
- SNSや共有サービスでの無断公開はしない
- 録音データの保存やセキュリティ対策を怠らない
① 録音に気を取られない
面接中に録音機器ばかり気にしていると、面接の内容に集中できません。まず大切なのは、面接官とのやり取りにしっかり向き合うことです。
事前にアプリの操作や設定を確認し、面接中に触れなくても済む状態にしておくと安心です。録音を始めてそのまま放置できるように準備しておきましょう。
録音に気を取られて会話がぎこちなくなってしまっては本末転倒です。あくまで面接の主役は「会話」であることを忘れないようにしてください。
録音機器に気を取られると、視線や反応がぎこちなくなりやすいです。面接官は表情や姿勢もよく見ています。録音よりも自然な対話を優先することが評価につながると意識してくださいね。
また、録音中、機器の不具合に気が付いても機器をいじらず、その場での録音は諦めて面接に集中しましょう。操作確認を済ませ、不具合がないよう備えておくことも大切です。
録音に気を取られてしまっては本末転倒です。あくまで面接では、面接官との会話を通じたコミュニケーションが重要になります。以下の記事では、面接で会話を意識して話す方法を紹介しているので、面接官と円滑にコミュニケーションを取りたい方はぜひ参考にしてくださいね。
② 録音機器のトラブルへの備えを怠らない
録音がうまくできていなかったというケースは意外と多いです。しかし、録音トラブルは少しの準備で防げるので、必ず事前確認をしておきましょう。
具体的には、充電状況や保存先、マイク設定をしっかり確認してください。また、無料アプリの場合は広告や強制停止などが起きにくいものを選ぶと安心です。
予備の手段として、スマートフォンとICレコーダーを併用するのもひとつの方法。念には念を入れ、面接当日に焦らないよう備えておくとよいでしょう。
③ 録音データを流出させない
録音はあくまで自分の確認用にとどめ、流出させるのは避けてください。
録音データを家族に聞かせたり、友人に送ったりといった軽い気持ちの行動は、予期せぬトラブルを引き起こす原因になります。
面接内容は機密性の高い情報を含むこともあり、外部に漏れれば企業との信頼関係にヒビが入る可能性があるので注意しましょう。
④ SNSや共有サービスでの無断公開はしない
録音した内容をSNSやファイル共有サービスで公開する行為は絶対に避けてください。たとえ面白いやり取りであっても、相手の同意なしに投稿するのは大きなマナー違反です。
企業名や担当者が特定できるような内容であれば、法的な問題につながるおそれもあります。内定取り消しや企業側からの正式な抗議を受ける事態も想定されるでしょう。
⑤ 録音データの保存やセキュリティ対策を怠らない
録音データをスマートフォンやパソコンに保存する場合でも、パスワードや指紋認証などのセキュリティ設定を必ず行ってください。
万が一、端末を紛失しても第三者が簡単に再生できないよう対策が必要です。
クラウドサービスにアップロードする場合は、共有設定をオフにするなど、情報が外部に漏れないよう細心の注意を払いましょう。アクセス権限の管理も見落とさないようにしてください。
データは必要な期間だけ保存し、不要になったものは早めに削除することが安心につながります。
面接以外でも録音ができるシーン
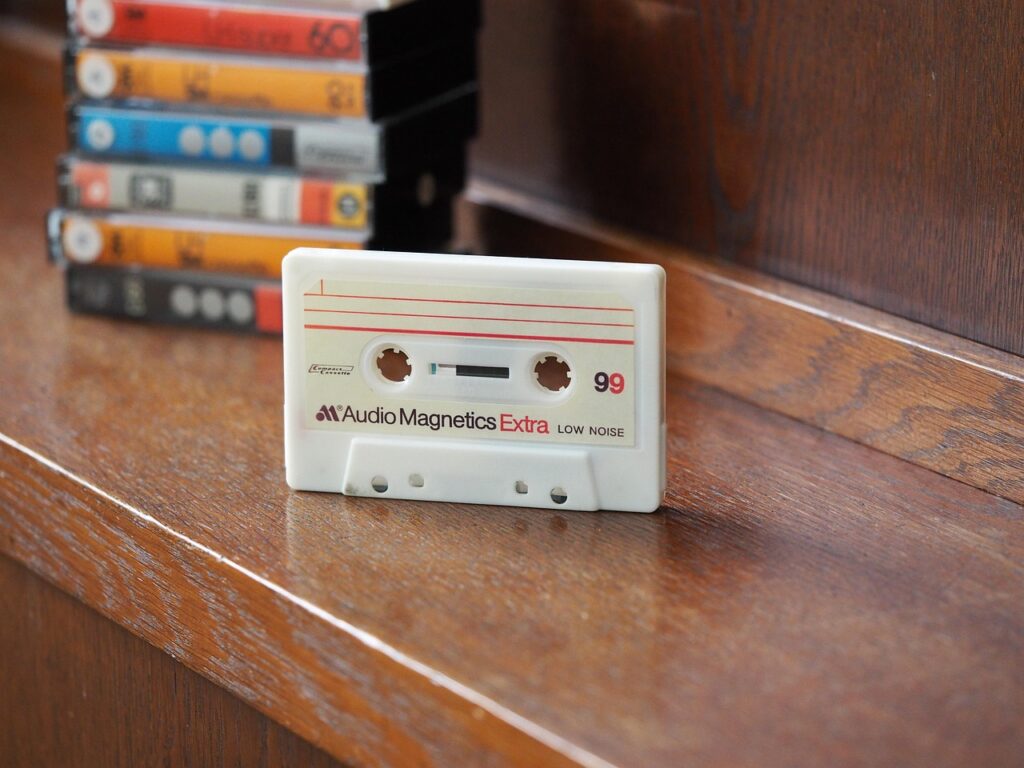
面接以外にも、就職活動中には録音を活用できる場面があります。ここでは、特に役立つ5つのシーンを紹介します。
ただ、どの場面においても録音の可否を事前に確認するようにしましょう。
- OB・OG訪問
- 企業説明会
- インターン中のフィードバック
- リクルーター面談
- 座談会や懇談会
① OB・OG訪問
実は、OG・OB訪問においても録音を活用することができます。
録音しておくと、会話中にメモを取る必要がなくなり、対話に集中できます。あとから内容を振り返ることで、理解も深まるはずです。
実際に働いている人からの話を聞くことで、働き方や職場の雰囲気、選考の進め方など、ネットでは手に入らない情報も多く得られるでしょう。
OB・OG訪問での会話を録音することで、自分が質問した意図や相手の回答のニュアンスをより正確に振り返れます。メモでは拾えない細かな言葉遣いや表現から、社風を感じ取れるのも大きなメリットです。
私たちも学生から、「その場では理解できなかったけど、録音を聞き直して気づいた」という声を聞くことがあります。聞き逃しを防ぐ意味でも有効ですし、訪問後の志望動機や面接対策に役立つ材料にもなりますよ。
② 企業説明会
多くの情報が得られる企業説明会においても録音は有効です。
企業説明会では、会社概要や選考スケジュール、求める人物像など、就活に関する情報がまとめて提供されます。録音しておけば、気になる点や細かな説明を後で確認できるでしょう。
特に複数の企業説明会に参加する場合は、情報が混ざってしまいやすいため、録音して整理するのは効果的です。
企業説明会での言葉を録音すると、話のトーンや人事担当者の強調ポイントまで後から確認できるため、履歴書やエントリーシートに活かせる表現のヒントも見つかります。
また、話の順序や具体例まで押さえると、面接時に自然に話せる材料になりますよ。企業説明会後に他の学生と情報を交換すると、さらに新しい理解を得られることもあります。
③ インターン中のフィードバック
フィードバックをもらえるインターンシップでも録音を活用できます。
録音をしておけば、口頭での指摘やアドバイスを漏らすことなく記録できるため、後日ゆっくり振り返ることが可能です。
具体的な行動や改善点が多いときほど、録音の価値は高まります。そしてその内容は自己成長のヒントとなり、今後の対策にも役立つでしょう。
④ リクルーター面談
リクルーター面談では、通常の面接では得られない情報を得られるため録音が有効です。
採用の裏話や選考通過のポイントなど、有益な内容が含まれる場合もあるでしょう。
録音しておけば、当日の話し方や質問の仕方も振り返ることができ、面談全体の質を高めることにつながります。
そもそもリクルーター面談とは何か分からないという方もいるでしょう。以下の記事では、リクルーター面談の目的や特徴、当日の流れから逆質問のコツまで詳しく解説しているので、ぜひ就活の参考にしてください。
⑤ 座談会や懇談会
座談会や懇談会では、複数人の発言を後からゆっくり確認できるため録音が便利です。
リラックスした雰囲気のなかで社員と自由に話ができる場が設けられています。
実際の職場の空気感や社員の人柄など、公式な説明では見えにくい要素を感じ取れる場でもあるのです。
企業側が面接を録音する理由

企業が面接を録音する背景には、公平な選考や採用の質を高める目的があります。ここでは、企業が録音を行う主な理由について、5つ解説します。
- 面接官ごとの評価基準を統一するため
- 採用会議での振り返り材料として活用するため
- トラブル防止の証拠として記録を残すため
- 新人面接官の教育に使用するため
- 面接内容の質を改善するため
① 面接官ごとの評価基準を統一するため
録音を行う理由の1つに、面接官ごとの評価のばらつきを防ぐ目的があります。
録音があれば、面接官全員が同じ内容を確認でき、評価の基準をそろえやすくなります。特に、複数の担当者が関わる選考や、応募人数が多いときには有効です。
評価のブレを減らすために、録音は重要な役割を果たしているのです。
このように就活では、ある程度評価されるポイントが決まっているため、事前に確認しておくことは非常に効果的です。以下の記事では、面接成功のためのコツや面接官が見ているポイントを紹介しているので、面接を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
② 採用会議での振り返り材料として活用するため
録音は、採用会議で候補者の内容を振り返る資料として活用されています。面接のメモだけでは伝わりづらいニュアンスや話し方も、音声であれば正確に確認できるからです。
選考では複数の候補者を比較する場面も多いため、印象だけでなく実際の発言に基づいた判断が必要。
録音を再生しながら意見を交わすことで、会議の内容にも具体性が増し、より納得のいく結論を導きやすくなります。正確な記録があれば、評価の根拠も明確になり、選考の質も向上するでしょう。
③ トラブル防止の証拠として記録を残すため
録音は、トラブル発生時の証拠としても機能します。たとえば、不適切な発言があったと指摘された場合、録音があれば事実関係を明らかにしやすくなるのです。
応募者と企業側の言い分が食い違ったときでも、録音があれば客観的に判断できるため公平な対応が可能になります。
企業にとっても、リスク管理のひとつとして録音を残すことは大切です。トラブルへの備えとして、記録の重要性は年々高まっています。
④ 新人面接官の教育に使用するため
録音データは、面接官の育成にも活用されています。特に経験の浅い担当者にとって、実際の面接のやり取りを聞くことは貴重な学習材料です。
先輩社員の面接を聞くことで、質問の仕方や話の進め方、評価のポイントなどを具体的に学ぶことができます。
こうした活用により、面接官のスキルが向上し、組織全体としての採用力の底上げにもつながっていきます。
⑤ 面接内容の質を改善するため
録音は、面接そのものの改善にも役立っています。たとえば、面接官の話し方が一方的になっていないか、質問の内容が偏っていないかといった点を確認できるのです。
録音を見直すことで、「もっと深掘りすべきだった」「わかりにくい質問だった」などの反省点が明確になります。これにより、次回以降の面接の質を高めることが可能です。
継続的に録音を活用することで、採用の場はより良いものに変わっていくでしょう。
録音を正しく活用して面接力を高めよう

面接で録音することは、マナーを守り正しく使えば、自己分析や対策の精度を高める有効な手段です。
録音が違法になるかどうかは利用目的や公開範囲によって分かれますが、どのような場合にも事前に録音の許可をとるようにしてください。
適切な方法とマナーを守って録音を活用することで、面接への自信と成果につなげましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













