面接で話す内容を暗記してはダメ?面接官の評価や暗記する際のポイントも紹介
「せっかく自己PRを暗記したのに、本番では頭が真っ白に…」
そんな経験をした就活生は少なくありません。緊張感のある面接では、覚えた文章をそのまま話すのは意外と難しく、むしろ逆効果になることもあります。
本記事では、面接で回答を暗記してはいけない理由や覚えられないときの原因、そして自然に伝えるための準備法を詳しく解説します。
暗記に頼らず、自分らしい言葉で面接官に想いを届けるための具体的な方法や緊張対策も紹介しているので、面接への不安を感じている方はぜひ参考にしてください。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者
記事の監修者
人事担当役員 小林
1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る面接で回答を暗記していく人は多い

就活の面接では、あらかじめ用意した回答を暗記して臨む学生が多く見られます。とくに緊張しやすい人や、話すのが得意ではない人にとっては、暗記しておけば安心できると感じるのかもしれません。
しかし実際には、この「暗記しておけば大丈夫」という考え方が、思わぬ落とし穴となることもあります。
面接で丸暗記した回答をそのまま話そうとすると、内容に感情が乗らず、棒読みのように聞こえてしまう場合も。その結果、相手に自分の熱意や人柄がうまく伝わらないかもしれません。
また、会話の流れの中で想定外の質問をされた際、準備した回答しか話せないと、柔軟性がないと見なされることもあります。
面接は、ただ正確に話すだけでなく、自分の言葉で考えを伝えることが求められる場です。そのため、内容を覚えること自体は悪いことではありませんが、それに頼りすぎるのは危険。
暗記ではなく「理解と再構成」を意識しながら準備することで、より自然で魅力的なコミュニケーションにつながるはずです。
回答を丸暗記してしまうと、表情が固くなったり声に抑揚がつきづらくなります。私たちも、面接練習で丸暗記された回答を聞くと「熱意が伝わらない」と感じることがありますね。
暗記するなら、キーワードや要点を覚える程度にしておくのがおすすめですよ。あらかじめ「どういう順番で、どのポイントを伝えるか」を考えておけば、想定外の質問にも答えやすくなります。
また、以下の記事でも、面接での受け答えの仕方について詳しく紹介していますよ。準備した回答を暗記しようとする前に、確認してみてくださいね。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
面接で回答を暗記するのがダメな理由

就職活動の面接対策で「回答は暗記すべきか」と迷う方は多いでしょう。しかし、面接官に良い印象を与えるためには、暗記に頼りすぎない姿勢が大切です。
ここでは、回答を丸暗記すると面接でマイナスに働いてしまう理由について、具体的に解説していきます。
- 棒読みになり印象が残らないから
- 感情が乗らず内容が伝わりにくいから
- 面接官との会話にならず双方向のやり取りができないから
- コミュニケーション力を評価されにくくなるから
- 予想外の質問に対応できないから
- 緊張で一部を忘れるとパニックになりやすいから
- 一カ所忘れるとすべてとんでしまう可能性があるから
- 覚えるのに時間がかかり過ぎるから
- ありのままの自分を伝えられないから
① 棒読みになり印象が残らないから
暗記した文章をそのまま話すと、どうしても抑揚がなくなり、棒読みになってしまいます。内容がどれだけ良くても、聞き手の心に響かなければ意味がありません。
一方で、自分の言葉で自然に話すと、少し言い間違えても熱意や人柄が伝わりやすくなります。印象を残すには、完璧な文章よりも話し方や雰囲気のほうが重要です。
対策としては、全文を覚えるのではなく、要点だけを押さえて、自分の言葉で伝える練習を重ねておくとよいでしょう。
② 感情が乗らず内容が伝わりにくいから
丸暗記の回答では、自分の気持ちや熱意をうまく表現できません。話しながら「何を感じたのか」「なぜその経験が印象に残っているのか」といった感情を込めて話すことが大切です。
面接官は、あなたの人柄や価値観を知りたいと思って質問しています。機械のような返答では、その思いに応えられません。
準備の段階では、エピソードを思い出しながら気持ちを整理し、自分の言葉で伝える練習をしておくと安心です。
③ 面接官との会話にならず双方向のやり取りができないから
面接は一方的に話す場ではなく、会話のキャッチボールです。暗記した内容をそのまま話すだけでは、やり取りが生まれません。
特に、質問の意図を無視して用意してきた答えを述べると、かえって印象が悪くなることも。相手の話を聞いたうえで、自分の考えをその場で伝える姿勢が求められます。
自然なやり取りを実現するためにも、理解に基づいて話せるようにしておくことがポイントです。
私たちも、丸暗記された回答を聞くと、「質問と答えがかみ合っていない」と感じてしまいます。そして、深堀りしたくても質問をしずらいですね。
面接はお互いを理解する場なので、暗記よりも、自然なやり取りの方が魅力を感じます。普段から話す練習をして、状況に応じて言い換えられる準備をしておくと安心ですね。
④ コミュニケーション力を評価されにくくなるから
企業は「この人と一緒に働きたいか」を重視して面接を行っています。そのため、コミュニケーションの取り方や臨機応変な対応を見ているのです。
暗記ばかりに頼っていると、自然な会話が難しくなり、評価されづらくなってしまいます。どんなに内容が整っていても、印象に残らなければ意味がありません。
普段の会話のように相手と向き合いながら話すことで、評価されるチャンスが広がります。
⑤ 予想外の質問に対応できないから
面接では、想定していない質問が出ることもよくあります。暗記だけに頼っていると、そうした場面で混乱してしまうかもしれません。
一方で、自分の考えをしっかり持ち、エピソードの背景を理解していれば、多少質問が変わっても落ち着いて答えられます。
柔軟に対応するためにも、暗記ではなく「理解して話す」ことを意識した準備が効果的です。
⑥ 緊張で一部を忘れるとパニックになりやすいから
本番では誰でも緊張します。暗記した内容の一部を思い出せなくなると、その瞬間に焦ってしまい、頭が真っ白になることもあるでしょう。
その結果、話の流れが崩れてしまい、自信を失ってしまうケースも少なくありません。こうした事態を防ぐには、文章ではなく話の流れやキーワードを覚えておくことが有効です。
安心して話すには、「覚える」のではなく「話せるようにしておく」意識が大切です。
暗記に頼りすぎると、思い出せない箇所が出た瞬間にフリーズしてしまいます。受け答えで不自然に言葉に詰まると準備不足な印象を与えてしまうので、できるだけ暗記に頼らず話せるようにしましょう。
私たちは、完璧に話せたかではなく、伝えたい内容や意図を重視しています。意識を「覚える」から「伝える」に切り替えて、自分の言葉で回答を組み立てることが大切ですよ。
⑦ 一カ所忘れるとすべてとんでしまう可能性があるから
暗記した文章は、一部を忘れると次が思い出せなくなり、全体が崩れてしまう危険があります。それによって、面接中に動揺してしまう可能性もあるでしょう。
ストーリーの骨組みだけをしっかり理解しておけば、多少の言い間違いがあっても柔軟に話を続けられます。暗記ではなく、理解を軸にした準備が本番での安定感につながりますよ。
話す内容の流れをイメージしながら準備を進めてください。
⑧ 覚えるのに時間がかかり過ぎるから
面接対策で回答を丸ごと暗記しようとすると、非常に多くの時間がかかってしまいます。
たとえば、1問あたりの回答を覚えるのに30分〜1時間かかる場合、それを10問用意するだけでも数時間以上の負担になるでしょう。
そのうえ、一度覚えた文章をキープするには繰り返しの復習も必要になり、効率が悪くなりがちです。その時間を、企業研究や自己分析、模擬面接などに使ったほうが、実践的な対策になります。
暗記に時間を費やしすぎると、逆に中身の理解や自己表現の力を高める機会を逃すかもしれません。短時間でも効果的な準備をするためには、ポイントを押さえて覚える工夫が必要です。
構成やキーワードさえ整理しておけば、本番でも自然に言葉が出てくるようになります。準備の質を高めるには、「全部覚える」より「要点で話せる」状態を目指すことが大切です。
私たちが面接で見ているのは、内容の深さや自分の言葉で話せているかどうかです。丸暗記に頼ると、こうした力を磨けず「結果的に面接がうまくいかない」ということもありますよ。
また、暗記した文章は一度忘れると別の言葉に言い換えるのが難しくなってしまいます。要点のみを覚えて、あとは自然と言葉を補いつつ回答する練習に時間を使うのがオススメです。
⑨ ありのままの自分を伝えられないから
面接の目的は、正解を伝えることではなく「あなた自身を理解してもらうこと」です。しかし、あらかじめ用意したセリフを完璧に話そうとすると、かえって自分らしさが表現できなくなってしまいます。
声のトーンや表情、話すテンポなども不自然になりがちで、結果的に面接官には本来の魅力が伝わりません。企業が知りたいのは、あなたの経験やスキルだけでなく、考え方や人柄、価値観です。
多少言い間違えても、言葉に迷っても、自分の言葉で話す姿勢のほうが信頼感につながります。むしろ、自然体で話しているほうが、熱意や真剣さが伝わりやすいのです。
緊張しても、完璧じゃなくても大丈夫です。あなたらしい言葉で、自分の思いを丁寧に伝えてください。それが、最終的に相手の心を動かす一番の方法になるでしょう。
「回答を丸暗記することのデメリットは分かったけど、暗記しておかないと、面接でうまく話せない…」という人は会話を意識して話してみましょう。こちらの記事で、円滑に受け答えをするための事前準備や練習法を紹介していますよ。
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
面接質問事例集100選|聞かれる質問を網羅して選考突破を目指そう

「面接がもうすぐあるけど、どんな質問が飛んでくるかわからない……」
「対策はしてるつもりだけど、いつも予想外の質問が飛んでくる……」
面接前の就活生が抱える悩みとして「どんな質問をされるのか分からない」という問題は大きいですよね。頻出質問以外が予想しきれず、面接で答えに詰まってしまった人もいるでしょう。
また、面接経験がほとんどない人は、質問を予想することも難しいはず。そこでオススメしたいのが、就活マガジンが独自に収集した「面接質問事例集100選」です!
400社以上の企業の面接内容を厳選し、特に聞かれやすい100の質問を分かりやすく紹介。自分の回答を記入する欄もあるため、事前に用意した回答を面接直前に見返すことも可能ですよ。
面接で特に失敗しやすいのが「予想外の質問に答えられなかったパターン」です。よくある質問内容を知っておくだけでも、心の準備ができますよ。
また、志望動機などの頻出質問も、企業によってはひねった聞き方をしてくることも。質問集では特殊な例も網羅しているため、気になる人はぜひダウンロードしてくださいね。
\400社の質問を厳選/
面接で回答を暗記できない理由

面接に向けて準備しているのに、なかなか回答を覚えられないと感じる人は少なくありません。覚えられない原因は人によって異なりますが、いくつかの共通したパターンがあります。
ここでは、覚えにくい理由とその背景にある問題点を紹介します。
- 文章を丸ごと覚えようとしているから
- 考えがまとまっていないまま暗記しているから
- 本心と違う内容を覚えているから
- 読み上げ練習ばかりでアウトプットが足りないから
- 本番のイメージトレーニングが不十分だから
① 文章を丸ごと覚えようとしているから
面接での回答を一字一句すべて覚えようとするのは、かえって逆効果になりやすいです。少しでも言葉を忘れると、次に何を言えばいいか分からなくなり、パニックになるリスクも高まります。
また、文章に引っ張られてしまうことで話し方が不自然になり、棒読みのような印象を与えることも。効果的な暗記には、文章ではなく「構成」と「要点」を覚える意識が必要です。
PREP法のように整理された話の流れを使えば、記憶しやすいだけでなく、面接官にも伝わりやすくなります。丸暗記に頼るのではなく、理解をもとにした記憶を心がけてください。
② 考えがまとまっていないまま暗記しているから
内容が頭に入らない最大の原因は、自分の考えがきちんと整理されていないことです。伝えたいことがぼんやりしたままでは、何を覚えようとしているのかも定まりません。
文章だけを丸暗記しても、意味を理解していなければ記憶の定着は難しいでしょう。
まずは、「なぜその内容を伝えたいのか」「どこを一番強調したいのか」を明確にしてから、構成を組み立てることが大切です。
しっかり考えを整理しておくことで、話す内容が自分の中にしっかり根づき、暗記というより自然な発話につながります。
③ 本心と違う内容を覚えているから
納得できない内容は、どれだけ練習してもなかなか覚えられません。
無理に「正解っぽいこと」を言おうとして、本心とは異なる内容を話そうとすると、言葉に実感がこもらず、感情も表情にも現れにくくなります。
これでは、面接官に響く自己PRにはなりません。自分が本当に伝えたいこと、経験してきたこと、心から誇れることを軸に自己PRを作ることが重要です。
心から納得して話せる内容なら、記憶にも残りやすく、自然な言葉で話せるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
④ 読み上げ練習ばかりでアウトプットが足りないから
回答を覚えたいとき、多くの人は文章を何度も読むという方法をとります。しかし、読むだけではインプット中心の練習になり、いざというときにスムーズに言葉が出てこない原因になります。
大切なのは、アウトプットを増やすことです。たとえば、自分の言葉で何度も話してみたり、友人や家族に聞いてもらいながら練習したりすることで、実際に話す力が身についていきます。
また、自分の表現を客観的に見つめ直す機会にもなります。読み上げだけでは不十分だと感じたら、声に出して何度もアウトプットしてみてください。
⑤ 本番のイメージトレーニングが不十分だから
本番を意識した練習をしていないと、実際の面接で緊張して頭が真っ白になりますよね。これは、暗記の内容が「使える状態」になっていないためです。
どんなに文章を覚えても、面接の雰囲気や流れに慣れていないと、うまく力を発揮できません。対策としては、模擬面接や想定問答の練習を繰り返すことが有効です。
立って話す、時間を計る、相手の目を見るなど、本番に近い環境を意識して取り組むことで、自信を持って言葉を引き出せるようになります。
暗記した内容を「実践できるレベル」に引き上げる準備を整えておきましょう。
また、本番を意識して練習することで、本番での緊張を和らげることができます。その他のメリットや面接練習の方法については以下の記事で紹介しているので、確認してみてくださいね。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
回答を暗記している人に対する面接官の評価

面接では「何を話すか」だけでなく、「どう伝えるか」も評価されます。回答を暗記している人は、内容以前に伝え方でマイナス印象を与えるかもしれません。
ここでは、面接官が暗記に頼る応募者に対してどのような評価をしているのかを整理して紹介します。
- 臨機応変な対応力が低く見える
- 会話力やコミュニケーション力が乏しく見える
- 熱意が伝わらず志望度が低く見える
- 自分の言葉で語っていないように見える
- 人柄や熱意がないように見える
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
① 臨機応変な対応力が低く見える
面接では予想外の質問が飛んでくることもあります。そのとき、丸暗記した答えしか用意していないと、柔軟に対応できない人だと思われやすいです。
質問にしっかり耳を傾け、その場で自分の考えを伝えることができれば、臨機応変な姿勢が伝わります。準備の段階でエピソードの理解を深め、自分の言葉で話せるようにしておくことが大切です。
対応力を示すには、暗記ではなく、理解をベースにした準備が効果的でしょう。
私たちも、想定問答をなぞるような回答には「応用力や対応力がない」と感じることがあります。反対に、多少拙くても、自分の言葉で考えながら話す姿勢のほうが、誠実さが伝わりますね。
また、質問の意図を理解しないまま焦って回答する人も低評価になります。回答の方向性が分からない場合は、焦らず質問の意図を問い返す癖をつけておくのがオススメです。
② 会話力やコミュニケーション力が乏しく見える
面接は一問一答ではなく、会話のキャッチボールです。暗記した答えを一方的に話してしまうと、やり取りが成立せず、コミュニケーション能力が弱いと見なされることがあります。
実際には話せる人でも、暗記に頼ると「会話が苦手な人」と誤解されるかもしれません。相手の質問にしっかり反応し、自然なやり取りを心がけてください。
そうすれば、本来の会話力が正しく伝わるはずです。
③ 熱意が伝わらず志望度が低く見える
どれだけ立派な内容でも、暗記して淡々と話すと、気持ちがこもっていないように見えてしまいます。その結果、「志望度が低い」と判断される可能性があるでしょう。
逆に、言葉につまづいても一生懸命に話していれば、面接官には熱意が伝わります。完璧な回答よりも、自分の思いを込めた伝え方が重要です。
準備の段階で、自分の考えをしっかり整理し、素直な言葉で語れるように準備しておきましょう。
暗記に頼ると、思い出すことに集中してしまい、表情や声の抑揚が少なくなりやすいです。私たちも面接の中で、「スムーズに話しているけれど、どこか心が動かない」と感じてしまうことがあります。
多少言葉につまっても、面接官の目を見てしっかり伝えてくれる方が好印象です。事前に言葉を決めすぎず、「なぜその企業で働きたいか」を自分なりに表現できるようにしましょう。
④ 自分の言葉で語っていないように見える
暗記した文章は、口調や言い回しが不自然になることがあります。すると、面接官には「この人の言葉ではないのでは」と疑われる恐れも。
信頼を得るためには、自分らしい表現で話すことが大切です。話したいことを理解し、自分の言葉で自然に伝えられるよう準備しておくと、印象がぐっとよくなります。
本音が伝わる話し方を意識してみてください。
⑤ 人柄や熱意がないように見える
面接官は、経験やスキル以上に人柄を重視することが多いです。ところが、暗記中心の回答では個性や雰囲気が伝わりにくく、結果として印象に残らないまま終わることもあります。
自分の体験を通じて何を感じたのかを、自分の言葉で語ることが重要です。表現に少しミスがあっても、感情が乗っていればそれが魅力に映ります。
人柄や思いが伝わる語り方が、評価の決め手になるはずです。
私たちも、一貫性のある人柄やその人なりの価値観が感じ取れるかどうかに注目します。エピソードの内容が素晴らしくても、機械的な話し方だと「本心やその人らしさが見えない」と低評価に繋がりかねません。
また、経験談を話すときは、うまく言おうとするより、感じたことを素直に伝えてくれる方が印象に残ります。「一緒に働きたい」と思うかどうかは、人柄であったり雰囲気の部分が大きいですね。
「どう話せば熱意を伝えることができるのだろうか…」と悩む人もいますよね。以下の記事では、面接で熱意を伝えるコツや熱意を伝えるポイントを詳しく解説しています。ぜひ参考にしてくださいね。
面接での回答の内容を暗記する際のポイント4つ

面接の回答をすべて正確に覚えるのは難しいと感じる方も多いでしょう。ただし、暗記のやり方を工夫すれば、自然に内容を思い出せるようになるのです。
ここでは、効果的な覚え方のコツを4つ紹介します。
- 要点だけを箇条書きで覚えるようにする
- 自分の言葉で言い換えて整理する
- 友人や家族に聞いてもらいながら練習する
- よくある質問にだけ絞って対策する
① 要点だけを箇条書きで覚えるようにする
文章を丸ごと暗記しようとすると、少しの言い間違いで混乱したり、話の流れを見失ったりする可能性があります。そこで、話したい内容は「要点」に絞って記憶するのが効果的です。
「何をしたのか」「なぜ取り組んだのか」「その結果どうなったか」「今後どう活かすか」といった構成で箇条書きに整理しておけば、順を追って自然に話せるようになります。
PREP法を使えば構成の流れが明確になり、思い出す際の手がかりにもなるでしょう。重要なのは完璧なセリフではなく、自分が伝えたい本質を理解することです。
その上で話す内容の骨組みをおさえておくと、本番での安心感にもつながります。
要点を箇条書きで整理する際は、できるだけシンプルにまとめるのがコツです。また、「結果:売上120%達成」など数字や具体的な成果を一言で添えるともっとよいですね。
また、要点をまとめた後は順番を覚えておくのがおすすめですよ。緊張で頭が真っ白になったとき、順番をたどって思い出しやすくするためです。ぜひ取り入れてみてくださいね。
② 自分の言葉で言い換えて整理する
他人の例文やテンプレートをそのまま覚えても、自分の口調と合わなければ違和感が残り、記憶にも定着しにくくなります。まずは参考にした文章を、自分が普段使っている言葉に置き換えてみてください。
言い換える作業を通じて内容が自然と整理され、理解も深まっていきます。結果として、覚えたことをそのまま話すのではなく、自分の言葉として語れるようになるでしょう。
相手に伝わる印象も変わり、信頼感のある話し方になります。話す力は自分の中から出てくる言葉によって磨かれるものです。まずは違和感を取り除くことから始めましょう。
自分の言葉に置き換えると、面接で質問の意図が少し変わっても柔軟に対応できるようになります。暗記したフレーズをそのまま話すと、少しでも順番が崩れたときに焦りやすいので注意しましょう。
また、置き換えることで「なぜその時そう思ったのか」などエピソードを振り返る機会にもなります。自然と深掘り質問への対策になり、自信をもって回答できるのでおすすめですよ。
③ 友人や家族に聞いてもらいながら練習する
ひとりで練習していると、表情や話し方の癖に気づくことが難しいものです。そんなときは、友人や家族に聞き役になってもらうのが効果的。
人前で話すことで本番に近い緊張感も体験でき、伝え方の練習にもなります。また、相手からのフィードバックを通じて、自分では見えていなかった改善点に気づけることもあるでしょう。
話すこと自体がアウトプットとなり、記憶にも定着しやすくなります。できる限り模擬面接の形で実践し、「伝わる」ことを意識した練習を重ねてください。自信につながり、本番の安心感にもつながります。
模擬面接を第三者に頼むときは、「特に見てほしいところ」を事前に伝えておきましょう。「回答が長すぎないか」「結論が先に出ているか」など具体的に頼むと、的確なフィードバックをもらいやすくなります。
また、感想をもらうだけで終わらないよう注意が必要です。1度受けたフィードバックをもとに練習し、次の模擬面接で修正できているか確認するという流れを繰り返すことで、より本番の回答の質が上がります。
④ よくある質問にだけ絞って対策する
面接で出そうなすべての質問に完璧な答えを用意しようとすると、時間も労力も膨大になってしまいます。
そのため、まずは「志望動機」「自己PR」「学生時代に頑張ったこと」など、頻出の質問に絞って対策するのが現実的で効果的です。特に頻度が高い質問ほど深く準備しておくことで、応用もしやすくなります。
想定外の質問が出たとしても、ベースとなる回答があれば落ち着いて対応できるでしょう。準備の段階で的を絞ることで、内容にも説得力が生まれます。
焦って全方位を対策するより、ポイントを押さえた深い準備が成功の鍵です。
企業側も限られた時間で「その人らしさ」を見極めるため、質問にはある程度パターンがあります。そのため、むやみに全回答を暗記するよりも、頻出質問に絞った準備が選考を突破するうえでの近道なんです。
また、頻出質問に絞った対策は、想定外の質問に対応する土台にもなります。まずは、「なぜその経験を話すのか」「その経験から何を伝えたいのか」といった自分の軸を言語化しておくことを優先しましょう。
さらに、質問に回答する際は、聞かれた意図を理解することも大切です。以下の記事では、面接でよく聞かれる質問とその意図を説明するとともに、回答例文も紹介しています。回答を作成するときの参考にしてくださいね。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
面接で丸暗記するとどうなる?先輩の体験談を紹介!
就職活動の面接で、「完璧に答えたいから回答を丸暗記しよう」と考える就活生は少なくありません。実際には、丸暗記にはメリットとデメリットの両方が存在します。
ここでは、回答を丸暗記することで失敗した例と成功した例を紹介します。「自分は丸暗記に向いているのかな……?」と悩んでいる人は参考にしてください。
- 失敗談|予想外の深掘り質問に困惑した体験
- 成功談|緊張しても落ち着いて回答できるようになった体験
① 失敗談|予想外の深掘り質問に困惑した体験
面接では、想定質問に対する回答を暗記して臨む方は少なくありません。ただ、回答を丸暗記することにはいくつかデメリットがあります。
ここでは、予想外の質問に答えられなかった体験談を紹介します。その後のSさんがどう工夫して改善したのかにも注目してみてください。
| Sさん(23歳・理系・私立)の体験談 |
|---|
| 私は最初、面接対策として回答をすべて丸暗記していたんです。 「自己PRをしてください」と聞かれたときには、「私は大学時代にゼミでリーダーを務めました。その経験から貴社でもリーダーシップを発揮できます」と、用意した文章をそのまま口にしていました。 ところが、面接官から「具体的にはどうメンバーをまとめたのですか?」と深掘りされ、頭が真っ白になってしまったんです。焦って暗記したフレーズを繰り返してしまい、会話がかみ合わなくなってしまいました。当然ですが、面接官の反応もあまり良くなかったんですよね。 そのときに、暗記は自分に合わないんだと気づいて、要点だけを暗記する方法に切り替えました。 例えば「役割分担」「進捗管理」というキーワードだけを押さえておき、「どんな工夫をしたのですか?」と聞かれたら「当時は役割分担が曖昧だったので、進捗管理シートを作って全員に共有しました」と、その場で文章を作って答えられるようにしたんです。 それ以降は面接官との会話がスムーズになり、評価にもつながるようになったなと思っています。 |
回答を丸暗記することのデメリットは、思い出すことに集中してしまい、想定外の質問に対応しにくくなることです。面接官は応募者の本音や考え方を知るために、あえて「定番ではない質問」を投げかけることも少なくありません。
臨機応変に対応するためにも、なるべく回答の要点を中心に押さえておくようにしましょう。重要なキーワードに絞って覚えておくことで、質問の切り口が変わっても一貫性のある回答ができ、評価につながりやすくなります。
深掘り質問は、「行動の背景」を聞く意図があります。普段から自分の行動を「なぜそうしたのか」とセットで話せるようにしておくと、本番で深掘りされても焦りにくいですよ。
また、キャリアセンターなどの模擬面接を活用するのもおすすめです。あえて想定外の質問をしてもらい、回答する経験を積んでおくことで、本番でもスムーズに答えられるようになります。
他にも、模擬面接をすることで第三者からのフィードバックが得られ、自分を客観視することができます。以下の記事で、模擬面接のやり方や流れ、事前準備について詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
② 成功談|緊張しても落ち着いて回答できるようになった体験
面接で緊張しやすい人にとって、「頭が真っ白になってしまう……」なんてことは珍しくありません。答えが出てこず沈黙してしまうと、ますます面接への不安が大きくなりますよね。
そこで今回は、丸暗記によって緊張しても答えられるようになった体験談を紹介します。Mさんのように、緊張でうまく答えられなくて困っている人は是非参考にしてください。
| Mさん(23歳・文系・私立)の体験談 |
|---|
| 私はとにかく面接で緊張するタイプで、質問された瞬間に頭が真っ白になることがよくありました。 どうしたらいいか分からず、就活アドバイザーに相談したところ「まずは丸暗記でもいいから質問に答えられるようにしよう」と言われたんです。それで、自分が想定できる質問に対する回答をすべて台本にして、夜遅くまで繰り返し練習しました。 例えば「学生時代に力を入れたことは?」という質問には、「私は大学2年生のときにゼミの研究発表でリーダーを務め、チームをまとめ上げることに注力しました」と一字一句覚えた文章をそのまま答えていました。 最初は不自然さもありましたが、緊張で固まりそうになった瞬間も、暗記した言葉がすっと出てきて沈黙せずに済んだんですよね。むしろ途中からは余裕が出てきて、表情もこわばらずに笑顔で話せました。 その後何度も面接をするうちに、暗記した言葉に頼らなくても自分の言葉で話せるようになったんです。今振り返ると、丸暗記は万能ではありませんが、当時の私にとっては不安を解消する足がかりになったと感じています。 |
面接官の質問に対して黙り込んでしまうと、企業側としても評価をつけられなくなってしまいます。そのため、まずは丸暗記でも「質問に答えられるようにする」ことが大切です。
Mさんのように、「面接で答えられた経験」を積むと、自信がつき、暗記しなくても自分の言葉で話せるようになるケースもあります。
面接で「緊張してどうしてもうまく話せない……」と悩んでいる人は、回答を丸暗記するのも一つの選択肢だと覚えておいてくださいね。
回答を丸暗記すると、どうしても棒読みに聞こえてしまうことがあります。そのため、「早く話しすぎない」ことや「声に抑揚をつける」を工夫しましょう。
また、丸暗記でうまく答えられるようになったら、「キーワードのみに絞って覚える」のがオススメです。そうすると、面接官からの想定外の質問にも慌てず答えられるようになりますよ。
暗記しやすい自己PRの作り方

自己PRの準備では、すべての内容を完璧に覚えようとすると難しく感じるかもしれません。しかし、構成や表現を工夫すれば、自然に言葉が出てくるようになるのです。
ここでは、覚えやすく、かつ伝わりやすい自己PRを作るためのポイントを紹介します。
- 自己PRの長さは1分以内におさめる
- PREP法を意識した構成にする
- 具体的なエピソードを交える
- 自己PRの要点は3つまでにまとめる
- キーワードを繰り返し使う
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
① 自己PRの長さは1分以内におさめる
自己PRが長すぎると、内容がぼやけて印象に残りにくくなります。また、話す側も聞く側も集中力を保つのが難しくなるでしょう。目安として、自己PRは1分以内に収めるのがおすすめです。
文字数でいえば、300〜350字ほどが適切です。短くまとめることで、要点が明確になり、暗記もしやすくなります。
自己PRを短く整理すると、本当に伝えたい強みが明確になり、より印象に残る内容になります。特に、「私の強みは○○です。」と冒頭の一言で強みを言い切る構成にすると、聞き手の記憶に残りやすいですよ。
また、端的にまとまっていることは、聞き手に「伝える力」があると印象づける上でも効果的です。限られた時間で的確に話す力は、実は選考全体を通じて見られているポイントでもあります。
② PREP法を意識した構成にする
PREP法とは、「結論→理由→具体例→まとめ」の順に話を組み立てる方法です。この構成を意識することで、内容に一貫性が生まれ、話しやすくなります。
暗記するときも、構成ごとに区切って覚えられるため、話が飛ぶことを防ぎやすくなるでしょう。聞き手にとっても理解しやすく、印象に残りやすくなります。
③ 具体的なエピソードを交える
抽象的な表現だけでは、自己PRに説得力が出ません。たとえば「努力家です」と言うだけでは伝わりづらいでしょう。
そこで、具体的な経験や成果をエピソードとして盛り込むことで、内容にリアリティが生まれます。
自分の体験をもとに構成することで、覚えやすくなるうえ、面接でもスムーズに話せるようになりますよ。
面接官は多くの学生の自己PRを聞くからこそ、インパクトを与えるためにも自分の体験をもとにしたエピソードは必須です。特に「その経験が業務とどうつながるか」まで語れると、一歩リードできますよ。
エピソードを考える際は、「行動→工夫→成果」の順で紙に書き出すと整理しやすいです。また、企業ごとに求める人物像と照らし合わせ、強調するべきポイントを調整しておきましょう。
④ 自己PRの要点は3つまでにまとめる
あれもこれもと盛り込みすぎると、内容がぼやけて伝わりにくくなります。自己PRで伝える要点は、最大でも3つに絞るのが効果的です。
ポイントを絞ることで、話の筋が通り、記憶にも定着しやすくなります。詰め込むよりも、「何を伝えたいか」に集中してください。
要点を絞るべき理由の1つに、「面接官がメモを取りやすいから」があります。面接官は話を聞きながらメモを取りますが、情報が多すぎると何を評価すべきか迷ってしまうためです。
まず「自分が一番伝えたいことは何か」を決めた上で、要点を3つ以内に整理しましょう。その際、各要点の方向性にブレがないかも見直すと、より一貫性のある自己PRになりますよ。
⑤ キーワードを繰り返し使う
自己PRを印象づけるためには、キーワードを繰り返すのが効果的です。
たとえば「責任感」や「挑戦」といった強みを繰り返すことで、メッセージ性が高まり、聞き手の記憶にも残りやすくなります。
自分がアピールしたい特徴を中心に言葉を選び、自然に繰り返すように意識してみてください。
余裕がある人は、以下の記事を確認することをおすすめします。評価を上げるポイントや面接官の評価の仕方を事前に把握して、自己PRの質を高めてみましょう。
面接本番で緊張しないためのリラックス方法

面接当日は誰でも緊張するものです。大事なのは緊張をなくすことではなく、うまく付き合って本来の力を出すこと。ここでは、簡単に実践できるリラックス方法を紹介します。
どれも面接直前に取り入れやすいものなので、自分に合う方法を試してみてください。
- ルーティンを決めて安心感を得る
- 前日はしっかり睡眠をとる
- 深呼吸やストレッチで緊張を和らげる
- 「緊張している」と素直に伝えてしまう
- 面接官も人間だと思って気負いすぎない
① ルーティンを決めて安心感を得る
緊張をやわらげるには、自分なりのルーティンを作っておくと効果的です。たとえば、お守りを持つ、同じ音楽を聴く、決まった服装で臨むといったことでも安心感につながります。
慣れた行動を面接前に取り入れることで、気持ちが落ち着きやすくなるはず。毎回同じルーティンを繰り返せば、自然と本番にも慣れていくでしょう。
自分に合ったリズムを見つけ、少しずつ整えてみてください。
② 前日はしっかり睡眠をとる
面接当日のパフォーマンスを高めるには、前日の睡眠が大切です。緊張で寝つけないこともありますが、できるだけ早めに寝る準備を始めましょう。
睡眠をしっかりとると頭がスッキリして、言葉も出やすくなります。逆に、寝不足だと集中できず不安も増すため、面接に悪影響が出てしまうかもしれません。
スマホの使用を控えるなど、眠りやすい環境を整えることも忘れずに。
③ 深呼吸やストレッチで緊張を和らげる
緊張したときには、深呼吸が効果的です。鼻からゆっくり息を吸って、口から長く吐くことを数回繰り返すだけで、気持ちが落ち着いてきます。
また、肩や首を軽く回したり、手足を動かしたりすると血の巡りがよくなり、身体のこわばりもやわらぐでしょう。どちらも面接直前に短時間でできる方法なので、ぜひ取り入れてみてください。
④ 「緊張している」と素直に伝えてしまう
緊張を無理に隠そうとすると、かえって不自然になることがあります。そんなときは、「少し緊張しています」と正直に伝えてしまって構いません。
面接官も人間ですから、素直な姿勢に共感してくれることが多いです。実際に、その一言が場の空気を和らげることもあります。うまく話そうとするより、自分らしくあることを大切にしてください。
⑤ 面接官も人間だと思って気負いすぎない
「面接官=怖い人」と思い込むと、必要以上に緊張してしまいます。しかし、相手も人間であり、就活生のことを理解しようとしているのです。
完璧な受け答えを求めるより、自然体で話してくれることを望んでいる面接官も多いでしょう。そう考えると、少し気が楽になるはずです。
相手を身近に感じながら話すことで、肩の力を抜いたやり取りができるでしょう。
面接での緊張は、事前準備の段階でも緩和させることができます。以下の記事で面接に対する緊張を緩和させる方法を様々な視点から紹介しているので、参考にしてみてくださいね。
面接に不安があるときはメモ持参してもいい?
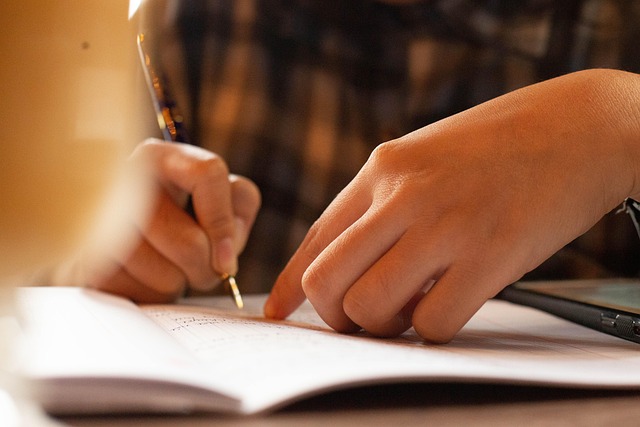
面接本番に強い不安を感じる人は、「念のためメモを持っていきたい」と考えることもあるでしょう。
結論から言えば、企業や面接形式によって違いはありますが、メモの持参自体が禁止されているケースはほとんどありません。
とくにオンライン面接では、手元にカンペを置いておく学生も一定数いるのが実情です。ただし、使い方には注意が必要です。
メモを読みながら話すと、すぐに面接官に伝わってしまい、「準備不足」や「自信がない」といったマイナスの印象を持たれる恐れがあります。
さらに、目線が合わずに会話のキャッチボールができないと、コミュニケーション力が低いと見なされる可能性もあるでしょう。
メモを使う場合は、あくまで補助的な存在として考えてください。キーワードや要点のみを簡潔にまとめておき、必要なときだけさりげなく確認しましょう。
また、なるべく目を合わせて自然な会話を意識してください。不安を和らげる手段としてメモを活用するのは有効です。
しかし最終的には、「見なくても話せる状態」まで準備を整えておくことが、もっとも安心につながります。
メモを見ることに夢中になったり、緊張したりして、評価を下げてしまうのは避けたいですよね。とはいえ、面接への苦手意識があり、不安になる方も多いでしょう。以下の記事で苦手を克服する方法などを紹介しているので、こちらもぜひ読んでみてくださいね。
面接では暗記する内容を絞って事前対策をしよう!

面接では回答を暗記する人が多いものの、丸暗記は逆効果になることが多く、印象に残らなかったり、臨機応変な対応が難しくなったりします。
実際に面接官からの評価も厳しくなりがちで、熱意や人柄が伝わりにくくなるおそれも。そのため、要点を絞って整理したり、自分の言葉で話すことを意識したりすることが大切です。
PREP法を使った自己PRの構成や、リラックス法を取り入れた準備も有効でしょう。覚えるべきなのは「正しい答え」ではなく、「自分の考えや想い」です。
暗記に頼らず、自分らしさを表現できる面接を目指してくださいね。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













