二次面接の通過率はどれくらい?落ちる理由や対策を解説
「一次面接は通過したけど、二次面接でいつも落ちてしまう…」
就活が本格化する中で、誰もがぶつかる壁のひとつが二次面接。
一次を突破した安心感も束の間、ここで足踏みをしてしまう就活生も少なくありません。
そこで本記事では、実際の通過率の目安や落ちる理由、そして通過のために押さえておくべき対策ポイントをわかりやすく解説します。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者
記事の監修者
人事担当役員 小林
1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る二次面接の難易度は高い?

一次面接を通過したものの、二次面接になると急に難易度が上がるのではないかと不安になる方も多いでしょう。
実際、二次面接では評価基準がやや厳しくなる企業が多いとされています。なぜなら、企業はこの段階で「本当に一緒に働ける人材かどうか」を見極めようとするからです。
一次面接では主に基本的なガクチカやマナーが見られますが、二次面接では志望動機の深さや企業への理解度、将来のキャリアビジョンまで問われることが増えます。
また、一次面接は集団で行われることが多いのに対し、二次面接では1対1で実施されるケースが一般的です。
そのため、一人ひとりの発言や思考がじっくりと見られ、深掘りされた質問を受けやすくなります。一次面接よりも質問の難易度も上がると言えるでしょう。
二次面接のポイントは、企業との「相性」や「志望度の高さ」を見極める場であることです。「なぜこの会社でなければならないのか」を論理的かつ具体的に語れるかは大きな評価ポイントになります。
そのため、一次面接よりもさらに「自分の将来像と企業が求める人物像のマッチ度」を意識して答えることが重要ですよ。また、「自分なら企業にどう貢献できるか」を掘り下げて準備しておくのもコツです。
また、難易度や倍率に左右されすぎないためにも、面接で成功する人の特徴を押さえておくことも大切ですよ。こちらの記事で面接に受かる人が実践している対策や先輩の体験談、選考別のポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
【新卒採用】二次面接の通過率はどれくらい?

一般的に、二次面接の通過率は企業や業界によって異なりますが、概ね30〜50%程度とされています。一次面接の通過率は50%〜70%の企業が多いため、やや厳しめの水準といえるでしょう。
一次面接よりも通過率が低くなる理由は、ここで企業が見極めたいポイントが変わるからです。
具体的には、ガクチカや基本的なマナーだけでなく、「社風との相性」や「中長期的な成長性」といった、より深い部分までチェックされます。
そのため、模範的な受け答えだけでは評価されにくく、自分の言葉で語る姿勢や、誠実な人間性が問われる場面が増えるでしょう。
こうした背景を踏まえると、面接の意図を理解したうえで準備を進めることが、結果的に合格への近道となるのです。
また、一次面接は乗り越えたものの「面接が怖い」と感じている就活生の方は以下の記事を参考にしてくださいね。怖さを和らげる方法や、それを克服する準備方法を紹介していますよ。
二次面接の通過率を予測する方法はある?

就職活動において、二次面接の通過率は気になるポイントの1つです。あらかじめ通過の可能性を見積もれれば、不安を軽減でき、効率的な準備にもつながりますよね。
ここでは、企業ごとの採用倍率や選考フロー、さらには通過率が高い・低い企業の特徴から、予測のヒントとなる情報を紹介します。
- 採用倍率から予測
- 採用フローから予測
- 二次面接の通過率が高い企業の特徴から予測
- 二次面接の通過率が低い企業の特徴から予測
① 採用倍率から予測
二次面接の通過率を見積もる手がかりとして、まず注目したいのが「採用倍率」です。
採用倍率とは、1つの採用枠に対して何人の応募があったかを示す数値で、倍率が高いほど競争が激しくなり、必然的に通過率も低くなる傾向があります。
企業が公表している採用予定人数や、過去の応募者数などから、おおよその倍率を逆算することも可能です。
特に、インターン参加者や過去の選考情報を参考にすれば、その企業の例年の傾向をより具体的に把握できるでしょう。
ただし、倍率は年度や職種によっても大きく変動するため、数字を鵜呑みにせず、複数の情報源をもとに冷静に分析することが重要です。
採用倍率は通過率を予測するための指標のひとつですが、倍率だけで単純に予測するのは難しいです。倍率はあくまで一つの目安として活用し、他の情報と照らし合わせつつ判断しましょう。
また、倍率が高くても必ずしも不利ではなく、実際には「企業が重視する評価軸」との相性も影響します。OB訪問などを活用して、「評価されやすい人物像」に合わせたアピール内容を練っておきましょう。
以下の記事では、採用倍率の活用方法を詳しく解説しています。基礎知識から、業界別・企業別の動向まで紹介しているので倍率を読み解いて自分の就活に活かしてくださいね。
② 採用フローから予測
企業の採用フローからも通過率はある程度予測できます。
たとえば、「エントリーシート→一次面接→二次面接→最終面接→内定」といった流れであれば、段階ごとに絞り込みが行われるため、二次面接の通過率は比較的高いと考えられます。
一方、「エントリーシート→一次面接→最終面接」のようにステップが少ない企業では、二次に相当する面接が最終判断の場となることもあり、より慎重な選考が行われるでしょう。
フローの長さや面接官の役職などからも、二次面接の重みを推測することが可能です。
採用フローの長さや構成によって、面接の重要度や通過率は大きく変わります。特に、フローが短い場合は二次面接が最終決定を左右する重要な段階となるため、評価も慎重になりやすいです。
また、面接官が「現場社員か管理職か」によって評価基準も変わります。採用フローを見つつ、過去の選考レポートを活用して「どの役職の人が出てくるか」「何を聞かれたか」を事前に調べるのがおすすめですよ。
③ 二次面接の通過率が高い企業の特徴から予測
通過率が高めの企業にはいくつか共通する傾向があります。まず、人手が求められる業界や急成長中のスタートアップ企業では、面接の通過率が高いとされています。
また、面接で重視されるポイントが志望動機や自己PRなど、明確で対策しやすい内容に絞られている企業も、学生にとって取り組みやすくなります。
ESや一次面接で評価されていれば、そのまま二次にも良い影響を与えることがあります。こうした情報は、企業説明会やOG・OB訪問などからも把握できるため、積極的に情報収集するとよいでしょう。
「人手が必要な業界」や「急成長しているスタートアップ」は通過率が高い傾向があります。こういった企業は、採用において柔軟さを持っている場合が多く、より多くの学生にチャンスを与えています。
また、面接で重視されるポイントが明確である企業では、力を入れるべきポイントが絞られ、対策しやすくなるでしょう。そのため、企業が求める人物像や面接の傾向を掴むことが大切になります。
④ 二次面接の通過率が低い企業の特徴から予測
通過率が低い企業には、明確で厳しい選考基準がある傾向があります。特に、企業の価値観や社風への共感度を重視する場合、わずかな方向性のズレでも評価が下がることがあります。
どれほどスキルが高くても、カルチャーフィットしないと判断されれば、先に進めないケースも少なくありません。
さらに、面接官に役員が含まれている企業では、会社全体を代表する立場から、より本質的で鋭い問いが投げかけられる傾向があります。
過去の経験だけでなく、将来のビジョンや業界への理解度まで深く掘り下げられることもあるでしょう。加えて、志望度の高さを見極めるために、あえて緊張感のある空気をつくり出す企業も存在します。
表情や話し方、反応のスピードといった非言語的な要素まで見られていることも珍しくありません。
こうした特徴を事前に知っておけば、ただ準備を重ねるだけでなく、自分自身の価値観との相性を見極める手助けにもなるでしょう。
通過率が低い企業は、選考基準がかなり厳しく、特に「企業文化にマッチするか」を重視します。そのため、「自分の価値観がどの点で企業文化に合うか」をアピールすることが成功のカギです。
また、役員が面接官を務める場合、業界研究だけでなく、その企業特有の課題や経営方針に対する意見まで持っていると、他の学生と差をつけられますよ。
面接質問事例集100選|聞かれる質問を網羅して選考突破を目指そう

「面接がもうすぐあるけど、どんな質問が飛んでくるかわからない……」
「対策はしてるつもりだけど、いつも予想外の質問が飛んでくる……」
面接前の就活生が抱える悩みとして「どんな質問をされるのか分からない」という問題は大きいですよね。頻出質問以外が予想しきれず、面接で答えに詰まってしまった人もいるでしょう。
また、面接経験がほとんどない人は、質問を予想することも難しいはず。そこでオススメしたいのが、就活マガジンが独自に収集した「面接質問事例集100選」です!
400社以上の企業の面接内容を厳選し、特に聞かれやすい100の質問を分かりやすく紹介。自分の回答を記入する欄もあるため、事前に用意した回答を面接直前に見返すことも可能ですよ。
面接で特に失敗しやすいのが「予想外の質問に答えられなかったパターン」です。よくある質問内容を知っておくだけでも、心の準備ができますよ。
また、志望動機などの頻出質問も、企業によってはひねった聞き方をしてくることも。質問集では特殊な例も網羅しているため、気になる人はぜひダウンロードしてくださいね。
\400社の質問を厳選/
一次面接と二次面接の違い

就活を進めていると、一次面接と二次面接の違いがわからず、対策の立て方に迷ってしまう人も多いかもしれません。
実は、それぞれの面接には目的や評価基準に明確な違いがあります。違いを理解しておくことで、面接で求められる内容がより具体的に見えるでしょう。
一次面接では、基本的なガクチカ、マナーなどが中心に評価されます。一方、二次面接になると、企業側は学生の人柄や価値観、将来性、そして組織との相性をより深く見極めようとします。
そのため、質問内容も抽象的で深掘りされる傾向が強まり、志望理由や自己PRに一貫性があるか、価値観が企業文化にマッチしているかといった点が問われるようになります。
より深い自己理解と企業理解をもとに、論理性と熱意をもって伝える準備が欠かせません。
「組織との相性」を深めるためには、組織に対する理解が最も重要です。企業分析のやり方や注意点を以下の記事で解説しているので、志望先の理解を深めるためにもぜひ参考にしてくださいね。
二次面接の目的は?
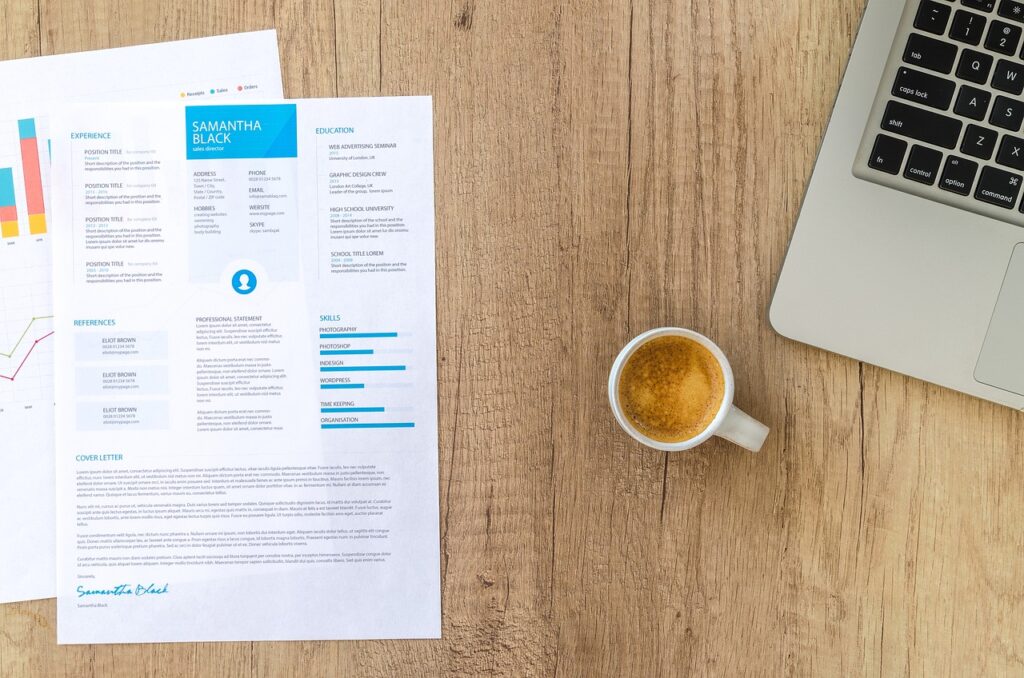
二次面接の主な目的は、一次面接だけでは見極めきれなかった人としての魅力や価値観をより丁寧に確認することにあります。
企業はここで、応募者の価値観が自社と合うかどうか、志望理由に一貫性があるか、そして将来的に活躍できる可能性があるかを確認します。
就活生の多くは、再び志望動機や自己PRを聞かれることに戸惑うかもしれませんが、これは単なる確認ではありません。話し方や受け答えの姿勢、考え方や熱意が細かく見られていると考えてください。
たとえば志望動機が曖昧だったり表面的だったりすると、「本当にうちを選んでいるのか?」という不信感につながりかねません。
一方で、企業研究をもとに自分の価値観と丁寧に結びつけた志望理由を伝えられれば、「この人なら長く一緒に働けそうだ」とポジティブに受け止められるでしょう。
緊張するのは当然ですが、自分らしさを忘れずに、相手と対話する意識を持って臨むことが大切です。準備の深さと伝え方次第で、評価は大きく変わるでしょう。
二次面接では、伝える姿勢や話し方がより大切になってきます。以下の記事では就活の面接で好印象になる話し方や、身だしなみの整え方を紹介しているのでぜひ参考にしてくださいね。
二次面接で見られるポイント

二次面接では、一次面接よりも深く志望動機や適性が掘り下げられます。そのため、どのような観点で評価されているのかを知っておくことが、通過率を上げるための第一歩です。
ここでは、ほぼすべての企業で共通して評価されるポイントを紹介します。面接対策の軸として意識しておきましょう。
- 内容の一貫性があるか
- 志望度が高いか
- 企業とのマッチ度が高いか
- 入社後の活躍イメージがあるか
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
① 内容の一貫性があるか
自己PR、学生時代の経験、志望動機のそれぞれの内容にブレや矛盾があると、面接官は違和感を覚えます。
二次面接では「この人の価値観や判断軸はどこにあるのか?」という本質的な部分が見られているため、話の流れや論理のつながりが非常に重要です。
たとえば、課題解決力をアピールした一方で、志望理由が「安定志向だから」などでは整合性が取れず、説得力を失ってしまいます。
エピソード→学び→志望理由といった一連の流れを意識し、企業が求める人物像と重ね合わせながら内容を組み立てておくと、自然と一貫性が生まれるでしょう。
② 志望度が高いか
二次面接では、志望度の高さも評価の対象となります。「御社の理念に共感しました」といった表現だけでは、ほかの企業でも通用しそうだと見なされかねません。
志望度を伝えるには、その企業独自の取り組みや事業内容について触れ、自分との関係性を具体的に話すことが効果的です。
たとえば「○○という事業の成長性に魅力を感じた」「説明会で話を聞いた○○さんの考え方に惹かれた」といった言及があると、企業側にも熱意が伝わりやすくなります。
「第一志望として入社したい」という意志を丁寧に伝えることが、好印象につながるはずです。
③ 企業とのマッチ度が高いか
企業との相性も、二次面接でよく見られるポイントです。いくら能力が高くても、社風や価値観が合わなければミスマッチと判断されてしまう可能性があります。
たとえば、個人プレーを重視する考え方を強調すると、チームワーク重視の企業では違和感を与えてしまうかもしれません。
企業の理念や働き方に共感したエピソードを交えて、自分との共通点を言語化しておくと、マッチ度を自然に伝えやすくなります。
④ 入社後の活躍イメージがあるか
二次面接では「この人は入社後に活躍できるだろうか」という点も見られます。そのため、成長意欲や将来の展望を明確に持っていることが大切です。
「入社後は〇〇の分野で経験を積み、3年後にはリーダーを目指したい」といった具体的なビジョンがあれば、面接官にも期待感を持ってもらえるでしょう。
その内容が企業のキャリアパスと合っていれば、より納得感が増します。
将来のビジョンに正解はありませんが、「どこで・どのように成長したいか」を自分なりに描けていることが、面接官の安心感につながるでしょう。
しかし、新卒の学生が将来働いている姿を具体的に伝えるのはなかなか難しいでしょう。以下の記事ではキャリアプランを明確にする方法や、具体的な例を紹介しているのでぜひ活かしてくださいね。
二次面接の面接官の特徴

二次面接では、一次面接とは異なる面接官が担当することが多く、評価されるポイントも変わってきます。主に配属予定の部署で責任を担うマネージャーや部課長クラスが面接官を務める場合が多いでしょう。
現場に近い立場から、実務に必要なスキルや職場への適応力を重視して評価されます。
そのため、これまでの経験や志望理由を語る際は、単なる意欲の表明ではなく、入社後にどう貢献できるかを具体的に伝えることが重要です。
また、受け答えの論理性や、会話の一貫性にも注目される傾向があります。一次面接の延長だと油断していると、思わぬところで評価を下げてしまうかもしれません。
企業ごとに求める人物像をしっかり理解し、それに沿った伝え方を工夫することが通過の鍵になります。
二次面接になり、面接官の役職が上がっていくと、「威圧感を感じてしまう…」と不安に思っている就活生もいるのではないでしょうか。以下の記事では威圧感を感じてしまう面接官との会話方法や対処法を解説しているのでぜひ参考にしてください。
二次面接の合格フラグとは?面接官の反応で見極める

二次面接では、合否のサインが面接官の言動に表れることがあります。合格フラグに気づければ、面接後の手応えをより的確に判断しやすくなるでしょう。
ここでは、面接官の反応から読み取れる代表的な合格フラグについて解説します。
- 質問の数が多いとき
- 面接官がたくさんメモを取っているとき
- 次の選考へのアドバイスをされるとき
- 採用前提の質問をされるとき
- 逆質問への回答が丁寧なとき
- 面接官が会社やチームの魅力をアピールするとき
① 質問の数が多いとき
質問が多い場合、面接官があなたに強く興味を持っている可能性があります。時間をかけて話を深掘りされるということは、それだけ人物像を詳しく知りたいという意図があると考えられるでしょう。
特に、自己PRや志望動機に関する質問が繰り返されるようであれば、前向きな評価を受けている可能性が高まります。
ただし、矛盾点を探す目的で質問が続く場合もあるため、相手の表情や雰囲気をよく観察して見極めてください。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
② 面接官がたくさんメモを取っているとき
あなたの発言を面接官が頻繁に書き留めている場合、それは評価材料として後から見返すためと考えられます。特に、志望理由や学生時代のエピソードなど、重要な場面でのメモは高評価の証となり得ます。
ただし、単に社内ルールとしてメモを取っているケースもあるため、あくまで全体の雰囲気や態度もあわせて判断することが大切です。
③ 次の選考へのアドバイスをされるとき
面接の終盤で「次は役員が出てくるよ」といった言葉があった場合、次の選考に進む可能性が高いと考えられます。企業側は通常、不合格の人には次のステップに関する情報を伝えません。
加えて、「とても印象が良かった」や「この調子で頑張って」といったポジティブなフィードバックも、合格のサインといえるでしょう。
とはいえ、あくまでも通過が確定したわけではないため、次に備えた準備は怠らないようにしてください。
④ 採用前提の質問をされるとき
企業は本当に入社の可能性がある人に対してのみ、入社後のビジョンを確認したいと考えるためです。
「入社後にやりたいことは?」「希望する部署はあるか?」といった内容の質問は、採用を前提としていることが多く、合格フラグの1つといえます。
ただし、他の候補者と比較する段階であることも想定されます。過度に期待せず、質問には真摯に、前向きな姿勢で答えることが大切です。
私たちも採用前提の質問を通して、学生の入社意欲や具体的なビジョンを確認したいと考えています。ただ、企業によっては他の候補者と比較している場合もあるので、過度に期待するのはNGです。
また、ポジティブな態度で自分の考えを伝えましょう。例えば「希望する部署は?」と聞かれた場合、「企業の未来に自分がどのように貢献できるか」まで具体的に伝えられると、強い印象を残せますよ。
⑤ 逆質問への回答が丁寧なとき
逆質問に対して、面接官が丁寧に回答してくれるときも、良いサインのひとつです。特に、個人的な体験や具体的なエピソードを交えて返してくれる場合には、親身に向き合ってくれている証と受け取れます。
一方で、逆質問が早々に切り上げられるような場合は、評価が低い可能性もあるため、態度や表情もよく観察しておくとよいでしょう。
⑥ 面接官が会社やチームの魅力をアピールするとき
面接の終盤で、面接官が自社の魅力や配属予定の部署について積極的に語り始めたときは、あなたを採用候補として前向きに検討している可能性があります。
これは、「一緒に働くイメージを持ってもらいたい」「内定を出した際に辞退されないようにしたい」といった意図が背景にあることが多いです。
特に、職場の雰囲気や働きがい、成長環境などを熱意を持って説明してくる場合は、その傾向が強いでしょう。ただし、全員に同様の説明をしている企業もあるため、話し方や具体性などから見極めてください。
特に部署配属やチームの雰囲気など、現場に近い具体的な話題が出た場合は、前向きに見ているサインの1つです。私たちも、採用に前向きな候補者には、「この人が入社したら…」という前提で話すことがあります。
一方で、全員に同じ話をしているかどうかの見極めも必要です。たとえば「◯◯さんのようなタイプはこのチームに合う」など個別の言及があるか、といった点から判断するのが良いですよ。
また、これらの合格フラグを引き出すためにも、本番さながらの模擬面接を通して、面接官に評価される受け答えを練習しておきましょう。模擬面接のやり方は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にして実践してみてくださいね。
二次面接で落ちる理由は?
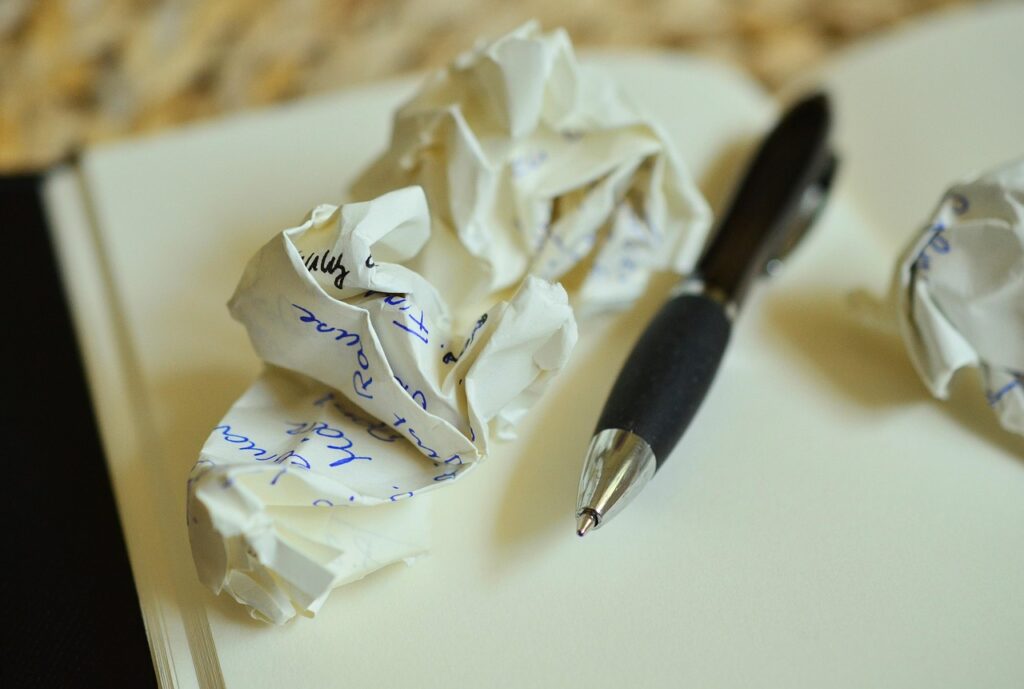
二次面接で不合格になるのは、一次面接とは異なる基準で見極めが行われるためです。企業側はこの段階で、「社風にマッチするか」「長く働く意欲があるのか」といった点を重視します。
ここでは、二次面接で落ちる主な理由を詳しく紹介します。
- 志望度が低いから
- 企業理解が浅いから
- マッチ度が低いから
- 回答に一貫性がないから
- キャリアプランが曖昧だから
① 志望度が低いから
志望度が低く見えると、企業は「内定を出しても辞退されるのでは」と不安に感じます。志望動機の浅さや逆質問の内容、面接中の話し方から本気度を見極められているのです。
受け答えが淡々としていたり、企業研究が不十分だったりすると、第一志望ではないと判断されてしまいます。
志望度を伝えるには、企業の魅力に対する共感や入社後のビジョンを具体的に語ることが効果的です。本気度が伝われば、信頼感も自然と高まります。
志望理由は、面接の事前に作成して第三者に添削してもらうことをお勧めします。以下では、志望動機を添削してもらえるサービスの利用方法やチェックポイントなどを説明していますよ。
② 企業理解が浅いから
企業の理念や事業内容を深く理解していないと、志望理由が表面的に聞こえてしまいます。とくに二次面接では、業界全体の動きや競合との差別化、自社の強みといった視点が問われる場面が増えます。
ホームページだけでなく、IR資料やインタビュー記事なども活用して情報を集めておくとよいでしょう。企業理解の深さが伝われば、自分と会社のつながりを自然にアピールできます。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
③ マッチ度が低いから
どれだけスキルがあっても、企業文化や職場の雰囲気と合わないと判断されれば通過は難しくなります。
企業は「この人と一緒に働きたいか」「うちのチームに合いそうか」といった視点でも選考を行っています。
そのため、自分の性格や価値観が企業の方針とどのように重なるかを言葉で伝えることが大切です。企業との相性を意識した自己PRが、説得力のあるアピールにつながります。
たとえば、チームで静かに落ち着いて進める文化の職場に対して、「自分は常に新しいことにチャレンジし、周囲を先導して動きます」と話すと、どれだけ意欲があってもミスマッチに映ることがあります。
特に二次面接では、現場の社員や直属の上司が出てくるケースが多く、チームとの相性を重視されやすいです。「その企業らしさ」を言語化して、自分と重なる部分を伝えることが重要ですよ。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
④ 回答に一貫性がないから
一次面接との発言にズレがあると、「この人は本音で話していないのでは」と思われてしまいます。質問ごとに考えが変わっているように聞こえる場合も要注意です。
こうした不一致は、事前準備が不足している証拠としてマイナス評価につながります。自己分析や志望理由、将来像をきちんと整理し、どの質問にも一本筋の通った答えができるようにしておくと安心です。
⑤ キャリアプランが曖昧だから
二次面接では、「入社後に何をしたいか」「将来的にどんな役割を担いたいか」といった質問がよく聞かれます。キャリアビジョンがぼんやりしていると、企業側は採用後のミスマッチを懸念するでしょう。
理想ばかりを語るのではなく、企業でどのような経験を積みながら成長していくかという現実的な道筋を描くことが大切です。具体的な将来像は、覚悟と熱意を伝える強い材料になります。
二次面接の通過率を上げるための対策方法

二次面接では、一次面接とは異なり志望度や企業理解がより深く問われます。そのため、入念な準備が求められます。
ここでは、二次面接の通過率を高めるために実践すべき5つの具体的な対策を紹介します。
- ESの内容を振り返る
- 一次面接を振り返る
- 企業理解を深める
- その企業でなくてはならない理由を明確にする
- 業界のトレンドを把握する
① ESの内容を振り返る
エントリーシート(ES)の内容は、二次面接でもほぼ確実に参照されます。面接官が異なる場合でも、過去の評価は共有されていることが一般的です。
たとえば、ESで「成長環境を求めている」と書いたのに、二次面接で「安定志向です」と言ってしまうと、志望軸に一貫性がないと判断されかねません。
これを防ぐには、ESの内容をあらかじめ整理し、志望動機や価値観にぶれがないかを確認しておくことが効果的です。
自分の回答を記録しておけば、後で客観的に振り返ることもできます。一貫した姿勢を伝えることが、面接官からの信頼獲得につながるでしょう。
ESと面接内容の一貫性は、私たちも特に注視しているポイントです。企業側の評価シートには、前回の面接官のコメントも共有されているため、少しのズレでも印象に残ってしまうんですよね。
また、ESの内容を振り返る際は、「なぜその言葉を使ったのか」という背景まで掘り下げておくと軸がブレにくくなります。感覚で書いた部分を無くして、論理的に説明できるように準備しておくと安心ですよ。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
② 一次面接を振り返る
一次面接の雰囲気や質問内容を振り返ることは、二次面接に向けた準備の土台になります。
どの質問に自信を持って答えられたか、逆に戸惑ってしまったかを整理することで、自分の弱点が明確になるはずです。
録音やメモを活用し、改善点を具体的に洗い出しておきましょう。また、面接官の反応や話の展開から企業が重視している価値観を読み取ることも大切です。
その価値観に沿って受け答えができれば、より企業に合った人物であると伝わりやすくなります。振り返りを「反省」で終わらせず、「次に活かす視点」で行うことが通過率向上のカギです。
評価コメントはそのまま次の面接官に共有されるので、一次面接の中で見えた「懸念点」が解消されていないと、二次も通過しにくいです。そのため、具体的にどこをどう改善するかまで整理しておくことが大切ですよ。
また、「前回の面接で◯◯と話していたけど、今はどう考えてる?」といった形で、継続的な一貫性を確認することもあります。質問内容だけでなく、自分の回答も振り返っておきましょう。
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
③ 企業理解を深める
二次面接では、企業についてどれだけ深く理解しているかが重視されます。
企業理念やサービス内容はもちろん、その企業がどのように社会課題を解決しようとしているのか、自分の言葉で説明できる状態にしておきましょう。
企業の公式サイトに加えて、プレスリリースやIR資料、業界専門メディアも確認しておくと、他の就活生と差をつけることができます。
表面的な知識ではなく、企業の中核に共感していることが伝われば、志望動機の説得力が増します。
企業理解を深めることで、自分が働くイメージを具体的に持てるようになり、受け答えにも自信が生まれるでしょう。
企業理解の深さは、「本気でうちの企業を選んでくれているのか」といった志望度を測る材料になります。実際、表面的な情報にとどまる学生と、自分の言葉で事業内容を語れる学生とでは、印象がまったく異なりますね。
私たちも、「どこまで企業の背景や業界構造を理解しているか」は自然と会話の中でチェックしています。IR資料や業界メディアまで調べている学生は少ないので、ここに時間をかけるだけで一歩リードできますよ。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
④ その企業でなくてはならない理由を明確にする
面接官が重視するのは、「なぜ数ある企業の中から当社を選んだのか」という点です。他社でも通用するような一般的な志望動機では、熱意は伝わりにくくなります。
たとえば、「業界最大手だから」といった理由だけではなく、「○○というプロジェクトで社会に△△な価値を提供している姿勢に共感した」といったように、具体的で独自性のある説明が必要です。
そのためには、企業の特色や強みを明確に把握し、自分の価値観や経験とどのように重なるかを整理しておくことが大切です。
「この会社で働きたい理由」が伝われば、志望度の高さを納得してもらいやすくなります。
「なぜこの企業なのか」の答えにも企業研究の深さが大きく影響します。特に、競合他社との違いをどう捉えているか、その企業の未来にどう関わりたいかまで語ると高評価になりやすいです。
また、自分の言葉で企業の強みや特徴に触れ、それが自分の価値観や経験とどう合致するかもアピールしましょう。具体的に理由を説明できる学生は、より強く印象に残りますよ。
⑤ 業界のトレンドを把握する
二次面接では、企業だけでなく業界全体に対する視野の広さも見られます。たとえば、IT業界を志望している場合は、AIやデジタルトランスフォーメーション(DX)などの話題が自然と出ることがあります。
こうしたトピックに対し、自分なりの意見や問題意識を持っていることを示せれば、企業研究の深さをアピールできるでしょう。
また、業界の動向を理解していることで、将来的にどう貢献したいかといったビジョンも具体的に語れるようになります。
企業と自分の将来像が一致していると伝えられれば、面接官にも好印象を与えるはずです。
業界のトレンドを把握していることは、「意欲をもって入社後に活躍できそうか」を見極める材料になります。「こういう影響があるのでは」と自分なりの視点を持てるとより高評価につながりますよ。
日経新聞や業界紙などで最近取り上げられているテーマを3つほど選び、「このテーマが業界にどう影響しているのか」「自分はそれにどう関わりたいか」をセットで整理しておくのがおすすめです。
「そもそも業界の分け方や種類をあまり理解できていなかった」という就活生は以下の記事を参考にしてくださいね。業界の種類だけでなく、それぞれの最新の動向と特徴を紹介していますよ。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
二次面接でよく聞かれる質問に対する答え方

二次面接では、一次面接よりも深く突っ込まれる質問が多くなり、受け答えの論理性や人柄との整合性が重視されます。
ここでは、頻出質問とその効果的な答え方を紹介します。あらかじめ想定問答を準備しておくことで、自信を持って本番に臨めるでしょう。
- 自己紹介
- ガクチカ
- 志望動機
- 入社後のキャリアプラン
- 他社の選考状況
① 自己紹介
自己紹介は第一印象を左右する大事な場面です。内容は簡潔かつ前向きにまとめましょう。大学での専攻や課外活動、そこから得た学びを交えて話すと、あなたの人となりが伝わりやすくなります。
面接官は話の内容だけでなく、話し方や表情からも人柄を判断する場合がほとんどです。緊張していても、落ち着いて明るく話す意識を持つと好印象につながるでしょう。
自己紹介では自分の強みや個性を簡潔に伝える力が求められます。過去の経験や学んだことを活かして話すと、「この人はどんな人か?」がより明確に感じられるので、印象に残りやすいです。
また、表情や話し方は想像以上に評価に影響します。「話の内容と態度が一致しているか」は、私たちも重視している点です。練習の段階から、表情や口調のチェックもセットで行うと安心ですね。
また、「自己紹介から他の就活生と差別化したい」と考えている就活生は、以下の記事を参考にしてくださいね。自己紹介の基本構成や好印象を与えるポイントを詳しく解説しています。
② ガクチカ
学生時代に力を入れたこと、いわゆる「ガクチカ」は、あなたの思考力や行動力を見るうえで重要です。
成果だけでなく、そこに至るまでの過程や工夫、乗り越えた課題がどうだったかを具体的に伝えてください。
「何を考え、どのように行動したか」が見えると、再現性のある強みとして評価されやすくなります。自分らしさを表すエピソードを選び、筋道立てて話すことが大切です。
二次面接では、ESや一次面接での話を踏まえて「なぜその行動を取ったのか」「その経験がどう活きているのか」まで深掘りされやすいです。表面的な説明で終わらせず、背景や自分の価値観まで掘り下げておきましょう。
また、同じエピソードでも伝え方を変えるのがコツです。「この経験は御社の○○事業における△△でも活かせると考えております。」など、企業との結びつきまでアピールできるとさらに差をつけられますよ。
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
③ 志望動機
二次面接では、志望動機が本気かどうかを細かく見られます。企業への関心が本物であることを、自分の経験や価値観と結び付けて伝えてください。
「なぜこの業界なのか」「なぜこの企業なのか」「どうして自分に合っていると思うのか」という順で整理すると、論理的な説明になります。
企業研究を丁寧に行い、自分の言葉で話せるようにしておきましょう。
志望動機では、企業の文化や業界の特性にどの点で自分の価値観やスキルがマッチしているのかを示すことが重要です。「マッチしているからこそ貢献したい」という姿勢を示すのも高評価に繋がるポイントですよ。
また、企業研究がしっかりできている人ほど、御社と他社との違いをしっかり語れます。パンフレットやHPの情報だけでなく、OB訪問や説明会での印象などを交えると、説得力が格段に増しますね。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
④ 入社後のキャリアプラン
入社後のキャリアプランについて聞かれるのは、あなたが自社でどのように成長し、貢献していきたいと考えているのかを知るためです。
具体性があるほど説得力が高まります。「まずは現場で経験を積み、ゆくゆくは〇〇の業務にも関わってみたい」といった中長期の視点が含まれると、将来のビジョンを持っている印象になります。
企業の育成制度やキャリアパスと矛盾がないように注意してください。
入社後のキャリアプランでは、具体性を持たせることが非常に重要です。例えば、「まずは現場で経験を積み、将来的にはマネジメント職に進みたい」など、段階的な成長を示すのがポイントですよ。
また、意外と見落とされがちなのが、「その会社だからこそ描ける未来」を語ることです。企業の育成制度やキャリアステップを理解したうえでの回答には、私たちも納得感を覚えますね。
⑤ 他社の選考状況
他社の選考状況については、正直に答えて問題ありませんが、志望度の高さを必ず添えてください。
「他にも数社の最終面接を控えていますが、企業理念や業務内容から、最も魅力を感じているのは御社です」といった伝え方が理想です。
志望順位が伝わることで、面接官もあなたの本気度を正確に判断できます。迷いがあるように見えないよう、自分の言葉で言い切ることが大切です。
他社の選考状況を伝えるときは、「どの企業がどの段階か」を簡潔に話した上で、「なぜその中でも御社を第一志望にしているのか」をセットで伝えると説得力が増しますよ。
たとえば、「他社の選考を受けていますが、御社の企業文化や業務内容が最も自分に合っています」という形で、他社について触れつつ、御社への強い興味と志望度の高さを強調することが大切です。
二次面接で聞くべき逆質問

二次面接では、企業からの質問に答えるだけでなく、自分から質問する「逆質問」も評価対象となります。
逆質問を通して企業への関心や入社意欲を示すとともに、自分に合った職場かどうかを見極める機会にもなるでしょう。ここでは、就活生が二次面接で積極的に尋ねたい質問を3つ紹介します。
- 入社後の働き方について尋ねる
- キャリアステップや評価制度を尋ねる
- 配属部署やチームの雰囲気を尋ねる
① 入社後の働き方について尋ねる
働き方についての質問は、自分がその企業でどのような生活を送るかをイメージするのに役立ちます。
「新人のうちはどのような業務に携わりますか?」や「リモートワークの導入状況はいかがでしょうか?」といった具体的な聞き方が好印象です。
企業側も、入社後の働き方に関心を持っている人に対して安心感を持ちますし、長く活躍してくれる可能性を感じ取ってくれるでしょう。
② キャリアステップや評価制度を尋ねる
キャリアパスや評価制度に関心を持つことで、成長意欲や将来のビジョンを持っていることを伝えられます。
「3年後にはどのようなポジションを目指せますか?」「評価はどのように行われていますか?」などの質問が効果的です。
このような話題に触れることで、働く意欲があることや、入社後も前向きに挑戦したいという姿勢が伝わりやすくなります。
③ 配属部署やチームの雰囲気を尋ねる
職場の環境や人間関係は、働きやすさに直結します。
「配属されるチームにはどのような特徴がありますか?」「チーム内でのコミュニケーションの雰囲気はどうですか?」といった質問で、実際の職場の様子を具体的に知ることができるでしょう。
職場の実情を把握しようとする姿勢は、企業側にとっても好意的に映りますし、自分に合った環境かどうかを判断するうえでも重要です。
また、「逆質問の具体例をもっと知りたい」「聞き方のマナーを再確認しておきたい」という方は、ぜひこちらの記事も確認してみてくださいね。逆質問例50選や先輩就活生の成功談と失敗談なども紹介していますよ。
二次面接の通過率を上げるための対策を理解しておこう!

二次面接は新卒採用において一次面接よりも難易度が上がり、通過率もおおむね30〜50%程度とされています。だからこそ、事前に対策を講じることが合格への近道です。
通過率を予測するには採用倍率や企業ごとの選考フローの把握が有効。通過率が高い企業と低い企業の特徴からも傾向が見えるでしょう。
加えて、一次面接との違いや二次面接の目的を理解した上で、志望度や一貫性、企業とのマッチ度を意識した受け答えが求められます。
面接官の反応を通じた合格サインを見逃さないことも大切です。通過率を上げるには、自己分析・企業理解・キャリア設計の準備を徹底し、逆質問も含めた双方向の対話を意識しましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












