コミュニケーション能力はどう言い換える?自己PRの例文・面接でアピールする方法も紹介
ES・面接でコミュニケーション能力をアピールしたい就活生も多いでしょう。
しかし単に「自分の強みはコミュニケーション能力です」と就活の自己PRの場面で伝えても効果的ではありません。言い換え表現などを用いて上手にアピールするしましょう。
今回は、コミュニケーション能力の言い換え方の16選と就活の自己PRでアピールするポイントについても詳細に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
自己PRをすぐに作れる便利アイテム
- 1自己PR自動作成ツール
- 最短3分!受かる自己PRを、AIが自動で作成
- 2ES自動作成ツール
- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

記事の監修者
記事の監修者
人事 鈴木
新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見るコミュニケーション能力の言い換え方リスト16選

コミュニケーション能力の言い換え表現を一覧リストで紹介します。
自分に最もマッチする表現を用いて、上手に言い換えを行いましょう。
- 簡単に理解できるように伝える力
- 言語化していない本音を読み取る力
- 相手の感情に共感し理解する力
- 論理的に伝える力
- 正確に状況を伝える力
- 的確な質問をする力
- 集団の円滑な会話を促す力
- チームの意見をまとめる力
- 相手の話を聞き要点を押さえる力
- 関係を構築し維持する力
- 素直に報告する力
- 解決策を提案する力
- その場の雰囲気に順応する力
- 協調性を持ってチームプレイを推進する力
- 必要な情報を詳細に聞き取る力
- 積極的に発言をする力
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
【言い換えで役立つ】コミュニケーション能力は3パターンに分けられる

前項のようにコミュニケーション能力には様々な種類がありますが、大きく分けると以下の3パターンのどれかに当てはまります。
- 相手に自分の考えを伝える力
- 相手の話を聞き、意図を汲み取る力
- 非言語的な能力
自分ががどれに当てはまるかを理解していると、言い換え表現を見つける際にもスムーズです。
①相手に自分の考えを伝える力
相手に分かりやすく、自分の伝えたいことを的確に伝える力を指し、言語化能力とも呼びます。
この能力は、さまざまなビジネスの場で必要不可欠です。自分の意見や考えを正確に伝えられなければ、期待する効果を得ることは難しいでしょう。
相手に理解してもらうためには、話の内容を整理し、簡潔かつわかりやすい言葉でまとめて伝える力が必要不可欠です。
②相手の話を聞き、意図を汲み取る力
ビジネスの場でのコミュニケーションでは、相手の話を聞く力(傾聴力)も非常に重要です。
ビジネスにおいて信頼関係を築くためには、相手の価値観や気持ちを理解することが求められます。まずは、相手の話を最後までしっかりと聴く姿勢が大切にしましょう。
また、傾聴力は相手が何を伝えようとしているのか正確に理解する能力であり、言葉の裏にある意図や感情を読み取る力も含まれます。
相手の言葉だけでは完全に理解できない場合でも、質問をしたり、「このように理解しているのですが正しいでしょうか?」と確認することも重要です。
③非言語的な能力
非言語的なコミュニケーションとは、言葉を使わずに行われる意思疎通のことです。「ノンバーバル・コミュニケーション」とも呼ばれますよ。
例えば視線、姿勢、身振り手振り、身だしなみなどです。人間は言語以外にもこのような手段で、無意識的にもメッセージを伝えています。
感情表現に関しては、発言より印象に変化を与えるので、注意しましょう。
プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつける自己PRを作ろう
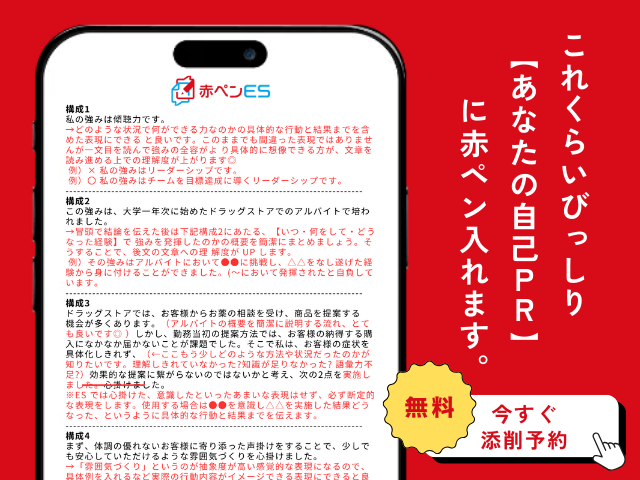
「自己PRが書けない……」「強みってどうやってアピールしたらいい?」など、就活において自己PRの悩みは尽きないものですよね。
そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたの自己PRの良い点も改善点もまるごと分かりますよ。
さらに、本記事の後半では実際に、接客業の自己PRの例文を添削しています!
「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。
就活におけるコミュニケーション能力のチェックポイント

採用担当者は、主に以下の7つのポイントをチェックし、コミュニケーションの面の良し悪しを判断しています。
- 会話している時の表情が自然か
- 声の大きさ・速さが適切か
- 相手に丁寧な印象を与える言葉遣いか
- 会話の際に相手の目を見れているか
- 質問の意図に対して的外れな回答をしていないか
- 姿勢が良いか
- 清潔な見た目か
意思疎通に問題があると捉えられないように、必ずこれらの点を注意しましょう。
①会話している時の表情が自然か
意思疎通において優れる人は、発言の内容だけでなく表情にも気を配っており、魅力的です。
企業は選考の際、応募者である学生がする発言だけでなく、仕草や態度を含めた総合的な印象で学生を評価していますよ。
口角を上げて柔和な表情で話をしたり、会話のたびに笑顔で対応するだけでも、意思疎通に問題がないと見なされる可能性が高まります。
表情は、非言語能力の中でも面接官に良い印象を与える要因です。
②声の大きさ・速さが適切か
コミュニケーションでは、言葉選びに加えて、相手を慮る気持ちが重要です。そのため、話すスピード・声の大きさに気をつけてください。
話すスピードが速すぎる場合、相手が聞き取りにくく不快な気持ちになってしま可能性があります。面接では緊張から話すスピードが速くなりがちですが、意識してペースを調整することが大切です。
相手に合わせた話し方を心掛けることで、コミュニケーション能力が高い就活生として評価されやすくなりますよ。
③相手に丁寧な印象を与える言葉遣いか
就活の場においては採用担当者の立場が上であることを認識し、丁寧な印象を与える言葉遣いを意識しましょう。
敬語は重要ですが、不自然な尊敬語や謙譲語を多用していないかに注意が必要です。また、ビジネスの場では、相手との距離が近すぎるのも問題です。
良好な人間関係を築くために、適度な距離感を保ちながら、丁寧かつ効果的なコミュニケーションを図るよう意識しましょう。
④会話の際に相手の目を見れているか
面接官と目線を合わせることで、自分の発言を相手により強くアピールできます。
どこを見ながら意思疎通を行っているかで相手の受け取り方が大きく変わるため、適宜視線を合わせましょう。また面接官との視線を適切に合わせることで、誠実さや信頼感も伝えやすくなります。
⑤質問の意図に対して的外れな回答をしていないか
面接は学生が自分をアピールする場であると同時に、面接官とスムーズに話を展開できるかチェックする場ですよ。
そのため重要なのは、その場の雰囲気を理解して、どのような意図で質問を投げかけているのか理解することです。単に言葉の表面だけでなく、相手の考えや気持ちを汲み取りましょう。
相手の意図を正確に理解し、それに応じた適切な返答をすることで、スムーズに会話を広げながら面接官に良い印象を与えられます。
⑥姿勢が良いか
面接官は、姿勢を含めた非言語部分も観察しています。
背もたれに寄りかかり、目を合わせずに話を聞くのと、真剣な表情で前傾姿勢になって話すのとでは、相手に対する関心の度合いが異なって見えますよね。
良い姿勢は相手への敬意や話に対する関心を示すものと認識されるため、面接の際の重要な要素です。適切な姿勢を保つことで、面接官に対して良い印象を与えられます。
⑦清潔な見た目か
洋服や髪型といった視覚情報によって、相手に与えるイメージは大きく変わります。ビジネスシーンではスーツなどのフォーマルな服装が適切ですよ。
一方で、TPOに合わない派手なネクタイやアクセサリーは、相手にネガティブな印象を与えるためNGです。清潔な服装や髪型を選ぶことで、面接官に対してクリーンな印象を与えられます。
コミュニケーション能力をESの自己PRでアピールするポイント

ESの自己PRでアピールするためには、言い換えを用いる以外にも以下のポイントを押さえることが重要です。
- 志望する企業から求められるコミュニケーション能力を理解する
- 自分の強みであるコミュニケーション能力を具体化して伝える
- 面接を見据えて自己PRを作る
それぞれについて詳細に解説します。
①志望する企業から求められるコミュニケーション能力を理解する
企業・職種によってどのような意思疎通が行われるかは異なりますが、それぞれで求められるコミュニケーション能力を理解し、自己PRに反映させることが重要です。
例えば、営業職では、相手の心を開かせる会話力や、自社の商品を効果的に紹介するプレゼンテーション能力が求められます。
一方、事務職では、正確でこまめな報告・連絡・相談を行う能力が重視されることが多いですよ。
そのため、自己PRを行う際には、応募職種に必要なスキルを具体的にイメージし、それに合った自己アピールを考える必要があります。
②自分の強みであるコミュニケーション能力を具体化して伝える
コミュニケーション能力を具体化して説明することも重要です。
「人と話すのが得意です」「わかりやすく説明できます」「印象が良いとよく言われます」といった漠然とした表現では、説得力が不十分だからです。
自分の強みを明確にするためには、「意見を伝える力」「聞く力」「人と連携する力」のどれが得意かを考えると良いでしょう。次に、特に何が得意なのかを具体的に掘り下げます。
掘り下げを行い具体的になったら、その能力1点にフォーカスしてアピールしましょう。伝わりやすく魅力的な自己PRに仕上がります。
③面接を見据えて自己PRを作る
自分の主張を具体的かつ明確に伝えられるよう、面接を見据えて練習や自己PR文の推敲をしっかりと行いましょう。
面接での実際の会話力や自己PRの文章自体が、意思疎通の面で優れていることを証明する場となります。
「誰にでも自分の考えを理解しやすく説明できる」と自己PRに書いていても、面接での説明がわかりにくい場合は逆効果です。
コミュニケーション能力を分かりやすくアピール!言い換え例文集
「コミュニケーション能力」と一言で言っても、その中身は多岐にわたります。就活でこの力をアピールしたい方にとっては、「自分の強みをどう表現すれば伝わるか」が悩みどころではないでしょうか。
本章では、そんな方のために「コミュニケーション能力」をそれぞれの特徴を捉えて言い換えた、自己PR例文を紹介します。
「話す」「聞く」「感じ取る」など、具体的な行動に落とし込んでみましょう。
- 簡単に理解できるように伝える力
- 言語化していない本音を読み取る力
- 相手の感情に共感し理解する力
- 論理的に伝える力
- 正確に状況を伝える力
- 的確な質問をする力
- 集団の円滑な会話を促す力
- チームの意見をまとめる力
- 相手の話を聞き要点を押さえる力
- 関係を構築し維持する力
- 素直に報告する力
- 解決策を提案する力
- その場の雰囲気に順応する力
- 協調性を持ってチームプレイを推進する力
- 必要な情報を詳細に聞き取る力
- 積極的に発言をする力
また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①簡単に理解できるように伝える力
この例文では、難解なテーマを丁寧に言い換えながら相手の立場に立ってわかりやすく伝える姿勢をアピールしています。
自己PRでは、単なる能力の主張ではなく、「どのように発揮したか」を具体的に伝えることが重要です。
| 【結論】 私の強みは、「複雑な内容をかみ砕いて、相手にわかりやすく伝える力」です。 |
| 添削コメント|この一文は簡潔かつ直接的に強みを表しており、テーマである「簡単に伝える力=コミュニケーション能力」を端的に示せています。言い換えとして自然で、企業にも意図が伝わりやすい良い導入です。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ活動では、毎週異なるテーマをもとにプレゼンテーションを行っており、私は発表担当の頻度が多く、 |
| 添削コメント|「自然と」では受け身な印象を与えるため削除し、「自ら積極的に」と言い換えることで主体性を明示しました。説明力=伝える力を発揮したことを読み手に強く印象づけられるように調整しています。 |
| 【エピソード詳細】 あるとき、専門的な経済理論について発表することになりましたが、内容が難解でゼミ内でも理解が進んでいない様子でした。そこで、私は理論を身近な例に置き換えたり、 |
| 添削コメント|「図解を使ったスライドを作成」だけでは工夫の具体性に欠けるため、「なぜ視覚的要素」を入れたのか、「その視覚的要素をどのように活用したのか」を詳しく記述しました。 |
| 【成果】 |
| 添削コメント|成果を客観的な評価に置き換えることで、テーマの「伝える力」を養えたことが根拠づけられています。「磨かれた」という表現も成長のニュアンスがあり、評価につながりやすい仕上がりです。 |
| 【入社後】 貴社での業務でも、社内外の関係者に対して情報を正確かつ明確に伝える役割を担い、 |
| 添削コメント|「円滑なコミュニケーション」という抽象表現を、実際の業務シーン(部署間連携や提案)に具体化することで、企業での再現性が高まりました。伝える力がどう活きるかを読者が明確に想像できます。 |
【NGポイント】
もともとの文章では「自然と役割を担った」など主体性に欠ける表現や、「図解を用いたスライド」など表面的な行動描写にとどまっていた点が課題でした。また、成果について客観的な意見がなく、強みを発揮したことへの説得力がなくなっていました。
【添削内容】
受動的な表現を主体的なものに変更し、図解や工夫の中身を「生活に即した例」「視覚的工夫」といった表現に言い換えました。成果についても、誰からどんな反応があったのかを明示しています。
【どう変わった?】
自ら伝える努力を重ねてきたことがはっきりと伝わる構成となり、企業側も業務への貢献可能性をイメージしやすくなりました。「コミュニケーション能力=わかりやすく伝える力」としての言い換えも自然です。
| ・主体性がある表現に言い換える ・伝え方の工夫を具体的に示す ・成果は客観的な評価を盛り込む |
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
②言語化していない本音を読み取る力
この例文では、自分の働きかけによって他者の発言を引き出した経験を通じて、傾聴力や対人理解力を強みとしてアピールしています。
周囲の言動や表情から相手の本音を汲み取り、適切な対応ができる力は、チームで成果を出すうえで重要なので積極的にアピールしましょう。
| 【結論】 私は、相手の言語化されていない気持ちを汲み取り、円滑な人間関係を築く力があります。 |
| 添削コメント|冒頭で「言語化されていない気持ちを汲み取る力」という特徴が端的に示されており、コミュニケーション能力の中でも非言語的理解力という独自の切り口を明確にしています。文章量も適切で、印象的な導入です。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ活動では、グループでの調査発表に向けてメンバーと協力する機会が多くありました。 |
| 添削コメント|「心がけた」は意図を示すのみで行動として弱く、採用担当者には評価されづらい表現です。改善案では“働きかけ”とし、能動的なコミュニケーション能力の発揮をアピールできるように調整しました。 |
| 【エピソード詳細】 あるプロジェクトで、1人のメンバーが会議中にほとんど発言しないことがありました。表情や態度から何か意見があると感じた私は、会議後に個別に声をかけました。話を聞くと、 |
| 添削コメント|本人の気持ちを深く理解した上で「支援した」行動の描写が足りていなかったため、心理的な背景への共感と行動によるサポートを補足しました。また、代弁ではなく「本人が話せるよう支援する」という姿勢に変更し、自己中心的な印象を避けました。 |
| 【成果】 その後、彼は自分の意見を少しずつ出せるようになり、チームの議論も活発になりました。 |
| 添削コメント|「ゼミ内で最も評価の高い発表」は主観的かつ曖昧な表現です。改善文では、チーム全体の成果としての達成感を強調し、読み手が納得できる客観性のある成果に言い換えました。 |
| 【入社後】 入社後も、相手の立場や感情を汲み取る姿勢を大切にし、 |
| 添削コメント|「組織全体の成果に貢献」は抽象的で、再現性が想像しづらい点が課題でした。改善後は「多様な価値観」「補い合う関係性」などを用いて、職場でも活かせる具体的な行動と価値を伝えられるよう補強しています。 |
【NGポイント】
当初は「心がけた」「最も評価された」といった抽象表現が多く、行動の具体性に乏しかった点が課題でした。また、「本人の代わりに意見を紹介した」という構図が自己PRにおいて主張が強すぎる印象を与えています。
【添削内容】
意見を出しやすくなるよう支援した行動に焦点を当て、傾聴とフォローを軸とした内容に変更しました。抽象的だった成果や入社後の展望も、読み手にイメージしやすいよう具体的な表現に言い換えました。
【どう変わった?】
行動の背景や目的が明確になり、受け身ではない自発的な姿勢が伝わる内容になりました。企業においても、他者の気持ちに寄り添いながら行動できる人物像として、評価されやすくなっています。
| ・抽象表現は行動に言い換える ・代弁より支援の姿勢を示す ・成果や入社後は具体性重視 |
③相手の感情に共感し理解する力
ここでは、「相手に共感し、理解を示してコミュニケーションを取った経験」を用いた自己PRを紹介しています。
結論→過去に取った行動→成果→強みの再現性の流れを意識し、実際の行動内容と具体的データで説得力を高めましょう。
| 【結論】 私は「相手の感情に共感し理解する力」を活かして、 |
| 添削コメント|「人と信頼関係を築ける」「円滑なコミュニケーションを図れる」などの抽象語だけでは業務貢献が伝わりません。強みによる状況把握→課題解決と強みを活かした流れを示し、強みが成果に直結すると強調しました。 |
| 【エピソード】 大学時代、地域の介護施設でのボランティア活動に参加し、高齢者の方々と交流する中で、 |
| 添削コメント|「この力を発揮しました」だけでは根拠が足りません。強みをどんな場面でどう活かしたかを補い、行動の再現性とテーマ「共感・理解する力」を明確化しました。 |
| 【エピソード詳細】 |
| 添削コメント|実際に体験した弱みの表示よりも、行動の描写を優先しました。Howの具体策(笑顔・声掛け)を追加し、強み発揮のプロセスが鮮明になりました。 |
| 【成果】 |
| 添削コメント|主観的な「言葉」を評価とするのではなく、客観的な指標(アンケート数値)に置換し、第三者評価の事実共有を加えて説得力を強化しました。 |
| 【入社後】 貴社でも、 |
| 添削コメント|冗長な重複表現を削除しました。自分の強みをどのように行動につしていくかのロジックを簡潔に再構成し、企業での再現性とテーマ性を両立しました。 |
【NGポイント】
抽象表現が多く成果を裏付ける客観的データが不足していました。行動と結果の因果が薄く、「共感力」が企業で再現可能か読み手が判断しづらかった点も課題でした。
【添削内容】
場面・行動・数値を補い、「共感→行動→成果」の因果を強調しました。曖昧な言い回しを削除し、アンケート結果や職員評価など第三者証拠を追加することで説得力を高めています。
【どう変わった?】
定量データと具体動詞により成果が一目で分かるようになり、採用担当者は強みの再現性を容易に想起できます。結果、コミュニケーション能力が業務課題解決へ直結する人材だと評価されやすくなったでしょう。
| ・数値提示で説得力を強化する ・行動と成果を論理的に繋げる ・強みをどう活かすのかを明示する |
④論理的に伝える力
ここでは、自分自身の意見を論理的に伝える力を強みとして自己PRに盛り込んだ文章を紹介しています。
相手の立場や理解度を踏まえて、順序立てて情報を整理し、伝える工夫ができるかどうかを意識した構成にしましょう。
| 【結論】 私は、相手の立場に立ちつつ、 |
| 添削コメント|「物事を」という表現は抽象的で、何を指しているのかが曖昧です。就活の場では「何をどうする力か」を明確に伝えることが重要であり、「伝える内容を筋道立てて整理し」としたことで、テーマである「論理的に伝える力」がより具体的に伝わるようになりました。 |
| 【エピソード】 |
| 添削コメント|元の文は抽象的で、実際にどんなテーマにどう取り組んだかが見えづらく、印象が弱いものとなっていました。具体的なテーマと行動内容を盛り込むことで、企業側が「論理的に伝える力」を発揮した状況をより明確にイメージできる構成に改善しました。 |
| 【エピソード詳細】 たとえば、社会問題に関する文献研究を発表する際には、聴き手の知識量を想定し、背景説明や要点の順序を工夫しました。 |
| 添削コメント|抽象的だった行動内容を、図解・事例引用・質疑応答での対応方法などに細分化し、「いつ・何を・どうしたのか」が明確になるようにしました。これにより、単に「わかりやすく伝えた」だけでなく、「伝えるための工夫・論理的対応」が見える構成になっています。 |
| 【成果】 その結果、「話の構成が明快で理解しやすかった」との評価を受け |
| 添削コメント|元の「選出された」だけでは成果としての客観性やインパクトに欠けました。「経済学部代表」「ニュース掲載」といった評価根拠を補うことで、読み手にとって「すごさ」が分かりやすくなり、成果としての説得力が飛躍的に向上しています。 |
| 【入社後】 入社後はこの論理的に伝える力を活かし、 |
| 添削コメント|テンプレート的な表現だった「円滑な意思疎通」を修正し、「課題や提案の整理」「共通認識の形成」など、ビジネスにおける具体的なシーンと結び付けました。企業視点での貢献イメージをより明確に示すことができました。 |
【NGポイント】
「情報を整理して伝える力があります」などの表現が抽象的で、就活生としてどんな行動を取ったのかが十分に伝わりませんでした。また、成果や入社後の活かし方についても汎用的な表現が多いです。
【添削内容】
全体を通して「5W1H」の観点で行動内容を細分化し、実際に何をどう工夫したのかが具体的に伝わるよう改善しました。また、「発表内容の図解化」などを加えることで、論理的に伝える力の裏付けを強化しています。
【どう変わった?】
今回の修正では、論理的な伝達力を、ゼミ活動から仕事に活かせるスキルとして言語化し、発信力だけでなく、受け手に合わせた伝達の工夫が見える内容となり、企業側も応用性を感じやすくなったでしょう。
| ・工夫を詳細に伝える ・成果は客観的に示す ・業務でどのように活かすのかを具体的に伝える |
⑤正確に状況を伝える力
飲食店アルバイトで培った「正確に状況を伝える力」を軸にした自己PR例文です。課題→行動→成果を数値で可視化する自己PR例です。
強みを企業が理解しやすい形で示すため、数字と手順を組み合わせ、エピソードについても「課題→行動→成果」を明快に繋げることがポイントですよ。
| 【結論】 私は「正確に状況を伝える力」を活かして、 |
| 添削コメント|抽象語を具体行動へ置換し再現性を明示しました。誰でも言える汎用な表現を削り、行動→効果の流れを示したことで強みの独自性と説得力が大幅に向上しました。 |
| 【エピソード】 飲食店のホールスタッフとして勤務していた際、混雑時の連携ミスが続き、 |
| 添削コメント|「頻発」を平均遅延時間とクレーム件数に置換し課題を定量化しました。数字で示すことで問題の深刻度が即時伝わり、以降の改善アクションへ説得力を持たせています。 |
| 【エピソード詳細】 私は厨房とホール間の情報共有のズレに着目し、オーダー内容を「調理順・卓番・提供時間」の3点で簡潔に伝えるメモを導入。 |
| 添削コメント|従業員それぞれがどのように動くのかを明確にして補強し施策の具体性を向上させました。複数アクションの因果関係と目的を一本化し、計画力と調整力を同時にアピールできる構成へ改善しました。 |
| 【成果】 結果、導入から1か月でクレーム件数はゼロになり、 |
| 添削コメント|離職率の減少については内容が曖昧だったため「定着率20%向上」に置換し、ここでも数値化を意識しました。数値での成果を第三者評価と並べて提示することで客観性が増し、取り組みと結果が直結したことを示しています。 |
| 【入社後】 貴社でも状況を整理し、 |
| 添削コメント|抽象的な表現をフォーマット活用という仕組みに言い換え、入社後のどのように活躍するのかを明示しました。学生時代の成功手法を企業課題へ転用できる未来像を描き、活躍イメージを具体化しました。 |
【NGポイント】
抽象語が多く、過去エピソード中の行動と成果が曖昧だったため、課題の深刻度も成果の大きさも採用担当に伝わりにくかったです。行動が成果に繋がっているかも分かりにくく、入社後の再現可能性が見えなかったことも評価を下げていたでしょう。
【添削内容】
過去エピソード中の行動を具体化し、「課題→行動→成果→評価」の流れを作りました。平均遅延5分やクレーム週5件など数値でデータを示し、改善策も5W1Hで整理したことで、分かりやすい自己PRになっています。
【どう変わった?】
課題と成果が数字で可視化され、行動の背景と結果が論理的に結び付いたことで、強みを企業でも活かせる印象が強まりました。採用担当が応募者の人物像を具体的にイメージしやすくなり、面接深掘りにもつながる自己PRへ進化しています。
| ・問題点と成果を具体的な数値で示す ・行動の背景を簡潔に示す ・入社後の活躍方法を明示する |
⑥的確な質問をする力
ここでは相手の意図を理解し、要点を明確にする力をアピールする自己PRを紹介しています。
今回の例文では、「的確な質問をする力」という切り口で、具体的にどのような質問をして議論を深めていったのかを伝えることが必要になります。
| 【結論】 私は、相手の意図を正確に理解するために的確な質問をする力を強みとしています。 |
| 添削コメント|結論では「的確な質問をする力」と強みが明確に示されており、テーマである「コミュニケーション能力の言い換え」が成立しています。簡潔かつ主張が伝わる表現で、採用担当にも好印象を与えやすい書き出しです。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ活動では、メンバー同士で議論しながら調査レポートをまとめる機会が多くありました。 |
| 添削コメント|「話の本質を掴むための質問」という表現は抽象的で、具体的な行動が見えにくい点が難点でした。改善後は「曖昧な点の確認」「背景の把握」など具体的な行動に置き換えることで、説得力が高まりました。 |
| 【エピソード詳細】 あるとき、レポートのテーマに関して意見が分かれ、議論が平行線をたどったことがありました。 |
| 添削コメント|質問例の提示自体はよかったものの、「どのような意図で」「どう機能したか」が不足していたため説得力に欠けました。改善後は5W1Hの視点で行動の因果関係を明示し、実践的スキルとして評価される内容に高めました。 |
| 【成果】 この経験を通じて、ただ発言するのではなく、相手の考えを引き出し、方向性を整える質問の重要性を学びました。 |
| 添削コメント|「感謝された」という成果は主観的で伝わりづらく、客観的評価に乏しい点が弱点でした。そこで「第三者評価」や「発表での高評価」といった具体的な成果に置き換えることで、企業側に伝わりやすいアピールとなりました。 |
| 【入社後】 入社後も、相手の話を受け止めながら |
| 添削コメント|「チーム内外での意思疎通」という表現は汎用的で、業務との接続が弱い印象を与えていました。改善後は「顧客」「社内」「業務の質とスピード」など具体的なシーンや成果につながる表現へと変更し、実務への応用力が伝わる内容になっています。 |
【NGポイント】
元の文章では、強みを裏付ける行動が抽象的な表現に留まっていたため、実際に何をしたのかが曖昧でした。また、成果や入社後の貢献内容についても主観的な言い回しに偏っており、評価に結びつきづらい構成です。
【添削内容】
抽象的な表現や主観的な成果を具体的な行動や客観的評価へと置き換えました。特にエピソード詳細では、質問による状況整理の流れを再構築し、成果では第三者評価が伝わる実績に修正しました。
【どう変わった?】
強みである「的確な質問をする力」が、具体的な場面でどう発揮され、どのような成果に結びついたかが明確になったことで、企業側も実際の職場での活躍を想像しやすくなったでしょう。
| ・質問の内容を具体的に伝える ・成果は客観的に伝える ・入社後の活用場面を明示する |
⑦集団の円滑な会話を促す力
ここで紹介するのは、グループ内の調整役としての行動を通じて、対人理解力や会話構成力をアピールする例文です。
自己PRでは「何を強みとし」「どのような行動で活かしたか」を明示し、入社後の活用まで一貫した構成に仕上げることが重要です。
| 【結論】 私は、集団の円滑な会話を促す力を強みとしています。 |
| 添削コメント|結論部分では「集団の円滑な会話を促す力」と明示されており、何を強みとしてアピールするのかが一目で分かります。抽象的になりやすい「コミュニケーション能力」を言い換えた表現としても適切です。 |
| 【エピソード】 大学の授業では、5〜6人のグループに分かれてディスカッションを行う機会が多くありました。 |
| 添削コメント|元の文は「議論が進まなかった」という結果だけに触れ、主体性が伝わりづらい表現でした。改善後は「空気を感じ取り接点をつくる」という能動的行動を加えることで、集団の雰囲気を察し行動する能力が明確になっています。 |
| 【エピソード詳細】 そのような場面では、まず全員の話をよく聞き、それぞれの考えに共通点を見つけて言い換えながら紹介するように心がけました。たとえば「〇〇さんの意見は〜という点で、△△さんの考えと近いかもしれませんね」と意見と意見をつなぎ、互いの理解を促しました。 |
| 添削コメント|話しづらい人に「声をかける」だけでは行動の深さが伝わりにくいため、「タイミングを見て」「安心できる空気づくり」といった表現に変更しました。これにより、配慮と場の調整力を伴う高度なコミュニケーション力が伝わります。 |
| 【成果】 その結果、ディスカッションでは活発な意見交換が生まれ、発表内容の質も高まりました。 |
| 添削コメント|「雰囲気がいい」という抽象的な評価は成果として弱いため、教員の具体的なフィードバックと代表選出という事実を加えることで、第三者からの信頼性のある評価として強化しました。 |
| 【入社後】 入社後も、チーム内での意見交換を円滑に進め、メンバーの意見を引き出す役割を担いたいです。 |
| 添削コメント|「協働の空気をつくる」という表現は抽象的で再現性が伝わりにくいため、改善後では「温度差や対立に気づく」「会話の架け橋になる」といった具体的な行動イメージに言い換えました。入社後の貢献がより明確になっています。 |
【NGポイント】
全体的に抽象的な表現が多く、具体的な行動や成果が伝わりづらくなっていました。特に「議論が進まなかった」「雰囲気が良い」といった表現は、採用担当が判断しにくい曖昧さが残っていました。
【添削内容】
抽象的な部分を具体化し、何を感じて、どのように行動したのかを明確に示すよう調整しました。加えて、成果や入社後の展望では、「誰が、どう評価し、どう任されたか」をはっきりさせ、信頼性を高めています。
【どう変わった?】
「気づく力」「空気を整える力」「関係性をつなぐ力」など、集団における調整力や働きかけの具体性が高まりました。企業側も「入社後にこの力をどう活かせるか」が自然に想像できる構成となっています。
| ・議論で何を大切にしたかを伝える ・成果は誰が見ても伝わる形にする ・入社後の行動を明確に描写する |
⑧チームの意見をまとめる力
ここでは、コミュニケーション能力を「チームの意見をまとめる力」という力に言い換えてアピールする文章を紹介しています。
就活生が自己PRを書く際、自分がどう行動したのか、どのように課題を解決したのかを具体的に示すことが重要です。
| 【結論】 私は部活動での経験を通じて、チームメンバー間の意見調整やまとめ役としてのコミュニケーション能力を高めました。 |
| 添削コメント|「この力を貴社でも活かし」の表現が抽象的で、どのように貢献できるかが不明確です。具体的に「意見交換を促進し、プロジェクトをスムーズに進行させる」とすることで、実際にどのように活かすかがより明確になっています。 |
| 【エピソード】 大学の部活動で、日常的な練習や活動方針を決める際に、メンバー間で意見が対立する場面がありました。練習内容やスケジュールの進行方法について、メンバーごとに異なる考えを持っており、 |
| 添削コメント|「話し合いが進まないことがありました」という表現は問題の本質を十分に伝えていません。より具体的に「議論が進まない状況」とすることで、問題が明確になり、読者に具体的な状況を伝えることができます。 |
| 【エピソード詳細】 その際、私はまずメンバー全員にそれぞれの意見をしっかりと聞き、その内容を整理してみんなに共有しました。各人が重視している点を理解し、問題となっている部分を明確にした上で、妥協案を提案しました。また、全員が納得できるように、それぞれの意見をどのように反映させるかを丁寧に説明し、意見交換を重ねました。 |
| 添削コメント|「妥協案を提案」のみではどのように全員の意見を反映させるのか、全員の意見を尊重できているのかが不明瞭です。そのため、意見反映の方法を具体的に追加しました。 |
| 【成果】 その結果、チーム全員が納得し、練習や活動がスムーズに進むようになりました。 |
| 添削コメント|「メンバー間のコミュニケーションが円滑になり」という表現もやや抽象的で、どのように改善されたのかが不明確です。「意見交換が活発になり、計画的な練習が進行した」という成果を示すことで、行動の具体性が増し、成果がより説得力を持ちます。 |
| 【入社後】 この経験を活かし、貴社のチームでも意見の調整や協力を引き出す役割を果たしたいと考えています。特に、 |
| 添削コメント|「チームメンバーの意見を尊重し、円滑に進行できるようサポートする力を発揮できると確信しています」という部分は抽象的で、実際にどのように円滑に進行させるのか、行動を述べることで、企業に対してより現実的で説得力のあるイメージを提供できます。 |
【NGポイント】
この例文では、結論部分が抽象的であり、企業が求める具体的な貢献が不明確でした。また、エピソード詳細では、問題解決に至る過程がわかりにくく、成果部分も抽象的であったため、説得力に欠けています。
【添削内容】
結論部分では、具体的な行動とその成果を示し、企業側が求める貢献を明確にしました。エピソード詳細では、実際に行動した具体的な内容を明示し、問題解決の過程を強調しました。
【どう変わった?】
結論部分が具体化され、企業が求める貢献が明確になりました。エピソード詳細に具体的な行動が追加され、どのように解決したのかを読者が理解しやすくなりました。成果部分も具体化されています。
| ・行動の過程や背景を述べる ・問題解決の過程を具体的に示す ・成果を具体的に述べ、企業にどのように貢献できるかを伝える |
⑨相手の話を聞き要点を押さえる力
この例文は「コミュニケーション能力」の中でも、相手の意見を傾聴してすり合わせる力を「調整力」と言い換えてアピールしています。
自己PRを作成する際は、強み→行動→成果→再現性の流れを意識し、抽象語を具体的行動と言い換えて説得力を高めましょう。
| 【結論】 私は、相手の声に耳を傾け要点を分かりやすくまとめ直す「調整力」を強みとして、 |
| 添削コメント|「チームの意思疎通を滑らかにします」は成果が曖昧です。意見の相違を整理し合意形成まで導けると示すことで、採用担当が業務での活用シーンを即座に想像できる具体性を付与しました。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ発表準備で十名のメンバーがそれぞれ異なる視点を持ち、 |
| 添削コメント|停滞時間だけでは課題の深さが伝わりません。対立状況を提示して危機感を醸成することで、傾聴力が必要とされる背景と自分の介入価値を際立たせ、読者に強みの必然性を示しました。 |
| 【エピソード詳細】 私はまず全員の主張をノートに書き取り、重複点と対立点を色分けしてホワイトボードに可視化しました。 |
| 添削コメント|目的再定義と納得取得を追記し、行動を時系列で示しました。対立点の整理から合意形成までのプロセスを描き、強みがどのように成果に結びついたかを説明しています。 |
| 【成果】 結果として討議時間を予定より三割短縮し、 |
| 添削コメント|賞の記述は過程の評価ではないため削除し、質疑応答対応と一体感の形成という具体的成果に置き換えることで、第三者が評価しやすい客観的指標と周囲の声を両立させ、説得力を高めました。 |
| 【入社後】 入社後は、部署や立場の異なる人同士の意見を整理し、共通認識を築く調整役として、 |
| 添削コメント|抽象的な「判断を迅速化」を、ズレ防止→短期合意→生産性向上の流れに変換しました。学生経験と業務成果が直結する構造を示し、入社後の再現性と即戦力性を明確にしています。 |
【NGポイント】
抽象語が多く課題の深刻度や成果の因果が曖昧でした。主体を示す動詞も弱く、賞の記述と本人の貢献が直結していなかったため、採用担当が強みを評価しづらかったです。
【添削内容】
抽象語を具体行動へ置換し、課題―行動―成果の因果を一本線で結ぶよう修正しました。目的再定義や納得感の醸成など主体的プロセスを追加し、質疑応答対応など直接効果を提示して客観性を強化しました。
【どう変わった?】
強みが「調整力」として鮮明になり、業務内での活用イメージを描きやすくなりました。行動の具体性と成果の客観性が向上し、読後に抱く信頼感と納得感が大幅に高まったと評価されるでしょう。
| ・行動は5W1Hで詳しく述べる ・抽象語は成果と紐付けする ・強みを明示する |
⑩関係を構築し維持する力
本例文は、チーム全体の課題を目的共有とフォローによって打開し、信頼を築いた流れを示しています。
自己PRでは課題・行動・成果を定量と評価主体で結び、関係性を構築するまでの過程を具体的に説明できると説得力が高まるでしょう。
| 【結論】 私は、関係を構築し維持する力を強みとしています。 |
| 添削コメント|抽象的な「臆せず歩み寄る」を削り目的共有と傾聴で信頼構築する行動プロセスを提示。再現性と成果イメージが明確になり企業は職場適用を具体的に想像できます。 |
| 【エピソード】 大学2年次に、学外の学生団体のプロジェクトに参加した際、他大学メンバーとの意思疎通が取れず、 |
| 添削コメント|課題を孤立からプロジェクト停滞という具体的リスクに置換し背景を明確化。採用側は状況判断力と主体的な問題解決姿勢を読み取りやすくなります。 |
| 【エピソード詳細】 そこで私は、週1回の定例ミーティング後に |
| 添削コメント|誰に何を行ったかを5W1Hで補強しフォロー面談と広報タスク可視化を追加。量的指標と手段が明確になり強みの再現性と説得力が向上しました。 |
| 【成果】 その結果、他大学メンバーとも密な連携が取れるようになり、 |
| 添削コメント|成果に推薦者と動員数を付加し評価主体と数値で客観性を担保。結果のインパクトが具体化され企業が貢献度を定量的に把握できます。 |
| 【入社後】 今後も、環境に左右されず |
| 添削コメント|抽象的な姿勢表現を行動に置換し目的提示→傾聴→共有のプロセスを明示。企業は入社後の再現シーンを具体的に連想でき強みが即戦力として評価されます。 |
【NGポイント】
当初は「臆せず歩み寄る」「孤立しかけた」など主観的語句が多く状況と課題が曖昧でした。また成果を事実のみで示し数値が不足したため客観性に欠け、行動と効果の結び付きが読み手に伝わりにくかったでしょう。
【添削内容】
課題を企画停滞と具体化しフォロー面談や広報タスク引受けなど行動を5W1Hで補強しました。成果には教授と代表者の推薦、450人動員という数値を追加し客観性を確保しました。
【どう変わった?】
強みが「信頼を築く力」として可視化され企業は初対面の顧客とも短期間で関係を構築する姿を具体的に想像できます。成果の信頼性が高まり、読み手の負担が減って印象が向上しました。
| 課題と目標を可視化させる ・行動を数値で定量的に提示する ・成果も客観的に証明する |
⑪素直に報告する力
本例文は「素直に報告する力」という言い換えでコミュニケーション能力を示した事例です。
自己PRでは強みを先に示し、行動と成果を数値で結び付けると説得力が増します。また強みを活かした入社後の活躍を記載することを忘れないでください。
| 【結論】 私の強みは、 |
| 添削コメント|抽象語の並置では再現性が伝わらないため「コミュニケーション能力」の言い換えとして「素直に報告する力」を明示し、即時共有という具体行動を示すことで採用担当が活用場面を想像しやすい表現に改善しました。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、10名のメンバーと地域活性化の提案を行った際、 |
| 添削コメント|失敗の事実だけではマイナスが強調されるため「不足を発見し共有した主体行動」に置き換え、強みがポジティブに発揮された場面を前面に押し出しました。 |
| 【エピソード詳細】 スケジュールを |
| 添削コメント|5W1Hを補強して「いつ・何を・どうしたか」を具体化し、自ら進行管理を担った行動を追加することで主体性と協働力の両方を詳細に示しました。 |
| 【成果】 失敗を隠さず、早期に共有したことで信頼関係を損なうことなく、 |
| 添削コメント|「対応力向上」は定性的で伝わりづらいため、時間短縮と納期厳守の定量成果を提示し、誰が見てもインパクトが把握できるように修正しました。 |
| 【入社後】 入社後も、些細なミスや違和感を見逃さず、素直に共有しチームの成果に貢献できるよう努めます。 |
| 添削コメント|抽象的な抱負を具体施策へ落とし込み、強みの再現性と企業での価値創出が明確にイメージできる内容へ仕上げました。 |
【NGポイント】
当初は強みが抽象的で、主体行動よりミス描写が長く、成果も定性的だったため強みが伝わりにくかったです。また、入社後の活躍が目的のみとなっており、数値などが含まれておらず説得力が弱かったです。
【添削内容】
強みを「素直に報告する力」と再定義し遅延発見→共有→再分担→納期遵守の流れを明示しました。半日短縮という数値を追加し入社後は日次共有と遅延ゼロ目標を掲げ、活躍を具体化させています。
【どう変わった?】
強みと行動が直感的に理解でき成果を数値で示したことで客観性が向上しました。課題発見から解決までのプロセスが具体化され主体性と協働性がバランス良く伝わる構成になりましたね。
| ・強みを端的に提示する ・行動→成果を時系列で描こう ・入社後は手法と数値目標を明確にする |
⑫解決策を提案する力
今回の例文は、コミュニケーション能力を「解決策を提案する力」と言い換え、課題整理から合意形成までのプロセスを具体化した自己PRです。
強み→行動→成果→入社後を一直線で示し、読み手が場面を想像できるよう人数や役割も数字で補足すると評価が高まりやすいでしょう。
| 【結論】 私は、相手の立場を理解しながら状況を整理し、円滑な対話を通じて |
| 添削コメント|強みをコミュニケーション力と明示し、「課題整理→最適解導出」というプロセスを示して抽象度を下げたことで、採用担当が能力の中身を即座に把握できる構成になっています。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ活動では、グループで地域課題の解決策を提案するプロジェクトに |
| 添削コメント|人数とリーダー役を補足し「誰が」「何をしたか」を具体化したことで、場面が想像しやすくリーダーシップも伝わります。 |
| 【エピソード詳細】 意見の対立が続いた際、私は各メンバーの主張を丁寧に聞き取った上で、 |
| 添削コメント|行動を「視覚化→比較→合意形成」の3段階で示し、5W1Hを充足させたことで強みを発揮したプロセスが一連の流れで伝わります。 |
| 【成果】 その結果、プロジェクトは無事に完遂し、 |
| 添削コメント|評価者と評価ポイントを明示し、定性的な「高評価」を定量的な「最優秀賞」に置き換えたことで成果の客観性とインパクトが向上しています。 |
| 【入社後】 貴社でも、チームやクライアントとの対話を重視し、 |
| 添削コメント|重複表現を削除し課題分解フレームを提示することで、解決策を提案する力=コミュニケーション能力というテーマを再強調し、入社後の再現性を示しました。 |
【NGポイント】
強みの定義が抽象的で読者が能力の具体像を掴みにくく、行動も「呼びかけた」「まとめた」に終始していたため具体策が不足していました。また成果は高評価とだけ示され評価者や指標が不明で客観性を欠いています。
【添削内容】
強みを課題整理→合意形成まで言語化し、8名チームや比較表・ホワイトボードなど具体的な手段を追加しました。成果も「自治体職員から実装可能性を評価され最優秀賞」と定量化しています。
【どう変わった?】
能力の具体像が数値と手段で可視化されたことで採用担当は実務での再現可能性を判断しやすくなりました。評価者や賞の情報で成果の信頼性が高まり、が対立を整理し建設的な合意を導く人材と伝わります。
| ・強みは行動プロセスで具体的に示す ・成果は評価者と指標を数字で補足する ・入社後の活躍をプロセスで言及する |
⑬その場の雰囲気に順応する力
ここでは、大学祭の窓口対応を通じて得た状況把握と声掛けを強みとして紹介しています。
自己PRでは、抽象になりがちなコミュニケーション能力を過程を明示することで具体化しましょう。特に「誰に何をどうしたか」を数値と合わせて示してください。
| 【結論】 私の強みは |
| 添削コメント|抽象語を行動に置換し「状況把握→声かけ→意見引き出し」を示すことで再現性と評価基準を明確化し、強み「コミュニケーション能力×その場適応力」を採用側に具体的に伝えています。 |
| 【エピソード】 大学祭実行委員として来場者対応窓口を担当した際、 |
| 添削コメント|件数・対象・担当人数を数値で示し負荷の高さと主体性を可視化。数字は仕事規模に換算しやすく採用側が「自社顧客対応でも発揮できる強み」と判断しやすくなります。 |
| 【エピソード詳細】 初対面の相手には |
| 添削コメント|「誰に何をどうしたか」を明確化し、成果を20%短縮と数値化しました。行動―成果の因果を隣接させることで論理の飛躍がなく、面接で深掘りされても説得力を維持できます。 |
| 【成果】 一日で対応した問い合わせのうち苦情はゼロで、アンケート満足度は |
| 添削コメント|前年比のみで母数不明だった点を絶対値へ修正し信頼性を向上させています。数字と具体役割をセットにすることで成果の大きさを客観的に示し、リーダーシップや後輩育成力も同時にアピールできています。 |
| 【入社後】 貴社でも、部署や顧客ごとの |
| 添削コメント|抽象的な抱負を「観察→場づくり→スケジュール遵守」の流れへ具体化し、効果測定の軸を提示。採用側が成果を定量想起できるため、テーマ「その場の雰囲気に順応する力」を企業内でどう活かすかのイメージが鮮明になります。 |
【NGポイント】
当初は強みが抽象的で「雰囲気に順応」といった結果表現に終始し、行動と成果の因果が不明瞭でした。また数値や役割規模が曖昧で採用側が再現性を測れず、入社後の活躍像を描きにくかった点も問題です。
【添削内容】
抽象語を動作レベルへ置換し、5W1Hで行動を描写しました。問い合わせ件数や待ち時間短縮率など具体数値を挿入して成果の客観性を高め、新入委員研修の実績を加えて育成力も示しています。
【どう変わった?】
強みの発揮プロセスと効果を定量的に示したことで、配属や顧客層が変わっても再現可能なスキルだと評価されやすくなりました。主体性・改善意識・影響範囲が明瞭となり、選考上の説得力が向上していますね。
| ・具体的な行動を提示する ・成果は数値で裏付ける ・入社後の活躍を示す |
⑭協調性を持ってチームプレイを推進する力
本例文は、部活中のトラブルに適切に対処し、チームワークを維持した経験から、コミュニケーション力=協調性によってチームを支える力をアピールしたものです。
強み→行動→成果→活かし方を一貫させると自己PRの説得力が高まるため、協調性の伝え方を工夫しましょう。
| 【結論】 私は、 |
| 添削コメント|冒頭の「互いの意見や状況を踏まえながら」は抽象的で強みがぼやけます。「多様な意見を整理して共通目標を描く」と置き換えることで「協調性」と「調整力」という強みを発揮できることを強調し、採用担当に強みを端的に伝えました。 |
| 【エピソード】 所属していたバスケットボール部では、3年時に副キャプテンを務めました。夏の大会前、 |
| 添削コメント|人数と具体的状況を明示し課題の深刻度を可視化、さらに士気低下を部員の発言で示すことでリアリティが向上し、採用担当がどんな困難だったかを瞬時に理解できます。 |
| 【エピソード詳細】 私は練習後に個別に話を聞き、悩みや不安を共有する場を設けました。 |
| 添削コメント|副キャプテンとして実行可能な施策に置き換えました。数値目標→再設計→意識共有という流れが見えるため、行動力と論理性がアピールできます。 |
| 【成果】 結果的に大会ではベスト8入りを果たし、コーチからは「まとまりと粘り強さがあった」と評価されました。 |
| 添削コメント|主観的な感想だけでは再現性が弱いため削除し、アンケート結果で定量化しました。客観指標と第三者評価の両方を示すことで成果の説得力が強まり、採用担当も業務への応用をイメージしやすくなります。 |
| 【入社後】 入社後も、 |
| 添削コメント|状況を把握では行動が見えにくいため、可視化ツール+役割調整を具体化。大学の経験をビジネス環境に転用する方法が示され、協調推進力=コミュニケーション能力の再現性が明確になります。 |
【NGポイント】
強みが「意見や状況を踏まえて動く」程度に留まり、行動も副キャプテンの権限を超える表現が散見され、裏付けが弱かったです。成果も後輩の感想中心で、入社後に強みが発揮できるか、採用担当が想像しにくい内容だったのも課題でした。
【添削内容】
強みを「多様な意見を整理し共通目標を描く力」と再定義し、負傷者数やパス成功率など具体的な数値で課題と行動を提示しました。アンケート結果や第三者評価を加えることで成果の客観性を補強しています。
【どう変わった?】
強み・行動・成果・展望が一本の線で結ばれ、コミュニケーション能力を入社後も発揮できる可能性を強調できています。部活動と同じように組織を動かす姿を具体的に想像できるはずです。
| ・強みは端的に具体化し印象付ける ・行動は数値と過程で明確に示す ・成果は客観性と評価で証明する |
⑮必要な情報を詳細に聞き取る力
大学祭で培った「必要な情報を詳細に聞き取る力」を軸に、抽象的なコミュニケーション能力を具体化した自己PR例です。
冒頭で強みと再現性を示し、5W1Hで行動と成果を結ぶ構成を意識すると説得力が高まります。
| 【結論】 私は「必要な情報を詳細に聞き取る力」を強みに、 |
| 添削コメント|「相手が本当に求めるもの」「雰囲気づくり」といった表現は抽象的で、聞き取る力の具体的行動と結びついていません。強みの核心である「必要な情報を引き出すためにどのような行動を取れるか」を端的に示す必要があります。 |
| 【エピソード】 大学祭の企画チームで |
| 添削コメント|「提案資料の作成」は作業主体の表現で“聞き取る力”がどのように活かされたか不明瞭です。企業担当者と直接ヒアリングした事実を示すことで強みとの関連性が明確になります。 |
| 【エピソード詳細】 初回打ち合わせでは企業の要望が漠然としていたため、目的・ターゲット・期待する効果を一つずつ質問し、相手の発言を要約して確認しながらニーズを明確化しました。 |
| 添削コメント|「質問→要約→確認」という流れで行動が具体的に示され、“聞き取る力”が発揮されたことが伝わります。一方「感謝の言葉」は主観的で成果として弱いため削除し、強みが活かされたことを明示しました。 |
| 【成果】 整理した要望をもとに企画案を改善し、前年比150%の協賛金を獲得 |
| 添削コメント|協賛金として表した成果だけだと、学園祭の来場者にどのような影響を与えられたのかが伝わりにくかったため、アンケートを用いて「聞き取る力」が顧客の満足につながったことを示しました。 |
| 【入社後】 御社でもヒアリング力を活かし、顧客の潜在課題を掘り起こして |
| 添削コメント|「最適なソリューション」「売上拡大」は抽象度が高いため、入社後の具体的な行動例(例:定期的なヒアリングシート作成→提案改善)を示すと再現性が高まり、企業が期待する将来像を描きやすくなります。 |
【NGポイント】
抽象表現が多く強みを裏付ける行動・数値が不足し説得力に欠けていました。成果と行動の因果が曖昧で冗長な情報も散見され読み手の集中が切れがちでした。また入社後の記述が一般論に終始しています。
【添削内容】
抽象語や冗長データに取り消し線を入れ、質問→要約→確認という具体プロセスと協賛金150%という定量成果を残しました。入社後はヒアリングシート作成→提案改善の手順を例示し、貢献イメージを補強しています。
【どう変わった?】
強み・行動・成果・再現の流れが一本化され、採用担当者は聞き取り力が売上成長へ直結する姿を即座に想像できます。数値で裏付けたことで信頼度が増し、要点が端的に伝わり読みやすさも向上したでしょう。
| ・強みは動作で端的に示す ・行動と成果を数値で表す ・入社後の活躍を詳細に記載する |
⑯積極的に発言をする力
この例文では、大学ボランティアの状況を用いて『積極的に発言する力』を強みとしてアピールしています。
結論で強みを明示し、5W1Hを押さえた行動と成果、入社後の積極的に発言する力の活用まで流れるように示すと説得力が高まるでしょう。
| 【結論】 私の強みは、 |
| 添削コメント|抽象語と重複語を削り「どんな場面でも」「建設的に進行」と具体化、さらに言い換えキーワード「対話推進」を残し独自性を担保することで、再現性と即戦力性が一文で伝わる構成にしました。 |
| 【エピソード】 大学の地域清掃ボランティアに参加した際、初対面同士の集まりで |
| 添削コメント|冗長な語句を整理し課題に焦点を当てたことで、「発言する力」が求められる必然性を瞬時に示し、読者の共感と検索ニーズ「言い換えで課題提示」の両方に応えています。 |
| 【エピソード詳細】 私は |
| 添削コメント|「いつ」「何を」したかを時刻と動詞で補完し台詞を行動描写へ置換しました。行動→結果の因果を明示したため、主導性が可視化され、短く言い換えるコツの実演にもなっています。 |
| 【成果】 活動後には運営スタッフの方から |
| 添削コメント|主観的な称賛を具体コメント+次回指名という客観事実に置換し、数字を付すことで成果を定量化しました。。面接官が評価しやすい指標を示し、成果の書き方見本として記事全体の網羅性を高めました。 |
| 【入社後】 貴社でも、会議や現場で発言を恐れず自分の意見や気づきを発信し、周囲の意見を引き出すことで、 |
| 添削コメント|願望表現を「議事可視化」「30%短縮」という定量目標付きアクションへ変換し、強みが現場でどう機能するかを具体化。企業ニーズとの橋渡しを明確にし検索意図「活かし方」にも応えています。 |
【NGポイント】
抽象語が多く行動がぼやけ、成果も主観的賛辞のみで定量性に欠けたため信頼性を損ねていました。また入社後の記述が願望止まりで再現性を示せなかった点も評価を下げる要因となっていました。
【添削内容】
抽象語を具体語へ置換し行動に時刻と頻度を追加、5W1Hを充実させました。さらに成果に「次回30名規模イベントの指名」を追記し客観データ化。入社後は議事可視化と30%短縮という定量目標を設定しました。
【どう変わった?】
強み・行動・成果・再現性が一本で結ばれ、面接官が職場での活用を具体的にイメージしやすくなりました。数値入りで成果規模が可視化されたことで信ぴょう性が高まり、即戦力という印象が強化されています。
| ・数字で成果規模を具体的明快に示す ・行動を過程と共に示す ・入社後の貢献を定量で示す |
コミュニケーション能力を面接で伝えるポイント

次に、面接で伝える際のポイントを紹介します。以下の4点を押さえましょう。
- 言い換えた表現を使う
- PREP法を用いる
- エピソードも交えて伝える
- どのように仕事で活かせるかまで伝える
①言い換えた表現を使う
面接でこそ必ず言い換え表現を用いるようにしましょう。
面接ではESのように書き直しができないため、言い換え表現を一層意識していないと同じことを何度も言うことになってしまいかねません。
ESの段階で自分のコミュニケーション能力を具体化し、言い換えができていればある程度対応できますが、パターンが少ないです。
面接では数十分間の会話になるため、同じワードの多用がないようにいくつかの言い換えパターンを準備しておくと安心できます。
②PREP法を用いる
コミュニケーション能力を面接で伝える際は、話の構成に気をつけることが大切です。綺麗にまとまる話の構成には型があります。
結論を冒頭と締めに持ってくるPREP法を用いることで要点が明確になり、わかりやすいです。
PREP法とは、結論(Point)、理由(Reason)、具体例(Example)、再度の結論(Point)の順に話を組み立てる方法です。
内容が整理され、伝えたいメッセージが簡潔かつわかりやすく伝わります。
③エピソードも交えて伝える
意思疎通の面で優れるだけでは、あなたの魅力を十分に伝えることは難しいでしょう。
魅力的な自己PRを作るには、コミュニケーション能力をどのように活かして課題を乗り越えたのかを、具体的なエピソードを交えて説明することが重要です。
自己PRでは、そのスキルが実際に備わっており、業務に活かせることを採用担当者に納得してもらう必要があります。
そのため、エピソードを選ぶ際には、「いかに自分の能力や長所を説得力のある形で示せるか」を意識しましょう。
④どのように仕事で活かせるかまで伝える
採用担当者は、あなたが実際に仕事でどのような貢献ができるか、またどのように働きたいのかを知りたがっています。
そのため、自己PRでは自分の強みを企業でどのように活かせるかを具体的にアピールすることが重要です。
応募する企業や職種において、あなたのコミュニケーション能力がどのように役立つかを考え自己PRに反映することで、入社後のイメージが湧きやすくなります。
コミュニケーション能力を強み・長所とする際の注意点

ここまでの内容を踏まえるだけでなく、以下の点にも注意をしましょう。
- 「コミュニケーション能力」はできる限り使わない
- 面接での受け答えで矛盾が生じないようにする
- 外交的かどうかは関係がない
①「コミュニケーション能力」はできる限り使わない
「コミュニケーション能力」という言葉は非常に曖昧で広義です。より一層具体的な表現に言い換えないと、企業から準備不足と見なされる可能性があります。
言い換えの際には、まず自分の言葉で「コミュニケーション能力」とは具体的にどのような強みであるかを考えてみましょう。
例えば、相手の意見をしっかりと聴き取る力、わかりやすく伝える力、円滑なチームワークを促進する力など、具体的な要素に分解してみることが重要です。
当てはまるものが見つかったら、代わりに使うと良いでしょう。
②面接での受け答えで矛盾が生じないようにする
コミュニケーション能力の高さをいくら書類選考の段階で伝えたとしても、実際の面接でその能力を発揮できなければ意味がありません。
面接の際には、まず面接官の目をしっかりと見る、適度にあいづちを打つといった基本的な礼儀を守ることが大切です。
質問に答える際は、「何を知りたいのか」を考え、意図を理解した上で回答を組み立てると良いでしょう。
非言語的な部分も含めて面接官との会話が円滑かつムードよく進めば、あなたのコミュニケーション能力が証明できます。
③外交的かどうかは関係がない
「外交的=コミュニケーション能力が高い」という認識は必ずしも正しいわけではありません。双方向のコミュニケーションができていない場合があるからです。
相手の話を聞かずに一方的に話し続けたり、相手の感情や状況を無視して発言するようでは、当然高評価に繋がりません。
重要なのは、相手の話を理解し、適切に反応する能力です。
内向的な性格や人見知りの人でも、相手の気持ちを察するスキルが高く、効果的なコミュニケーションを図る能力を持っている場合があります。
コミュニケーション能力は上手に言い換えてアピールすることが重要
「コミュニケーション能力」は広範かつ曖昧な表現です。そのため言い換え表現を上手に使い、具体化しながら伝えるようにしましょう。
書類・面接の両方で、自分のコミュニケーション能力に最もマッチした表現を用い、明確に伝わる内容にすることが重要です。
この記事を参考に、コミュニケーション能力が効果的に伝わる自己PRを作成してみてください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










