ゼミは自己PRに使える!最強の自己PRの書き方から注意点まで解説
「ゼミで勉強したことって自己PRになるの?」
ゼミで頑張っていることを自己PRにしたいけど使って大丈夫かなと不安になりますよね。
この記事では、ゼミでの経験を自己PRに使う方法を徹底解説しています。入りたいゼミの選考に通過するために、アピール法を理解して、ゼミでの経験から最強の自己PRを作り上げましょう!
自己PRをすぐに作れる便利アイテム
- 1自己PR自動作成ツール
- 最短3分!受かる自己PRを、AIが自動で作成
- 2ES自動作成ツール
- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

記事の監修者
記事の監修者
人事 鈴木
新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る企業が自己PRで見ている3つのポイント

まずは企業が自己PRで何を見ているのかを確認するところから始めましょう。
企業が学生の自己PRを通じて確認しているのは、主に以下の3つのポイントです。
それぞれ詳しく解説していきます。
①志望者の人間性
企業がまず重視しているのは、志望者の人間性です。
自己PRからは、自己紹介と同じくらい志望者がどのような性格で、どのような価値観を持っているのかがわかります。
自己PRを通じて、企業は志望者という人間そのものを理解しようとしているのです。
②志望者の強み
また自己PRでは志望者がどのような強みを持っているのかも確認しています。
自己PRには、志望者が強く自覚している自分の長所が書かれるはずなので、そこからその人の強みを知ろうとしています。
そのため、自己PRに書く強みは、その企業に合ったものをアピールするのがおすすめですよ。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
③志望者と企業のマッチ度合い
最後に、企業は自己PRから志望者と企業がどのくらい相性がいいのかも判断しようとしています。
前述の通り、自己PRには性格や強みが現れ、その人自身を理解するのにうってつけの情報が載っているのです。
そのため、志望者自身が企業が求める人材に近いのかどうか、自己PRを通じて企業は確認しています。
また、企業とのマッチ度の高さを示すには、企業分析を深めておくことが必須です。こちらの記事で企業研究のやり方や情報の集め方についてより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
ゼミでの経験を自己PRにつなげる手順3STEP

企業が自己PRの何を見ているのかがわかったところで、ここからはゼミの経験を自己PRに繋げる方法を紹介します。
ゼミでの経験を自己PRにするには以下の3STEPに沿って進めていきましょう。
それぞれ詳しく見ていきますね。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
①ゼミへの志望動機を言語化する
まずは自分がどのような動機でゼミに入ったのか、志望動機を言語化してみましょう。
志望動機の中には自分の興味関心や強みが現れているので、自己PRに活かしやすくなります。
自分がどんなことに興味があり、どのような強みを活かしたくてゼミに入ったのかを思い出すことがおすすめですよ。
②ゼミと企業の志望動機の共通点を見つける
ゼミの志望動機が言語化できたら、次は企業への志望動機と照らし合わせてみましょう。
ゼミと企業双方で、持っている興味関心や活かしたい強みで同じものを探していくのがポイント。
ゼミと企業への志望動機に共通点があれば、それが自己PRに活かせる内容になります。
③具体的なゼミでのエピソードを書き出す
最後に、ゼミと企業への志望動機の共通点をゼミでの具体的なエピソードに落とし込んでいきましょう。
企業で活かせる強みや興味関心が現れている実際のエピソードを思い出すことがポイント。
ゼミで活かした強みを企業でも活かせるというメッセージが伝わるので、この書き方がおすすめになりますよ。
また、「ゼミ活動で自己PRを書きたいけど、具体的なエピソードが出てこない……」という方は以下の記事も読んでみてください。エピソードが無いと感じる原因はいくつかあるので、対処法と併せて確認してみましょう。
【自己PR】ゼミ活動の経験から得られる強み5選

ここまで、ゼミでの経験をガクチカに書き上げる方法を解説してきました。
ここからは、具体的にどのような強みをアピールすればいいのか、おすすめを5つ紹介していきます。
それぞれ詳しく解説していきますね。
①探究心
まずおすすめのアピールポイントとしては、探究心が挙げられます。
ゼミ活動は大学生活のなかでも最も力を入れる勉強になることが多く、新たな知識を主体的に学ぶ機会です。
企業に入ってからもさまざまなことを学ぼうとする探究心をアピールできれば、その主体性を高く評価してもらえますよ。
②リーダーシップ
次におすすめのアピールポイントとしては、リーダーシップが挙げられます。
ゼミ活動では自分1人ではなく少人数のグループで研究に取り組むことが基本です。
また企業に入ってからも、ほとんどの企業では社内外の人間と関わりながら仕事をすることになるでしょう。
集団で活動する際に自分がリーダーシップを持って引っ張った経験があれば、企業に入ってからも活躍する見込みが高いと評価されますよ。
リーダーシップをアピールするコツについては、以下の記事でも解説しています。「企業が求めるリーダーシップ」の種類など、自己PR作成に活用できる情報が多く紹介されているので、ぜひ読んでみてください。
③図太さ
ゼミ経験から考えられるアピールポイントとしては、性格の図太さや大胆さも挙げられるでしょう。
ゼミ活動ではプレゼンテーションをする機会が多く、人前で話したり議論したりするときに堂々とする必要があります。
これは社会に出てからも同じで、自分の意見を社内外の人間に自信を持って伝える機会が増えるでしょう。
自分の意見をしっかり持って発言できる姿勢は、どの企業においても重要な能力ですよ。
④課題解決能力
ゼミでの活動を通じて課題解決能力を発揮したという経験も、大きなアピールポイントです。
ゼミ活動では、論文執筆やディスカッションなどの研究活動を通じて、ロジカルシンキングを多用しますよね。
目の前の問題に対して論理的に解を導き出すことは社会に出てからも当然重要な能力なので、面接官からも期待されやすいですよ。
⑤根気強さ
ゼミを通じて、粘り強い根気強さを発揮した経験がある人は、それもしっかりアピールしていきましょう。
ゼミの研究は楽しいことばかりでなく、ときには辛い時期を乗り越える必要もあるでしょう。
社会に出て企業で働き出してからも辛い時期は必ず訪れます。
そのときに粘り強く仕事をやり抜けると評価されれば、面接官からはかなり好印象をもらえますよ。
ゼミでの経験から自己PRを作る時のおすすめ4段階構成
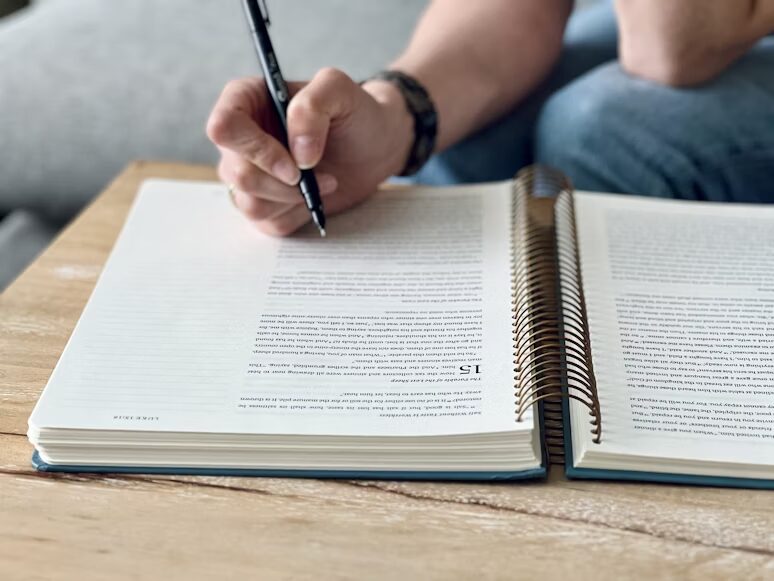
自分のアピールしたい強みが定まれば、実際に自己PRを書き上げてみましょう。
自己PRを文章にするときには以下の4段階の構成に従って書くのがおすすめですよ。
各ステップごとに解説していきますね。
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
①結論|自分のアピールしたい強みを言い切る
自己PRを書く際には、まずは自分のアピールしたい強みをはっきりと冒頭で言い切りましょう。
これからどんな強みについての話が始まるのか、文章のテーマが聞き手に伝わるので、文章全体を理解しやすくなります。
また、自己PRを伝える側としても、最初にテーマを言い切ることで頭が整理されるのでおすすめですよ。
とはいえ、そもそもアピールする強みが定まっていないという方は、こちらの記事を参考に自己分析を行ってみましょう。見つける方法や強みの例も、ぜひチェックしてみてくださいね。
②背景|ゼミでの活動・勉強内容などの背景情報を説明する
自己PRのテーマを言い切ったら次は自己PRの背景となる情報を説明していきましょう。
冒頭から突然自分の強みを伝えられても、聞き手としては、信憑性もなければ状況もよくわかりません。
自分の強みがどういう環境でどのように表れていたのかを理解するのに必要な情報を伝えていきましょう。
③具体例|特に自分の強みが表れた経験を話す
背景情報まで伝えられたら、実際に自分の強みが表れた具体的なエピソードを話していきましょう。
いくら自分の強みをアピールしたくても、エピソードがなければ具体的なイメージが湧かず、面接官には伝わりません。
臨場感を持ってエピソードを伝えることで、自分の強みをよりはっきりと面接官に理解してもらえますよ。
④結果|エピソードから得た強みを再度説明
具体的なエピソードまで伝えられたら、最後にもう一度自分が伝えたかった強みを言いましょう。
具体的なエピソードを言って自己PRを終えてしまうと、面接官としては結局何が言いたかったのかよくわからなくなります。
自己PRの最初と最後を端的な言葉で言い切ることで面接官に強い印象を残せますよ。
エピソード別|ゼミで身につく強みの自己PRの例文8選

自己PRの構成について理解できたところで、ゼミ経験を基にした実際の自己PRの例文を見てみましょう。
ここでは、自己PRで有効な強みごとに8つの例文を紹介していきますね。
- 活動の中で身につけた専門性の高さ
- 活動の中で発揮したリーダーシップ
- 人前で話すプレゼン力
- 研究論文や学会で高い評価を得た継続力
- 研究を通じて困難を乗り越えた課題解決力
- 新たな視点で糸口を見つけた洞察力
- チームで成果を出したマネジメント力
- 活動に積極的に参加した主体性
それぞれ見ていきましょう。
また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①活動の中で身につけた専門性の高さ
ここでは経済データ分析力を軸とした自己PRを添削しています。
ゼミならではの学んだことをアピールする際に、自身の学びの専門性の高さは十分にアピールポイントになります。注意点としては、専門性の高さそのものの自己PRでとどまらず、専門性をそこまで高められた方法や過程をメインに伝える意識を持ちましょう。
| 【結論】 私はゼミ活動を通して、 |
| 添削コメント|修正前は「情報を的確に整理し、論理的に伝える力」とやや抽象的な表現にとどまっていたため、強みの内容が漠然としていました。修正後では「経済データを専門的に分析し、論理的に提案へ落とし込む力」と具体的かつ専門性の高い内容に言い換えられており、実務への応用イメージが明確になっています。 |
| 【エピソード】 経済学ゼミに所属し、「地域経済の活性化」をテーマに、地元商店街の実態調査と地元事業者のヒアリングを行い、 |
| 添削コメント|修正前は「調査・ヒアリング」の記述に留まり、具体的な手法が不明確なため、強みの裏付けに乏しい印象がありました。修正後では「回帰分析」「SWOT分析」といった統計手法が明示され、データに基づいた分析力が伝わりやすくなっています。その結果、企業は実践的な課題解決力や再現性の高いスキルとして評価しやすくなります。 |
| 【エピソード詳細】 活動の中では、統計データの収集や現地での聞き取り調査、アンケートの設計・実施などを担当しました。 |
| 添削コメント|修正前は「課題に取り組んだ姿勢」が中心で、具体的な行動や使用ツールが見えづらく、強みの再現性が伝わりにくい内容でした。修正後は「統計ソフトRの活用」「視覚資料の工夫」「リハーサルの繰り返し」といった実践的なプロセスが追加され、課題解決への具体的なアプローチが明確になっています。その結果、企業は応募者のスキルが実務でも再現可能であると評価しやすくなります。 |
| 【成果】 その結果、学内発表会では「構成が分かりやすく、提案に説得力がある」と高評価をいただきました。 |
| 添削コメント|修正前は「自信を持てた」という主観的な表現が中心で、成果の根拠が不明確でした。修正後では「学内2位」や「審査員からの評価」といった客観的な実績や第三者のコメントが加わり、成果の信頼性と説得力が高まっています。その結果、企業は実績の再現性や成果の水準を具体的に把握しやすくなります。 |
| 【入社後】 入社後もこの力を活かし、複雑な情報を整理して的確に伝え、 |
| 添削コメント|修正前は「円滑に連携できる存在」といった抽象的な表現が主で、入社後の具体的な活躍イメージが見えづらい内容でした。修正後は「経済指標の分析」から「施策立案」への流れを明示し、強みの実務適用が明確になっています。その結果、企業は応募者のスキルが新規事業への具体的貢献につながると判断しやすくなります。 |
【NGポイント】
当初の強みは「情報整理」と抽象的で、専門性とのつながりが見えにくくなっていました。調査手法が不明確で成果も主観的だったため、企業側が再現性や実力を評価しにくい構成になっていたといえます。また、入社後の貢献内容も「連携」にとどまり、実務への接続が曖昧な印象を与えていました。
【添削内容】
強みを「データ分析と提案力の連携」として定義し、回帰分析やSWOTなどの具体的手法を明記しました。Rでの可視化や指標の抽出といった行動を加えることで、分析プロセスの実践性を高めています。成果については、順位や審査員コメントを用いて定量的に表現し、主観表現を排除しました。入社後の貢献は施策立案へとつなげ、読み手が業務との関連性を自然に想起できるよう整理しています。
【どう変わった?】
強みと行動内容の関係が明確になり、「課題を分析し、提案まで担える人材」としての印象が強まりました。成果に第三者評価と数値的根拠が加わったことで、説得力も向上しています。入社後の役割も具体化され、面接官が再現性を感じやすい内容へと改善されました。
| ・強みは専門性と結び付ける具体用語で示すこと ・成果は数字と第三者評価で可視化し説得力高める ・入社後の活用場面を具体的に描写し再現性示す |
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
②活動の中で発揮したリーダーシップ
ここでは、ゼミ活動での展示企画を題材にリーダーシップを強みに添削し、課題解決プロセスを可視化した就活用自己PR例です。
ポイントとしては、リーダーシップを発揮したことだけではなく、ゼミのグループが何かしら成果を出しているかまで言及しましょう。
| 【結論】私はゼミ活動を通じて、 |
| 添削コメント|修正前は「周囲を巻き込む」という抽象的な表現に留まり、具体的にどのような価値を生み出したかが見えづらい内容でした。修正後では「課題を解決へ導く」まで言及することで、行動の目的と成果が明確になり、リーダーシップの本質が伝わりやすくなっています。ゼミ活動を軸とした記述により、経験の信頼性と一貫性も保たれています。た |
| 【エピソード】所属する経済学ゼミで学園祭の展示企画を任され私が代表を務めましたが、 |
| 添削コメント|修正前は「意見がまとまらない」という抽象的な表現にとどまり、課題の深刻度や背景が伝わりにくい内容でした。修正後では「模擬店かパネル展示かで意見が割れ、テーマ決定が遅延」といった具体的な対立構図と影響が示され、リーダーシップが求められる状況が明確になっています。これにより、強みが発揮された場面としてのリアリティと説得力が高まっています。 |
| 【エピソード詳細】私はまずゼミ生全員の意見を付箋に書き出し共有し、 |
| 添削コメント|修正前は行動の流れや工夫の詳細が見えづらく、リーダーシップの実態が伝わりにくい構成でした。修正後はKJ法や評価表の活用、進捗管理の仕組み、フォロー体制までが段階的に整理され、行動の再現性と合理性が明確になっています。企業側も、自社での業務遂行に重ねて具体的にイメージしやすくなります。 |
| 【成果】その結果、 |
| 添削コメント|修正前は「印象に残った展示」といった主観的な表現にとどまり、成果の規模や反響が伝わりにくい内容でした。修正後では「312名中トップ」といった具体的な数値が加わり、成果の大きさと他者評価の客観性が強調されています。企業にとっても実力の裏付けとして、選考判断の材料になりやすい構成です。 |
| 【入社後】今後はこの経験を活かし、 |
| 添削コメント|修正前は「どのような環境でも協力する」という抽象的な意欲表現にとどまり、入社後の具体的な行動像が描きにくい内容でした。修正後はKJ法やタスクボードの活用といった実践的なフレームを明示し、業務での再現性が高い貢献イメージへと転換されています。企業は実務への応用や初期段階でのリーダーシップ発揮を具体的に想像しやすくなります。 |
【NGポイント】
課題が「意見がまとまらない」など抽象的で、状況の具体性や深刻度が見えづらく、再現性の判断が困難でした。行動も単なる羅列にとどまり、どのような工夫を行ったかが伝わりにくくなっていました。成果には数値的根拠が乏しく、入社後の貢献も曖昧だったため、強みの信頼性や活用可能性が不明確でした。全体の語尾が単調で読みにくく、見出しとの整合性も薄かった点が課題です。
【添削内容】
「未決定による停滞」といった課題の具体化に加え、KJ法やタスクボードなど実際に用いた手法を明示しました。行動は時系列で整理し、リーダーシップのプロセスを可視化。成果は回答数や順位を提示し、定量的な裏付けを加えました。入社後の貢献は具体業務に落とし込み、語尾や語彙も調整することで文章全体のリズムと可読性を高めています。
【どう変わった?】
課題・行動・成果が一貫してつながる構成となり、企業が評価しやすい再現性の高い内容に改善されました。特に数値と手法が組み合わさることで、読み手に行動の実効性が明確に伝わるようになっています。業務への応用イメージも具体化され、選考時の深掘りにも論理的に対応できる自己PRへと昇華されました。文体の緩急も加わり、読後の印象にも残りやすくなっています。
| ・課題→行動→成果の順序を一貫で示すことが鍵 ・手法と数字で再現性提示を明確に述べること ・入社後の活用場面を具体化して説得力強化を |
③人前で話すプレゼン力
この例文は『人前で話すプレゼン力』を強調すべくゼミ発表の課題・行動・成果を数値で補強した添削例です。
プレゼン力のアピールは主観になりがちではあるので、具体的な数字やデータなどを提示することを意識しましょう。
| 【結論】私はゼミ活動を通じて、 |
| 添削コメント|修正前は「人前でわかりやすく伝える」といった抽象的な表現により、スキルの再現性や評価基準が不明確でした。修正後では「聞き手に合わせて要点を伝える」と具体的な行動に言い換えることで、状況適応力や論理的整理力が伝わりやすくなっています。企業側も実務での発揮場面を具体的にイメージしやすくなります。 |
| 【エピソード】所属する経営学ゼミでは、毎月1回、班ごとにテーマを決めて発表を行っていました。私は最終発表で班の代表として、 |
| 添削コメント|修正前は「発表を担当した」という事実の羅列にとどまり、役割の重みや意図が伝わりにくい構成でした。修正後は「来場者数10%増」という数値目標と施策内容が加わり、課題意識と成果を見据えた主体的な行動が明確化されています。企業にとっては、目標設定から実行に至るプロセスを持つ人物として評価しやすくなります。 |
| 【エピソード詳細】もともと人前で話すことに苦手意識があったため、 |
| 添削コメント|修正前は「苦手意識を克服した」という抽象的な描写が中心で、具体的な取り組み内容や工夫が見えづらい状態でした。修正後はリハーサル回数や協力者数を明示し、伝える力を高めるための行動が定量的かつ論理的に整理されています。企業は課題への向き合い方や改善プロセスを通じて、実務での応用力を具体的に想像しやすくなります。 |
| 【成果】発表後には教員から「聞き手を意識した構成と説明が良かった」と評価され、 |
| 添削コメント|修正前は「印象に残った」といった主観的な表現に依拠しており、成果の明確な裏付けに欠けていました。修正後は「30名中30票の投票」や「最優秀発表として表彰」といった具体的な数値と実績が加わり、評価の客観性と成果の重みが強調されています。これにより、企業は他の候補者と比較する際にも判断しやすくなります。 |
| 【入社後】今後はこの経験を活かし、社内外の関係者に対しても、 |
| 添削コメント|修正前は「信頼を築けるビジネスパーソンを目指す」といった抽象的な意欲表現にとどまり、実務での活用イメージが曖昧でした。修正後では「営業提案」「社内プロジェクト説明」など具体的な業務シーンを示し、図示による可視化や合意形成まで踏み込んで表現することで、再現性と即戦力の印象が高まっています。企業にとっては入社後の活躍が明確に想起しやすい構成です。 |
【NGポイント】
初稿では強みが「伝える力」といった抽象表現に留まり、プレゼン内容も事実の羅列に近く、取り組みの工夫や努力量が見えにくくなっていました。成果に数値的根拠がなく、入社後の活用場面も曖昧だったため、企業側が再現性や即戦力としての価値を把握しづらい状態でした。
【添削内容】
課題設定から成果に至る流れを、リハーサル回数やフィードバック人数などの数値で補強し、プロセスの信頼性を高めました。説明手法として視覚資料や専門用語の言い換えも加え、伝達力の工夫が明確になっています。入社後の活用場面は営業・社内説明など実務に即した形で具体化しました。
【どう変わった?】
行動の工夫と成果が数値とエピソードで裏付けられたことで、プレゼンテーション力が実務にも応用可能であると判断しやすくなりました。業務での発揮イメージが明確になり、読み手が「現場で活かせる力」として認識しやすくなっています。全体を通じて説得力と再現性が強化されました。
| ・課題から成果までを具体的な数値で結ぶ ・改善プロセスを行動と回数で具体的に可視化する ・入社後の活用場面を業務シーンで具体化して示す |
④研究論文や学会で高い評価を得た継続力
本例文は「研究論文や学会で高い評価を得た継続力」を題材に、数値と成果を補強し実績信頼性をより明瞭化した添削事例です。
実際に論文や学会での成果が出ているので、その内容をしっかりと伝えましょう。注意点としては、論文や学会の詳しい内容まで記載しようとすると伝わりづらく、制限字数がある場合はオーバーしてしまうので、簡潔にわかりやすく記載する意識を持ちましょう。
| 【結論】私はゼミ活動を通じて、目標に向かって粘り強く取り組む継続力を身につけました。 |
| 添削コメント|結論で強みと獲得経緯を完結に示しており、企業は評価軸を即把握できます。語数も過不足なく、読み手が要点を逃さない構成が好印象です。 |
| 【エピソード】所属する心理学ゼミでは、「SNSと自己肯定感の関係」をテーマに研究を進め、 |
| 添削コメント|修正前は「学会発表を目指した」という目標表現にとどまり、成果や役割の具体性が伝わりづらい構成でした。修正後では「採択・発表」という実績を明示し、さらに調査設計から分析までを一貫してリードしたとすることで、主体性と専門性が強調されています。企業は実務でも主導的に動ける人材としての再現性を具体的に想像しやすくなります。 |
| 【エピソード詳細】研究を進める中で、アンケート回答数が伸びずに分析に十分なデータが集まらないという壁に直面しました。そこで私は質問項目を見直し、SNS利用者が関心を持ちやすい内容へ調整したうえで、 |
| 添削コメント|修正前は「回答が集まらない」「統計ソフトに苦戦した」といった課題の描写にとどまり、対応の工夫や努力量が見えづらい内容でした。修正後では対象者数の拡大手法や学習時間を数値で示し、問題解決に向けた行動が具体化されています。企業にとっては、課題対応力と継続的な努力を備えた人材としての再現性が明確に伝わります。 |
| 【成果】その結果、無事に200件以上の有効回答を集めることができ、分析結果も論理的にまとまり、 |
| 添削コメント|修正前は「優秀賞をいただいた」という成果の記述がやや主観的で、受賞の価値や競争性が伝わりにくい状態でした。修正後では「日本心理学会」「60件中の受賞」といった具体的な名称と数字を加えることで、実績の希少性と評価の高さが客観的に示されています。企業にとっては、他候補と比較可能な成果指標として受け止めやすくなっています。 |
| 【入社後】この経験を通じて得た継続力を、業務の中でも一つひとつ丁寧に向き合い、 |
| 添削コメント|修正前は「継続力を活かしたい」という抽象的な抱負にとどまり、業務への具体的な接続が不明瞭でした。修正後では「データ分析プロジェクトでの仮説検証」や「計画の柔軟な修正」といった実務シーンを明示することで、継続力の発揮場面が具体化されています。企業にとっては、入社後の活躍イメージが自然に想起しやすくなっています。 |
【NGポイント】
研究成果が「学会発表を目指した」と目標止まりで記述されており、努力量も「毎日2時間以上」と曖昧だったため、行動量や成果の裏付けが不足していました。配布方法も「知人に依頼」と受動的で主体性が伝わらず、採用担当は継続力や課題解決力の再現性を判断しにくい状態でした。加えて、入社後の活用場面が抽象的で、企業貢献のイメージにつながりにくくなっていました。
【添削内容】
学会発表を「日本心理学会・学生部門での採択」と具体化し、成果を事実ベースで明示しました。回答数や学習時間は数値で可視化し、1,000人規模の配布拡大施策や60時間の分析学習など、努力量と手法の具体性を補強しています。入社後は仮説検証型プロジェクトでの再現を想定し、貢献可能性を描写。全体を一文ごとに整理し、接続詞や主観語の削減によって論理構造と読みやすさを高めました。
【どう変わった?】
具体的な数値と名称を盛り込んだことで、努力の規模と成果の希少性が明確になり、説得力が飛躍的に高まりました。行動・工夫・結果が因果関係で結ばれたことで再現性が可視化され、選考担当者が業務での活躍を想像しやすくなっています。また、入社後の業務適用シーンが具体化されたことで、面接時の深掘りにも対応しやすい構成に変わり、評価リスクの低下と印象強化の両面で効果が生まれています。
| ・数字と固有名詞で成果を具体化して説得力増 ・努力量は時間・回数で定量提示し実効裏付ける ・入社後の活用場面を具体業務シーンまで明示 |
他にも「継続力」をアピールする自己PR例文を見たい方は、ぜひこちらの記事も読んでみてください。要点を押さえて書くコツや注意点も解説していますよ。
⑤研究を通じて困難を乗り越えた課題解決力
本例文は「⑤研究を通じて困難を乗り越えた課題解決力」を題材に、回答不足を打破する具体策を示した添削済みサンプルです。
研究の際に起きた課題をしっかりと明記し、困難を乗り越えた際の過程もしっかりと伝えましょう。
| 【結論】私は、ゼミ活動で直面した研究の行き詰まりを粘り強く分析し |
| 添削コメント|修正前は「打開策を見出した経験から課題解決力を培った」と同様の内容が繰り返されており、強みの印象が曖昧になっていました。修正後では「核心を捉えて解決へ導いた」と簡潔に要約され、成果と行動のつながりが明確化されています。企業は課題への着眼点と対応力を一読で把握しやすくなり、実務での再現性も伝わりやすくなっています。 |
| 【エピソード】所属していたゼミでは、「地域活性化のための消費傾向分析」をテーマに研究を進めていました。 |
| 添削コメント|修正前は「十分なサンプルが集まらず」といった漠然とした表現にとどまり、課題の深刻さや緊急性が伝わりづらい内容でした。修正後では「目標200名に対し60名」という具体的な数値を示すことで、データ不足の影響が明確になり、状況の切迫感が伝わりやすくなっています。これにより、企業は課題解決に向けて主体的に動いた背景を自然に理解しやすくなります。 |
| 【エピソード詳細】そこで私は、調査対象の選定方法に問題があると考え、チームに対して配布媒体の見直しを提案しました。具体的には、大学構内だけでなく、 |
| 添削コメント|修正前は「調査対象の見直し」や「設問の改善」といった抽象的な記述が中心で、具体的な工夫や行動の規模が伝わりづらい内容でした。修正後では「商業施設での声かけ」や「設問数の削減とイラスト導入」など、数値と施策を明示することで行動の工夫と効果が可視化されています。企業にとっては、課題を分析し自ら改善策を実行できる人物としての再現性が伝わりやすくなります。 |
| 【成果】最終的には、約300名分の有効データを得て、当初立てた仮説を裏付ける分析結果を導き出すことができました。 |
| 添削コメント|修正前は「課題を乗り越えたと感じている」といった主観的な振り返りが中心で、成果の裏付けが弱い印象を与えていました。修正後では「約300名の有効データ」「教授からの評価」「優秀賞の受賞」といった具体的な数値と第三者評価を加えることで、成果の客観性と信頼性が高まっています。企業にとっては、結果に基づいた実力の再現性を判断しやすい構成になっています。 |
| 【入社後】入社後も、目の前の課題に対して粘り強く向き合い、最適な解決策を自ら考え行動に移すことで、 |
| 添削コメント|修正前は「課題に粘り強く向き合う」といった抽象的な姿勢の表明にとどまり、入社後の具体的な行動像が見えづらい構成でした。修正後では「データ不足」や「業務フローのボトルネック」といった実務課題を明示し、それに対する分析と改善行動を具体化することで、再現性のある課題解決力が強調されています。企業にとっては、即戦力としての活躍を明確にイメージしやすくなります。 |
【NGポイント】
課題や成果の記述が抽象的で、数値などの定量的な裏付けが不足していたため、説得力に欠けていました。また、行動内容は5W1Hの観点が不十分で具体性が弱く、入社後の活用イメージも曖昧だったことで、企業側にとって再現性や貢献可能性を判断しづらい内容になっていたと考えられます。
【添削内容】
課題規模や成果を具体的な数字で示し、行動面では「どこで・誰に・何を」実施したかを明確化しました。さらに主観的な言い回しを削除し、教授からの評価など客観的視点を補強。入社後については業務場面と結び付け、仮説検証や改善提案といった強みの発揮シーンを具体的に描くよう修正を加えています。
【どう変わった?】
定量情報と客観的評価を加えたことで、成果の信頼性が高まり、採用担当者はスキルや実績を明確に把握できるようになりました。行動の具体化により取り組みの説得力も増し、強みが実務でどのように発揮されるかが想起されやすくなっています。結果として、選考時に深掘りされても一貫した説明が可能な自己PRに仕上がりました。
| ・数値で課題規模を提示 ・行動を5W1Hで記述 ・成果は第三者評価で裏付け |
⑥新たな視点で糸口を見つけた洞察力
商店街集客減少の真因をデータから見抜き、仮説を再構築した洞察力の添削例で、課題の特定から施策提案まで一貫して示します。
「洞察力」をアピールする場合は、その気づきが一味違う必要があります。誰もが気づく観点ではなく、鋭い視点や今までの常識の変革などのエピソードがあれば言及しましょう!
| 【結論】私は、 |
| 添削コメント|修正前は「多面的に捉え直す」「新たな気づきを得る」など抽象的な語句が続き、強みの内容や再現プロセスが伝わりづらい構成でした。修正後では「視点を切り替え本質を見抜く」と動作を明確にし、思考過程と成果がひと続きで示されています。企業側は、論理的思考力と課題発見力を実務にどう活かせるかを直感的に理解しやすくなります。 |
| 【エピソード】所属するゼミでは「商店街の集客減少」について研究しており、当初「SNSの活用不足」が原因と仮定し店舗への聞き取りやアンケートを実施しましたが、 |
| 添削コメント|修正前は「仮説とのズレに直面した」という表現にとどまり、どのような矛盾が生じたのかが不明確でした。修正後では「SNSの有無にかかわらず来街者が減少」と具体的な調査結果を明示し、仮説再検討の根拠が論理的に整理されています。これにより、洞察力がどのように発揮されたかが明確になり、企業も課題発見力の再現性を具体的にイメージしやすくなります。 |
| 【エピソード詳細】私は集まったデータを再確認する過程で「目的を持たずに訪れる層が減っている」という回答に注目し視点を変えて来街者の動機に着目した追加調査を提案し商店街利用者の行動パターンを調べました。 |
| 添削コメント|修正前は「偶然の立ち寄りが減っている」という定性的な気づきにとどまり、分析結果の裏付けが弱く、説得力に欠けていました。修正後では「前年比30%減少」と具体的な数値を提示することで、行動の根拠と結果の信頼性が高まりました。企業は仮説再構築から検証までの論理的プロセスを明確に把握でき、分析力や洞察力の再現性を評価しやすくなります。 |
| 【成果】仮説修正により調査結果に一貫性が生まれ最終的に回遊性を高める施策提案へ結び付きました。 |
| 添削コメント|修正前は「評価された」「貢献した」といった主観的な表現が中心で、成果の重みや信頼性が伝わりにくい構成でした。修正後では「教授による講評」や「学内発表会での優秀賞受賞」といった具体的な評価主体と実績を明示することで、成果の客観性と説得力が高まりました。企業側は、強みが第三者からも認められた実績として把握しやすくなります。 |
| 【入社後】入社後も表面的な要因にとらわれずデータと現場の声を丁寧に読み解くことで課題の本質を見極め最適な改善策を提案していきたいです。 |
| 添削コメント|修正不要。洞察力を業務で再現する姿勢が端的に示され前段の実績と自然に連動しており高評価です。 |
【NGポイント】
仮説のズレが抽象的に語られており、裏付けとなるデータが不足していたため、洞察力の信ぴょう性が弱くなっていました。追加調査の結果にも件数や割合といった数値が示されておらず、ビジネス応用に耐える分析力として評価されにくい構成でした。また、施策提案の効果も曖昧で、全体として客観性が乏しかったといえます。
【添削内容】
仮説の再検討理由を「SNSの有無にかかわらず来街者が減少」と明示し、分析の根拠を明確化しました。追加調査では「偶然立ち寄った層が前年比30%減少」と定量データを挿入し、洞察の根拠を補強しています。さらに教授講評と優秀賞の実績を加えることで、第三者評価による信頼性も高めました。結論は文を整理し、強みが一読で伝わるよう簡潔化しています。
【どう変わった?】
数値と評価実績が加わったことで、分析・洞察の再現性と信頼性が明確になり、スキルとしての説得力が増しました。仮説修正から提案に至るまでの流れが整理され、業務上の課題解決場面への応用も想像しやすくなっています。文章は簡潔で読みやすく、短時間で本質を把握できる自己PRへと仕上がっています。
| 課題規模と成果を具体的数値で明示する 洞察に至る視点転換を行動と時系列で詳しく描写 第三者評価と受賞実績で信頼性を確実に補強 |
⑦チームで成果を出したマネジメント力
本例文はゼミで培ったマネジメント力を中心に、チーム成果を定量的に示すよう具体的にブラッシュアップしたものです。
ゼミ活動でリーダーの経験がある場合は効果的なアピールになります。チームを率いたアピールだとリーダーシップの強みと重なるので、チームメンバーにどのような役割を任せ、連携していたのかなどの経験を伝えてみましょう。
| 【結論】私は、目標達成に向けてメンバーの強みを活かし、チームをまとめるマネジメント力があります。 |
| 添削コメント|強み・行動・目的を一文に凝縮し再現性を即時提示できている点が高評価。「ゼミ経験×マネジメント力」というテーマ性と企業の選考基準を同時に示し、冒頭で合格要素を網羅しています。 |
| 【エピソード】所属するゼミでは、地域活性化を目的とした企画提案を行うプロジェクトがあり、私は7人チームのリーダーを担当しました。 |
| 添削コメント|修正前は「意見がまとまらず進行が遅れた」という表現にとどまり、課題の具体性や深刻さが伝わりにくい構成でした。修正後では対立の具体的な論点と「2週間の遅延」という数値を明示することで、状況の複雑さとリーダーに求められる対応力が明確になっています。企業にとっては、マネジメント力を発揮すべき必然性が伝わりやすくなり、後続の行動や成果にも納得感を持たせる基盤となっています。 |
| 【エピソード詳細】私はまず、メンバー一人ひとりの得意分野や関心を整理し、役割分担を見直しました。 |
| 添削コメント|修正前は「役割分担の見直し」や「体制の工夫」といった抽象的な表現が中心で、どのような仕組みで課題を解決したのかが不明確でした。修正後では、班の再編理由や意思決定プロセス、使用ツール、実施頻度、タスク管理の指標までが具体化されており、リーダーとしての戦略的な思考と実行力が明確に伝わります。企業はチーム運営の再現性や業務推進力を具体的にイメージしやすくなっています。 |
| 【成果】役割が明確になったことでチームの意見交換が活発になり、当初予定よりも早く企画案をまとめることができました。 |
| 添削コメント|修正前は「高評価を得る提案として選出」「取り組みの過程が評価された」といった抽象的な表現が中心で、成果の根拠や規模が曖昧でした。修正後では「200名のアンケート」「満足度4.6/5.0」「全8案中1位」と具体的な数値と比較結果を提示することで、提案の説得力と第三者評価の客観性が明確化されています。企業にとっては、実績の再現性とチームでの成果創出力を判断しやすい構成になっています。 |
| 【入社後】入社後も、メンバーの特性を理解したうえで適切に支援・調整し、チーム全体で成果を出せるような動きができる存在を目指します。 |
| 添削コメント|大学で実証したマネジメントサイクルを企業業務へ展開する意図を示し再現性を証明。結論から成果まで一貫したストーリーが完成し、配属後の貢献イメージを具体的に描ける構成になっています。 |
【NGポイント】
当初は「意見がまとまらない」といった抽象的な表現に留まり、課題の深刻度が読み手に伝わりにくい内容になっていました。成果も「高評価」とのみ記載され、客観的な指標に欠けていたため、行動の効果が不明確でした。入社後の貢献内容も具体性に乏しく、配属後の活躍をイメージしづらい構成となっていました。
【添削内容】
課題は「企画テーマ・予算配分・ターゲット層の三点での対立」「2週間の遅延」と定量化し、事態の深刻さを明示しました。行動では班再編や意思決定フロー、共有ツールといった要素を5W1Hで整理し、取り組みの実行力を強調しています。成果は「200名中平均4.6点・1位」と数値で示し、入社後には業務への応用方法を具体的に追記しました。
【どう変わった?】
課題・行動・成果が定量データで結び付けられたことで、リーダーシップの再現性や汎用性が伝わりやすくなりました。特にICTやKPIを活用した運用設計が加わったことで、企業は入社後の即戦力性をより具体的に想像できるようになっています。全体として説得力が増し、面接時にも一貫した説明が可能な構成へ改善されました。
| 課題は数値で深刻度を具体的に可視化提示すべき 行動は5W1Hとツールまで示し再現性担保 成果は人数・平均点・順位で客観性を大幅強化 |
⑧活動に積極的に参加した主体性
本例文はゼミ観光企画プロジェクトで発揮した主体性を訴求する自己PRを、企業視点で全面的にブラッシュアップしたものです。
ゼミ活動自体に主体的に取り組むには当たり前ではあるので、たとえば課題を見つけて行動するなど、普段の活動にプラスして行動していた経験などをアピールしましょう!
| 【結論】私は、 |
| 添削コメント|修正前は「自ら考えて行動」「チームの活性化に貢献」といった抽象的かつ冗長な表現が並び、強みの焦点が曖昧になっていました。修正後では「課題発見」や「方向付け」といった具体的な行動に言い換えることで、主体性の発揮場面が明確になり、採用担当が強みを一読で把握しやすい構成に整えられています。 |
| 【エピソード】所属するゼミでは、地方の観光資源を活かした企画を立案するプロジェクトに取り組んでいました。 |
| 添削コメント|修正前は「指示を待つ雰囲気」「消極的」といった主観的な印象表現が多く、課題の実態が伝わりづらい構成でした。修正後では「発言をためらい議題が停滞」「企画案が具体化しない」といった具体的な状況描写に置き換えることで、問題の深刻さと主体性が求められる必然性が明確になっています。企業にとっては、行動の背景を客観的に理解しやすくなり、強みの発揮が自然に伝わる構成です。 |
| 【エピソード詳細】このままでは良い案が出ないと感じた私は、観光地に関する情報を自ら収集し、資料を作って初回のミーティングで提案しました。 |
| 添削コメント|修正前は「情報を収集し提案した」という概要にとどまり、行動の具体性や工夫のレベルが伝わりにくい構成でした。修正後では、収集元・件数・分析内容・成果物(インフォグラフ)までを明示することで、主体的な働きかけと工夫のプロセスが可視化されています。企業にとっては、周囲を巻き込む起点となる行動力と、課題解決への再現性が自然に伝わる内容に仕上がっています。 |
| 【成果】最終的に、提案内容はゼミ内で高く評価され、プレゼンテーションでは「準備と構成が分かりやすい」との好評を得ました。 |
| 添削コメント|修正前は「良い影響を与えられたと感じている」といった主観的な振り返りが中心で、成果の裏付けが弱い印象を与えていました。修正後では「優秀賞の受賞」や「発言数2倍」といった客観的な成果と数値を提示することで、取り組みの効果が明確に伝わる構成になっています。企業にとっては、行動の影響力とチームへの貢献度を具体的に評価しやすくなっています。 |
| 【入社後】 |
| 添削コメント|修正前は「前向きに行動できる存在でありたい」という抽象的な抱負にとどまり、実務での具体的な貢献イメージが伝わりづらい内容でした。修正後では「地域活性プロジェクト」「現地調査から仮説検証」「部門横断での実行」など、具体的な業務と行動プロセスを示すことで、大学で培った主体性がどのように活かされるかが明確になっています。企業にとっては、即戦力としての再現性を具体的に想起しやすい構成です。 |
【NGポイント】
課題や行動に抽象的・主観的な表現が多く、強みの輪郭が曖昧でした。5W1Hが不足し、行動や成果の規模感が伝わらず、再現性・客観性の判断が難しい構成になっていました。また、入社後の活用場面が描かれておらず、企業への貢献が想像しづらかった点も評価を下げていたと考えられます。
【添削内容】
課題は客観的事実と因果で構成し、行動には分析手法・データ量を具体的に盛り込みました。成果は外部評価と数値で裏付け、入社後は想定業務と接続して再現性を補強しています。構文を一文一意に整え、主語と述語の距離を縮めることで読みやすさも向上させました。
【どう変わった?】
課題から成果までの論理が一本化されたことで、主体性や実行力が明確に伝わるようになりました。客観データと第三者評価により信頼性が高まり、入社後の活躍イメージも想起しやすくなっています。冗長な記述が整理され、面接官が読み進めやすい構成に改善されています。
| ・課題→行動→成果の因果を一貫させ説得力強化 ・数値と第三者評価で客観性を担保し信頼獲得 ・企業業務で再現する活用イメージを具体提示 |
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
ゼミの経験から自己PRを作る時の差別化方法2選

ここまで、例文を5つ紹介してきました。
ここからは、周りの学生から更に1歩差をつける差別化方法を2つ紹介していきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①ゼミの凄さではなく自分で考えた内容をアピールする
まず、ゼミの名前を出し過ぎないようにすることが重要です。
大学のゼミによっては、教授が業界で有名な教授で、どうしても威厳を借りたくなることもあります。
しかし企業が見たいのはゼミの名前ではなく、志望者の強みなので、ゼミの名前に関係なく自分の強みをアピールするようにしましょう。
②具体的な数字を用いて成果をアピールする
また、自己PRを書くときにはできるだけ具体的な数字や固有名詞を含めて書くようにしましょう。
どれだけ凄い内容を書いていても、具体性のない話はイメージがつきづらく、信憑性にも欠けます。
自己PRを伝える際には、聞き手がしっかり理解できるかを意識しながら文章を作るようにしましょう。
また、どうしても曖昧なエピソードになってしまう場合は、こちらの記事で紹介されている質問リストを参考に深掘りを行うのがおすすめです。具体性のあるエピソードでアピールできるよう、ぜひ参考にしてくださいね。
ゼミで自己PRを作るときの2つの注意点

最後に、ゼミ経験から自己PRを作るときの注意点について解説していきます。
以下の2つのポイントには注意しながら、自己PRを作るようにしましょう。
それぞれ詳しく解説していきますね。
①専門的な話題に偏らせすぎない
まずは自己PRの内容を専門的にしすぎないようにしましょう。
自己PRを聞くのは、ゼミの教授やゼミ生ではなく、その分野で勉強したことのない面接官です。
あまりに専門的な話ばかりしてしまうと、肝心のアピールしたい強みが相手に伝わらず、評価が下がってしまいますよ。
②抽象的な学習内容の説明に終始しない
自己PRの内容が抽象的な話に終始しないようにすることにも注意が必要です。
自己PRの背景をしっかり説明しようと、ゼミでの学習内容の背景ばかり話していても、面接官が聞きたいのはそこではありません。
自分が1番伝えたいアピールポイントが自己PRのメインになるように、伝える内容の分量には気をつけましょう。
また、自己PRを書き上げた後は第三者に確認してもらうことも大切ですよ。自分では気づきにくいポイントを改善するきっかけにもなるため、こちらの記事を参考に添削を受けてみてくださいね。
ゼミでの経験を自己PRにして企業から好印象を獲得しよう!
この記事では、ゼミでの経験を自己PRにする方法について解説しました。
この記事を参考に、ゼミ活動から最高の自己PRを書き上げましょう!
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














