履歴書の職歴が書ききれない時の対処法と正しい書き方を解説
「履歴書の職歴欄に全部書ききれない…どうしたらいいの?」と悩む人は多いのではないでしょうか。
転職経験が多い人や、アルバイトや派遣など働き方が多様な人ほど、限られたスペースに収めるのは難しいものです。
しかし、省略の仕方を誤ると「経歴を隠しているのでは?」と不信感を持たれる可能性もあります。
そこで本記事では、省略しても問題ないケースや職務経歴書の活用法、正しい書き方と働き方別の例文まで詳しく解説します。ぜひ就活や転職活動の参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
職歴の多さをマイナスに捉えられないように工夫しよう!

転職活動をしていると「職歴が多いと悪い印象を持たれるのでは」と心配になる方も多いでしょう。
確かに数が多いと「落ち着きがない」と思われることもありますが、必ずしもマイナス評価になるとは限りません。むしろ工夫次第で、豊富な経験を持つ人材として見てもらえる場合もあるのです。
大切なのは数を並べるだけでなく、応募先にとって価値がある職歴を整理して伝えること。
例えば、短期で辞めた仕事をすべて書くのではなく、業務内容や成果に関連性の高いものを中心にまとめれば説得力が増します。
職歴欄はただ経歴を記す場所ではなく、自分をどう見せたいかを示す場でもあるのです。書き方を工夫すれば「転職回数が多い人」から「経験豊富で柔軟性のある人」へと印象を変えられるでしょう。
履歴書の職歴欄とは?

履歴書の職歴欄は、これまでの勤務経験を採用担当者に伝える大切な項目です。職務経歴の流れやキャリアの一貫性を示すために使われるため、会社名を並べるだけでは十分とはいえません。
正しく書くことで「どのような環境で経験を積んできたか」が一目でわかり、選考で評価されやすくなります。
反対に、省略や曖昧な記載をすると「経歴を隠しているのでは」と不信感を持たれる場合もあるでしょう。
そのため、職歴欄は単なる経歴の一覧ではなく、応募先に自分の信頼性や適性を伝える役割を持っています。つまり、丁寧で正確に記載することが採用担当者へ安心感を与える第一歩になるのです。
履歴書の職歴欄に書ききれない時は省略してもバレない?

転職活動をしていると、これまでの職歴が多くて履歴書の欄に入りきらないことがあります。そのとき「全部書かなくても問題ないのでは」と考える人もいるでしょう。
しかし安易に省略すると、採用担当者に不信感を持たれる恐れがあるのです。特に社会保険や雇用保険の記録は企業側で確認できるため、短期勤務であっても完全に隠すのはリスクが高いでしょう。
一方で、数日のアルバイトやごく短期の派遣などは、記載しなくても問題視されにくい場合もあります。ただし原則はできるだけ正確に記入することが安心につながるのです。
書ききれないときは履歴書の余白や別紙にまとめて提出する方法を取ると誠実さを示せます。省略すればバレないと考えるより、正直さと整理の工夫で信頼を得ることを意識してください。
履歴書に職歴を書ききれないときの対処法

転職活動では、これまでの経歴が多く履歴書に収まらないことがあります。そのまま省略すると「隠しているのでは」と不信感を持たれる恐れもあるため、工夫が欠かせません。
ここでは職歴を正しく整理して伝えるための方法を紹介します。採用担当者にとって見やすく、信頼を得られる履歴書を仕上げてください。
- 職歴欄が大きい履歴書を使用する
- 別紙(職務経歴書)に詳細をまとめる
- 同じ会社での異動・部署変更を1行にまとめる
- アルバイトやパートの職歴を簡潔にまとめる
- 「現在に至る」「以上」を1行で書く
- 学歴の記載を簡潔にして職歴スペースを確保する
①職歴欄が大きい履歴書を使用する
職歴が多く書ききれない場合は、職歴欄が大きい履歴書を使うのが有効です。市販の履歴書にはいくつか種類があり、職歴を多く記載できるものを選べば無理なく整理できます。
一般的なフォーマットは学歴と職歴が同じ欄にありますが、職歴専用欄が広めのタイプを選ぶと省略せずに済むでしょう。逆に、狭い欄に無理やり詰め込むと文字が小さくなり、読みづらくなってしまいます。
採用担当者が見やすいことは大前提なので、最初から適切なフォーマットを使うことが大切。つまり、履歴書の種類を工夫するだけで、正確に伝えるための準備が整うのです。
②別紙(職務経歴書)に詳細をまとめる
履歴書に収まらない場合は、職務経歴書を別紙として添付するのが効果的です。履歴書には主要な勤務先を簡潔に書き、詳しい内容は職務経歴書にまとめれば見やすさと正確さを両立できます。
職務経歴書では仕事内容や成果も記載できるため、自分の強みを詳しく伝えることが可能です。履歴書は全体像、職務経歴書は詳細という役割分担を意識すると良いでしょう。
経歴を省略すると「隠している」と疑われる恐れがありますが、この方法なら信頼を損なうことはありません。つまり、履歴書と職務経歴書を併用することで情報不足と読みづらさを同時に解決できるのです。
③同じ会社での異動・部署変更を1行にまとめる
同じ会社で異動や部署変更が多い場合、それぞれを細かく書くと職歴欄がすぐに埋まってしまいます。その際は「株式会社〇〇 入社、営業部配属。その後人事部へ異動」といった形で1行にまとめてください。
異動を省略すると経歴の一部が抜けたように見えてしまいますが、1行で整理すれば正確さと簡潔さを両立できます。
採用担当者にとっては社歴の長さや経験分野がわかれば十分なので、細かい説明は職務経歴書で補足すれば問題ありません。
無理にすべてを羅列するより、要点を押さえてまとめた方が読みやすく信頼性も高まります。つまり、異動や配置転換は1行にまとめるのが効率的な方法です。
④アルバイトやパートの職歴を簡潔にまとめる
アルバイトやパートの経験が多い場合、すべてを詳しく書く必要はありません。「飲食店で接客業務に従事」「販売職として複数店舗で勤務」といった形でまとめれば十分です。
応募先の職種と関係のない職歴は簡潔で構いませんが、関連性の高い経験は仕事内容を少し具体的に書くと評価につながります。
アルバイト経験でも積極性や責任感を示せることがあるため、省略しすぎるのは逆効果でしょう。つまり、全てを細かく書く必要はなく、応募先に役立つ情報を中心に整理することが大切です。
⑤「現在に至る」「以上」を1行で書く
職歴欄の締めくくりには「現在に至る」「以上」といった言葉を使いますが、これを1行で書くとスペースを有効に使えます。
この際も、「現在に至る」は左寄せ、「以上」は右寄せで書くという基本的なルールは適用されます。同一の行の左側に「現在に至る」、右側に「以上」と記載すれば職歴欄がすっきりと整理されるでしょう。
特に経歴が多いときは、こうした小さな工夫が大きな差につながります。採用担当者にとっても簡潔にまとまっている方が見やすいでしょう。
つまり、終わりの表現も1行に収めることで、限られた欄を有効に活用できるのです。
⑥学歴の記載を簡潔にして職歴スペースを確保する
学歴を簡潔に記載することで、職歴のスペースを確保することも可能です。例えば「〇〇高校 卒業」「〇〇大学 経済学部 卒業」といった最低限の情報に絞れば、職歴欄に余裕が生まれます。
専攻や在学中の活動は職務経歴書や面接で伝えれば十分でしょう。職歴が多い場合は、学歴を簡潔に記載するだけでも大きな助けになります。
採用担当者が重視するのは直近の職歴や実績であることが多いため、学歴はシンプルで問題ありません。つまり、学歴を簡潔にすることで職歴欄を広く使えるように工夫することが大切です。
職歴欄の正しい書き方

履歴書の職歴欄は、採用担当者が応募者の経験や経歴を確認する際に最も注目する部分です。ここが不十分だと、内容が充実していても信頼性に欠けて見える可能性があります。
逆に、基本的なルールを理解し正しくまとめることで、読み手に安心感を与えられるでしょう。ここでは職歴欄を書くうえで押さえておきたい基本的な流れやポイントを整理します。
- 学歴の次に職歴を記載する
- 古い職歴から順番に書く
- 会社名や部署名は正式名称で書く
- 入社と退職の年月を統一形式で記載する
- 最後に「以上」で締める
①学歴の次に職歴を記載する
職歴欄は学歴の直後に続けて記載するのが一般的なルールです。採用担当者は学歴から職歴までを一連の流れとして確認するため、順序が入れ替わると不自然に感じるでしょう。
特に職歴を先に書いてしまうと、成長の経過が正しく伝わらず、内容を読み解くのに余計な時間がかかってしまいます。
一方で、学歴のあとに自然な流れで職歴を書くと、学んだ知識や経験からどのように社会で活かしてきたのかがスムーズに理解できるでしょう。
結果として応募者の努力や積み重ねが一貫して伝わりやすくなり、信頼感を与えられるのです。
②古い職歴から順番に書く
職歴は古いものから順に記載するのが基本。これは応募者がどのような過程を経て現在に至ったのかを、時系列で理解できるからです。
新しい職歴を先に書くと、短期の在籍や転職回数だけが目立ち、落ち着きがない印象を持たれる危険があります。
逆に古い順で並べると、長期の勤務経験やキャリアの一貫性が自然と強調され、安心感を与えるでしょう。読み手が理解しやすい形に整えることは、選考を受けるうえで大きなプラスになります。
順序を守るという小さな心がけが、信頼につながるのです。
③会社名や部署名は正式名称で書く
会社名や部署名を記載する際には、省略や略称を使わず正式名称を用いることが欠かせません。例えば「株式会社」を「株」や「(株)」と省略せず、「株式会社〇〇」と書くことが望ましいです。
部署についても同じで、正式な呼称を記載することで正確さと誠実さを示せます。このような細部への配慮は、応募者が丁寧に対応できる人物であることを間接的に伝えられるでしょう。
仮に小さな省略や誤記があると、全体の信頼性に影響しかねません。形式を守り、正確な表現を心がけることが、読み手からの好印象につながります。
④入社と退職の年月を統一形式で記載する
入社や退職の年月は、必ず統一した形式で書きましょう。例えば「20XX年4月入社」「20XX年3月退職」といった形で揃えるのが一般的です。
もし年月の書き方がバラバラだと、読む側は見づらく感じ、場合によっては誤解が生じる可能性もあります。
逆に統一した形式で整えておくと、全体の印象がぐっと引き締まり、履歴書全体が読みやすくなるでしょう。このような小さな配慮は、応募者の誠実さや細部への気配りを示す有効な手段です。
採用担当者がストレスなく読み進められるように整えることが、選考で好印象を持たれる大きなポイントになるでしょう。
⑤最後に「以上」で締める
職歴欄を終える際には、文末に「以上」と記載して締めるのが通例です。この一言があることで、すべての職歴を書き終えたことを明確に示せます。
もし「以上」を省いてしまうと、記載漏れがあるのではと誤解される可能性があるでしょう。短い一言ではありますが、履歴書全体の完成度を高め、丁寧に仕上げている印象を与えるのです。
採用担当者は細部に注目して応募者の姿勢を判断するため、この一手間を惜しまないことが信頼獲得につながります。誠実さを示す最後の仕上げとして「以上」を忘れないようにしましょう。
職歴欄の書き方のポイント

履歴書の職歴欄は、採用担当者が応募者の経験や適性を判断する重要な部分です。正しく整理して書けば信頼を得られますが、誤った省略や記載は不安を与える原因になりかねません。
ここでは職歴欄を作成する際に意識すべき具体的なポイントを紹介します。読みやすく、自分の強みを的確に伝えられる工夫を取り入れてください。
- 応募企業が知りたい情報を優先して書く
- 省略する場合は職務経歴書で補う
- 成果や役割を簡潔にまとめる
- レイアウトを整えて見やすくする
- 面接で聞かれても一貫性を持たせる
①応募企業が知りたい情報を優先して書く
職歴欄は、採用担当者が「この人は活躍できるか」を判断する材料です。そのため、自分が伝えたいことよりも応募先が知りたい情報を優先して書く必要があります。
たとえば営業職を希望する場合は「顧客対応」「売上達成」など具体的な経験を強調すると良いでしょう。逆に関連の薄いアルバイトや短期の仕事を細かく書いても評価にはつながりません。
採用側が求めるスキルや経験に焦点を当てれば、短いスペースでも効果的にアピールできます。
つまり、職歴欄は単なる経歴の一覧ではなく、企業に「役立つ人材」と思わせるための情報を選ぶことが大切なのです。
②省略する場合は職務経歴書で補う
職歴が多く履歴書に収まらないとき、無理にすべてを書き込む必要はありません。ただし省略だけで済ませるのではなく、職務経歴書を別紙として添付し、詳細を補うことが望ましいです。
履歴書には主要な経歴を簡潔にまとめ、職務経歴書で仕事内容や実績を詳しく記すと、採用担当者に理解してもらいやすくなります。
経歴を隠すような書き方は不信感を与える可能性がありますが、この方法なら安心して全体像を伝えられるでしょう。
特に転職回数が多い人や複雑なキャリアを持つ人にとっては、履歴書と職務経歴書の併用が不可欠です。つまり、省略が必要なときでも補足資料を活用すれば信頼を損なうことはありません。
③成果や役割を簡潔にまとめる
職歴欄は会社名と在籍期間を並べるだけでは十分とはいえません。採用担当者が知りたいのは「どんな役割を担い、どのような成果を出したか」です。
例えば「営業職として新規顧客を開拓し、前年比120%の売上を達成」「店舗運営を担当し、アルバイトスタッフ10名を指導」といった形で、短くても具体的に書くと効果的。
長文でなくても、成果や役割が明確なら印象に残ります。特に応募先と関連のある経験を中心にまとめれば、即戦力として期待される可能性が高まるでしょう。
つまり、職歴欄は経歴を列挙するのではなく、自分の強みを端的に示す場として活用すべきなのです。
④レイアウトを整えて見やすくする
どれほど内容が充実していても、レイアウトが乱れていれば読みづらくなり、印象を損ないます。会社名や部署、役職、在籍期間を揃えて記載すると見やすさが増すでしょう。
日付は「20XX年4月 入社」「20XX年3月 退社」のように形式を統一してください。バラバラに書くと信頼性を疑われることもあります。さらに、余白や改行を工夫することで全体の見栄えが良くなるのです。
履歴書は第一印象を左右する大切な書類ですから、内容だけでなく見やすさも重視しましょう。つまり、レイアウトを整えることは自分を効果的にアピールする大事な要素なのです。
⑤面接で聞かれても一貫性を持たせる
職歴欄に書いた内容は、面接で質問される可能性が高い部分です。そのため、履歴書の記載と面接での説明に一貫性を持たせることが欠かせません。
曖昧に書いていると面接で矛盾が生じ、「経歴を誤魔化しているのでは」と疑われる恐れがあります。記載した内容をもとに、自分の言葉で説明できるよう準備しておくと安心です。
退職理由は履歴書に書かず、面接で聞かれた際に簡潔に答える方が自然でしょう。一貫した回答ができれば誠実さや信頼性を伝えられます。
つまり、職歴欄はただ記入するだけでなく、面接で話すことまで見据えて準備する必要があるのです。
履歴書の職歴欄に退職理由は書くべきか?

履歴書の職歴欄に退職理由を書くべきか迷う人は多いでしょう。結論として、基本的に履歴書には退職理由を記載する必要はありません。
履歴書は経歴を簡潔に示す書類であり、詳しい事情を説明する場ではないからです。退職理由については、面接で質問されたときに伝えれば十分でしょう。
一方で、空白期間が長い場合など、採用担当者に不安を与えかねないケースでは備考欄や職務経歴書に簡潔に触れると誠実さを示せます。
例えば「一身上の都合により退職」や「契約満了のため退職」といった表現であれば問題ありません。長々と書くと逆に印象を悪くする恐れがあるため、詳細は避けるのが無難です。
履歴書は第一印象を左右する大切な書類ですので、職歴は正確に記載し、退職理由は必要に応じて別の場で補足する姿勢を意識してください。
【働き方別】履歴書の職歴欄の書き方例文

自分の働き方によって職歴欄の書き方は変わるため、どうまとめるべきか悩む人は多いでしょう。
ここでは正社員や契約社員だけでなく、派遣やアルバイトなど多様なケースに対応できる具体的な例文を紹介します。
実際の状況に合わせて参考にすることで、より正確で読みやすい履歴書を作成できるはずです。
正社員の例文
ここでは、正社員として勤務した職歴を履歴書にまとめる際の例文を紹介します。学生時代にアルバイト経験しかなかった人が、初めて正社員として入社したケースを想定。
| 2020年4月 株式会社〇〇 入社 営業部に配属され、法人営業を担当。新規顧客の開拓や既存顧客への提案活動を行い、2021年度には新人賞を受賞。 2023年3月 株式会社〇〇 退職 一身上の都合により退職。 |
正社員の職歴では、会社名や部署名を正式名称で記載し、入社から退職までを一貫して表現してください。実績や担当業務を簡潔に盛り込むことで、採用担当者に具体的なイメージを伝えやすくなります。
契約社員の例文
ここでは、契約社員として働いた場合の職歴を履歴書に記載する際の例文を紹介します。大学を卒業した後、まずは契約社員として勤務を始めたケースをイメージしました。
| 2021年4月 株式会社△△ 入社 契約社員として総務部に配属。 勤怠管理や書類整理、社内イベントの運営を担当し、業務改善に貢献。上司や同僚から協調性を評価され、業務フローの効率化にも携わる。 2023年3月 株式会社△△ 契約満了により退職 |
契約社員の場合は「契約社員で入社したこと」を明確に示すことが大切です。退職理由には「契約満了」と記載すると、前向きな印象を与えやすくなります。
業務内容を簡潔にまとめると読みやすくなるでしょう。
派遣社員の例文
ここでは、派遣社員として勤務した職歴を履歴書に記載する際の例文を紹介します。大学を卒業した後、派遣会社を通じてさまざまな現場で働いたケースを想定しました。
| 2020年6月 株式会社◇◇(派遣元:株式会社○○)入社 派遣社員として事務業務に従事。 データ入力や電話対応、来客応対などを担当し、正確性とスピードを評価される。社内研修で得た知識を活かし、チームの業務効率向上にも貢献。 2022年5月 株式会社◇◇ 派遣期間満了により退職 |
派遣社員の場合は、派遣元と派遣先を明確に記載することが重要です。退職理由は「派遣期間満了」と書くことで自然な印象になります。業務内容は簡潔にまとめ、採用担当者に伝わりやすくしましょう。
アルバイトの例文
ここでは、大学生活の中で経験したアルバイトを履歴書に記載する際の例文を紹介します。勉学と両立しながら続けた仕事の経験をどのように書けばよいかをイメージしてみてください。
| 2019年4月 株式会社△△ 入社 飲食店のホールスタッフとして勤務。 接客や注文管理、レジ業務を担当し、忙しい時間帯にも落ち着いた対応を心がける。常連のお客様に名前を覚えていただくなど、人との関わりから学びが多かった。 シフト調整や後輩への指導も経験し、協調性と責任感を養う。 2022年3月 大学卒業に伴い退職 |
パートやアルバイトの職歴は、長く続けた場合や学んだ内容が明確な場合に記載すると効果的です。業務内容を具体的に書きつつ、そこで得たスキルや成長を短くまとめると良い印象につながります。
自営業・フリーランスの例文
ここでは、自営業やフリーランスとして取り組んだ活動を履歴書に書く場合の例文を紹介します。アルバイトや会社員と異なり、主体的に行動した経験をどのように伝えるかがポイントです。
| 2020年4月 大学在学中にWebデザイン業務を個人で受注開始 知人の紹介をきっかけに、地域の飲食店や小規模店舗のホームページ制作を担当。 お客様との打ち合わせからデザイン作成、納品まで一貫して対応しました。納期を守るために計画的に作業を進め、依頼主から追加発注をいただくなど信頼を得ることができました。 2022年3月 大学卒業に伴い受注終了 |
自営業やフリーランスの経験は、自主性や責任感をアピールできる材料になります。案件の規模や実際に工夫した点を具体的に書くと、実績として採用担当者に伝わりやすいでしょう。
副業・兼業がある場合の例文
ここでは、副業や兼業の経験を履歴書に記載する場合の例文を紹介します。本業と並行して取り組んだ内容をどう書くかによって、努力や調整力が伝わりやすくなるのです。
| 2021年4月 株式会社○○ 入社 営業職として新規顧客の開拓や既存顧客のフォローを担当。 チームでの目標達成に向けて積極的に行動しました。 2021年6月 副業として家庭教師を開始 大学受験を控えた高校生に数学を中心に指導。学習計画を一緒に立て、弱点克服をサポートしました。 生徒が志望校に合格した際には大きなやりがいを感じ、教える力や時間管理の大切さを実感しました。 |
副業や兼業の記載では、本業と両立できていた点を強調することが大切です。単なるアルバイト経験ではなく、工夫や成果を簡潔に盛り込むと説得力が増すでしょう。
履歴書の職歴欄に書ききれないときの注意点
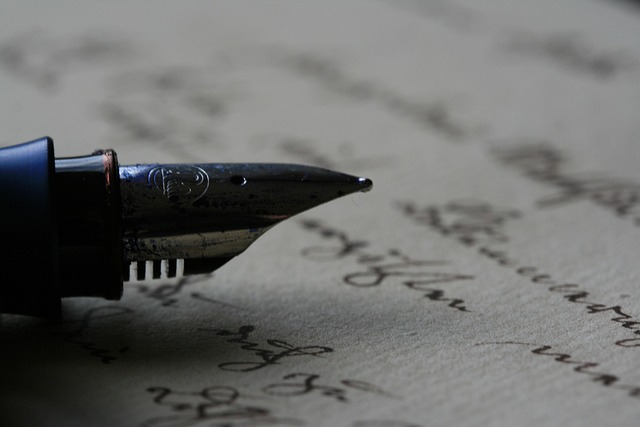
履歴書の職歴欄が狭く、すべての経歴を書ききれないと悩む人は多いでしょう。ここでは、省略してもよい場合と注意すべき点を整理し、採用担当者に誤解を与えないための工夫を解説します。
大切なのは、正直さを保ちながら、読みやすく整理した履歴書を仕上げることです。
- 直近の職歴は必ず詳細に記載する
- 入退社は1行でまとめてもよい
- フォーマットやレイアウトを工夫して見やすくする
- 採用担当者が疑問を持たないよう一貫性を意識する
- 全ての職歴を正直に記載する姿勢を持つ
①直近の職歴は必ず詳細に記載する
履歴書にすべてを書けない場合でも、直近の職歴は必ず詳しく記載してください。なぜなら採用担当者は、最新の経験からスキルや即戦力を判断するからです。
役職や担当業務を丁寧に書くことで、面接時の質問がスムーズになり、信頼にもつながるでしょう。省略するなら10年以上前の短期勤務や、応募先に関係の薄い仕事が適しています。
ただし直近3社以内の経験を省くと「何か隠しているのでは」と疑われかねません。紙面が足りない場合は、職務経歴書で補足してください。
最新の経歴をしっかり示すことが、職歴が多い人にとって最大のアピールにつながります。
②入退社は1行でまとめてもよい
職歴が多く枠に収まらないときは、入退社を1行にまとめる工夫が有効です。例えば「2018年4月 株式会社〇〇入社/2020年3月退職」と書けば、省スペースで必要な情報を伝えられます。
この方法はアルバイトや短期契約が多い人に特に適しているでしょう。年月・会社名・在籍期間を簡潔に書くのがポイントです。
ただし重要なポジションや応募職種に直結する経歴は、詳細に記載した方がよいでしょう。省略と詳細を上手に使い分けることで、読みやすさと誠実さを両立できます。
③フォーマットやレイアウトを工夫して見やすくする
職歴が多い場合は、フォーマットやレイアウトを工夫することが大切です。文字サイズや行間を少し調整するだけで、書ける情報は増えます。
さらに、職歴の区切りを明確にすれば、採用担当者が一目で経歴を追いやすくなるでしょう。インターネットには職歴欄が広めに設計された履歴書テンプレートもあります。
そうしたものを選ぶのも有効です。無理に小さい文字で詰め込むと読みづらくなるため避けてください。採用担当者は短時間で多くの履歴書を見るため、見やすさが評価に直結します。
レイアウトの工夫で「読まれる履歴書」を意識してください。
④採用担当者が疑問を持たないよう一貫性を意識する
職歴を省略するときに最も注意したいのは、一貫性を欠かないことです。同じ形式で年月や会社名を記載し、統一感を保つことが信頼性につながります。
書き方が途中で変わると「重要な情報を隠しているのでは」と思われる可能性があるのです。採用担当者は履歴書から人物像を想像します。小さな違和感でもマイナス印象になりやすいため注意してください。
経歴が多い人は、最初に書く基準を決めてから作成すると統一感を保ちやすいでしょう。少しの工夫で「誠実で分かりやすい応募者」という評価を得られます。
⑤全ての職歴を正直に記載する姿勢を持つ
最後に重要なのは、すべての職歴を正直に書く姿勢です。省略の工夫は必要ですが、意図的に経歴を隠すと経歴詐称とみなされ、内定取り消しや信用失墜につながる恐れがあります。
特に転職回数が多い人ほど不安を感じるかもしれませんが、採用担当者は経歴の多さよりも成長や努力の軌跡を重視することが多いです。面接で質問を受けても正直に説明できる内容なら問題ありません。
誠実さこそが信頼を得る最大のポイントです。職歴欄はあなたの歩みを示す大切な記録ですので、正直さを基本に工夫して仕上げてください。
履歴書で職歴を書ききれないときに意識すべきこと

履歴書の職歴欄は採用担当者にとって信頼性を判断する大切な材料です。
そのため、書ききれない場合でも曖昧に省略するのではなく、職務経歴書を活用したり、異動を1行にまとめたりと工夫する必要があります。
特に直近の職歴や応募先に関連する経験は丁寧に記載することが重要でしょう。さらに、形式を統一して見やすく整えれば、誠実さが伝わりやすくなります。
つまり「履歴書 職歴 書ききれない」と悩んだときでも、工夫次第で不安を解消できるのです。
正しい書き方と補足方法を理解し、一貫性を持った経歴の伝え方を意識すれば、採用担当者に安心感を与えられるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











