例文付き!学外活動をESで魅力的に書く方法とコツ
履歴書やエントリーシートで必ず問われるのが「学外活動」です。授業やゼミ以外での経験をどう表現するかによって、企業からの評価は大きく変わります。
この記事では、学外活動の定義や課外活動との違い、企業が注目するポイント、そして効果的な書き方のコツを解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
学外活動とは?課外活動との違いも知ろう

学外活動とは、大学の授業や学内の部活動などとは異なり、大学の外で自発的に取り組む活動のことを指します。具体的には、アルバイトやボランティア、インターン、社会人サークルなどが該当します。
一方、課外活動は学内外を問わず、授業以外のすべての活動を含むため、学外活動はその中の一部と考えるとよいでしょう。
就職活動においては、こうした学外活動を通じて得た経験やスキルが企業から高く評価される傾向にあります。特に、自発性や社会性、実践力が身についているかどうかがポイントになるでしょう。
学外活動を通して得られた気づきや成長に焦点を当てることで、企業にとって魅力的な自己PRに仕上がります。
学外活動で企業が評価しているポイント

学外活動は、企業が学生の人間性や成長可能性を見極めるうえで大切な判断材料になります。特にエントリーシートや履歴書では、どのような姿勢で取り組み、どんな力を得たのかが重要です。
企業は学業以外の時間をどう使ってきたかに注目しており、何を経験し、どんな行動を取ったのかを知ろうとしています。ここでは、企業が注目している9つの具体的なポイントを紹介します。
- リーダーシップの発揮経験
- 主体的に行動する力
- 課題発見・解決能力
- 目標達成に向けた行動力
- 協調性とコミュニケーション力
- 継続して努力できる力
- 責任を持ってやり抜く姿勢
- 柔軟な対応力と適応力
- 計画性とスケジュール管理能力
①リーダーシップの発揮経験
チームをまとめた経験は、企業からの評価が高いポイントです。
特にアルバイトや学生団体、ゼミ活動などで、メンバーの力を引き出しながら目標に向かって行動した経験は、実践的なマネジメント力として受け止められます。
リーダーというと「大規模なプロジェクト」や「肩書きのある役職」をイメージしがちですが、実は小規模なグループや日常の活動の中でも発揮できます。
自分の意見を押しつけるのではなく、周囲の意見を取り入れて方向性を定めたような行動ができていれば、それは共創型のリーダーシップとして高く評価されるでしょう。
リーダー経験に自信がない場合でも、少人数の場で自発的に動いた経験があれば、積極的にアピールして問題ありません。
②主体的に行動する力
就活では、与えられたことだけをこなすのではなく、自ら動ける人が求められています。社会人になってからは指示待ちの姿勢では通用せず、自発的に行動できるかが大きな分かれ道になるためです。
特に「なぜその行動を起こしたのか」「どんな工夫をしたのか」といった思考の流れを伝えることで、表面的な行動だけでなく考え方までアピールできます。
学生生活は自由度が高く、自分の意思で行動を選べる時間です。そのなかで、自らチャンスを見つけて行動した経験がある人は、企業から「成長意欲が高い」と見なされやすいでしょう。
行動の背景と結果を結びつけて伝えることがポイントです。
③課題発見・解決能力
企業は、現場で起こるさまざまな課題に対し、自ら気づいて行動できる人材を求めています。
ただ言われたことをこなすだけでなく、問題点に気づいて改善策を考える力は、業種を問わず重宝される力といえます。
例えば、学外プロジェクトで作業が非効率だと感じたときに、新しいツールを導入して作業時間を短縮させた経験や、イベントの集客が伸び悩んでいたときにSNSの活用を提案して成果を出した経験などが該当します。
大学生活の中では、与えられた課題に取り組むことが多いですが、学外では自分で課題を見つける力が必要です。だからこそ、学外活動はこの力を示す絶好の機会といえるでしょう。
④目標達成に向けた行動力
設定したゴールに向かって努力し、結果につなげた経験は、仕事への取り組み姿勢を伝えるうえで大きなアピール材料になります。
企業は、達成意識のある人材を通じて組織の成果を上げたいと考えているため、目標に対して粘り強く向き合った経験は魅力的に映るのです。
たとえば、「半年で売上を20%向上させる」といった目標を立てて行動した経験や、「定員50名のイベントを満席にする」といった具体的な目標がある場合、その達成までの過程に工夫があるとより説得力が増します。
大学では、目標が曖昧なことも多いですが、自分で明確なゴールを設定し、達成のために行動できた経験は大きな価値を持ちます。数値や成果を交えて語ることで、実践力をしっかりアピールできます。
⑤協調性とコミュニケーション力
一人では成し得ないことを、チームでやり遂げた経験は、協調性を示すうえで重要なポイントになります。企業では多くの業務がチームで動くため、人と連携して成果を出せるかどうかが重視されるのです。
たとえば、学外のプロジェクトで意見がぶつかったとき、相手の立場を理解しながら妥協点を見つけて方向性をまとめた経験があるなら、それを具体的に伝えるとよいでしょう。
単に「話し合った」というだけでなく、どんな工夫をして関係を良好に保ったのかまで言及できると印象に残ります。
自分とは違う考え方や価値観を尊重しながら、目標に向かってチームで取り組んだ経験があれば、それは立派な協調性のアピール材料です。
⑥継続して努力できる力
短期間ではなく、長期的に継続して取り組んだ経験は、粘り強さや誠実さを伝えるための重要な要素になります。
大学生活は自由な時間も多いため、何かを続ける意志がないと途中で投げ出してしまいがちですが、あえて継続を選んだ経験には説得力があります。
さらに、「なぜ続けられたのか」「困難なときにどう乗り越えたか」など、内面の動機や工夫も合わせて伝えると良いでしょう。続ける力は目立たないようでいて、社会に出てから非常に大切な要素です。
だからこそ、学外活動で得た“継続力”を丁寧に語ることで、誠実で責任感のある人物だと感じてもらえる可能性が高まります。
⑦責任を持ってやり抜く姿勢
途中で投げ出さず、与えられた役割を最後まで果たした経験は、社会人としての信頼性につながります。特に困難な状況に直面しても、逃げずにやりきった姿勢は、多くの企業にとって魅力的です。
たとえば、イベント当日にメンバーが急に欠席し、急きょリーダー代行として全体をまとめた経験や、途中でトラブルが起きた際に責任を持って解決策を講じた経験があると、それだけで印象的なエピソードになります。
結果の成否よりも、責任を引き受けてやり抜いた姿勢が重視されるケースは少なくありません。
学生のうちは、責任という言葉に重みを感じづらいかもしれませんが、小さなことでも“やり遂げる”ことを経験しておくと、それが大きな武器になります。
⑧柔軟な対応力と適応力
現代のビジネス環境は常に変化しており、柔軟に対応できる人材が求められています。
だからこそ、環境の変化や予期せぬ出来事に対し、前向きに対応した経験があれば、それは大きなアピールポイントになります。
たとえば、天候不良で予定していたイベントが急きょ中止になった際、すぐにオンライン開催に切り替えて実行できたような経験があれば、臨機応変に行動できる人物として高く評価されるでしょう。
ただ対応するだけでなく、自分の役割や周囲への影響を冷静に考え、適切な行動を選べたことが伝われば効果的です。
学外活動は予定通りに進まないことも多く、それが逆に柔軟性を示す絶好のチャンスになります。ピンチをどう乗り越えたかにこそ、あなたの力が表れます。
⑨計画性とスケジュール管理能力
複数の活動を同時にこなした経験は、計画性や時間管理の力を伝えるうえで有効です。
学業、アルバイト、学外プロジェクトなどを並行して行った際には、どのようにスケジュールを組んでいたのかを具体的に伝えてください。
たとえば、「週に3つの活動をこなしながらも、毎週のToDoリストを使って優先順位を明確にした」「突発的な予定変更にも柔軟に対応できるよう、あらかじめ時間の余白をつくっていた」
といった工夫を伝えると、計画力の高さが伝わりやすくなります。学生生活では自由時間が多いため、逆にスケジュール管理が難しいこともあります。
だからこそ、自分で時間をコントロールし、目的達成のために調整してきた経験は、社会に出たあとも大きく活かせるでしょう。
ES・履歴書でアピールできる学外活動とは
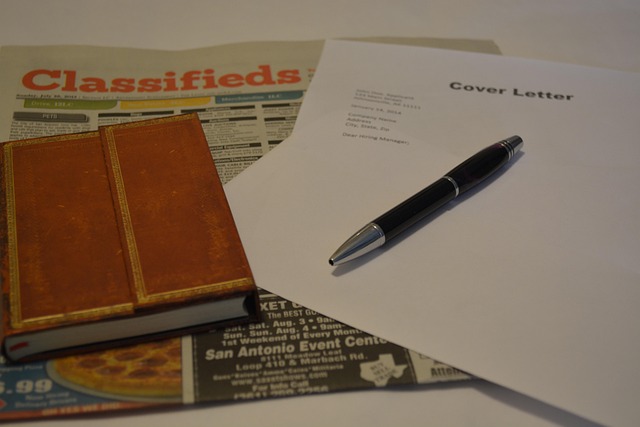
学外活動とは、大学の正課外で自発的に取り組んだ経験を指します。企業はその経験を通して、学生の主体性や継続力、行動力などを見ています。
就活では「学生時代に頑張ったこと」の定番テーマでもあるため、しっかり準備しておくことで面接でも自信を持って話せるようになります。
- 長期インターンでの実務経験
- アルバイトでの店舗運営や接客経験
- ボランティア活動への継続的な参加
- 習い事への取り組みとスキル習得
- 資格取得に向けた学習活動
- 地域活動への参加やイベント運営
- 趣味を通じた継続的な取り組み
- 副業・フリーランス・個人事業の実施
- 国際交流や短期留学などの海外体験
- SNS・ブログ・動画投稿などの発信活動
- 大会やコンテストへの挑戦
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
①長期インターンでの実務経験
長期インターンは、企業での実務を体験できる貴重な学外活動です。特に企画立案や営業、マーケティングなどに携わった経験は、社会で必要とされるスキルや思考力を身につけた証になります。
学生にとって未知のビジネスの現場で責任ある仕事を任された経験は、就活での説得力を大きく高めるでしょう。
たとえば営業で数字目標を追いながらチームでPDCAを回したり、自分の提案が実際に採用されてサービス改善につながったようなエピソードがあると、企業側に印象づけられます。
単に「参加した」だけでなく、「どう行動して何を得たか」を言語化できるかが鍵です。実務を通じて成長した点を具体的に示すようにしてください。
②アルバイトでの店舗運営や接客経験
アルバイト経験は就活生にとって身近な題材ですが、他の学生と差別化するには一歩踏み込んだアピールが求められます。
レジや接客などの作業内容よりも、その中で自分が主体的に工夫や提案をした経験があるかどうかが問われるポイントです。
たとえば混雑時の対応をマニュアル化したり、売上向上を目的にPOPを自作してみた、後輩育成を任されたなどの経験があると、働きながらも「考えて動いていた」ことが伝わります。
どのような役割で、何を改善・達成したのかまで掘り下げて説明できると、ESの説得力が高まるでしょう。
③ボランティア活動への継続的な参加
ボランティア活動は、社会貢献の意識や継続力、他者との関わり方を伝えるうえで非常に有効です。企業は利他的な行動から見える人柄や、物事への姿勢を重視することもあります。
特に長期的な参加や運営面での関与がある場合は、単なる「参加」に留まらない視点で伝えることが可能です。
たとえば「子ども食堂の現場で調理や配膳を行うだけでなく、ニーズに合わせて新メニューを提案した」「リーダーとしてスタッフ配置を最適化した」など、数字や改善点を交えて話せると具体性が出ます。
自分の行動が周囲にどんな変化をもたらしたのかを意識して書いてみてください。
④習い事への取り組みとスキル習得
長年続けてきた習い事も、学外活動として十分な価値を持ちます。
ただし「何年続けた」だけではアピールにならないため、どんな意図で取り組み、どのような成果やスキルを得たかを明確にすることが重要です。
たとえば「ピアノを10年続けて、地域の演奏会にも出演した」「書道で段位を取得し、大学では展示会の運営に関わった」など、目標達成のための努力や継続力が見えると強みになります。
習い事を通じて得た思考習慣や集中力など、社会人になっても役立つ資質を言語化してみましょう。
⑤資格取得に向けた学習活動
資格取得は「努力の証」として評価されやすいですが、それ以上に大事なのは背景にある目的や学びのプロセスです。
単なる合格報告にとどまらず、どんな工夫をして勉強したのか、どんな点で成長を実感したのかまで記すと、内容に深みが生まれます。
たとえば「TOEIC800点を目指して、毎朝1時間の英語学習を継続」「簿記2級の取得を通じて、数字に強くなり経営の視点を学べた」など、目標達成に向けて努力した姿勢が伝わると好印象です。
志望業界との関連性があれば、それも忘れず盛り込んでください。
⑥地域活動への参加やイベント運営
地域活動やイベント運営の経験は、地元や社会とのつながりを意識した行動として評価されやすいです。
特に、自治体やNPOと連携して企画・運営に携わった場合は、その過程で得た調整力や行動力を伝えることができます。
たとえば「地域のお祭りで集客戦略を考案」「学生団体で地元商店街とコラボイベントを開催」などのエピソードは、実行力や周囲を巻き込む力を示す材料になります。
イベント当日だけでなく、準備段階で直面した課題とその対応も詳しく書くと、企業からの評価が上がるでしょう。
⑦趣味を通じた継続的な取り組み
一見就活と関係なさそうな趣味も、継続的に取り組んでいるものであれば十分アピールになります。
特に、明確な目標を持って努力してきた経緯がある場合は、自己管理能力やチャレンジ精神として評価されることがあります。
たとえば「毎日絵を描き続けてSNSに投稿し、作品集を作った」「登山が趣味で、日本百名山の制覇を目指している」など、定量的な目標があると伝わりやすいです。
趣味に本気で取り組む姿勢は、仕事にも活かせるという前向きな印象につながるでしょう。
⑧副業・フリーランス・個人事業の実施
学生時代から副業や個人での仕事に挑戦することは、自発的な行動力や計画力を伝える強力なエピソードになります。
企業視点では「自己判断で挑戦し、責任を持って結果を出す力」として高く評価されやすいです。
たとえば「クラウドソーシングでライティング案件を50件以上納品した」「ハンドメイド作品をECサイトで販売し、月3万円の売上を継続している」など、数字があると説得力が出ます。
失敗した経験も含めて、そこから学んだことをポジティブに伝えてみてください。
⑨国際交流や短期留学などの海外体験
海外での経験は、異文化への適応力や柔軟性を伝える上で効果的です。語学力に加え、現地の人々とどのように交流し、何を得たのかを掘り下げて書くことが大切です。
たとえば「2週間の短期留学で、英語プレゼンに挑戦し自信がついた」「ホームステイ中に文化の違いに直面したが、積極的に質問し乗り越えた」といった経験は、成長の具体例として伝わります。
企業は、海外体験からの学びをどう行動に活かしているかを見ています。
⑩SNS・ブログ・動画投稿などの発信活動
情報発信系の活動は、近年とても注目されている分野です。SNSやYouTube、ブログなどを通じて継続的にコンテンツを発信している学生は、計画性・継続力・分析力を持っていると判断されます。
たとえば「大学生活のVlogを投稿し、半年でフォロワー1,000人を獲得」「ブログ記事を毎週更新し、月5,000PVを達成」など、成果だけでなく工夫のプロセスや目標への姿勢もあわせて伝えてください。
バズらせることよりも、内容の一貫性や継続力が評価されやすいです。
⑪大会やコンテストへの挑戦
コンテストや大会への挑戦は、目標に向かって努力し続ける力をアピールできる貴重な学外活動です。入賞経験がなくても、準備や本番での取り組み姿勢に価値があります。
たとえば「ビジネスコンテストで企画立案を担当し、最終選考まで進出」「デザインコンペに応募するために、独学でソフトの使い方を習得」など、挑戦の過程を丁寧に伝えてください。
困難にどう向き合い、自分をどう成長させたかが、企業の評価ポイントになるでしょう。
ES・履歴書で学外活動を書く時の5ステップ
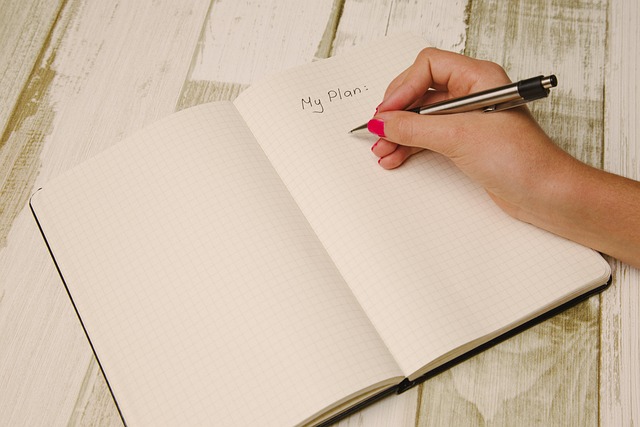
エントリーシート(ES)や履歴書において「学外活動」は、自分らしさや主体性を伝える重要な項目です。企業は学外活動を通じて、あなたの人柄や行動力を評価しています。
しかし、どのように書けば効果的にアピールできるのか、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。ここでは、5つのステップに沿って、読み手に伝わる学外活動の書き方を分かりやすく解説していきます。
就職活動が本格化するなかで、「学外活動って何を書けばいいの?」と不安を感じている学生にも役立つ内容となっています。
- 活動の概要と期間・頻度の記述
- 活動を始めたきっかけや背景の説明
- 目標や取り組んだ課題の提示
- 実施内容や工夫した点の具体的記述
- 得られた学びと将来への活かし方の明示
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
①活動の概要と期間・頻度の記述
まずは、学外活動の全体像を明確に伝えることが大切です。採用担当者は多くのESに目を通しており、活動内容や規模がすぐに理解できないと、関心を持ってもらえないかもしれません。
たとえば、「地域ボランティア活動に大学2年の4月から月2回参加」といったように、活動内容・期間・頻度を簡潔にまとめるとよいでしょう。これにより、継続性や責任感、また主体性を自然にアピールできます。
大学生活では、サークル活動やアルバイトなど多くの経験がありますが、学外活動は特に個性が出やすい分野です。
だからこそ、まずは自分の取り組みを事実に基づいて丁寧に整理することが重要です。どんなに小さな活動でも、客観的に分かりやすく伝えることが、印象アップの第一歩になります。
②活動を始めたきっかけや背景の説明
学外活動に取り組むようになった理由や背景を伝えることで、あなたの価値観や考え方をより深く理解してもらえます。
ただ出来事を並べるのではなく、「なぜそれをやろうと思ったのか」を自分の言葉で語ってみてください。
たとえば、「地方創生に関心があり、地域の課題解決に携わるボランティアに参加した」という動機があれば、活動への姿勢や志向性がはっきり伝わります。
自分自身の興味や考え方と、活動との接点を見つけ出し、それを具体的に言語化することが、説得力を高めるコツです。
③目標や取り組んだ課題の提示
学外活動でどんな目標を持ち、どのような課題に向き合ったのかを示すことで、あなたの行動力や問題解決力が伝わります。
特に企業は、「この学生が仕事の中で課題に対してどう動くか」を知りたがっているため、ここはしっかりアピールしておきたいポイントです。
また、活動中に直面した困難や、想定外のトラブルにどう対処したかも忘れずに書きましょう。「準備段階で予算が削減され、限られた資源で工夫する必要があった」などの具体例があると、現実感が生まれます。
就活生の多くは、「成果が出せなかったら書けないのでは」と不安になりますが、重要なのは結果そのものよりも、課題に向かう姿勢や行動の過程です。
失敗も成長の証として評価されることを意識してみてください。
④実施内容や工夫した点の具体的記述
ESでは、どのような行動をとったのかを具体的に記すことが必要不可欠です。抽象的な表現ばかりでは、読み手にとって印象に残りにくくなってしまいます。
特に、あなた自身が工夫したポイントを盛り込むことで、オリジナリティが際立ちます。
たとえば、「地域イベントで10代の参加者が少なかったことから、Instagramを使ったキャンペーンを企画・運営した」などの行動は、自分のアイデアを形にした好例です。
また、他のメンバーとどう連携したか、リーダーとしてどんな役割を果たしたかといった協働の面にも触れると、社会性やチーム力も伝えることができます。
実際の行動にフォーカスし、どんな工夫が成果に結びついたかを明確に描いてください。
⑤得られた学びと将来への活かし方の明示
活動を通じて得た学びを、今後の社会人生活にどう活かしたいかまで書くことで、あなたの視野や将来像を印象づけることができます。
企業は、「この学生はどんな強みを持ち、どんな姿勢で働いてくれるか」を知りたがっています。たとえば、「イベント企画を通じて、多様な意見を調整しながら物事を進める力を学んだ。
この経験を活かして、営業職として顧客のニーズに柔軟に対応したい」といったように、経験と志望動機をつなげると非常に効果的です。
また、「自分に足りない部分に気づいた」というような内省の要素も加えると、成長への意欲が伝わります。学外活動の中にある小さな気づきを、将来の仕事と結びつけて言葉にしてみてください。
ES・履歴書で学外活動をアピールするコツ

就職活動において「学外活動」は、企業が人物像を判断するための重要な要素の一つです。ただ活動を並べるだけでは評価にはつながりません。どう伝えるかが大切です。
ここでは、ESや履歴書で学外活動を効果的にアピールするためのコツを紹介します。
「何を書けばいいのかわからない」「特別な経験がない」と不安を感じる方も、ポイントを押さえれば十分に伝わる内容になります。
- 企業が評価する能力に結びつける
- アクション・成果を具体的に表現する
- 応募職種に関連する経験を優先する
- ガクチカとの整合性を意識する
- 汎用的な力(リーダーシップ・継続力)に昇華する
- 同じ活動でも視点を変えて複数パターンに分ける
- 独自性・自分らしさを伝える視点を持つ
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①企業が評価する能力に結びつける
学外活動を評価につなげるには、その経験が企業で活かせる力と関係している必要があります。
たとえば、ボランティア活動でのリーダー経験を通じて「調整力」や「責任感」を身につけた場合、それはチームで働く際にも強みになるでしょう。
企業の採用担当者は、「この学生はうちの仕事でどう活躍できるか」を常に考えています。
ただ「楽しかった」や「頑張った」という感想だけでは、仕事に直結するイメージを持ってもらうのは難しいかもしれません。
自分の経験をどんな力として言語化し、それがどんな場面で役立つのかまで落とし込むことがポイントです。企業の求める人物像を調べたうえで、自分の経験がどうリンクするかを意識して書いてみてください。
②アクション・成果を具体的に表現する
エントリーシートでは、「何をしたか」だけでなく、「どのように行動し、その結果どうなったか」を具体的に書くことが求められます。数字やエピソードを交えて説明すると伝わりやすくなります。
たとえば、「SNS運用を担当し、3か月でフォロワー数を500人増加させた」といった表現は、成果がひと目で伝わるでしょう。こうした具体性があると、読んだ人もイメージしやすくなります。
とはいえ、「成果がない」と感じることもあるかもしれません。その場合は、周囲からの評価や、自分なりに工夫した点、変化を生み出したプロセスを丁寧に伝えることが大切です。
結果が目立たなくても、取り組み方に誠実さがあれば、十分に評価されることもあります。
③応募職種に関連する経験を優先する
学外活動をアピールする際は、応募する職種と関係が深い経験を選ぶと効果的です。
営業職を希望している場合は、プレゼンや交渉といった要素を含む活動を優先して紹介すると、職種に合った適性を示せます。
採用担当者は、学生時代の経験から「この人は入社後どのように活躍しそうか」を見ています。
自分が希望する職種の仕事内容をあらかじめ調べておき、それに沿ったスキルや行動をアピールできるように準備しましょう。
たとえば、マーケティング職なら「企画力」や「分析力」、エンジニア職なら「論理的思考力」や「粘り強さ」など、求められる素養があります。
自分の経験の中で、どれが最もその職種に近いかを選び取ってみてください。
④ガクチカとの整合性を意識する
学外活動とガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の内容がかけ離れていると、全体の印象に一貫性がなくなってしまいます。
逆に、一貫した価値観や強みが表れていると、芯のある人物として評価されやすくなります。就活では、自分自身の「軸」があるかどうかが重視されることが多いです。
そのため、学外活動でも同じ価値観や姿勢が見える内容にしておくと、信頼感が増すでしょう。
たとえば、ガクチカで「主体性」をアピールしているのに、学外活動では受け身な経験しか書かれていないと、少しちぐはぐな印象になるかもしれません。
内容を選ぶ段階で「共通点はあるか?」を意識してみるのがおすすめです。
⑤汎用的な力(リーダーシップ・継続力)に昇華する
学外活動で得られた経験は、ただの出来事ではなく、仕事に通じる「汎用的な力」として伝えることが大切です。
たとえば、アルバイトで続けた努力は「継続力」、後輩の指導経験は「リーダーシップ」などに置き換えることができます。
就職後は、業種や職種を問わず、土台となる能力が必要です。どんな場面でも通用する「人としての力」を、自分の経験からどう導き出せるかがポイントになります。
具体的には、「1年間欠かさずシフトに入った」「3人の新人教育を担当した」といった事実を通して、自然にスキルを伝えるのが効果的です。
自分にとっては当たり前のことも、企業から見ると価値のある力であることもあります。
⑥同じ活動でも視点を変えて複数パターンに分ける
一つの活動でも、異なる視点で見直すと、さまざまなエピソードに分けることができます。
たとえばサークル運営の経験からは、「人間関係構築力」「マネジメント力」「課題解決力」など、見る角度によって違う強みを示せるでしょう。
この考え方は、特に「経験が少ない」と感じている学生におすすめです。ひとつの経験から得た学びを、切り口を変えて伝えることで、複数のESや面接で使い分けることができます。
また、応募先によって求められる人物像も変わります。企業ごとに「どう見せるか」を変えることで、同じ活動でも印象を大きく変えることができるでしょう。
無理に経験を作るよりも、今ある経験をどう使い分けるかがカギになります。
⑦独自性・自分らしさを伝える視点を持つ
他の学生と差をつけるには、自分らしさを意識することが重要です。同じような活動でも、自分がどんな思いや価値観で取り組んだのかを伝えることで、印象に残りやすくなります。
たとえば「なぜその活動を始めたのか」「どんなことにやりがいを感じたのか」「どんな工夫を重ねたのか」といった背景や心情に触れると、読み手にも共感が生まれやすくなります。
「他の人と同じことしかやっていない」と思う必要はありません。大事なのは、そこでどんなふうに考え、動いたかです。言葉にすれば、それが自分だけのストーリーになります。
遠慮せず、自分の想いを素直に書き出してみてください。
ES・履歴書で学外活動をアピールするときのNGポイント

エントリーシートや履歴書で「学外活動」を記載することは、自分の人柄や経験を伝える良いチャンスです。ただし、伝え方を間違えると、かえって印象を悪くしてしまうこともあります。
学生生活で頑張ったことをうまくアピールできれば、他の就活生との差別化にもつながるでしょう。ここでは、企業の評価につながらない「NGな書き方」について、具体的な例とともに解説します。
- 抽象的すぎて印象に残らない
- 使う言葉が就活向きではない
- 一貫性がなく自己PRとズレている
- 成果を誇張しすぎてリアリティがない
- 企業との関連性が見えないエピソードである
- 「特になし」とだけ書いてしまう
①抽象的すぎて印象に残らない
学外活動の内容があいまいで、具体性に欠けていると印象に残りにくくなります。たとえば「ボランティアを頑張りました」だけでは、どのような背景や役割があったのかがわかりません。
活動の目的や自分の立場、どのような課題があってそれをどう乗り越えたのか、さらには結果的にどんな学びを得たかまで伝えることが求められます。
たとえば、「地域の清掃活動に参加しました」ではなく、「毎週土曜日に地域の清掃ボランティアとして、メンバーの出欠管理や清掃エリアの調整を担当しました」
といったように、自分の行動を具体的に描写することが大切です。自分だからこそ語れる経験を意識しながら、説得力のあるエピソードに仕上げてください。
②使う言葉が就活向きではない
普段使っている話し言葉やフランクな表現をそのまま書類に使ってしまうと、就活では不利に働くことがあります。
たとえば、「マジで頑張った」「めっちゃ大変だった」などは、友達との会話では問題なくても、企業に提出する書類としては不適切です。
企業側は、応募者が社会人としての常識やマナーを身につけているかもチェックしています。つまり、表現や言葉づかいも評価の対象になっているのです。
学生だからこそ、言葉づかいの重要性を意識的に高めていく姿勢が大切でしょう。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
③一貫性がなく自己PRとズレている
自己PRと学外活動のエピソードに一貫性がないと、書類全体の説得力が薄れてしまいます。
たとえば、自己PRで「積極性」が強みと書いているにもかかわらず、学外活動では「周囲のサポートを受けながら慎重に行動していた」
など矛盾するような内容では、読み手に混乱を与えることになりかねません。
企業は一貫したストーリーの中で、応募者がどのような価値観を持ち、どのように行動してきたかを見ようとしています。そのため、自分の強みや志望動機とつながるエピソードを選ぶことが重要です。
書類全体を通して一つのストーリーになるよう、意識して構成しましょう。
④成果を誇張しすぎてリアリティがない
成果を大きく見せたい気持ちは理解できますが、事実以上に話を盛ってしまうと、内容の信ぴょう性が疑われてしまいます。
たとえば、「3か月で売上を200%に伸ばした」といったような話が、他の経験や実力と見合っていないと、疑念を持たれることになりかねません。
採用担当者は、過去のエピソードに一貫性があるかどうか、そしてその実績が現実的かどうかをしっかり見ています。誇張がバレた場合、「この人は信用できない」とマイナスの印象につながることもあるでしょう。
小さな成果でも、その背景や過程をしっかり語れば、むしろ誠実さが伝わります。真実に基づいたストーリーこそが、最も強いアピールになるのです。
⑤企業との関連性が見えないエピソードである
学外活動そのものは素晴らしくても、志望する企業の業務内容や求める人物像と全く関係がないように見えてしまうと、評価にはつながりにくくなります。
企業は、応募者の経験がどのように自社に活かせるかを見ています。
たとえば、IT企業を志望しているのに、農業体験の話だけを熱く語っても、その経験がどう役立つのかが伝わらなければ意味がありません。
ただし、農業体験の中で「ITツールを使って作業効率を上げた」などの要素があれば、企業との接点が生まれます。
ポイントは、自分の経験のどの部分を切り取って伝えるかにあります。企業理解と自己分析の両方を深め、リンクするポイントをしっかり言語化しましょう。
⑥「特になし」とだけ書いてしまう
学外活動欄に「特になし」と記入するのは、せっかくの自己アピールの場を自分で放棄してしまっているようなものです。
もちろん、他の就活生のように目立った実績がないと感じることもあるかもしれませんが、それでも何かしら取り組んできたことはあるはずです。
たとえば、アルバイトで責任あるポジションを任された経験、地元イベントのスタッフとして活動した経験、SNSを活用した自主的な情報発信なども、立派なアピール材料になります。
「自分には書けることがない」と決めつけず、日々の行動を振り返ってみてください。意外なところに魅力的なエピソードが見つかるかもしれません。
【パターン別】ES・履歴書に使える学外活動の例文

学外活動を自己PRに活かしたいけれど、どのように書けばよいか迷っていませんか?このセクションでは、目的やエピソードごとに使える例文を紹介します。自分に合った表現を見つけるヒントにしてください。
- アルバイトの例文(接客・リーダーシップ)
- ボランティアの例文(継続性・協調性)
- インターンの例文(業務理解・実行力)
- 習い事の例文(目標達成・向上心)
- 地域活動の例文(社会貢献・多様性理解)
- 資格勉強の例文(計画力・継続力)
- 趣味の例文(独自性・創造力)
- 国際経験の例文(多文化理解・適応力)
①アルバイトの例文(接客・リーダーシップ)
こちらでは、大学生活中に飲食店での接客アルバイトを通じて得られた学びをテーマにした例文をご紹介します。対人スキルの成長やリーダーシップ経験を伝えたいときに適した内容です。
《例文》
| 大学1年の春から、近所のカフェで接客のアルバイトを始めました。最初は緊張してお客様との会話もぎこちなかったのですが、毎回の業務を通じて少しずつ笑顔で対応できるようになりました。 2年目には店長から「後輩の指導を頼みたい」と言われ、アルバイトリーダーとして新人教育を担当するようになりました。 特に、繁忙期の土日は新人が戸惑いやすいため、事前にマニュアルをまとめて配布したり、こまめに声をかけたりして、不安を和らげるよう努めました。 その結果、後輩から「働きやすい」と感謝されるようになり、自分自身も責任感や気配りの大切さを実感しました。こうした経験は、今後社会に出たときにも必ず役立つと感じています。 |
《解説》
日常的なアルバイトでも、成長過程や周囲への働きかけを具体的に書くことで、説得力のある内容になります。特に「誰かの役に立った」体験を盛り込むと印象が良くなります。
②ボランティアの例文(継続性・協調性)
学外活動の中でも、ボランティアは継続的な努力と協調性をアピールできるテーマとして非常に効果的です。ここでは、地域の清掃活動を通じて得た学びを紹介します。
《例文》
| 大学1年の春から、地元の商店街で毎月実施される清掃ボランティアに参加しています。きっかけは、通学路のポスターで活動を知ったことでした。 最初は一人での参加に不安もありましたが、活動を重ねるうちに地域の方々や他の学生と自然に会話が生まれ、毎回の参加が楽しみになっていきました。 2年目からは運営側のサポートも行い、新メンバーの案内や、掃除ルートの調整を担当するようになりました。この経験を通して、継続することの大切さと、異なる立場の人と協力する姿勢を学びました。 地道な活動でも積み重ねることで信頼関係が生まれることを実感し、今後も地域に貢献できる行動を続けていきたいと考えています。 |
《解説》
この例文は、参加のきっかけから継続性、そして役割の変化までが自然に描かれており、成長や協調性が伝わります。自身の立場の変化や周囲との関係性を盛り込むと、より具体的で魅力的な内容になります。
③インターンの例文(業務理解・実行力)
学外活動の中でも、インターンを通じて得た経験は説得力があり、採用担当者にも好印象を与えやすいです。ここでは、業務理解と実行力をアピールできるインターン経験をテーマにした例文を紹介します。
《例文》
| 大学3年の夏、地方自治体と連携する中小企業支援のインターンに参加しました。私は主に地元企業の魅力を学生向けに発信するプロジェクトを担当し、SNS運用やイベント企画に携わりました。 最初は企業情報を一方的に発信してしまい、フォロワー数が伸び悩みましたが、ターゲット層である学生のニーズを把握するためアンケートを実施。 その結果を基に投稿内容を見直し、イベントでも参加型コンテンツを増やしたところ、フォロワーが2倍に増え、イベント集客数も当初目標の150%を達成しました。 この経験から、課題を分析し改善策を実行する力を身につけることができました。 |
《解説》
業務に対する理解と、自ら考えて改善を図った行動が具体的に伝わる例文です。数字を使って成果を示すと、実行力の説得力が増すので意識して取り入れましょう。
④習い事の例文(目標達成・向上心)
大学生活では、学内の勉強だけでなく、学外での習い事に取り組むことで得られる成長も多くあります。
ここでは、「目標達成」や「向上心」に関するテーマで使える、習い事を通じたエピソードの例文を紹介します。
《例文》
| 大学1年の春から、以前から興味のあった英会話教室に通い始めました。 最初は日常会話すらままならず、先生の話を理解するのも難しい状態でしたが、週に2回の授業に加えて、自宅でも毎日30分の復習を欠かさず行いました。 半年後には、外国人観光客に道案内ができるまでに成長し、大学の国際交流イベントでも積極的に通訳ボランティアに参加しました。 この経験を通じて、コツコツと継続する力の大切さを実感し、自分の努力次第で着実に成果が出ることを学びました。 |
《解説》
学外活動としての習い事は、向上心や継続力をアピールするのに適しています。努力と成長の過程を具体的に示すことで、読者に共感を与える文章になります。数字や期間を入れると、より説得力が増します。
⑤地域活動の例文(社会貢献・多様性理解)
大学生が地域活動に関わることで、社会との接点を持ち、視野を広げる経験をすることがあります。ここでは、地域ボランティア活動に参加した体験を通じて得た気づきや成長についての例文をご紹介します。
《例文》
| 大学1年生の春、地元商店街の清掃活動に参加しました。 友人に誘われてなんとなく行ってみたのがきっかけでしたが、実際に参加してみると、普段何気なく歩いている道が多くの人の手で守られていることに気づきました。 活動中、近隣の方々と挨拶を交わしたり、お礼を言われたりする中で、自分も地域の一員であるという意識が芽生えました。 また、参加者には留学生も多く、互いの文化について話す機会もあり、多様な価値観に触れることができました。 この経験を通じて、身近な場所から社会に貢献できることの大切さと、異なる背景を持つ人々と関わることの面白さを実感しました。 |
《解説》
地域活動への参加を通じて得た「社会貢献意識」や「多様性理解」を具体的なエピソードとともに示すことで、説得力のある文章になります。日常の延長にある体験を選ぶと、読者に共感されやすくなります。
⑥資格勉強の例文(計画力・継続力)
学外活動の中でも、資格勉強は継続力や計画性をアピールするのに効果的なテーマです。ここでは、大学生活の中で資格勉強に取り組んだ経験を軸にした例文をご紹介します。
《例文》
| 私は大学2年の春から、日商簿記2級の取得を目指して学外での資格勉強に取り組みました。きっかけは、将来の就職活動に向けて、実務に役立つ知識を身につけたいと考えたことです。 部活動との両立が難しい時期もありましたが、毎週の勉強計画を立て、平日は1日1時間、休日は2~3時間を学習にあてることを習慣化しました。 途中で模擬試験の点数が伸びず、モチベーションが下がったこともありましたが、大学の図書館を活用したり、同じ資格を目指す友人と勉強会を開いたりすることで、継続する環境を自ら作りました。 結果として試験には一度で合格でき、自信と達成感を得ることができました。 |
《解説》
この例文では、資格取得に向けた努力を通して「計画力」と「継続力」を伝えています。自分で環境を整えた工夫や、習慣化のエピソードを入れることで、説得力のある内容になります。
⑦趣味の例文(独自性・創造力)
趣味を通じた学外活動も、個性や創造力をアピールできる貴重なテーマです。今回は写真撮影という趣味を通じて、自分なりの発信を行った経験の例文をご紹介します。
《例文》
| 高校時代から写真を撮ることが好きで、大学入学後は学外の風景を撮影することが習慣になりました。あるとき友人に「写真を発信してみたら?」と勧められ、SNSに作品を投稿し始めました。 最初は数人しか見ていませんでしたが、撮影の角度や色味を工夫するうちにフォロワーが徐々に増え、今では地域のカフェから撮影依頼をいただくこともあります。 大学で学んだデザインの知識も活かしながら、自分らしい表現を追求することにやりがいを感じています。自分の好きなことが、誰かの共感や行動につながる喜びを学びました。 |
《解説》
「好き」から始まる活動も、成長や社会とのつながりを意識すると深みが出ます。発信や工夫を加えることで、独自性が際立ちます。
⑧国際経験の例文(多文化理解・適応力)
大学生のうちに国際交流を通じて多文化に触れる経験は、社会人になってからも役立つ視野や柔軟性を育てます。ここでは、語学留学中の体験を通じて多文化理解や適応力を得た例文を紹介します。
《例文》
| 大学2年の夏に、3週間の短期語学留学でオーストラリアを訪れました。初めてのホームステイで、文化や生活習慣の違いに戸惑うことも多く、最初は積極的に話しかけることができませんでした。 しかし、現地の大学で行われたグループワークやボランティア活動に参加する中で、自分からコミュニケーションをとる大切さを実感し、積極的に質問や意見を述べるよう心がけました。 その結果、言葉の壁を越えて信頼関係を築けるようになり、多様な価値観を理解する力が身についたと感じています。 この経験を通じて、自分とは異なる背景を持つ人々とも前向きに関わっていく姿勢を学びました。 |
《解説》
この例文では、異文化環境での戸惑いから成長へとつながるストーリーが自然に描かれています。同じようなテーマでは、「困難→行動→成長」という流れを意識することで、読み手に伝わりやすい構成になります。
学外活動に書ける内容がないときの対処法

就活でエントリーシートや履歴書を書く際、「学外活動の欄に書ける内容が見つからない」と悩む学生は少なくありません。けれど、少し視点を変えれば、多くの人が評価される経験を持っています。
ここでは、学外活動欄に書けるエピソードがないと感じている方に向けて、その解決方法を紹介します。
実は「目立った活動がない」と思っていても、日々の生活やアルバイト経験などからでも十分なアピールが可能です。
学生生活の中で得たことを丁寧に振り返ることで、自信につながる内容を見つけられるでしょう。
- 過去の活動を時系列で振り返る
- 身近な日常にある「学外活動」を再定義する
- 自己分析ツールやガクチカ作成ツールを活用する
- 企業が評価する経験と接点を見つける
- エピソードを深掘りして意義を明確化する
- 「特になし」と書かない代わりの表現を工夫する
①過去の活動を時系列で振り返る
自分では特別だと感じていなくても、就活に役立つエピソードは意外と多くあります。
学外活動が思いつかないと感じる理由は、経験そのものがないのではなく、それを就活用に整理・言語化できていないからかもしれません。
まずは、高校〜大学までをざっくりと年ごとに振り返ってみてください。
そのとき、何を頑張ったかだけでなく「なぜそれを始めたのか」「どんな気持ちで取り組んだか」なども思い出すと、より深い自己理解につながります。
特に、自分なりに工夫した点や困難を乗り越えた経験に注目すると、企業が重視するポイントが見つかるはずです。まずは、自分の歩みを棚卸しするつもりで、気軽に手を動かしてみてください。
②身近な日常にある「学外活動」を再定義する
日常生活の中にも、就活で評価される経験は数多くあります。
特別なリーダー経験や大会での実績がないと不安になるかもしれませんが、企業が重視しているのは「何をしたか」よりも「どう考え、どう取り組んだか」です。
たとえば、「毎朝家族の弁当を作っていた」「3年間読書を習慣にしてきた」など、一見学外活動に見えないようなことでも、自己管理力や継続力、責任感などを伝えることができます。
企業側も、どこかで見たようなテンプレート的な内容より、その人自身の個性が伝わる経験を知りたいと思っているものです。
普段の生活の中で「他の人と違うかもしれない」と思うことを、改めて見つめ直してみてください。
③自己分析ツールやガクチカ作成ツールを活用する
書けないと悩んでいるなら、ツールの力を借りるのも一つの方法です。
「どこから手をつければいいか分からない」「自分の強みが分からない」と感じているなら、自己分析ツールやガクチカ作成ツールを使ってみてください。
最近ではスマホでも手軽に使える診断ツールが増えており、価値観や性格傾向、行動パターンなどを視覚的に整理することができます。
自分の言葉で書きたい気持ちは大事ですが、最初のハードルを下げるために、こうした補助ツールを活用するのは十分アリです。手詰まり感を解消するだけでも、前向きな気持ちで就活に取り組めるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
④企業が評価する経験と接点を見つける
企業の視点で見直せば、意外な経験が強みに変わることもあります。企業が評価しているのは、必ずしも目立つ成果や有名団体での経験ではありません。
それよりも「その人がどう考えて動いたか」「そこから何を学んだか」に注目しています。
たとえば、コンビニのアルバイトで新人の指導を任された経験でも、工夫して教えたプロセスや、ミスを減らすために取り組んだ内容があれば、それは評価の対象となります。
自分の経験と企業が求める力が重なる部分を探すには、企業研究も必要です。企業の求める人物像を読んだ上で、自分の経験をあてはめて整理してみてください。
少し手間がかかりますが、確実に内容の質が上がります。
⑤エピソードを深掘りして意義を明確化する
表面的な出来事だけでなく、その背景や思考を伝えることが大切です。
「イベントを企画しました」「部活でキャプテンをしていました」といった活動内容だけを述べる学生は多いですが、それだけでは印象に残りません。
企業が知りたいのは、「なぜその活動を選んだのか」「どんな苦労があったのか」「そこから何を学んだのか」といった深い部分です。
さらに、「その経験を通じてどんな価値観を得たのか」「今後どう活かしたいと考えているか」まで言及できると、志望動機とのつながりも強くなります。
小さな経験でも、深く掘り下げることで就活で武器になるエピソードに変わるでしょう。
⑥「特になし」と書かない代わりの表現を工夫する
「何もない」と感じても、前向きな姿勢を見せることはできます。
どうしても書ける内容が思い浮かばない場合でも、「特になし」と書くのは避けてください。それでは消極的な印象を与えてしまい、せっかくの評価のチャンスを自ら手放すことになってしまいます。
たとえば、「これまでは学業に専念してきたが、最近は資格取得に取り組んでいる」「今後は社会人になる準備として、ボランティア活動に参加する予定」といった、前向きな姿勢を見せる工夫をしましょう。
それだけでも、自発性や成長意欲が伝わり、評価につながります。何もしていないことを隠すのではなく、そこに向き合う姿勢を見せることが、実は最も評価されるポイントかもしれません。
よくある質問|学外活動のアピールに関する疑問を解消!

就職活動で「学外活動」を履歴書やエントリーシートにどう書くか迷う人は多いです。特に、アルバイトやボランティアのような一般的な活動が評価されるのか不安になることもあるでしょう。
成果が出ていない経験をどう扱うか、「学び」や「成長」が思い浮かばないときの対処法など、気になる疑問を解消していきます。
- アルバイトは当たり前すぎて評価されないのでは?
- 成果が出ていない活動は書かない方がいい?
- 「学び」や「成長」が思いつかないときはどうすればいい?
①アルバイトは当たり前すぎて評価されないのでは?
アルバイト経験は就活でよく見かける学外活動の一つですが、「誰でもやっているし、評価されにくいのでは」と感じる方も多いかもしれません。
ですが、本当に重要なのは“何をしたか”ではなく“どう取り組んだか”です。仕事内容をただ並べるのではなく、自分がどんな工夫をし、どう行動したかを伝えてみてください。
たとえば、忙しい時間帯にレジ対応を分担し効率を上げた経験や、クレーム対応から学んだ対人スキルなどは、企業にとって注目すべきポイントになります。
アルバイトだからと軽視せず、自分の視点や努力を明確にすれば、しっかりと評価される内容になります。ありきたりと感じても、伝え方次第で印象は大きく変わるでしょう。
②成果が出ていない活動は書かない方がいい?
「結果が出なかったから書かない方がいい」と思ってしまう方もいますが、決してそうとは限りません。就活で重視されるのは、最終的な成果だけでなく、その過程にあります。
たとえば、学生団体でのプロジェクトが成功しなかったとしても、課題への向き合い方や仲間との連携、工夫した点などに注目して書けば、主体性や粘り強さをアピールできます。
企業は「困難にどう立ち向かったか」を見ています。たとえ目に見える成果がなくても、真剣に取り組んだ経験であれば、それ自体が価値となるのです。
結果だけにとらわれず、自分の姿勢を伝えることを意識してください。
③「学び」や「成長」が思いつかないときはどうすればいい?
エントリーシートや面接で求められる「学び」や「成長」が見つからず、悩むことはよくあります。そういったときは、まず自分の経験を振り返ることが大切です。
なぜその活動を始めたのか、どんな場面で戸惑ったのか、どのように対応したのかを順に思い返してみてください。大きな成果がなくても、小さな気づきや考え方の変化は立派な成長です。
たとえば、ボランティア活動でさまざまな立場の人と接し、視野が広がった経験。文化祭の準備で意見をまとめる難しさに直面した経験。こうした体験には、就活で伝えるべき価値が十分にあります。
何をしたかよりも、その中で何を感じ、何を考えたか。自分なりの気づきを言葉にすることで、「学び」や「成長」をきちんと伝えられるはずです。
学外活動の重要性を理解し、効果的なアピールで内定を掴もう

学外活動は、課外活動との違いを理解したうえで、企業が評価するポイントを踏まえて取り組むことが重要です。リーダーシップや課題解決力、継続力などを磨くことで、履歴書やESでの説得力が増します。
また、アルバイト・ボランティア・長期インターン・海外体験など多彩な経験は、主体性や計画性、柔軟な対応力などを示すチャンスです。
さらに、ESでは活動の目的・背景・成果・学びを明確にし、応募先企業が求める能力と結びつけて表現することがポイントです。これらを意識することで、自己成長と企業への好印象を同時に実現できます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










