SPI非言語の頻出問題と解き方徹底ガイド!
「SPI非言語って難しそうで不安…」と感じている人は多いのではないでしょうか。
数学の知識や計算力が問われる分野なだけに、苦手意識から勉強の手が止まってしまうことも少なくありません。
しかし、SPI非言語は出題パターンがある程度決まっており、公式や解法の型を覚えて練習すれば確実に得点源にできます。
この記事では、SPI非言語の全体像や頻出問題の解き方、効果的な勉強法を徹底的に解説していきます。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
SPIとは?

SPIとは、就職活動において多くの企業が導入している適性検査のひとつで、正式名称は「Synthetic Personality Inventory(総合適性検査)」です。
言語・非言語・性格の3つの分野で構成されており、応募者の基礎能力や思考力、人間性を評価する目的があります。
とくに非言語分野では、数学的な問題を通して論理的思考力や計算力を問われるため、苦手意識を持つ学生も少なくありません。
ただし、出題形式にはある程度のパターンがあり、適切な準備をすれば高得点も狙えます。SPIは単なるテストではなく、企業が「入社後に活躍できるか」を判断するための重要な指標です。
対策を後回しにせず、早めに取り組むことで合格への道が近づくでしょう。SPIを実施する企業は非常に多く、ここでの得点が就職活動全体に影響する可能性もあることを忘れないようにしてください。
SPI非言語とは?言語分野との違い
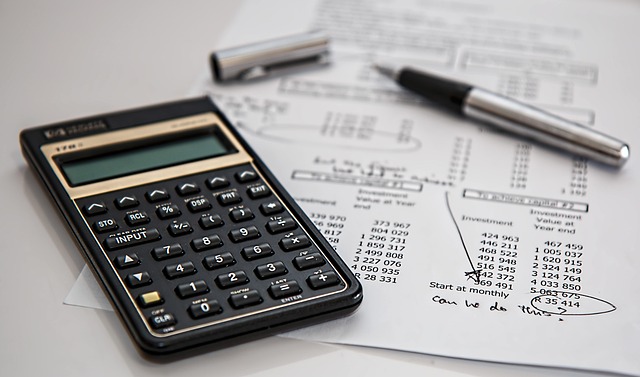
SPI非言語分野は、就活生が直面する大きな壁の一つです。企業の採用選考で広く使われているSPI(Synthetic Personality Inventory)は、「言語」と「非言語」の2分野で構成されています。
SPI非言語は、数的処理や資料の読み取り、推論を通じて数学的・論理的思考力を問う分野です。基礎計算力に加え、情報整理と判断力が必要なため、多くの学生が苦手意識を抱きやすいのが特徴です。
SPI言語は語彙力や読解力を問うため読書習慣のある学生に取り組みやすい一方、非言語は感覚では解けず、パターン理解と時間配分を意識した正確な解答力が求められます。
SPIの得点が企業の選考に直結する今、早い段階から意識的に取り組むことが非常に重要といえるでしょう。ここではSPIの非言語分野と言語分野の違いをより詳しく説明します。
- SPI非言語の概要
- SPI非言語の位置づけ
- SPI言語との違い
①SPI非言語の概要
SPI非言語とは、就活で受ける適性検査の中でも特に数的・論理的な力を評価する項目です。
企業が重視するのは計算速度ではなく、条件を整理して合理的に答えを導くビジネス的思考力です。大学入試のような正確な計算や公式暗記とは異なる視点での対策が求められます。
SPI非言語では、グラフや表の読み取り、割合・損益計算、集合・順列、条件整理などが出題されます。シンプルに見えても短時間で解く必要があり、焦りや混乱を招きやすいのが特徴です。
SPI非言語は最初こそ難しく感じても、頻出パターンを押さえれば得点源にできます。慣れによって大きく伸びる分野なので、苦手意識を持たず継続的に問題に触れることが攻略の第一歩です。
最初は時間をかけてもいいので、丁寧に問題に取り組んで土台を固めておくと、後の伸びがスムーズになるでしょう。
②SPI非言語の位置づけ
SPI非言語は単なる計算問題ではなく、「数字を使って正確に判断する力」を測る重要な指標です。企業がSPI非言語に注目する理由は、業務の中で数値情報を扱う場面が非常に多いからです。
たとえば営業での売上管理、企画職での市場分析、経理・財務の予算計算など、数字を正しく読み取り、そこから適切に行動を判断する能力は、職種を問わず必要とされています。
SPI非言語で高得点を取ることは、単なる学力の証明ではなく、論理的判断力を持つ人材として評価される要素です。スコアはESや面接と同様に、企業へポテンシャルを示す指標となります。
SPIは一次選考の足切りに用いられることが多く、点数が基準を下回れば面接にも進めません。特にSPI重視の企業では、非言語分野の得点がボーダーを超えなければ不合格となる場合があります。
だからこそ、就活の準備段階からしっかりと向き合っておくべき分野だといえるでしょう。
③SPI言語との違い
SPI言語と非言語は、出題形式も問われる力もまったく異なる分野です。SPI言語では、語彙・文法・読解力など日本語の基礎力が問われます。長文の主張把握や文の並び替えなどが代表的な出題形式です。
SPI非言語は数的処理や論理パズル、資料読み取りが中心で、数字や図表をもとに考える力を問われます。感覚や読解では対応できず、構造的な理解と判断力が必要となる分野です。
たとえば、非言語では「〇人の中から条件に合う人を選べ」や「割引率をもとに利益を計算せよ」といった実務を想定した問題が中心です。そのため、学習のアプローチも当然異なってきます。
SPI言語は基礎知識で対応できることもありますが、非言語は慣れが不可欠です。計算や整理が苦手な人は時間がかかりますが、繰り返し解くことでパターンに気づき、解法をスムーズに理解できるでしょう。
両分野を同じように扱うのではなく、それぞれの特性を理解し、対策方法を分けて取り組むことがスコアアップへの近道です。
SPI非言語は難しすぎる?就活生が感じる壁とは
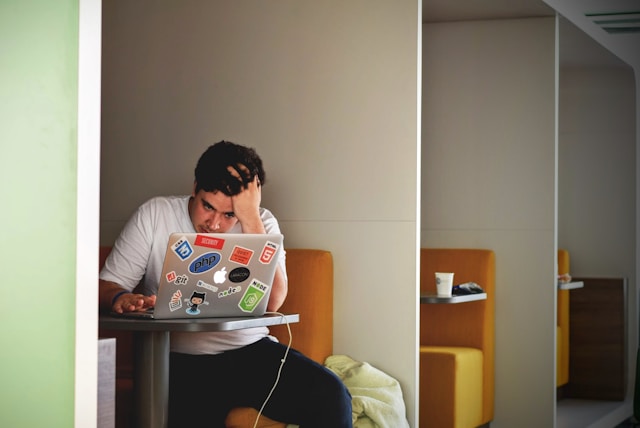
SPI非言語は、就職活動において特に不安視されがちな分野です。とくに数的な処理に苦手意識がある学生にとっては「難しすぎる」と感じる瞬間も多くあるでしょう。
実際、問題の難易度だけでなく、試験ならではのスピード感や形式のクセが大きな壁となっています。
さらに、大学生活で計算問題に触れる機会が減っていることで、取り組み方そのものに戸惑う学生も多く見られます。
ここでは、SPI非言語で多くの就活生が直面する「心理的なつまずき」や「準備不足による落とし穴」に焦点を当て、実態に即した課題を整理していきます。
- 数学に対する苦手意識
- 出題形式への不慣れ
- 時間制限によるプレッシャー
- 解法パターンの習得不足
- 過去問題とのギャップ
①数学に対する苦手意識
「数学アレルギー」と自認する就活生は少なくありません。中高時代から数字に苦手意識を持ち続け、SPIの出題を見るだけで「もう無理だ」と感じてしまうケースも多く見られます。
しかし本質的な問題は、「計算が苦手」というよりも「思い出し方を知らない」ことにあります。SPI非言語の問題は、知識よりも処理の慣れが問われるものが大半です。
そのため、数学の知識がゼロではなくても、感覚を忘れてしまっていることで難しく感じてしまうのです。まずは数字に触れること自体への抵抗感を減らすことが重要です。
日常生活の中で数的な思考を意識してみるなど、少しずつ「数字との距離」を縮めるアプローチが有効です。
②出題形式への不慣れ
SPI非言語の出題には「問題文が長い」「日常的な設定が多い」「条件が複雑」といった特徴があります。
これらは学校のテストとは異なり、単純な知識の確認ではなく「状況整理→計算→判断」という一連の処理を求められるものです。
しかし、大学ではこのような実践形式の問題に触れることが少なく、初めて見ると混乱してしまうのも無理はありません。
特に、条件を読み飛ばしたり、順序立てて考える経験が少ないと、どこから手をつけてよいか分からなくなってしまいがちです。
まずは問題の出され方に慣れることが第一歩です。形式の特徴を把握しておくだけでも、初見での戸惑いは大きく減ります。
③時間制限によるプレッシャー
SPI非言語試験は、「時間内に解き切れなかった」という声が非常に多いです。これは、問題が難しいというよりも、「時間に追われる焦り」から実力を発揮できないことが要因になっていることがほとんどです。
本番では、1問にかけられる時間は非常に限られており、「考え込む余裕」がありません。にもかかわらず、準備段階で時間を測らずに学習している学生も多く、スピード感への適応ができていないのが現状です。
まずは時間感覚を養い、自分のペースで効率よく取り組む工夫が必要です。慣れと意識で、制限時間の中でも安定したパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。
④解法パターンの習得不足
SPI非言語には出題傾向に「型」があります。たとえば割合、仕事算、損益算など、それぞれに典型的な解き方が存在します。
しかし、表面上の理解にとどまっていると、少し出題形式が変わるだけで解けなくなってしまうのが怖いところです。
これは「定着していない」状態の典型例です。何となく分かったつもりでも、別の問題になると応用できない。つまり、知識がまだ「自分の言葉」になっていないということです。
理解したつもりの解法を、別の切り口でも再現できるかを確認しながら、定着度を高めていく意識が必要です。
⑤過去問題とのギャップ
「SPIって高校数学の復習だよね」と思っていた学生ほど、実際の問題を見て戸惑うことが多いです。
たしかに出題内容自体は難しくないのですが、日常生活をテーマにした設問や、資料から読み取る情報処理など、想像と違う形式に「面食らう」ことがよくあります。
これは、過去のテスト経験との認識のズレが原因です。SPIの目的は「地頭力」や「状況理解力」を測ることであり、単なる計算能力ではありません。
そのことを理解していないと、「なんか難しい」という曖昧な苦手感につながってしまいます。
まずは出題の意図を知ること。そして、自分の感覚とのギャップを認めたうえで、冷静に適応していく姿勢を持つことが大切です。
SPI非言語の特徴
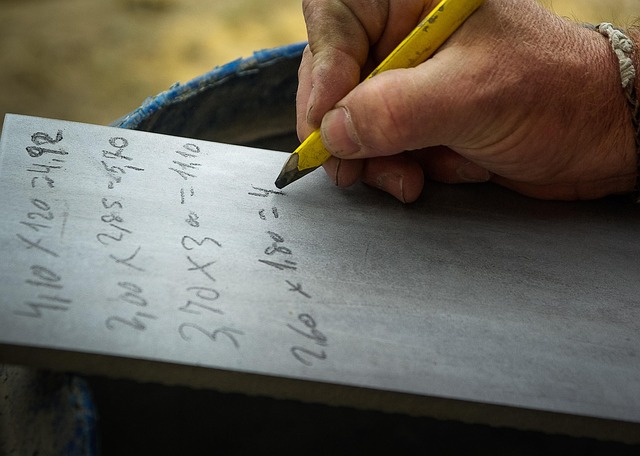
SPIの非言語分野は、就活の筆記試験で避けて通れない関門のひとつです。数学が苦手な人にとっては不安が大きいかもしれませんが、実は正しい準備と対策で誰でも乗り越えられます。
ここでは、SPI非言語の具体的な特徴を理解し、自分に合った対策方法を見つけるための第一歩として、5つの観点から詳しく解説します。
- 出題範囲は中学〜高校レベルの数学
- 計算力と論理的思考力が求められる
- 出題数が多く解答スピードが重要
- 試験の形式は受検方法によって異なる
- 企業ごとに配点や重視度が異なる
①出題範囲は中学〜高校レベルの数学
SPI非言語では、中学から高校1年程度の数学知識が中心となって出題されます。たとえば、割合や比、速さ、図形、確率、表の読み取りなどが頻出です。
つまり、高度な数学力ではなく、基本的な計算力と理解力が求められているのです。「高校数学なんて忘れた」と不安になるかもしれませんが、焦らず基礎からやり直すことで十分に対応できます。
大切なのは、限られた時間内で正確に問題を解くスキルです。難問を解ける必要はなく、むしろ基本問題を確実に処理する力が合否を左右します。
中学数学の総復習から始め、SPIの問題形式に慣れていけば、着実に得点できるようになるでしょう。
②計算力と論理的思考力が求められる
SPI非言語では、単なる計算の速さだけでなく、情報を整理して筋道立てて解決する論理的思考力も重視されます。
たとえば、「売上の増減」や「作業効率」など、状況を理解し、数字を根拠に判断する問題がよく出題されます。
このような問題では、数式をそのまま当てはめるだけでは解けません。
文章をしっかり読み、必要な情報を見極め、それを図や式に置き換える力が必要です。計算が得意でなくても、論理的に考える習慣がある人は有利になるでしょう。
問題文を丁寧に読み、条件を整理して考える習慣をつければ、得点力は自然と高まっていきます。
③出題数が多く解答スピードが重要
SPI非言語では、短時間で多くの問題を処理することが求められます。おおむね1問あたり1分以内で解かなければ、最後までたどり着くことが難しいです。
理解していても、時間内に解けなければ得点にはなりません。実際の試験では、難問に時間をかけすぎると、解けるはずの問題を落とすリスクが高まります。
そのため、「捨て問」を見極める力が非常に重要です。確実に得点できる問題を優先して解く意識を持つことが大切でしょう。
過去問や模擬試験を使い、時間を測りながら実践形式でトレーニングすることで、スピードと正確性の両方を鍛えられます。
④試験の形式は受検方法によって異なる
SPIには、「テストセンター」「ペーパーテスト」「Webテスト」など複数の受検形式があります。それぞれ出題傾向や制限時間、問題の難易度が異なるため、形式に応じた対策が必要です。
たとえば、テストセンター方式では高難度の問題も多く、スピードと正確さの両立が求められます。
一方でWebテストでは、自宅で受けられるものの、画面操作に慣れていないとスムーズに進まない可能性もあるでしょう。
受検する企業の試験形式を事前に確認し、それに合った練習をしておけば、当日のパフォーマンスが安定します。練習用のサイトや模試などを活用するのがおすすめです。
⑤企業ごとに配点や重視度が異なる
SPIは多くの企業で導入されていますが、その重視度や選考への影響度は企業によってさまざまです。
たとえば、SPIの結果が面接と同じくらい重視される企業もあれば、足切り目的でしか使わない企業もあります。
配点が高い企業では、SPI非言語で高得点を取ることが内定に直結するケースもあるでしょう。逆に、あまり重視されない企業では、基本的な点数さえ取れていれば問題にならないことも多いです。
志望先の選考情報をよく調べて、SPIの位置づけを把握することで、効率のよい学習計画が立てられます。無理なく、効果的に準備を進めてください。
SPI非言語の頻出分野

SPIの非言語分野は、就職活動を控えた大学生にとって重要な試験項目です。特に文系学生の中には数学が苦手という人も多く、非言語問題に対して不安を抱くケースが目立ちます。
ただ、出題される問題にはある程度のパターンがあり、事前に頻出分野を知っておくだけでも気持ちに余裕が持てるはずです。
ここでは、SPI非言語でよく出題される8つの代表的な分野を紹介します。各分野の出題傾向を知っておくことが、対策の第一歩になるでしょう。
- 推論問題
- 表の読み取り問題
- 集合問題
- 場合の数・確率問題
- 割合・比率問題
- 金額・料金計算問題
- 仕事算・分担計算問題
- 速度算・距離計算問題
①推論問題
推論問題は、限られた情報から正しい結論を導けるかどうかが問われます。いかにも就職試験らしい知的な印象を持たれる問題ですが、実際には複雑な計算よりも論理的な思考力が試される傾向があります。
問題文に書かれている条件を正確に読み取り、そこから導き出せる事実を丁寧に積み重ねていく必要があります。
情報が複数あると、頭の中だけで整理しようとして混乱しがちですが、焦らず一文ずつ意味を捉えていくことが大切です。
また、選択肢の中には意図的にひっかけを狙った表現も含まれていることがあるため、「すべて」「必ず」など極端な語句が使われている場合は特に注意が必要でしょう。
こうした問題は、論理的な読解力を磨く良い機会ともいえます。
②表の読み取り問題
表の読み取り問題は、企業の業績やアンケート結果など、実務にも通じる形式が多いのが特徴です。出題されるデータは一見するとシンプルですが、注意深く読み解かなければ正確な判断はできません。
表の見た目に惑わされず、まずはどんな項目が並んでいて、どういった情報がまとめられているのかをざっくり把握することが大切です。
そのうえで設問を読んで、必要な情報がどこにあるのかを的確に探していきましょう。読み飛ばしやすい単位(%や千円単位など)にも注意が必要です。
そうした細かい部分を見落とすと、答えの精度が一気に下がってしまいます。慣れないうちは緊張するかもしれませんが、焦らず着実に読み進めることが正答への第一歩といえます。
③集合問題
集合問題では、「AにもBにも属する人」や「Aには属するがBには属さない人」など、複数の条件を組み合わせて正確に整理する力が試されます。文章の中に隠れている情報をいかに把握できるかが問われます。
表現には「〜のみ」「〜以外」といった限定語が頻出するため、細かい違いにも注意が必要です。こうした言い回しに慣れていないと、正しい人数を求めるのが難しく感じられるかもしれません。
特に文系の学生にとっては見慣れない形式に見えるかもしれませんが、典型的な出題が多く、ある程度のパターンを把握しておけば慣れやすい分野です。
図を描くことは対策の一つですが、ここでは出題傾向を知ることに留めておきましょう。
④場合の数・確率問題
場合の数や確率の問題は、単に数え上げるだけでなく、条件に応じて整理する力も求められます。出題文には「順番がある」「順番は関係ない」といったヒントがあり、それに応じた考え方が必要となります。
「以上」「未満」といった範囲を示す表現も頻繁に登場しますが、読み飛ばすと条件の解釈を誤ってしまうため、注意して読むことが求められます。
また、確率の問題では、全体のパターン数と該当するパターン数をしっかりと区別しないと混乱しがちです。こうした点は計算力よりも読解力に近い要素といえるかもしれません。
数学が苦手でも、出題パターンに触れるだけでぐっと取り組みやすくなります。
⑤割合・比率問題
割合や比率の問題は、「〇〇の何%」といった表現が頻出し、一見シンプルな計算問題に見えることが多いです。しかし、読み間違いをすると正しい数値が導けなくなってしまいます。
特に「どちらを基準にしているのか」という視点が大切です。比の問題でも、部分と全体の関係を理解しなければ答えがずれてしまいます。
また、実際の問題では分数や少数の計算も含まれているため、数字の扱いに慣れておくことが必要です。社会に出てからも使うことの多いテーマなので、苦手意識はなるべく早めに払拭しておきたいところです。
まずはどういった形式で出題されるのかを知ることが第一歩となるでしょう。
⑥金額・料金計算問題
金額・料金計算の問題は、身近な題材が多いため一見すると取り組みやすく思えるかもしれません。しかし、実際には複数の条件が絡むことが多く、丁寧な整理が必要です。
たとえば「定価の〇割引」「原価の〇%増し」といった情報が組み合わされることがあり、それぞれの意味を混同してしまうと答えが大きく外れてしまいます。
また、「1個あたりの価格」なのか「合計金額」なのかといった前提を見落とすと、計算が合わなくなることも珍しくありません。
見た目以上に注意力を要する分野なので、どういったパターンが出るのかを把握しておくことが大切です。
⑦仕事算・分担計算問題
仕事算や分担計算の問題は、「1人あたりが1時間でどれだけ作業できるか」といった作業量の考え方が基本となります。最初はなじみにくく感じられるかもしれませんが、慣れると考え方はシンプルです。
また、作業を交代で行う、あるいは複数人で同時に行うといったパターンもあり、それぞれの状況に応じた考え方が求められます。
前提となる作業全体を「1」と見なす発想が理解のポイントになりますが、ここでは問題の出題傾向を把握するところまでにとどめましょう。
あまり見慣れないタイプの問題かもしれませんが、出題例を知っておくだけでも十分に準備になります。
⑧速度算・距離計算問題
速度算・距離算では、「速さ=距離÷時間」の公式を基本として、移動に関する様々な状況が問われます。たとえば、追い越し・すれ違い・往復など、日常生活でも見かける場面が題材になります。
こうした問題では、単位の違い(km/hとm/sなど)や移動時間の設定に注意しなければなりません。条件をしっかり整理できていないと、式の立て方を間違えてしまいます。
「すれ違いのときは2人の速さを足す」など、問題の構造に対する基本的な理解が求められるため、まずはどのような形式で出題されるのかを把握することが大切です。
大学生にとっては身近なテーマでもあるため、出題傾向を知っておくと取り組みやすく感じられるかもしれません。
SPI非言語の問題形式ごとの解き方のコツ

SPI非言語の問題に取り組む際は、分野ごとに異なるアプローチを理解しておくことが鍵です。
同じ数学的知識を使う問題でも、出題形式や意図によって解き方が変わるため、分野ごとの「型」を掴んでおくと、効率的に得点を積み重ねることができるでしょう。
ここでは、出題頻度の高い8つの形式それぞれに対して、実際の解答時に意識したい考え方や注意点を紹介します。理解することで苦手意識の払拭にもつながるはずです。
- 推論問題の解法と注意点
- 表の読み取り問題の解法ステップ
- 集合問題の解法パターン
- 場合の数・確率問題の解き方
- 割合・比問題の計算方法
- 金額・損益算の解法テクニック
- 仕事算・分割払いの攻略法
- 速度算・距離算の考え方
①推論問題の解法と注意点
推論問題では、与えられた文章情報をもとに妥当な結論を導き出せるかが試されます。
正解を選ぶには、各前提が示している事実を正確に読み取り、そこから論理的に導ける結論だけに限定して考えることが重要です。
注意すべき点は、情報が暗に含む関係性や順序を読み違えないことです。表面上は正しそうに見えても、前提と無関係な推測に基づいた選択肢が混ざっていることもあります。
また、「~とは限らない」「~である必要はない」など、逆説的な発想が求められる場面もあるため、単にキーワードを拾うのではなく全体の構造を把握する読解力が問われます。
論理に忠実な思考を身につけておくと、ほかの文章問題にも応用が利くようになるでしょう。
②表の読み取り問題の解法ステップ
表の読み取り問題は、限られた時間内に正確な数値判断を行う力が求められます。出題される表はシンプルながらも、実務的な内容を反映しており、問われる情報の範囲も多様です。
まず、全体のレイアウトを把握したうえで、設問に関連する情報だけを抽出するという意識が大切です。
特に複数項目にまたがる場合や、合計・平均を求める場合などは、表の構造を理解したうえで効率よく処理する必要があります。
さらに、数値の単位や桁の読み違いにも注意が必要です。見た目は単純でも、わずかな見落としが命取りになりかねません。
実務でも役立つスキルが求められる分野なので、正確さとスピードのバランスを意識してトレーニングしておきたいところです。
③集合問題の解法パターン
集合問題では、与えられた条件をもとに人数や該当項目を論理的に絞り込む力が問われます。複数のグループの重なりや排除を頭の中で整理するには、視覚的な補助が非常に有効です。
たとえば、ベン図などを活用して情報を図式化すれば、複雑な条件関係も整理しやすくなります。文章だけで処理しようとせず、一度図や表に起こしてみることで見落としを防ぐことができるでしょう。
また、「同時に満たす」「片方だけに該当する」といった条件文の言い回しには要注意です。ほんの少しの表現の違いが、求められる答えを大きく変えることもあります。
着実に整理する力をつければ、計算以上に頭を使うこの形式にも自信が持てるようになります。
④場合の数・確率問題の解き方
場合の数・確率の問題は、パターンを正しく整理する力が最も重要です。出題される条件をもとに、まず全体の可能性を把握し、そのなかから条件に一致するパターンを数え上げていきます。
間違えやすいのは、同じように見えて順番の有無が異なるケースです。順列なのか、組み合わせなのかを適切に判断する力が必要です。
また、数え漏れや重複にも注意が必要で、表や図を使って明確にしておくと安心です。
確率問題の場合、「少なくとも」「ちょうど」といった表現をどう扱うかもポイントになります。設問の意図をしっかり読み取れないと、数式以前の段階でミスをしてしまいます。
具体的に書き出して考える練習を積んでおくと、自然と理解が深まっていくでしょう。
⑤割合・比問題の計算方法
割合や比の問題では、計算そのものよりも「何を基準にしているか」を正しく認識することが大切です。
たとえば、「AはBの80%」という表現でも、AとBのどちらを軸に考えるかで求める数値が変わってきます。
また、比の問題は「部分と全体」の関係を見抜くことが必要で、比率のままにしておくのではなく、実数に置き換えて考えることでミスが減らせます。
数字に強くなるためには、分数や少数の扱いに慣れておくこともポイントです。特に、単位を統一せずに計算を始めてしまうと、途中で整合性が取れなくなるので要注意です。
実際の業務でも登場する考え方が多く含まれているため、SPI対策を通じて実践力も高めることができるでしょう。
⑥金額・損益算の解法テクニック
金額や損益算の問題は、「利益率」「割引率」「原価」といった概念が組み合わさることで、複雑に見えるケースが多くなります。
混同しがちな用語も多いため、用語ごとの意味をしっかり理解しておくことが重要です。計算の工夫としては、基準値を100に設定する方法が効果的です。
たとえば、「定価を100と仮定し、そこから〇割引」「原価に〇%上乗せ」といった形で進めれば、数値の関係が明確になります。
また、「利益が出ているのか」「損失が出ているのか」という構造も読み解く必要があり、単なる計算では対応しきれない場面もあります。
数字の操作にとどまらず、ビジネス的な視点での理解が求められる応用力重視の分野といえるでしょう。
⑦仕事算・分割払いの攻略法
仕事算では、「全体の作業量を1と仮定し、各作業者がどのくらいの割合で進められるか」という視点が基本になります。
単位時間あたりの進捗を表すという考え方が理解できれば、問題を整理しやすくなるはずです。
また、複数人での同時作業や交代作業、途中参加といったパターンでは、それぞれの貢献度を正確に加算・減算していく必要があります。
分割払いの問題では、全体金額と各支払額・回数の関係を式として整理し、利息が含まれるかどうかも意識しなければなりません。
どちらも「作業量」や「支払い」という抽象的なものを具体的な数式に置き換える力が求められるため、まずはパターンに慣れておくと安心です。
⑧速度算・距離算の考え方
速度算・距離算の問題は、「速さ=距離÷時間」の公式を出発点として、さまざまな移動パターンに応じた応用力が求められます。
追い越し、すれ違い、往復など、条件によって扱い方が大きく変わるため、構造理解が重要です。
たとえば、すれ違いのときは相手との合計の速さを使うといった基本ルールを把握しておけば、複雑な条件でもスムーズに式を立てられるでしょう。
注意したいのは、単位変換のミスです。「km/h」と「m/s」の違いを正確に理解し、問題に応じて統一しておくことが求められます。
構造と単位の両方を正しく理解できれば、速度算の問題は得点源に変わる可能性があります。
SPI非言語の基本の勉強方法

SPI非言語分野は、多くの就活生が苦手意識を持ちやすい分野です。特に文系出身の方にとっては、「数学=難しい」という先入観から敬遠されがちですが、実は中学〜高校初級レベルの内容が中心です。
ここでは、非言語問題に取り組む前段階として押さえておくべき基本的な勉強方法を、5つの観点から紹介します。焦らず、着実に基礎を固めていきましょう。
- 出題形式の理解と分析
- 公式と解法パターンの暗記
- 例題を使った基礎の反復練習
- 問題集での反復学習
- 苦手分野の可視化
①出題形式の理解と分析
SPI非言語の学習を始める際、最初に取り組むべきは出題形式を知ることです。問題には、「割合」「損益算」「速さ」「グラフや表の読み取り」「集合」など、複数のジャンルが含まれています。
これらは一見バラバラに見えても、形式に慣れてしまえば対応しやすくなるものです。最初は、出題範囲がどのように構成されているかをざっくりと把握してください。
問題集の目次やカテゴリ別の設問リストを見るだけでも、自分がどういう問題に出会うかをイメージしやすくなります。形式ごとの特徴を知っておくことで、無駄に戸惑う時間を減らせるようになるでしょう。
②公式と解法パターンの暗記
SPI非言語の問題では、一定のパターンに沿った解法や数式が頻繁に登場します。つまり、問題ごとにゼロから考えるよりも、よく使う公式や手順をあらかじめ覚えておくことで、無駄な思考時間を減らせます。
たとえば、「割合=比×基準値」「損益=売価−原価」といった公式は、使い慣れておくほど素早く答えに近づけます。
また、「条件整理→式の立て方→計算」といったプロセスにも一定の型があります。覚えるだけでなく、自分で使ってみることで記憶に定着させましょう。
暗記が目的ではなく、使いこなすための「準備作業」として取り組むのがポイントです。
③例題を使った基礎の反復練習
基礎力を養ううえで有効なのが、例題を使った反復学習です。例題は典型問題の代表であり、出題パターンの理解や考え方の練習に最適です。
いきなり応用問題に挑むよりも、まずは例題の解法をスムーズに再現できることを目標にしましょう。特に最初は、「なぜそのように考えるのか」という思考のプロセスを重視してください。
公式や計算結果だけに注目するのではなく、解説の中にある図や補足説明にも目を通すと、問題の構造が見えてきます。
同じ例題でも数日おいて再挑戦することで、本当に理解できているかの確認にもつながるでしょう。
④問題集での反復学習
ある程度例題に慣れてきたら、問題集を活用してアウトプットを強化していきましょう。市販のSPI対策問題集には、基礎から応用までの幅広い問題が収録されており、理解を深めるにはうってつけです。
ただし、数冊を手あたり次第に使うのではなく、1冊を徹底的にやり込む姿勢が重要です。1度解いた問題でも、正解できたからといって放置せず、繰り返し解いて解法を定着させてください。
さらに、解答解説の読み込みを通じて、自分の考え方と違う視点を吸収することも大切です。やり込みの過程で自然と計算力や問題処理スピードも磨かれていきます。
⑤苦手分野の可視化
勉強を続けていると、「この分野だけ何度やっても間違える」と感じる場面に出会うはずです。そうした苦手を感覚的に捉えるのではなく、記録をつけて可視化することで、改善のきっかけが得られます。
たとえば、解いた問題ごとに「正解/不正解」「分野」「ミスの種類」をメモしておくだけで、自分がどこでつまずきやすいかが見えてきます。
アプリやスプレッドシートを使って管理するのもおすすめです。苦手分野が明確になると、次に何を重点的に復習すればよいかが判断しやすくなり、勉強の効率が大きく高まるでしょう。
SPI非言語で高得点を狙うための勉強方法

SPI非言語試験で高得点を狙うためには、単に問題をたくさん解くだけでは不十分です。大切なのは、得点に直結する戦略的な勉強法を実践することです。
ここでは、基礎を押さえたうえで、さらにスコアを伸ばすための具体的な学習アプローチを5つの観点から紹介します。限られた時間を最大限に活用し、着実に得点力を高めていきましょう。
- 問題集の周回による実力強化
- 時間配分を意識した実践演習
- 模擬試験を活用した本番対策
- ミスの分析と復習による弱点克服
- 頻出単元の徹底反復による精度向上
①問題集の周回による実力強化
高得点を目指すには、問題集を使った繰り返し演習が欠かせません。1回解いただけで終わらせるのではなく、最低でも2〜3周は取り組むことをおすすめします。
初回は理解重視で進め、2周目以降では正答率やスピードを意識してください。
また、各問題に対して「なぜ間違えたのか」「どこで時間を使ったのか」など、簡単な記録を残すと次の学習に活かしやすくなります。
こうした習慣を取り入れるだけで、ただの反復から「質の高い演習」へと変化します。問題の背景や出題の意図に目を向ける姿勢が、応用力のある実力に結びつくでしょう。
②時間配分を意識した実践演習
本番のSPIでは、1問ごとにかけられる時間が限られており、慎重すぎても雑になっても得点は伸びません。ここでは、時間配分を強く意識した実践型の演習が効果を発揮します。
たとえば、「1問につき60秒」「20分で何問解けるか」など、タイマーを使いながら練習することで、解答感覚を養えます。
時間内で解けない問題があっても気にしすぎず、全体のリズム感を大切にしてください。
演習後には必ず見直しの時間を取り、「なぜ解けなかったのか」「時間がかかりすぎたのはどこか」を確認することで、時間感覚が徐々に整っていくはずです。
③模擬試験を活用した本番対策
模擬試験は、実力を確認するだけでなく、集中力や体力の調整にも役立ちます。本番と同じような制限時間・問題数で模試を行うことで、緊張感や疲労感に慣れておくことができます。
就活本番における焦りやミスを減らすには、このような「本番慣れ」も重要な準備の一つです。模試は複数回受けるのが理想ですが、そのたびに自己採点と振り返りを必ず行いましょう。
得点の変化や出題傾向、自分の弱点が見えてくることで、次の対策が明確になります。模試を「受けるだけ」で終わらせず、「学びに変える」ことを意識してください。
④ミスの分析と復習による弱点克服
高得点を狙うには、ミスの再発を防ぐことが最も効果的です。自分のミスの傾向を把握しておくことで、対策も的確に行えるようになります。
たとえば「読み間違い」「計算ミス」「単位の勘違い」といった分類をするだけでも、ミスの性質が見えてくるでしょう。
間違えた問題はその場で直すのではなく、1~2日おいて再挑戦すると、理解が定着しやすくなります。また、間違いをメモしておく「ミスノート」を活用するのも有効です。
弱点に向き合うことで、得意分野ばかりに偏る学習を避け、バランスのよい得点力を育てられます。
⑤頻出単元の徹底反復による精度向上
SPI非言語には、特定の単元が頻出する傾向があります。たとえば、「集合」「表の読み取り」「損益算」などは例年高い出題率を誇ります。
こうした単元を優先的に練習することで、少ない時間で得点アップにつなげることができます。単元ごとに演習を重ねていくうちに、自然と出題パターンに慣れていきます。
同じ形式の問題を数日おきに繰り返すことで、記憶の定着も促進されます。
完璧を目指す必要はありませんが、頻出分野での失点を最小限にする意識が、結果として全体の得点力を底上げすることにつながるでしょう。
SPI非言語の公式一覧
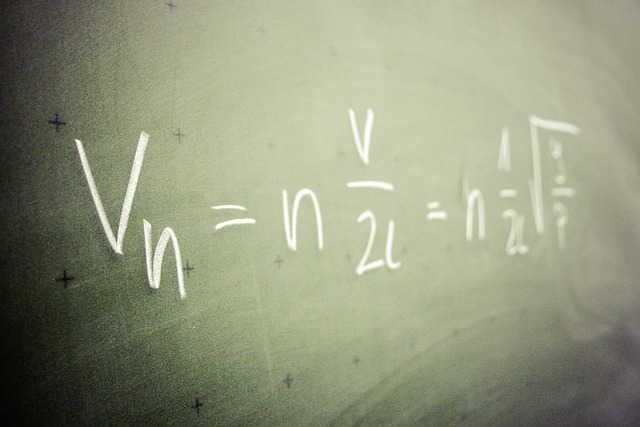
SPI非言語の問題では、特定の公式を正しく理解しているかどうかが得点に直結します。出題されやすい公式をテーマ別に整理しておくことで、確認や復習がしやすくなります。
ここではSPI非言語で頻出する公式を、ジャンルごとに紹介します。
- 割合・比の公式
- 確率・場合の数の公式
- 仕事算・分担計算の公式
- 速度算の公式(距離・時間・速度)
- 損益算・割引の公式
①割合・比の公式
割合の基本公式は「割合=比べられる量÷もとにする量」です。比は「A:B」のように表し、内項と外項の積が等しいという性質があります(A:B=C:Dのとき、A×D=B×C)。
また、「AがBの何倍か」は「A÷B」、「AはBの何%か」は「A÷B×100」で求められます。比の合成や内項・外項の関係を使った式の変形なども、計算に役立ちます。
比の値を使って割合を表すことで、複数の量の関係を簡潔に整理できます。
②確率・場合の数の公式
確率の基本公式は「起こる場合の数÷全体の数」です。
場合の数を求める際には、「順列(並べる)」「組み合わせ(選ぶ)」の考え方があり、順列は「nPr=n!/(n−r)!」、組み合わせは「nCr=n!/(r!(n−r)!)」で表します。
順列では並べる順番が関係し、組み合わせでは順番を区別しません。また、「AまたはBが起こる」場合は加法、「AかつBが起こる」場合は乗法を使うというルールもあります。
③仕事算・分担計算の公式
仕事算の基本公式は「仕事量=仕事率×時間」です。仕事率は「1÷かかる時間」で求められます。
たとえば、1人で10時間かかる作業であれば、1時間あたりの仕事率は1/10です。2人で作業をする場合は、それぞれの仕事率を足して合計の仕事率を求めます。
複数人が同時に作業する場合、合計の仕事率に対して「仕事量=1」と置いて、時間を求める形になります。
④速度算の公式(距離・時間・速度)
速度算の基本は「距離=速さ×時間」、またはその変形である「速さ=距離÷時間」「時間=距離÷速さ」です。
すれ違いや追い越しの問題では、2つの速さの和や差を用いて相対的な速さを計算します。出発時間の差があるときは、それぞれの進んだ距離を時間ごとに分けて考えます。
単位の換算(km/hとm/sなど)も頻出で、「1m/s=3.6km/h」という変換を使うこともあります。
⑤損益算・割引の公式
損益算では、「利益=売価−原価」「利益率=利益÷原価×100」「売価=原価×(1+利益率)」が基本となります。
割引に関しては、「割引後の価格=定価×(1−割引率)」という公式を使います。
また、損益率と売価・原価の関係や、複数回の割引に関する計算式なども出題されることがあります。それぞれの語句の意味と使い方に注意して公式を当てはめます。
SPI非言語に関するよくある質問

SPI非言語に関する疑問は、就活生が対策を進める中で避けて通れないテーマです。
合格基準や試験でのルール、効果的な勉強時間、数学が苦手な人でも対応できるかなど、実際の選考で焦らないために知っておくべき情報を詳しく解説します。
特に、大学3年生・4年生の皆さんにとっては、学業やゼミ、バイトと両立しながら効率よく対策を進めることがポイントです。
- SPI非言語の合格ラインはどれくらい?
- SPI非言語に電卓は使える?
- SPI非言語対策に必要な勉強時間は?
- 数学が苦手でもSPI非言語は解ける?
- SPI非言語の出題がある企業はどう見分ける?
①SPI非言語の合格ラインはどれくらい?
SPI非言語の合格ラインは、一般的に正答率60〜70%が一つの基準です。ただ、企業によって評価基準はまちまちで、人気企業や外資系などでは80%以上の得点が求められることもあります。
SPIは絶対評価ではなく、相対評価が採用されているケースが多いため、「合格点」に達するだけでは安心できません。
つまり、自分だけができてもダメ、みんなができる問題を落とすと厳しい、といった差がつく問題への対応力が問われるのです。
特にSPIは短時間で大量の問題を処理する必要があり、正確さとスピードの両方が求められます。就活生としては、模試や過去問演習を通じて、自分の現在地を知ることがとても大切です。
自信のない分野を放置せずに復習し、合格ラインを超えるための実力を一歩ずつ積み上げていくことが成功の鍵となります。
②SPI非言語に電卓は使える?
SPI非言語では、基本的に電卓の使用は認められていません。
とくにテストセンター方式やWebテスティング方式では、試験中に外部ツールの使用が禁止されており、電卓を使っていることが発覚すれば不正行為とみなされるリスクもあります。
そのため、複雑な計算でも自分の頭で素早く処理できる力が必要になります。特に、割合・比・速さ・集合などの計算問題は頻出なので、基礎的な計算能力を高めておくことが不可欠です。
ちょっとした暗算力や筆算の工夫が、合否を分ける場面もあるでしょう。学生のうちは、授業やレポートでは計算機に頼ることも多いかもしれませんが、SPI対策では「素の自分の計算力」が試されます。
だからこそ、普段から手計算の練習を重ね、時間を意識して解く習慣をつけておくことが重要です。
③SPI非言語対策に必要な勉強時間は?
SPI非言語の対策に必要な勉強時間は、一般的に20〜30時間ほどとされています。しかし、数学が苦手だったり、計算問題に苦手意識がある場合は、50時間以上の学習時間を見積もったほうが安全です。
大切なのは、ただ時間をかけるのではなく、内容の濃い学習をすることです。過去問や模試などの実践的な問題に取り組みながら、自分の間違いや傾向を分析して、効率的に対策を進めていきましょう。
また、大学の講義やゼミ、アルバイトなどで忙しい学生にとっては、1日1〜2時間ずつコツコツ継続する方法が現実的です。
スマホアプリやスキマ時間を活用した学習スタイルも効果的です。通学時間や授業の合間など、少しの時間をうまく使って取り組むことで、自然と力がついていきます。
④数学が苦手でもSPI非言語は解ける?
数学が苦手でも、SPI非言語を攻略することは十分に可能です。実際のところ、出題される問題は高校数学の基礎的な範囲が中心であり、難解な数式や高度な知識は必要ありません。
SPI非言語で重要なのは、問題の「解き方の型」を覚えることです。たとえば、割合や速さ、集合など頻出分野のパターンを繰り返し練習すれば、自然と慣れていくものです。
逆に、何も知らずにいきなり本番を迎えると、焦って手が止まってしまう可能性があります。不安な人ほど、まずは1日1問でもいいので、成功体験を積むところから始めてみてください。
「あ、意外と解けるかも」と感じられれば、自信も湧いてきます。時間がかかっても、諦めずに基礎から積み上げれば、苦手意識はきっと克服できるでしょう。
⑤SPI非言語の出題がある企業はどう見分ける?
SPI非言語が出題されるかどうかを見極めるには、企業の選考情報を事前に調べることが大切です。とくに企業の採用ページや就活口コミサイト、先輩の体験談などは有力な情報源になります。
また、文系・理系を問わず、技術職や総合職では非言語問題が出題される傾向があります。志望業界によっても対策の優先度は異なるため、まずは自分がエントリー予定の企業について調べてみましょう。
ゼミの先輩や就活支援サービスを活用して、選考体験談を集めておくのもおすすめです。情報を持っているだけで、試験本番の心構えが変わります。
出題形式がわかっていれば、そのぶん落ち着いて対策できますし、他の学生より一歩リードできるはずです。
出題傾向と対策を押さえてSPI非言語を攻略しよう

SPI非言語対策で成果を出すためには、出題傾向と自分の弱点を的確に把握し、効果的な学習を行うことが重要です。SPI非言語は中学〜高校レベルの数学を中心に、計算力と論理的思考力が求められる分野です。
数学に苦手意識がある就活生にとっては壁に感じやすい部分もありますが、頻出問題を理解し、出題形式に慣れることで十分に克服可能です。
特に、問題形式ごとの解き方のコツや、勉強の進め方を押さえて反復演習を行うことが得点アップのカギになります。
つまり、SPI非言語は決して難しすぎるものではなく、ポイントを押さえた学習を続ければ、誰でも攻略できる試験です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














