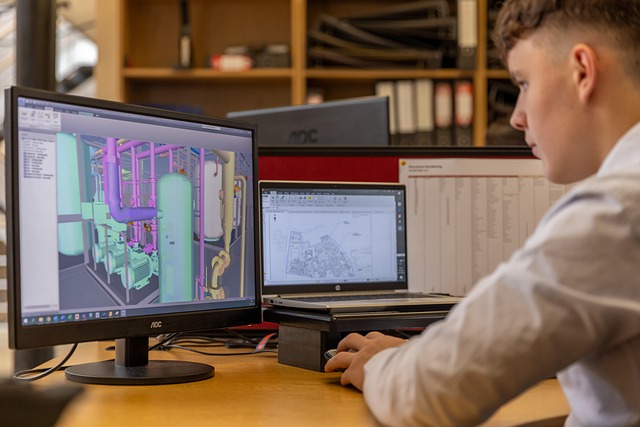縁の下の力持ちの魅力とは?就活で光る自己PRと例文集
「自分は目立つタイプじゃないし、就活でアピールできる強みなんてあるのかな…」と悩んでいませんか。実は、組織やチームを陰で支える「縁の下の力持ち」タイプの人こそ、多くの企業で高く評価される存在です。
本記事では、「縁の下の力持ち」の意味や特性、向いている仕事、そして自己PRの作り方を、豊富な例文とともに詳しく解説します。
自己PRをすぐに作れる便利アイテム
- 1自己PR自動作成ツール
- 最短3分!受かる自己PRを、AIが自動で作成
- 2ES自動作成ツール
- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
「縁の下の力持ち」とは?

就活で「縁の下の力持ち」という言葉を使う人は多いですが、その意味を正しく理解していないと、自己PRの内容にズレが生じてしまうかもしれません。
「縁の下の力持ち」とは、目立たない場所で人や組織を支える存在で、自分が表に出ることは少なくても、周囲の成功をフォローしている人を指します。誰かのために動くことにやりがいを感じる人が当てはまるでしょう。
就活では、「自分は主役ではないけれど、周囲のために動ける人間です」と伝えたいときに使われることが多いです。ただし、「サポート役です」とだけ話してしまうと、主体性に欠けると思われる可能性があります。
そのため、具体的な行動や、その結果どんな影響を与えたのかを一緒に伝えることが重要です。
このように、使い方次第で強みとして印象づけることができます。意味を理解したうえで、伝え方を工夫していきましょう。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
「縁の下の力持ち」はどんな人が当てはまる?

就活でサポート力があることを表現したいと思っても、本当にそう言えるのか不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここでは、その特徴に当てはまるかを判断しやすいよう、5つの共通点を紹介します。
- 献身的に努力を続けられる人
- 自ら進んで裏方の役割を担える人
- 周囲をよく観察しながら行動できる人
- いつでも謙虚な姿勢を忘れない人
- サポート役としてのやりがいを感じられる人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①献身的に努力を続けられる人
「縁の下の力持ち」が強みの人は、目立つ成果を求めるのではなく、地道な努力をコツコツと続けられるところが特徴です。
たとえば、チームの片付けや備品管理を任されても、率先して取り組む人は信頼されやすいでしょう。ただし、「頑張った」と言うだけでは自己PRにはなりません。
どう工夫したか、その結果どうなったのかを具体的に伝えることで、努力が価値あるものとして相手に伝わります。
②自ら進んで裏方の役割を担える人
指示を待たずに、自分から動ける人はまさに「縁の下の力持ち」と言えるでしょう。人手が足りないと感じたら自然に補助に入る、そんな行動ができる人は組織の中で重宝されます。
裏方の役割は目立ちにくくても、チームの円滑な運営には欠かせない存在です。アピールする際は、どのように自発的に行動し、結果的にどんな影響を与えたかをセットで伝えるようにしてください。
③周囲をよく観察しながら行動できる人
周囲の状況に気を配り、必要なタイミングで適切な行動ができる人も、「縁の下の力持ち」の素質があります。
たとえば、困っている人に声をかけたり、進行が遅れている場面で自然にフォローに入ったりと、観察力を生かした行動は高く評価されます。
大切なのは、ただ気づくだけでなく、すぐに行動に移せることです。相手の立場を考えて動ける力は、十分アピール要素になります。
④いつでも謙虚な姿勢を忘れない人
どれだけ周囲に貢献していても、それをひけらかさない姿勢は、多くの人に信頼される要因になります。
人や組織を支える姿勢を評価される人は、成果を声高に主張するのではなく、自然体でフォローする力を持っています。ただし、就活の場では自分の行動を客観的に伝えることが大切です。
謙虚な姿勢を保ちつつ、どんな貢献をしてきたのかを具体的に説明することで、控えめでもしっかり印象に残る自己PRが可能でしょう。
⑤サポート役としてのやりがいを感じられる人
誰かを支えることにやりがいを見いだせる人も、該当します。たとえば、後輩にアドバイスをして「ありがとう」と言われたときや、チームが成功した瞬間に喜びを感じた経験はありませんか?
そのようなエピソードは、就活で大きな強みになります。やりがいを感じた理由や、そのときの気持ちを丁寧に伝えることで、相手に共感を持ってもらえる自己PRになるでしょう。
縁の下の力持ちが向いている仕事

サポート力が強みということを就活で伝えるには、どのような職種や働き方が合っているのかを知ることが大切です。
ここでは、裏方としてチームや組織を支えることにやりがいを感じる人に向いている仕事を3つ紹介します。
- サポート力が求められるバックオフィス系の仕事
- チームと顧客をつなぐ支援系の仕事
- チームプレイが重視される職場環境の仕事
①サポート力が求められるバックオフィス系の仕事
バックオフィスの仕事は、表舞台に立つことは少ないですが、企業を内側から支える大切な役割です。たとえば、人事や経理、総務などが挙げられます。
これらの仕事では、チーム全体の動きをスムーズにするための気配りや、丁寧で正確な作業が求めらるでしょう。特に、ミスが許されない場面も多いため、責任感や集中力のある人が向いています。
直接目立つことは少なくても、自分の行動が誰かの助けになり、会社全体を動かす力になるという実感を持てるのが魅力です。
②チームと顧客をつなぐ支援系の仕事
営業職のように直接顧客とやり取りする立場ではなく、営業をサポートする仕事や、システムの運用・保守なども、「縁の下の力持ち」として力を発揮できる職種です。
営業事務やカスタマーサポートなどでは、社内外のやり取りを円滑に進める工夫や気配りが求められます。
表には出なくても、自分の対応が信頼につながったり、チームの成果を後押ししたりすることが多くあるでしょう。感謝される場面も多いため、やりがいを感じながら働けます。
③チームプレイが重視される職場環境の仕事
個人の成果よりも、チームとしての達成を重視する人には、連携が欠かせない職場が合っています。たとえば、教育・医療・介護・製造などの分野では、まわりとの協力が何より大切です。
自分の役割を理解しながら、必要に応じて自然とフォローに入れる人は、こうした現場でとても頼りにされます。
目立つことよりも、信頼や貢献が評価される風土の中では、控えめな性格の人でも力を発揮しやすいはずです。働くことで人の役に立ちたいという想いを持つ人におすすめします。
アピールNG!サポート力が評価されにくい仕事

「縁の下の力持ち」の特性は、どんな職種でも評価されるわけではありません。中には、自ら前に出て活躍することが求められる仕事もあります。
ここでは、サポート力が評価されにくい職種の具体例を紹介します。
- 積極性が必要な営業や企画系の仕事
- リーダーシップが求められるマネジメント職系の仕事
- 常に自発的なアイデア発信が求められるクリエイティブ系の仕事
①積極性が必要な営業や企画系の仕事
営業や企画の仕事では、自ら積極的に動き、提案や交渉を行う姿勢が重要です。
このタイプの人は、周囲のサポートに回ることにやりがいを感じやすい反面、前に出て相手とやり取りする場面では緊張しやすい傾向もあります。
こうした職種では、行動力や自発的な提案が特に評価されやすいため、自分の良さが伝わりにくいかもしれません。
自分の強みを無理に押し出すよりも、自然に活かせる環境を選ぶほうが、働く上での納得感にもつながるでしょう。
②リーダーシップが求められるマネジメント職系の仕事
マネジメント職では、チーム全体をけん引するリーダーシップが求められます。このタイプの人は、チームの調和を支える力に長けていても、リーダーとして前に立つ役割では負担を感じることがあるでしょう。
もちろん、縁の下からフォローする姿勢も重要ですが、明確な意思決定や方向づけを行う役割には向かない場合もあります。
自分にとって無理のない働き方を考えるためにも、役割の特性はしっかりと理解しておく必要があるでしょう。
③常に自発的なアイデア発信が求められるクリエイティブ系の仕事
クリエイティブ系の仕事では、常に新しいアイデアや表現を自分から発信する力が求められます。
このタイプの人は、誰かのアイデアを支える側に回るほうが得意な場合が多く、独自性やひらめきが必要な場面ではプレッシャーを感じやすいかもしれません。
もちろん、制作の進行を支持するポジションでは適性がありますが、常に発信し続ける立場を目指す際は、自分に合っているかを慎重に見極めてみてください。
縁の下の力持ちをアピールする3ステップ

就活で「縁の下の力持ち」という強みを伝えるには、話し方の順序や内容の工夫が大切です。
ここでは、採用担当者に「縁の下の力持ち」をアピールするための、3つのステップを紹介します。
- サポート力が強みだと結論づける
- 強みを証明する具体的なエピソードを伝える
- 入社後に縁の下の力持ちとして活躍するイメージを述べる
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
①サポート力が強みだと結論づける
最初に、自分が「縁の下の力持ち」であることをはっきりと伝えましょう。就活では第一印象が非常に重要なので、話の冒頭で強みを明言することによって、面接官の記憶に残りやすくなります。
また、「なぜそう思ったのか?」という根拠を簡潔に添えることで、自己分析ができている印象を与えられるでしょう。
たとえば、「私はチーム全体の成功を優先して裏方に徹する場面が多く、その姿勢を評価されることが多かったため、縁の下の力持ちタイプだと自覚しています」といったように、実体験に基づいた説明があるとより説得力が増します。
②強みを証明する具体的なエピソードを伝える
次に、サポート力という強みを裏づけるためのエピソードを紹介してください。実際に誰かをサポートした経験や、チームを支えるために自ら進んで行動した場面などが効果的です。
目立つ成果がない場合でも、周囲から感謝された出来事や、自分の働きで環境が改善されたことなどを丁寧に語れば、その価値は十分に伝わります。
たとえば「大会直前にチームメンバーの代わりに裏方作業を担ったことで、全体の進行がスムーズになり、後日リーダーから感謝された」といったストーリーは、あなたの貢献度を明確に示してくれるでしょう。
③入社後に縁の下の力持ちとして活躍するイメージを述べる
最後に、自分の強みをどのように仕事に活かしていくかを具体的に伝えましょう。面接官にとっては「入社後に活躍してくれるかどうか」が最大の関心ごとです。
たとえば、「周囲の変化に常に気を配り、困っている人を見つけたらすぐにサポートするよう努めたい」など、自発的に支援する姿勢を示すと好印象につながります。
また、「裏方の視点から業務改善につながる工夫を続け、チーム全体がより効率的に動けるよう支援したい」といった具体的な貢献イメージがあれば、面接官の中であなたの働く姿がリアルに想像できるようになるでしょう。
【経験別】縁の下の力持ちをアピールする自己PR例文

自己PRで「縁の下の力持ち」という強みをアピールするには、自分の経験に基づいた具体的なエピソードを伝えることが大切です。
ここでは、学生生活のさまざまなシーンにおける実例を紹介します。自分に近いシチュエーションを見つけて、自己PRの参考にしてください。
- サークル活動でサポート力を発揮した例文
- 部活動(プレイヤー)として貢献した例文
- 部活動(マネージャー)として支えた例文
- ボランティア活動でのサポート経験を伝える例文
- 留学生活で裏方として行動した場面の例文
- 飲食店アルバイトでの体験を伝える例文
- 塾講師アルバイトで指導支援をした経験の例文
- アパレル販売でチームをフォローした場面の例文
- インターンでのバックアップ業務を工夫した際の例文
- ゼミ活動で陰から支えた行動を伝える例文
また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①サークル活動でサポート力を発揮した例文
大学時代のサークル活動では、多くの学生がチームでの協力を経験します。ここでは、目立たない役割でもチームに貢献できる姿勢をアピールする自己PRの例文を紹介しています。
| 私は大学のダンスサークルで、イベント運営を担当した経験があります。 人前で踊ることは得意ではありませんでしたが、メンバー全員が安心して本番に臨めるよう、照明や音響、タイムスケジュールの調整など裏方の仕事に力を入れました。 特に、当日はトラブルが起きないよう事前に何度もリハーサルを重ね、他のメンバーが気づかない細かい点まで準備することに。 その結果、本番は大きなミスもなく終えることができ、出演したメンバーから「安心してパフォーマンスできた」と感謝の言葉をもらいました。 この経験から、私は目立つ役割でなくてもチームの成功に貢献できることにやりがいを感じ、状況を見て必要な行動を取ることが自分の強みだと気づきました。 |
この例文は「裏方の貢献」を主軸に置きつつ、実際の行動と結果をしっかり伝えている点がポイントです。自分が行った工夫や周囲の反応を具体的に書くことで、説得力のある自己PRになります。
②部活動(プレイヤー)として貢献した例文
プレイヤーとして活動していても、裏方としてチームを支える姿勢は十分にアピールポイントになります。
ここでは、部活動で自ら目立つというよりも、周囲を支えることで貢献した経験を活かした自己PRの例を紹介しましょう。
| 私は大学のテニス部に所属し、プレイヤーとして練習や試合に取り組んでいました。ただ、部内には実力の高い選手も多く、自分が常に試合に出られるとは限りませんでした。 そこで私は、練習メニューの調整や、練習用具の準備、試合中のサポートなどを率先して行い、チーム全体が円滑に活動できるよう努めたのです。 特に新人のサポートには力を入れ、練習後には声をかけてアドバイスやフォローを行いました。 その結果、部員同士の信頼関係が深まり、主将から「見えないところでの支えがチームをまとめている」と評価していただきました。 こうした経験から、私は自分の役割を理解し、組織全体のために動けることが自分の強みだと実感しています。 |
この例文では、「プレイヤー=目立つ役割」ではなく、「チームを支える行動」に焦点を当てています。役割の大小ではなく、チームにどう貢献したかを明確に伝えることが成功のカギです。
③部活動(マネージャー)として支えた例文
部活動でマネージャーを経験した人は、日々の地道なサポートや気配りの積み重ねを通じて「縁の下の力持ち」としての強みを発揮できます。ここでは、マネージャー経験を活かした自己PR例文を紹介しています。
| 私は、大学のサッカー部でマネージャーを務めた経験があります。選手が練習や試合に集中できるよう、備品の準備やスケジュール管理、体調管理の声かけなど、裏方の仕事に力を入れていました。 特に遠征時には、前日の持ち物リストを作成し、当日のスムーズな移動ができるようタイムテーブルを何度も見直しました。その結果、トラブルなく移動でき、試合に集中できる環境を整えられたと感じています。 また、選手が落ち込んでいるときにはさりげなく声をかけるなど、精神的なサポートも意識しました。 これらの経験から、私は人を支えることにやりがいを感じ、自らの役割を理解して行動できる力が自分の強みだと実感しています。 |
この例文は、マネージャーという立場からチームを支える具体的な行動と成果を丁寧に示しています。場面の工夫や気配りの描写が、サポート力をよりわかりやすく伝えるポイントです。
④ボランティア活動でのサポート経験を伝える例文
ボランティア活動は、「縁の下の力持ち」としての行動が自然に求められる貴重な経験です。今回は、支える姿勢を大切にしたボランティア活動をテーマにした自己PR例文を紹介します。
| 私は大学2年の夏に、地域の子ども向けイベントの運営ボランティアに参加したことがあります。 主な役割は受付や会場の誘導、備品の準備などで、目立つ仕事ではありませんでしたが、来場者が安心して楽しめるように細部まで気を配ることを意識しました。 特に、雨が降りそうだった日のイベントでは、急遽屋内に会場を変更する必要があり、スタッフ全員が慌ただしく動く中で、私は進行表をもとに各担当へ情報を正確に伝える役割を担うことに。 その結果、混乱を最小限に抑え、無事にイベントを終えることができました。 この経験から、私は目立たない場面でも状況を見ながら周囲を支える行動にやりがいを感じるようになり、それが自分の強みだと自覚するようになりました。 |
この例文では、ボランティア活動という非日常の場面で発揮したサポート力を具体的に描いています。状況判断や行動の工夫を入れると、より説得力が増します。
⑤留学生活で裏方として行動した場面の例文
留学先での生活では、言葉の壁や文化の違いに直面しながらも、周囲を支える行動が求められる場面があります。ここでは、留学中にチームを支えた経験を活かした例文を紹介しましょう。
| 私は大学3年の夏に、3週間の短期留学プログラムに参加したことがあります。現地での課題は、他大学の学生と混成チームを組み、地域の課題について英語で発表するというものでした。 私は英語力に自信がなかったため、リーダーを務めるよりも、進行の整理やメンバー間の調整、資料作成のサポートなど裏方の仕事を担当。 特に、意見がぶつかった場面では、一人ひとりの意見を丁寧に聞き取り、翻訳を交えながら調整を行いました。その結果、全員が納得できる発表内容にまとまり、発表も成功しました。 この経験を通じて、私は表に立たなくてもチーム全体の成果に貢献できることに喜びを感じ、自分の強みは周囲を支える行動にあると実感しています。 |
この例文では、留学中という特別な環境でも「支える姿勢」を発揮した点がポイントです。語学や異文化をテーマにする場合は、チーム内でどう役割を果たしたかに焦点を当てると良いでしょう。
⑥飲食店アルバイトでの体験を伝える例文
飲食店でのアルバイト経験は、接客だけでなくチーム全体を支える行動が求められる場面が多くあるでしょう。ここでは、目立たない業務を通じて「縁の下の力持ち」として活躍したエピソードを紹介します。
| 私は大学時代、駅前のカフェでホールスタッフとしてアルバイトをしていました。接客はもちろんですが、店全体のスムーズな運営を意識して、洗い場や備品の補充、キッチンとの連携にも積極的に取り組みました。 特に土日などの忙しい時間帯には、料理が遅れているテーブルをフォローするためにドリンクを先に出すなど、細かな配慮を意識して動いていたのを覚えています。 また、新人スタッフが不安そうにしているときには、声をかけてマニュアルの確認を手伝うなど、チーム全体の雰囲気作りにも努めました。 その結果、店長から「あなたがいると安心できる」と評価していただき、裏方としてチームを支えることの大切さと自分の強みに気づくことができました。 |
この例文は、目立たない業務を丁寧に行う姿勢と、それがチームにどう貢献したかを具体的に伝えています。接客以外の気配りや行動にも触れることで、自己PRに深みが出ます。
⑦塾講師アルバイトで指導支援をした経験の例文
塾講師のアルバイトでは、教えるだけでなく、生徒一人ひとりの状況を見ながら丁寧にサポートする力が求められます。ここでは、目立たない支援の中でサポート力を発揮したエピソードを紹介しています。
| 私は大学時代、個別指導塾で講師として中学生を担当した経験があります。 成績が思うように伸びずに悩んでいた生徒の担当になった際、ただ教えるだけではなく、学習計画の見直しや自習の時間割作成、授業外のフォローまで行いました。 また、生徒がモチベーションを維持できるように、毎週の進歩を記録して一緒に確認するなど、精神面でのサポートも意識しました。 その結果、3か月後には成績が安定し、生徒や保護者から「丁寧に見てくれてありがとう」と感謝の言葉をいただきました。 この経験から、私は目立たない部分でも信頼関係を築き、相手の成果を支えることに喜びを感じるようになり、自分の強みとして大切にしています。 |
この例文では、塾講師としての教える役割に加え、裏方としてのサポートや気配りを具体的に示しています。生徒目線で考えた行動を盛り込むことで、説得力が高まります。
⑧アパレル販売でチームをフォローした場面の例文
アパレルショップでのアルバイトでは、接客だけでなく裏方として店舗全体を支える行動も重要です。ここでは、アルバイトでチームを支えた具体的な体験を紹介します。
| 私は大学時代に、アパレルショップでアルバイトをしていた経験があります。 店舗では接客に注目が集まりがちですが、私は在庫整理やディスプレイ変更、スタッフ同士の連携を大切にして、店舗全体が円滑に回るよう意識して行動していました。 特に新作の入荷時には、限られた時間の中で素早く商品を陳列し、他のスタッフがスムーズに接客に集中できるように準備を整えたこともあります。 また、後輩スタッフが接客で困っている様子を見かけた際には、声をかけてフォローに入り、接客後には振り返りの時間もつくるようにしました。 こうした行動が評価され、店長から「目立たないけれど店舗を支える存在」と言っていただけたことが自信につながりました。 |
この例文では、接客以外の業務に焦点を当て、どのようにチームをフォローしたのかが明確になっています。アパレルの現場では、裏方の貢献も自己PRに活かせる好例です。
⑨インターンでのバックアップ業務を工夫した際の例文
インターンでは、限られた時間の中でどれだけチームに貢献できるかが問われます。ここでは、目立つ成果だけでなく、裏方としての工夫と支援で評価された経験を紹介しましょう。
| 私は、大学4年時に参加した2週間のインターンシップで、営業チームのサポート業務を担当した経験があります。 主な業務は、提案資料の修正やデータの整理などで、外に出ることはほとんどありませんでしたが、社内で効率よく動けるよう意識して行動しました。 特に、先輩方が時間に追われていることに気づき、使用頻度の高いテンプレートや過去資料を分類・整理して、すぐに取り出せるよう工夫していたのを覚えています。 その結果、資料作成の時間が短縮できたと感謝され、最終日のフィードバックでは「自分の役割を理解し、自ら動ける人」と評価をいただきました。 この経験から、私はチームの土台を整えることにやりがいを感じ、それが自分の強みであると実感しました。 |
この例文では、表に出ないインターン業務の中でも、自発的な気づきと工夫で貢献した点をアピールしています。裏方での行動も、改善や支援の視点を入れることで強みに変えられます。
⑩ゼミ活動で陰から支えた行動を伝える例文
ゼミ活動では、リーダーや発表者の陰で支える役割が重要になる場面も多いです。ここでは、目立たないポジションからチームに貢献した行動を紹介します。
| 私は大学のゼミで、卒業研究に向けたグループ発表を行いました。私は発表者ではありませんでしたが、全体の進行管理と資料作成の取りまとめを担当。 スケジュール通りに進まないことも多く、メンバーの予定を調整しながら、各担当の進捗を確認し、必要に応じてサポートに回るよう努めました。 また、全体のストーリーが一貫するよう、資料を見直して構成を整えることにも力を入れました。 その結果、発表当日は大きなトラブルもなく、教授から「チームの連携がよく取れていた」と評価されたのがよい思い出となっています。 この経験を通じて、自分は前に出るよりも、周囲を支えながら全体をまとめることにやりがいを感じるタイプだと実感しました。 |
この例文では、ゼミ活動での裏方としての行動を、チーム全体への影響とともに表現しています。発表者でなくても、チームの成果に貢献できたことを丁寧に伝えるのがコツです。
縁の下の力持ちが伝わらない自己PRのNG例

せっかくの強みであっても、伝え方を間違えると「縁の下の力持ち」が評価されにくくなります。
ここではサポート力の特性をうまく伝えられず、逆効果になってしまう自己PRの失敗例を紹介しましょう。
- 具体性に欠ける曖昧な自己PRは避ける
- ネガティブな印象を与える表現は控える
- 「サポート=雑用」と誤解される伝え方は避ける
①具体性に欠ける曖昧な自己PRは避ける
「私は、縁の下の力持ちタイプです」などの、具体性に欠けた曖昧な自己PRは避けましょう。採用担当にあなたの価値が伝わりにくくなります。
たとえば「チーム全体の成功を意識して行動しました」と話したとしても、それだけでは「どのような行動だったのか」「どんな場面だったのか」がイメージしにくいため、印象に残りません。
自己PRでは、必ず「いつ」「どこで」「誰に対して」「何をしたか」まで具体的に語るようにしましょう。さらに、自分の行動によってどのような効果や反応があったかまで伝えると、より説得力が増します。
たとえ成果が定量的に表しにくい場合でも、周囲の反応や変化を交えることで、あなたの貢献がしっかり伝わるようになるでしょう。
②ネガティブな印象を与える表現は控える
「自分には目立った実績がなく、裏方を担当してきました」といった表現は、つい謙遜のつもりで使ってしまいがちですが、採用担当者に「自信がない」「主体性がない」といったマイナスイメージを与えてしまうリスクがあります。
たとえ表立った功績がなくても、支え役としての存在価値を前向きに伝えることが重要です。
たとえば「チームが円滑に進むよう、細かな部分に気を配って行動してきました」など、自らの姿勢や工夫をポジティブに語るだけでも印象が変わります。
裏方であることに自信を持ち、自分の役割をどう捉えていたかを伝えることで、誠実さや責任感といった評価につながる可能性が高まるでしょう。
③「サポート=雑用」と誤解される伝え方は避ける
雑用と誤解されるような表現は避けましょう。自分の行動を過小評価してしまう結果になりかねません。
どんな業務にも目的や意図があるはずなので、それを明確にしたうえで伝えることがポイントです。
たとえば「チームがスムーズに進行するよう、会議資料の準備や進行補助を行いました」といったように、単なる作業ではなくチームへの影響を含めて話すと、評価されやすくなります。
特に就活では、「なぜその行動を選んだのか」「結果的にどんな効果があったのか」という文脈を示すことで、サポート業務の意義が伝わりやすくなることも。
雑用のように見える仕事でも、伝え方次第で十分な強みに変えられるでしょう。
縁の下の力持ちを自己PRで伝える際の注意点

サポート役の魅力を正しく伝えるためには、言葉選びやエピソードの描き方に工夫してください。
ここでは、「縁の下の力持ち」を自己PRで伝える際の注意点を紹介します。以下の5つのポイントを押さえることで、説得力のある自己PRになるでしょう。
- 面接で他の回答と矛盾しないようにする
- サポート役でも主体性を感じさせる伝え方をする
- 消極的と受け取られないようにカバーする
- 自分の成果ばかり強調しないようにする
- 評価されづらい行動も言語化してアピールする
①面接で他の回答と矛盾しないようにする
自己PRで伝える内容は、志望動機や学生時代の経験など他の質問と矛盾がないように気をつけてください。
たとえば「サポート役としての強み」を語る一方で、「常に前に立って指示を出していた」などと主張してしまうと、一貫性に欠けてしまいます。
あなたの価値観や行動スタイルを軸に、ストーリー全体に整合性があるかを事前に確認しておくことが大切です。
②サポート役でも主体性を感じさせる伝え方をする
サポートする立場にいたとしても、ただ指示を待っていたのではなく、自分から働きかけたことを伝えてください。
「声をかけて状況を把握した」「自分から改善案を提案した」など、行動の中に自発性が感じられると説得力が増します。受け身な印象を与えずに、積極的な姿勢をアピールすることが効果的です。
③消極的と受け取られないようにカバーする
「縁の下の力持ち」は「前に出るのが苦手」という印象を持たれやすい表現でもあります。そこで、行動力や判断力など、積極的な面も合わせてアピールしましょう。
たとえば「全体の進行を見ながら裏側で準備を進めた」「誰よりも早く課題に気づき、動いた」といった具体的な行動があると、前向きな印象につながりやすくなります。
④自分の成果ばかり強調しないようにする
サポート役の魅力は、チーム全体のために貢献する姿勢にあります。自分だけの成果ばかり強調してしまうと、協調性に欠ける印象を与えるおそれがあるかもしれません。
むしろ「他メンバーが成果を出せるように、どう支えたか」など、全体の成功に向けた取り組みを語ることで、「縁の下の力持ち」としての価値がより伝わるでしょう。
⑤評価されづらい行動も言語化してアピールする
裏方の行動は目立ちにくく、評価されにくい傾向にあります。だからこそ、あなたがどんな意図を持って動いたのかを、言葉でしっかり説明することが大切です。
たとえば「会議資料をまとめる」という行動も、「議論がスムーズに進むように見やすさを工夫した」と伝えるだけで、印象が大きく変わります。地道な努力こそ丁寧に言語化して伝えてください。
就活で使える「縁の下の力持ち」の言い換え一覧

「縁の下の力持ち」という表現は、自分のサポート力や貢献姿勢をアピールするうえで非常に有効ですが、就活の場では言い換え表現を使うことで、より洗練された印象を与えることができます。
また、似たような表現が繰り返されるエントリーシートや面接では、語彙の工夫が個性を引き立てるポイントにもなるでしょう。
ここでは、「縁の下の力持ち」の言い換えをご紹介します。
<言い換え一覧>
- 裏方として支える存在
- チームの潤滑油
- 陰で支えるタイプ
- 支援型リーダー
- 調整役に徹するタイプ
- 全体最適を意識して動ける人
- 裏方のプロフェッショナル
- サポートに長けた協力者
- 影で成果をフォローする存在
- 組織を支える縁の下のエンジン
大切なのは、ただ表現を変えることではなく、あなたの性格や行動スタイルに合った言葉を選ぶことです。意味を取り違えず、面接官に伝わりやすい言い回しを心がけてください。
「縁の下の力持ち」に関するよくある質問

就活で「縁の下の力持ち」をアピールするにあたり、「この言葉を使うと地味に思われないか」と自信がない人もいるかもしれません。
ここでは、就活生からよくある疑問を4つ取り上げ、わかりやすく解説します。
- 就活でアピールすると地味な印象にならない?
- 「協調性」や「チームワーク」とどう違う?
- 目立つ成果がなくても「縁の下の力持ち」は伝えられる?
- エピソードが思いつかないときはどうすればいい?
①就活でアピールすると地味な印象にならない?
たしかに「縁の下の力持ち」という言葉には、あまり目立たず地味な印象を持たれることがあります。
ですが、それは表面的なイメージにすぎません。自分の働きが誰かの成功やチームの成果を支えていたことを丁寧に伝えれば、むしろ「信頼できる」「安心して任せられる」といった好印象につながります。
特に企業では、表に出るだけでなく、全体のバランスを取れる人材も重要視されています。
役割の華やかさにとらわれず、自分の行動がどんな影響をもたらしたのか、どれほど周囲の支えになったかをしっかり言葉で表現することが、印象アップのカギとなります。
②「協調性」や「チームワーク」とどう違う?
「協調性」や「チームワーク」と「縁の下の力持ち」は、どれも集団の中でうまくやっていく力を示していますが、そのニュアンスには違いがあります。
「協調性」は周囲と調和を保ち、対立せずに行動できることを指し、「チームワーク」はお互いの力を合わせて成果を出す姿勢です。
一方で「縁の下の力持ち」は、自分が一歩引いた立場で周囲をよく観察し、必要なときに必要な行動を取る、より能動的で気配りに富んだ特性を含みます。
つまり、ただ従うのではなく、誰かを支えるために自ら動くことに重きを置いた表現だといえるでしょう。
③目立つ成果がなくても「縁の下の力持ち」は伝えられる?
もちろん伝えられます。自己PRで重要なのは、数字や結果だけではありません。
たとえば「部活動でキャプテンを支える立場として、練習メニューを調整し全体の士気を保つよう努めた」といったように、誰かのために尽力した過程を丁寧に語れば、十分に評価されます。
また、裏方の行動によって周囲の信頼を得たエピソードなども強みになるでしょう。
目立つ成果がなくても、「どう考えて、どう行動し、どんな反応があったか」を明確に語ることで、あなたの「縁の下の力持ち」としての魅力が伝わりやすくなります。
④エピソードが思いつかないときはどうすればいい?
もし、今すぐに印象的なエピソードが思い浮かばない場合は、まず日常の中で「誰かを支えた場面」や「周囲のために行動した経験」を思い出してみましょう。
サークルでの準備作業、アルバイト先での気配り、家族や友人とのやり取りの中にも、ヒントは隠れています。
無意識のうちに行っていた行動を意識的に振り返ることで、自分の中の強みが見えてくることもあります。
特別な成果にこだわる必要はありません。あなたらしい支え方に気づくことが、魅力的な自己PRにつながる第一歩です。
就活で「縁の下の力持ち」の魅力を伝えるにはどうすればいいか

「縁の下の力持ち」という言葉は、表立った活躍ではなく裏方として支える人を指します。就活においても、そうした強みを持つ人材はチームに不可欠です。
しかし、伝え方を間違えると「地味」「消極的」と受け取られるおそれもあります。だからこそ、自分の行動に主体性ややりがいがあることを具体的なエピソードで示す必要があるでしょう。
自分がどのような場面で支えとなり、どう行動したのかを言語化することが、面接官の評価につながるポイントです。
サポート力を効果的にアピールするには、役割の重要性や達成感、仕事との相性まで丁寧に伝えることが成功のカギです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。