内定とは?内々定や採用との違いと承諾・辞退の流れを解説
「内定って具体的にどういう意味?内々定や採用とは何が違うの?」
就活を進める中で耳にすることが多い「内定」ですが、その定義や承諾・辞退のルールを正しく理解している人は意外と少ないものです。
そこで本記事では、内定の正しい意味や内々定・採用との違い、承諾や辞退の流れ、さらに内定後にやるべき準備までを分かりやすく解説します。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
内定とは

就職活動における「内定」とは、企業が応募者に対して「採用します」と意思を伝えることを意味します。内定は単なる合格通知ではなく、法的にも意味を持つ大事なステップです。
内定は口頭でも成立する可能性があるという点も知っておきましょう。たとえば面接の場で「ぜひうちに来てください」と言われたとき、それが内定とみなされることもあります。
ただし、通常は「内定通知書」という書面が発行され、両者の認識を明確に一致させることが一般的です。注意したいのは、「内定=採用決定」だと早合点しないでくださいね。
どのタイミングで、どのような伝達があったかを冷静に確認するようにしましょう。
特に複数社から内定を受けた場合や、内々定との違いに戸惑う場面では、自分が何に同意したかを把握しておく必要があります。
内々定や採用との違い

「内定」「内々定」「採用」は、就活でよく聞く言葉ですが、それぞれ意味が異なります。「内定」は、企業が正式にあなたを採用すると決めたことを通知する段階であり、労働契約が成立した状態を意味します。
これに対して「内々定」は、企業が採用の意志を非公式に伝える段階で、法的な拘束力はまだありません。また、「採用」という言葉は、人材を集めて選考し、内定・入社まで進める一連の活動全体を指します。
つまり、「内定」や「内々定」は「採用活動」の中の一部という位置付けです。「内々定」はあくまで企業側の意志表示にすぎないという点に注意してください。
状況によっては取り消しになることもあり得ます。内定と誤認して、準備を進めてしまうとトラブルの原因にもなりかねません。こうした用語の違いを理解し、状況に応じた正しい判断ができるようにしておきましょう。
内定が出る時期

内定が出るタイミングを知っておくと、就活のスケジュールを立てやすくなります。特に「内々定」と「正式な内定」は出される時期が異なるため、それぞれの違いを理解することが重要です。
ここでは、企業が内定を出す一般的な時期について解説します。
- 正式な内定は10月以降が基本
- 内々定は3月〜10月に出ることが多い
①正式な内定は10月以降が基本
正式な内定は、例年10月1日以降に出されるのが基本とされています。これは、文部科学省や経済団体が定めた「採用選考に関する指針」に基づくもので、学生の学業への影響を減らす目的があるのです。
多くの企業はこのルールに従っており、書面で内定通知を出すのが一般的です。ただし、企業によっては10月より前に「内定を出します」と口頭やメールで伝えることもあります。
しかしこの場合、正式な書類がない限り、内定とみなすのはやや不確かです。実際には「内々定」として扱われることが多く、誤解が生じやすいので注意してください。
正式な内定には、雇用条件や入社日などが明記された内定通知書が伴います。これを受け取ることで、はじめて企業との間に共通認識が生まれるのです。
口頭のやりとりだけでは不十分なため、必ず書面の有無を確認するようにしましょう。
②内々定は3月〜10月に出ることが多い
内々定は、企業が本格的な内定通知の前に「あなたを採用する予定です」と伝える非公式なものです。一般的には3月から10月にかけて出されることが多く、早期選考やインターンを通じて得られるケースもあります。
内々定をもらうと、安心感から就活を終えたくなる人もいるかもしれませんが、慎重さが必要です。なぜなら、内々定は法的な拘束力が弱く、企業の都合で撤回される可能性があるから。
また、「ぜひうちに来てください」などの言葉があっても、それが内々定なのか単なる好意的な評価なのか、はっきりしない場合も多いでしょう。
このようなときは、担当者に内容を確認し、不明な点はそのままにしないことが大切です。内々定を受けた後も、他の企業の選考を続けることは可能です。
比較のうえで最善の選択をするためにも、複数の企業を見ておくことをおすすめします。焦らず、冷静な判断を心がけてください。
内定承諾・辞退の返信期限

内定をもらったあとの対応は、就活の大切なステップです。企業の信頼を損なわないためにも、承諾や辞退の連絡は期限を守って行う必要があるでしょう。
ここでは、承諾と辞退それぞれの返信期限について詳しく解説します。
- 内定承諾の連絡は取得から2週間以内
- 内定辞退は取得後1週間以内
①内定承諾の連絡は取得から2週間以内
内定を受け取ったら、基本的には2週間以内に承諾の意思を伝えるのが一般的です。企業側は人員の調整や今後の採用活動を進めるため、早めの返答を必要としています。
連絡が早ければ、信頼感も生まれやすく、スムーズなやりとりにつながるでしょう。もし複数社から内定をもらっていて迷っている場合でも、そのまま放置するのは避けてください。
すぐに返事ができないときは、「いつまでに決めたいか」「検討している理由」などを添えて、保留の旨を伝えると丁寧です。期限を過ぎると、辞退したと見なされる場合もあります。
内定はゴールではなく、社会人としてのスタートラインです。最初の対応一つで印象が決まることもあるため、誠意をもって対応しましょう。
②内定辞退は取得後1週間以内
内定を辞退する場合は、なるべく早く連絡を入れるのがマナーです。一般的には、内定をもらってから1週間以内に連絡するのが望ましいとされています。
企業側が次の候補者に声をかけるなどの対応を進めやすくするためです。辞退を伝えるのは気まずいと感じるかもしれませんが、連絡を遅らせるほど迷惑が大きくなります。
電話やメールで丁寧に謝意を示しつつ、辞退の意思を明確に伝えてください。「選考を通して学ぶことがあった」など、感謝の気持ちをひと言添えると、印象もよくなります。
辞退の伝え方ひとつで、あなたへの評価が変わることもあるでしょう。迷いがある場合でも、決断したら速やかに行動することが大切です。円満な就活のためにも、辞退の連絡は早めに済ませておきましょう。
内定から入社までの流れ

内定をもらったあと、実際に入社するまでには複数の段階があります。この流れを事前に知っておけば、就活後の不安を減らし、社会人への移行もスムーズに進められるでしょう。
特に初めての就職活動では、「内定=就活終了」と考えて気を抜いてしまいがちですが、実際にはそこからが本番とも言えます。
ここでは、企業から内定をもらってから入社までの標準的な流れを、時系列でわかりやすく解説します。
- 企業から内定通知を受け取る
- 労働条件通知書や契約内容を確認する
- 内定承諾書を記入し、期日までに提出する
- 10月頃に内定式に参加する
- 内定者研修や懇親会などに参加する
- 翌年4月に入社する
①企業から内定通知を受け取る
最終面接に合格すると、企業から内定の連絡が入ります。電話で直接伝えられる場合が多く、担当者から「内定をお出しします」などの言葉を受けると、大きな安心感と達成感を得られるでしょう。
ただし、ここで気をつけたいのは、口頭だけでは正式な内定と見なされない可能性がある点です。
内定通知書や採用通知書といった正式な書面が届くまで、安易に他の選考を辞退したり進路を決定したりしないよう注意してください。
通知書には、採用ポジションや連絡日、入社予定日などの基本情報が書かれている場合が多いです。書類が届くまでに数日かかることもあるため、焦らず待つ姿勢も必要になります。
連絡内容に不明点がある場合は、そのままにせずメールなどで問い合わせて確認しましょう。小さな疑問を放置しておくと、後から大きな誤解につながるおそれもあります。
②労働条件通知書や契約内容を確認する
内定通知の後には、「労働条件通知書」や「雇用契約書」など、具体的な雇用条件を明示する書類が届きます。内容をしっかり確認しておきましょう。
内容をしっかり確認せずに承諾してしまうと、入社後に「こんなはずではなかった」と感じる原因になります。特に注意すべきは、労働時間の扱いや残業代の支給条件、勤務地の変更可能性などです。
企業によっては、入社後に部署異動や転勤があることを前提としている場合もあるため、将来的なキャリアパスや生活に与える影響まで見越して確認しておく必要があります。
疑問に思ったことは遠慮せず企業に質問し、自分の中で納得できる形にしてから次のステップへ進みましょう。また、企業によっては条件面での交渉が可能な場合もあります。
また、勤務地や入社日について柔軟に対応してくれるケースもありますので、自分にとって重要なポイントがあれば率直に相談してみるのもひとつの手です。
③内定承諾書を記入し、期日までに提出する
内定通知を受け取り、条件に納得できた場合は、企業から届く「内定承諾書」へ署名・記入をして期日までに返送します。
この書類は、あなたがその企業での内定を正式に受け入れる意思を表すものであり、今後の入社手続きや研修案内などもこの承諾をもって進められるものです。
提出期限が設定されていることがほとんどなので、書類を受け取ったらすぐに内容を確認し、できるだけ早めに返送してください。
郵送の場合は、投函から相手に届くまでの日数も考慮して行動するようにしましょう。提出が遅れると、企業側に不安や不信感を与えてしまう可能性があるため注意が必要です。
また、承諾後に他の企業に気持ちが傾いてしまった場合は、辞退が可能かどうかやその際の影響もよく考えたうえで行動してください。承諾の意思を伝えるということは、それだけ責任も伴うという意識が求められます。
④10月頃に内定式に参加する
企業の多くは、10月1日付近に「内定式」を開催します。
このイベントは、企業から内定者に対して歓迎の意を表すとともに、今後のスケジュール説明や経営陣からのメッセージ、内定者同士の顔合わせなどが行われる貴重な機会です。
内定式はビジネスの場であり、今後の社会人生活の第一歩とも言えます。そのため、服装や持ち物、集合時間などの指定がある場合は、必ず事前に確認してください。
スーツの着こなしや立ち居振る舞いなど、マナー面にも注意を払いましょう。印象はこの段階から形成され始めるため、第一印象で信頼感を得られるような行動を心がけてください。
内定式では今後の研修や入社手続きに関する資料が配布される場合もあります。メモを取るための筆記用具や配布資料を保管するファイルなども忘れずに持参しましょう。
⑤内定者研修や懇親会などに参加する
企業によっては、入社前の期間中に「内定者研修」や「内定者懇親会」が開催されることがあります。
これらは、企業文化や業務理解を深めるだけでなく、同期や先輩社員との交流を通じて会社への親しみや信頼感を育む場でもあるのです。
研修では、ビジネスマナーや企業理念、業界の基礎知識などを学ぶことが多く、社会人になるうえでの準備として非常に有意義な時間になるでしょう。
また、懇親会ではフランクな雰囲気の中で、同期や人事担当者と話す機会が得られます。緊張せず、自然体で臨むことが大切です。
参加は任意とされるケースもありますが、可能であればぜひ出席しておきましょう。早い段階で社内の雰囲気に慣れておくことで、入社後の不安やストレスが軽減されます。
⑥翌年4月に入社する
大学を卒業したあとは、原則として翌年の4月に入社することになります。新しい環境や生活が始まるタイミングでもあるため、準備は計画的に行ってください。
具体的には、引っ越しや生活環境の整備、入社前に読んでおきたいビジネス書籍の確認などが挙げられます。
また、社会人としての基本的なマナーや、言葉遣い、報連相(報告・連絡・相談)などのスキルを身につけておくと安心です。
これらは一朝一夕で身につくものではないため、早めに意識して習慣化することが重要でしょう。内定から入社までは、約半年〜1年という長い期間があります。
焦る必要はありませんが、少しずつでも社会人への意識を高めていくことで、良いスタートを切る準備ができるはずです。
内定獲得後にやるべきこと

内定をもらったからといって、就活がすべて終わるわけではありません。ここから社会人としての準備が本格的に始まります。
ここでは、内定をもらった後にやるべきことを6個紹介します。何をすべきかを把握し、一歩ずつ確実に進めましょう。
- 企業との雇用条件や価値観のマッチ度を再確認する
- 他社選考が残っている場合は継続するか検討する
- 内定承諾書や添え状の作成・提出を行う
- 大学のキャリアセンターやゼミに報告する
- 引っ越しや引継ぎなど入社準備を計画的に行う
- 社会人に向けたスキルやマナーを学んでおく
①企業との雇用条件や価値観のマッチ度を再確認する
内定をもらったあとでも、本当にその企業が自分に合っているかを見直すことが重要です。入社後に「想像と違った」と感じるケースは珍しくありません。
労働条件や勤務地、給与だけでなく、企業の考え方や社風が自分に合うかどうかも確認しておきましょう。判断に迷うときは、会社説明会や選考中に得た印象を振り返ってみてください。
人事担当者の対応や社内の雰囲気など、細かい点が参考になるはずです。納得できないまま進めてしまうと、早期離職のリスクもあります。
安心して社会人生活をスタートさせるためにも、自分の価値観と照らし合わせて冷静に判断してください。
②他社選考が残っている場合は継続するか検討する
内定をもらっても、まだ他社の選考が進んでいることはよくあります。そうした場合、他者の選考を続けるかを早めに判断しましょう。
就活は「早く決まった人が勝ち」ではなく、「自分に合った会社に出会えるか」が大事です。今の内定先が納得できる内容かどうかを基準に判断してください。
迷う場合は、内定企業に保留の意向を伝えることもできます。ただし、期限の確認と誠実な連絡は忘れないようにしましょう。
他社を受け続けることで内定を失う可能性もあるため、慎重に決めることが大切です。情報を整理して、自分が後悔しない道を選んでください。
③内定承諾書や添え状の作成・提出を行う
内定通知を受け取ったあとは、承諾書や添え状の提出が必要です。これは形式的な作業ではなく、あなたの意志とマナーを伝える大切な手段といえるでしょう。
承諾書では、内定の条件を理解し、入社する意志があることを伝えます。添え状には、簡単なお礼の言葉と、今後への前向きな姿勢を添えると好印象です。
書類は丁寧に仕上げてください。手書き指定がある場合は、清書に注意が必要です。ミスがあると印象が下がるため、確認は入念に行いましょう。
小さな書類のやり取りでも、社会人としての姿勢が問われています。丁寧な対応を心がけてください。
④大学のキャリアセンターやゼミに報告する
内定が決まったら、大学のキャリアセンターやゼミの教員にも報告をしましょう。サポートを受けていた場合は、結果を伝えるのが礼儀でもあります。
また、報告しておくことで、書類の確認や卒業に関する手続きのサポートを受けやすくなるでしょう。将来的に企業とのやり取りが発生する際にも、大学側が把握しておくと対応しやすくなります。
感謝の気持ちを忘れずに伝えることで、良い関係を築いたまま卒業を迎えられます。社会人に必要な「報告・連絡・相談」の第一歩として、丁寧に対応してください。
⑤引っ越しや引継ぎなど入社準備を計画的に行う
内定が決まると、住まいや生活環境の準備、大学やアルバイトでの引継ぎなどが必要になります。これらはすぐに終わることではないため、早めにスケジュールを立てておくことが大切です。
特に引っ越しが必要な場合は、物件探しや契約手続きに時間がかかります。入社直前に慌てないよう、余裕を持って進めておきましょう。
大学関係者やアルバイト先にも早めに予定を伝えておくと、引継ぎもスムーズです。新生活を気持ちよく始めるためにも、少しずつ準備を進めてください。
⑥社会人に向けたスキルやマナーを学んでおく
内定後の期間は、社会人としての基本を学ぶ絶好のタイミングです。ビジネスマナー、メールの書き方、電話対応など、入社前に知っておきたいことは多くあります。
慣れていないうちに仕事が始まると、覚えることが多くて負担になりがちです。今のうちに少しずつ学んでおくと、入社後の不安が減るでしょう。
大学の講座や書籍、オンライン講座などを活用して、学びの習慣をつけておくのがおすすめです。社会人としてのスタートをスムーズに切るためにも、基本的な準備を怠らないようにしてください。
内定承諾の連絡のポイント
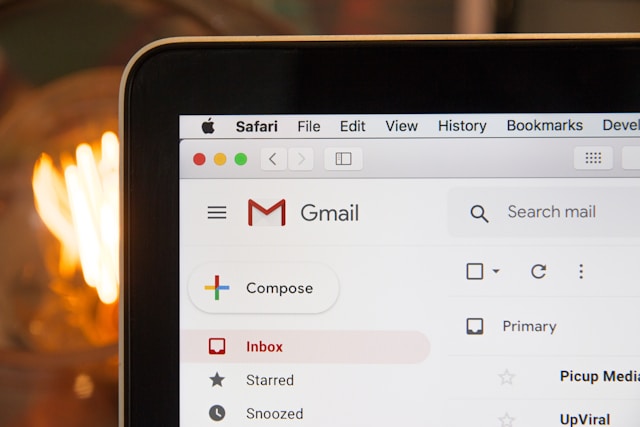
内定を承諾する際は、企業が期待するマナーやルールに沿って、丁寧かつ正確に意思を伝えることが大切です。連絡方法やタイミングを誤ると、企業に不信感を持たれるおそれもあります。
ここでは、承諾の連絡で押さえておきたい基本のポイントを紹介します。
- 企業が指定した期限を事前に確認する
- 承諾の連絡は期限より早めに行う
- 企業が指定した連絡方法に従う
- 電話またはメールで意思をはっきり伝える
- 文面には自己紹介と感謝の言葉を含める
①企業が指定した期限を事前に確認する
内定を承諾する前に、まず確認すべきなのは返信の期限です。企業ごとに設定されている締切日は異なるため、通知書やメールに記載された期限を見逃さないようにしてください。
見落としたまま放置すると、企業側に「意欲が低い」と受け取られる可能性があります。期限が書かれていない場合は、企業に確認を取るのが安心です。
自分の選考状況や他社との兼ね合いがあるにせよ、企業側の都合も意識し、スケジュールを調整する姿勢が求められます。
②承諾の連絡は期限より早めに行う
返事をする際は、できるだけ期限より前に連絡しましょう。ギリギリの返答は相手に不安を与えかねません。早めの連絡は誠実な対応と受け取られ、印象も良くなるでしょう。
ほかの企業と比較して悩む場合でも、連絡を先延ばしにするのではなく、期限内に相談することで、企業側も対応しやすくなります。連絡のタイミングは誠意を示すひとつの材料です。
③企業が指定した連絡方法に従う
「電話で」「メールで」といった連絡手段の指定がある場合は、必ずその指示に従ってください。
指定がないときは、まず電話で連絡し、その後にメールで確認の文面を送るという方法が丁寧でおすすめです。
自己判断で連絡方法を変えてしまうと、企業側と認識がずれてしまうことがあります。小さなことでも信頼を築く行動につながるため、注意が必要です。
④電話またはメールで意思をはっきり伝える
連絡をする際は、「内定を正式に承諾いたします」とはっきり伝えましょう。あいまいな表現や遠回しな言い方は避けたほうが安全です。
電話であれば、話す内容をメモにまとめておくと、緊張しても安心して話せます。メールの場合は、件名・宛名・署名など、基本のビジネスマナーを守ることが求められるでしょう。
改行や敬語の使い方にも注意し、誠実な文面を心がけてください。
⑤文面には自己紹介と感謝の言葉を含める
文面では、最初に自分の名前と学校名を伝えたうえで、内定への感謝と承諾の意思を述べるのが基本です。
「○○大学の△△と申します。このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました」のような形が自然でしょう。
また、今後のスケジュールや必要書類に関しても、「何か不明点があればご連絡ください」など一言添えておくと、丁寧な印象を与えられます。細やかな気配りが、社会人としての第一歩になるでしょう。
内定辞退の連絡のポイント

内定を辞退する場面は、就活生にとって避けて通れない可能性があります。失礼のない連絡を心がけることで、企業との関係を損なわずに就活を終えられるでしょう。
ここでは、適切な辞退連絡の流れと伝え方を紹介します。
- 辞退を決めたら即日中に連絡する
- まずは電話で人事担当者に伝える
- メールで連絡する場合は電話後に送る
- 「お世話になったこと」への感謝を伝える
- 辞退理由は前向きに簡潔にまとめる
①辞退を決めたら即日中に連絡する
内定を辞退することを決めたら、当日中に企業へ連絡してください。連絡が遅れると、採用担当者の業務に支障が出る可能性がありますし、社会人としての印象も悪くなりかねません。
企業側は返答を待ちながら、次の採用ステップを検討しています。そのため、早めの連絡が双方にとって望ましい結果につながるのです。
決断したら、ためらわず行動に移しましょう。迅速な連絡は、誠実な姿勢として評価されるはずです。
②まずは電話で人事担当者に伝える
辞退の連絡は、まず電話で行うのが基本になります。メールよりも気持ちが伝わりやすく、誠意を示しやすいです。
電話をかける際は、相手の勤務時間を考慮してください。始業直後や昼休み、終業直前は避け、落ち着いた時間帯を選ぶと安心です。
話す内容はあらかじめ簡単にメモしておくと、緊張してもスムーズに伝えられます。率直で丁寧な言葉づかいを意識しましょう。
③メールで連絡する場合は電話後に送る
電話で辞退の意思を伝えたあとは、確認のためにメールを送りましょう。口頭だけでなく、文書で記録を残すことがビジネスマナーとして求められます。
メールには、辞退の旨とお礼の言葉を簡潔に記載してください。電話での内容と矛盾がないよう注意しながら、丁寧な文章を心がけましょう。
相手に負担をかけない配慮と、社会人としてのマナーが伝わるかどうかがポイントです。
④「お世話になったこと」への感謝を伝える
辞退する際は、これまで対応してくれたことへの感謝も忘れずに伝えてください。企業はあなたのために時間と労力をかけてくれたのです。
「選考を通して学ぶことが多くありました」や「丁寧にご対応いただき、ありがとうございました」といった言葉を添えるだけで、印象は大きく変わります。
こうした気遣いは、社会人になってからも役立つはずです。辞退という結果であっても、礼儀を尽くせば誠意が伝わるでしょう。
⑤辞退理由は前向きに簡潔にまとめる
辞退理由を尋ねられた際は、前向きで簡潔に伝えることが基本です。批判的な内容やネガティブな言い回しは避けたほうが無難でしょう。
たとえば「自分のやりたいこととより一致する企業があったため」や「キャリアの方向性を再考した結果」など、自分の判断を軸にした表現が適しています。
細かく説明しすぎる必要はありません。誠実な態度を保ちつつ、分かりやすく伝えてください。
内定取消しとは

内定取消しとは、企業が一度出した内定を撤回することを意味します。就活生にとっては非常にショックな出来事であり、「なぜ取り消されたのか」「自分に落ち度があったのか」と不安になる場面かもしれません。
ただし、すべての内定取消しが正当な理由によるものとは限らず、企業側の都合で行われるケースも少なくないのが現実です。
一般的に、企業が内定通知を出した時点で、企業と学生の間には「労働契約の予約」が成立していると見なされます。つまり、企業が一方的に内定を取り消すことは、法的に問題になる可能性があるのです。
とはいえ、卒業見込みがなくなる場合などは、企業が内定を取り消す正当な理由として認められることがあります。そのため、内定を得たあとも、気を緩めることなく学生としての本分を果たしてくださいね。
また、万が一内定が取り消された場合には、大学のキャリアセンターや法律の専門家に早めに相談して、適切な対応策を講じましょう。
内定取り消しになるケース
内定を受けたからといって、必ず入社できるとは限りません。条件次第では、内定が取り消されることもあるのです。
ここでは、代表的なケースを挙げながら、注意すべきポイントを解説します。
- 学業不振で卒業見込みが立たなくなる場合
- 履歴書やエントリー内容に虚偽がある場合
- 内定後に重大な犯罪・不祥事を起こした場合
- 病気や事故で長期就業が困難になった場合
- 企業の経営悪化による場合
①学業不振で卒業見込みが立たなくなる場合
多くの企業では「大学を卒業できること」が内定の前提条件です。必要な単位が不足して卒業見込みが立たない場合、内定は取り消される可能性があります。
就活が一段落すると、気が緩んでしまうこともあるかもしれません。しかし、出席や課題提出をおろそかにすれば、取り返しのつかない事態に発展するかもしれないのです。
卒業までが学生の本分です。内定を無駄にしないためにも、最後まで責任を持って学業に取り組んでください。
②履歴書やエントリー内容に虚偽がある場合
書類や面接で伝えた内容に事実と異なる情報が含まれていた場合、発覚した時点で内定が取り消されることがあります。特に学歴や資格、インターン経験の詐称は重大な問題です。
企業は、学生の能力だけでなく、誠実さや人間性も見ています。信頼を損なえば、たとえ入社前でも採用は取り消されてしまうでしょう。
小さなことでも誤魔化さず、正直な情報を伝えることが、社会人への第一歩です。
③内定後に重大な犯罪・不祥事を起こした場合
内定後に重大な問題行動を起こした場合、企業は内定を取り消す可能性があります。たとえば、飲酒運転や暴力行為などが挙げられるでしょう。学生とはいえ、企業は社会人としての自覚を求めています。
日常生活でも責任ある行動を意識してください。SNSでの発言や投稿も、誤解を招く表現がないか見直しておくと安心です。思わぬところで信頼を失わないよう注意しましょう。
④病気や事故で長期就業が困難になった場合
入社前に病気や事故により長期間働けないと判断された場合、企業側の判断で内定が取り消されるケースがあります。ただし、すべてが即取り消しにつながるわけではありません。
体調に不安がある場合は、早めに企業に相談することが大切です。事情をきちんと説明し、回復の見込みがあれば配慮されることもあります。無理をせず、誠実に対応することが信頼を保つポイントです。
⑤企業の経営悪化による場合
自分に問題がなくても、企業の業績悪化が理由で内定が取り消されることがあります。人員整理や採用方針の見直しによって、やむを得ず取り消しが発生するケースです。
こうした状況は予測が難しいため、内定後も複数の選択肢を持っておくと安心。取り消しが決まった場合は、大学のキャリアセンターや支援機関に相談してください。
万が一に備えて、情報収集や行動の準備をしておくとリスクを軽減できます。
内定を正しく理解し、確実なスタートを切るために

内定とは、就活の一つの区切りであり、企業と学生の間で結ばれる約束です。内々定や採用との違いを正しく理解することで、今後の行動に迷いがなくなります。
内定が出る時期や、承諾・辞退の返信期限にも注意し、企業との信頼関係を築く姿勢が大切です。
内定通知後は、労働条件の確認や書類提出、内定式や研修への参加など、入社までにやるべきことが数多くあります。
また、承諾・辞退の連絡方法にもマナーが求められるため、丁寧かつ迅速な対応を心がけてください。内定取り消しのリスクを知っておくことも、安心して入社を迎えるための一歩です。
内定をゴールではなく社会人としてのスタートと捉え、準備を怠らずに行動しましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










