内定を複数もらった時の判断基準は?対処法と辞退マナー
「複数の内定をもらったけれど、どの企業を選べばいいのか分からない…」
就活を頑張った結果、複数内定を獲得できるのは喜ばしいことであると同時に、将来のキャリアや働き方に直結する大事な決断しなければなりません。
そこで本記事では、複数内定をもらった時の判断基準や選び方のポイント、迷った時の対処法、そして辞退する際の正しいマナーまで、具体例とともに詳しく解説します。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
複数内定をもらったら、よく考えて判断しよう

複数の企業から内定をもらうことは、とても喜ばしいことです。ただし、どの企業を選ぶべきか迷ってしまう人も多いでしょう。納得のいく判断ができるよう、時間をかけて考えることが大切です。
焦って決めてしまうと、入社後に「想像と違った」と感じて後悔するかもしれません。だからこそ、最終的な決断を下す前に、自分の価値観や将来の方向性を一度整理してみてください。
たとえば企業のビジョンや社風、自分との相性、成長できる環境があるかどうかなど、多角的な視点で見ていくと判断の材料になります。
情報を整理して自分の気持ちを確かめることで、迷いが減り、自信を持って選べるようになるでしょう。内定が複数ある状況は恵まれている一方で、大きな決断を迫られるタイミングでもあります。
だからこそ、「早く決める」よりも「よく考えて決める」ことを意識して行動してください。
複数の内定先で絞れない理由

就活で複数の内定をもらうのは嬉しい一方で、どこに決めるか迷うことも多いでしょう。なかなか決断できない背景には、共通するいくつかの原因があるのです。
ここでは、その主な理由を挙げながら、判断に迷ったときのヒントを紹介します。
- 自己分析が浅く、就活の軸が明確でないから
- 複数の企業に同程度の魅力を感じているから
- 将来のキャリア像が定まっていないから
- 企業情報が不足して判断しきれないから
①自己分析が浅く、就活の軸が明確でないから
複数の内定先から選べない理由のひとつに、自己分析が十分でないことが挙げられます。自分の価値観や働くうえでの優先順位が曖昧だと、どの企業にも魅力を感じる一方で、決め手に欠けてしまいます。
たとえば、「大手だから安心そう」「福利厚生がしっかりしているからよさそう」といった理由で選んだ企業は、似たように見えて比較が難しくなりがちです。
こうした場合は、一度立ち止まって自分自身と向き合ってみてください。自分が何を大切にしたいか、どんな働き方を理想としているかをノートに書き出してみましょう。
そのうえで、各企業がその理想にどれくらい近いかを確認すると、判断しやすくなります。最終的にどこに入社するかを決めるとき、ぶれない軸があると大きな支えになるのです。
自己分析をし直すことは、納得のいく選択につながる大切なプロセスといえるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②複数の企業に同程度の魅力を感じているから
どの企業にも同程度の魅力を感じているため、どこに決めるべきか悩んでしまうこともあります。条件や雰囲気が違っていても、それぞれに惹かれる部分があると、選択は簡単ではありません。
こんなときは、「自分が何を最も重視しているか」を明確にしてみましょう。
たとえば、勤務地、仕事内容、働く人の雰囲気、キャリアの成長スピードなど、自分にとって外せないポイントを整理し、優先順位をつけてみてください。
さらに、条件だけでなく、働く人の様子や日々の業務内容、入社後のキャリアパスなどにも注目することが大切です。
入社後の生活をリアルに想像してみると、「ここで働きたい」と感じるかどうかがわかってきます。どの企業も魅力的に見えるときこそ、自分の軸に立ち返ることが大切です。
③将来のキャリア像が定まっていないから
将来どんな社会人になりたいかが明確でないと、どの企業に進むべきか迷いやすくなります。目の前の内定に目を奪われてしまい、自分の将来像を見失ってしまうことはよくあるでしょう。
たとえば、「営業職も面白そうだし、企画も興味がある」というように、方向性が決まっていない場合は、どちらの企業を選んでも不安が残ってしまうかもしれません。
こんなときは、「5年後、10年後の自分がどうなっていたいか」を考え、その将来像に近づける環境がどこにあるかを探してみてください。
また、実際に社会人として働く人の話を聞いてみると、理想と現実のギャップにも気づけます。キャリアの道筋は1つではありませんが、目指す方向が見えていれば、判断しやすくなるでしょう。
自分の未来に対して主体的に向き合うことで、納得できる選択ができるはずです。
④企業情報が不足して判断しきれないから
企業についての情報が足りないと、どこに決めればいいのか迷ってしまうのは当然です。特に、選考中や説明会だけでは見えにくい部分も多く、入社後の姿を想像するのは難しいかもしれません。
情報が不十分なまま決めてしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔する可能性もあります。そうならないよう、内定後でも自分から積極的に情報を集めていくことが大切です。
たとえば、内定者懇親会や社員訪問を通じて、実際に働いている人の声を聞いてみましょう。
さらに、SNSや口コミサイト、企業のIR資料などをチェックすると、社内の雰囲気や将来性についてのヒントも得られるはずです。情報の多さは安心感にもつながります。
迷っているときこそ、「もっと知る」ことで判断材料が増え、後悔のない選択がしやすくなるでしょう。
複数内定から1社に決めるための判断基準

複数の企業から内定をもらった場合、「どの企業を選べばよいのか分からない」と迷う人は多いものです。
ここでは、後悔のない選択をするための判断基準を紹介します。自分に合った企業を選ぶための視点を、以下の5つのポイントから確認してみてください。
- 企業の理念やビジョンへの共感
- 仕事内容と自分のやりたいことの一致
- 働き方や福利厚生など条件面の充実度
- 社風や人間関係の相性
- 成長環境やキャリアパスの有無
①企業の理念やビジョンへの共感
企業の理念やビジョンに共感できるかどうかは、長く働くうえで大切なポイントです。
たとえば「社会課題を解決する」「革新的な技術で未来を変える」といった方向性に、自分自身が共鳴できるかどうかを考えてみてください。
共感できる理念を持つ企業であれば、仕事の中で多少の困難があっても「ここで頑張りたい」と思えるでしょう。
一方、待遇や条件が良くても、会社の考え方に違和感があるとモチベーションが続かない可能性があります。
判断する際は、企業のホームページや会社説明会の資料だけでなく、実際に社員と話す機会を活用してください。理念への共感は、自分らしく働ける職場かどうかを判断するための大きな手がかりになります。
②仕事内容と自分のやりたいことの一致
仕事内容が自分のやりたいことと一致しているかどうかも、重要な判断材料です。
たとえば「人と関わる仕事をしたい」と考えている場合、ほとんどがデスクワークの職場では満足できないかもしれません。
「やりたいこと」とは、必ずしも夢や目標である必要はなく、「興味がある分野」や「苦にならない作業」などでも構いません。
そうした観点から、企業ごとの業務内容が自分に合っているかを比較してみてください。説明会や社員インタビューを通じて、配属後の仕事内容や育成方針などを確認しておくと安心です。
自分にとって「無理なく続けられる仕事か」を見極めることが、納得できる選択につながるでしょう。
③働き方や福利厚生など条件面の充実度
どれほど仕事内容や理念に魅力を感じても、働く環境が合わなければストレスを感じやすくなります。
たとえば、残業が多い、休みが取りにくい、福利厚生が不十分といった条件があると、日々の働き方にも影響が出るでしょう。
自分がどんなライフスタイルを大切にしたいのかを明確にしたうえで、企業の条件と照らし合わせてください。
「通勤時間は短くしたい」「住宅手当が欲しい」「リモート勤務が可能な職場がいい」など、自分の希望を整理しておくことが大切です。
制度の有無だけでなく、実際にそれが利用されているかも確認しておくと安心でしょう。企業によっては制度があっても形だけの場合もあるため、社員への質問や口コミのチェックが有効です。
④社風や人間関係の相性
職場の雰囲気や人間関係は、日々の働きやすさに直結します。いくら待遇や仕事内容が良くても、居心地が悪いと感じる環境では本来の力を発揮しにくくなるでしょう。
たとえば、上下関係が厳しい体育会系の文化がある会社と、穏やかでフラットな雰囲気の会社では、合う合わないが分かれます。自分がどんな環境で働きたいかをイメージしてみてください。
会社のホームページや説明資料だけでは社風は分かりにくいため、可能であれば社員との面談や座談会に参加して雰囲気を体感してみましょう。
自分に合った空気感かどうかを確認することで、入社後のミスマッチを防げます。
⑤成長環境やキャリアパスの有無
自分が将来的にどうなりたいかを考えたうえで、その企業にどれだけの成長機会があるかを見てみましょう。
研修制度が整っていたり、若手にも裁量が与えられる文化がある企業では、スキルアップが期待できます。
逆に、評価制度が不透明だったり、部署異動が自由に選べなかったりする場合は、自分の希望するキャリアを築きにくいこともあるでしょう。
だからこそ、自分が身につけたいスキルやキャリア像と照らし合わせて、長く働ける環境かを見極めてください。成長できる環境かどうかは、仕事へのやりがいにもつながります。
企業を選ぶ際には、今の条件だけでなく、数年先の自分を想像しながら判断することが大切です。
複数内定から1社を選ぶ前にやるべきこと

複数の内定をもらったあと、どの企業に進むかを決めるのは大きな選択です。
悩んでいるうちに時間が過ぎてしまうと、企業側に迷惑がかかる場合もあるため、納得したうえでできるだけ早く判断しましょう。
ここでは、内定先を決める前に取り組んでおきたい行動を紹介します。
- 自己分析を深めて軸を再確認する
- 比較表を作って条件を整理する
- 社員面談などで情報を補う
- 信頼できる人に相談する
- 優先順位をリスト化する
①自己分析を深めて軸を再確認する
複数の内定先から1社を選ぶためには、自分の軸をもう一度明確にすることが大切です。内定をもらうことが目的になっていた場合、「どこで働くべきか」という視点が抜け落ちているかもしれません。
まずは、自分がどのような価値観を大切にし、どんな働き方を望んでいるのかをノートなどに書き出して整理してみましょう。
そして、それぞれの企業がその理想にどの程度合っているのかを比べてみてください。選択に迷う背景には、判断基準が曖昧なことがあります。
軸がしっかりしていれば、選ぶべき方向性も見えてくるでしょう。選考が終わった今だからこそ、視野を広げて自分の希望を見つめ直すことが重要です。
②比較表を作って条件を整理する
複数の企業を客観的に比較したいときは、比較表の作成が有効です。頭の中だけで整理しようとすると、印象に引っ張られたり、細かい点を見落としたりする可能性があります。
比較する際は、給与や福利厚生、勤務地といった条件面に加えて、社風や働く人の雰囲気、将来性なども含めるようにしましょう。
また、自分が重視しているポイントに印をつけるなど、視覚的にも分かりやすくすると比較しやすくなります。表にまとめることで、どの企業が自分の希望により近いかを見極めやすくなります。
感覚に頼るだけでなく、情報をもとに判断することが後悔の少ない選択につながるでしょう。
③社員面談などで情報を補う
求人票や説明会だけでは企業の本当の姿は見えにくいものです。判断材料が足りないときは、実際に働いている人から情報を得ることが効果的でしょう。
企業によっては、内定者向けに社員との懇談会を用意してくれることがあります。もし案内があれば、積極的に参加してみてください。また、自分からOB・OG訪問を申し込むのもおすすめです。
現場の声を聞くことで、実際の働き方や社内の雰囲気、キャリアパスなどを具体的にイメージできるようになります。情報が増えれば選択にも自信が持てるはずです。
④信頼できる人に相談する
自分一人で悩んでいると、考えが偏ったり、判断に自信が持てなくなったりすることもあります。そんなときは、信頼できる人に相談してみてください。
たとえば、家族や大学のキャリアセンター、先輩など、自分をよく知っている人の意見は客観的で貴重な参考になります。話すことで自分の考えが整理され、新たな気づきが得られるかもしれません。
ただし、最終的に決めるのは自分自身です。他人の意見をそのまま受け入れるのではなく、自分の気持ちと照らし合わせながら判断するようにしましょう。
⑤優先順位をリスト化する
複数の内定先に対して、あれもこれも比べようとすると判断が難しくなります。そんなときは、自分が就職先に求める条件をリスト化し、それぞれに優先順位をつけてみましょう。
仕事内容、勤務地、給与、成長環境、人間関係など、気になるポイントを洗い出し、どれがより重要かを明確にすると、自分の希望がはっきりしてきます。
リストがあることで、選ぶべき企業が自然と浮かび上がってくるでしょう。頭の中を整理し、納得できる選択につなげるための有効な手段です。
内定先を迷っている際の対応方法

複数の企業から内定をもらったとき、どこに決めるか迷ってしまうのは自然なことです。
ここでは、その迷いを整理し、自分に合った企業を選ぶための具体的な対応策を紹介します。
- 判断の期限を設けて動く
- 迷いを整理して優先順位を決める
- 採用担当に相談して状況を伝える
- 企業訪問や面談で現場を確認する
①判断の期限を設けて動く
まずは自分で期限を決め、その日までに結論を出すと決めて行動を始めてください。期限があることで、情報収集や比較に集中しやすくなります。
内定先に迷い、なんとなく時間が過ぎてしまうのは避けたいです。また、判断を後回しにすると、企業への連絡が遅れて印象を損ねる可能性があります。
実際に行動を始めると、悩みの原因や解決のヒントが見つかることもあるでしょう。期間は3日から1週間ほどを目安に設定すると、無理のないペースで進められます。
企業ごとに承諾期限が異なるため、事前にメールや書類で確認しておくことも忘れないようにしましょう。自分でリミットを設けることが、納得できる判断につながります。
②迷いを整理して優先順位を決める
どの企業に魅力を感じているのか分からないまま悩み続けると、決断がどんどん難しくなります。まずは自分が大切にしたい価値観や就活の軸を整理し、重視する条件を書き出してみてください。
「成長環境」「勤務地」「働きやすさ」など、比較したい項目に優先順位をつけていくと、判断しやすくなります。迷いの原因が条件のあいまいさにある場合、こうした整理が大きな助けになるでしょう。
そして、企業ごとの情報を自分の軸に照らして見直すことで、選択肢の中から最適な1社が見えてくるはずです。焦らずに一つずつ整理することが、後悔のない選択への近道でしょう。
③採用担当に相談して状況を伝える
迷いを一人で抱え込んでしまうと、不安ばかりが大きくなってしまいます。そんなときは、思いきって採用担当者に相談してみるのも有効な手段です。
就活生からの相談は珍しいことではなく、誠実に向き合う姿勢として受け止められることが多いでしょう。たとえば「他社と迷っている」「もう少し情報が欲しい」といった内容でも問題ありません。
率直に話すことで、自分の考えが整理されていくこともあるでしょう。ただし、伝え方には注意が必要です。あいまいな表現を避け、誠意をもって丁寧に伝えるよう心がけてください。
そうすることで、企業との信頼関係も保たれたまま、安心して判断を進められるでしょう。
④企業訪問や面談で現場を確認する
企業ごとの雰囲気や働き方を深く理解するためには、実際に現場を見たり、社員と直接話したりするのが効果的です。
説明会やWeb情報だけでは分からないことが、訪問や面談を通じて明らかになる場合があります。
たとえば、オフィスの雰囲気や社員の様子を見て、自分がその環境で働く姿をイメージできるかを確認してみてください。
「百聞は一見にしかず」という言葉のとおり、実際に感じる空気感は重要な判断材料になります。希望すれば、企業によっては個別に面談や座談会の機会を設けてくれることも。
遠慮せずに問い合わせてみましょう。自分の目と耳で確かめることで、納得感のある選択がしやすくなります。
内定のキープはいつまで可能?
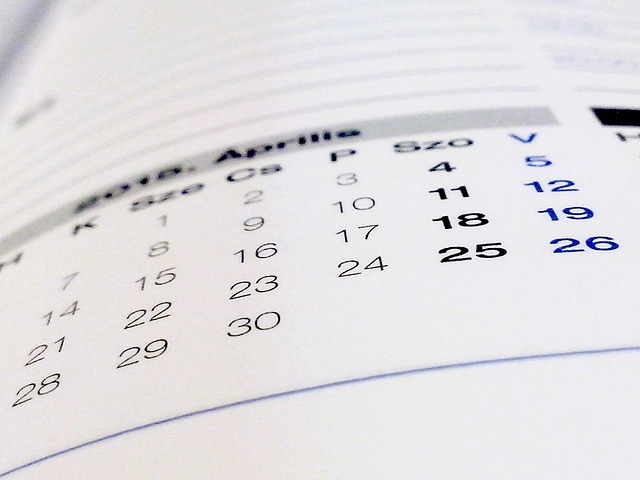
企業によって異なりますが、一般的には、内定通知とともに送られてくる「内定承諾書」の提出期限が、その企業の回答期限と考えてよいでしょう。
「○月○日までにご返信ください」と指定されている場合、その日を過ぎると辞退と見なされることもあります。返答をせずに放置してしまうと、企業に不信感を与えてしまう恐れもあるため注意が必要です。
期限が明示されていないときは、自己判断せず、企業に直接確認するようにしてください。
「他社の選考状況も踏まえて慎重に検討したいため、少しお時間をいただけますか」といった丁寧な姿勢で伝えることで、多くの企業はある程度の配慮をしてくれるはずです。
ただし、返答を長期間保留にするのは避けましょう。内定をキープするには、相手の立場も考慮しながら、自分の意思を期限内に伝えることが大切です。
内定を複数もらった際に避けるべき行動
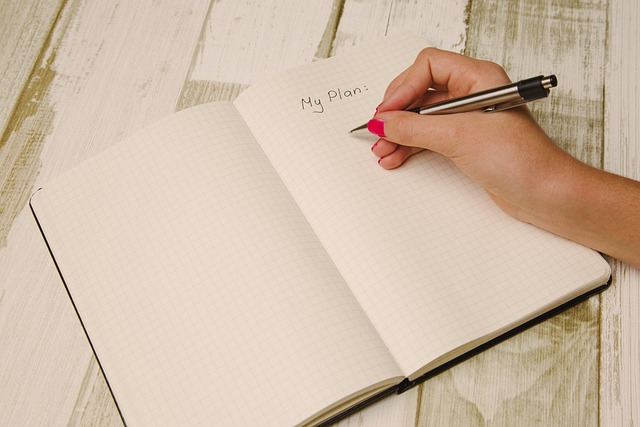
複数の企業から内定をもらったとき、うれしさと同時に悩みも生まれやすいものです。
ここでは、判断ミスによる後悔を防ぐために、避けるべき行動とその理由を整理して紹介します。就活の終盤で誤った選択をしないよう、以下のポイントを意識してください。
- 複数の内定を同時に承諾しない
- 人の意見だけで決めない
- 条件面だけで判断しない
- 印象や雰囲気だけで決めない
- 判断基準が曖昧なまま承諾しない
①複数の内定を同時に承諾しない
複数の企業に同時に「入社します」と伝えるのは避けるべきです。企業は内定承諾を前提に、研修や配属の準備を進めています。
あとから一方を辞退すると、企業側にとって大きな損失になるだけでなく、自身の誠実さにも疑問を持たれかねません。行動には責任を持ちましょう。
「とりあえず押さえておこう」という軽い気持ちで承諾することは、社会人としての信用を失うリスクがあります。また、場合によっては大学や就職支援機関に迷惑がかかる可能性もあります。
迷っている場合は、正直に迷っていることを伝えたうえで、保留をお願いするのが適切です。企業によっては、数日から1週間ほどの猶予を設けてくれることもあります。
どの企業にも真摯に向き合い、後悔のない判断を下すことが社会人としての第一歩につながるのです。
②人の意見だけで決めない
家族や友人、大学のキャリアセンターなど、周囲の意見は就職活動を進めるうえで貴重な情報源になりますが、人の意見だけで決めるのは避けてください。
あくまで、「参考にする」程度にしましょう。人の意見だけで決めてしまうと、後悔する原因になりやすいのも事実です。
たとえば、「親がその企業を知っているから」「先生がすすめたから」「みんなが良い会社だと言っていたから」といった理由だけで入社を決めてしまうと、自分の価値観とズレが生じやすくなります。
実際に働くのは自分自身であり、他人の人生ではありません。もちろん、就活で不安になることは多く、意見にすがりたくなる気持ちも自然なことです。
しかし、まずは「自分はどんな働き方をしたいか」「将来どうなりたいか」といった視点を持ち、自分なりの判断軸を持つことが大切でしょう。周囲の声に流されず、自分の納得できる選択をしてください。
③条件面だけで判断しない
給与や休日数、勤務地、福利厚生などの「条件面」は目に見える分かりやすい情報であり、企業比較をするうえでも重要な要素ですが、条件だけで判断しないようにしましょう。
それだけで企業を選ぶと、仕事そのもののやりがいや人間関係といった「目に見えにくい要素」で苦労する可能性があります。
逆に、条件面はやや劣っていても、居心地の良さや成長の実感が得られる職場のほうが、長く働き続けられるかもしれません。
重要なのは、条件だけを軸にせず、「総合的に自分に合っているか」を見極める姿勢です。
働き方や成長環境、社内の雰囲気など、さまざまな観点からバランスよく判断することで、自分にとって最適な選択が見えてくるはずでしょう。
④印象や雰囲気だけで決めない
面接官が親切だった、説明会の雰囲気が良かった、社員が笑顔だった。こうしたポジティブな第一印象は、その企業への好感度を大きく高める要素ですが、印象や雰囲気で判断するのは危険でしょう。
面接や会社説明会は、あくまで「企業が学生に魅力を伝える場」であり、意図的に良い印象を演出していることも多いです。
現場のリアルな雰囲気や働く環境、人間関係といった情報は、その場だけでは見えにくい場合があります。
入社後のギャップを防ぐには、実際に社員に話を聞く機会を設けたり、可能であれば職場訪問をして、自分の目と耳で確かめることが大切です。
第一印象に流されず、長く働く自分を想像しながら慎重に判断してください。
⑤判断基準が曖昧なまま承諾しない
「とりあえず決めないといけないから」「なんとなく印象が良かったから」といった曖昧な理由で承諾してしまうと、入社後に「やっぱり違ったかも」と後悔する可能性があります。
就職はゴールではなく、新たなスタート地点です。選んだ会社で自分がどんなふうに働き、成長していきたいかをしっかり考えることが必要でしょう。
判断基準が不明確だと、企業を比較する際の軸もぶれやすくなります。まずは「自分が譲れない価値観」や「理想の働き方」を整理し、その基準に合った企業を選ぶことが重要です。
たとえば「人間関係を大切にしたい」「若いうちから挑戦したい」といった観点を明確にすることで、自分に合う企業像が見えてくるはず。
しっかりと自分の軸を持ち、納得したうえで承諾することが、充実した社会人生活の第一歩になります。
内定を辞退する際の正しい断り方の例文
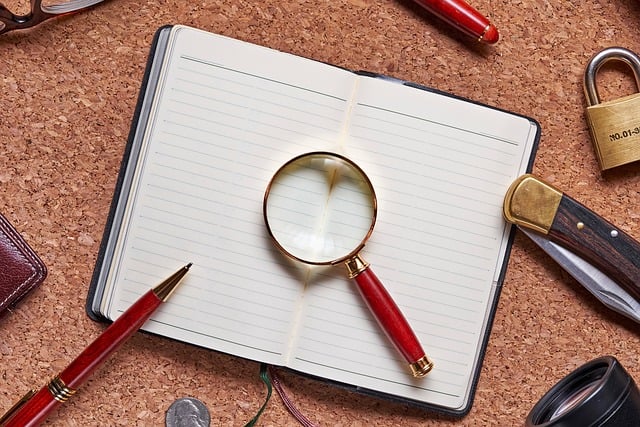
複数の内定を受けたあと、最終的に1社を選ぶと他社を辞退する必要が出てきます。そのとき、「どう伝えれば失礼にならないか」と不安になる方も多いでしょう。
ここでは、内定辞退の伝え方を基本の型から理由を添える応用パターンまで分かりやすく紹介します。
内定辞退を伝える基本パターン
複数の企業から内定をもらった場合、最終的に選ばなかった企業には辞退の連絡を入れる必要があるのです。ここでは、失礼のないシンプルな内定辞退のメール例文を紹介します。
| 件名:内定辞退のご連絡(◯◯大学 氏名) 株式会社◯◯ 人事部 ◯◯様 いつも大変お世話になっております。 ◯◯大学◯◯学部の◯◯です。 このたびは、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。貴社の選考を通じて、貴重な学びと出会いの機会をいただけたこと、心より感謝申し上げます。 大変悩みましたが、自分の将来や価値観を見つめ直したうえで、別の企業への入社を決意いたしました。誠に勝手ではございますが、内定を辞退させていただきたく、ご連絡差し上げました。 何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 末筆ながら、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。 ◯◯大学 ◯◯学部 ◯◯ ◯◯ メールアドレス:xxxx@xxx.xx 電話番号:090-xxxx-xxxx |
相手企業への感謝の気持ちをしっかり伝えたうえで、辞退の意向を丁寧に示しています。自分の気持ちを簡潔に整理し、「選ばなかったこと」ではなく「感謝と誠意」に重点を置いて構成しましょう。
他社に決めた理由を添える場合の伝え方
内定辞退の連絡をする際に、他社を選んだ理由を丁寧に伝えることで、相手企業にも納得感を与えることができるでしょう。ここでは、自分なりの判断基準を明確に示した内定辞退メールの例文を紹介します。
| 件名:内定辞退のご連絡(◯◯大学 氏名) 株式会社◯◯ 人事部 ◯◯様 お世話になっております。◯◯大学◯◯学部の◯◯です。 このたびは、内定のご連絡をいただき誠にありがとうございました。 選考中は貴社の社員の皆さまのあたたかさや誠実な対応に触れ、働く環境としてとても魅力を感じました。 しかし、自分が将来やりたいことや成長イメージを改めて見つめ直した結果、最も共感できた企業に進むことを決意いたしました。 誠に恐縮ではありますが、今回は内定を辞退させていただきたくご連絡差し上げました。 貴重な機会をいただいたこと、心より感謝申し上げます。貴社の今後ますますのご発展をお祈りしております。 ◯◯大学 ◯◯学部 ◯◯ ◯◯ メールアドレス:xxxx@xxx.xx 電話番号:090-xxxx-xxxx |
相手企業の魅力をきちんと伝えたうえで、自分の意思をはっきりと伝える構成にしています。企業に対する敬意を忘れず、理由は簡潔かつ前向きに伝えるのがポイントです。
複数の内定に迷ったら、自分にとって最良の選択をしよう

複数の内定をもらったとき、どの企業に進むべきか迷うのは自然なことです。しかし、安易に決めてしまうと後悔につながりかねません。
まずは「なぜ選べないのか」を明らかにし、自分の価値観や将来像に合った判断基準を持つことが重要です。そのうえで、企業を冷静に比較し、信頼できる人にも相談しながら優先順位を整理しましょう。
期限やマナーを守りつつ、誠実な対応を心がけることも忘れてはいけません。
複数の内定はチャンスでもあり責任でもあるため、自分らしく納得できる選択をすることが、後悔のないキャリアの第一歩になります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










