内定式プログラム完全ガイド|内容や流れ・注意点を解説
「内定式ってどんなプログラムがあるの?」と疑問を持つ人も多いですよね。
内定式は、就職活動の一区切りであり、入社に向けた大切な第一歩です。企業によって内容や流れは異なりますが、事前に全体像を把握しておくことで、当日も落ち着いて臨めます。
そこで本記事では、内定式の目的や開催時期、一般的なプログラム内容から、服装・持ち物・マナーのポイント、さらにオンライン開催の特徴や具体的な事例まで、詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
内定式とは?

内定式とは、企業が内定者を一堂に集めて実施する、入社前の重要なイベントです。ここでは、これから共に働く仲間との顔合わせや、先輩社員・人事担当者との交流の場が設けられることが多いです。
こうした機会を通じて、職場の雰囲気や価値観を肌で感じることができるでしょう。
内定者同士のつながりが生まれるのも大きなポイントです。学生生活の中では出会うことのなかった多様な人々と関わることで、自分の視野が広がったり、新たな刺激を受けたりする場面も少なくありません。
また、企業によっては内定者向けに研修やグループワークを実施するケースもあります。こうした内容を通して、入社前に求められる心構えや、基本的なビジネスマナーを身につけることができるでしょう。
形式ばかりにとらわれず、参加する姿勢や関わり方を意識することが、より実りある経験につながります。
内定式の目的

内定式は、企業が内定者に向けて正式に内定を通知し、今後のつながりを深める大切なイベントです。ただのお祝いの場と思われがちですが、実は複数の重要な目的があります。
ここでは、内定式が果たす主な5つの目的について詳しく解説します。
- 内定辞退の防止
- 内定者の不安軽減
- 入社意欲の向上
- 企業理解の促進と配属判断
- 手続き・書類確認の場としての役割
①内定辞退の防止
企業が内定式を開くもっとも大きな目的のひとつは、内定辞退の防止です。就活生の中には、複数の企業から内定を得ている人もおり、入社を決めかねているケースも少なくありません。
そうした状況で、内定式という正式なイベントがあると、企業とのつながりを実感しやすくなります。
たとえば、内定証書の授与や社長からの挨拶などを通じて、「この会社の一員になるんだ」という意識が芽生えやすくなるでしょう。
このように、形式的に見えるイベントでも、実際には入社の意思を固めてもらうための工夫が詰まっています。結果として、企業側も安心して準備を進められるようになるのです。
②内定者の不安軽減
内定から入社までの間、仕事内容、職場の雰囲気、人間関係など、学生はさまざまな不安を抱えています。内定式では、内定者の不安を和らげるためのプログラムが用意されていることも多いのです。
たとえば、先輩社員との交流や会社説明の時間が設けられることで、実際の働き方や雰囲気をイメージしやすくなるでしょう。
また、同期となる他の内定者と顔を合わせることで、「仲間がいる」という安心感も得られます。このような仕組みを通じて、不安が期待に変わっていくのです。
③入社意欲の向上
内定式は、内定者の入社意欲をさらに高める場でもあります。特に、社長や経営層から直接話を聞ける機会は、企業のビジョンや方針を深く理解するきっかけになるでしょう。
自分がその会社で働く意味を見いだせると、入社への意識も変わります。企業の雰囲気を実際に体験することで、「ここで働きたい」という気持ちが強くなる人も多いです。
こうした経験を通じて、入社を単なる通過点ではなく「自分の選択」として捉えられるようになり、入社後のミスマッチも減らせます。
④企業理解の促進と配属判断
内定式では、入社前に会社への理解を深めてもらうために、企業の事業内容や部門の役割、キャリアパスなどについて説明されることがあります。
同時に、企業側も内定者の反応や興味のある分野を観察し、配属先の参考にしています。つまり、内定式はお互いの理解をすり合わせる重要な機会でもあるのです。
こうした背景があるため、学生側も受け身ではなく積極的に情報収集をしておくことが求められます。事前の企業研究が、その後の配属や働き方に影響を与えることもあるでしょう。
⑤手続き・書類確認の場としての役割
内定式には、セレモニー以外にも実務的な意味があります。たとえば、誓約書や入社承諾書の提出、各種書類の確認や説明など、入社に向けた準備が進められるのです。
学生にとっては慣れない手続きも多く、直接質問できるこの機会はとても貴重です。疑問をその場で解消できるため、入社までの不安も軽減されるでしょう。
また、企業側もこの場で情報を整理し、全体のスケジュールを調整しやすくなります。内定式は単なる行事ではなく、社会人生活への第一歩といえる重要なイベントなのです。
内定式はいつ開催される?
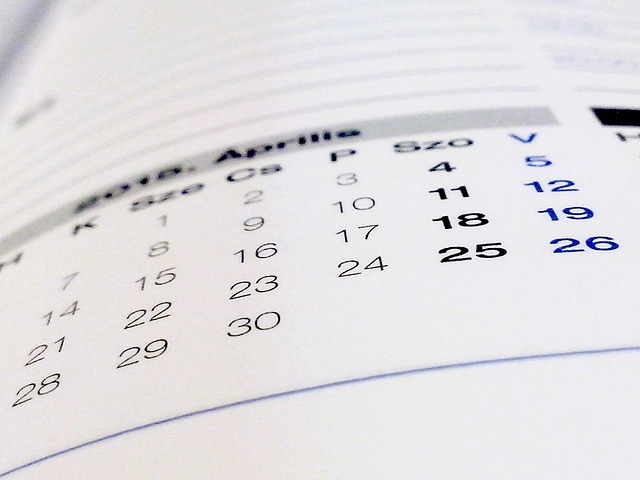
内定式は、例年10月1日ごろに開催されることが多いです。これは、かつて経団連がその日を「内定解禁日」と定めていた名残によるもので、今も多くの企業がこの時期に実施しています。
ただし、業界や企業の規模によっても違いがあります。たとえば、大手や金融、メーカーでは10月1日に一斉開催することが一般的ですが、ベンチャーやIT業界では9月中や11月以降に行われることもあります。
また、大学の授業や卒業論文の準備と重なる可能性があるため、あらかじめスケジュールの確認をしておくと安心です。
また、最近では複数回に分けて開催したり、オンラインと対面を組み合わせたりするケースも増えています。中には冬や翌年初めに実施する企業もあります。
「内定式=10月1日」と決めつけず、企業からの案内をしっかり確認して、自分の予定と合わせて準備を進めてください。
内定式の一般的なプログラム内容とは
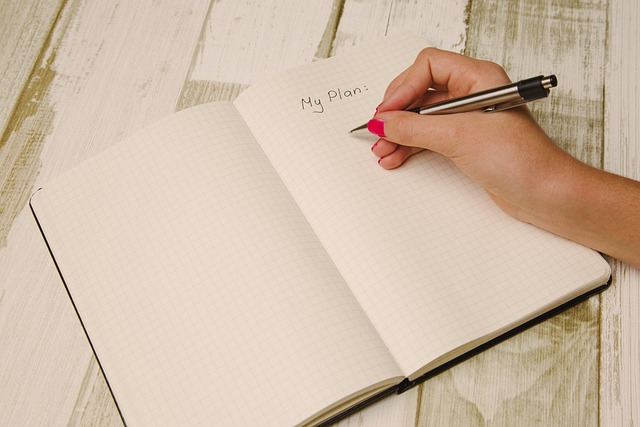
内定式は、企業が内定者に向けて行う正式なセレモニーです。採用活動の一環でありながら、社会人生活の第一歩としての意味もあります。
ここでは、内定式でよく実施されるプログラム内容を具体的に紹介します。
- 社長・役員からの挨拶
- 内定証書・通知書の授与
- 内定者による自己紹介
- 会社概要・業務内容の説明
- 今後のスケジュール・事務連絡
- 懇親会やグループディスカッション
①社長・役員からの挨拶
内定式の冒頭で行われるのが、社長や役員からの挨拶です。企業の理念や今後の展望について、トップの言葉で直接聞ける貴重な機会といえるでしょう。
形式的なスピーチだと思って油断していると、大切なポイントを見逃すおそれがあります。
自分がこれから入社する企業がどんな未来を描いているのかを意識しながら話を聞くことで、仕事へのモチベーションにもつながるはずです。
会社のホームページやパンフレットで事前に理念や方針を確認しておくと、内容をより深く理解できるでしょう。
姿勢を正し、しっかり目を見て話を聞くことも大切です。社会人としての第一印象が問われる場でもあるため、気を抜かないようにしてください。
②内定証書・通知書の授与
この時間は、企業から内定者一人ひとりに内定証書や通知書が手渡される、内定の正式な証しとなる場面です。就職活動の成果を改めて実感できる瞬間であり、多くの人にとって記憶に残るひとときとなるでしょう。
しかし、これは単なる儀式ではありません。企業からの信頼の証でもあるため、授与の際には丁寧な受け取り方やお礼の言葉が重要です。
ビジネスマナーが自然と身についているかどうかが見られるため、所作や表情に注意が必要です。
緊張してしまうこともあるかもしれませんが、落ち着いて丁寧に対応することが社会人としての第一歩といえます。
③内定者による自己紹介
内定式のプログラムの中でも、内定者による自己紹介はお互いの距離を縮める大事な場面です。
自分のことを相手に知ってもらうだけでなく、印象づけるチャンスでもあるため、話す内容は事前に整理しておくとよいでしょう。
自己紹介では、名前や出身、専攻に加えて、入社への意欲や将来の目標を簡潔に伝えると効果的です。暗記した文章を読み上げるよりも、自分の言葉で語るほうが自然で好印象です。
この自己紹介がきっかけで、懇親会などで会話が生まれることもあります。緊張するとは思いますが、笑顔を忘れずに、落ち着いて臨んでください。
④会社概要・業務内容の説明
会社概要や業務内容の説明では、企業の歴史や事業内容、業界での位置づけなどが紹介されます。これまで調べた情報と重なる部分もあるかもしれませんが、より実践的な内容が語られることが多いです。
知らなかった部署の話や、新しい取り組みなどに触れられることもあるため、ただ聞くだけでなく積極的に理解を深めておきましょう。
自分が配属されたらどんな仕事をするのか、イメージを膨らませることも大切です。
メモを取りながら話を聞くと、あとで見返したときにも役立ちます。この時間を通じて、企業理解をさらに深めてください。
⑤今後のスケジュール・事務連絡
内定式の終盤では、入社までのスケジュールや手続き、必要な書類などについての具体的な説明があります。説明を聞き漏らすと、後で困る可能性があるため注意が必要です。
健康診断の実施日や書類提出の締め切り、事前研修の有無など、細かな内容が共有されることも多いため、しっかりメモを取っておきましょう。場合によっては、事前課題や動画視聴などの準備も指示されます。
その場で不明点があれば、ためらわずに質問する姿勢も大切です。社会人としての責任感を持って、ミスなく対応してください。
⑥懇親会やグループディスカッション
懇親会やグループディスカッションは、内定者同士や先輩社員と交流する貴重な機会です。形式ばらない場に見えても、企業は参加者の協調性や積極性を見ていることが多いでしょう。
グループディスカッションでは、意見を言うだけでなく、相手の話をきちんと聞くことも大切です。バランスの取れた姿勢が評価されやすいため、話しすぎず黙りすぎず、全体を意識して行動してください。
懇親会では、先輩社員との会話を通じて社風や実際の働き方を知るチャンスがあります。気軽に話すことを心がけながらも、礼儀や配慮を忘れないようにしましょう。
内定式に向けた準備のポイント【服装・持ち物・心構え】

内定式は、企業との初めての正式な接点となる大切なイベントです。しっかり準備をしておけば、当日も安心して臨めるでしょう。
ここでは、服装や持ち物、心構えに関する具体的なポイントを紹介します。
- 清潔感のある服装を心がける
- 必要な持ち物を事前に揃える
- 自己紹介や発言を準備する
- 会社の理念や沿革を事前に確認する
- 当日のスケジュールを把握しておく
①清潔感のある服装を心がける
内定式では第一印象がとても重要です。たとえ「私服可」とされていても、TPOを踏まえた清潔感のある服装を選ぶのが基本でしょう。
企業側は、マナーや社会性を内定者から見極めようとしています。スーツ指定がある場合は、シワや汚れのないダークカラーのスーツが無難です。髪型や靴も整えておきたいところです。
私服参加が認められていても、派手なデザインや露出の多い服は避け、ビジネスカジュアルを意識してください。服装ひとつで印象は大きく変わります。
自信を持って臨むためにも、事前に鏡の前で全身を確認しておくと安心です。
②必要な持ち物を事前に揃える
内定式での忘れ物は、印象を損ねる原因になりかねません。前日までにバッグにすべて入れて、準備しておきましょう。
よくあるのが筆記用具やメモ帳の忘れです。これらは当日の情報をしっかり記録するために必須といえます。また、A4サイズのクリアファイルや案内メールの印刷物も、資料を整理するのに役立ちます。
企業によっては身分証や印鑑の持参が求められる場合もあります。案内メールを確認し、必要なものはリスト化してチェックしておくと忘れにくくなるでしょう。
③自己紹介や発言を準備する
内定式では、自己紹介や一言コメントを求められるケースが多くあります。準備不足のまま話し始めてしまうと、内容が薄くなってしまうため、事前に話す内容を考えておきましょう。
名前や大学、専攻といった基本情報に加えて、企業への期待や自分の強みを添えると印象に残る紹介になります。
表情や話し方も大切な要素です。緊張してしまいがちな人は、事前に家族や友人に話してみるのがよいでしょう。
場慣れしておけば、自分らしさも出しやすくなります。短くても心のこもった言葉を伝える準備が大切です。
④会社の理念や沿革を事前に確認する
内定式では、企業の代表や社員から話を聞く機会が多くあります。そのとき、企業理念や沿革に対する理解があると、会話の内容もより深く受け取れるでしょう。
事前に企業サイトをチェックし、創業の背景や事業の方向性、価値観などを確認しておいてください。
企業理念と自分の価値観が重なる点を見つけておくと、質問を受けたときや意見を求められた際にも、自然な受け答えができるようになります。
準備不足は興味のなさと誤解されることもあるため、丁寧な下調べが大切です。
⑤当日のスケジュールを把握しておく
内定式当日は、集合時間や会場の場所、所要時間などをしっかり把握しておく必要があります。初めての会場なら、Googleマップなどで最寄り駅からのルートも確認しておくと安心です。
交通機関の遅れに備えて、余裕を持った行動を心がけてください。
昼食の有無や服装の指示があるかどうかも、案内文を読めばわかります。読み飛ばしてしまうと、当日困ることになりかねません。
事前に予定を把握しておくことで、気持ちに余裕を持って式に参加できます。
内定式でのビジネスマナー
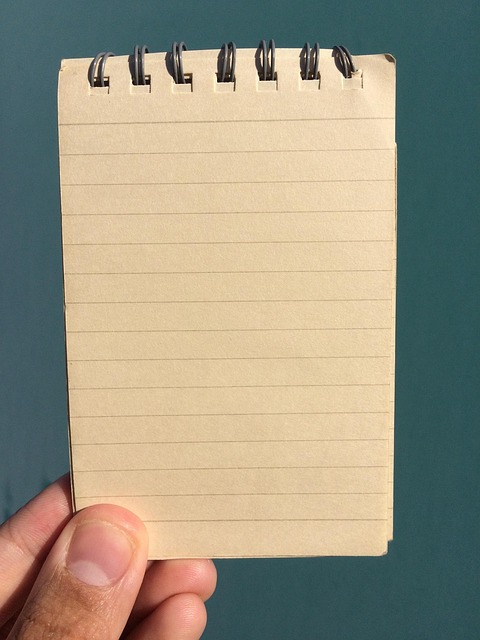
内定式での立ち居振る舞いは、企業側があなたのビジネスマナーや適応力を見極める基準になります。そのため、基本的なマナーを理解して実践することが欠かせません。
ここでは、内定式でのビジネスマナーについて4つ紹介します。
- 時間を厳守する
- 丁寧な言葉遣いや挨拶を心がける
- 指示を正確に聞き取り行動する
- 欠席時の連絡マナーに配慮する
①時間を厳守する
時間を守ることは、社会人としての基本です。内定式で遅刻してしまうと、「自己管理が甘い」「やる気がない」と受け取られてしまうおそれがあります。
開始の10分前には到着できるように、余裕を持って出発しましょう。
万が一、電車の遅延など避けられない事情がある場合は、すぐに企業へ電話で連絡してください。「ギリギリで間に合えばいい」という考えではなく、「早めの行動が当然」ととらえることが大切です。
この意識は、今後の仕事でも確実に役立ちます。信頼される社会人を目指すうえで、時間を守る習慣は欠かせません。
②丁寧な言葉遣いや挨拶を心がける
内定式では、初めて顔を合わせる人も多く、第一印象が今後に影響します。丁寧な言葉遣いや明るい挨拶を心がけることで、相手に好印象を与えることができます。
「お疲れ様です」「よろしくお願いいたします」など、基本的なビジネス用語は事前に確認しておくと安心です。また、姿勢や表情、アイコンタクトなども印象を左右します。
緊張していても、笑顔で挨拶するだけで雰囲気が和らぎます。誠実な態度は、相手に信頼感を与えるきっかけになりますので、意識して行動しましょう。
③指示を正確に聞き取り行動する
内定式では、担当者や社員から説明や指示を受ける場面が多くあります。説明を受ける際は、メモを取りながら真剣に聞きましょう。
聞き逃しや思い込みで動くと、トラブルにつながることもあるため注意が必要です。
また、不明点があれば遠慮せず確認する姿勢も大切です。「一度で完璧に理解すること」より、「確実に理解しようとする姿勢」が評価されます。
こうした対応は、入社後の業務でも信頼を得るうえで重要な力になります。内定式をその練習の場として活用してみてください。
④欠席時の連絡マナーに配慮する
やむを得ない事情で内定式を欠席する場合、その対応によって印象が大きく左右されます。欠席がわかった時点で、できるだけ早く電話で事情を伝え、謝意を伝えることがマナーです。
メールだけの連絡では不十分な場合もあるため、必ず電話で直接話すようにしましょう。後日、あらためてメールでお詫びを送るとより丁寧です。
「事情があれば欠席も仕方ない」と思うかもしれませんが、誠実な対応が社会人としての信頼を築きます。早めの連絡と感謝の気持ちを忘れずに伝えてください。
オンライン内定式の特徴

オンライン内定式は、従来の対面式と比べて多くのメリットがある一方で、特有の注意点も存在します。気軽に参加できる反面、意識が低く見えてしまう場面もあるため、事前準備が重要です。
ここではオンライン内定式の特徴について、ポイントごとに解説します。
- 場所を問わず参加できる
- 通信トラブルのリスクがある
- 参加者同士の交流が少ない
- 服装や背景などに配慮が必要
①場所を問わず参加できる
オンライン内定式の大きな利点は、自宅や帰省先など好きな場所から参加できることです。遠方に住んでいる人や体調に不安がある場合でも安心して出席できるでしょう。
移動にかかる時間や費用も削減でき、精神的にも余裕を持ちやすくなります。
ただし、この手軽さが気の緩みにもつながりがちです。たとえば、部屋着のまま参加してしまったり、背景に生活感がにじみ出てしまったりすることがあります。
それでは企業に良い印象を与えるのは難しいでしょう。
オンラインであっても、対面と同じ意識を持つことが大切です。カメラの映り方を意識しながら、周囲の環境も整えておきましょう。
②通信トラブルのリスクがある
オンライン開催では、ネット環境がそのまま式のスムーズさに直結します。接続が不安定だと、音声が途切れたり、映像が固まったりする可能性があるでしょう。
重要な説明を聞き逃してしまうことも起こり得ます。
こうしたトラブルを避けるためにも、前日までに通信テストを行っておくことをおすすめします。また、自宅のWi-Fiが不安な場合は、スマートフォンのテザリングを準備しておくと安心です。
スムーズな参加は、企業に対する誠意の表れでもあります。事前の確認と備えが印象を左右するポイントになります。
③参加者同士の交流が少ない
オンラインでは、内定者同士が自然に会話を交わす機会が少なくなります。対面であれば何気ない雑談が生まれることもありますが、画面越しではそうしたやり取りは起きにくいものです。
企業側がグループワークや少人数の交流の場を用意しているケースもありますが、受け身の姿勢では人間関係は築けません。笑顔で自己紹介をし、積極的に話しかける姿勢が求められます。
今後、同期として関わっていく仲間になる可能性もあるため、第一印象は大切です。画面越しでも積極性を意識してください。
④服装や背景などに配慮が必要
オンラインであっても、内定式は正式なイベントです。スーツ着用が基本で、髪型やメイクにも清潔感を意識する必要があります。
服装が整っていても、背景に洗濯物や私物が映ってしまえば、台無しになるかもしれません。
バーチャル背景を使う方法もありますが、PCのスペックによっては動作が不安定になることもあります。無地の壁を背にする、明るさを調整する、といった工夫をしてみてください。
画面に映る情報すべてがあなたの印象を形づくります。細かいところまで気を配る姿勢が、社会人としての一歩につながるはずです。
内定式プログラムの具体例まとめ【対面・オンライン別】

内定式のプログラムは、企業によって大きく異なります。近年ではオンライン開催やハイブリッド形式も増えており、開催形態に合わせた工夫が求められます。
ここでは、対面・オンライン・ハイブリッドそれぞれの印象的な事例を紹介し、内定式に参加する際の不安を解消できるよう詳しく解説します。
- 【対面】印象的な内定式事例
- 【オンライン】ユニークなオンライン企画例
- 【ハイブリッド】両立型プログラムの成功例
①【対面】印象的な内定式事例
企業が実施する対面形式の内定式では、単なる挨拶や会社説明だけでなく、記憶に残る演出が取り入れられることが多くあります。
たとえば、内定者が一人ひとり自己紹介を行ったり、社長から直接内定証書を手渡されるなど、参加者の印象に残るよう工夫されています。
こうした演出には、内定者に安心感や企業への親しみを持ってもらいたいという意図があるのでしょう。さらに、先輩社員との交流時間を設けることで、実際の職場の雰囲気を肌で感じられるメリットもあります。
一方で、事前の準備を怠ると、緊張のあまりうまく話せないこともあるかもしれません。自分の強みや学生生活で得た経験を事前に整理しておくことで、スムーズに話せるようになります。
対面式では身だしなみや立ち居振る舞いといった非言語的な要素も大きく影響します。清潔感のある服装や礼儀正しい態度を意識することが、良い印象につながるポイントです。
②【オンライン】ユニークなオンライン企画例
オンライン形式の内定式では、物理的な距離を超えて一体感を生み出す工夫がされています。たとえば、事前に内定証書を郵送し、全員が同時に開封する演出や、バーチャルオフィスツアー、などです。
中には、アイスブレイクをゲーム形式で行ったり、先輩社員とのテーマ別対談を用意する企業もあります。
これにより、画面越しであっても内定者同士や社員とのつながりが生まれ、安心感や親近感が育まれるのです。
ただし、オンラインならではの課題もあります。通信トラブルや周囲の雑音など、予期せぬトラブルが発生することもあるでしょう。そのため、通信環境を整え、静かな場所を確保することが重要です。
また、画面越しの印象も軽視できません。表情やカメラ位置、話し方など、細かい部分に配慮することで、相手に好印象を与えることができます。
③【ハイブリッド】両立型プログラムの成功例
ハイブリッド形式の内定式は、遠方からの参加者にも配慮しつつ、対面の良さも取り入れた柔軟なスタイルです。
成功事例としては、一部の内定者を本社に集めてライブ配信を行い、他の参加者がオンラインで視聴・参加する形式が挙げられます。
対面参加者とオンライン参加者が分断されないよう、グループワークや共通テーマのディスカッションを通じて交流を促す仕掛けもあります。
こうした形式は、準備に時間と手間がかかるものの、双方のメリットを最大限に活かせる方法でもあります。オンライン参加だからといって油断せず、服装や態度には十分に注意してください。
対面側も配信されていることを意識し、行動や言葉遣いに気を配る必要があります。形式にとらわれず、状況に応じた振る舞いを意識しましょう。
内定式プログラムの重要性と効果的な活用方法

内定式は、内定者との信頼関係を築き、入社意欲を高めるために欠かせない企業イベントです。内定辞退を防止し、企業理解を深める機会としても重要な役割を果たします。
その開催時期やプログラム内容には企業ごとの工夫が見られ、特に社長挨拶や懇親会などは印象に残るポイントです。近年ではオンライン内定式も増え、通信環境や背景への配慮が求められます。
また、対面・オンラインを問わず、内定者の不安を軽減するための、プログラムが組まれているはずです。
対面だけでなく、オンラインでも服装・持ち物・心構えなどの事前準備やビジネスマナーの徹底が大切になります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












