内定式は欠席できる?理由と注意点を徹底解説!
「内定式って絶対出席しないといけないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
内定をもらった後、企業からの正式な案内として送られてくる内定式ですが、どうしても都合がつかない、または参加したくないという場合もありますよね。
本記事では、内定式を欠席することが可能かどうか、欠席の際に注意すべきこと、そして適切な対処法について詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
内定式とは?

内定式とは、企業が内定を出した学生に対して、正式な内定通知を行い、今後のスケジュールや会社の方針を伝える場です。一般的には10月初旬に開催され、多くの企業で毎年恒例の行事とされています。
当日は、企業の代表者からのメッセージや役員挨拶、今後の研修内容の説明、内定者同士の交流などが行われることが多いです。
学生は会社への理解を深めるとともに、仲間とのつながりを築くきっかけにもなります。入社前に企業文化や価値観に触れることで、不安を和らげ、社会人としての自覚を持つ第一歩となるでしょう。
形式的なイベントに見えるかもしれませんが、企業にとっては大切な節目であり、内定者への期待を込めた場でもあります。
このように、内定式は単なる案内や顔合わせではなく、入社までの準備を円滑に進めるための重要なイベントといえます。
内定式は欠席できる?

結論から言えば、内定式を欠席することは可能です。内定式は、あくまで企業が内定者に向けて開催する任意の行事です。そのため、やむを得ない事情があれば参加を見送っても問題はありません。
大学の授業やゼミと重なる場合、体調不良や家庭の都合など、正当な理由があれば企業側も理解を示すケースがほとんどです。
欠席の連絡はできるだけ早く、メールか電話で丁寧に行いましょう。その際には、欠席せざるを得ない理由を具体的に伝えると同時に、内定をいただいた感謝の気持ちも忘れずに添えると好印象です。
企業によっては、内定式を通じて会社の雰囲気を知ってもらったり、同期とのつながりを築いたりすることを重視している場合があります。
そのため、可能であれば出席するのが理想ですが、どうしても出席が難しい場合は、誠実かつ丁寧な対応を心がければ、欠席による悪影響は最小限に抑えられるでしょう。
内定式に参加したくない学生は多い

内定式に参加したくないと感じる学生は、意外に多くいます。
主な理由として、「まだ入社を決めきれていない」「内定先に迷いがある」「周囲との関係が不安」といった心理的な壁が挙げられます。さらに、あまり堅苦しい場が得意ではないという人も一定数いるでしょう。
こうした気持ちは決して珍しいものではないため、「参加したくない」と感じること自体に、必要以上の罪悪感を持つ必要はありません。
ただし、企業側は内定式を通じて学生の意欲やコミュニケーション力を確認し、今後の配属や評価の参考にする場合もあります。そのため、欠席によって印象を悪くするリスクも無視できません。
参加を迷うときは、自分がなぜ不安なのかを整理し、友人やキャリアセンターなど信頼できる相手に相談してみてください。自分にとって何が大切かを見つめ直すきっかけにもなるはずです。
内定式に参加したくないと感じる理由
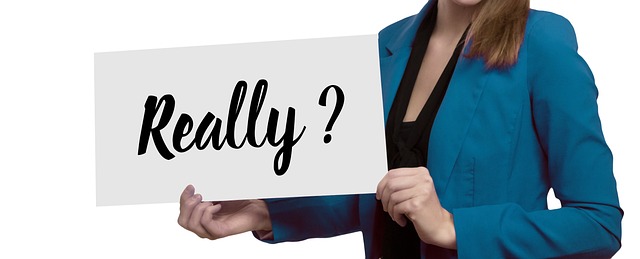
内定式に対してネガティブな感情を抱く理由はさまざまですが、まず挙げられるのが、「雰囲気に馴染めるかどうか」という不安です。
内定式では、初対面の同期や人事と交流する機会が多くあります。人付き合いが得意でない学生にとっては、強い緊張や負担を感じやすい場面といえるでしょう。
また、企業に対して信頼が持てなかったり、他社と迷っていたりする段階では、気持ちが固まらないまま参加することに抵抗を感じる場合もあります。
内定を辞退する可能性があるときは、「出席しても意味があるのか」と迷ってしまうのも無理はありません。とはいえ、欠席の判断は慎重に行う必要があります。
さらに、実家からの移動に時間や費用がかかる、授業や試験と重なるなど、物理的・時間的な負担も理由の一つです。まずは自分の状況や気持ちを整理し、無理のない選択をしてください。
内定式を欠席することで考えられるリスク
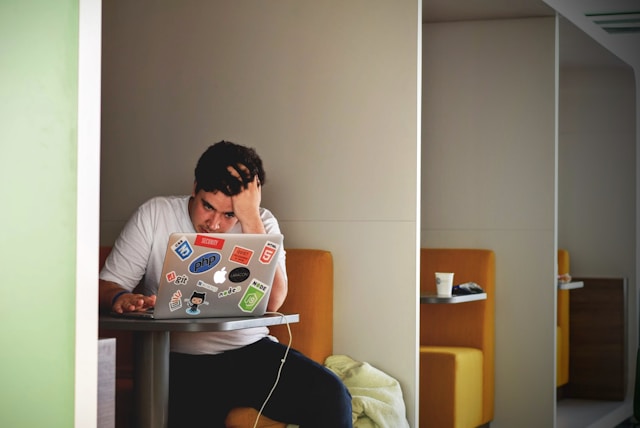
内定式は、入社前の大切な一歩です。しかし、さまざまな事情で欠席を検討する就活生も少なくありません。
ここでは、内定式を欠席することで生じる可能性のあるリスクについて、具体的に紹介します。
- 人事担当者からの印象が悪くなる可能性
- 同期との関係構築の機会を失う
- 会社の雰囲気や文化を理解できない
- 内定後のフォロー体制から外れるリスク
- 他の内定者と情報格差が生まれる
①人事担当者からの印象が悪くなる可能性
内定式に参加しないと、人事担当者に与える印象が悪くなるおそれがあります。会社側は内定者を「これから一緒に働く仲間」として迎える準備を進めており、内定式はそのスタートラインです。
欠席の連絡がなかったり、理由が曖昧だったりすると、「熱意がない」「社会人としての常識がない」といったネガティブな印象につながりかねません。
とはいえ、事前に丁寧な連絡を入れ、やむを得ない事情があることを誠意を持って説明すれば、大きな問題には発展しないでしょう。重要なのは、誠実な姿勢とタイミングの良い対応です。
②同期との関係構築の機会を失う
内定式は、同期と初めて顔を合わせる貴重な場です。この機会を逃すと、入社後に人間関係を築くまでに時間がかかってしまうかもしれません。
特に、チームワークが求められる職場では、早期に信頼関係を築いておくことが、その後の働きやすさに直結します。
もし欠席する場合は、後日行われる懇親会や研修などの場を活用し、積極的に関係づくりに取り組んでください。少しの工夫で、距離を縮めるきっかけは作れます。
③会社の雰囲気や文化を理解できない
内定式は単なるセレモニーではなく、会社の雰囲気や文化を知るチャンスでもあります。先輩社員の話や経営陣の方針を直接聞くことで、その企業がどのような価値観を持っているのかを体感できます。
こうした「肌で感じる情報」は、資料や説明会だけでは得られません。欠席すると、そうした感覚的な理解の機会を失い、入社後に「思っていた職場と違った」と感じるリスクも高まるでしょう。
④内定後のフォロー体制から外れるリスク
内定式では、今後のスケジュールや必要な手続きについて説明されることがよくあります。欠席した場合、こうした情報を受け取るのが遅れたり、伝達ミスが起きたりする可能性もあります。
また、フォロー体制の中で「連絡が取りづらい内定者」と認識されてしまうと、サポートの優先度が下がってしまうかもしれません。
欠席せざるを得ないときは、事前に連絡を入れたうえで、必要な情報を確実にキャッチアップする姿勢を持ちましょう。
⑤他の内定者と情報格差が生まれる
内定式では、同期同士で情報交換をする機会が自然と生まれます。こうした非公式なやりとりから得られる情報は、意外と多く、入社後の安心感にもつながります。
しかし、欠席してしまうと、そうしたやりとりに加われず、ほかの内定者との間に情報格差が生まれることもあります。
その差は、準備の質や不安の大きさに影響を与えるため、できる限り補える方法を考えておくとよいでしょう。
内定式を欠席したいときの対処法と事前準備

内定式を欠席したいと考えている就活生にとって、「どう伝えるべきか」「どんな準備が必要か」といった不安はつきものです。
適切な対処法を知っておけば、企業との信頼関係を保ちながら、自分の都合にも対応できます。ここでは、欠席時の準備や伝え方を具体的に解説します。
- 欠席理由の整理と明文化
- 企業への早期連絡の実施
- 参加代替手段の相談
①欠席理由の整理と明文化
内定式を欠席する際にまず必要なのは、欠席理由を整理し、明確にしておくことです。理由が曖昧なままだと、企業に不信感を与えてしまうかもしれません。
たとえば、家庭の事情、大学の予定、やむを得ないイベントなど、正直で具体的な内容を整理しておくと安心です。
重要なのは、単に「行けません」と伝えるのではなく、「どうしても参加が難しい事情がある」と納得してもらえる伝え方を意識することです。
どう伝え、どう対応するかによって、相手の受け止め方は大きく変わってきます。誠意ある説明が、信頼につながるはずです。
②企業への早期連絡の実施
欠席の意思が固まったら、できるだけ早めに企業へ連絡を入れるようにしてください。直前になってしまうと、企業側の準備に支障が出たり、対応が難しくなったりする恐れがあります。
内定式は企業にとっても重要なイベントのひとつであり、事前に事情を共有しておけば柔軟に対応してもらえる可能性もあります。
電話での連絡が基本ですが、その後にメールでも一報を入れておくと記録が残るため安心です。
誠意を持って早めに動くことで、信頼を損ねることなく欠席の意向を伝えられるでしょう。できる限りスムーズな連絡を心がけてください。
③参加代替手段の相談
「出席できない場合は、完全に情報が得られない」とは限りません。内定式参加の代替手段があるのかの相談をしてみましょう。
最近では、オンライン参加や後日資料の送付、録画配信などの代替手段を用意している企業も増えています。
ただ「出られません」と言うのではなく、「別の形で内容を把握したい」という意欲を示すことが大切です。自分から積極的に提案を持ちかければ、企業側も柔軟に対応してくれることがあるでしょう。
参加できない事情があっても、代替案を通じて企業との接点を保ち、社会人としての責任感を伝えることが大切です。前向きな姿勢を持って対応してみてください。
内定式を欠席する際のマナーと注意点
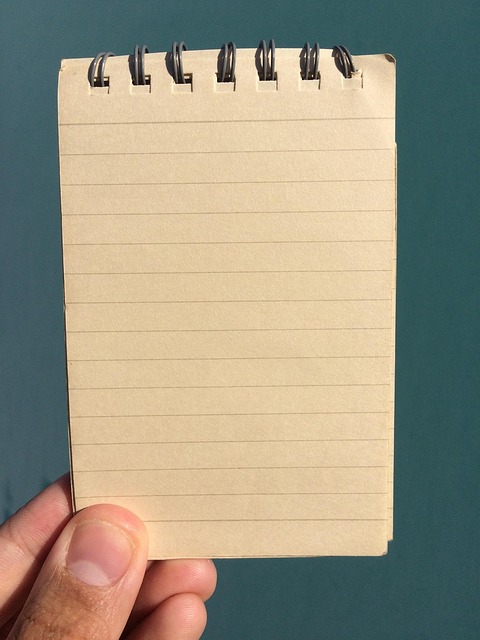
内定式を欠席する場合、たとえやむを得ない事情があっても、企業との信頼関係に影響を与えるおそれがあります。就活生としての第一歩ともいえる内定式に出席しない際は、誠意ある対応が求められます。
ここでは、欠席時に注意すべきマナーや、適切な連絡方法について詳しく解説します。
- 電話で丁寧に理由を伝える
- メールの場合はビジネスマナーを守る
①電話で丁寧に理由を伝える
内定式を欠席する際に最初に検討したいのが、電話での連絡です。電話は文章よりも感情や誠意が伝わりやすく、直接話すことで相手に安心感を与えられるでしょう。
体調不良や家庭の事情など、やむを得ない理由があるなら、できる限り率直かつ丁寧に説明してください。
曖昧な説明は誤解を生みやすく、企業側の不信感につながる可能性もあります。電話をかける時間帯にも配慮が必要で、一般的には午前中の業務が始まって間もない時間が望ましいでしょう。
また、緊張を和らげるためにも、話す内容を事前にメモにまとめておくと安心です。対面に近い手段だからこそ、欠席というマイナスな報告でも誠実な印象を残すことができるはずです。
②メールの場合はビジネスマナーを守る
どうしても電話が難しい場合や、企業からメールでの連絡を求められているときは、メールでも問題ありません。ただし、ビジネスマナーを意識し、丁寧でわかりやすい文章を心がけることが必要です。
件名は「内定式欠席のご連絡」など、用件が明確に伝わる内容にしましょう。
宛名には企業名と担当者の氏名を正確に記載し、冒頭で自分の氏名と所属を名乗ってください。その後、欠席の理由とお詫びの言葉を簡潔に伝えることが大切です。
最後に、今後のご指導への感謝や、引き続きのよろしくの旨を添えると、印象がより良くなります。
絵文字やカジュアルな表現は避け、敬語を丁寧に使うよう意識しましょう。送信前には誤字脱字や表現の不備がないかをしっかり確認することを忘れないでください。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
内定式欠席の連絡例文【メール・電話対応の例】

急な体調不良や家庭の事情などで、内定式を欠席せざるを得ないこともあるでしょう。そんなとき、「どのように連絡すれば失礼がないのか…」と不安に思う方も多いはずです。
ここでは、電話やメールでの適切な連絡方法と、その例文をまとめて紹介します。
また、ビジネスメールがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジン編集部が作成したメール自動作成シートを試してみてください!
ビジネスマナーを押さえたメールが【名前・大学名】などの簡単な基本情報を入れるだけで出来上がります。
「面接の日程調整・辞退・リスケ」など、就活で起きうるシーン全てに対応しており、企業からのメールへの返信も作成できるので、早く楽に質の高いメールの作成ができますよ。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
①電話での欠席連絡例文
内定式を体調不良などで欠席せざるを得ない場合、電話での連絡は丁寧かつ誠意を込めて行うことが重要です。ここでは、一般的な大学生が実際に使える電話での欠席連絡の例文を紹介します。
| お世話になっております。〇〇大学の〇〇と申します。 内定式についてのご連絡でお電話させていただきました。実は、数日前から体調を崩しており、病院でインフルエンザと診断されました。 大変残念なのですが、当日の参加が難しい状況です。ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、欠席させていただければと存じます。 後日、資料等がございましたらご共有いただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 |
体調不良という理由は多くの学生が経験するため共感を得やすく、無理のないストーリーとして使いやすいです。相手への配慮や今後のフォローへの意欲も忘れずに含めましょう。
②メールでの欠席連絡例文
内定式をやむを得ず欠席する際は、企業への誠意を伝える丁寧なメールが重要です。ここでは、大学の授業やゼミなどが理由で出席できないケースを想定した例文を紹介します。
| 件名:内定式欠席のご連絡(〇〇大学・氏名) 〇〇株式会社 人事部 ご担当者様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇〇〇と申します。 この度は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。 さて、10月〇日に予定されております内定式についてご連絡申し上げます。 誠に申し訳ございませんが、当日は大学にて必修授業およびゼミ活動が重なっており、どうしても欠席せざるを得ない状況でございます。 貴重な機会に参加できず、大変心苦しく存じますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。 内定者としての自覚を持ち、今後の連絡事項や課題等には誠実に対応してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 何卒よろしくお願い申し上げます。 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 氏名:〇〇〇〇 メールアドレス:xxxxx@xxxxx.jp 電話番号:090-xxxx-xxxx |
大学の授業を理由にする場合は「必修」「ゼミ」などを具体的に記載すると信頼感が増します。感謝の言葉と欠席の無念さを丁寧に伝えることで、誠意ある印象を与えられる構成にしましょう。
③当日連絡が必要な場合の例文
内定式当日にやむを得ず欠席する必要が生じた場合、企業への連絡は速やかに、誠意を持って行うことが重要です。ここでは、体調不良により急遽欠席するケースを想定した例文を紹介します。
| お世話になっております。〇〇大学の〇〇です。 本日は内定式に出席する予定でしたが、今朝から体調が優れず、発熱もあるため、やむを得ず欠席させていただきたくご連絡いたしました。突然のご連絡となり、大変申し訳ございません。 内定式という大切な場に欠席することは心苦しいのですが、他の皆さまへのご迷惑を考慮し、このような判断をいたしました。後日、改めてご挨拶やご説明の機会を頂けますと幸いです。 このたびはご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。 |
当日の欠席連絡では、「なぜ欠席するのか」を簡潔に述べた上で、謝罪と今後の対応への意欲を示すことがポイントです。文面は丁寧かつ控えめに、感情よりも状況説明を優先して書くと信頼感が高まります。
内定式欠席に関するよくある質問(Q&A)

内定式を欠席したい、もしくは欠席しなければならないと考えている就活生にとって、不安や疑問は尽きません。
ここでは「内定式を欠席する場合の対応やリスク」について、よくある質問をもとに詳しく解説します。
欠席しても問題ないのか、どんな点に注意すればよいのかなど、内定を守りながら冷静に判断するためのヒントをお届けします。
- 内定式を欠席しても内定者研修に参加できる?
- 欠席理由として認められやすいケース
- 内定式の出欠確認はいつどのように行われる?
- 内定式と内定者懇親会の違い
①内定式を欠席しても内定者研修に参加できる?
基本的に、内定式を欠席しても内定者研修には問題なく参加できます。内定式は企業文化の共有や内定者同士の顔合わせを目的としており、研修とは性質が異なるためです。
ただ、何の連絡もせずに欠席すると「入社意欲が低い」と受け取られてしまうかもしれません。欠席する事情があるなら、早めに企業へ丁寧な連絡を入れたうえで、研修への参加意思を明確に伝えることが大切です。
誠意ある対応が、企業との信頼関係を築く第一歩になります。社会人としての心構えを示す機会ととらえましょう。
②欠席理由として認められやすいケース
内定式を欠席しても、納得されやすい理由であれば悪い印象につながることはほとんどありません。代表的な例としては、授業や試験といった学業の都合、身内の冠婚葬祭、体調不良などが挙げられます。
一方で、「参加したくない」「気が進まない」といった曖昧な理由は理解されにくく、注意が必要です。欠席連絡をする際は、理由を明確かつ簡潔に伝え、謝意や今後への意欲もあわせて示しましょう。
誠実で前向きな姿勢を見せることで、欠席によるリスクは最小限に抑えられるはずです。
③内定式の出欠確認はいつどのように行われる?
多くの企業では、内定通知の後、メールや郵送で出欠確認の案内が届きます。時期としては内定式の1〜2か月前が一般的です。
案内には、開催日時や場所、服装の指定、返信の締切などが記載されています。うっかり見落とすとトラブルになりかねませんので、内容をよく確認したうえで、指示された方法で必ず返信してください。
返信が遅れると「連絡がない=出席しない」と判断されてしまうこともあります。丁寧かつ迅速な対応を心がけましょう。
④内定式と内定者懇親会の違い
内定式と内定者懇親会は、目的も内容も大きく異なります。内定式は企業からの正式な内定通知の場であり、組織の一員になることを伝えるフォーマルな行事です。
一方、懇親会は、内定者同士や先輩社員との交流を目的としたカジュアルなイベントにあたります。服装や雰囲気も異なるため、混同しないように注意が必要です。
特に内定式は企業にとって重要なセレモニーですので、欠席する場合は十分な配慮と連絡を欠かさないようにしてください。
内定式を欠席する場合に押さえておきたいポイント

内定式を欠席することは可能ですが、事前の準備と丁寧な対応が重要です。参加を望まない学生は意外と多く、理由もさまざまですが、欠席によるリスクも無視できません。
たとえば、人事担当者からの印象悪化や、同期との関係構築の機会を失う可能性があります。さらに、会社の雰囲気を知る機会を逃したり、情報格差が生じたりすることもあります。
だからこそ、欠席したい場合には早めに連絡を取り、代替手段を相談する姿勢が大切です。電話やメールでの連絡例文や注意点を参考に、適切なマナーを守りましょう。
内定式を欠席しても、フォロー体制や内定者研修には参加できるケースもあるため、確認しておくと安心です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













