情報系出身者向け|公務員の仕事内容と必要なスキル
「情報系の進路って、やっぱり民間企業が主流なのかな…」
そう考える人も多い中で、「公務員になる」という選択肢に興味を持つ情報系出身者が増えています。行政のDX推進やセキュリティ強化の重要性が高まる今、公務員としてITスキルを活かす道は、十分に現実的で魅力的なキャリアのひとつです。
本記事では、情報系出身の公務員の仕事内容や求められるスキル、転職ルート、メリット・デメリットまでを丁寧に解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
情報系出身の求職者に採用側が期待していること

情報系を学んだ方が公務員を目指す場合、民間と異なり、スキルだけでなく社会的使命への理解も評価対象になります。行政の視点で物事を考える姿勢が求められるのです。
行政機関では、システム設計やネットワーク管理など、デジタル化を推進できる専門人材が重宝されています。高度な技術が実務に直結する場面も少なくありません。
ただし、単に技術を実装するだけでは不十分です。住民の利便性や業務の効率化といった観点で応用する柔軟さが、現場では重要視される傾向にあります。
加えて、他部署との連携や説明の場面も多いため、協調性や伝える力も欠かせません。「技術の高さ」と「公共性への理解」、その両立が情報系出身者に強く期待されています。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
情報系公務員の主な仕事内容

情報系公務員の仕事は、庁内のIT環境整備から行政サービスのデジタル化まで幅広く求められます。
民間企業で培ったITスキルを活かせる場面も多く、情報系出身者にとってやりがいのある職種といえるでしょう。ここでは、情報系公務員の代表的な仕事内容を5つの観点から紹介します。
- 庁内システムの企画・管理業務
- ネットワークやサーバーの保守・運用
- 情報セキュリティ対策の立案と実行
- 行政サービスのデジタル化推進
- 技術動向に応じたシステム改善提案
①庁内システムの企画・管理業務
庁内システムの企画や管理は、情報系公務員にとって基本となる業務の一つです。職員が日常的に使うシステムの安定運用は、業務全体の効率を大きく左右します。
たとえば、文書管理や人事給与、住民情報のシステムなどは、組織の基盤を支える重要な要素です。その運用を支えるためには、現場のニーズを正確に把握し、実情に合った設計や調整をする必要があります。
民間での開発経験がある方は、その知識を強みにできるでしょう。一方で、予算や組織の制約もあるため、すべてを理想通りに導入できるとは限りません。
そこで必要になるのが、現実とのバランスを見極めた調整力です。柔軟な対応力を身につけることができれば、他の分野にも応用しやすく、公務員としての信頼も高まります。
②ネットワークやサーバーの保守・運用
ネットワークやサーバーの保守・運用は、庁内の情報インフラを支える非常に重要な業務です。これらの機器が安定して稼働しているからこそ、職員の業務や住民向けサービスが円滑に提供されます。
障害が発生した際には、原因を迅速に特定し、スムーズに復旧させることが求められるのです。この対応の正確さと速さが、組織内の信頼にもつながるでしょう。
さらに、セキュリティの観点からは、構成管理や定期的なアップデートも不可欠です。公的機関には独自のルールや仕様があるため、それに沿って安定した運用を続けるには工夫が必要になります。
こうした経験を積むことで、技術だけでなく、組織運営に対する理解も深まるはずです。
③情報セキュリティ対策の立案と実行
行政では、個人情報や機密情報を数多く扱うため、情報セキュリティは極めて重要なテーマです。情報系公務員は、ポリシーの策定からシステム面の対応、さらには職員への啓発まで広く関わります。
近年では、サイバー攻撃も多様化しており、従来型のウイルス対策だけでは不十分といえるでしょう。
そのため、最新の攻撃手法や脆弱性に関する知識を身につけ、それに応じた具体的な対策を講じる力が求められます。たとえば、アクセス制御の強化や人的ミスを防ぐための運用ルールづくりが重要です。
専門知識を持つ人材は特に評価される傾向にあり、自身の知識を活かせる業務でもあります。
④行政サービスのデジタル化推進
住民サービスの向上を目指すうえで、行政のデジタル化は欠かせません。情報系公務員は、電子申請やオンライン受付の導入など、サービス改革の中心的な役割を担います。
たとえば、住民票のコンビニ交付やオンライン相談窓口など、実際に効果を上げている取り組みも増えてきました。
これらを実現するには、現場の職員や外部ベンダーと連携しながら進めていく必要があります。ときには現場の理解を得るために工夫が求められますが、その過程でプロジェクト推進力が磨かれるはずです。
一度導入して終わりではなく、利用者の声を取り入れて改善を重ねる視点が大切でしょう。
⑤技術動向に応じたシステム改善提案
ITの技術は日々進化しており、古いシステムを使い続けることはリスクにもなりかねません。情報系公務員には、常に新しい技術に目を向け、その導入を提案する力が期待されています。
クラウド化やAIの活用、ゼロトラストなどの先端技術を行政に取り入れるには、現場に合った形で展開することが必要です。ただし、最新技術だからといってすぐに導入すればよいわけではありません。
重要なのは、業務上の課題を見極め、それに対して効果的な解決策として技術を活用する姿勢です。現実的な提案を行うことができれば、住民サービスの質向上にもつながっていくでしょう。
情報系公務員に求められるスキル
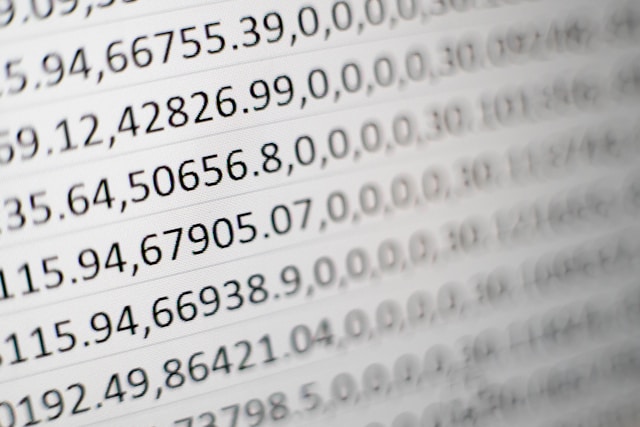
情報系出身者が公務員として活躍するには、ITの知識だけでは不十分です。公共機関ならではの環境に対応できる「総合力」が必要とされます。
ここでは、情報系公務員に期待される主なスキルを5つ紹介します。
- ICTインフラに関する専門知識
- 課題解決力と論理的思考力
- チームでの連携を重視するコミュニケーション能力
- セキュリティ意識とリスク管理能力
- 行政と民間技術の橋渡しをする応用力
①ICTインフラに関する専門知識
公務員として情報システムの整備や運用に関わるには、サーバやネットワーク、クラウドなど幅広い知識が求められます。
たとえば、庁内ネットワークの安定運用や拠点間接続の保守、トラブル発生時の対応などが主な業務です。公共機関では、最新技術だけでなく、古いシステムとの共存も前提となります。
そのため、レガシーシステムを理解しつつ、段階的な更新計画を描ける柔軟性が必要です。紙ベースの運用が残る現場もあり、そこにITをどうなじませるかが課題となるでしょう。
技術を使いこなすだけでなく、現場や制度の制約をふまえて適切に活用できる力が重視されます。専門知識と現実的な応用力の両方が、強く求められているのです。
②課題解決力と論理的思考力
情報系公務員には、単なる作業者ではなく「問題解決者」としての活躍が期待されます。自ら課題を見つけ、改善策を提案する力が重視される立場です。
たとえば、住民サービスのデジタル化が停滞している場合、原因を論理的に分析し、改善の方向性を導き出す姿勢が求められます。
操作の難しさや利用者層の特性まで深掘りし、誰もが納得できる改善策を検討する姿勢が、公務の現場では特に評価されます。
さらに、複数部署との連携も頻繁に発生します。筋道を立てて説明し、関係者を巻き込みながら前に進める力があれば、大きな戦力となるでしょう。
③チームでの連携を重視するコミュニケーション能力
情報システムの導入や運用は、1人では進められません。他部署の職員や外部の協力業者、時には住民との連携も必要です。そのため、情報系でも「黙々と作業していればいい」とは限りません。
特に行政現場では、ITに詳しくない人とも一緒に業務を進める場面が多くあります。その際には、専門用語をわかりやすく伝えたり、相手の立場を理解しながら調整したりする力が求められるのです。
意見がぶつかる場面でも、感情的にならず妥協点を探れる柔軟さが大切。スムーズな業務推進のためには、的確に伝える力と、相手の話をしっかり聴く力の両方が欠かせません。
こうした「対話力」を持った人材は、組織の中でも非常に重宝されるでしょう。
④セキュリティ意識とリスク管理能力
公務員は、個人情報や機密文書など、重要なデータを多く扱います。そのため、情報セキュリティに対する高い意識が求められるのです。
たとえば、USBメモリの使用制限やファイルの取り扱いルールなど、細かい規定を守る姿勢が大切。また、万が一トラブルが起きたときには、迅速な初動対応と再発防止策の検討が必要になります。
セキュリティソフトの導入だけでは不十分で、制度・運用・技術の3つを組み合わせた総合的な対応が求められるのです。
最近では、自治体を狙ったサイバー攻撃も増えており、セキュリティ対策の重要性は一段と高まっています。自分には関係ないと思わず、積極的に関与していく姿勢が信頼される要素になるでしょう。
安全な行政サービスを維持するには、日頃からリスクに向き合える人が不可欠です。
⑤行政と民間技術の橋渡しをする応用力
情報系公務員には、民間企業で使われている技術を行政にうまく応用する力が求められます。
たとえば、チャットボットやRPA(業務自動化ツール)を、住民サービスや職員業務の改善にどう生かすかを考える必要があるでしょう。
ここで大切なのは、技術の新しさそのものではなく、「それが現場で役立つかどうか」です。さらに、予算や導入にかかる手間など、行政ならではの制約も踏まえたうえで提案できることが重要になります。
こうした制限の中で、効果的で無理のない施策を考えられる人は、組織の中でも貴重な存在となるでしょう。民間と行政の技術ギャップを埋める「橋渡し役」としての視点が、今後ますます重要になります。
情報系公務員になるメリット

情報系の知識を活かして公務員を目指すことには、多くのメリットがあります。安定した雇用や社会貢献の実感、将来を見据えたキャリア形成、働き方の柔軟さなどがその代表例です。
ここでは、情報系出身者が公務員として働くことで得られる具体的な利点を紹介します。
- 安定した雇用環境で長く働き続けることができる
- 公務を通じて社会貢献を実感することができる
- 情報系の専門知識を活かして活躍することができる
- 将来を見据えたキャリアプランを構築することができる
- プライベートとの両立がしやすい働き方ができる
①安定した雇用環境で長く働き続けることができる
公務員の魅力としてまず挙げられるのが、景気に左右されにくい安定した雇用です。
とくに情報系の職種は、社会全体のデジタル化の流れにともなってニーズが高まっており、将来的にも継続した需要が見込まれます。
民間企業では、業績や人員整理などの影響で突然職を失う可能性がありますが、公的機関ではそのリスクが低めです。
さらに、人事評価や昇進の仕組みも整っており、着実にキャリアを築いていける環境が整っています。腰を据えて長く働きたい方にとっては、大きな安心材料になるでしょう。
②公務を通じて社会貢献を実感することができる
情報系の技術を使って、地域や社会に直接役立てる点も公務員ならではの強みです。
たとえば、オンライン申請や住民向けポータルの整備、防災情報の発信インフラ構築など、公共性の高い業務に携わる機会があります。
民間と違い、利益を目的とせず住民の利便性を重視して取り組むため、仕事の成果が生活に直結しやすく、やりがいを感じやすいのも特徴です。
自分のスキルが誰かの役に立っていると実感したい方には、充実感のある職場といえるでしょう。
③情報系の専門知識を活かして活躍することができる
情報系出身者にとって、公務員は知識とスキルを活かしやすい職場です。庁内ネットワークの構築やセキュリティ対策、システム導入の計画など、専門的な業務に関わる場面が多くあります。
また、新技術の活用や改善提案が求められる場面も多く、自らの知識を生かして組織の課題解決に貢献できます。
民間での経験を公的分野で応用したいと考えている方にとって、公務員は理想的なキャリアの選択肢といえるでしょう。
④将来を見据えたキャリアプランを構築することができる
公務員はキャリアパスが明確で、将来設計を立てやすい点も大きな特長です。異動や昇進の制度が整っており、自分の意欲やスキルに応じて段階的にステップアップすることができます。
とくに情報系分野では、研修や技術研鑽の機会が充実しており、専門性をさらに深めていけるでしょう。庁内のシステム担当からデジタル施策の企画立案へと職域を広げることも可能です。
将来を見据えて着実に成長したい方には、安心して長期的なプランを立てられる環境といえます。
⑤プライベートとの両立がしやすい働き方ができる
働き方の柔軟性も、公務員としての大きなメリットです。最近では、多くの自治体や省庁でフレックスタイム制やテレワーク制度が導入されており、生活に合わせた働き方が実現しやすくなっています。
また、残業が少なく、休暇も取得しやすい傾向にあるため、家庭やプライベートの時間を大切にしながら仕事に取り組むことができるのです。
無理なく長く働きたいと考えている方にとって、公務員は非常に適した選択肢でしょう。
情報系公務員になるデメリット

情報系のスキルを持つ方にとって、公務員の仕事は安定性や社会的意義の高さが大きな魅力です。しかし一方で、民間とは異なる特有の課題もあるでしょう。
ここでは、情報系公務員として働く際に注意したい5つのデメリットを紹介します。
- 技術革新への対応が遅れることがある
- 開発業務よりも管理業務が中心となる
- キャリアアップの選択肢が限られることがある
- 民間と比べて給与水準が低めに設定される
- 新技術の導入に時間を要することが多くなる
①技術革新への対応が遅れることがある
公務員の情報分野では、最新技術の導入が民間に比べて遅れがち。なぜなら、新しい技術を導入するには安全性やコスト、影響範囲を慎重に検討する必要があるからです。
たとえば、クラウドサービスやAIなどを導入する場合、関連法令や住民への影響、既存システムとの互換性まで踏まえて判断する必要があります。
このため、現場で新しいツールやフレームワークに触れる機会は限られるでしょう。変化の速いIT分野において、スキルの陳腐化を不安に感じる方にはやや不向きかもしれません。
とはいえ、行政基盤を支える重要な役割を担う点にはやりがいがあります。
②開発業務よりも管理業務が中心となる
情報系の職種であっても、公務員の業務は開発よりもプロジェクト管理や業者対応などの業務が中心です。実際の開発作業は、外部のシステム会社に委託するケースが大半を占めます。
職員自身がコードを書いたり、ツールを構築したりする機会は限られています。技術者というよりは発注者としての立場で動くことが多いでしょう。
そのため、「自ら手を動かして開発したい」と考えている方にはギャップを感じるかもしれません。
一方で、幅広い部門と連携してプロジェクトを動かす調整力や、ベンダーとの折衝力を磨きたい方には適した環境です。自分の志向と照らし合わせて判断してください。
③キャリアアップの選択肢が限られることがある
公務員の人事制度は年功序列を基本としており、配属先も本人の希望とは無関係に変わることがあります。たとえ情報系の知識や経験を積んでいても、他部署に異動する可能性は十分にあるでしょう。
また、昇進も技術力や実績だけでなく、組織全体での評価や役職枠の空き状況によって左右されます。このため、専門性を活かしたキャリアを積みたい方には、選択肢が物足りなく感じられるかもしれません。
一方で、行政という大きな組織でさまざまな経験を積むことで、視野が広がるという側面もあります。どちらを重視するかがポイントです。
④民間と比べて給与水準が低めに設定される
情報系人材の市場価値が高まる中、公務員の給与は一定の基準に基づいて設定されており、成果に応じた大幅な昇給は見込めません。
特に若手のうちは、同じスキルを持つ民間ITエンジニアと比べて年収に差が出ることもあるでしょう。また、残業代や各種手当も厳密に管理されており、「頑張った分だけ稼げる」仕組みではありません。
そのため、収入を重視する方にとってはデメリットとなり得ます。
とはいえ、安定した雇用や充実した福利厚生、退職金制度などを含めた「総合的な待遇」では、安心感が得られる職場です。長期的な視点で考えることが大切でしょう。
⑤新技術の導入に時間を要することが多くなる
行政機関では、どんな技術を導入するにも多くの手順と承認プロセスを踏む必要があります。
予算審議、上層部の承認、住民説明などが必要であり、実際の導入までに年単位の時間を要することも珍しくありません。
たとえば、民間で主流となっているクラウドサービスやAIツールであっても、「安全性」「平等性」「説明責任」などの観点から、慎重に検討されます。
その結果、タイミングを逸してしまい、せっかくの提案が形にならないこともあるでしょう。
スピード感を求める方にはもどかしく感じるでしょうが、一方で多様なステークホルダーの利害を調整しながら実現へ導く経験は、公務員ならではのやりがいともいえます。
情報系から公務員になるための転職ルート

情報系のスキルを活かして公務員を目指す場合、選べる転職ルートは複数あります。
地方自治体や国家機関での情報職採用、社会人経験を活かした試験制度、さらには任期付きの職員枠まで、選択肢は豊富です。ここでは、それぞれのルートについてわかりやすく紹介します。
- 地方自治体の情報職枠に応募する
- 国家公務員の技術系区分を受験する
- 社会人経験者採用試験を利用する
- SE経験を活かした行政職への転職
- 公募制や任期付き職員制度を活用する
①地方自治体の情報職枠に応募する
地方自治体では、IT関連業務を担当する情報職を独自に募集するケースが増えています。
具体的には、庁内システムの管理やネットワークの運用、情報セキュリティ対策といった業務を担う技術者の採用が進んでいるのです。
この採用枠では、専門スキルや実務経験が重視される傾向があるため、職務経歴書などで実績をしっかり伝えることが求められます。
なお、自治体ごとに試験の内容や募集要項が異なるため、事前に公式サイトなどを確認し、準備を進めてください。地元で長く働きたい方や、地域社会に貢献したい方にはぴったりの選択肢でしょう。
②国家公務員の技術系区分を受験する
国家公務員試験には、情報系の知識を活かせる技術系区分があります。
たとえば「電子・情報」や「情報工学」といった区分では、情報技術に関する専門知識が求められており、情報系出身者にとって有利な分野といえるでしょう。
合格すると、中央省庁や出先機関で働くことになり、国家規模のITシステムや政策に関わるチャンスが広がります。
非常にやりがいのある仕事ですが、筆記試験の出題範囲が広いため、早めに学習を始めることが大切。安定性と専門性の両方を重視したい方におすすめです。
③社会人経験者採用試験を利用する
民間企業での経験を活かして公務員を目指すなら、社会人経験者採用試験を活用しましょう。
この試験では、筆記試験に加え、面接や実績が重視されるため、これまでの職務内容や成果を整理しておくことが重要です。
情報システムの開発や保守、ITコンサルなどの実務経験を持っている場合、それをどのように公務に活かせるかを具体的に伝えることが評価につながります。
自治体や官公庁によって応募条件や選考方法が異なるため、最新の募集情報をこまめに確認してください。民間出身者がスムーズに移行しやすい試験制度といえるでしょう。
④SE経験を活かした行政職への転職
情報職だけでなく、行政職でも情報系スキルを活かせる場面は多数あります。たとえば、庁内業務のデジタル化や、業務プロセスの改善提案を担当する仕事では、SEとしての経験が非常に役立つでしょう。
行政職は、試験の内容が比較的標準的な教養試験中心であることから、対策が立てやすい点も魅力です。
また、技術力に加えて、課題解決力やチームでの調整力なども評価されるため、自分の強みをバランスよくアピールすることがポイント。より幅広い職種を検討したい方に適しています。
⑤公募制や任期付き職員制度を活用する
任期付き職員制度や公募制を活用することで、情報系スキルを活かして短期間で行政に携わることが可能です。
こうしたポジションでは、実務経験や即戦力が強く求められ、特定プロジェクトの推進などに関わるケースもあります。
任期付きであることに不安を感じるかもしれませんが、行政の現場を経験する貴重な機会になるでしょう。将来的に正規職員へのステップアップを見据えるきっかけにもなるはず。
柔軟に働きながら行政分野でキャリアを築きたい方には、有力なルートの一つです。
情報系出身者向けの公務員試験対策方法

情報系のスキルを活かして公務員を目指す場合、筆記と面接の両方に備えた対策が必要です。民間とは異なる出題傾向や評価基準があるため、計画的に取り組むことが合格への近道となるでしょう。
ここでは、情報系出身者が実践したい公務員試験対策のポイントを5つ紹介します。
- 筆記試験範囲とスケジュールを把握する
- 専門科目と一般教養のバランスを取る
- 過去問演習で出題傾向を掴む
- 公務員試験に強い通信講座を活用する
- 面接・人物試験の対策を行う
①筆記試験範囲とスケジュールを把握する
対策を始めるうえで最初に確認すべきなのは、試験の内容と時期です。情報系の区分であっても、専門科目に加えて一般教養が課されることは珍しくありません。
試験要項をよく読み、何を、いつまでに学ぶ必要があるのかを明確にしてください。
たとえば、国家公務員試験では「情報工学」や「電気電子」などが出題され、地方公務員試験では自治体独自の技術問題が出ることもあります。
また、どの試験でも判断推理や数的処理といった教養問題への対応が不可欠です。出題範囲と試験日程を把握すれば、無駄のない学習計画が立てられます。
余裕をもって準備を始めることが、合格の鍵を握るでしょう。
②専門科目と一般教養のバランスを取る
情報系出身者は専門科目には自信があっても、一般教養に苦手意識を持つ傾向があります。とはいえ、教養試験の比重が高い試験もあるため、得点源を限定しすぎると合格が遠のくおそれも。
そこで意識したいのが、学習のバランスです。得意分野である専門科目は確実に得点できるよう磨きつつ、数的処理・文章理解・社会常識などの一般教養にも計画的に取り組んでください。
どちらか一方だけに偏ってしまうと、試験全体での得点力が下がってしまいます。自身の弱点を見極めながら、苦手分野にもこまめに向き合う姿勢が必要です。
③過去問演習で出題傾向を掴む
過去問を活用することは、公務員試験対策において非常に効果的です。出題傾向や難易度、頻出分野を把握することで、無駄のない勉強ができます。
特に情報系の専門試験は、毎年似た形式の問題が出題される傾向があるのです。また、実際の問題形式に慣れておくことで、本番での緊張も和らぐでしょう。
時間配分や設問の読み取り方を身につけておけば、焦らず対応できるはずです。ただし、答えを暗記するだけでは実力はつきません。
各問題の正解理由と間違いの根拠を言語化できるよう意識しながら解くことが大切です。
④公務員試験に強い通信講座を活用する
独学に不安を感じる方や、学習ペースの管理が苦手な方には、通信講座の活用をおすすめします。情報系の専門分野に対応した講座も多く、教養試験や面接対策まで幅広くサポートしてくれるでしょう。
特に、動画講義や模擬試験、添削指導がセットになっている講座は、理解度の確認やモチベーションの維持に役立ちます。
スキマ時間にスマートフォンで学習できる環境も整っているため、忙しい方にも向いているのです。選ぶ際は、自分が目指す試験区分に対応しているかをよく確認してください。
適切な講座を選べば、合格までの道のりを効率よく進められるはずです。
⑤面接・人物試験の対策を行う
筆記対策ばかりに気を取られて、面接の準備が後回しになっていませんか?公務員試験では、最終的な合否は人物評価に左右されることが多く、面接対策は避けて通れません。
情報系のスキルをアピールするだけでなく、「その技術をどう社会に役立てるのか」「市民のためにどのように活かすのか」といった視点が求められます。
志望動機や自己PRを深掘りして、自分の言葉で伝えられるよう練習を重ねてください。模擬面接や質問集を活用し、想定される質問に対する回答を用意しておくと安心です。
人物試験は一発勝負ですので、準備に抜かりがないようにしましょう。
情報系出身者が公務員として活躍するために必要な視点

情報系から公務員を目指すなら、自身の強みと公務員の特性を正しく理解することが重要です。
採用側は専門知識だけでなく、課題解決力や協調性も重視しており、仕事内容も開発よりも管理業務が中心になる傾向があります。
一方で、公務員は安定した雇用や社会貢献といったメリットがある反面、新技術の導入が遅れるなどのデメリットもあるでしょう。
自分に合った転職ルートを選び、公務員試験の対策を早めに進めることで、情報系出身者として強みを最大限に活かせるはずです。
情報系人材が公務員として活躍できる可能性は十分にあるため、制度や働き方を正しく理解して準備を整えてください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










