【例文5選】就活で役立つお礼メールの書き方|メールを送る理由や注意点も紹介
「就活中のお礼メールって、本当に送るべき?」
説明会や面接、OB・OG訪問などの度に「お礼メールを送った方がいいのかな?」と悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。
マナーとしては送るべきと分かっていても、何を書けばいいか迷ったり、形式的になりすぎていないか不安になったりしますよね。
そこで本記事では、就活で役立つお礼メールの書き方や送るべき場面、押さえておきたいマナーをわかりやすく解説します。
実際に使える例文も紹介しているので、企業との信頼関係を築く一歩として、ぜひ活用してくださいね。
就活中のメール対応はこれだけでOK!
- ◎メールが最短3分で書けるテンプレシート
- 「このメールで失礼じゃないかな…」と悩みがちな場面でも、コピペするだけで安心してメールを送れる
就活のお礼メールは社会に出ても役立つ

就活のお礼メールは、ただの形式的なあいさつではありません。
件名の書き方や宛名の表記、署名の位置など、基本的なフォーマットを就活の段階から身につけておくことで、社会に出てからのギャップが小さくなるでしょう。
実際に、採用担当者はこうしたマナーを通じて「社会人としての準備ができているか」を見ています。就活のお礼メールは、単なるマナーではなく、将来につながる実践的なトレーニングです。
日々の就活を通じて、メール作成のスキルと相手を思いやる気持ちの両方を育てていきましょう。
就活でお礼メールが必要な場面

就活におけるお礼メールは、単なる形式的なあいさつではなく、印象を左右する大事なコミュニケーション手段です。
送るタイミングや内容を誤ると逆効果になることもあるため、場面ごとの特徴を正しく理解しておくことが重要ですよ。
ここでは、就活でお礼メールを送るべき代表的な場面を5つ紹介します。
- 会社説明会の後
- 面接の後
- OB・OG訪問の後
- インターンに参加した後
- 内定通知を受け取った後
① 会社説明会の後
会社説明会のあとにお礼メールを送るべきか迷う方もいるかもしれませんが、送ることで他の参加者と差をつけるきっかけになります。
お礼メールでは、説明会で得た具体的な学びや印象に残った話題に触れると効果的です。
ただし、テンプレートをそのまま使ったような形式的な内容や、送信ミスには気をつけましょう。
自分の言葉で感謝の気持ちを伝えることが、他の学生との差別化につながります。
② 面接の後
面接後のお礼メールは、誠意や熱意を企業に伝える良い手段です。面接中に話題になった質問や内容に触れると、採用担当者にも強く印象が残るでしょう。
形式ばった文面より、自分の言葉で丁寧に感謝を表現することが大切です。送信のタイミングにも注意が必要です。できれば当日中、遅くとも翌日午前中までに送るようにしてください。
内容が長すぎると読み手の負担になるため、感謝の気持ちを簡潔にまとめて伝えるとよいでしょう。
③ OB・OG訪問の後
OB・OG訪問の後にお礼メールを送るのは、社会人としての基本的なマナーです。相手は忙しい中、時間を割いて学生の相談に乗ってくれています。
丁寧なメールを送ることで、感謝の気持ちだけでなく誠実さや礼儀も伝わるのです。また、相手が社内で影響力を持つ方であれば、今後の選考や紹介にも関わってくるかもしれません。
フランクすぎる言葉や略語、敬語の間違いには注意してください。学生らしい素直さと、社会人としてのマナーのバランスを意識することが大切です。
④ インターンに参加した後
インターン後のお礼メールは、次の選考に直結する可能性があるため、とても重要です。
参加した企業に対して、感謝の気持ちとともに、自分がどんなことを学び、どう成長したかを伝えることが好印象につながります。形式的な内容では気持ちが伝わらず、逆効果になることも。
印象に残った出来事や学びについて、具体的にふれると良いでしょう。インターンは選考の一環と捉えられることが多いため、メールの文面ひとつでその後の対応が変わる可能性もあります。
⑤ 内定通知を受け取った後
内定通知を受け取ったあとは、感謝の気持ちを伝える最後のチャンスです。ここで丁寧なメールを送ることで、今後の内定者フォローや入社後の印象にも良い影響を与えるでしょう。
内容としては、「内定ありがとうございます」と明記し、これまでの選考を振り返っての感謝や、今後の意気込みを簡潔に添えると効果的です。
堅苦しくなりすぎないよう、自分らしい言葉を使うことも大事。誠実さと前向きな気持ちが伝わるよう、落ち着いて書き上げてください。
就活でお礼メールを送る理由

お礼メールは、選考後に企業へ送ることで自分の印象を高める有効な方法です。形式的なものと思われがちですが、実際には重要な意味があるのです。
ここでは、就活でお礼メールを送る主な理由を5つ紹介します。
- 面接や説明会の時間を割いてもらった感謝を伝えるため
- 自分の志望度の高さを企業にアピールするため
- ビジネスマナーがあることを示すため
- 面接で言いそびれたことをフォローするため
- 他の候補者との差別化を図るため
① 面接や説明会の時間を割いてもらった感謝を伝えるため
企業の担当者は、多忙な中で多くの学生に対応しています。そのような状況で、自分のために貴重な時間を割いてくれたという事実には、しっかりと感謝を示すべきです。
お礼メールを通してその気持ちを丁寧に伝えることができれば、あなたの人柄や礼儀正しさが伝わりやすくなりますよ。
短くても誠意のこもった言葉を自分の言葉で届けることで、信頼感を持ってもらいやすくなるでしょう。
② 自分の志望度の高さを企業にアピールするため
お礼メールには、ただ「ありがとうございました」と伝えるだけでなく、自分の本気度をさりげなく示す役割もあります。
たとえば「選考を通じて、より御社で働きたいと強く感じました」といった言葉を添えるだけでも、企業側は志望度の高さを感じ取ってくれるでしょう。
あくまで自然な文章の中で、自分の思いを伝えることが重要です。
③ ビジネスマナーがあることを示すため
お礼メールの内容や形式から、ビジネスマナーの基本が身についているかが見られています。
メールの件名や宛名、文末の結びなど、社会人としての基本が整っているかどうかは、意外とチェックされているポイントです。
お礼メールを書くこと自体が、将来の練習にもなるのです。丁寧な文章を書く力や、状況に応じた言葉選びができる学生は、仕事においても信頼されやすくなるでしょう。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
④ 面接で言いそびれたことをフォローするため
面接本番では、緊張のあまり言いたいことを言えなかったり、伝えそびれてしまったことがある方も多いはず。お礼メールは、そうした内容をさりげなく補足するのに最適な手段です。
たとえば「面接では触れられませんでしたが、ゼミで取り組んだテーマも御社の業務に通じると感じております」といった一文を加えることで、自分の強みや熱意をもう一度アピールできます。
ただし、あくまで補足にとどめ、長くなりすぎないよう注意しましょう。
⑤ 他の候補者との差別化を図るため
多くの応募者がいる中で、自分を印象づけることは簡単ではありません。だからこそ、お礼メールという「プラスアルファ」の行動が差別化のきっかけになります。
とくに自分の言葉で丁寧に書かれたメールは、担当者の記憶に残りやすい傾向があるのです。
小さな努力が大きなチャンスにつながることを意識してみてください。
就活でお礼メールを送るメリット

就活で送るお礼メールは、ただの礼儀ではなく、選考の結果に影響を与えることもある大切なコミュニケーションです。
どのようなメリットがあるのかを理解しておくことで、より効果的な活用ができるようになるでしょう。
ここでは、代表的な5つの利点を紹介します。
- 「入社意欲が高い」と評価される可能性がある
- マナーや社会人意識をアピールできる
- 採用担当者の印象に残りやすくなる
- 次回の選考への良い影響が期待できる
- 自己PRの補足やアピールの機会になる
① 「入社意欲が高い」と評価される可能性がある
お礼メールは、企業への熱意を示す効果的な手段です。とくに選考中は、やる気や真剣さが重視されるため、面接や説明会後にメールを送ることで好印象を与えやすくなります。
一方、まったく反応がないと関心が薄いと受け取られてしまうこともあるため、注意が必要です。気持ちがこもっていない文章や定型文のような内容では、逆効果になるかもしれません。
形式にこだわりすぎず、自分の言葉で簡潔に伝えることを意識してください。
② マナーや社会人意識をアピールできる
お礼メールを送る行動そのものが、社会人としての基本的なマナーを身につけている証になります。面接や訪問に対して、感謝の気持ちをすぐに伝える姿勢は、ビジネスの現場でも重視される対応です。
採用担当者は、こうした細かな対応も含めて学生を見ています。たとえば、お礼をしなかったり、文面が雑だったりすると、それだけで評価を下げられる可能性もあるでしょう。
言葉づかいに気を配り、礼儀を守った文面で送ることが大切です。
③ 採用担当者の印象に残りやすくなる
採用担当者は毎日多くの学生と接しているため、個別の印象が薄れてしまうことがあります。そこで、お礼メールを送ることで、改めて自分の存在を思い出してもらえる可能性が高まるのです。
とくに、面接中の話題や担当者の発言にふれた内容を入れると、「この学生はよく覚えているな」と感じてもらえるでしょう。
感謝の気持ちを前面に出しながら、自然な形で印象に残るような工夫をしてみてください。
④ 次回の選考への良い影響が期待できる
丁寧なお礼メールは、次回の選考に好影響を与えることがあります。たとえば、真摯な対応や礼儀正しさが伝われば、「もう一度会いたい」と思ってもらえるかもしれません。
もちろん、メールを送れば必ず通過できるとは限りませんが、細かな気配りが印象を左右する場面は多くあります。
競争の激しい選考では、少しの差が結果を分けることもあるため、積極的に取り組んでおきたいポイントです。
⑤ 自己PRの補足やアピールの機会になる
お礼メールでは、面接や訪問の場では伝えきれなかった内容を補足することも可能です。
たとえば、うまく言葉にできなかった強みや実績を、さりげなく書き添えることで印象を上書きできる場合があります。
ただし、自己アピールが強すぎると、かえってマイナスになることもあるため注意が必要です。あくまで感謝が主旨であることを忘れず、その中で自然に自分らしさを伝えるようにしましょう。
バランスを意識することが大切です。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
就活でお礼メールを送るデメリット
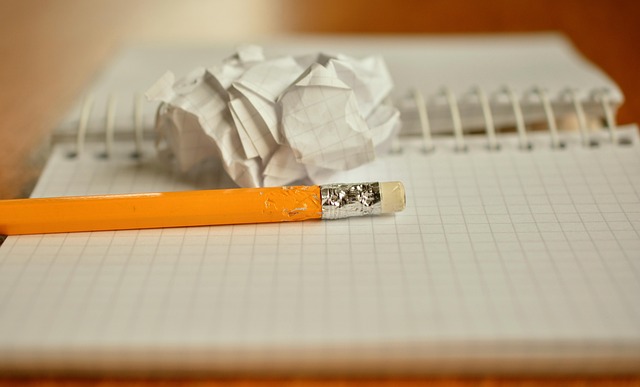
お礼メールは印象を良くする手段のひとつですが、やり方を誤ると逆効果になるおそれもあります。
ただ送ればよいというものではなく、内容やタイミング、伝え方に気をつける必要があるのです。
ここでは、お礼メールを送る際に注意したいデメリットを5つ紹介します。
- 内容が形式的すぎると逆効果になる
- タイミングや表現を誤るとマイナス評価につながる
- 企業によっては不要とされることがある
- 他の応募者と差別化できない可能性がある
- 過剰なアピールが押しつけがましく映ることがある
① 内容が形式的すぎると逆効果になる
お礼メールを送る際に気をつけたいのが、内容があまりにもテンプレート的で、感情のこもっていない文章になってしまうことです。
たとえば、「本日はありがとうございました」といった文面だけでは、相手に形式的な印象を与えてしまう可能性があります。
効果的なお礼メールにするためには、感謝の気持ちとともに自分自身の言葉で1文でも補足することが重要です。
面接の内容に触れた感想や、印象に残ったエピソードを添えることで、あなたらしさや誠意が伝わりやすくなるでしょう。
② タイミングや表現を誤るとマイナス評価につながる
お礼メールは早ければ早いほど好印象を持たれますが、焦って不適切な時間帯に送ってしまうと逆効果になることもあります。
たとえば、深夜や早朝にメールを送ると、常識がないと捉えられてしまうおそれがあるでしょう。
また、敬語表現が過剰だったり、不自然に丁寧すぎたりすることで、かえって読み手に違和感を与える場合もあります。
ちょっとした違和感が評価を左右することもあるため、油断は禁物ですよ。
③ 企業によっては不要とされることがある
お礼メールを評価する企業もあれば、逆にあまり重要視しない企業も存在します。
とくにベンチャー企業やIT業界など、スピード感と効率を重視する風土のある企業では、「お礼メール=ビジネスマナー」という前提が通じない場合も。
また、メールの受信数が非常に多い企業では、丁寧なつもりで送ったお礼メールがむしろ業務の妨げと受け取られてしまう可能性もあります。
闇雲にすべての企業へメールを送るのではなく、相手に合わせた対応を意識してください。
④ 他の応募者と差別化できない可能性がある
近年では、お礼メールを送る就活生が増えており、もはや特別な行動とは言えなくなっています。
差別化を図るには、自分の経験や感じたことを具体的に盛り込み、あなた自身の言葉で感謝の気持ちや意欲を伝えることが大切です。
「この学生はちゃんと考えて送っている」と思ってもらえるようなひと工夫が、最終的に評価を左右することにつながります。
⑤ 過剰なアピールが押しつけがましく映ることがある
お礼メールに「ここで働きたい」という強い意欲を込めることは重要ですが、過度なアピールはマイナスに働くこともあります。
とくに、何度も繰り返し熱意を伝えたり、長々と自己PRを重ねたりすると、「押しつけがましい」と感じられてしまう可能性があるのです。
お礼メールの目的はあくまで感謝を伝えることであり、選考に有利に働かせるための道具ではないという基本を忘れてはいけません。
バランスの取れた文面を心がけ、相手の負担にならない配慮あるアプローチを意識してください。
就活のお礼メールの書き方ステップ

お礼メールは感謝を伝えるだけでなく、印象を左右する重要な要素です。
書き方ひとつで評価が変わることもあるため、順序立てて丁寧に作成する必要があるでしょう。
ここでは、就活で使えるお礼メールの基本ステップを7つに分けて紹介します。
- ステップ:件名を具体的に記載する
- ステップ:宛名は正式名称で書く
- ステップ:感謝の気持ちを簡潔に伝える
- ステップ:印象に残った内容に触れる
- ステップ:今後の意欲や抱負を添える
- ステップ:結びの言葉を丁寧に書く
- ステップ:署名に氏名・連絡先を記載する
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
① ステップ1:件名を具体的に記載する
件名はメールで最初に目に入る部分であり、内容を伝えるうえで非常に大切です。「お礼」や「ありがとうございました」だけでは、相手にとって何のメールかわかりません。
「7月10日 面接のお礼(山田太郎)」のように、日付・内容・氏名を含めると明確になります。
担当者は1日に何通ものメールを受け取っているため、件名が曖昧だと開封されないまま埋もれてしまう可能性もあるでしょう。読み手の立場に立って「開いてもらえる件名」を意識することが重要です。
相手が読みやすいよう配慮し、マナーを踏まえた工夫をしてください。
② ステップ2:宛名は正式名称で書く
宛名は、相手に敬意を示すうえで基本となる要素です。「○○部 部長 ○○様」や「人事部 採用担当 ○○様」といったように、所属部署や役職を含めた書き方が望ましいでしょう。
形式を間違えたり、苗字だけの表記だったりすると、失礼な印象を与える可能性があります。また、名前や役職を間違えると信頼を損ねる原因になるのです。
送信前に、必ず公式な情報源で確認しましょう。もし相手の名前がわからない場合は、「採用ご担当者様」と記載するのが無難です。細かな点でも丁寧さが伝わるよう心がけましょう。
③ ステップ3:感謝の気持ちを簡潔に伝える
本文のはじめには、感謝の気持ちを明確に伝えることが大切です。「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」のような一文から始めると、誠意が伝わりやすくなります。
面接や訪問、インターンなど、状況に応じた表現を使い分けてください。また、単なる形式的な文章にならないように、自分の言葉で感謝を述べることを意識しましょう。
「貴重なご意見をいただき、大変参考になりました」など、感じたことを具体的に言葉にすることで、相手にもその気持ちがより伝わります。心からの感謝を、短く、しかし丁寧にまとめてください。
④ ステップ4:印象に残った内容に触れる
面接や訪問の際に印象に残った内容に触れると、個別性のあるメールになります。
たとえば「御社が大切にされている理念についてのお話が非常に印象的でした」など、相手が話してくれたことに対して具体的にふれると、しっかり聞いていたことが伝わるでしょう。
このひと言を入れることで、テンプレート的な印象から脱し、自分だけのオリジナルなメールになります。
内容が自然であることが大切なので、無理に褒めるのではなく、自分が本当に共感した点や関心を持った話題を選んでください。その真剣な姿勢が好印象につながります。
⑤ ステップ5:今後の意欲や抱負を添える
感謝の言葉のあとには、今後の意欲や抱負を簡潔に述べると、前向きな気持ちが伝わるでしょう。
「今回のご縁を大切にし、引き続き選考に向けて努力してまいります」といった一文を入れることで、意欲や誠実さが表現できます。
ただし、自己アピールが過度にならないよう注意が必要です。感謝のメールであることを忘れず、「今後もよろしくお願いいたします」など、控えめで丁寧な表現にまとめましょう。
また、自分の考えや価値観を簡単に添えることで、より個性が伝わりやすくなります。
⑥ ステップ6:結びの言葉を丁寧に書く
メールの締めくくりは、相手に好印象を残すための最後のポイントです。
「今後のご活躍をお祈り申し上げます」や「引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします」など、ビジネスシーンにふさわしい結びの一文を選びましょう。
また、再度感謝の気持ちをさりげなく伝えることも効果的です。「本日は誠にありがとうございました」と改めて書くことで、丁寧さと誠実さが伝わります。
文章の余白や改行も工夫して、全体を読みやすく整えることで、より洗練された印象を与えられるでしょう。
⑦ ステップ7:署名に氏名・連絡先を記載する
メールの最後には署名を必ず入れましょう。氏名だけでなく、大学名・学部・学年・電話番号・メールアドレスなどを記載すると、相手が返信しやすくなります。
署名が抜けていると、誰からのメールか分からず対応が遅れる原因になるため注意してください。署名部分はビジネスメールの基本構成のひとつです。
あらかじめテンプレートとして保存しておけば、毎回のメール送信もスムーズ。体裁が整った署名は、それだけで印象を底上げする効果があります。細部まで丁寧さを意識して書き上げましょう。
就活のお礼メールを書くときのポイント

お礼メールは送ること自体も大切ですが、どのような内容で書くかによって、相手に与える印象は大きく変わります。
文面の工夫やタイミングを意識することで、より好印象を残すことができるでしょう。
ここでは、お礼メールを作成するうえで押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
- できるだけ当日中に送信する
- 送信時間は営業時間内を心がける
- 相手に合わせた文面を作成する
- 具体的なエピソードを簡潔に入れる
- 形式的すぎない自然な文章にする
① できるだけ当日中に送信する
お礼メールは、できるだけ当日中に送ることが望ましいです。時間が経つにつれて、感謝の気持ちは伝わりにくくなり、相手の記憶からも自分の印象が薄れてしまう可能性があります。
その日のうちに連絡することで、迅速な対応ができる人という印象も与えられるでしょう。また、すぐにお礼を伝える姿勢は、ビジネスマナーとしても高く評価される傾向があります。
時間が取れない場合でも、短い内容で構わないので、簡潔に感謝の気持ちだけでも伝えておくと安心です。早めの行動が、誠実さや本気度を示す手段にもなります。
② 送信時間は営業時間内を心がける
お礼メールの送信タイミングにも注意が必要です。たとえば、深夜や早朝にメールを送ると、相手によっては「時間をわきまえていない」と受け取られてしまうかもしれません。
社会人としての常識が問われる部分でもあるため、配慮が欠かせないのです。一般的には、企業の営業時間である9時〜18時の間に送るのが理想的。
どうしてもその時間帯に送れない場合は、翌営業日の朝に送信するようにしましょう。メールの内容だけでなく、送るタイミングまで意識することで、さらに信頼感を高めることができます。
③ 相手に合わせた文面を作成する
お礼メールでは、相手ごとに文面を調整することが大切です。説明会や面接でどのような方と接したかによって、伝えるべき内容や言葉選びも変わってきます。
誰にでも同じ文章を送っているような印象を与えてしまうと、誠実さが伝わりません。たとえば、相手がフランクな口調で接してきた場合は、やや柔らかい言葉づかいで返すと、自然な印象になります。
一方で、堅めの話し方をする担当者には、より丁寧な文面がふさわしいでしょう。やり取りの内容や雰囲気を思い出しながら、自分の言葉で文面を組み立ててください。
④ 具体的なエピソードを簡潔に入れる
感謝の言葉に加えて、面接や説明会で印象に残った内容や、学んだことを一言添えると、より相手の心に残るメールになります。
たとえば「○○の事例がとても印象的でした」や「○○という考え方に共感しました」など、具体性のある表現が効果的です。
このような一文を入れることで、しっかり話を聞いていたことや、関心を持っていたことが伝わります。
定型的な文ではなく、あなただけの気づきや感想を短く盛り込むことが大切です。
⑤ 形式的すぎない自然な文章にする
丁寧な表現はもちろん必要ですが、かたすぎる言い回しばかりでは、機械的で感情のこもっていない印象を与えることもあります。
たとえば、定型文をそのままコピーするのではなく、自分の体験や感じたことを短く加えることで、文章に温かみが出ます。
相手にとって自然に読めるよう、過剰に飾り立てた表現は避け、シンプルで思いやりのある文章を意識してください。自然な文章ほど、読み手の心に残りやすいものです。
就活で使えるお礼メールの例文
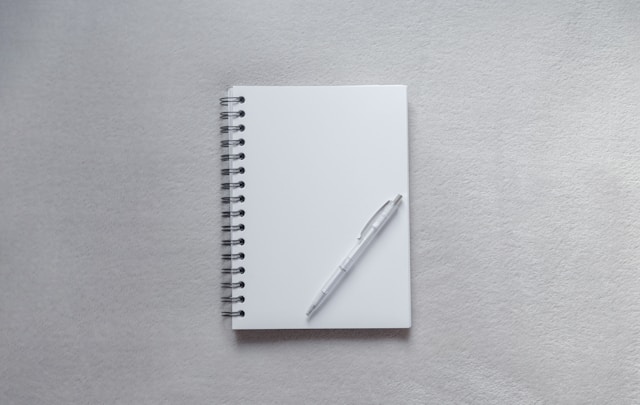
お礼メールを書こうとしても、「どんな内容にすればいいのか分からない」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
ここでは、就活の各シーン別に使えるお礼メールの具体例を紹介します。
状況に合わせて参考にしてみてくださいね。
また、ビジネスメールがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジン編集部が作成したメール自動作成シートを試してみてください!
ビジネスマナーを押さえたメールが【名前・大学名】などの簡単な基本情報を入れるだけで出来上がります。
「面接の日程調整・辞退・リスケ」など、就活で起きうるシーン全てに対応しており、企業からのメールへの返信も作成できるので、早く楽に質の高いメールの作成ができますよ。
①説明会後に送るお礼メールの例文
企業説明会に参加したあと、「お話は参考になったけれど何を書けばいいの?」と迷う方は多いです。参加日時が新しいほど印象も残っていますので、早めに感謝と学びを伝えておきましょう。
《例文》
| 株式会社〇〇 人事部 △△様 本日開催の会社説明会に参加いたしました、〇〇大学△△学部の□□と申します。 お忙しい中、事業の成長分野と若手の挑戦環境について詳しくうかがうことができ、大変勉強になりました。 特に、開発職でも文系出身の社員が活躍しているとのお話には勇気をいただき、貴社で学びながら成長したい思いが一層強まっております。 短い時間ではありましたが、質問にも丁寧にご対応くださり、感謝申し上げます。今後の選考機会がありましたら、ぜひ参加させてください。 引き続きよろしくお願いいたします。 〇〇大学△△学部4年 □□ □□ TEL:000-0000-0000 mail:xxxx@example.com |
《解説》
説明会で心に残った具体的ポイントを1文で示し、志望意欲につなげると好印象です。相手の時間に触れて礼を述べ、次の選考へ前向きな姿勢を添えてください。
②面接後に送るお礼メールの例文
面接後は、感謝の気持ちと共に自分の印象をもう一度アピールできる貴重なタイミングです。特に会話の中で印象に残った内容に触れると、丁寧さが伝わりやすくなります。
《例文》
| 株式会社〇〇 人事部 △△様 本日、一次面接のお時間をいただきありがとうございました。〇〇大学△△学部の□□と申します。 面接の中で、貴社が新たに取り組まれている〇〇事業についてお話をうかがい、学生時代にゼミで取り組んでいた内容との共通点が多く、貴社への関心がいっそう高まっております。 とくに、△△様がお話しされていた「若手の意見も積極的に取り入れる社風」には大きく共感し、自分もその一員として成長していきたいと強く感じております。 本日うかがった貴重なお話を、今後の行動にしっかりと活かしてまいります。 引き続き、何卒よろしくお願いいたします。 〇〇大学△△学部4年 □□ □□ TEL:000-0000-0000 mail:xxxx@example.com |
《解説》
面接中のエピソードに具体的に触れることで、相手に記憶を呼び起こさせる効果があります。印象に残った言葉や共感した点を、自分の志望動機とつなげて表現しましょう。
③OB・OG訪問後に送るお礼メールの例文
OB・OG訪問のあとは、時間を割いてくれたことへの感謝をしっかり伝えることが大切です。印象に残ったアドバイスを具体的に触れると、丁寧さと理解力が伝わります。
《例文》
| 株式会社〇〇 人事部 △△様 〇〇大学△△学部4年の□□と申します。 本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございました。 お話の中で、入社後すぐに任されたプロジェクトについて伺い、挑戦を恐れず行動することの大切さを強く感じております。 学生時代、部活動で初めてマネージャーを任された経験と重なる部分もあり、仕事に対する姿勢を改めて見直すきっかけになりました。 現場で働く方のリアルな声を直接うかがえたことで、〇〇株式会社での働き方や成長のイメージが一段と鮮明になっております。今後の就職活動にしっかり活かしてまいります。 改めて感謝申し上げますとともに、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
《解説》
訪問の中で印象的だったエピソードに触れることで、感謝の気持ちが伝わりやすくなります。自分の体験と結びつけて共感を示すと、より好印象です。
④インターン終了後に送るお礼メールの例文
インターン終了後は、学んだことへの感謝と今後への意欲を伝える絶好の機会です。印象に残った業務体験を具体的に書くと説得力が増します。
《例文》
| 株式会社〇〇 人事部 △△様 このたびは〇日間のインターンに参加させていただき、誠にありがとうございました。〇〇大学△△学部の□□と申します。 実際の業務を通じて、チームでの連携や納期への意識など、教室では得られない実践的な力の重要性を身をもって感じております。 中でも、営業同行の機会を通じて「相手の立場で考える」姿勢に触れられたことは、今後に大きく活かせる経験となりました。 貴社の明るく前向きな職場の雰囲気に触れ、志望度がいっそう高まっております。今回の学びを、今後の行動にしっかりとつなげてまいります。ご多用の中、ご指導くださり感謝申し上げます。 〇〇大学△△学部4年 □□ □□ TEL:000-0000-0000 mail:xxxx@example.com |
《解説》
インターン中の具体的なエピソードを交えて書くことで、学びの深さが伝わります。感謝の気持ちと今後への前向きな姿勢をセットで表現すると効果的です。
⑤内定通知を受けた際に送るお礼メールの例文
内定をいただいた後のお礼メールでは、感謝の気持ちだけでなく、入社への意欲を丁寧に伝えることがポイントです。企業への期待感を具体的に示しましょう。
《例文》
| 株式会社〇〇 人事部 △△様 このたびは、内定のご連絡をいただき誠にありがとうございました。〇〇大学△△学部の□□と申します。 貴社より内定のご連絡を頂戴し、大変光栄に存じます。 学生時代に地域ボランティア活動へ取り組んできた経験を通じて、「人の役に立つこと」を仕事にしたいという思いを大切にしてまいりました。 説明会や選考を通じて、貴社の事業内容や人を大切にする姿勢に強く共感し、ぜひその一員として成長していきたいと感じております。 今後のご案内を楽しみにお待ちしております。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 〇〇大学△△学部4年 □□ □□ TEL:000-0000-0000 mail:xxxx@example.com |
《解説》
内定後のお礼メールでは、感謝と共に自分の思いや将来の姿勢を伝えるのが大切です。志望動機やエピソードを少し盛り込むことで誠意が伝わりやすくなります。
就活のお礼メールの注意点

お礼メールは、就活において印象を大きく左右する大切な要素です。
どれだけ丁寧な文章を書いても、基本的なマナーが欠けていれば逆効果になってしまうかもしれません。
ここでは、見落としがちな注意点を5つに整理して紹介します。
- 件名は一目で内容がわかるようにする
- 本文は簡潔にまとめる
- 誤字脱字や敬語の誤用に注意する
- 「返信不要」の一文を忘れずに入れる
- 改行や句読点を工夫して読みやすくする
① 件名は一目で内容がわかるようにする
件名は、メールの中で最初に表示される重要な情報です。内容が曖昧な件名では、受信者が何についての連絡か判断できず、開封されないまま埋もれてしまうこともあります。
たとえば「お礼」という言葉だけでは不十分で、「7月10日 面接のお礼(田中太郎)」のように日付と目的、差出人の名前を明記すると親切です。
件名が的確であることは、社会人としての基本的な配慮でもあります。
読み手の時間を無駄にしない工夫として、具体的でわかりやすい件名をつけることを意識しましょう。
② 本文は簡潔にまとめる
お礼メールでは、必要な内容を簡潔に伝えることが大切です。
たとえば「本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました」や「○○についてのお話が印象に残りました」といったように、要点を押さえた文章構成が理想です。
自分の気持ちをすべて詰め込むのではなく、相手が読みやすいかを基準にして取捨選択することが大切です。
③ 誤字脱字や敬語の誤用に注意する
文章の内容がどれほど丁寧で好印象でも、誤字や脱字、敬語の使い方に誤りがあると、評価を下げる要因になります。
とくに注意したいのが、敬語の不自然な使い方です。
「ご苦労様です」や「参考になりました、ありがとうございました」などは相手によっては不適切に感じられることがあります。
正しい敬語表現を使うためには、類似表現との違いを理解しておくと安心ですよ。
④ 「返信不要」の一文を忘れずに入れる
お礼メールは、返信を期待するものではないという前提で書くのが基本です。
そのため、「ご返信には及びません」「お忙しいところ恐縮ですが、ご返信は不要です」などの一文を添えておくと、相手への配慮が伝わります。
返信を求めるような文面になっていると、逆に気を遣わせてしまうこともあります。
感謝の気持ちとともに、相手の時間を尊重する姿勢を示すことが、好印象につながりますよ。
⑤ 改行や句読点を工夫して読みやすくする
内容がいくら丁寧でも、改行のない文章や句読点が少ない文は読みづらく、相手にストレスを与えてしまいます。
1文が長くなりすぎないように注意し、文のまとまりごとに改行を入れることで、視認性がぐっと高まるのです。
また、適度に余白があると、全体の印象もすっきり見えるでしょう。
形式的な文面であっても、見た目の整え方ひとつで印象が大きく変わるため、文字の内容だけでなく視覚的な読みやすさにも配慮するようにしましょう。
就活でお礼メールを正しく活用するために

就活のお礼メールは、社会に出てからも通用するビジネスマナーのひとつです。
説明会や面接、OB・OG訪問などのさまざまな場面で送ることで、感謝や志望度を伝えられる貴重な手段になります。
メリットも多く、印象づけや自己PRにもつながりますが、形式的すぎる内容や送信タイミングによっては逆効果になる可能性もあるでしょう。
基本のステップやポイントを押さえたうえで、自分らしさを込めた丁寧なメールを心がけましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









