大学院卒の初任給が高い理由は?大卒との比較や就職のメリットも紹介
「院卒の初任給って、本当に大卒より高いの?」
そんな疑問を持つ方も多いでしょう。大学院に進学すると、研究経験や専門性が高まる一方で、就職が遅れるイメージもありますよね。
しかし実際には、院卒の初任給は大卒よりも明確に高い傾向があります。
そこで本記事では、院卒と大卒の初任給の違いや、給与が高くなる理由、さらに就職面でのメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
院卒の平均初任給はいくら?

ここでは、全国平均のデータをもとに、院卒の初任給の現状をわかりやすく解説します。
結論として、院卒(修士課程修了)の初任給は全国平均でおよそ29万円前後です。厚生労働省の調査によれば、大学卒が約25万円であるのに対し、院卒は約4万円高い水準となっています。
この差が生まれる主な理由は、大学院で培った専門知識や研究スキルが企業にとって即戦力として評価されるためです。
特に理系分野では、研究開発や技術職など専門性の高い職種で採用されることが多く、初任給も高く設定される傾向があります。
一方で、文系の院卒は大学卒との差が比較的小さいこともありますが、論理的思考力や課題解決力が重視される企業では高く評価される場合もあります。
院卒としての価値は給与だけでなく、将来のキャリア選択の幅や専門分野での活躍機会にも表れます。数字の差を参考にしながら、自分がどのような働き方を望むのかを考えることが大切でしょう。
引用:厚生労働省『賃金構造基本統計調査 令和6年 結果の概況(PDF)』
院卒と大卒の初任給を比較

大学院を修了した学生と、学部を卒業した学生では、初任給にどの程度の差があるのでしょうか。ここでは、院卒と大卒の給与差の実態をデータに基づいて解説します。
さらに、給与以外の待遇面の違いにも触れ、就活生が進学を検討する際の判断材料として役立つ情報を紹介します。
- 院卒と大卒の初任給を比較
- 学歴別の平均初任給の違い
- 初任給以外の待遇差(賞与・昇給・福利厚生など)
①院卒と大卒の初任給を比較
まず、最も気になる初任給の差について見ていきましょう。厚生労働省の統計によると、2024年度の平均初任給は大卒が約25万円、院卒が約29万円前後となっています。
差額はおよそ4万円で、年間にすると約48万円の差です。この金額差は決して小さくありませんが、企業や職種によってはさらに広がる場合もあります。
たとえば、研究職や技術職では大学院での専門知識が評価されやすく、初任給が高く設定される傾向にあります。一方で、営業職や事務職などでは学歴による給与差がほとんど見られません。
そのため、「どの業界・職種を目指すのか」によって受ける印象は大きく変わるでしょう。
つまり、院卒だからといって必ず高収入になるとは限りません。自分の進みたい分野の傾向を理解した上で、学歴とキャリアのバランスを考えることが大切です。
②学歴別の平均初任給の違い
文部科学省の調査によると、学歴ごとの平均初任給には明確な階層構造が見られます。
最も高いのは大学院修士課程修了者で約29万円、次いで大学卒が約25万円、高専・短大卒が約22万円、高卒が約20万円です。この差は、学歴による専門性の深さや採用ポジションの違いが影響しています。
また、理系と文系でも傾向が異なります。理系の院卒は研究や開発職で需要が高く、初任給が高めに設定されるケースが多いです。
一方で、文系の院卒は専門職を除けば大卒との差がやや小さくなる傾向があります。
初任給は学歴だけで決まるものでもありません。どの分野でどのようなスキルを磨くのかを見据えて進路を選ぶことも、将来的な収入やキャリア形成において重要な鍵となります。
③初任給以外の待遇差(賞与・昇給・福利厚生など)
初任給の差だけでなく、長期的な待遇の違いにも注目することが大切です。院卒はスタート時点の給与が高い分、昇給ペースがやや緩やかに設定される企業もあります。
その一方で、専門職や管理職への昇進が早いケースも多く、長期的に見ると年収面では大卒より上回る傾向があります。
さらに、賞与(ボーナス)は基本給を基準に計算されるため、初任給が高ければその分ボーナス額にも差が出やすいです。
福利厚生については学歴による違いはほとんどありませんが、院卒が採用されやすい企業は大手や研究機関など、制度が充実している場合が多いです。
引用:厚生労働省『賃金構造基本統計調査 令和6年 結果の概況(PDF)』
院卒の初任給が高い理由

大学院卒の初任給が高いのは、学歴だけでなく専門性や将来性に対する評価が含まれているためです。
企業は専門知識を持つ人材を求めており、院卒には研究経験や問題解決能力など、即戦力として期待できるスキルが備わっています。ここでは、院卒の給与が高くなる主な6つの理由を紹介します。
- 高度な専門知識・研究スキルの評価
- 採用競争力を高めるための企業戦略
- 研究職や技術職など専門職の需要増加
- 学部卒と比べた職務内容や責任の違い
- 大学院での成果(論文・研究実績)の評価
- 将来的な成長性・リーダー候補としての期待
①高度な専門知識・研究スキルの評価
大学院では、学部よりも深く専門分野を学び、課題設定から実験・分析・考察までを自ら行う力を身につけます。こうした経験は、企業が求める「自ら考え行動する力」とつながっていると言えるでしょう。
そのため、理系・文系を問わず、研究や企画開発などの職種では高く評価されます。
特に理系分野では、データ分析や論理的思考を実務に活かせるため、初任給に差が出やすくなります。知識を応用し成果を出せる能力が、院卒の給与水準を押し上げる要因の1つです。
②採用競争力を高めるための企業戦略
企業が院卒の給与を高めに設定する背景には、優秀な人材を確保するための戦略があります。
特に研究開発や技術革新を重視する企業では、他社との採用競争が激しいため、魅力的な待遇を提示することで応募者の質を高めようとしているのです。
このような取り組みは単なるコストというだけではなく、将来的な成果を見据えた「人材投資」と言えるでしょう。
長期的なリターンを得るための合理的な判断として院卒の初任給を上げるケースが多い状態です。
③研究職や技術職など専門職の需要増加
AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中で、専門知識を持つ人材の需要は高まり続けています。
研究職や技術職はもちろん、データ分析や製品開発などの分野でも、論理的思考や専門スキルが求められています。
こうした職種では、学部卒よりも即戦力として活躍できる院卒が優遇されやすいです。その結果、給与水準にも反映され、特に理系院卒では初任給が高くなる傾向が見られます。
専門性が高いほど評価も上がる傾向にあります。
④学部卒と比べた職務内容や責任の違い
院卒は採用時点で、より高度な業務を担当することを前提に配属されるケースが多いです。
たとえば、学部卒が補助的な立場でプロジェクトに参加するのに対し、院卒はリーダー候補や分析担当など、責任のある役割を担うことがあります。
職務の難易度や期待される成果が異なるため、初任給にも差が生まれるのです。これは学歴差だけではなく、「求められる役割の違い」による正当な評価といえるでしょう。
⑤大学院での成果(論文・研究実績)の評価
大学院での研究成果や論文発表は、専門性の証明として企業から高く評価されます。特に学会での発表や共同研究の経験は実践的なスキルですから、企業にとって即戦力だと判断されるでしょう。
また、長期的な課題に粘り強く取り組む姿勢や、チームで研究を進める協調性も社会人として重要な資質です。
こうした「実績」と「姿勢」の両面が評価され、院卒の初任給は自然と高めに設定される傾向があります。
⑥将来的な成長性・リーダー候補としての期待
企業は院卒を、将来的に組織を引っ張るリーダー候補として採用することが多いです。
高度な知識に加えて、論理的思考力や問題解決力を備えた人材は、マネジメントや新規事業の推進役としてのポテンシャルを持っています。
そのため、初任給を高く設定することで「成長への期待」を示す意味もあります。企業が重視しているのは、入社時点の能力だけではなく、将来にわたって活躍できる可能性なのです。
院卒で就職するメリット

大学院を修了して就職することには、専門知識を深められるだけでなく、将来のキャリア形成にも多くの利点があります。
ここでは、院卒ならではの強みを具体的に紹介します。学部卒との違いを理解し、自分に合った進路を見つける参考にしてください。
- 専門分野を活かせるキャリアパス
- 給与・待遇が高い傾向にある
- 技術職・研究職への就職で有利
- 学内推薦やキャリア支援制度の充実
- キャリアの選択肢が広がる可能性
- 昇進・昇給スピードが早いケースもある
①専門分野を活かせるキャリアパス
大学院では、学部よりも深く専門分野を掘り下げて学びます。そのため、就職後は研究や開発、コンサルティングなど、専門知識を活かせる仕事に就くことが多いです。
理系の場合、新技術の開発や製品設計、データ解析などに携わることがあり、研究成果が実際の社会に役立つ場面を実感できるでしょう。
文系でも、経済・心理・教育などの分野を極めた院卒の方々は、企業の戦略立案や調査業務などで強みを発揮できるはずです。
つまり、大学院で培った専門知識や研究経験は、社会での信頼につながる大きな武器と言えるでしょう。
②給与・待遇が高い傾向にある
一般的に、院卒は大卒より初任給や待遇が高い傾向があります。企業が院卒の高度な知識や技術力を評価しているためです。
厚生労働省の調査でも、修士課程修了者の初任給は学部卒より数万円高いとされています。わずかな差に見えても、昇給や賞与での積み重ねによって、数年後には大きな差になることも。
また、一部の企業では博士号取得者に特別な手当を設ける場合もあります。
つまり、大学院進学は短期的な収入よりも、長期的なキャリア価値を高める投資とも言えるでしょう。
③技術職・研究職への就職で有利(推薦・支援制度も充実)
技術職や研究職を目指す場合、大学院での研究経験は非常に大きな強みです。開発部門や研究所では、理論の理解やデータ分析の力が重要であり、院卒の知識は即戦力として期待されます。
また、論文執筆や学会発表を経験した学生は、課題発見力や論理的思考力に優れており、プロジェクトを牽引する立場に立ちやすいです。
特に製造業やIT業界、医療・バイオ分野などでは「院卒限定採用」を設ける企業もあります。専門職志向の人にとって、大学院進学は理想的な道でしょう。
さらに、大学院生は就職活動で教授や研究室の推薦を受けられる機会が多く、自分の専門に合った企業や研究機関へスムーズに応募できます。
このように、院生は「専門性を活かした支援体制」を利用できるため、就職活動を有利に進めやすいでしょう。
④キャリアの選択肢が広がる可能性
大学院進学は、専門職に限らず、将来的な選択肢を広げる手段にもなります。研究職だけでなく、教育、行政、コンサルティングなど、専門知識を活かせる分野は多岐にわたります。
さらに、社会人になってから博士課程に進む、海外で研究を行うなど、新しい挑戦への道も開けます。
大学院で得られるのは、専門スキルだけではなく「自分で道を切り開く力」でもあります。
柔軟なキャリア形成を目指すうえで、院卒の経験は大きな価値を持つでしょう。
⑤昇進・昇給スピードが早いケースもある
企業によっては、院卒が昇進や昇給のスピードで優遇される場合があります。
入社時点で専門性や課題解決力が高く、早くからリーダー候補として期待されるためです。
特に技術系職種では、大学院で培った知識が新技術の理解や後輩指導にも活かされ、組織の成長を支える存在として重宝されます。
もちろん成果が前提ではありますが、大学院での経験はキャリアのスタート地点を一歩先に押し上げるでしょう。努力次第で早期に評価されやすいのも、院卒の魅力です。
院卒で就職するデメリット

大学院まで進学して就職することには多くの利点がありますが、一方で注意すべき点もあります。
特に「社会人としてのスタート時期」「費用」「業界による評価の差」などは、進学を検討するうえで理解しておきたいポイントです。
ここでは、院卒が就職の際に直面しやすい主なデメリットを紹介します。
- 社会人としてのスタートが遅れるリスク
- 学費や生活費の負担が増える
- 学部卒との差が少ない業界もある
- 実務経験不足による即戦力性の課題
- 院卒枠が少ない業界での就職難
- 学歴より実績重視の企業文化との相性問題
①社会人としてのスタートが遅れるリスク
大学院に進学すると、社会人として働き始める時期が学部卒より2年前後遅くなります。
これはキャリアのスタートが遅れることを意味しますから、「早く社会に出て経験を積みたい」と考える人には不安の種となるでしょう。
ただし、遅れて社会に出る分、大学院で得た専門知識や研究力を生かし、より専門的な職種を目指すことが可能です。
大切なのは、この時間を「準備期間」と捉え、将来のキャリア形成にどう結びつけるかを考えることです。
②学費や生活費の負担が増える
大学院進学には、授業料や研究費、生活費などの経済的な負担が伴います。特に私立大学院や理系専攻では、年間100万円以上かかる場合もあります。
奨学金を利用する人も多いですが、卒業後に返済が負担となるケースも少なくありません。
一方で、近年は企業の研究支援や給付型奨学金の制度も増えています。経済的な不安を感じる場合は、進学前に利用可能な制度を確認し、将来の返済計画を立てておくことが大切です。
③学部卒との差が少ない業界もある
院卒だからといって、すべての業界で待遇が大きく向上するとは限りません。特に文系職種や営業職など、実績を重視する業界では「学部卒との差」がほとんどないこともあります。
そのため、「大学院に進めば自動的に給与が上がる」と思い込むのは危険です。
どの業界でどのスキルが評価されるのかを把握し、自分の進路がその基準に合っているかを確認することが、後悔を防ぐポイントです。
④実務経験不足による即戦力性の課題
院卒者は研究能力が高い一方で、実務経験が少ない点を懸念されることがあります。
企業は新卒でも「現場での応用力」や「チームでの成果」を重視する傾向があり、研究テーマが実務に直結しない場合、アピールが難しくなることもあります。
この課題を補うには、在学中にインターンや共同研究に積極的に参加することが効果的です。研究で培ったスキルを実践的な経験に結びつければ、就職活動でも強みとして伝えられるでしょう。
⑤院卒枠が少ない業界での就職難
一部の業界では、大学院卒を対象とする採用枠が限られています。たとえば、一般企業の事務職や営業職などは学部卒中心の採用が多く、院卒向けの募集が少ない傾向があります。
そのため、希望する職種や企業によっては応募の段階で選択肢が狭まることもあります。
進学を検討する際は、自分が目指す業界の採用傾向を確認し、院卒でも活躍できる環境かを見極めておくと安心です。
⑥学歴より実績重視の企業文化との相性問題
企業の中には「学歴よりも実績」を重視する文化が根付いているところもあります。
特にスタートアップ企業や外資系企業では、スピードや成果が重んじられるため、学歴の高さだけでは評価されにくい傾向があります。
このような職場では、院卒であることよりも「どんな経験を積み、何を成し遂げたか」が重要です。研究で得たスキルをどのように業務へ生かせるかを明確に伝えられるようにしましょう。
学歴に頼らず、実績で信頼を得る姿勢が求められます。
院卒の初任給に関するよくある質問
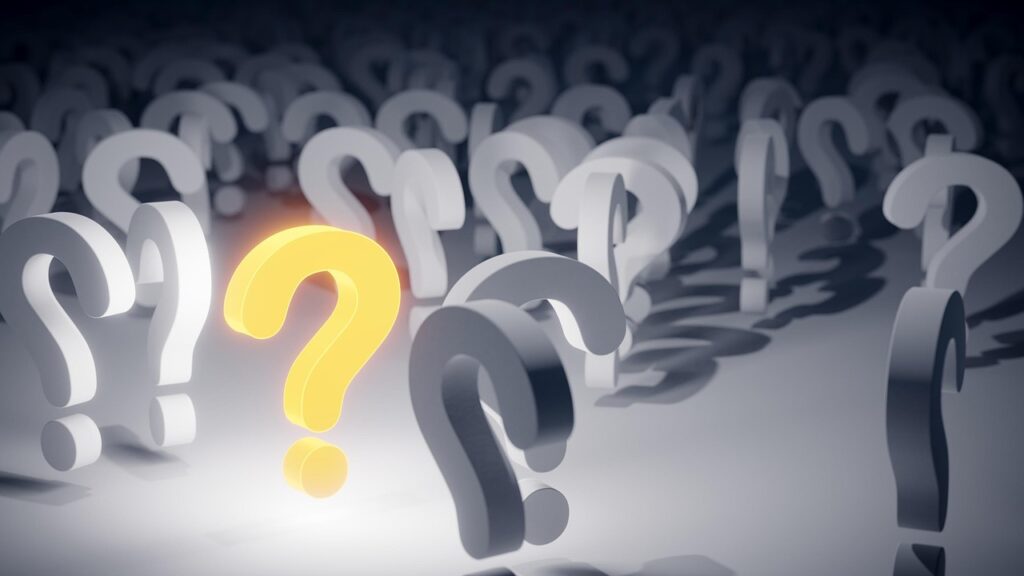
大学院を卒業した就活生の多くが気になるのが、「初任給はどのくらい違うのか」「採用の幅は広いのか」という点です。
ここでは、よくある2つの質問を取り上げ、国公立・私立による違いや、院卒が学部卒向け採用に応募できるかどうかについてわかりやすく解説します。
- 国公立と私立で初任給に差はある?
- 院卒が学部卒採用で就職するのは可能?
①国公立と私立で初任給に差はある?
国公立大学と私立大学の院卒を比べても、初任給に大きな差はほとんど見られません。企業は出身大学よりも、学んだ内容やスキル、実績を重視する傾向があります。
そのため、どの大学を卒業したかよりも、大学院で何を研究し、どのように成果を出したかが評価されるのです。
一部の有名私立や旧帝大などでは、研究テーマや共同プロジェクトの機会が豊富なため、結果的に待遇が良くなる場合もあります。
しかし、出身校にこだわるよりも、自分の強みを明確にし、企業にどう貢献できるかを示すことが重要です。主体的な姿勢が信頼につながるでしょう。
②院卒が学部卒採用で就職するのは可能?
結論として、院卒が学部卒採用枠で応募することは可能です。ただし、企業によっては「学歴過剰」と見られることもあるため、応募の目的を明確に伝える必要があります。
「研究よりも現場で経験を積みたい」「専門知識を社会で役立てたい」といった前向きな理由を示すと好印象です。
また、学部卒採用枠では初任給が大卒と同等になることが多く、給与面での差が出る可能性もあります。
それでも、自分のキャリアプランに合う職場を選ぶことが長期的には大きなプラスになります。肩書きにこだわらず、自分に合った働き方を選んでください。
院卒の初任給を踏まえたキャリア選択のポイント

院卒の初任給は全国平均で見ると大卒よりも高く、専門知識や研究スキルが高く評価される傾向にあります。
一方で、学費や在学期間の長さといったコスト面や、即戦力としての実務経験不足といった課題も存在します。
とはいえ、企業は院卒に対して「将来的なリーダー候補」としての期待を寄せるケースが多く、昇進やキャリアアップのチャンスも広がります。
自分の専門分野や希望業界の初任給・待遇を正しく理解し、将来のキャリア形成を見据えて進路を選ぶことが大切でしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














