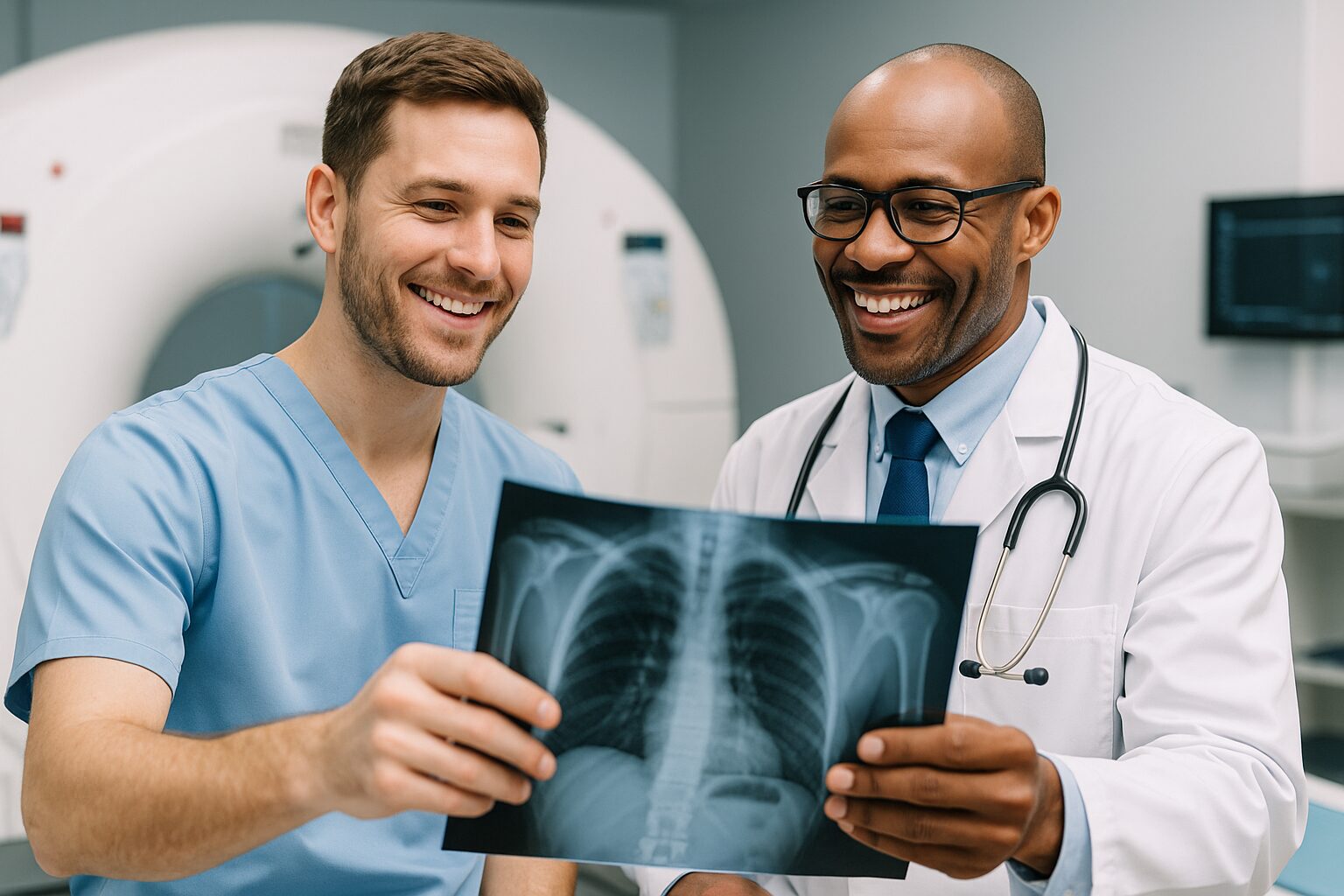ボーナスは給与の何か月分?年代別・業種別の平均支給額を徹底調査
「ボーナスって、給与の何か月分もらえるのが普通なんだろう?」
そんな疑問を持ったことはありませんか。ボーナスはモチベーションにも生活設計にも関わる大切な収入源ですが、実際の平均額や支給月数は年代や業種によって大きく異なります。
そこで本記事では、ボーナスの、年代別・業種別の平均支給額やその傾向を徹底調査。自分のボーナス水準を客観的に把握し、今後のキャリアや転職の参考にできるよう詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
ボーナス(賞与)とは?基本的な仕組みと種類

就活を控える学生にとって、ボーナスは将来の収入を見通すうえで大切な要素です。基本給とは別に支給される報酬であり、その金額や算出方法は企業ごとに異なります。
ここでは「ボーナスとは何か」「賞与という言葉との違い」「計算方式」「制度の種類」といった基本知識を整理しておきましょう。
- ボーナスとは基本給とは別に支給される報酬
- ボーナスと賞与の言葉の使い分け
- ボーナスの主な計算方式(定額方式・業績連動方式・利益配分方式)
- ボーナスの制度形態(基本給連動型・業績連動型・決算賞与など)
①ボーナスとは基本給とは別に支給される報酬
結論として、ボーナスは毎月の給与とは別に企業から支給される特別な報酬です。一般的には年2回、夏と冬に支給され、社員の働きや業績への貢献を評価する意味を持ちます。
なぜ大切かといえば、基本給だけでは生活設計が難しい場合でも、ボーナスが加わることで年収全体が大きく変わるからです。
たとえば同じ月給でも、ボーナスの有無によって手取り年収に数十万円から数百万円の差が生じます。就活生にとっては「月収だけでなく年収トータルで確認する」視点が欠かせません。
②ボーナスと賞与の言葉の使い分け
「ボーナス」と「賞与」という言葉は混同されやすいですが、意味には違いがあります。一般的に「ボーナス」は日常会話や求人広告でよく使われるカジュアルな表現です。
一方で「賞与」は就業規則や労働契約書などの正式な文書に用いられます。この違いを知っておくと、企業説明資料や労働条件通知書を読む際に誤解を避けられるでしょう。
特に法律上の議論や人事制度では「賞与」が正確な表現となります。就活生は制度の正式名称として理解しておくことが必要です。
逆に面接や座談会などでは「ボーナス」という言葉が自然に使われるため、文脈に合わせて読み替えるとスムーズでしょう。
③ボーナスの主な計算方式(定額方式・業績連動方式・利益配分方式)
企業のボーナスは一律に支給されるわけではなく、複数の算出方式があります。まず「定額方式」は役職や勤続年数に応じて一定額を支給するシンプルな方法です。
次に「業績連動方式」は会社全体や個人の成果に基づいて金額が決まるため、成果が収入に直結します。
さらに「利益配分方式」は企業の利益から一定割合を社員に分配する方法で、経営状況に左右されやすい一方、景気が良いときには高額になる可能性があります。
就活生にとって重要なのは「自分の努力がどの程度収入に反映される仕組みか」を理解しておくことです。
④ボーナスの制度形態(基本給連動型・業績連動型・決算賞与など)
ボーナスの制度は企業ごとに異なり、大きく3つの形態に分けられます。1つ目の「基本給連動型」は毎月の給与額を基準に支給額が決まり、安定性が高く将来設計が立てやすいです。
2つ目の「業績連動型」は個人や部門、会社全体の成果に応じて変動し、実力主義的な傾向が強まります。3つ目の「決算賞与」は年度末の業績に応じて支払われる臨時的なものです。
これらの制度は企業文化や経営方針を反映するため、単なる金額だけでなく「評価のされ方」や「成果と待遇の結びつき方」を知る材料になります。
就活生は求人票や説明会で提示されるボーナス制度の形式に注目することで、自分の働き方との相性を見極めやすくなるはずです。
ボーナスの支給時期と回数

ボーナスは給与とは別に支給される一時金ですが、時期や回数は企業ごとに異なります。
就活生にとっては「いつ支給されるのか」「どのくらいの頻度なのか」を知ることが生活設計や企業選びの参考になるでしょう。
ここでは一般的な夏・冬の支給に加え、業界差や特別なケースについて整理します。
- 夏季ボーナス(6〜7月支給)
- 冬季ボーナス(12月支給)
- 年2回支給が一般的な理由
- 業種や企業による支給回数の違い
- 特殊な支給(決算賞与・臨時賞与)
①夏季ボーナス(6〜7月支給)
夏のボーナスは6月から7月にかけて支給されることが多く、上半期の成果を反映する役割を持ちます。
就活生にとっては新生活の費用や旅行資金に充てられることも多く、生活にゆとりを与えてくれる存在です。
企業にとっては社員の努力を評価し、意欲を高める機会となります。ただし、景気や業績によって支給額が下がることもあり、必ず一定額を受け取れるとは限りません。
変動の可能性を理解しておくことで、安心して将来の資金計画を立てやすくなるでしょう。
②冬季ボーナス(12月支給)
冬のボーナスは12月に支給されるのが一般的で、下半期の成果を総括する意味があります。多くの家庭では年末年始の出費に充てられるため、まとまった収入として頼りになるはずです。
就活生にとっても「冬に大きな収入がある」という前提を知っておくと、年間の収入イメージを正しく描けます。
ただし、業績が悪い年には減額や支給見送りの可能性もあるため、求人票に「賞与あり」と書かれていても過去の実績を確認することが大切です。
冬季ボーナスは期待と同時にリスクも伴うことを意識してください。
③年2回支給が一般的な理由
日本企業で年2回の支給が定着しているのは、歴史的な慣習と経営管理上の理由があります。
もともとボーナスは「臨時の利益配分」として始まりましたが、高度経済成長期に労使の合意を通じて定期的な支給に変わりました。
その結果、夏と冬の支給が一般化し、社員の生活安定と企業の資金繰りを両立させる仕組みになったのです。
就活生にとって重要なのは、これは「法律上の義務」ではなく「慣習」であるという点でしょう。法定給付ではありませんが、就業規則や労働契約に定めがある場合は、その範囲で法的義務が生じます。
企業の状況によって金額や回数が変わることを知っておくと、誤解や落胆を防げます。
④業種や企業による支給回数の違い
支給回数は業種や企業によって違いがあります。製造業や大企業では年2回が多い一方で、ITベンチャーやスタートアップでは不定期だったり、成果次第で支給回数が変わることもあります。
また、外資系企業では年1回が一般的で、日本企業との違いに驚く学生も少なくありません。
多様な支給形態を知ることで、「ボーナスがあるから安心」と単純に考えず、自分の価値観に合った働き方を選べるようになります。
安定を取るか、成果主義に挑戦するかという視点で確認することが大切です。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
⑤特殊な支給(決算賞与・臨時賞与)
一部の企業では、夏や冬のボーナスに加えて決算賞与や臨時賞与が支給される場合があります。決算賞与は年度の利益に基づいて支払われ、業績が良い年には思わぬ収入となります。
臨時賞与はプロジェクトの成功や特別な成果への報酬として支給されることが多く、社員の大きな励みになるでしょう。
ただし、これらはあくまで特別な支給であり、毎年必ずもらえるわけではありません。就活生は過度に期待せず、あくまでプラスアルファとして認識しておくことが賢明です。
ボーナスは給与の何か月分?平均支給額の目安

ボーナス(賞与)は、就活生が企業を選ぶときに欠かせない収入要素です。「給与の何か月分もらえるのか」「どのくらいの金額になるのか」と気になる人も多いでしょう。
ここでは、平均支給月数の目安を「2か月前後」として統一し、季節ごとの傾向や変動要因、景気との関係を一次情報をもとに解説します。数値は主に令和5〜6年の公的統計を参照しています。
- 平均支給額は給与の概ね2か月前後
- 夏季・冬季の平均ボーナス額
- 平均支給月数の変動要因
- 経済動向とボーナス支給月数の関係
①平均支給額は給与の概ね2か月前後
全体の平均感覚としては、年間のボーナスは月給の「約2か月前後」です。実態は業種・規模などで「2〜3か月」に分布します。たとえば月給が25万円なら、年間50万円前後が目安です。
厚生労働省の『賃金構造基本統計調査(令和5年)』では、「年間賞与その他特別給与額」として平均値が公表されています。ただし、業種や企業規模、役職などによって支給水準は大きく異なります。
大企業では3か月を超える場合もある一方で、中小企業では1か月に満たない例もあります。志望企業を調べる際は、必ず過去の支給実績や給与規定を確認しておくと安心でしょう。
②夏季・冬季の平均ボーナス額
多くの企業では、ボーナスが夏(6〜7月)と冬(12月)の年2回に分けて支給されます。一般的には、冬のほうが金額が大きくなる傾向があります。
一方、『賃金構造基本統計調査』には季節別の平均額は掲載されていません。そのため、厚生労働省の『毎月勤労統計』が発表する「夏季賞与(6〜8月の特別給与)」のデータを参考にする形になります。
ただし、これは期間内に支給された特別給与額であり、年間の賞与とは定義が異なるため、月数換算や年間比較はあくまで目安として捉えてください。
また、入社1年目は在籍期間の関係で支給されない場合もあります。初年度の収入を計画する際は、支給条件や在籍要件を事前に確認しておきましょう。
③平均支給月数の変動要因
ボーナスの支給月数は、企業の業績・規模・評価制度といった複数の要因によって左右されます。
まず、業績連動型の企業では、利益が減ると支給額が抑えられ、反対に業績が好調な年には上乗せされる傾向があります。
業績連動の度合いが強い業界ほど、景気や為替動向の影響を受けやすい点が特徴です。また、企業規模が大きいほど内部留保や資金力に余裕があり、平均支給月数が相対的に高くなる傾向があります。
大企業は「約2か月超」が比較的多く、中小企業は「約1.5か月前後」にとどまる例も珍しくありません。さらに、役職や人事評価制度によっても支給額に差が生じます。
厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』では、企業規模別・産業別に「年間賞与その他特別給与額」が公表されています。
就活生は志望する業界や企業規模を意識しながら、信頼できる公的統計をもとに年収の見通しを立てておくとよいでしょう。
④経済動向とボーナス支給月数の関係
ボーナスは企業の利益をもとに支給されるため、景気や業績と密接に関係しています。景気が良いときは支給額が増える傾向がありますが、不況期には減額や支給見送りが行われることもあります。
そのため、志望企業の決算情報や業界全体の動向を確認しておくことが大切です。景気の影響を受けにくい業界(インフラ、公務員、医療など)を志望するのも安定した収入を得る一つの選択肢でしょう。
ボーナスは企業の健全性を映す指標でもあります。入社後の年収を考えるときは、業績と支給実績の両方をチェックしておくことをおすすめします。
引用元一覧
厚生労働省『賃金構造基本統計調査 令和5年 結果の概況(PDF)』
e-Stat『賃金構造基本統計調査(統計表DB)』
厚生労働省『毎月勤労統計 令和6年9月分 結果速報(PDF)』
年代別・男女別のボーナス平均額

ここでは、年代ごとのボーナス平均額を一次情報に基づいて紹介します。数字の背景にある傾向を正しく理解し、就活時に企業を比較する際の判断材料にしましょう。
- 新卒・20代の平均ボーナス額
- 30代の平均ボーナス額
- 40代の平均ボーナス額
- 50代の平均ボーナス額
- 男女別の平均ボーナスの違い
①新卒・20代の平均ボーナス額
20代前半は社会人として経験を積み始める時期であり、ボーナスの水準が特に気になる世代です。
厚生労働省の『賃金構造基本統計調査(令和5年)』によると、20〜24歳の年間賞与は約38万円、25〜29歳は約66万円です。月給を25万円と仮定すると、約2.6か月分に相当します。
年2回の支給であれば、1回あたり1〜1.5か月分が一般的です。入社初年度は在籍期間の関係で支給が少なくなる傾向がありますが、勤続年数の増加やスキル向上に伴い、徐々に平均水準に近づいていきます。
短期的な金額だけで判断せず、評価制度や業績連動型の仕組みも確認しておくとよいでしょう。
②30代の平均ボーナス額
30代は昇進や昇給の機会が増え、収入全体が安定する時期です。統計によると、30〜34歳の年間賞与は約80万円、35〜39歳では約94万円となっています。
月給を30万円前後と想定すると、2.7〜3.1か月分に相当します。20代より確実に上昇しており、管理職やリーダー職に就くことでさらなる増加も期待できます。
企業規模による差はありますが、「30代で3か月前後」が平均的な水準でしょう。金額だけでなく、評価方法や業績反映の仕組みを確認することで、将来的な収入の見通しを立てやすくなります。
③40代の平均ボーナス額
40代は部下を指導したり、組織を支える立場となる年代です。40〜44歳の年間賞与は約103万円、45〜49歳では約112万円と報告されています。
月給を35〜40万円と仮定すると、2.8〜3か月分ほどに相当します。30代より上昇幅は緩やかですが、役職によっては3か月を超えることもあります。
業績変動の影響を受けやすい企業では支給額にもばらつきが生じるため、最新の決算情報や支給基準をチェックしておくと安心です。
④50代の平均ボーナス額
50代になると役職や責任の重みが支給額に反映されます。50〜54歳では約120万円、55〜59歳では約122万円と、ピークに達する水準です。
月給を40〜45万円と想定すると、2.7〜3か月分が目安となります。労務行政研究所の調査によれば、2025年の年末一時金(ボーナス)の平均支給月数は「約2.55か月」でした。
これは50代でも3か月前後の支給が一般的であることを示しています。役職や業績によって差は出ますが、長年の成果が正当に評価される段階といえるでしょう。
⑤男女別の平均ボーナスの違い
男女でボーナス額に差があるかどうかは、多くの就活生が気になる点です。統計上は男性のほうが平均額が高い傾向がありますが、その背景には勤続年数や職種構成の違いがあります。
近年は「同一労働同一賃金」の浸透により、格差が縮まっている企業も増えています。
性別だけで判断せず、等級制度や評価基準、職務内容を確認し、納得できる評価環境かどうかを見極めることが大切です。自分の努力が正当に評価される企業を選びましょう。
引用元一覧
厚生労働省『賃金構造基本統計調査 令和5年 結果の概況(PDF版)』
e-Stat『賃金構造基本統計調査 表6:職種別・年齢階級別 年間賞与その他特別給与額』
東京都産業労働局統計部『令和6年 夏季賞与の実態調査 結果報告(PDF)』
労務行政研究所『東証プライム上場企業の2025年 年末一時金(賞与・ボーナス)の妥結水準調査』
業種別のボーナス平均額

業界や企業の規模によって、ボーナス(賞与)の金額や支給月数には大きな差があります。就活生が志望する業界の相場を理解しておくことは、将来のキャリア設計において重要です。
ここでは、厚生労働省・経団連・労務行政研究所などの一次情報をもとに、主要業種の平均支給額と特徴を紹介します。
- 電気・ガス業界の平均
- 情報通信業界の平均
- 製造業(自動車・機械など)の平均
- 金融業(銀行・証券・保険)の平均
- 建設・不動産業界の平均
- 流通・小売・サービス業の平均
- 医療・福祉・教育分野の平均
- 公共性の高い業種(交通・インフラなど)の平均
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①電気・ガス業界の平均
電気・ガス業界は国内でも特に安定した収益基盤を持ち、ボーナス水準が高いことで知られています。
厚生労働省の『毎月勤労統計調査(令和6年9月分)』によると、電気・ガス・熱供給・水道業の…平均賞与は約81万円で、支給月数に換算すると「約1.8か月分」です。
公益性が高く安定した収益構造を持つ一方で、エネルギー価格の変動や政府の規制政策が支給水準に影響を与えることもあります。
安定志向の人には魅力的ですが、今後は再生可能エネルギーなど変化に対応できる柔軟性も求められるでしょう。
②情報通信業界の平均
情報通信業界は成長性が高く、デジタル化の波に乗る産業として注目されています。厚生労働省の統計では、令和6年夏季賞与の平均支給額が約74万円で、前年より増加しました。
支給月数にするとおよそ2か月分前後です。企業によって成果主義の度合いが異なり、エンジニア職や営業職など職種ごとに評価基準が細かく分かれています。
スキルや成果がダイレクトに報酬へ反映されやすく、努力次第で収入を伸ばしやすい業界といえるでしょう。
③製造業(自動車・機械など)の平均
製造業は日本経済の中心を担う業界で、ボーナス水準も高めです。経団連の『2025年 夏季賞与・一時金調査』によると、製造業の平均妥結額は約96万円でした。
前年(2024年:95.8万円)とほぼ同水準で、安定的な傾向が続いています。
自動車、電機、精密機械などの大手メーカーは海外需要や為替動向によって支給額が左右されやすく、業績連動型の色合いが強い点が特徴です。
グローバル市場を見据えた経営視点や、業界動向を読む力が求められます。
④金融業(銀行・証券・保険)の平均
金融業は全産業の中でも特に高いボーナス水準を誇ります。経団連の統計によれば、非製造業全体の平均妥結額は約84万円で、その中でも金融業は上位に位置します。
営業職や投資関連部門では成果に応じて支給額が決まり、優秀な社員ほど高額な報酬を得ることが可能です。
ただし、金融政策や金利動向によって業績が変動しやすく、支給額にも波があります。成果主義の環境で成長したい人に向いた業界といえるでしょう。
⑤建設・不動産業界の平均
建設業は景気変動に左右されやすいものの、比較的高水準のボーナスが支給される業界です。厚生労働省の統計によると、建設業の平均ボーナス額は約54万円で、前年より微増しています。
大手ゼネコンや不動産デベロッパーでは、賞与が5か月分を超えるケースも見られます。一方で中小企業ではプロジェクトの進行状況や完了時期によって支給額が変わることもあります。
長期的に安定収入を得たい場合は、案件規模や企業の経営基盤を確認しておくとよいでしょう。
⑥流通・小売・サービス業の平均
流通・小売・サービス業は他業種と比べてボーナス水準が低い傾向にあります。厚生労働省の調査によると、卸売・小売業の平均支給額は約38万円、宿泊・飲食サービス業は約7.6万円でした。
近年は人手不足対策として待遇改善が進んでいますが、依然として全体水準は控えめです。
業績よりも個人の成果に報いるインセンティブ制度を採用する企業も多く、固定的な賞与よりも変動報酬の比重が高い特徴があります。
⑦医療・福祉・教育分野の平均
医療・福祉分野の平均賞与は約28万円とされ、全産業の中では低めの水準です。国や自治体の補助金を主な収益源とする施設が多く、業績による変動が小さい点が特徴です。
教育分野では、公立と私立で給与体系が異なり、私立学校では法人の財務状況によって支給額が左右されます。
社会的意義が大きい分、報酬面だけで判断しない姿勢が求められます。安定よりも使命感を重視する人に向いた分野といえるでしょう。
⑧公共性の高い業種(交通・インフラなど)の平均
運輸・郵便業などの公共性の高い分野は、安定した支給傾向が続いています。厚生労働省の統計では、運輸・郵便業の平均支給額が約39万円で、月給換算では1〜1.5か月分に相当します。
景気変動の影響を受けにくく、安定志向の人には魅力的な業界です。昇給スピードはゆるやかですが、福利厚生や労働環境の整備が進んでおり、長期的なキャリア形成に向いています。
引用元一覧
厚生労働省『毎月勤労統計調査 令和6年9月分 結果速報(夏季賞与支給状況)』
経団連『2025年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(加重平均)』
経団連『2024年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(加重平均)』
労務行政研究所『東証プライム上場企業の2025年 年末一時金(賞与・ボーナス)の妥結水準調査』
セクター別ボーナスの違い(民間企業と公務員)

企業や組織の種類によって、ボーナス(賞与)の支給額や仕組みには大きな違いがあります。ここでは「公務員」と「民間企業」を比較し、それぞれの平均支給額や制度の特徴を整理します。
就活生にとって、安定性と収入見通しのバランスを考えるうえで重要な判断材料となるでしょう。
- 公務員の平均支給額と月数
- 民間企業の平均支給額と月数
- 制度や安定性の違い
①公務員の平均支給額と月数
公務員のボーナス(期末・勤勉手当)は、人事院勧告に基づいて決定されるため、景気に左右されにくい安定した水準を保っています。
2024年度(令和6年)の人事院勧告では、年間支給月数を「4.60か月分」とするよう勧告されました。これは33年ぶりの大幅な引き上げとなります。
月収30万円のケースでは、年間約138万円前後が支給される計算です。国家公務員の支給は6月と12月の2回に分かれており、金額は俸給や勤務成績、勤続年数に応じて決まります。
公務員制度では「民間準拠の仕組み」が採用されており、毎年民間企業の動向を調査したうえで勧告が行われます。これにより、社会全体の賃金バランスを維持する構造となっています。
このように、公務員の賞与は安定性が高く、経済変動の影響を受けにくい点が特徴です。長期的な収入見通しを立てやすい職種といえるでしょう。
②民間企業の平均支給額と月数
民間企業では、ボーナスの金額や支給回数は業績や評価、企業規模によって大きく異なります。
経団連の『2025年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)』によると、大手企業97社の平均妥結額は99万3,000円で、前年(2024年:98万3,000円)を上回り、3年連続の上昇となりました。
また、労務行政研究所の調査によると、2025年の年末一時金(ボーナス)の…平均支給月数は全体で「約2.55か月」。業種別では製造業が「約2.8か月」、非製造業が「約2.0か月」です。
一方で、民間企業の賞与は景気や業績に大きく左右されます。好景気時には大幅な増加が見込まれる反面、不況時には支給額が減少、場合によっては支給が見送られるケースもあります。
成果主義の企業では、個人の業績がボーナス額に強く反映される傾向があり、努力次第で公務員より高い収入を得ることも可能です。
③制度や安定性の違い
公務員と民間企業のボーナス制度には、安定性を重視するか、成果主義を重視するかという明確な違いがあります。公務員は国家予算に基づくため、景気変動の影響をほとんど受けません。
給与改定は人事院勧告を通じて社会全体の賃金動向を反映しながら実施され、長期的な安定性を維持しています。一方で民間企業は、企業の業績や個人評価に基づく支給体系が一般的です。
景気が良いときは高額なボーナスを得られますが、業績が悪化すると支給額が減少するなどリスクも存在します。
安定した収入と社会貢献を重視するなら公務員、成果と報酬の伸びしろを求めるなら民間企業。どちらを選ぶかは、自身の価値観やキャリア観に合わせた判断が必要です。
引用元一覧
人事院『令和6年 人事院勧告・報告の概要(国家公務員の給与等の改定について)』
経団連『2025年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(加重平均)』
経団連『2024年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(加重平均)』
労務行政研究所『東証プライム上場企業の2025年 年末一時金(賞与・ボーナス)の妥結水準調査』
企業規模別ボーナスの違い(大企業と中小企業)

就職活動を進めるうえで、「ボーナスがどのくらいもらえるのか」は多くの学生が関心を寄せるテーマです。企業の規模によって平均支給月数や金額には大きな差があります。
ここでは、大企業と中小企業の特徴を比較し、その格差が生まれる背景をわかりやすく解説します。
- 大企業の平均支給月数と特徴
- 中小企業の平均支給月数と特徴
- 規模による格差が生まれる要因
①大企業の平均支給月数と特徴
大企業のボーナス水準は高く、支給額・支給月数の両面で安定しています。経団連の最新調査によると、従業員500人以上の大手企業の平均妥結額は約99万円で、前年を上回る水準となりました。
特に製造業では100万円を超えるケースも多く、景気回復の恩恵を受けやすい業種であることがわかります。
また、労務行政研究所の調査では、上場企業(東証プライム)の平均支給月数は「約2.55か月」とされています。
これらのデータから、大企業では「安定して2か月以上の支給」が一般的なボーナス水準といえるでしょう。
さらに、大企業では「会社業績×個人評価」によって支給額が決定される仕組みが多く、評価制度の透明性や納得感が得やすいのも特徴です。
景気や業績による変動はあるものの、生活設計を立てやすい安定的な環境といえます。
②中小企業の平均支給月数と特徴
中小企業のボーナスは、大企業と比べて支給額が低めの傾向にあります。
厚生労働省の『毎月勤労統計調査』によると、事業所規模30人以上の夏季賞与の平均支給額が約73万円、支給月数は「約1.5か月」と報告されています。
事業規模が小さいほど景気や取引先の影響を受けやすく、支給額にばらつきが生じやすい点が特徴です。
ただし、中小企業の中にもニッチ分野で強みを持つ企業や、高収益なベンチャーでは大企業並みの賞与を支給する例もあります。
また、経営者の裁量が大きい分、成果が直接報酬に反映されやすく、実力次第で大幅な報酬アップも狙える環境です。
安定性よりもスピード感や実績重視の環境で働きたい人にとっては、魅力的な選択肢となるでしょう。
③規模による格差が生まれる要因
企業規模によるボーナス格差は、主に「利益構造」「資金力」「人事制度」の3つに起因します。まず、利益構造の違いです。大企業は複数の取引先を持ち、景気変動を吸収しやすい構造を持っています。
一方で中小企業は取引先が限られることが多く、業績の波を受けやすい傾向があります。次に、資金力の差です。
大企業は内部留保が厚く、安定した賞与支給が可能ですが、中小企業では設備投資や人件費に資金が割かれ、賞与に回す余力が限られます。最後に、人事制度の整備度です。
大企業では等級制度や評価基準が体系化され、公平な査定が行われる一方で、中小企業は経営者の判断に依存するケースが多く、支給の安定性にばらつきが生じやすい傾向にあります。
就活生は、「支給月数」や「金額」だけでなく、「評価制度の透明性」や「報酬決定プロセスの納得感」にも注目して企業を見極めることが重要です。
引用元一覧
経団連『2025年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)』
日本経済団体連合会『2025年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果』
労務行政研究所『東証プライム上場企業の2025年 年末一時金(賞与・ボーナス)の妥結水準調査』
厚生労働省『毎月勤労統計調査 令和6年 夏季賞与』
東京都産業労働局統計部『令和6年 夏季賞与 調査結果』
ボーナス支給額の決まり方と支給条件

就活生にとって、ボーナスの支給基準や条件は就職先を決める上で大切な要素です。
企業ごとに算定方法や支給条件が異なるため、内容を理解しておかないと入社後に不満や誤解が生じやすくなります。ここでは代表的な決まり方と注意点を整理します。
- 人事評価による決定
- 会社業績による変動
- 勤続年数や役職による差
- 就業規則に基づく支給条件
- 退職予定者や転職者の支給条件
- 年俸制・成果主義企業での扱い
- 支給基準や計算方法の詳細
①人事評価による決定
ボーナスは多くの企業で人事評価に基づいて決まります。評価が高ければ支給額も増え、反対に評価が低いと減額されることもあります。
勤続年数だけで自然に増えるわけではなく、成果を意識して働く姿勢が重要です。この点を理解しておくと、入社後の行動の指針が明確になりやすいでしょう。
②会社業績による変動
業績連動型の企業では、会社全体の売上や利益がボーナス額に直結します。業績が好調なときは高額が期待できますが、不況期には大幅に減る可能性もあります。
自分の努力だけでは左右できない部分があるため、安定性を重視するなら業績が安定している業界を選ぶのも有効です。
③勤続年数や役職による差
同じ評価を受けても、勤続年数や役職によって金額に差が生まれます。新入社員のうちは少額にとどまることもありますが、昇進や経験を重ねるにつれて増えていくのが一般的です。
長期的な視点を持つと、短期的な差に振り回されずに済むはずです。
④就業規則に基づく支給条件
ボーナスの有無や算定方法は就業規則に明記されています。規則に「業績が著しく悪化した場合は支給しない」と記されていることも珍しくありません。
内定後に就業規則を確認しておくと、安心感を持って働き始められるでしょう。
⑤退職予定者や転職者の支給条件
支給日に在籍していることを条件とする会社は多くあります。そのため、退職や転職を控えている人は注意が必要です。在籍日の取り扱いは会社ごとに異なるため、誤解が生じやすい点でもあります。
⑥年俸制・成果主義企業での扱い
年俸制を採用する企業では、ボーナスを設けず年収に含めている場合があります。
成果主義の会社では、業績によっては支給がゼロになることもあるでしょう。制度を理解せずに入社すると、想定より収入が少なくなるおそれがあります。
⑦支給基準や計算方法の詳細
支給額は「基本給×支給月数」で計算されるのが一般的です。支給月数は業界や会社規模によって異なり、平均では2〜3か月分程度とされています。
計算方法を知っておくことで、自分の給与水準と合わせて将来の収入を見積もりやすくなります。
ボーナスから税金・社会保険料を引いた手取り額の計算方法

ボーナスは額面のまま受け取れるわけではなく、税金や社会保険料が差し引かれるため、実際の手取りは少なくなります。
就活生にとっては将来の収入を具体的にイメージするうえで、控除の仕組みを理解しておくことが重要です。ここでは主な控除項目と、最終的にどの程度の手取りになるのかを説明します。
- ボーナスにかかる所得税の計算
- 健康保険料の控除
- 厚生年金保険料の控除
- 雇用保険料の控除
- 社会保険料と税金を差し引いた手取り額
- ボーナス明細の確認ポイント
①ボーナスにかかる所得税の計算
ボーナスには給与と同じように所得税がかかります。計算は「ボーナス支給額から社会保険料を引いた金額」に税率をかけて算出され、源泉徴収という形で自動的に引かれます。
税率は扶養の有無や月給で変わるため人によって差があります。例えば月収20万円ほどの新入社員なら、数千円から1万円程度が引かれる場合が多いです。
自分の条件に合わせて大まかな目安を理解しておくと安心でしょう。
②健康保険料の控除
健康保険料もボーナスから天引きされます。料率は協会けんぽや健康保険組合によって異なりますが、一般的に支給額の10%前後と考えると分かりやすいです。
これは医療費の一部負担や出産手当金などの財源になっています。単に手取りが減るという見方ではなく、将来の安心につながる仕組みと理解しておくことが大切です。
③厚生年金保険料の控除
厚生年金も主要な控除項目です。支給額の約9%を会社と折半し、本人負担はその半分ほどです。ボーナス20万円なら、約18,000円が差し引かれる計算になります。
負担に感じるかもしれませんが、老後資金として将来に返ってくる大切な積み立てです。就活の段階で知っておくと、長期的な視点を持ちやすくなるでしょう。
④雇用保険料の控除
雇用保険料は失業や教育訓練給付に備える制度で、料率は0.6%前後と低めです。ボーナス20万円の場合、控除額は約1,000円にとどまります。
少額でも万一のときに支えとなるため、安心材料と考えておくとよいでしょう。普段意識しづらい項目ですが、働くうえで重要な仕組みです。
⑤社会保険料と税金を差し引いた手取り額
実際の手取りは額面よりも少なくなり、支給額の75〜85%程度がおおまかな目安です。例えばボーナスが20万円なら手取りは15万円前後になります。
控除額は勤務先や扶養条件によって異なりますが、あらかじめ「数万円は引かれる」と想定しておくことが現実的です。就活生も額面だけでなく、手取りを基準に生活設計を考えると安心できます。
⑥ボーナス明細の確認ポイント
ボーナスを受け取るときには必ず明細が渡されます。ここには支給額、控除額、手取り額が記載されているので、必ず確認してください。
控除の内訳を理解しておけば、自分のお金がどのように社会保障や税金に回っているかを把握できます。
驚くだけでなく、制度的な意味を理解しておくことが、将来の家計管理や資産形成につながります。
結論として押さえておきたいポイント

ボーナス(賞与)は、基本給とは別に支給される重要な報酬制度であり、支給方法や支給回数は企業ごとに異なります。
一般的には年2回、夏季と冬季に支給され、平均額は給与の約2か月分とされています。ただし、業種や企業規模、景気動向によって金額や支給月数は変動するのが実態です。
年代別に見ると年齢が上がるにつれて支給額も増える傾向があり、さらに業種別では電気・ガス、金融業界が高水準で、サービス業や福祉分野は低めに推移しています。
また、大企業と中小企業、公務員と民間企業の間でも差が見られるため、自分のキャリア設計に合わせて理解しておくことが大切です。
支給額は人事評価や業績、勤続年数などで決まり、さらに税金や社会保険料が控除されるため、手取り額は額面より減少します。
こうした仕組みを知っておくことで、就職活動や転職活動での判断材料として有効に活用できるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。