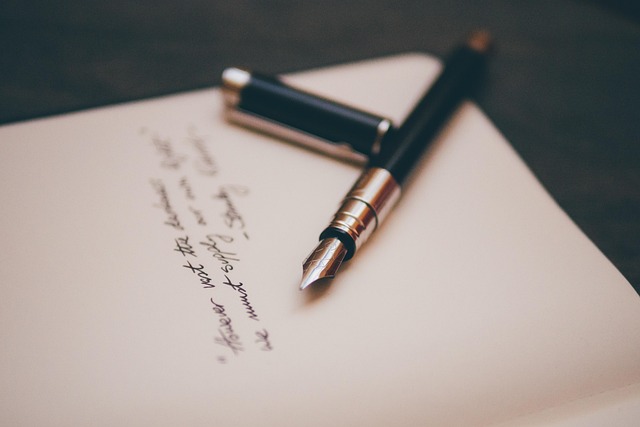会社見学の準備とマナー完全ガイド|質問例・NG行動もわかる
会社見学は、企業にあなたの印象が直接伝わる「評価の場」でもあります。服装やマナー、質問内容など、ちょっとした準備の差が印象を大きく左右することも。
この記事では、会社見学の基本的な流れから、事前準備・当日のマナー・質問例・NG行動までを完全解説し、初めての見学でも自信を持って臨めるよう、就活に直結するポイントをわかりやすく紹介します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
会社見学とは?

会社見学とは、学生が企業を訪問して職場の雰囲気や社員の働き方を直接確かめる機会のことです。
就活生にとっては企業研究の一環であり、単なるイベントではなく将来の選択を左右する重要な体験になります。
なぜなら、説明会やホームページだけでは分からないリアルな職場の姿を知ることで、自分に合うかどうかを判断できるからです。
実際にオフィスを歩いたときの空気感や社員同士のやり取りを観察すると、企業文化との相性を具体的にイメージしやすくなります。
つまり、会社見学は受け身で参加する学びの場ではなく、自分の将来像を描くための主体的な行動の場と考えることが大切です。準備をしっかり整えて臨めば、単なる見学以上の価値を得られるはずです。
会社見学は評価対象となる

会社見学は単なる説明会ではなく、企業側が就活生の姿勢や素質を評価する重要な場です。参加者の第一印象やビジネスマナー、会話の仕方から、社会人としての基礎力や協調性が見抜かれます。
就活生にとっては、短い時間で好印象を与える大きなチャンスでもあります。ここでは企業視点の評価項目を理解し、どのように準備すれば良いかを具体的に解説します。
- 企業視点での評価
- 第一印象での評価
- ビジネスマナーでの評価
- 積極性での評価
- コミュニケーション力での評価
- 社会人基礎力での評価
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①企業視点での評価
会社見学で企業は、就活生の社会人としての適性を見極めようとします。時間管理や服装、立ち居振る舞いから誠実さや責任感を確認されるでしょう。
さらに、質問の内容や受け答えからは、志望度や主体性が判断されます。見学だからと気を抜くのは危険です。
企業目線を意識した行動を心がけるだけで、印象は大きく変わり、採用活動にも良い影響を与えるはずです。
②第一印象での評価
第一印象は数秒で決まり、その後の評価にも影響します。入室時のあいさつや表情、身だしなみは特に重要です。清潔感のあるスーツや整えた髪型、明るい声でのあいさつが基本となります。
さらに、姿勢や立ち方からも積極性や自信が伝わります。事前に鏡で笑顔や姿勢をチェックし、あいさつの練習をしておくと良いでしょう。小さな準備が、信頼を得る大きな鍵になります。
③ビジネスマナーでの評価
会社見学では、基本的なビジネスマナーが見られます。時間に余裕を持って到着する、正しい敬語を使う、名刺交換や着席の順番に気を配るといった行動は必須です。
スマートフォンを机に置いたままにする、メモを取らない、上座下座を意識しないなどの行動は評価を下げる可能性があります。細部まで注意を払い、社会人らしい振る舞いを心がけてください。
④積極性での評価
積極性は大きな評価ポイントです。質問をせず、ただ話を聞いているだけでは受け身な印象を与えてしまいます。業界や企業の情報を下調べし、具体的な質問を用意しておくことで熱意が伝わります。
ただし、自分を過度にアピールすると逆効果になりかねません。相手の話をよく聞きながら、自然な会話を意識することで印象が良くなるでしょう。
⑤コミュニケーション力での評価
会話の受け答えや質問の仕方から、コミュニケーション力や協調性が判断されます。話を最後まで聞く、うなずきや相づちを適切に入れるといった基本が評価に直結します。
質問は要点を絞り、簡潔に伝えることが好印象のコツです。小さな配慮や対応力が、結果的に良い評価を引き寄せる要因となります。
⑥社会人基礎力での評価
社会人基礎力とは、主体性・実行力・柔軟性などを総合した力のことです。短時間の会社見学でも、これらは十分に見抜かれます。
説明中に疑問を持ったらその場で質問する、指示があれば即座に対応するなどの行動は、実行力や判断力を示します。
日頃から時間管理や報連相を意識し、初対面でも臆さない姿勢を養うと評価が高まるでしょう。
会社見学の流れ

会社見学の流れを理解しておくことで、当日の不安が和らぎ、適切な行動を取りやすくなります。受付での第一印象から、最後の挨拶や退出後のフォローまで、一連の流れを把握することが大切でしょう。
以下では各ステップのポイントを整理しました。
- 受付での対応
- オリエンテーションや説明会
- オフィス案内
- 社員との交流
- 質疑応答
- 見学終了時の挨拶
- 退出後の行動
①受付での対応
受付は会社見学の最初の関門であり、印象が決まる重要な場面です。到着は10分前を目安にし、身だしなみを整えて明るい笑顔で名乗ってください。
名前と訪問理由を簡潔に伝えるとスムーズです。緊張で声が小さくなる場合もありますが、相手にしっかり届く声量を意識しましょう。
受付での立ち居振る舞いは採用担当者にも共有されるため、礼儀正しさが評価されます。スマホを操作しながら待つなどの行為は控え、周囲への配慮を忘れないことが大切です。
②オリエンテーションや説明会
オリエンテーションでは、企業理念や事業内容、職場環境について説明を受けます。ここで得た情報は面接の志望動機や逆質問に直結するため、聞き漏らさない姿勢が求められます。
メモを取りながら頷くことで、熱意や理解度を示せます。質問があればメモに残し、適切なタイミングで尋ねてください。
受け身ではなく、興味を持って参加する姿勢を行動で示すと印象が良くなります。説明が長くても集中力を切らさず、相手の目を見て話を聞く姿勢が評価されるでしょう。
③オフィス案内
オフィス案内は、職場の雰囲気や働き方を直接確認できる貴重な機会です。デスク周りや設備を注意深く観察し、気になる点は後で質問できるよう記録すると良いでしょう。
移動中は話しかけるタイミングを見極め、案内役の社員が話す内容に耳を傾けてください。雑談の中から企業文化を感じ取ることもあります。
歩くスピードや距離感を相手に合わせるなど、細かな配慮が印象を高めます。無駄に周囲を見回さず、自然な興味と礼儀を意識しましょう。
④社員との交流
社員との交流は、会社のリアルな雰囲気や価値観を知る絶好の場です。自己紹介は簡潔にまとめ、相手の話に共感しながら会話を進めると良好な関係が築けます。
質問をする際は、相手が答えやすい具体的かつ前向きな内容を意識してください。ネガティブな比較や待遇だけに偏った質問は避けるのが無難です。
交流中は笑顔や適度なリアクションを心がけ、会話のテンポを合わせると良いでしょう。相手の名前を覚えて呼ぶと親近感が増します。
⑤質疑応答
質疑応答は、自分の関心を示しつつ理解を深める大切な時間です。企業研究を行い、具体的な質問を3つほど用意しておくと安心でしょう。
業務内容やキャリアパス、求める人物像など、答えやすい質問を選ぶと好印象です。「特に質問はありません」と答えると意欲不足と見なされることがあるため避けてください。
質問後には「参考になりました」と感謝を伝えることも重要です。
⑥見学終了時の挨拶
見学終了時には、担当者に感謝の気持ちをしっかり伝えてください。お礼の言葉は具体的な内容を添えるとより良い印象になります。
例えば「オフィスの雰囲気を直接見られて、働くイメージが具体化しました」などと一言添えると効果的です。深いお辞儀や目を見た挨拶も忘れずに行いましょう。
退出時に手を振るなど、不要な行動は控えることが無難です。
⑦退出後の行動
退出後は、当日中にお礼メールを送ると良いでしょう。メールでは、見学で学んだ具体的な点や感謝の気持ちを簡潔にまとめてください。
この一手間が採用担当者に好印象を与えます。また、気づきや感想をすぐメモしておくことで、面接や志望動機作成に役立ちます。最後まで礼儀を意識することが重要です。
会社見学前の準備

会社見学を成功させるには、事前準備が結果を大きく左右します。企業は学生の細かな行動を見て、社会人としての素養やマナーを判断します。
しっかり準備することで安心感が生まれ、余裕をもって臨めるでしょう。ここでは、会社見学前に押さえておくべき重要なステップを紹介します。
- 企業・業界研究の徹底
- 訪問目的の整理
- 質問内容の整理
- スケジュールの確認
- 集合場所の確認
- 身だしなみの準備
- 必要書類のチェック
- 持ち物のチェック
- 挨拶の練習
- 自己紹介の練習
①企業・業界研究の徹底
会社見学で良い印象を与えるには、事前の企業・業界研究が欠かせません。事業内容や競合との差、最近のニュースを把握しておくと、会話の中で具体的な質問や意見を交えやすくなります。
例えば「御社の〇〇というサービスについて拝見しましたが、現場ではどのような強みを感じますか?」といった質問は準備の深さが伝わるでしょう。
研究不足だと表面的な会話に終わり、志望度が低いと思われる可能性があります。公式サイトだけでなく、ニュース記事やSNSも活用し、最新情報を押さえることが大切です。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
②訪問目的の整理
会社見学は目的意識を持つことで得られるものが大きく変わります。「職場の雰囲気を確認したい」「業務内容をより詳しく知りたい」など、具体的なゴールを設定しておきましょう。
目的が曖昧だと質問も浅くなり、せっかくの機会を十分に活かせません。紙やスマートフォンのメモに目的を書き出しておくと、当日も確認しやすいです。
整理された目的を持つことで社員との対話も深まり、企業理解が進みます。
③質問内容の整理
会社見学では質問が評価のポイントになることが多いです。事前に5~6個の質問を用意し、優先順位をつけておくとスムーズでしょう。
「入社後のキャリアパス」「社内の研修制度」「最近のプロジェクト例」などは関心の高さを示す質問です。一方で、調べれば分かる情報や待遇面ばかりを聞くと、熱意が疑われる可能性があります。
自分が知りたい内容と企業が答えやすいテーマをうまく組み合わせることがコツです。
④スケジュールの確認
見学日のスケジュールは必ず前日に再確認してください。集合時間や所要時間、当日の流れを理解しておくことで慌てずに行動できます。
特に交通機関の遅延リスクを考え、30分以上の余裕をもって出発するのがおすすめです。スマートフォンのカレンダーに予定を入れてリマインドを設定すると、忘れ防止になります。
スケジュールを軽視すると遅刻のリスクが高まり、信頼を失う原因となりかねません。
⑤集合場所の確認
集合場所を事前に確認しておくことも重要です。初めて訪れる場所や大きなビルは迷いやすいため、当日焦る原因になりがちです。
Googleマップで経路や建物の外観、周辺の目印をチェックしましょう。可能であれば、同じ時間帯に移動を試しておくとさらに安心です。
早めに到着し、落ち着いた状態でスタートを迎えることが理想です。
⑥身だしなみの準備
会社見学では第一印象が非常に大切です。清潔感のある服装や整えられた髪型は、それだけで好印象を与えます。スーツやジャケットは前日に皺や汚れを確認し、必要であればクリーニングしてください。
男性はネクタイ、女性はメイクやアクセサリーの過不足にも注意が必要です。香水や柔軟剤の匂いが強すぎると逆効果になる場合もあるため、控えめを心がけてください。
⑦必要書類のチェック
会社見学では、履歴書やエントリーシートなどの提出を求められることがあります。必要な書類が揃っていないと準備不足と見られ、マイナス評価につながります。
案内メールや企業の指示を確認し、筆記用具や名刺が必要かもチェックしましょう。書類はクリアファイルにまとめ、折れや汚れを防ぐ工夫をしてください。前日までに準備を整えておくと安心です。
⑧持ち物のチェック
筆記用具やメモ帳、案内状、身分証明書は必須アイテムです。水分補給用のペットボトルやハンカチ、モバイルバッテリーなども必要に応じて用意しましょう。
不要な荷物は極力減らし、軽快に動ける状態で参加するのが望ましいです。持ち物リストを作成し、当日に再確認すると忘れ物防止に役立ちます。
⑨挨拶の練習
当日の挨拶は、その場の雰囲気を左右する重要なポイントです。明るくはきはきとした挨拶は、積極性や礼儀を印象づけます。声のトーンや表情も意識すると効果的です。
鏡を見ながら練習したり、友人に聞いてもらって改善すると自然な笑顔と声が作れます。自信を持てるまで繰り返し練習しておきましょう。
⑩自己紹介の練習
会社見学で求められることが多いのが自己紹介です。名前、大学、専攻、関心分野などを30秒~1分でまとめて話せるよう準備してください。
事前に台本を作り、声に出して練習するとスムーズです。志望動機を少し織り交ぜると熱意が伝わりやすくなります。本番で緊張しても自然に話せるまで繰り返し練習することが大切です。
会社見学の持ち物チェックリスト

会社見学では、事前の持ち物準備が印象を左右する大切な要素です。忘れ物をすると、必要な場面で対応できず評価が下がる可能性があります。
ここでは、就活生が最低限用意すべき持ち物を具体的に解説し、安心して見学に臨めるようチェックリストをまとめました。
- メモ帳
- 筆記用具
- スマートフォン
- 充電器
- A4サイズ対応のカバン
- 履歴書やエントリーシート
- 身分証明書や学生証
- 印鑑
- 証明写真
- ハンカチ
- 身だしなみ用品
①メモ帳
メモ帳は、説明会や見学中の情報を正確に記録するための必須アイテムです。担当者の話をただ聞くだけでは、後から重要な内容を忘れてしまうでしょう。
業務内容や社風の特徴、社員のコメントなどを要点ごとに記録することで、後日の企業研究や志望動機作成に役立ちます。
質問の際に「先ほどのお話について伺いたいのですが」と切り出せば印象も良くなります。
スマートフォンのメモ機能も便利ですが、操作中に「話を聞いていない」と誤解されることもあるため、紙のメモ帳を用意するほうが無難です。
②筆記用具
筆記用具は、メモ帳とセットで必要な基本アイテムです。黒ボールペンとシャープペンシルを1本ずつ用意すると便利です。
黒ボールペンは書類記入やサイン用、シャープペンシルは素早くメモを取る際に適しています。安価なペンはインクがかすれやすいため、書きやすいものを選んでください。
さらに予備を1本入れておけば、インク切れにも対応できます。小さな準備の積み重ねが「段取りが良い人」という評価につながります。
③スマートフォン
スマートフォンは連絡や情報確認に欠かせません。場所の確認や到着遅れの連絡、メール確認など、見学当日に活躍する場面は多いです。
見学中はマナーモードに設定し、着信音が鳴らないよう注意しましょう。質問やメモをスマートフォンに記録するのは便利ですが、画面操作中に集中していないと誤解される場合があります。
メインの記録はメモ帳に任せ、スマートフォンは補助的に使うと良いでしょう。バッテリー切れを避けるため、前日に充電を済ませておいてください。
④充電器
スマートフォンを多用する就活生にとって、充電器やモバイルバッテリーは必携品です。移動中に地図アプリや連絡ツールを利用すると電池消耗が早く、電源切れは大きなトラブルにつながります。
軽量のモバイルバッテリーなら持ち運びも楽です。ケーブルもセットにしておきましょう。こうした小さな準備が「先を読める人」として好印象を与える場合もあります。
⑤A4サイズ対応のカバン
A4サイズ対応のカバンは、企業資料や履歴書を折らずに持ち運ぶために必要です。ビジネスバッグやシンプルなトートバッグを選ぶと良いでしょう。
カジュアルなバッグやリュックは場に合わない印象を与える場合があります。仕切りがあるカバンは筆記用具やスマートフォンを整理しやすく、取り出しもスムーズです。
クリアファイルを一緒に入れると書類が汚れません。
⑥履歴書やエントリーシート
履歴書やエントリーシートは、会社見学時にも求められる場合があります。事前提出が不要な場合でも、持参しておくと安心です。誤字や脱字を確認し、印刷はA4サイズで統一すると良いでしょう。
複数部をクリアファイルに入れておくと慌てずに対応できます。履歴書は「準備力の象徴」と見られるため、丁寧な作成が誠実さのアピールになります。
⑦身分証明書や学生証
身分証明書や学生証は、受付や入館手続きで必要となることが多いです。セキュリティが厳しい企業では提示を求められるのが一般的です。
忘れてしまうと入館できない場合があるため、財布や定期入れに常に入れておくと安心です。有効期限の確認も忘れないでください。コピーを1枚持参すると、紛失時も対応がスムーズです。
⑧印鑑
印鑑は、書類記入や確認書に押印が必要なときに備えて持参すると良いです。特にシャチハタ以外の印鑑を用意すると安心です。印鑑ケースに入れておけば汚れや紛失も防げます。
不要だと思っていても、念のため小さな印鑑を1つ入れておくと安心です。
⑨証明写真
証明写真は、急な提出依頼に備えて予備を持っておくと便利です。提出が求められるケースは少ないですが、準備しておけば安心感があります。
3か月以内に撮影した清潔感のある写真を用意してください。クリアケースに入れれば折れや汚れも防げます。
⑩ハンカチ
ハンカチは、手を拭く、汗をぬぐうなど、見学中の身だしなみに欠かせません。特に夏や雨の日には必須です。無地や落ち着いた色合いのハンカチを選ぶと、ビジネスシーンにも合います。
薄手のものは持ち運びしやすく、かさばりません。
⑪身だしなみ用品
身だしなみ用品は、直前の最終チェックに役立ちます。鏡、ヘアブラシ、制汗シート、口臭ケア用品などを小さなポーチにまとめると便利です。
女性なら化粧直し用のパウダーやリップも持参すると安心でしょう。身だしなみを整えることで自信を持って臨めます。
会社見学前に押さえておきたいマナー

会社見学は、企業との初めての接点になることが多く、第一印象がその後の評価に直結します。見学前の準備やマナーを怠ると、面接や選考に悪影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、特に重要な基本マナーを確認し、事前に意識すべき行動ポイントを解説します。
- 遅刻をしない
- スマートフォンの電源を切る
- 服装・髪型を整える
- 事前連絡や確認の対応
- 周囲への礼儀や態度
①遅刻をしない
会社見学に遅れることは、社会人としての信頼を損なう大きな要因です。企業側が時間を割いて案内してくれるため、約束の時間を守れないと「基本的なマナーが欠けている」と判断されやすいでしょう。
遅刻を防ぐには、現地までの移動時間を事前に調べ、余裕を持って行動することが大切です。電車遅延など避けられないトラブルが起きた場合は、すぐに連絡を入れて誠意を伝えてください。
こうした準備と対応が、信頼感を高める行動につながります。
②スマートフォンの電源を切る
見学中にスマートフォンの音が鳴ると、集中力を欠くだけでなく、社会人としての配慮が足りないと見なされます。電源を完全に切るか、サイレントモードに設定しておくと安心です。
バイブレーション音も意外と目立つため注意が必要でしょう。さらに、スマートフォンを見ながら歩く行為も印象を悪くするので控えてください。
企業との接触時間は限られています。誠意のある態度が評価につながるでしょう。
③服装・髪型を整える
服装や髪型は第一印象を左右する重要な要素です。派手な色やカジュアルすぎる服装は避け、清潔感を意識してください。男性はシャツやジャケット、女性はシンプルで動きやすいスタイルがおすすめです。
髪型は顔が明るく見えるよう整えると良いでしょう。靴やバッグなどの小物も事前にメンテナンスをしておくと、より好印象を与えられます。
④事前連絡や確認の対応
見学の日時や集合場所、必要な持ち物は必ず確認しましょう。不明点があれば、早めに企業に問い合わせを行うことで責任感や積極性が伝わります。
メールで連絡をするときは、簡潔で丁寧な言葉遣いを心がけてください。体調不良などで参加が難しくなった場合も、当日ではなくできるだけ早く連絡を入れることがマナーです。
⑤周囲への礼儀や態度
会社見学では、担当者以外の社員や来客の目にも触れます。挨拶をきちんと行い、廊下での歩き方や声の大きさにも気を配りましょう。
明るく控えめな態度は礼儀正しさを印象付けます。同行する学生同士の会話もトーンを抑え、見学中は企業への敬意を示してください。
会社見学中のマナー

会社見学は、採用担当者だけでなく、現場社員の印象も左右する大切な機会です。見学中の立ち居振る舞いは、社会人としての素養や適性を測る評価基準になります。
ここでは、就活生が意識したい具体的なマナーや心構えをまとめました。
- 担当者への丁寧な挨拶
- 姿勢を正して話を聞く
- しっかりメモを取る
- 適度なアイコンタクトを保つ
- 質問のタイミング
- 周囲の社員への配慮
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①担当者への丁寧な挨拶
第一印象は面接と同様に、会社見学でも重要な評価要素です。特に担当者には、明るい笑顔と適度な声量で、はっきりと挨拶をすると好印象を与えます。
例えば「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます」と一言添えると丁寧です。緊張で声が小さくなるときは、深呼吸して気持ちを整えると良いでしょう。
担当者は学生の礼儀や誠実さを見ているため、過度にかしこまらず自然な笑顔を心掛けてください。
②姿勢を正して話を聞く
見学中の姿勢は、興味や熱意を伝える大きな要素です。背筋を伸ばし、軽く前傾してうなずきながら話を聞くと、真剣な態度が伝わります。
腕を組んだり椅子に寄りかかると、無意識にネガティブな印象を与えるかもしれません。社会人は細かな仕草から心構えを見抜くため、自然な姿勢を意識することが大切です。
自宅で鏡を使い、日頃の癖を確認しておくと安心でしょう。
③しっかりメモを取る
説明や案内の際に要点をメモすることは、積極性と誠実さを示す行動です。話をそのまま書き写すのではなく、要点を簡潔にまとめると振り返りにも役立ちます。
メモに夢中になると会話が途切れがちになるため、必要な箇所だけを素早く記録し、時折目線を上げると良いでしょう。事前にノートやペンを準備しておくと、落ち着いて対応できます。
④適度なアイコンタクトを保つ
話を聞く際のアイコンタクトは、信頼感を高める重要な要素です。相手の目を見続けると圧迫感を与えることがあるため、自然に視線を外しつつ要所でしっかり目を合わせると良いでしょう。
特に質問をするときは、相手の目を見て自信を持って話すと好印象です。日常生活でも家族や友人と意識的に視線を合わせる練習をしておくと自然に身につきます。
⑤質問のタイミング
質問をする際は、相手の話をさえぎらず、適切なタイミングを見極めることが大切です。説明の区切りや「質問はありますか」と促された時に聞くとスムーズでしょう。
質問が複数あるときは、メモに書き留めて最後にまとめて聞くと効率的です。焦って割り込むと礼儀を欠いた印象になるため、落ち着いて短く要点を伝えることを心掛けてください。
⑥周囲の社員への配慮
会社見学では、担当者以外の社員の目もあります。社内で出会う社員には軽く会釈し、邪魔にならない位置に立つなどの気配りが必要です。
職場は多くの人が業務を行う場なので、静かに行動し、声のトーンや歩き方にも注意しましょう。周囲への配慮が自然にできる人は、社会人としてのマナーが備わっていると判断されやすいでしょう。
会社見学後のマナー

会社見学は訪問中の態度だけでなく、終了後の対応も採用担当者の印象に影響します。退出時の言葉や感謝の伝え方、SNS投稿の注意点などを意識することで、誠実さやビジネスマナーを示せます。
ここでは、見学後の具体的なマナーと行動のポイントを解説します。
- 退出時の感謝の言葉
- 寄り道を避ける
- お礼メールを送る
- お礼状の送付
- 当日の学びの振り返り
- SNSなどへの不用意な投稿を避ける
①退出時の感謝の言葉
退出時には担当者への感謝をしっかりと伝えることが大切です。
見学の機会を得られたことや対応してくれた時間に対して、「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」といった一言を添えると良いでしょう。
緊張して言葉が短くなりがちですが、最後の瞬間こそ印象を決める場面です。目を見て丁寧に感謝を述べることで、人柄や礼儀正しさが伝わります。
②寄り道を避ける
会社を出た後は、そのまま帰宅するのが望ましい行動です。オフィス周辺で長く滞在すると、採用担当者や社員からの印象が悪くなる可能性があります。
どうしても立ち寄る必要がある場合は、場所を移動するか時間をずらしてください。訪問後の行動も見られていると意識することで、より良い印象を残せます。
③お礼メールを送る
会社見学の後は、当日または翌日中にお礼メールを送るのが基本です。感謝の気持ちに加え、印象に残った話題や学びを一言添えると、誠意がより伝わります。
件名や宛名の正確さ、誤字脱字のチェックも欠かせません。「お世話になりました」「お時間をいただき感謝しています」など、シンプルで丁寧な言葉が適しています。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
④お礼状の送付
メールに加えて手書きのお礼状を送ると、さらに丁寧な印象を与えられます。特に礼儀を重んじる業界では有効です。
お礼状では、訪問で印象に残った具体的なエピソードや学んだ内容に触れると好印象です。送付は1〜2日以内を目安にし、迅速な対応を心がけてください。
⑤当日の学びの振り返り
見学後は、得られた情報や気づきを振り返りメモにまとめると役立ちます。企業に感じた魅力や課題を整理することで、志望動機や面接対策の質が向上します。
振り返りを行うことで、質問の精度も高まり、次の企業訪問や面談に活かせるでしょう。
⑥SNSなどへの不用意な投稿を避ける
会社見学の内容や社内の様子をSNSに投稿するのは避けてください。企業情報や社員の姿が無断で公開されると、マナー違反や機密漏洩と判断される恐れがあります。
発信する情報は将来の信頼にも影響するため、一般的な感想だけにとどめ、具体的な内容は控えましょう。
会社見学でした方がいい質問例

会社見学では、ただ説明を受けるだけではなく、自分から積極的に質問することで企業への理解が深まり、面接にも有利に働くでしょう。
特に、仕事内容や社風、キャリアパスに関する具体的な質問は、入社後のミスマッチを防ぐ上で有効です。ここでは、就活生が参考にしやすい質問例を紹介します。
- 仕事内容に関する質問
- 会社の雰囲気や社風に関する質問
- キャリアパスや成長機会に関する質問
- 入社後の研修・サポート体制に関する質問
- 業界動向や競合との違いに関する質問
- 先輩社員のやりがいに関する質問
①仕事内容に関する質問
仕事内容を理解することは、志望動機やキャリアプランを明確にするための第一歩です。実際の業務や一日の流れを知ることで、働く姿がより具体的にイメージできるでしょう。
例えば「入社1年目はどのような業務を担当しますか」や「1日のスケジュールはどうなっていますか」といった質問が適しています。
こうした質問によって、企業が求めるスキルや働き方を把握し、自分が準備すべき点を明確にできます。また、興味を持って情報を集めている積極性をアピールできるでしょう。
②会社の雰囲気や社風に関する質問
職場の雰囲気や社風は、働きやすさやモチベーションに直結します。
「チーム間のコミュニケーションはどのような特徴がありますか」「社員の年齢層や職場の雰囲気を教えてください」などの質問は有効です。
社風を知ることで、自分がその環境に適応できるか判断でき、入社後のギャップを減らせます。こうした質問は「人や文化に関心がある」という誠意を示すきっかけにもなります。
③キャリアパスや成長機会に関する質問
将来の成長やキャリア形成は、多くの就活生が気にする点でしょう。
「どのようなキャリアパスを歩む社員が多いですか」「昇進や異動の仕組みはどうなっていますか」といった質問は、企業の育成方針や人事制度を知るのに役立ちます。
さらに、自分がどのような成長機会を得られるかを見極め、長期的なビジョンを描く材料になります。キャリア志向の高さを伝えることで、企業に前向きな印象を与えられるでしょう。
④入社後の研修・サポート体制に関する質問
入社後の研修やフォロー体制は、社会人として安心してスタートを切るために欠かせません。
「新入社員研修の内容や期間はどうなっていますか」「メンター制度やOJTはありますか」といった質問が効果的です。
研修体制を確認することで、どの程度サポートが受けられるかを把握でき、入社後の成長イメージがより明確になります。学ぶ姿勢を示すことは、企業に対して良い印象を与えるポイントです。
⑤業界動向や競合との違いに関する質問
業界全体の動きや競合との差別化について尋ねることで、企業研究の深さをアピールできます。
「業界の課題や今後の成長分野はどこですか」「競合と比べた強みは何でしょうか」といった質問は、志望動機の説得力を高める材料になります。
さらに、企業独自の戦略を知ることで、自分がどの部分に魅力を感じているのかを明確にできるでしょう。
⑥先輩社員のやりがいに関する質問
現場の声を知るために、先輩社員のやりがいについて質問するのは有効です。
「先輩社員が仕事で達成感を感じるのはどんな時ですか」「印象的なエピソードを教えてください」といった質問で、働くイメージがより具体的になります。
現場視点で理解しようとする姿勢は、担当者にも好印象を与えやすいでしょう。
会社見学でしない方がいい質問例

会社見学の場でどのような質問をするかは、企業への印象を大きく左右します。うっかり失礼な質問をすると、マナー不足や志望度の低さを疑われてしまうかもしれません。
ここでは、避けるべき質問例とその理由をわかりやすく解説します。
- 給与や待遇に関する直接的な質問
- 調べればわかる基本情報の質問
- 面接官や社員のプライベートな質問
- ネガティブな印象を与える質問
- 他社比較を前提とした質問
- 志望度の低さが伝わる質問
①給与や待遇に関する直接的な質問
給与や待遇は採用条件と直結するため、見学の段階で尋ねると金銭面しか興味がないと受け取られる恐れがあります。
企業はまずモチベーションや人柄を見たいと考えているため、待遇面の質問はタイミングを見極めることが大切でしょう。気になる場合は、公式サイトや求人情報で事前に確認するのが無難です。
②調べればわかる基本情報の質問
企業概要や沿革など、ホームページを見ればすぐにわかる内容を質問すると、下調べをしていないと感じられてしまいます。会社見学は現場の空気や働く人の声を直接聞く機会です。
公式情報よりも、現場でしか得られない実際の業務や社風について質問すると良いでしょう。
③面接官や社員のプライベートな質問
社員の年収や趣味、家庭環境などは個人のプライバシーに踏み込みすぎてしまい、相手を不快にさせる可能性があります。特に初対面では、ビジネス上の距離感を意識しておくことが重要です。
質問する際は、仕事の内容やキャリアに関する話題に限定するのが安心でしょう。
④ネガティブな印象を与える質問
「残業は多いですか?」や「離職率は高いですか?」といった聞き方はネガティブな印象を与えかねません。こうした情報は求人票や口コミでも把握できます。
どうしても聞きたい場合は、「どのような働き方が多いですか?」と前向きな言い回しに変えて質問すると良いでしょう。
⑤他社比較を前提とした質問
「他社では○○ですが、御社はどうですか?」という質問は比較している印象を与え、志望度の低さを疑われる可能性があります。
見学は企業独自の魅力を知る場であり、他社との差異を問うより、自分の興味や強みとどう結び付くかを意識した質問を用意すると誠実さが伝わります。
⑥志望度の低さが伝わる質問
「御社に入社しなくても他に選択肢がありますが…」のような発言は、やる気がない印象を与えてしまいます。
企業は前向きな態度を求めていますので、質問は入社意欲や理解を深める内容にすると良いでしょう。ポジティブな動機をもとに話すことで、評価につながるはずです。
会社見学を成功させるためのポイント

会社見学は、企業に好印象を与える貴重な場面です。限られた時間の中で自分の魅力を伝えるには、事前準備から当日の行動、終了後の対応まで計画的に動く必要があります。
以下のポイントを押さえることで、採用担当者に「一緒に働きたい」と思わせる印象を残せるでしょう。
- ポイント:事前準備を徹底する
- ポイント:第一印象を良くする
- ポイント:質問内容を整理する
- ポイント:姿勢や態度に注意する
- ポイント:お礼メールを欠かさない
- ポイント:学びを次に活かす
①ポイント:事前準備を徹底する
会社見学の成否は準備に左右されます。まずは企業のホームページや採用情報をよく確認し、業界動向や競合との違いを把握してください。
これにより、当日の質問が具体的で意義あるものとなり、積極性も伝わります。服装や持ち物の確認も忘れずに行いましょう。
スーツのシワや靴の汚れは印象を悪くするため、前日までに整えておくと安心です。さらに、会社までのアクセスや移動時間を下見しておくことで遅刻を防げます。
こうした準備が整うことで当日は自信を持って臨め、自然と好印象を与えられるでしょう。
②ポイント:第一印象を良くする
第一印象は数秒で決まるといわれます。会社見学の場でも、入室時の挨拶や姿勢、笑顔が相手の評価を大きく左右するでしょう。
明るくはっきりとした声で挨拶し、目線を合わせて背筋を伸ばすだけで誠実さが伝わります。服装や髪型などの身だしなみも整えることが大切です。
これらの点は一見些細ですが、採用担当者は社会人としての基本マナーを見ています。初対面の相手に安心感を与えることが、今後の選考にも良い影響を与えるはずです。
③ポイント:質問内容を整理する
質問は自分の関心や理解度を示す機会です。しかし、調べれば分かる内容や曖昧な質問は逆効果になることもあります。
事前に企業研究を行い、「働く上で気になる点」「現場のリアルな声を聞きたいこと」を整理してください。たとえば、社員のキャリアパスやプロジェクトの進め方など、具体的な質問は好印象を与えます。
質問のタイミングや言い回しにも配慮し、答えやすい形にすることが大切です。これにより、積極性と準備の丁寧さが伝わり、記憶にも残りやすくなるでしょう。
④ ポイント:姿勢や態度に注意する
見学中の態度は採用担当者がよく見ている部分です。椅子に座る姿勢や話を聞く際のうなずき、歩き方など、あらゆる動作が評価対象となり得ます。
スマートフォンを見たり無表情で聞く態度はマイナス要因になるため注意してください。反対に、しっかり目を見て話を聞き、要所でうなずくことで真剣さや礼儀が自然に伝わります。
言葉遣いも大切で、適度な敬語を使いながら自然な会話を心がけることが求められます。こうした態度の積み重ねが、社会人としての素養を示す鍵となるでしょう。
⑤ポイント:お礼メールを欠かさない
会社見学後は感謝の気持ちをお礼メールで必ず伝えましょう。見学翌日までに送るのが理想で、文章は簡潔かつ丁寧にまとめてください。
当日に得た学びや印象に残った点を具体的に記すと誠意が伝わります。たとえば「〇〇の説明が特に参考になりました」といった一文は効果的です。
お礼の一言で企業との関係が良好になり、選考でプラス評価になる場合もあります。社会人としての基本マナーを示すためにも、この手間は欠かさないようにしてください。
⑥ポイント:学びを次に活かす
会社見学は就職活動を有利に進めるための貴重な機会です。得られた情報や気づきを放置せず、次の行動に反映させることが重要です。
具体的には、面接対策や自己PRの改善、業界理解の深掘りなどに活かせるでしょう。当日の振る舞いや質問を振り返り、改善点をメモすることも効果的です。
こうした振り返りと改善を繰り返すことで就活全体の質が向上し、内定獲得の可能性も高まるはずです。
会社見学で意識すべき最終ポイント

会社見学は就活生が企業を理解するだけでなく、企業からも評価される重要な機会です。事前準備やマナー、当日の振る舞いは、採用担当者があなたの印象を判断する基準となります。
特に、第一印象やビジネスマナー、積極的な質問は評価を左右します。事前に企業研究や質問内容を整理し、必要な持ち物を準備することが成功の鍵です。
また、見学後のお礼メールや学びの振り返りは、誠実な姿勢を示す有効な手段です。これらのポイントを押さえることで、会社見学を通じた好印象の獲得と就活成功につながるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。