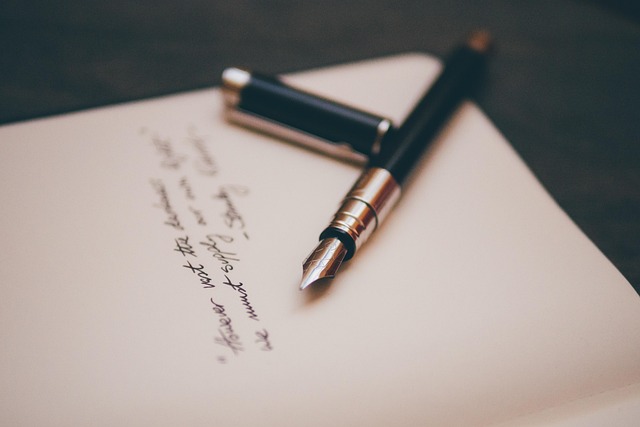「担当者様御中」は誤用?正しい敬称と使い分けを徹底解説
「担当者様 御中」という宛名表記を目にして、これって正しいのかな?と疑問に思った人も多いのではないでしょうか。
応募書類やビジネスメールを送る際、敬称の使い方ひとつで印象が左右されることもあります。特に「様」と「御中」を併用してよいのかどうかは、多くの人が迷いやすいポイントです。
そこで本記事では、「担当者様 御中」の正誤や二重敬称の注意点、さらに状況に応じた正しい宛名表記について詳しく解説していきます。
書類送付やメールで宛名の正しい表記を理解することで、安心してビジネスマナーを実践できるはずです。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
「担当者様御中」は正しい?

就活で応募書類やメールを送るときに「担当者様御中」と書いてしまう学生は実は多くいます。しかし結論から言うと、「担当者様御中」という表現は二重敬語になり、正しい使い方ではありません。
ここでは、なぜ誤りなのか、そして代わりにどう書けばよいのかを解説します。まず「御中」は会社や部署、組織などの宛名に使う敬称です。
一方「様」は個人に向ける敬称であり、この2つを同時に用いると意味が重なります。そのため「担当者様御中」は過剰表現とされ、ビジネス上では不適切と判断されるのです。
正しい表記の仕方としては、「採用ご担当者様」や「採用担当御中」が適切です。基本的には、担当者の名前がわからない場合には「御中」を、特定の個人に宛てる場合は「様」を使いましょう。
「担当者様御中」のような誤りは一見小さなことに思えても、社会人としての常識を疑われ、評価に影響しかねません。だからこそ、敬称の正しい使い分けを理解しておくことが大切です。
「担当者様 御中」の使い方

就活で企業へ応募書類を送るとき、多くの学生が悩むのが宛名の書き方です。特に「担当者様 御中」という表現は、一見ていねいに見えても、実際には誤用となる場合があります。
宛名は応募書類全体の印象を左右するため、正しい知識を持って臨むことが大切でしょう。ここでは、個人名が分からない場合、分かる場合、部署宛てに送る場合の使い方を整理します。
- 個人名が分からない場合の宛名表記
- 個人名が分かる場合の宛名表記
- 部署名宛てに送る場合の宛名表記
①個人名が分からない場合の宛名表記
応募書類の宛名には、「採用ご担当者様」と書くのが望ましいでしょう。受け取る側に安心感を与えられ、基本的なマナーを守っていることも伝わります。
また、部署名が分かっている場合には「人事部 採用ご担当者様」と書くとさらに適切です。部署名を明記することで、宛先がより明確になり、担当部署の中でスムーズに処理されやすくなります。
敬語を正しく理解できていない印象を与えるおそれがあるので、自己流で「担当者様 御中」や「採用担当様御中」としてしまわないよう注意しましょう。
宛名の正確さは細部への気配りを示すものであり、選考に直接関係はなくとも、信頼感の積み重ねにつながる大切な要素です。
②個人名が分かる場合の宛名表記
宛先の担当者名が判明している場合は、個人宛ての書き方を徹底することが求められます。「〇〇様 御中」と書いてしまう例も見られますが、これは誤りです。
「御中」は組織全体に用いる表現であり、個人名と併記すると不自然さが際立ちます。
正しい表記は「株式会社△△ 人事部 山田太郎様」となり、会社名や部署名には敬称を付けず、最後に個人名と「様」を組み合わせるのが基本です。
重要なのは、敬称の役割を理解して正しく使い分けることです。担当者が目にする最初の情報が宛名である以上、誤った敬称を使ってしまうと、知識不足など、マイナスの印象を与えかねません。
しかし、宛名を正しく書いているだけで、「誠実さ」や「理解力」を評価されることもあります。小さな部分ですが、この違いを押さえておくことで安心して書類を提出できるはずです。
③部署名宛てに送る場合の宛名表記
担当者の個人名が不明で、部署名だけ分かっている場合は「御中」を使うのが正しいやり方です。例えば「株式会社△△ 人事部御中」と記載すれば、部署全体に対して失礼のない形で届けられます。
このときに気を付けたいのは、部署名の後に「様」を重ねて書かないことです。組織には「御中」、個人には「様」と役割が異なり、それを混同すると不自然さが目立つでしょう。
郵送で送る場合は封筒の中央に大きく部署名と「御中」を書き、はっきりと見やすくすることも忘れてはいけません。こうすることで、配達や社内での書類仕分けも円滑に進みます。
また、部署名宛ては採用チーム全体で共有されることが多く、担当者が限定されていない場合には特に有効です。
宛名を正確に記載することは、自分の配慮や誠実さを表す行動であり、結果的に書類全体の信頼度を高めることにつながります。部署宛ての表記に迷ったら「御中」を選べば間違いないと言えるでしょう。
二重敬称の注意点

就活の応募書類やメールでは、敬語の誤りが採用担当者にマイナスの印象を与えやすいものです。その中でも特に多いのが二重敬称の間違いです。
ここでは「御中」と「様」の併用や、役職名への誤った敬称付与など、知らないと恥をかく落とし穴を整理して解説します。正しい使い方を理解すれば、文章全体の信頼感が高まるでしょう。
- 「御中」と「様」を併用する誤り
- 役職名に「様」を付ける誤り
- 「様」と「各位」を組み合わせる誤り
- 話し言葉で「御中」を使う誤り
①「御中」と「様」を併用する誤り
応募書類を送る際に「担当者様 御中」と書いてしまう人は少なくありません。しかしこれは二重敬称の典型で、正しい表現ではありません。
「御中」が組織や部署に対する敬称であり、「様」が個人に対する敬称であるため、両方を同時に使うと意味が重なってしまい、採用担当者からは敬語を正しく理解していないと思われかねません。
正しい書き方は、部署や会社宛なら「御中」、特定の個人宛なら「様」と明確に分けることです。
例えば「人事部御中」「採用ご担当者様」「田中様」といった表記が適切です。対象を曖昧にすると不自然な併用をしやすくなるので、宛名を書く前に「誰に向けて出すのか」を確認しましょう。
②役職名に「様」を付ける誤り
役職名の後に「様」を付けるケースもよく見られます。例えば「部長様」や「課長様」と書いてしまうと、役職そのものに敬称を付けていることになり、過剰表現です。
役職名にはもともと敬意が含まれているため、それにさらに「様」を重ねる必要はありません。誤用してしまうと、相手から「社会人としての基本が身についていない」と思われる危険性もあります。
正しい形式は「〇〇部 部長 田中様」といった形で、役職は肩書きとして明記し、個人名に「様」を付けます。もし個人名が分からない場合には「採用ご担当者様」と書けば問題ありません。
さらに、ビジネスの場では今後も役職名を目にする機会が多いため、学生のうちから正しい使い方を覚えると社会人になってからも役立ちます。
このルールを理解しておくと、相手に誠実な印象を与えられます。細部への気配りができるかどうかは信頼に直結するため、役職と敬称の使い方は早めに習得してください。
③「様」と「各位」を組み合わせる誤り
複数人宛に書く場合に「各位」という表現を使うのは一般的ですが、そこに「様」を付けて「各位様」とするのは誤りです。
「各位」自体に敬意が含まれているため、「社員各位様」など、「様」を加えると二重敬語になり、相手に違和感を与えてしまいます。
正しい表現は「関係者各位」「社員各位」のように「様」を付けずに使用することです。特定の人物に加えて全体へ呼びかけたいときは「田中様、関係者各位」と表記すれば適切です。
特に就活では、説明会やイベント案内のメールを送る際に複数人宛ての宛名を書く場面もあるでしょう。その際「各位様」と表記すると、相手には丁寧というより知識不足と映るかもしれません。
複数人宛の場合は「各位」のみで十分に敬意が伝わるので、迷わず使い分けられるようにしておくと安心です。
④話し言葉で「御中」を使う誤り
「御中」を口頭で使ってしまうのも注意すべきポイントです。「御中」は文書で団体や部署に敬意を示す表現であり、会話には向いていません。
例えば電話で「人事部御中の方にお願いします」と言うと、不自然な印象を与え、「敬語を正しく使えていない」と思われる可能性があります。
話し言葉では「人事部のご担当者様」「人事部の方」と表現するのが自然です。
就活生にとって、電話や面接での言葉遣いは第一印象を左右する重要な要素です。書面と会話で使う敬語を切り分ける習慣を身につけることが、信頼感を高める一歩になるでしょう。
特に面接や問い合わせの電話など一瞬の会話で評価が決まる場面では、「御中は文書でのみ使う」と意識しましょう。
敬語表現の正しい使い方

就活生はまだ社会人としての歴が浅く、誤った敬語を使ってしまう人も多くいます。
間違った敬語を使うと、相手を敬うつもりでも逆に失礼に見えることもあるでしょう。思い込みで書類を書かずに正しく理解して取り組むことで、応募書類の印象を高めることができます。
ここでは尊敬語・謙譲語・丁寧語の基本を整理し、誤用を防ぐ知識を紹介します。
- 尊敬語の基本
- 謙譲語の基本
- 丁寧語の基本
①尊敬語の基本
尊敬語は相手の行動を高めて表現することで、敬意を示します。例えば「言う」を「おっしゃる」、「行く」を「いらっしゃる」と言い換えるのが代表例です。
就活では企業の担当者や面接官に対して頻繁に使う場面が出てきます。重要なのは、尊敬語を使うときに必ず主語が相手であることです。
自分の行動に誤って尊敬語を使うと、不自然さが目立ち、相手に違和感を与えてしまいます。また、尊敬語は単語の置き換えだけでなく、文章全体の調子を整える役割も持ちます。
例えば「ご覧になる」「召し上がる」といった言い回しを適切に使えると、応募書類や面接での会話が自然に聞こえるでしょう。
逆に使い方を誤ると、相手から「敬語が使いこなせていない」と判断されかねません。正しい尊敬語を身につけておけば、企業に対して礼儀正しい印象を与えられ、やり取りが円滑に進みやすくなります。
②謙譲語の基本
謙譲語は自分の行動を控えめに表現し、相手を立てるために用います。例えば「言う」を「申し上げる」、「行く」を「伺う」と言い換えるのが典型です。
たとえば応募書類や面接で「ご説明申し上げます」と表現すると、謙虚で誠実な姿勢を伝えることができるでしょう。
さらに、謙譲語は相手への配慮を示す重要な道具でもあります。相手の行動に謙譲語を当ててしまうと誤用となり、信頼を損なう可能性があるため気を付けましょう。
また、「担当者様にお伺いになられる」といった二重敬語にも注意が必要です。
謙譲語を正しく使えると、社会人としての基礎力を評価されやすくなります。間違いなく伝えるためには、自分の行動をどう表現するかを常に意識してください。
③丁寧語の基本
丁寧語は「です・ます」や「ございます」などで表され、文章全体をやわらかく整える役割を持ちます。
応募書類では本文を最後まで丁寧語で統一することが基本であり、読み手に対して礼儀を欠かさない印象を与えるでしょう。ただし、宛名部分に丁寧語を用いるのは誤りです。
また、丁寧語を使うときには、文章のリズムも意識することが大切です。同じ語尾を繰り返すと単調になりやすいため、「お願いいたします」「よろしくお願い申し上げます」など表現を工夫しましょう。
さらに、書き出しで「お世話になっております」と添えるだけで、相手への配慮が自然に伝わります。丁寧語は単に形式的なものではなく、言葉づかい全体を整える効果を持っています。
応募書類やメールを読む相手が安心して受け取れるよう、最後まで一定のトーンを維持してください。そうすることで、文章に安定感と信頼性が備わるでしょう。
敬称の使い分けで間違いやすいパターン

就活で応募書類を送る際に、宛名や敬称を正しく書けていないと、企業に失礼な印象を与えるおそれがあります。特に「担当者様 御中」のように誤った敬称を使ってしまうケースは多いでしょう。
ここでは、就活生がよく間違える敬称の使い方を具体的に解説し、正しい形を理解できるよう整理しました。
- 「係」「行」を消さずに送付する誤り
- 宛名の部署名や個人名が不明確な場合の誤り
- コピペで発生しやすい敬称ミス
- 複数の担当者宛てに敬称を誤用するケース
- 会社名と部署名の組み合わせで敬称を誤るケース
①「係」「行」を消さずに送付する誤り
宛名に「人事部御中」と記載すべきところを、「人事部行」や「採用係行」のまま送ってしまう学生は少なくありません。
これは企業から見ると「相手に届ける意志がない」と受け取られる重大なマナー違反です。なぜなら「行」は自分が送付する際の仮の表現であり、正式な宛名ではないからです。
正しい対応は、封筒を出す段階で必ず「行」や「係」を二重線で消し、「御中」または「様」に書き換えることです。この一手間を怠ると、不注意な印象を与える可能性があります。
敬称の正しさは合否を直接左右するわけではありませんが、誤りがあると減点対象になり得るため注意が必要です。
②宛名の部署名や個人名が不明確な場合の誤り
応募書類を送る際、相手の部署名や担当者名がわからない場合は特に注意が必要です。誤って「担当者様御中」と二重敬称を記載すると、マナーを知らないと判断されかねません。
原則として、部署名がわかっていれば「人事部御中」と書き、個人名がわかっている場合は「〇〇様」とするのが正解です。どうしても不明なときは「採用ご担当者様」と書けば問題ないでしょう。
重要なのは、誰が受け取っても失礼にならない形を整えることです。企業HPや求人票を確認すれば、必要な宛名情報が見つかることも多いので、必ず確認してください。
加えて、可能であれば電話やメールで問い合わせを行うことも有効です。積極的に正しい宛名を調べる姿勢は、丁寧で誠実な印象を与えます。
情報収集を怠らない姿勢は、社会人としての基礎力を示すアピールポイントにもつながるでしょう。
③コピペで発生しやすい敬称ミス
メールや応募書類の作成でありがちな失敗が、コピペによる敬称の誤りです。
前に送った文章を流用した結果、本来「御中」とすべきところが「様」のまま残っていたり、「様御中」と二重敬称になるケースがよく見られます。
これでは相手に注意不足を示しかねません。送信前に宛名を声に出して確認したり、テンプレートを利用する場合でも宛名だけ最後に手動で入力すればミスを減らせます。
さらに、文章全体を見直す際には敬称部分を赤ペンでチェックするなど、自分なりの確認ルールを設けるとより安心です。
こうした確認の積み重ねは時間を取られるように思えるかもしれませんが、結果的に信頼感を与える行為につながります。社会人として信頼を築く第一歩は、こうした小さな配慮から始まるのです。
④複数の担当者宛てに敬称を誤用するケース
複数の担当者に書類を送るとき、敬称の扱いを誤る学生は多いです。例えば「〇〇部 △△様 御中」と書くと、個人と組織の敬称を同時に使う二重敬称になってしまいます。
正しいのは、個人名がわかる場合はそれぞれの名前を「様」で書き並べることです。個人名が不明な場合は「〇〇部御中」とまとめるのが適切です。状況ごとに敬称の使い分けを意識しましょう。
形式的なルールに思えても、社会人にとっては基本のマナーとして判断される部分です。複数人宛てだからこそ、誰にとっても失礼のない形を意識してください。
また、就活においては採用担当がチームで対応していることも多く、1人だけを名指しするよりも部署全体を宛先とした方が自然な場合もあります。
選考に悪影響を与えないよう、相手の体制を踏まえて宛名を選ぶ視点も欠かせません。
⑤会社名と部署名の組み合わせで敬称を誤るケース
会社名と部署名を組み合わせた宛名で誤用する例もよくあります。「株式会社〇〇御中 人事部御中」と書くと「御中」が重なり、不自然な表現になります。
正しい形は「株式会社〇〇 人事部御中」と、敬称を1回だけ使うことです。敬称は最終的な宛先にのみ付けるものだと理解してください。
また、会社名に「様」をつける間違いにも注意が必要です。「株式会社〇〇様」と記載すると、一見丁寧に見えても企業名に「様」をつけるのは誤りとされています。
敬称はあくまで部署や個人に対してつけるものですので、相手に違和感を与えないためにも正しく整理して書く必要があります。
応募書類は学生を評価する最初の材料です。誤って使えば、基本的なマナーを学んでいないと見られる可能性があります。反対に正しく使えば、細部まで配慮できる誠実さを示せるでしょう。
応募書類送付時の注意点

就職活動における応募書類の送付は、第一印象を左右する大切な場面です。内容が整っていても送付方法に不備があると評価を下げる可能性があります。
ここでは、就活生が見落としやすい注意点を具体的に紹介します。
- 添え状を同封する
- 書類をクリアファイルに入れる
- 封筒のサイズや切手を確認する
- 送付前に最終確認を行う
①添え状を同封する
応募書類を送る際は、必ず添え状を同封してください。理由は、書類を受け取る担当者に「誰から・何のために」送られたかを明確に伝えられるからです。
添え状がない場合、いきなり書類だけが届くことになり、雑な印象を与えかねません。添え状には宛名や日付、送付する書類の一覧を丁寧に記し、最後に署名や連絡先を入れておくと安心です。
さらに、自分の志望意欲を簡潔に添えると、ただの事務的な書類ではなく「前向きに応募している」というメッセージを伝えることもできます。
形式や書き方が整っているかどうかは、細かいところまで気を配れる人物かを見極める判断材料になります。
就活生は履歴書やエントリーシートに力を注ぎがちですが、添え状の有無や内容次第で印象が大きく変わることを忘れないでください。
②書類をクリアファイルに入れる
応募書類を送る際は、必ず透明のクリアファイルに入れるようにしましょう。これは郵送中に折れや汚れを防ぐためだけでなく、受け取った側がスムーズに中身を確認できるという利点もあります。
もしそのまま封筒に入れてしまうと、到着時に角が折れていたり、封筒内でしわが寄っていたりする可能性が高まります。そのような状態ではせっかく丁寧に作成した書類の価値が下がってしまいます。
クリアファイルは無色透明で薄手のものを選び、余計なデザインや色付きのタイプは避けた方が無難です。
さらに、ファイルの表面に付箋で「応募書類在中」と書いて添えるなど、受け取る側への配慮を一歩加えるとより印象が良くなります。
小さな工夫に見えても、誠実さや気配りを伝える強力な手段となるでしょう。
③封筒のサイズや切手を確認する
応募書類を送付する際に見落としがちなのが、封筒のサイズと切手の金額です。封筒が小さいと、履歴書やエントリーシートを折らなければならず、清潔感を損ねてしまいます。
角形2号サイズの封筒を使えば、A4の書類を折らずに収められるため、もっとも適しています。また、切手の料金不足は大きなトラブルにつながりかねません。
返送されてしまうと、応募期限を守れず選考に参加できなくなる危険性すらあるのです。料金は重さによって変わるため、必ず郵便局の窓口で確認してから貼り付けましょう。
さらに、封筒の表面には「応募書類在中」と赤字で明記しておくと、受け取る担当者にも親切です。こうした細やかな準備は社会人としての基本的な姿勢を示すものであり、就職活動の成功に直結します。
④送付前に最終確認を行う
応募書類を封入して切手を貼ったあとも、送付前の最終確認を必ず徹底してください。記入漏れや誤字脱字、署名や押印の有無はもちろん、封筒の宛名や敬称の誤りも見逃せません。
特に「担当者様 御中」といった二重敬称は多くの就活生がやってしまう典型的な間違いです。
正しいのは「〇〇会社 人事部 採用ご担当者様」と書く方法であり、この点を誤ると基本的な敬語すら理解していないと判断されかねません。
また、添え状の内容に誤りがないか、送付書類の数が揃っているかも1枚ずつ照らし合わせて確認すると安心です。加えて、封筒の表裏に誤字や記載漏れがないかも再度見直すことをおすすめします。
最終確認を丁寧に行うことで、自信を持って送付でき、企業側に対しても誠実で責任感のある姿勢を示せるでしょう。
正しい敬称表記に理解しよう!

「担当者様 御中」という表現は、ビジネス文書において誤用とされる二重敬称です。
正しいマナーとしては、相手が個人の場合は「担当者様」、部署や会社宛ての場合は「御中」と使い分ける必要があります。
誤って併用すると、相手に違和感を与え信頼性を損なう可能性があるため注意が必要です。さらに、尊敬語・謙譲語・丁寧語の基本を押さえ、状況に応じて適切に選択することが重要です。
特に応募書類などフォーマルな場面では、宛名の敬称や封筒の扱い方を丁寧に確認することで、相手に好印象を与えることができます。
したがって、敬称の正しい使い方を理解し、場面に応じた適切な表現を選ぶことが、信頼関係を築く第一歩となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。