団体職員の平均年収はいくら?仕事内容やボーナス事情も徹底解説
公務員に近い安定性や社会貢献性が魅力の職種ですが、団体の種類や役職によって収入には大きな差があります。さらに、ボーナスや昇給制度、福利厚生なども勤務先によって特徴が異なります。
そこで本記事では、仕事内容や種類別の違い、メリット・デメリットを交えながら詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
団体職員とは?

団体職員とは、非営利の団体や組織に所属し、社会や地域に貢献することを目的として働く人のことです。
団体職員は、公益性の高い活動を行う非営利組織(NPO・財団法人・社団法人など)に所属し、社会課題の解決に取り組む職業です。主な目的は利益の追求ではなく、公共サービスの提供や地域の発展への貢献にあります。
たとえば、環境保全に取り組むNPO法人、地域経済を支援する商工会、福祉サービスを担う社会福祉法人などが代表的です。
団体職員の魅力は、「安定性」と「社会貢献性」の両立にあるでしょう。公務員に近い待遇が期待できる一方で、現場では人々の生活に寄り添いながら働く機会も多いです。
ただし、団体によって仕事内容や給与水準が大きく異なるため、入職前に「どの団体で働くのか」を理解しておくことが大切です。
団体職員の平均年収はいくら?

団体職員の年収を正確に知るには、公的な統計データと実際の職員口コミ情報の両方を参考にすることが重要です。団体の規模や性質によって給与は大きく異なり、
NPOや学校法人、JAなど、それぞれの特徴を理解することがキャリア選択のポイントになります。ここでは、団体職員の年収を3つの観点から詳しく解説します。
- 団体職員の平均年収データ
- 年齢別・勤続年数別の年収相場
- 団体の種類別(NPO・JA・学校法人など)の年収比較
①団体職員の平均年収データ
団体職員全体を対象とした公的な年収統計は存在しませんが、非営利組織(NPOや公益法人など)で働く職員の給与水準から一定の目安を得ることができます。
一般的に、NPOや中小規模の非営利団体では年収が300万円〜450万円前後、規模の大きい法人や公的色の強い団体では400万円〜550万円程度が中心です。
また、民間企業のような業績連動型の給与体系ではなく、年功序列に近い安定した給与体系が多いのも特徴です。
団体によっては、ボーナスや諸手当が支給されるケースもありますが、予算規模によって変動する点には注意が必要です。
②年齢別・勤続年数別の年収相場
団体職員の年収は、年齢や勤続年数によって緩やかに上昇する傾向があります。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、正社員の平均月給は約30万円前後で、賞与を含めると年収はおおむね400万〜500万円程度となります。
団体職員もこれに近い水準で、20代では300万〜400万円台、30代で450万円前後、40代以降で500万円を超えるケースも見られます。
ただし、昇給幅は限定的で、勤続による安定はあるものの、民間企業ほど大きな年収上昇は期待しにくい傾向にあります。
③団体の種類別(NPO・JA・学校法人など)の年収比較
団体の種類によって、給与水準には大きな違いがあります。
- NPO法人
予算規模が小さい団体が多く、年収は250万円〜400万円前後にとどまることが一般的です。社会貢献を目的とするため、給与よりも「意義」や「やりがい」を重視する人に向いています。 - 学校法人・教育関連団体
安定した財源を持つ学校法人や教育関連団体では、年収400万〜600万円程度と比較的高い傾向にあります。特に私立大学などでは、福利厚生も手厚く、長期的に働きやすい環境が整っています。 - JA(農業協同組合)
金融や共済、営農支援など多様な事業を行っており、職種によって年収に差があります。一般職員で400万円台、管理職クラスで600万円以上に達する場合もあります。地域性も強く、地方では安定した雇用先として人気です。
このように、団体職員の年収は「どの団体に属するか」「どんな業務を担当するか」によって大きく変わります。
給与の高さだけでなく、安定性や社会貢献度といった要素も含めて、自分に合った団体を選ぶことが大切です。
引用:
団体職員の仕事内容

団体職員の仕事内容は、所属する団体の目的や活動内容によって大きく異なります。NPO法人や医療法人、学校法人など、多種多様な団体が存在し、それぞれが社会や地域に対して独自の役割を果たしています。
ここでは、代表的な団体ごとに仕事内容の特徴とやりがいを詳しく解説します。
- NPO法人の仕事内容
- 社会福祉法人の仕事内容
- 医療法人の仕事内容
- 農業協同組合(JA)の仕事内容
- 商工会・商工会議所の仕事内容
- 学校法人・教育関連団体の仕事内容
- 財団法人・社団法人の仕事内容
①NPO法人の仕事内容
NPO法人の団体職員は、社会的課題の解決や地域の活性化を目的に活動しています。主な業務は、イベントの企画運営、ボランティアの募集・管理、広報活動、寄付金の受付や報告書の作成などです。
事務作業と現場活動の両方を担当することが多く、組織運営の幅広いスキルが求められます。
特に中小規模のNPOでは、職員一人が複数の業務を兼任するケースが多く、柔軟な対応力が必要です。
数字で成果が見えづらい分、地域の変化や人々の笑顔が大きなモチベーションになります。課題解決に向けて粘り強く行動できる人にとって、NPO法人の仕事は非常にやりがいのある環境といえるでしょう。
②社会福祉法人の仕事内容
社会福祉法人の職員は、高齢者や障がい者、子どもなどの生活を支える福祉事業に携わります。介護施設や保育園、障がい者支援センターなどでの運営業務や事務処理、行政との連携業務などが中心です。
利用者の日常を支援する現場職から、組織全体を管理する総務職まで、幅広い役割があります。
この仕事では、思いやりと同時に、正確な対応力や調整力も重要です。
現場での人との関わりが多く、感謝の言葉を直接受け取れる機会も多いです。人の生活や成長を支えたいという気持ちが強い人にとって、社会福祉法人で働くことは非常に意義のある選択になるでしょう。
③医療法人の仕事内容
医療法人の職員は、病院やクリニックなど医療機関の円滑な運営を支える役割を担います。受付や会計といった医療事務業務に加え、職員の勤怠管理、経理、総務、人事、経営企画などの事務全般を担当します。
医師や看護師といった専門職を支える存在として、医療現場を裏から支援することが主な使命です。
医療の専門知識を持たない場合でも、正確な書類作成や患者さんへの丁寧な対応が求められます。
命に関わる現場を支えているという責任感と緊張感がある反面、医療チームの一員として貢献できる充実感も大きいです。安定性のある職場で、人の健康に関わる仕事をしたい人に向いています。
④農業協同組合(JA)の仕事内容
JAの職員は、地域の農業と経済を支える重要な存在です。主な業務には、農家への営農指導、農産物の販売・流通支援、共済(保険)や金融業務(貯金・ローン)、購買業務などがあります。
地域農業を支えると同時に、組合員との信頼関係を築くことが不可欠です。
また、近年は農業の高齢化や後継者不足に伴い、地域活性化や新しい農業ビジネスの支援に携わるケースも増えています。
JAの職員は、地元に密着しながら地域全体を支える仕事であり、地元貢献を重視する就活生に特に人気があります。地域の人と深く関わりながら働きたい人にぴったりの職場です。
⑤商工会・商工会議所の仕事内容
商工会・商工会議所の職員は、地域の中小企業や商店を支援し、地域経済の活性化に貢献します。
具体的には、経営相談や補助金申請の支援、講習会の運営、会員企業への情報提供、イベント企画などを行います。行政や企業との連携も多く、地域の経済ネットワークの中心的な役割を担います。
この仕事では、経済の動向に関する知識や、企業との信頼関係を築く力が求められます。自分の提案やサポートが地域産業の発展につながるため、達成感を得やすい職種です。
地域経済を支える仕事に興味がある人や、地元企業の成長をサポートしたい人におすすめです。
⑥学校法人・教育関連団体の仕事内容
学校法人や教育関連団体の職員は、大学・高校・専門学校などの教育機関の運営を支える業務を行います。
入試広報、学生支援、経理、人事、国際交流、施設管理など幅広い部署があり、教育現場の裏側を支える立場です。教育の質を保ちながら、学生が安心して学べる環境づくりを行うのが大きな使命です。
また、学校行事やオープンキャンパスの運営など、学生や教職員と関わる機会も多く、コミュニケーション力が重視されます。
教育を通して社会に貢献したい、学生の成長をサポートしたいという気持ちを持つ人にとって、やりがいを感じやすい仕事といえるでしょう。
⑦財団法人・社団法人の仕事内容
財団法人・社団法人の職員は、特定の目的をもって設立された非営利団体で活動します。文化・芸術の振興、科学研究、国際交流、地域振興、環境保全など、団体ごとに専門分野が異なります。
業務内容は、助成金の管理、調査研究の補助、広報活動、イベント運営、行政への報告業務など多岐にわたります。
こうした仕事では、社会的意義の高いプロジェクトに関われる機会が多く、自分の専門分野を生かして社会貢献ができます。
表に立つよりも裏で支える業務が多いですが、長期的に社会を動かす仕組みづくりに関わることができるため、知的好奇心が強い人や企画が得意な人に向いているでしょう。
団体職員に求められる能力

団体職員として働くには、安定した業務遂行力だけでなく、組織の目的を理解し、周囲と協力しながら成果を出す総合的な力が求められます。
ここでは、団体職員として活躍するために必要な主なスキルと心構えを6つの観点から詳しく解説します。
- コミュニケーション能力
- 調整力・協調性
- PCスキル・事務処理能力
- 企画力・プレゼンテーション力
- 社会貢献意識・倫理観
- 組織運営に関する理解と責任感
①コミュニケーション能力
団体職員にとって、コミュニケーション能力は最も重要なスキルの一つです。
行政や地域住民、企業、ボランティアなど、多様な関係者と協働しながら業務を進めるため、相手の立場を理解したうえで円滑に意思疎通を図る力が必要になります。
特に、非営利組織では一人ひとりの意見や想いを尊重する姿勢が大切です。相手の話を丁寧に聞き、自分の考えをわかりやすく伝えることで、信頼関係が築けます。
コミュニケーションは単なる会話ではなく、組織全体を円滑に動かすための基盤です。日頃から人との関わりを大切にする姿勢を持ちましょう。
②調整力・協調性
団体職員の仕事では、さまざまな立場の人々をつなぐ「調整役」としての能力が欠かせません。行政、地域団体、企業、住民など、多くの関係者の意見をまとめながら一つの方向に導く場面が多くあります。
意見の対立が起きたときも、冷静に状況を分析し、双方の立場を理解して折り合いをつける柔軟さが求められます。
また、組織の内部でも部署間の協力が不可欠であり、個人プレーよりもチームワークが重視されます。協調性を持って動ける人ほど信頼され、組織にとって欠かせない存在になれるでしょう。
③PCスキル・事務処理能力
団体職員の業務では、文書作成やデータ管理、報告書の作成など、事務作業の比重が大きい傾向にあります。そのため、WordやExcel、PowerPointなどの基本的なPCスキルは必須です。
最近では、クラウドサービスやオンライン会議ツールを使う場面も増えており、デジタルリテラシーの高さが仕事の効率を左右します。
また、正確さとスピードの両立も大切です。ミスのない事務処理は信頼につながり、結果的に業務全体の品質向上にも寄与します。
PCスキルは一度身につければどの団体でも役立つため、早めに習得しておくと安心です。
④企画力・プレゼンテーション力
団体職員には、社会課題の解決に向けた新しい企画を立案する力も求められます。地域イベントの運営や広報活動、助成金申請など、成果を上げるためには自ら考え行動する姿勢が欠かせません。
また、企画を実行するには、上司や外部関係者に対して内容をわかりやすく説明するプレゼンテーション力も必要です。数字や資料だけでなく、目的や背景をしっかり伝えることで共感を得られます。
創意工夫をもって提案し、チームを動かすことができる人は、団体の成長に大きく貢献できるでしょう。
⑤社会貢献意識・倫理観
団体職員は、営利を目的としない組織の一員として、社会や地域の課題に誠実に向き合う姿勢が求められます。利益よりも公共性を優先するため、常に公平で透明な判断を心がけることが大切です。
また、補助金や寄付金を扱う業務も多く、誠実さと高い倫理観が不可欠です。小さな不注意や不正が信頼を損なうことにもつながるため、ルールや法令を正しく理解し、責任を持って行動する必要があります。
社会の一員として、自分の仕事が誰のためになるのかを意識できる人こそ、団体職員にふさわしいと言えるでしょう。
⑥組織運営に関する理解と責任感
団体職員は、組織全体を支える立場としての責任を常に意識しなければなりません。経理、総務、人事、企画など、多岐にわたる業務を通して組織を安定的に運営することが求められます。
そのためには、組織の方針や財務状況を理解し、自分の行動が全体に与える影響を考える姿勢が必要です。
責任感を持って業務に取り組むことで、信頼を得るだけでなく、将来的にリーダーとして活躍するチャンスも広がります。
団体の運営は個人の努力の積み重ねによって成り立つため、自分の役割を意識しながら一つひとつの仕事を丁寧に遂行することが大切です。
団体職員として働くメリット

団体職員の仕事には、公務員に近い安定性と、社会の役に立つやりがいの両方があります。就活生の中でも「安定して長く働きたい」「人の役に立つ仕事がしたい」と考える人に人気の職種です。
ここでは、団体職員として働く代表的なメリットを6つの観点から詳しく見ていきましょう。
- 収入と雇用の安定性
- 社会貢献性の高さ
- ワークライフバランスの取りやすさ
- 精神的な安心感
- 福利厚生や待遇の充実
- 長期的に働ける職場環境
①収入と雇用の安定性
団体職員の多くは、公的な資金や会員費、補助金などで運営されており、経営が比較的安定しています。そのため、景気の影響を受けにくく、長期的に安定した収入が得られる点が大きな魅力です。
給与水準は民間企業よりやや低い場合もありますが、ボーナスや各種手当が充実しており、総合的に見ると安心感があります。
また、倒産や大量解雇といったリスクが少ないことも特徴です。定期的な昇給や勤続年数に応じた待遇改善もあり、長く勤めるほど収入が安定していく傾向があります。
安定を重視する就活生にとって、団体職員は安心してキャリアを築ける選択肢と言えるでしょう。
②社会貢献性の高さ
団体職員の仕事は、営利目的ではなく社会的意義のある活動を支えることにあります。
地域福祉、環境保全、教育支援、国際協力など、分野ごとに目的は異なりますが、いずれも社会の課題解決に直結しています。
自分の仕事が誰かの役に立ち、地域や社会をより良くすることにつながる実感を得やすいのが特徴です。
「人のために働きたい」「社会を支える立場になりたい」という想いを持つ人にとって、団体職員は理想的な職業です。
成果が数字では見えにくい反面、活動を通じて人々の笑顔や感謝の言葉を直接感じられることが、働く上での大きなモチベーションとなるでしょう。
③ワークライフバランスの取りやすさ
団体職員は、比較的残業が少なく休日もしっかり取れる傾向があります。業務が年間スケジュールに沿って進むことが多いため、仕事とプライベートの両立がしやすい職場が多いです。
また、産休・育休制度や時短勤務制度なども整備されており、家庭や育児と両立しながら働くことが可能です。特に女性職員が多い団体では、ライフイベントに柔軟に対応できる環境が整っています。
自分のペースで無理なく働きたい人や、生活の充実を大切にしたい人にぴったりの働き方です。
④精神的な安心感
団体職員の仕事は、競争やノルマが比較的少なく、安定した環境で落ち着いて働けるのが特徴です。
業務の性質上、チームで協力しながら進めることが多いため、個人に過度なプレッシャーがかかることはあまりありません。
また、社会的に意義のある活動を行っているため、自分の仕事に誇りを持ちやすく、精神的な充実感を得やすいです。
もちろん、責任感や柔軟な対応力は求められますが、短期的な成果よりも長期的な信頼関係を重視する環境のため、ストレスを感じにくい職場と言えるでしょう。
⑤福利厚生や待遇の充実
団体職員は、公的機関に近い性質を持つため、福利厚生が手厚い傾向にあります。社会保険や退職金制度はもちろん、住宅手当や扶養手当、資格取得支援などを用意している団体もあります。
休暇制度も充実しており、有給休暇の取得率が高い点も魅力の一つです。
さらに、研修制度やキャリアアップ支援が整っている場合もあり、安定した環境でスキルを磨き続けることが可能です。
安心して働ける基盤が整っているため、長く勤めたい人にとって非常に魅力的な職場環境です。
⑥長期的に働ける職場環境
団体職員は、離職率が比較的低く、長く働ける環境が整っています。安定した給与体系や充実した福利厚生、無理のない働き方ができる点が、その要因です。
さらに、定年まで働く職員も多く、キャリアを通じて地域や社会に貢献し続けられる職場です。
また、年功序列や勤続年数を重視する文化が残っている団体も多く、着実に経験を積めば管理職やリーダー職を目指すことも可能です。
短期的な成果よりも、継続的な努力と信頼を大切にする職場だからこそ、腰を据えて働きたい人に向いているでしょう。
団体職員として働くデメリット

団体職員の仕事は安定性が高く、社会的意義のある職業として人気がありますが、一方で注意しておくべきデメリットも存在します。
就職を目指す前に、メリットだけでなく現実的な課題も理解しておくことが大切です。ここでは、団体職員として働くうえで知っておきたい代表的なデメリットを6つの観点から解説します。
- 年収の伸びにくさ
- 転職やキャリアアップの難しさ
- 採用倍率の高さ・狭き門
- 組織間で待遇格差が大きい
- 地域や人間関係のしがらみ
- 業務の変化や柔軟性の低さ
①年収の伸びにくさ
団体職員の年収は、全体的に安定している一方で、民間企業のように大幅に昇給するケースは多くありません。
給与は年功序列や規定に基づく昇給制度で決まることが多く、成果を出してもすぐに給与へ反映されにくい傾向があります。
また、予算は補助金や会費などの外部資金で成り立つため、経営状況に応じて昇給やボーナスが抑えられることもあります。
生活に困るほどではありませんが、収入アップを目指す人には物足りなく感じるかもしれません。安定を取るか、成長を取るか、自分の価値観を見極めることが重要です。
②転職やキャリアアップの難しさ
団体職員は専門性が高く、組織の性質も独特なため、転職やキャリアチェンジが難しい場合があります。
特に非営利組織特有の運営体制や文化に慣れていると、民間企業のスピード感や成果主義の環境に馴染みにくいことがあります。
また、同業他団体への転職も少なく、キャリアアップを目指すなら、管理職への昇進や専門スキルの向上が中心です。
安定志向の人には向いていますが、スピード感のある成長を求める人にとっては物足りなさを感じる可能性があります。自分のキャリアプランを明確にしておくことが大切です。
③採用倍率の高さ・狭き門
団体職員は人気職種の一つであり、採用倍率が高いことでも知られています。
特に地方自治体関連や公的団体は「安定していて福利厚生が良い」という理由から応募者が多く、競争率が非常に高くなる傾向があります。
求人が出るタイミングも限られており、募集枠が少ないため、希望する団体に応募できるチャンスが少ないことも特徴です。
採用試験や面接では、団体の理念や活動への理解度が問われるため、十分な事前準備が欠かせません。就職を目指す場合は、早めに情報収集を始め、複数の団体を視野に入れると良いでしょう。
④組織間で待遇格差が大きい
団体職員と一口に言っても、その待遇や給与水準は所属する団体によって大きく異なります。
公的な性格が強い団体では安定した収入が得られる一方、小規模なNPOや地域団体では予算が限られており、年収が低い場合もあります。
また、同じ職種でも、都市部と地方では給与差が出ることも珍しくありません。福利厚生の内容にも差があり、ボーナスが支給されない団体も存在します。
団体職員を目指す際は、「団体の規模」「財源」「活動内容」を確認し、自分に合った環境を慎重に選ぶことが大切です。
⑤地域や人間関係のしがらみ
団体職員の仕事は地域密着型であることが多く、地元の人々や関係団体との関係性が密接です。
そのため、人間関係のバランスに気を使う場面が多く、時には地域の慣習や上下関係に合わせて行動する必要もあります。
特に小さな地域団体では、関係者同士の距離が近く、プライベートと仕事の線引きが難しい場合もあります。人との関わりが得意でない人にとっては、精神的な負担を感じることもあるでしょう。
ただし、信頼関係を築ければ、地域の中で大きな存在感を発揮できるやりがいもあります。
⑥業務の変化や柔軟性の低さ
団体職員の仕事は、規定やルールに基づいて進めることが多く、自由な発想やスピード感のある意思決定が難しい場合があります。
特に公的性格の強い団体では、上層部の承認を経なければ新しい取り組みを始められないこともあります。
そのため、自分のアイデアをすぐに形にしたい人や、変化のある環境を好む人にとっては物足りなさを感じるかもしれません。
安定して働ける反面、業務内容が固定化されやすく、刺激が少ないのも事実です。柔軟な発想を求める場合は、創意工夫を活かせるNPO法人などを選ぶと良いでしょう。
団体職員に向いている人の特徴

団体職員は、安定性と社会貢献性を兼ね備えた仕事です。しかし、どんな人にも向いているわけではなく、性格や価値観によって適性が大きく変わります。
ここでは、団体職員に向いている人の特徴を6つの観点から詳しく紹介します。自分の性格と照らし合わせながら、適職かどうかを判断してみてください。
- 安定志向で長く働きたい人
- 人の役に立つ仕事に魅力を感じる人
- チームワークを重視する人
- 地道な業務をコツコツ進められる人
- 社会的な使命感や公共心が強い人
- 変化よりも安定を求めるタイプの人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①安定志向で長く働きたい人
団体職員の仕事は、景気に左右されにくく、長く安定して働けるのが特徴です。そのため、「一つの職場で腰を据えて働きたい」「転職を繰り返さずにキャリアを築きたい」と考える人に向いています。
勤続年数に応じて昇給や昇格があるため、着実にキャリアを積むことができるでしょう。特にライフイベント(結婚・出産など)を見据えて安定を重視する人にとって、安心して働ける環境です。
変化の少ない職場でコツコツと成長したい人には理想的な職種です。
②人の役に立つ仕事に魅力を感じる人
団体職員の業務は、社会や地域の課題を解決することを目的としています。そのため、「人のために働きたい」「誰かの役に立つ仕事がしたい」と考える人に最適です。
日々の業務が直接的に誰かの生活を支えることにつながるため、感謝の言葉をもらう機会も多く、仕事へのやりがいを感じやすいです。
利益を追求するよりも、人の幸せや社会の発展を支えることに価値を感じられる人が向いているでしょう。
③チームワークを重視する人
団体職員の仕事は、個人プレーよりもチームで進める場面が多いです。部署内はもちろん、行政・地域団体・企業など、さまざまな関係者と協力しながらプロジェクトを進行します。
そのため、他人の意見を尊重し、協調性を持って行動できる人が向いています。
また、相手の立場に立って考える姿勢も重要です。自分の意見を押し通すよりも、全体の調和を重視できる人が評価されやすい環境です。
協力して成果を出すことにやりがいを感じる人にとって、団体職員は魅力的な職種です。
④地道な業務をコツコツ進められる人
団体職員の仕事は、華やかな成果よりも地道な努力の積み重ねが中心です。データ整理、報告書作成、予算調整など、日々の細かな業務を丁寧にこなすことが求められます。
一つひとつの仕事を正確にこなす忍耐力があり、焦らずじっくり取り組める人に向いています。結果がすぐに見えなくても、組織の信頼を支える重要な役割を担うことになります。
表に出るタイプではなく、縁の下の力持ちとして支えることに喜びを感じる人にぴったりの仕事です。
⑤社会的な使命感や公共心が強い人
団体職員は、社会のために行動することが使命であり、公共性の高い仕事です。そのため、社会的な責任を意識し、誠実に業務に取り組める人が求められます。
個人の利益よりも、組織や地域、そして社会全体の利益を優先できる姿勢が大切です。また、倫理観を持ち、正しい判断を下せる人は信頼されやすく、組織の中でも重宝されます。
社会課題の解決に強い関心を持ち、自分の行動が誰かの支えになることに喜びを感じる人に向いているでしょう。
⑥変化よりも安定を求めるタイプの人
団体職員の仕事は、民間企業のような急激な変化やスピード感のある環境ではありません。その分、安定して同じ業務を継続できることが魅力です。
変化の少ない環境を好み、決まったルールの中でコツコツ働くことに安心感を持てる人に向いています。また、慎重に物事を進めたいタイプの人にとっては、自分のペースを保ちながら働ける職場といえます。
新しい挑戦よりも、確実な成果を積み重ねることを重視する人におすすめです。
団体職員になるには?必要な資格・就職ルートを解説
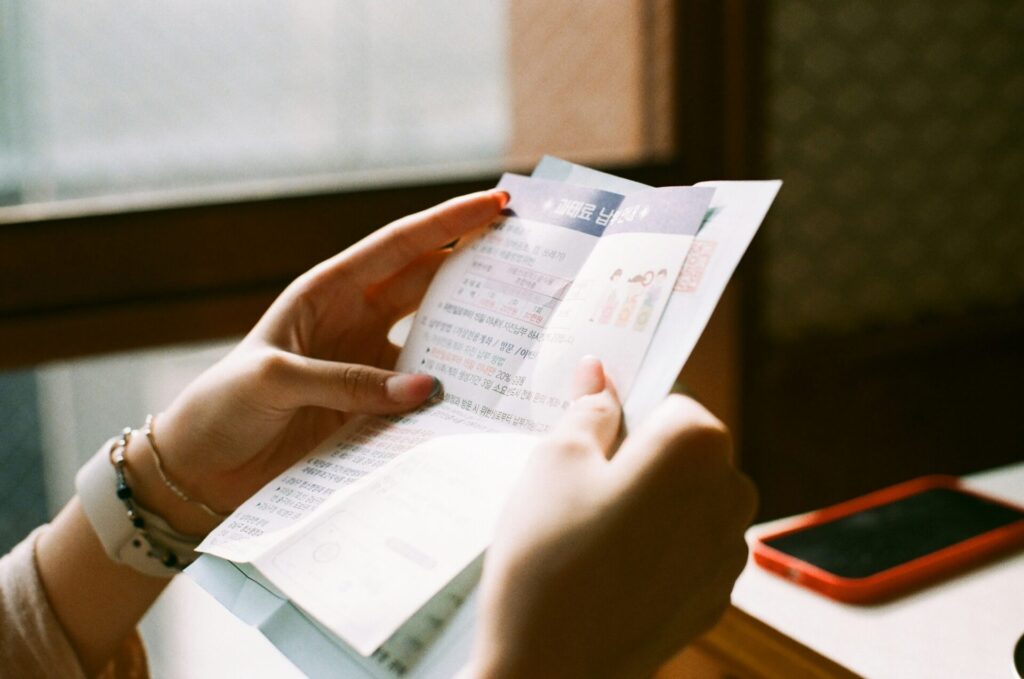
団体職員を目指すには、一般企業とは異なる就職ルートや準備が必要です。特に、団体の理念や活動内容を理解し、社会的意義への共感を示すことが採用のカギとなります。
ここでは、団体職員になるための具体的なステップを7つの観点から詳しく解説します。
- 団体職員の採用試験を受ける
- 大学や学部で関連分野を学ぶ
- インターンやボランティアに参加する
- 団体の理念や活動内容を研究する
- 履歴書・エントリーシートを準備する
- 面接で志望動機を明確に伝える
- 必要な資格を取得してアピールする
①団体職員の採用試験を受ける
団体職員になるための最も一般的なルートは、各団体が実施する採用試験を受けることです。公的性格の強い団体では、公務員試験に近い筆記試験や面接が課される場合もあります。
試験内容は、一般常識、時事問題、作文、適性検査などが中心で、団体によって出題傾向が異なります。
応募時期は年度ごとに限られるため、大学3年生のうちに採用スケジュールを確認しておくと安心です。
倍率が高い団体も多いので、早めに準備を始め、面接練習や過去問題の対策を行うことが成功のポイントです。
②大学や学部で関連分野を学ぶ
団体職員として働くうえで、大学での学びは大きな武器になります。法律・経済・社会学・教育学などの学部は、団体の運営や地域活動に直結する知識を身につけやすい分野です。
また、環境、国際協力、福祉など、団体の活動テーマに関連する学問を専攻しておくと、就職後の業務にも活かせます。学業の中で社会問題への関心を深め、課題解決の視点を持つことが重要です。
自分がどんな分野に貢献したいかを意識しながら学びを進めましょう。
③インターンやボランティアに参加する
団体職員を目指すなら、インターンやボランティアへの参加は非常に有効です。実際の現場を経験することで、団体の活動内容や雰囲気を理解でき、自分に合っているかを確認できます。
また、採用面接では「現場を体験した上での志望動機」を問われることが多いため、実務経験を積むことは大きなアピールポイントになります。
特に長期ボランティアやプロジェクト型の活動は評価されやすく、自己成長にもつながります。積極的に社会貢献活動に参加することで、将来のキャリア形成にも役立つでしょう。
④団体の理念や活動内容を研究する
団体職員を目指す際には、その団体の理念や目的を深く理解することが欠かせません。組織によって取り組むテーマや対象が異なるため、「自分がなぜその団体を志望するのか」を明確にする必要があります。
公式サイトや活動報告書、SNSなどを通じて情報を集め、団体のミッションやビジョンを把握しましょう。また、説明会やイベントに参加することで、職員の働き方や価値観を直接知ることもできます。
理念への共感を具体的に伝えられることが、選考突破の大きなカギになります。
⑤履歴書・エントリーシートを準備する
団体職員の採用では、履歴書やエントリーシート(ES)を通じて「社会貢献への意欲」や「組織とのマッチ度」を見られます。
一般企業とは異なり、利益ではなく公共性を重視するため、志望動機や自己PRで“どんな社会を実現したいか”を明確に伝えることが重要です。
また、文章の構成力や誠実さも評価対象となるため、丁寧な言葉遣いと具体的なエピソードを意識しましょう。
提出前には必ず第三者にチェックしてもらい、伝わりやすく整った内容に仕上げることをおすすめします。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
⑥面接で志望動機を明確に伝える
面接では、「なぜその団体で働きたいのか」「どのように貢献できるのか」を具体的に伝えることが重要です。抽象的な言葉ではなく、自分の経験をもとにしたエピソードを交えると説得力が増します。
また、団体によっては個人面接だけでなく、グループディスカッションやプレゼン形式の面接を行うこともあります。
社会問題に関する意見を求められることも多いため、ニュースや時事テーマへの理解も欠かせません。面接では熱意と共感をバランスよく表現しましょう。
⑦必要な資格を取得してアピールする
団体職員になるために必須の資格はありませんが、取得しておくと有利に働く資格はいくつかあります。代表的なものに、社会福祉士、行政書士、日商簿記、TOEICなどがあります。
これらの資格は、団体の業務に直接関係する知識やスキルを証明できるため、選考時の強みになります。特に国際協力団体や教育系団体では、語学力や国際感覚が評価されやすいです。
資格は単なる肩書きではなく、「自分がどう社会に貢献できるか」を具体的に示す手段として活用しましょう。
団体職員として安定と社会貢献を両立したいあなたへ

団体職員は、安定した収入を得ながら社会に貢献できる魅力的な職業です。非営利団体や協同組合、学校法人など多様な組織で働ける点が特徴で、仕事内容は地域支援から教育、福祉まで幅広く存在します。
平均年収は300万〜600万円程度と安定しており、ワークライフバランスを保ちやすい環境が整っているのも強みです。
一方で、年収が伸びにくい傾向や転職の難しさなど、慎重なキャリア設計が求められる側面もあります。
社会貢献意識や協調性を持ち、地道に仕事へ取り組める人には非常に向いている職種です。就職を目指す場合は、団体の理念を理解し、ボランティアやインターンを通して実績を積むことが重要です。
団体職員という働き方は、「安定」と「やりがい」の両方を求める就活生にとって、長期的に充実したキャリアを築ける選択肢といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














