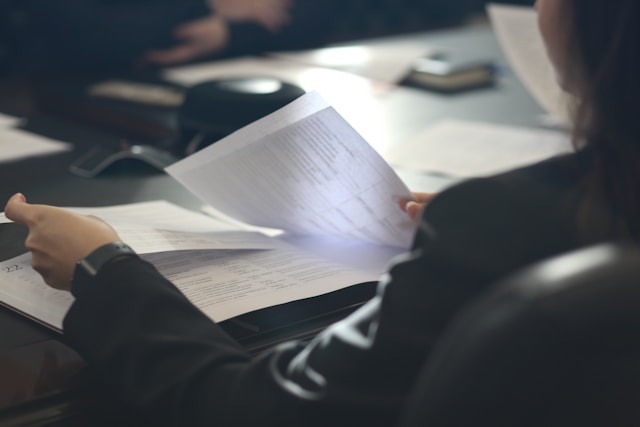「お大事に」は敬語?正しい使い方と目上の人への伝え方を解説
「体調を崩した人に対して就活の場で『お大事に』と伝えるのは正しいのかな?」と迷ったことはありませんか。
日常的によく使う言葉ですが、実は敬語表現としての位置づけや、目上の人への使い方には注意が必要です。
ビジネスメールや上司・取引先に対して使う場合、より丁寧な言い換えや場面に応じた表現を選ぶことで、思いやりの伝わり方が大きく変わります。
この記事では、「お大事に」の意味や敬語としての正しさ、シーン別の言い換え例、さらに言われた時の返し方まで例文付きで詳しく解説します。
正しい言葉選びを身につけて、ビジネスでも好印象を与えられるようにしましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
「お大事に」の意味とは?

「お大事に」という言葉は、病気やけがをしたときに「早く元気になってほしい」という気持ちを込めて使う言葉ですが、就職活動やビジネスの場面で使う場合は、少し注意が必要です。
例えば、面接官や企業担当者に対して気遣う場合、「お大事にしてください」という言葉は丁寧に感じられます。しかし、ビジネスシーンや目上の人に使う際、カジュアルすぎると捉えられてしまうことも。
そうした場合には、「どうぞご自愛ください」や「ご無理なさらないでください」といったより丁寧な言い換えを選ぶと良いでしょう。意味を正しく理解したうえで、正しく言葉を選ぶ姿勢が重要になります。
相手との関係性や場面に応じて言葉を選ぶことで、より自然に誠意や気遣いが伝わります。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
「お大事に」の一般的な使い方

就職活動中は、体調を崩した面接官や企業担当者に気遣いの言葉をかける場面があるかもしれません。そのときによく使われるのが「お大事に」という表現です。
ここでは、「お大事に」がどんな状況でどのように使われるのかを理解し、自然に使いこなすためのポイントを紹介します。
- 体調を気遣う場面で日常的に使う
- 怪我や病気の相手に対して労わりを伝える
①体調を気遣う場面で日常的に使う
「お大事に」は、風邪や疲労などで体調を崩している相手に向けて使う言葉です。別れ際のあいさつやメッセージの締めくくりとして使われることが多く、相手の健康を気遣う丁寧な印象を与えます。
柔らかい印象を与えられ、相手の立場に寄り添った言葉としてビジネスシーンでも好まれています。特に就活では、面接官やOB訪問の相手に対して使うと、気配りが伝わり印象が良くなるでしょう。
たとえば「体調を崩されていると伺いました。どうぞお大事になさってください」と伝えると、自然な敬意と心遣いが伝わります。
また、「お大事にしてください」だとやや命令口調に聞こえてしまうことがあります。「お大事になさってください」と伝えるとより上品に伝えられるでしょう。
「お大事に」はシンプルな言葉ですが、使い方一つで印象が大きく変わります。状況や相手に合わせて自然に使い分けることで、就活生としての思いやりや信頼感、マナーの有無が伝わるでしょう。
②怪我や病気の相手に対して労わりを伝える
けがや病気の相手に「お大事に」と伝える際は、形式的なあいさつではなく、相手を思いやる気持ちを込めることが大切です。就職活動中は、インターンや面接などさまざまな人と接する機会があります。
その際、丁寧な言葉づかいで相手を気遣えるかどうかが印象を左右するのです。たとえば「お怪我をされたと伺いました。どうぞお大事になさってください」と伝えると、丁寧でやさしい印象を与えます。
また、「お大事に」は一時的な体調不良だけでなく、長く健康を願う場合にも適した言葉です。「ご無理なさらずご自愛ください」と言い換えることで、より丁寧で落ち着いた印象を与えることができます。
相手の立場や関係性を意識して表現を選ぶことが、信頼関係を築く上で欠かせません。相手の状況を思いやりながら、自然な気遣いを伝える表現を身につけておくこと。
それが社会人としての基本的なマナーであり、就活でも好印象を与えるポイントになるでしょう。
「お大事に」の基本の敬語表現
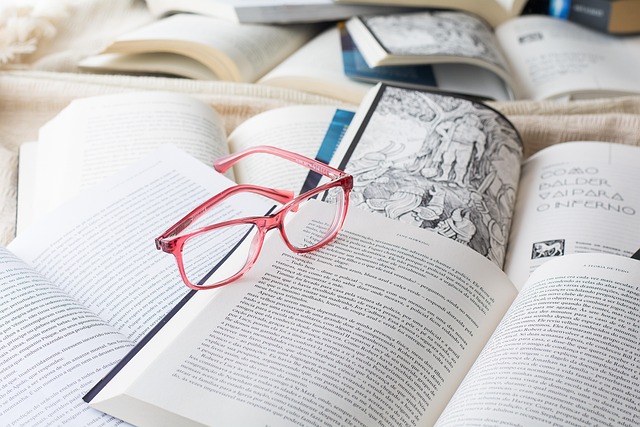
「お大事に」という言葉は、日常生活でもよく使われますが、敬語としての正しい使い方を理解しておかないと、場面によっては軽い印象を与えてしまうこともあります。
就職活動中に企業の担当者や面接官に伝える際は、丁寧で落ち着いた言葉遣いを意識することが大切でしょう。基本的に「お大事に」は尊敬語や謙譲語ではなく、丁寧語にあたります。
そのため、ビジネスの場ではやや口語的に聞こえる場合があるのです。たとえば、面接官が「風邪をひいていて」と話したときに「お大事になさってください」と伝えると、より丁寧で自然な印象になります。
さらに、文章やメールでは「どうぞご自愛ください」や「ご無理なさらないように」と書くと好印象です。
相手の立場や場面に合わせて言葉を選ぶことが、社会人としての心配りを感じさせるポイントになります。
「お大事に」の言い換え表現

就活中は、面接官や担当者など目上の人に体調を気遣う場面があります。そのとき「お大事に」だけでなく、より丁寧な表現を知っておくと印象が一段と良くなるでしょう。
ここでは「お大事に」の言い換えとして使える敬語表現を紹介し、それぞれの使い方や注意点を詳しく解説します。
- ご自愛ください
- お身体をお労りください
- 養生なさってください
- おいといください
- ご無理なさらないでください
- お身体にお気をつけください
- 一日も早いご回復をお祈り申し上げます
①ご自愛ください
「ご自愛ください」は、「ご自身の身体を大切にしてください」という意味を持つ丁寧な言葉です。季節の変わり目や繁忙期など、相手の健康を気遣う挨拶としてよく使われます。
たとえば、就活メールの締めくくりに「季節の変わり目ですので、ご自愛ください」と添えると、自然で優しい印象になるでしょう。相手を気遣う姿勢が伝わり、礼儀正しさを感じさせる表現です。
ただし、相手がすでに体調を崩している場合には、この言葉はやや不適切。
「自分で体調管理をしてください」という意味に取られるおそれがあるため、「ご無理なさらないでください」や「一日も早いご回復をお祈り申し上げます」といった別の表現を使うほうが丁寧です。
相手の状況を正しく判断し、最もふさわしい言葉を選ぶことで、社会人としての配慮と誠実さを伝えられるでしょう。
②お身体をお労りください
「お身体をお労りください」は、相手の疲れや体調を気遣う丁寧な表現です。「労る(いたわる)」という言葉には、感謝と優しさの気持ちが込められています。
たとえば、「お忙しい中ご対応いただき、誠にありがとうございます。どうぞお身体をお労りください」と伝えると、相手を思いやる誠実な印象を与えられるでしょう。
この表現は、フォーマルな印象が強いため、ビジネスや就活のような改まった場面で使うのが最適です。友人や親しい相手との会話では、少し堅く感じられることもあるでしょう。
その場合は「ゆっくり休んでくださいね」と言い換えると自然です。TPOに応じた使い分けができると、言葉の印象がぐっと良くなります。
③養生なさってください
「養生なさってください」は、病気やけがをした相手に対して「しっかり休んで回復してください」という意味で使われます。少し古風な表現ではありますが、非常に丁寧で上品な響きを持つ言葉です。
「お風邪とのこと、どうぞご無理なさらず養生なさってください」と伝えると、相手に思いやりと誠実さが伝わります。ただし、日常会話で使うとやや堅く聞こえることも。
そのため、メールやお礼状などの文章で使うと自然です。また、「養生」という言葉には「休養しながら体を整える」という意味も含まれており、長期の療養が必要な相手にも適しています。
現代的な表現に言い換えるなら、「ゆっくりお休みください」や「お体を休めてください」などが柔らかく聞こえるでしょう。
④おいといください
「おいといください」は、「体を大切にしてください」という意味を持つ非常に丁寧な表現です。日常会話で使われることは少ないものの、手紙や公式文書などで用いると上品で敬意のある印象になります。
「どうぞおいといくださいませ」とすれば、より丁寧で柔らかな言い方になるのです。一方で、この言葉は古風な響きを持つため、若い世代同士の会話ではやや堅苦しく感じられることもあります。
使う相手や場面を慎重に選ぶことが大切です。目上の人やフォーマルなシーン、たとえばお礼状や弔事の際などに使用すると、相手への敬意と心遣いが自然に伝わります。
⑤ご無理なさらないでください
「ご無理なさらないでください」は、相手の体調や多忙さを気遣うときに幅広く使える表現です。
「お忙しい中ありがとうございます。どうかご無理なさらないでください」と伝えると、優しさと誠実さが感じられます。
この言葉は、相手が体調を崩している場合にも、元気な状態でも使える汎用性の高い表現です。相手を気遣う姿勢を自然に示せるため、ビジネス・就活・日常のいずれの場面でも活用できます。
また、「どうか」をつけることで柔らかく丁寧な印象になるのです。相手の状況を考えながら心を込めて伝えると、温かい気持ちがしっかり届くでしょう。
⑥お身体にお気をつけください
「お身体にお気をつけください」は、健康を気遣う最も一般的で使いやすい表現です。面接後のお礼メールや取引後の文末に添えると、礼儀正しく誠実な印象を与えられます。
「季節の変わり目ですので、お身体にお気をつけください」といった使い方が自然で、就活メールにもぴったりです。
ただし、「お気をつけてください」とだけ言うと口語的で少し軽く聞こえるため、ビジネスや就職活動などのフォーマルな文面では「お身体にお気をつけください」と丁寧に言い換えることをおすすめします。
また、この表現は目上の人やあまり親しくない相手にも失礼がないため、汎用性の高い気遣い表現として覚えておくと便利です。
⑦一日も早いご回復をお祈り申し上げます
「一日も早いご回復をお祈り申し上げます」は、体調を崩した相手への最も丁寧な言葉の一つです。フォーマルな手紙やメールで使われることが多く、相手の健康を真摯に気遣う表現。
「お加減が優れないと伺いました。一日も早いご回復をお祈り申し上げます」と伝えると、真心と敬意のこもった印象になります。
この言葉は、就活中に企業担当者や面接官が体調を崩したときなど、改まったやり取りに非常に適しているでしょう。文章に使う際は、短いながらも誠実なトーンを意識することが大切です。
また、口頭で伝える場合は「早く良くなられますように」など、少し柔らかく言い換えると自然に聞こえます。
相手の立場や距離感に応じて使い分けることで、思いやりと礼儀の両方が感じられる言葉になるのです。
「お大事に」を使う際のポイント

「お大事に」という言葉は、相手の健康や体調を気遣う温かい表現です。しかし、使う場面や相手との関係によって印象が変わることもあるでしょう。
ここでは、就活生が社会人として好印象を与えるために意識したい「お大事に」の使い方のポイントを紹介します。
- 相手の体調や立場に合わせた言葉選びを意識する
- ビジネスシーンでは敬語の使い分けが重要
- メールでは直接的すぎない表現を選ぶ
- 病状や状況を詮索するような言葉は避ける
- 相手への思いやりを込めて自然に伝える
- タイミングを見て適切な場面で伝える
- 短くても誠実さが伝わる言い方を心がける
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①相手の体調や立場に合わせた言葉選びを意識する
「お大事に」は便利で汎用的な表現ですが、誰に対しても同じように使うのは適切ではありません。
友人や同僚など対等な立場の人なら問題ありませんが、上司や面接官のような目上の人に対しては「お大事になさってください」など丁寧に言い換える必要があります。相手の立場を尊重することが重要です。
また、相手の体調の程度がわからない場合は、「どうぞご無理なさらないでください」など、控えめでやさしい表現を選ぶと安心です。
さらに、相手の状況に応じて言葉の重みを調整する意識も大切。親しい間柄では、明るく励ますようなトーンでも構いませんが、ビジネスでは落ち着いた言葉遣いが求められます。
相手の気持ちに寄り添いながら自然に伝えることで、短い言葉でも思いやりが感じられる印象を与えることができるでしょう。
②ビジネスシーンでは敬語の使い分けが重要
就活や職場で「お大事に」を使うときは、相手との関係性やシーンに応じて言葉を選ぶことが欠かせません。
丁寧な印象は与えられますが、ややカジュアルに捉えられる場合もあります。その際は「ご自愛ください」や「お体を大切になさってください」と伝えると、より敬意を込めた表現が可能です。
一方で、同僚や社内の人に使う場合は、「お大事になさってください」でも十分丁寧です。言葉のトーンや話し方にも気を配ると、形式的ではなく誠実さのある対応になります。
特に就活生は、敬語の使い方一つで印象が大きく変わるのです。相手との距離感を考えたうえで、自然で思いやりのある敬語を選ぶことが、社会人としての信頼を得る第一歩。
③メールでは直接的すぎない表現を選ぶ
ビジネスメールで「お大事に」を使う際は、言葉のトーンと文脈に注意が必要です。口頭での「お大事に」は温かみがありますが、メールでそのまま書くと少し軽い印象になることもあります。
そのため、「どうぞご自愛ください」や「ご無理なさらないようにお過ごしください」といった柔らかく丁寧な表現を選ぶとよいでしょう。また、文章の流れの中に自然に組み込むことがポイントです。
たとえば、「季節の変わり目ですので、どうぞご自愛ください」や「お忙しい時期かと思いますが、ご無理なさらないでください」といった書き方にすると、思いやりのある印象になります。
さらに、件名や挨拶の中で相手の状況を少し気遣う言葉を入れると、より丁寧な印象を与えられるのです。
就活メールでもこのような気遣いができると、社会人としてのマナーや人柄を感じさせる効果があるでしょう。
④病状や状況を詮索するような言葉は避ける
相手を気遣う気持ちは大切ですが、体調の詳細を尋ねるような表現は避けるべきです。「どのくらい悪いのですか?」や「何の病気なんですか?」などの質問は、相手のプライバシーを侵害する恐れがあります。
特にビジネスの場では、親しみよりも節度を重視する姿勢が求められるでしょう。
そのため、「お体にお気をつけください」や「ご無理をなさらないようにしてください」といった控えめで温かい言葉を使うのが最適です。相手が多忙な時期であれば、「お忙しいところ申し訳ありません。
ご体調にはくれぐれもお気をつけください」と添えると、礼儀正しく思いやりも伝わります。
また、相手の立場を考慮し、必要以上に長い言葉や重い表現を避けることで、相手が負担に感じない自然な気遣いを示すことができるのです。
⑤相手への思いやりを込めて自然に伝える
「お大事に」は、形式的に言うだけでは心に響きません。大切なのは、相手を思いやる気持ちをしっかり込めて伝えることです。
たとえば、面接や打ち合わせの中で相手の体調を気遣う場面では、「それは大変でしたね。どうぞお大事になさってください」と一言添えるだけで、印象がぐっと柔らかくなります。
また、言葉の内容と同じくらい、声のトーンや表情も重要です。やさしい口調や落ち着いた笑顔を添えることで、相手に安心感を与えられます。
逆に、冷たい言い方や無表情で伝えると、せっかくの気遣いも伝わりにくくなるのです。さらに、相手の話に共感を示す姿勢を見せると、より心がこもった対応になります。
こうした細やかな配慮が、短い一言でも信頼や好印象を生む秘訣です。
⑥タイミングを見て適切な場面で伝える
「お大事に」は、伝えるタイミング次第で印象が大きく変わります。相手が体調不良を伝えた直後や、会話やメールの締めくくりに自然な流れで使うと、心のこもった言葉になるでしょう。
一方で、関係のない話題の途中で唐突に伝えると、不自然に感じられる場合があります。
また、相手の体調が深刻な場合や長期の休養を取っている場合には、「一日も早いご回復をお祈りしております」や「どうぞご無理をなさらずお過ごしください」といった、
より丁寧で重みのある言葉を選ぶことが適切です。状況に応じて言葉の強さを調整することが、相手への敬意と配慮を示す鍵になります。
相手の反応を観察しながら、自然なタイミングで伝えることが、真の思いやりを感じさせるポイントです。
⑦短くても誠実さが伝わる言い方を心がける
「お大事に」は短くても十分に誠意を伝えられる表現です。重要なのは、言葉の長さではなく気持ちの込め方。
面接やビジネスメールで「お体にお気をつけください」と一言添えるだけでも、相手への思いやりは伝わります。
また、同じ表現を繰り返すと形式的に感じられるため、「ご自愛ください」「ご無理なさらないでください」など場面に合わせて変化をつけることが効果的です。
状況や相手の性格に合わせた言葉選びを心がけることで、より自然で温かみのある印象を与えられます。さらに、声のトーンや書き方にも誠実さを感じさせる工夫を加えるとよいでしょう。
短いながらも気持ちのこもった言葉は、人間関係を円滑にし、社会人としての信頼感を高めてくれます。
「お大事に」と言われた時の適切な返し方

「お大事に」と声をかけられたとき、どのように返すのが正しいのか迷う人も多いでしょう。相手との関係性や状況に応じて言葉を選ぶことで、より自然で丁寧な印象を与えられるのです。
ここでは、感謝を伝える基本の返し方から、親しい人・ビジネスの場面まで、シーン別に紹介します。
- 「ありがとうございます」と感謝を伝える
- 状況に応じて「お気遣いありがとうございます」と返す
- 親しい間柄では「ありがとう、気をつけるね」など柔らかく返す
- ビジネスでは「ご心配いただきありがとうございます」が丁寧
①「ありがとうございます」と感謝を伝える
「お大事に」と言われたときに最も一般的で無難な返し方は、「ありがとうございます」です。短くても相手の気遣いに対して感謝を伝えられ、どんな場面でも使いやすい表現です。
就活中に、担当者に体を気遣われた際に用いると、自然で感じのいい印象を与えることもできます。また、「お気遣いありがとうございます」や「ご心配いただき恐縮です」と一言添えるのもおすすめです。
このように丁寧な表現を加えることで、社会人らしい落ち着いた印象を与えることができます。会話だけでなく、メールの返信などでも応用できるため、覚えておくと役立つでしょう。
さらに、相手の言葉に対して笑顔で返すことも大切です。たとえ短い言葉でも、表情や声のトーンによって印象は大きく変わります。
「ありがとうございます。お気遣いいただき嬉しいです」といった柔らかい言葉を添えれば、相手に安心感を与えることもできます。相手の思いやりを受け取る気持ちを、誠意をもって示しましょう。
②状況に応じて「お気遣いありがとうございます」と返す
特に目上の人に対しても違和感がなく、就活のメールや面接の場などでも使いやすい言葉といえるでしょう。
「お気遣いありがとうございます」は、体調や状況を気にかけてくれた相手に対して丁寧に感謝を伝える表現です。目上の人に使っても違和感なく、メールや面接の場でも使えるため、汎用性は高いといえます。
たとえば「お大事に」と言われたときに、「お気遣いありがとうございます。無理せず回復に努めます」と返せば、礼儀正しく誠実な印象を与えられます。
メールの場合には、「このたびはお気遣いいただき、誠にありがとうございます」と書くとよりフォーマルになるのです。文章で使うときは、文末の表現をやや長めにしてバランスを取るとよいでしょう。
さらに、「温かいお言葉をいただき感謝しております」や「ご配慮いただき、心より御礼申し上げます」と続けると、より丁寧で気持ちのこもった印象を与えられるでしょう。
相手の気持ちをきちんと受け止めたうえで感謝を伝えることが、信頼を築く第一歩になります。
③親しい間柄では「ありがとう、気をつけるね」など柔らかく返す
友人や家族など、親しい人に「お大事に」と言われたときは、堅苦しい言葉よりも「ありがとう、気をつけるね」「うん、しっかり休むよ」「優しいね、ありがとう」など、気持ちが伝わる自然な言葉が合います。
一方で、冗談まじりの返しや軽いトーンには注意が必要です。「大丈夫大丈夫」とだけ言ってしまうと、せっかくの相手の思いやりを軽視している印象を与えるかもしれません。
たとえ親しい関係でも、相手の優しさを受け取る気持ちを忘れずに、「ありがとう」「気をつけるね」といった一言を添えるようにしましょう。
さらにメールやメッセージでは、顔が見えない分言葉選びが重要です。「ありがとう、気にかけてくれて嬉しい」や「心配してくれてありがとう。早く元気になるね」と伝えると、温かく誠実な印象を残せます。
感謝の言葉に少し気持ちを加えることで、言葉に優しさが宿るでしょう。相手の思いやりを受け止め、素直に伝えることが、良好な関係を築くコツです。
④ビジネスでは「ご心配いただきありがとうございます」が丁寧
ビジネスの場面では、「ご心配いただきありがとうございます」という表現が最も丁寧で、社会人として信頼を得られる言い回しです。上司や取引先など目上の人にも違和感なく伝えられます。
たとえば「このたびはご心配いただきありがとうございます。しっかり休んで早く回復いたします」と伝えると、責任感のある社会人としての姿勢が伝わるでしょう。
また、メールでは「ご心配をおかけして申し訳ございません」とセットで使うとさらに丁寧です。「現在は回復に向かっております」など、状況報告も添えることで、相手を安心させる意識も大切になります。
さらに、言葉のトーンも意識すると良いでしょう。口頭で伝える場合は、相手の目を見ながら、落ち着いた声のトーンでゆっくりと話すと丁寧さが増します。
社会人として大切なのは、言葉の丁寧さだけでなく、その背後にある誠実な姿勢です。「ご心配いただきありがとうございます」という言葉を、形式的ではなく心からの表現として使えるよう意識してください。
「お大事に」を正しく使って印象を高めるために

「お大事に」は、相手の健康を気遣う優しい言葉ですが、使い方を誤ると軽く聞こえてしまうこともあります。特に就活やビジネスの場では、状況に合った敬語表現を選ぶことが大切です。
たとえば、面接官や上司には「ご自愛ください」や「お身体をお労りください」といった丁寧な言い換えが適しています。
また、相手の体調や立場に合わせて言葉を選ぶことで、思いやりのある印象を与えられるのです。
さらに、「お大事に」と言われた際には「ありがとうございます」や「お気遣い感謝します」と返すことで、円滑なコミュニケーションにつながるでしょう。
言葉の意味と敬語の使い方を正しく理解し、場面に応じて自然に使い分けることが、社会人としての信頼感を高めるポイントです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。