助産師の平均年収は?看護師との違いや給料アップの方法も解説
「命に関わる仕事をしたい」「女性や家族の人生に寄り添う仕事がしたい」という思いから、助産師という仕事について関心がある人もいるでしょう。
助産師は、妊娠・出産・産後のサポートを通じて、新しい命の誕生に立ち会い、母子の健康や安心を支える役割を担います。
一方で、「資格取得の流れは?」「年収や働き方はどのくらい?」と疑問に思う方もいるでしょう。
この記事では、助産師の仕事内容や年収、キャリアの築き方、将来性まで、初めて学ぶ方にもわかりやすく解説します。
助産師という仕事の魅力や専門性を理解し、自分に合ったキャリアを考える参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
助産師の平均年収はいくら?

助産師の平均年収は、看護師と比べて高めである傾向にあります。勤務先の種類や地域、経験年数によっても差があるため、キャリア設計の参考にしておきたい重要な情報といえるでしょう。
助産師の年収はおおよそ450万〜500万円とされており、月収に換算すると約30万円台中盤です。さらに、賞与や各種手当が加わるため、年収は勤務環境によって上下します。
助産師は妊産婦や新生児に特化した専門職であり、その高度なスキルと判断力が収入に反映されやすい職種です。
また、夜勤やオンコール体制の有無、副業の可否、役職や管理職への昇進といった要素も収入に影響を与えていますよ。
引用:
助産師と看護師との違い

助産師と看護師は同じ医療の現場で働いていますが、仕事内容や専門性には大きな違いがあります。
どちらの職業にも魅力がありますが、将来のキャリアを考えるうえでは、それぞれの役割や資格取得の道のり、給与体系などを理解しておくことが大切です。
ここでは、以下の5つの観点からその違いを詳しく解説します。
- 資格取得までの過程の違い
- 業務内容と専門性の違い
- 夜勤・手当など給与構成の違い
- 就職先や職場の選択肢の違い
- 社会的評価や責任範囲の違い
①資格取得までの過程の違い
看護師になるには、看護専門学校や大学に通い、約3〜4年かけて必要な知識と実習経験を積み、国家試験に合格することで免許を得られます。
一方で助産師は、まず看護師免許を取得することが前提です。その後、助産師養成課程を1年以上修了し、さらに助産師国家試験に合格する必要があります。
そのため、助産師を目指す場合は、進路計画を早めに立てることが重要です。
看護大学のなかには、助産師課程を併設しているところもあり、効率的に資格取得を目指すことも可能です。
入学前からキャリアの最終目標を意識し、将来像を描いておくことで、無理のないスケジュールで学びを進められるでしょう。
②業務内容と専門性の違い
看護師は、内科・外科・小児科・精神科などさまざまな診療科で働き、医師の指示に基づいて処置やケアを行います。
業務内容は広範で、患者の全身管理や心理的サポートも含まれます。一方、助産師は妊娠中の女性の健康管理、分娩介助、産後の母子ケアなど、限られた領域に特化して働きます。
特に正常分娩の場合、助産師は医師の立ち会いなしで分娩を行うことが許されています。これは高度な判断力と知識、そして現場での経験が求められる証です。
また、妊婦や新生児だけでなく、家庭や地域全体に目を向けた支援を行う場面もあります。例えば、母親学級の運営や家庭訪問を通して、生活全体の支援を行うこともあります。
つまり助産師は、医療従事者であると同時に、生活支援の専門家としても活躍しているのです。
③夜勤・手当など給与構成の違い
助産師の平均年収は、看護師よりもやや高い傾向にあります。これは、助産師特有の業務手当や深夜勤務手当が比較的手厚く支給されることが理由です。
また、助産師は専門職として位置づけられることが多く、基本給そのものが看護師より高く設定されている場合もあります。
特定のスキルや経験年数によって役職や資格手当が加算されることもあり、キャリアを積むほど収入アップが期待できるでしょう。
収入面での安定を重視する人にとって、助産師は選択肢として十分魅力的です。ただし、職場ごとに手当の内容や支給条件が異なるため、就職の際はしっかり確認しておくことが大切です。
④就職先や職場の選択肢の違い
助産師の就職先は、産婦人科専門病院や総合病院の産科、助産院などが中心です。業務が妊産婦に特化しているため、職場も自然と限られてきます。
場合によっては、自治体の保健センターや母子保健施設での勤務もあり、地域密着型の働き方が求められることもあります。
一方で看護師は、病院やクリニックだけでなく、介護施設、訪問看護ステーション、企業の医務室、学校など幅広い分野での活躍が可能です。
職場選びにおいては、自分がどんな環境で働きたいのか、どのようなスタイルで人と関わりたいのかをよく考えておくことが、満足度の高いキャリアにつながるでしょう。
⑤社会的評価や責任範囲の違い
助産師は、出産という命の誕生に直接関わる職業であることから、医療職のなかでも特に高い社会的評価を得ています。妊婦と赤ちゃんの両方の命を守る役割を担っており、その責任の大きさは計り知れません。
特に正常分娩を単独で扱えることは、専門性と信頼性の高さを示す重要な証です。その分、判断ミスが大きな事故につながるリスクもあるため、常に緊張感を持って業務にあたる必要があります。
しかし、そのプレッシャーを乗り越えて無事に出産を終えたときには、母親や家族からの深い感謝の言葉を受け取れるため、大きなやりがいを感じるでしょう。
助産師の年収を上げる方法
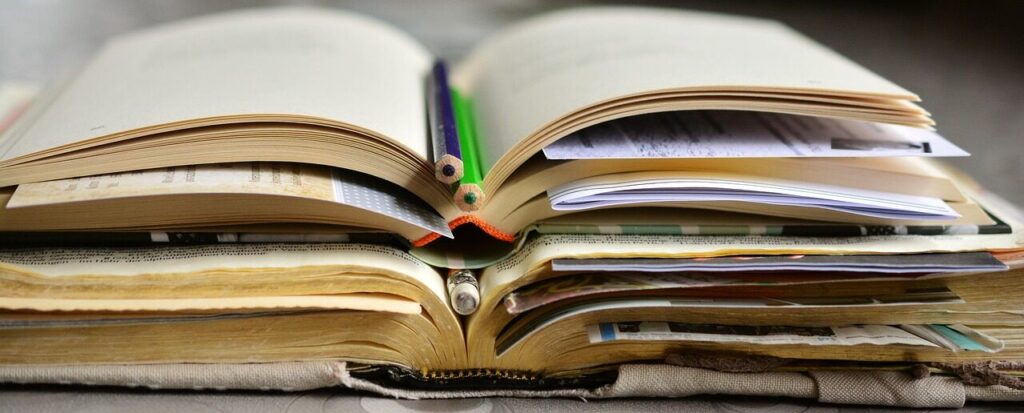
助産師として働く中で、年収を上げたいと考える人は少なくありません。年齢や経験を重ねるだけでなく、戦略的な行動によって収入を上げることが可能です。
ここでは、収入アップのために実践できる6つの方法について詳しく紹介します。
- 夜勤回数を増やす
- 役職に就いて昇給を狙う
- 待遇の良い職場へ転職する
- スキルアップ・資格取得による昇給
- 独立開業による収入の増加
- 地方から都市部への転職
①夜勤回数を増やす
助産師の給与は、夜勤手当の有無によって大きく変わります。特に分娩は深夜にも発生するため、夜勤の頻度が高くなることで手当も多く支給されます。
夜勤回数を意識的に増やせば、基本給に加えて収入全体を大きく底上げできるでしょう。とはいえ、夜勤が多くなると体力的な負担も増します。
そのため、自身の健康管理をしっかり行い、無理のないスケジュールでシフトに入ることが重要です。
また、病院によっては夜勤手当の金額に差があるため、就業先選びの際には給与構成の詳細にも注目しておくことが必要です。
②役職に就いて昇給を狙う
職場内でリーダーや主任といった役職に就くことで、基本給や役職手当が加算されるようになります。
助産師としてのスキルだけでなく、マネジメント力や後輩の指導能力も評価されるため、総合的な働き方が求められます。
昇進を目指す場合は、日々の業務を着実にこなしながら、周囲との信頼関係を築くことがポイントです。院内研修や勉強会への積極的な参加も、昇進の評価材料になります。
役職に就くことは責任が増える反面、やりがいも大きく、年収アップと同時にキャリアの幅を広げることにもつながるでしょう。
③待遇の良い職場へ転職する
同じ職種であっても、勤務先によって給与や福利厚生に大きな差があります。公立病院や大学病院は安定性が高い一方で、民間の医療機関やクリニックではインセンティブ制度や手当が手厚いところもあります。
年収を上げたい場合は、現在の職場での昇給に限界を感じたときに、転職を視野に入れてもよいでしょう。特に、分娩件数が多い施設や夜勤体制が充実している病院は、高収入が期待できます。
転職を成功させるには、求人票の条件をよく読み、面接では具体的な勤務内容や手当の仕組みについて確認することが大切です。
加えて、職場の雰囲気や働き方の柔軟性、教育体制の充実度も収入面と同じくらい重要です。長く安心して働ける環境かどうかを見極めることが、転職による年収アップを実現するうえでのカギになります。
④スキルアップ・資格取得による昇給
助産師としての基本スキルに加えて、母乳育児相談員、性教育アドバイザー、メンタルヘルス関連資格などを取得することで、業務の幅が広がり、給与面にも良い影響を与えることがあります。
また、これらのスキルを持つことで、専門外来の担当や外部講師、地域活動への参加など、通常業務以外の収入源が得られることもあります。
資格取得は自己投資となりますが、長期的に見れば収入アップやキャリア形成において大きな武器になります。定期的に新しい知識を取り入れる姿勢が、収入向上の鍵となるでしょう。
さらに、認定看護管理者や特定行為研修など、高度な資格を取得することで病院内での役割が拡大し、それに見合う手当やポジションを得られることもあります。
日々の業務にプラスして、学び続けることが収入と評価の両方に反映されていきます。
⑤独立開業による収入の増加
助産師には、助産院を開業したりフリーランスとして活動したりする道もあります。独立することで自分の働き方を自由に設計できるうえ、受け持つ件数やサービス内容によって収入も大きく変動します。
ただし、開業には経営知識や資金計画、行政手続きなどが必要です。責任も増しますが、その分やりがいも格別です。
個人の信頼と実績がものをいう世界のため、独立前には実務経験を十分に積み、地域のニーズを把握しておくことが求められます。
また、助産院に加えオンライン相談や講師業、セミナー開催など多角的に収益化することで、柔軟かつ安定した収入を目指すことも可能です。
自分のスタイルで働きながら、社会に貢献できる魅力ある働き方といえるでしょう。
⑥地方から都市部への転職
一般的に、都市部の医療機関は地方よりも給与水準が高く設定されていることが多いです。分娩件数や夜勤体制、人員配置などの違いから、都市部ではより高収入が見込めます。
ただし、家賃や生活費も上がるため、手取りでどれほど差があるかを慎重に見極める必要があります。
また、都市部は競争が激しく、即戦力を求められる傾向も強いため、転職前に自己研鑽を重ねておくことが重要です。収入を増やす手段の一つとして、地域を変える選択肢も十分に検討する価値があります。
加えて、都市部では最新の医療機器や教育環境が整っている施設が多いため、自分のスキルアップや専門性の深化にもつながるでしょう。
生活環境の変化に備えながら、より良い条件での勤務を目指すことが可能です。
助産師になるためのステップ
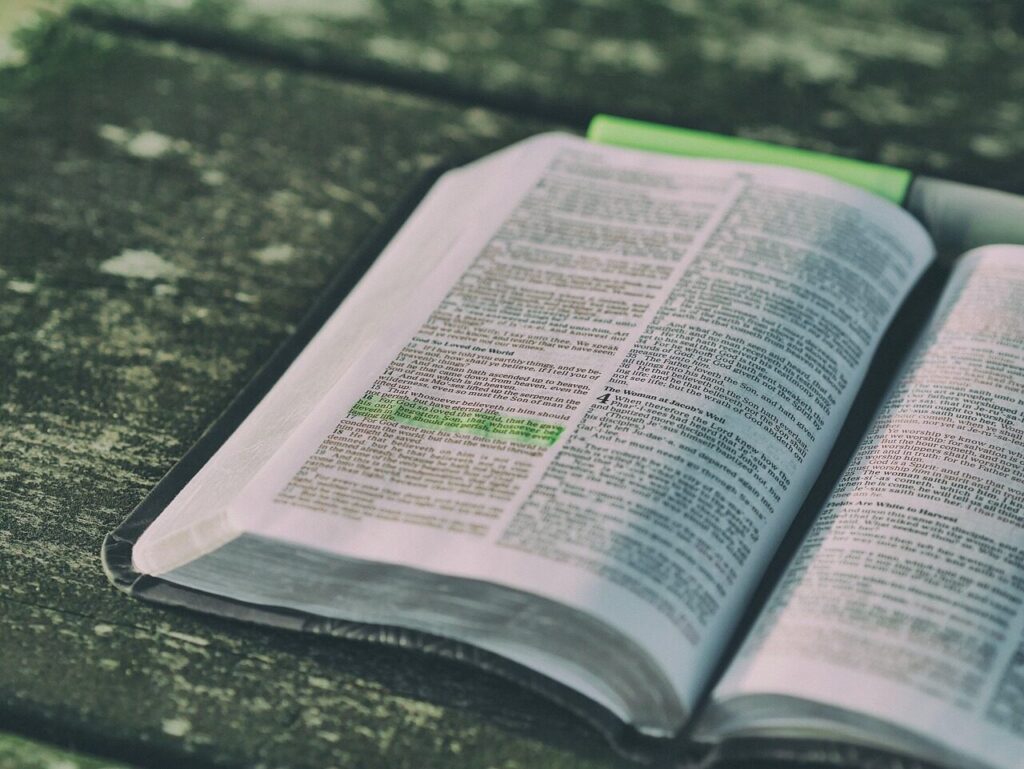
助産師を目指すうえで、どのようなステップが必要なのかを明確に理解しておくことはとても重要です。
看護師との違いを把握し、自分が進むべき道を計画的に歩むためにも、ここでは、紹介する7つのプロセスを順に確認してみてください。
- 看護師国家資格を取得する
- 助産師養成課程を修了する
- 助産師国家試験に合格する
- 助産師として免許登録を行う
- 就職先を選定して応募する
- 臨床現場で実務経験を積む
- 専門スキルや知識を継続的に学ぶ
①看護師国家資格を取得する
助産師になるには、まず看護師国家資格を取得する必要があります。これは助産師が看護師の上位資格にあたるためで、看護の基礎が身についていなければ助産業務を行えません。
そのため、最初のステップとして看護大学や専門学校に進学し、3~4年間で必要なカリキュラムを修了しましょう。
看護師資格を取ったあと、すぐに助産師課程に進む人もいれば、臨床経験を積んでから目指す人もいます。
どちらを選ぶかは自分のキャリア設計次第ですが、目指す時期によって進路が変わるため、早いうちから明確にしておくことが大切です。
また、学校選びでは実習先や国家試験の合格率、卒業後の進路サポートなどにも注目しましょう。
看護師資格はゴールではなくスタート地点であることを意識し、将来的に助産師を目指す前提で学校生活を送ると、その後のステップがスムーズに進みやすくなります。
②助産師養成課程を修了する
看護師資格を取得したら、次は助産師養成課程に進みます。大学の専攻科や大学院、または指定の専門学校で学び、1年かけて助産の専門知識と技術を習得します。
ここでは出産の介助や妊婦のケア、緊急時の対応まで、実践的な内容を深く学ぶことになります。
理論だけでなく実習も重視されるため、妊産婦や新生児への接し方を丁寧に身につけることが求められるでしょう。この課程では、患者さん一人ひとりの気持ちに寄り添う姿勢や、的確な判断力も養われます。
また、学校によっては助産学演習や地域母子保健活動など、現場に近いカリキュラムを取り入れているところもあります。
入学試験や学費、生活費との両立に不安を感じることもあるかもしれませんが、事前に奨学金制度や教育ローンの情報を調べておくと、安心して学びに集中できるでしょう。
③助産師国家試験に合格する
養成課程を終えると、いよいよ助産師国家試験を受験する段階です。この試験は毎年2月ごろに実施され、合格率は90%前後と高めではありますが、油断はできません。
出題範囲が広く、専門的な内容も多いため、日々の学びを積み重ねておくことが大切です。暗記だけでなく、状況判断や応用力が問われる出題もあるため、単なる知識ではなく実践的な理解が求められます。
また、看護師国家試験と日程が近いため、両方を同時に受ける人は学習計画の立て方がとても重要になります。
どちらも合格するためには、苦手分野を早めに把握し、優先順位を決めて効率よく取り組むことが欠かせません。模試や過去問を活用しながら、本番に向けて実践的な対策をしておきましょう。
合格後はすぐに免許登録の準備を進める必要があるため、必要書類や手続きの流れも事前に確認しておくと安心です。
④助産師として免許登録を行う
国家試験に合格した後は、正式に助産師として働くための免許登録を行います。これは厚生労働省を通じて手続きし、必要書類の提出と手数料の支払いが必要です。
内容自体は難しくありませんが、書類の不備や手続きの遅れが原因で、就職時期がずれるケースもあります。特に就職活動と並行して進める場合は、スケジュールに余裕を持って行動したいところです。
登録完了までは一定の時間がかかるため、内定先との連絡も忘れずに行っておきましょう。登録が済めば、ようやく助産師として働くことが認められます。
この時点で初めて、国家資格を活かした医療従事者としてのキャリアがスタートします。小さなステップに見えて、非常に大切な過程といえるでしょう。
⑤就職先を選定して応募する
免許を取得したら、次は就職活動です。助産師の就職先には、総合病院や産婦人科クリニック、地域の母子保健施設などがあります。
職場によって働き方や求められる役割が異なるため、自分の理想とするキャリア像を明確にしておくことが重要です。
待遇や立地だけで選んでしまうと、実際の仕事とのギャップに悩まされる可能性もあるでしょう。
助産師としてどのようなケアを提供したいのか、どの年齢層・ライフステージに関わりたいのかなどを考え、応募先を選定するとミスマッチを防げます。
また、可能であれば見学やインターンに参加して、職場の雰囲気や実際の業務を肌で感じてみてください。現場のスタッフの対応や働く環境を見ることで、自分に合う職場かどうかを具体的にイメージできるはずです。
⑥臨床現場で実務経験を積む
助産師として就職したら、実際の現場でさまざまな経験を積んでいきます。出産の立ち会いや妊婦指導、新生児ケアなど、多岐にわたる業務に関わることで、知識とスキルが磨かれていきます。
最初のうちは不安や緊張もあるでしょうが、先輩やチームのサポートを受けながら一歩ずつ慣れていけば大丈夫です。日々の振り返りや自己学習を続けることで、着実に成長を感じられるようになります。
また、実務を通して学ぶのは技術面だけではありません。患者さんやその家族とのコミュニケーション力や、チーム医療における協調性も非常に重要です。
急なトラブルやイレギュラーな対応が求められる場面では、冷静な判断力も必要になります。これらは机上の学習では身につけにくいため、現場での経験こそが何よりの財産になるでしょう。
⑦専門スキルや知識を継続的に学ぶ
助産師として長く活躍するには、現場経験に加えて継続的な学びが不可欠です。医療の世界は日々進化しており、新たな技術やケアの方法が次々と生まれています。
たとえば、周産期医療や精神的サポート、地域連携に関する知識を深めるために、研修や学会への参加を検討してみてください。また、認定助産師や高度実践助産師といった上位資格を目指すことも可能です。
こうしたスキルアップは、助産師としての専門性を高めるだけでなく、キャリアの幅を広げることにも繋がりますよ。
助産師の仕事内容

助産師は「出産をサポートする仕事」というイメージが強いかもしれませんが、実際には妊娠中から出産、産後まで幅広い支援を行っています。
ここでは、助産師が担う代表的な仕事内容について5つの視点から詳しくご紹介します。
- 妊婦への保健指導と相談対応
- 分娩時の介助と緊急対応
- 新生児のケアと母乳育児支援
- 産後のメンタルケアや育児指導
- 妊娠〜出産後までの継続的支援
①妊婦への保健指導と相談対応
助産師は、妊婦が安心して妊娠期間を過ごせるように、保健指導や生活面のアドバイスを行います。具体的には、体重管理や食事の指導、運動方法の提案など、母体と胎児の健康を保つための助言が中心です。
また、不安や疑問を抱える妊婦からの相談に応じ、気持ちを受け止めながら心理的サポートも行います。妊娠は心身ともに大きな変化が起こる時期であり、些細なことでも悩みがちです。
たとえば「体重が増えすぎて不安」「お腹の張りが気になる」といった声に対し、医学的な知識をもとに適切な対応が求められます。
妊婦健診の場では医師と連携しながら、妊娠経過に応じたサポートを提供するため、観察力とコミュニケーション力が欠かせません。
②分娩時の介助と緊急対応
出産の現場では、助産師は分娩の中心的な存在として活躍します。陣痛の進行を見極めながら妊婦を励まし、呼吸法や体位の指導を通じて出産の流れをサポートします。
分娩台のそばで手を握り、声をかけながら妊婦の不安を和らげる役割も担っています。
また、予定外の急変や異常出産にも対応しなければなりません。出血が多い、胎児の心拍が落ちるなど、緊急事態に備えて医師への迅速な報告や処置の補助を行います。
そのため、冷静な判断力と的確な行動力が求められます。医療機器の操作や胎児モニターの読解など、専門的なスキルも必要とされる場面が多く、分娩介助はまさに助産師の腕の見せどころといえるでしょう。
③新生児のケアと母乳育児支援
出産後は、新生児の健康状態を確認しながら、授乳やスキンシップを通じて母子の絆づくりを支援します。
具体的には、体重測定や呼吸状態の確認、黄疸の有無などの観察を行い、必要に応じて医師と連携します。
母乳育児のサポートも重要な仕事の一つです。うまく吸えない赤ちゃんへの対応や、乳腺炎に悩む母親へのアドバイスなど、個別の悩みに寄り添う姿勢が求められます。
また、母親が自信を持って育児を始められるよう、抱っこの仕方や授乳姿勢なども丁寧に教えます。赤ちゃんと母親の両方の状態を常に見守りながら、穏やかな育児のスタートを支えることが助産師の役割です。
④産後のメンタルケアや育児指導
出産直後の母親はホルモンバランスの影響で、気分が落ち込みやすくなる傾向があります。助産師はそうした心の変化にも目を配り、産後うつの兆候が見られた場合は医師と連携して早期に対応します。
声かけや傾聴を通じて、不安を抱える母親の心に寄り添う姿勢が欠かせません。また、育児が初めての母親にとって、抱っこや沐浴、授乳などの基本的な動作も戸惑いの連続です。
助産師はそれらを一つひとつ丁寧に指導し、安心して赤ちゃんと向き合えるようサポートします。
自信のない母親にとって「大丈夫ですよ」「よくできていますよ」といった温かい言葉がどれほど力になるかは計り知れません。
心と体の両面から母親を支えることで、より良い家庭のスタートにつながるのです。
⑤妊娠〜出産後までの継続的支援
助産師の仕事は、妊娠から出産、そして育児期に至るまで長期間にわたります。
一貫して同じ助産師が関わる「継続ケアモデル」では、妊婦との信頼関係を築きやすく、個別のニーズにきめ細かく対応できる利点があります。
妊娠中の生活指導から始まり、出産の立ち会い、産後の心身のケアまで、ライフステージに寄り添ったサポートが可能です。
家庭訪問や地域の母子支援センターでのフォローアップを通じて、医療機関だけではカバーしきれない部分にも手が届くのが助産師の強みといえるでしょう。
特に核家族化や育児の孤立が進む現代において、こうした継続的な支援は母子の安心感を支える大きな力となります。
助産師の仕事の魅力

助産師という職業には、他の職種ではなかなか得られないやりがいと感動が詰まっています。ここでは、助産師として働くことの魅力を7つの観点からご紹介します。
- 命の誕生に立ち会える
- 女性の一生に寄り添える
- 専門職として誇りを持てる
- 安定したキャリアを築ける
- 患者との深い信頼関係を築ける
- 女性支援の専門家として活躍できる
- 国家資格による高い信頼性がある
①命の誕生に立ち会える
助産師の仕事の中で、最も感動的で特別な瞬間のひとつが「命の誕生に立ち会うこと」です。赤ちゃんの産声を初めて聞く瞬間は、何度経験しても胸を打たれます。
妊婦の努力と生命の神秘を間近で感じられるこの体験は、医療職の中でもとても貴重です。
また、出産の瞬間に立ち会うだけでなく、その前後のケアを通じて家族の喜びや感謝の気持ちを直接受け取れます。
感謝の言葉や涙に触れるたび、自分の仕事が誰かの人生に深く関わっていることを実感できるでしょう。
このような経験は、日々の忙しさの中でも強いモチベーションとなり、助産師という職業ならではの醍醐味といえます。
②女性の一生に寄り添える
助産師は、妊娠・出産だけでなく、思春期から更年期まで、女性のあらゆるライフステージに関わる存在です。
女性特有の悩みや体の変化に寄り添いながら、必要な支援を行うことで、女性が自分らしく生きられるようサポートできます。
たとえば、妊娠期の身体の変化への対応や、産後の育児の不安、月経や更年期に関する相談など、幅広いテーマで女性に寄り添います。
女性の身体と心の両方に深く関われる仕事だからこそ、やりがいも大きく、長期的な関係を築くことも可能です。人生に寄り添う専門職として、信頼される存在になれるのが大きな魅力です。
③専門職として誇りを持てる
助産師は専門性の高い国家資格であり、専門的な知識と技術を必要とする職種です。
解剖学・生理学をはじめとした医療知識や、分娩や新生児ケアに関する実践的なスキルを習得して初めて、一人前の助産師として働けます。
そうした背景から、患者や医療チームから高い信頼を得られる点も大きな魅力です。
また、学会や研修に積極的に参加することで、知識を更新し続けられる環境が整っており、自分の専門性を高めながら長く活躍できます。
自らのスキルで命を守り、誰かの人生を支えているという誇りを日々感じながら働けるのは、助産師ならではのやりがいです。
④安定したキャリアを築ける
助産師は需要が高く、全国どこでも必要とされる職業です。出産は社会に欠かせない営みであるため、景気に左右されにくいという特徴があります。
また、医療・福祉分野における人材不足の影響もあり、今後も安定した雇用が期待されています。
さらに、病院勤務に限らず、助産院や保健センター、教育機関、行政など活躍の場が多様にあるため、ライフスタイルに合わせた働き方も可能です。
結婚・出産などライフイベントを経ても復職しやすく、長く続けられるキャリアを築きたい人にはぴったりの職種でしょう。職場選びやキャリアの設計次第で、柔軟で自立した働き方が叶います。
⑤患者との深い信頼関係を築ける
助産師は妊婦やその家族と深く関わる仕事であり、日々のやり取りを通して信頼関係を育んでいきます。
体調の変化や不安を共有し、ときにはプライベートな相談を受けることもあるため、強い絆が生まれやすい職業です。
たとえば、妊娠中のサポートから出産立ち会い、産後の育児相談まで一貫して関わることで、「あなただから安心して任せられる」といった声をもらえる場面も少なくありません。
こうした関係性は、ただ業務をこなすだけでは得られない、助産師ならではの魅力です。相手の人生に深く関わり、信頼される喜びを実感できるのは、この仕事の醍醐味といえるでしょう。
⑥女性支援の専門家として活躍できる
助産師は、女性の健康や人生設計を支える「女性支援のプロフェッショナル」として、社会的にも重要な役割を果たします。
出産だけでなく、性教育や家族計画、更年期の健康相談など、幅広いテーマで女性の生活に寄り添う存在です。
とくに最近では、ジェンダーや女性の社会進出に関する課題が注目されており、女性の心身の健康を支える助産師の重要性が高まっています。
医療機関にとどまらず、学校や地域活動の場でも知識を活かして活躍できる点も、この職業の魅力です。
女性のライフサイクルに関する幅広い知識と対応力を持ち、社会的課題の解決にも貢献できる専門職といえるでしょう。
⑦国家資格による高い信頼性がある
助産師は国家資格であり、その専門性と信頼性の高さが社会的にも広く認められています。
厳格な教育課程と国家試験を経て得られる資格であるため、医療現場では重要な役割を担い、患者からの信頼も厚くなります。
また、国家資格を保有していることで、転職や復職時にも有利に働くケースが多く、キャリアの選択肢が広がります。
さらに、国際的にも通用する資格であるため、海外での医療支援やボランティア活動など、国境を越えて活躍することも可能です。
高い信頼性と専門性を武器に、自分らしい働き方を築けるのは、大きな強みといえるでしょう。
助産師の仕事の大変さ

助産師の仕事は命と向き合うやりがいのある仕事ですが、その一方で、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかる場面が少なくありません。
ここでは、助産師の仕事における大変な面を7つに分けてご紹介します。
- 夜勤や長時間勤務による体力的負担がある
- 命に関わる場面での精神的プレッシャーが大きい
- 突発的な対応が求められる不規則な勤務がある
- 患者や家族とのコミュニケーションに気を遣う
- チーム医療での連携にストレスを感じることがある
- 出産に関するリスク対応が求められる
- 人手不足による業務の過重が生じやすい
①夜勤や長時間勤務による体力的負担がある
助産師は24時間体制の医療現場で働くことが多く、夜勤や長時間の勤務が避けられません。とくに分娩は時間を選ばないため、深夜や早朝の対応も頻繁にあります。
一晩中分娩に付き添い、体力を使い切ってしまうことも少なくありません。さらに、立ちっぱなしの時間が長く、緊張感の続く現場では、疲労が蓄積しやすくなります。
慢性的な睡眠不足に陥ったり、生活リズムが崩れることで体調を崩す人もいます。そのため、体力を維持するための日頃のケアや、休息時間をしっかり確保する意識が欠かせません。
体調管理もまた、助産師にとって大切な仕事の一部といえるでしょう。
②命に関わる場面での精神的プレッシャーが大きい
助産師の仕事は、常に「命」と隣り合わせです。正常な出産ばかりではなく、急変や異常分娩といったリスクの高い場面にも直面するため、強い精神的プレッシャーがかかります。
万が一の判断ミスが、母子の命に関わる結果となる可能性もあるのです。とくに分娩中は一瞬一瞬の判断が重要であり、冷静な対応が求められます。
自分の判断に自信が持てず、不安を抱えながら仕事をしている助産師も少なくありません。
精神的な負担を軽減するためには、知識と経験を積むだけでなく、周囲の医療スタッフと密に連携し、相談しやすい環境を整えることが大切です。
③突発的な対応が求められる不規則な勤務がある
出産は予定どおりに進むとは限らず、突発的な対応が必要になるケースも多くあります。
たとえば、勤務終了間際に緊急の分娩が入ることや、休日や夜間に急に呼び出されることもあるため、生活のペースが乱れやすい職業です。
予定が立てづらく、プライベートの時間を確保しにくいという悩みを抱える人も少なくありません。家族や友人との予定が合わなかったり、突然の勤務変更に対応しなければならない状況も発生します。
不規則な働き方に慣れるまでには時間がかかりますが、職場によってはオンコール体制や交代制を工夫することで、ある程度の働きやすさを確保しているところもあります。
④患者や家族とのコミュニケーションに気を遣う
助産師は患者本人だけでなく、その家族とも多く関わる仕事です。とくに妊娠・出産というデリケートなテーマを扱うため、言葉選びや対応の仕方には細心の注意が求められます。
少しの言葉の違いが、不安や不信感を招くこともあるため、コミュニケーションには常に気を遣わなければなりません。
また、出産に対する考え方や希望は人それぞれ異なります。そのため、個別の価値観や文化的背景を尊重しながら、対応していく力も必要です。
丁寧で思いやりのある対応を心がけることで信頼関係が築けますが、その一方で精神的に疲れてしまうこともあります。助産師にとって、対人関係のスキルは欠かせない能力のひとつといえるでしょう。
⑤チーム医療での連携にストレスを感じることがある
助産師は医師や看護師、臨床検査技師などと連携しながら働く「チーム医療」の一員です。業務が多岐にわたる中で、情報共有のズレや方針の違いがストレスにつながることもあります。
とくに緊急時には意思疎通のスピードと正確性が問われ、責任の所在があいまいになる場面もあります。また、職場によっては人間関係のトラブルや上下関係に悩むケースもあるでしょう。
良好なチームワークを築くためには、相手の立場を尊重しながら柔軟に対応する姿勢が必要です。ストレスを感じたときは、溜め込まずに相談したり、適切にリフレッシュする工夫も大切です。
⑥出産に関するリスク対応が求められる
どれだけ準備をしていても、出産には予期せぬリスクがつきものです。出血多量や胎児の異常、陣痛が進まないといったトラブルが突然発生することもあり、迅速かつ的確な対応が求められます。
こうしたリスクへの対応力は、経験と判断力の積み重ねによって身につくものです。助産師は医師と連携しながらリスクを最小限に抑える努力をしますが、そのプレッシャーは大きなものとなります。
事前の観察力や患者との信頼関係が、緊急時の対応にも影響するため、日頃からの丁寧なケアが不可欠です。万が一のときに備えた心構えと冷静さも、この職業には欠かせません。
⑦人手不足による業務の過重が生じやすい
医療業界全体で人手不足が課題となっており、助産師も例外ではありません。限られた人数で多くの妊婦や産婦、新生児をケアしなければならないため、どうしても業務量が多くなりがちです。
一人ひとりに十分な時間をかけたくても、現実的には難しい場面があるのが現状です。忙しさのあまり、心のゆとりがなくなってしまうと、業務ミスやコミュニケーションのすれ違いを招くおそれもあります。
だからこそ、職場の人員配置や労働環境の見直しが求められています。また、自分自身でできる工夫として、業務の優先順位を明確にしたり、適度に休憩を取るなど、セルフケアの意識も重要です。
助産師の将来性

医療や社会の変化に伴い、助産師の役割や働き方も広がりを見せています。ここでは、今後の助産師という職業の可能性と将来性について、6つの視点から詳しくご紹介します。
- 高齢出産の増加によるニーズ拡大
- 地域包括ケアにおける役割の広がり
- キャリアアップの選択肢の多様化
- 独立・開業助産師の可能性
- オンライン支援やテレヘルスの活用
- 助産師教育の充実による人材育成
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①高齢出産の増加によるニーズ拡大
近年、30代後半〜40代での出産が増加しており、いわゆる高齢出産が珍しくなくなっています。
高齢出産は妊娠や出産に伴うリスクが高まる傾向があるため、より専門的な知識と対応力を持つ助産師の存在が重要視されています。
妊娠中の体調管理や精神的なサポート、リスクの早期発見など、助産師の役割は今後ますます求められるでしょう。
また、晩産化が進む中で、不妊治療や妊活に関する相談のニーズも高まっており、助産師の活躍の場は拡大しています。こうした背景から、将来的にも安定した需要が期待できる職業といえます。
②地域包括ケアにおける役割の広がり
高齢化社会の進展とともに、地域包括ケアが注目を集めています。これは、医療・介護・生活支援を地域全体で提供する仕組みであり、その中で助産師が果たすべき役割も増えています
。具体的には、妊産婦だけでなく、若年女性や高齢女性への健康相談、性教育の実施など、多様な世代への支援が求められるようになっています。
地域に根ざした活動として、保健センターや学校、地域イベントでの啓発活動などに参加する助産師も増えています。
医療機関だけにとどまらず、地域の一員として幅広いケアに関わることで、助産師の社会的価値はさらに高まっていくでしょう。
③キャリアアップの選択肢の多様化
助産師のキャリアパスは、単に現場で働くだけではありません。経験を積んだあとには、管理職や教育者、研究者としての道も開かれています。
たとえば、認定助産師や専門助産師、母性看護の講師といった立場で、後進の育成に関わる人もいます。また、大学院に進学して医療経営や保健政策を学び、行政や政策立案に携わるキャリアもあります。
このように、キャリアの幅が広く、ライフステージに合わせて柔軟に選択できる点も魅力です。助産師としての経験を活かして、専門性をさらに深めたい人にとって、将来の選択肢は多彩です。
④独立・開業助産師の可能性
病院などに所属せず、自ら助産院を開業する「開業助産師」という道もあります。
これは、妊娠・出産・産後ケアを一貫して提供できる自由度の高い働き方であり、特に自然分娩や個別ケアを重視する妊婦からの需要があります。
助産師として独立するには、豊富な経験と経営面の知識が求められますが、自分らしいケアを実現できる大きな魅力があります。
地域に密着したサービスを展開したり、訪問型のケアを提供するなど、働き方もさまざまです。自分の理念を反映させた施設運営ができる点で、キャリアの集大成として開業を目指す助産師も少なくありません。
⑤オンライン支援やテレヘルスの活用
近年では、遠隔診療やオンライン相談など、医療現場でもデジタル化が進んでいます。助産師も例外ではなく、妊婦との面談や育児相談をオンラインで行うケースが増加しています。
とくに外出が難しい妊婦や、子育て中の母親にとって、自宅から相談できる環境は大きな安心材料です。
今後は、アプリやウェアラブル端末を活用した母子管理など、テクノロジーを取り入れたケアの形が広がっていくと予想されます。
ICTを活用することで、助産師の働き方もより柔軟になり、働く側・利用する側双方にとってメリットのある仕組みが構築されていくでしょう。
⑥助産師教育の充実による人材育成
助産師の専門性を高めるための教育体制も年々整ってきています。
大学・大学院での高度な教育や、シミュレーション実習など、実践的なカリキュラムの導入が進んでおり、即戦力となる人材の育成が可能になっています。
また、卒後教育や継続教育を通じて、知識のアップデートを支援する体制も拡充しています。
国や自治体も、地域の母子保健を担う人材として助産師の育成に力を入れており、将来的にはさらに高度な専門職としての役割が期待されるでしょう。
教育の充実は、助産師という職業の地位向上にもつながる大切な要素です。
助産師の年収から見る将来性とキャリアの展望

助産師は、医療の中でも専門性が高く、安定した収入と将来性を兼ね備えた職業です。平均年収は看護師よりやや高めで、経験や勤務形態によって大きく変動します。
なぜなら、助産師は命の誕生に立ち会い、母子の健康を支える重要な役割を担うため、高い専門性と責任が求められるからです。
さらに、今後は高齢出産の増加やオンライン支援の普及により、助産師の需要はますます拡大するでしょう。
つまり、助産師という仕事は、専門職としての誇りと安定した収入の両立が可能な職業といえますよ。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














