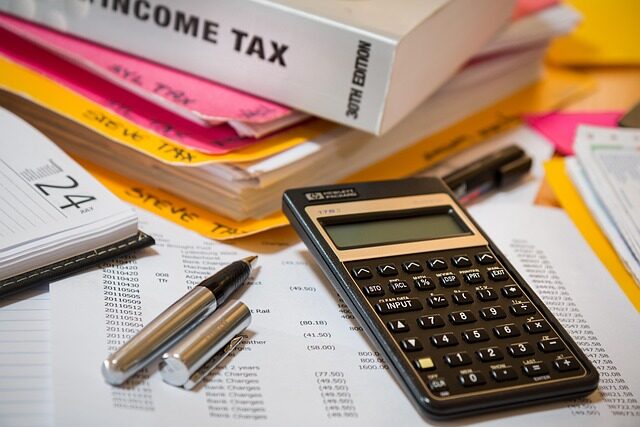【最新版】公認会計士の生涯年収はいくら?平均年収・勤務先別で徹底比較
「公認会計士の生涯年収って、実際どのくらいなんだろう?」
高い専門性と社会的信頼を誇る国家資格である一方、その報酬の実態は勤務先やキャリアによって大きく異なります。
BIG4監査法人、一般企業、コンサル、独立開業など、どの道を選ぶかで「生涯の稼ぎ方」はまったく違うのです。
本記事では、公認会計士 生涯年収の平均値や勤務先別の年収比較、そして年収を上げるためのキャリア戦略までを徹底解説していきます。
資格の価値を最大化するためのヒントを、一緒に見ていきましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公認会計士の平均年収

公認会計士の平均年収は、専門性の高さを反映して、一般の給与所得者よりも相当高い水準にあります。
公的統計では平均年収がおよそ856万円前後とされており、経験を積むことで年収1,000万円を超える人も少なくありません。
大手監査法人に勤める場合は昇進に応じて報酬が上がる仕組みが整っており、努力が結果として収入に反映されやすい環境です。
さらに、独立開業を選ぶ人も多く、実務経験と人脈を活かすことでさらに高収入を得ることも可能でしょう。安定した収入に加え、社会的信用が高い点も大きな魅力です。
ただし、資格取得までには長期的な学習と実務経験が必要となるため、計画的に準備を進めることが大切です。
引用:
公認会計士の生涯年収はいくら?

公認会計士の平均的な生涯年収はおおよそ3億〜4億円と見積もられています。初任給は一般企業と大きく変わりませんが、経験や資格を重ねるほど専門性が評価され、年収が上昇していきます。
特に30代以降は役職や独立によって年収が大きく伸び、一般的なサラリーマンよりも安定して高収入を得られる傾向があります。
勤務先別に見ると、監査法人勤務では年収800万〜900万円前後が目安で、マネージャー職に昇進すれば1,000万円を超えることも多いです。
外資系法人やコンサルティングファームではさらに高く、報酬体系がグローバル基準のため、年収1,200万円以上に達するケースもあります。
多様な働き方ができることが、公認会計士の生涯収入を押し上げる大きな要因といえるでしょう。
引用:
- 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
- MS-Japan「公認会計士の年収」
- OpenWork「EY新日本監査法人 年収情報」
- OpenWork「トーマツ 公認会計士年収情報」
- OpenWork「PwC Japan 公認会計士年収情報」
【勤務先別】公認会計士の年収比較

公認会計士の年収は勤務先や役職、専門分野によって大きく変化します。監査法人で経験を積む人もいれば、事業会社やコンサルティング業界で活躍する人、独立して自身の事務所を経営する人もいます。
それぞれにメリットと課題があり、収入の幅も広いのが特徴です。ここでは、代表的な勤務先ごとの平均年収と、その背景にある要因を詳しく解説します。
- BIG4監査法人の年収
- 中小監査法人・地方監査法人の年収
- 一般事業会社で働く公認会計士の年収
- コンサルティングファームでの年収
- 独立開業した公認会計士の年収
「自分らしく働ける会社が、実はあなたのすぐそばにあるかもしれない」
就活を続ける中で、求人票を見て「これ、ちょっと興味あるかも」と思うことはあっても、なかなかピンとくる企業は少ないものです。そんなときに知ってほしいのが、一般のサイトには載っていない「非公開求人」。
①あなたの強みを見極め企業をマッチング
②ES添削から面接対策まですべて支援
③限定求人なので、競争率が低い
「ただ応募するだけじゃなく、自分にフィットする会社でスタートを切りたい」そんなあなたにぴったりのサービスです。まずは非公開求人に登録して、あなたらしい一歩を踏み出しましょう!
①BIG4監査法人の年収
BIG4監査法人では、入社初年度で年収500万円前後、マネージャー職になると900万円を超えることが一般的です。
シニアマネージャーやパートナー職まで昇進すれば、1,500万円を超える水準に達することもあります。
こうした高水準の報酬は、業務の専門性の高さと国際的な案件への対応力が求められることに起因しています。
グローバル企業の監査やM&A関連の監査業務では、英語力や国際会計基準(IFRS)への理解が不可欠であり、専門スキルを持つほど評価が上がります。
業務量は多いものの、努力が昇進や報酬に結びつく構造になっているため、成長志向の高い人にとって非常に魅力的な職場といえるでしょう。
②中小監査法人・地方監査法人の年収
中小監査法人や地方監査法人の年収は、平均で400〜700万円ほどです。BIG4と比べると報酬水準は低いものの、安定したワークライフバランスが確保しやすく、柔軟な働き方を選びやすい点が特徴です。
繁忙期以外は残業が少なく、有給休暇も取得しやすい環境にある法人が多いです。地域密着型の業務が中心で、中小企業や医療法人、学校法人など地元企業との関係構築を重視した働き方が求められます。
経営者と直接関わることで、会計だけでなく経営全般の理解を深められる点は大きな魅力です。
ただし、業務範囲が限定的で昇給スピードが遅い傾向があるため、長期的なキャリア設計を意識する必要があります。
税務や財務コンサルティングの知識を磨けば、より幅広い顧客に対応でき、報酬を上げることも可能です。自分のペースで専門性を高めたい人に向いた環境でしょう。
③一般事業会社で働く公認会計士の年収
一般事業会社で働く公認会計士の年収は、平均で600〜900万円程度です。上場企業の経理・財務部門では1,000万円を超えるケースも見られます。
会計・監査の専門知識を活かして経営判断に関与できる点が大きなやりがいです。事業会社では、内部監査や経営企画、CFO候補など、経営層に近いポジションでキャリアを積める可能性があります。
安定した勤務環境や福利厚生の充実度も魅力で、結婚や子育てと両立しやすい働き方を選びやすいのも利点です。
ただし、昇進や昇給は企業ごとの評価制度に依存するため、成果がすぐに収入に反映されにくい場合もあります。
スキルアップを目指すなら、MBA取得や海外子会社での勤務を経験し、経営全体を理解する視点を身につけるとよいでしょう。安定と挑戦を両立させたい人におすすめです。
④コンサルティングファームでの年収
コンサルティングファームに転職した場合、年収は700〜1,200万円前後で、成果次第ではさらに高収入を得られます。
M&Aや企業再生、業務改善プロジェクトなど、多岐にわたる案件に携わることができ、実力が直接報酬に反映されやすい環境です。
公認会計士資格を持つことで、財務デューデリジェンスやリスク管理といった高度な分析業務を担当でき、他職種よりも初任給が高めに設定されることもあります。
若いうちから企業の経営層と対話し、実務を通じて経営戦略の本質を学べる点は大きな成長機会です。ただし、成果主義が強いため、常に高いパフォーマンスが求められます。
残業時間も長く、短期間で結果を出すプレッシャーがかかることは避けられません。それでも、自らのスキルを市場価値として磨き続けたい人にとって、最も成長できる舞台でしょう。
⑤独立開業した公認会計士の年収
独立開業した公認会計士の年収は、初年度で300〜500万円前後が一般的ですが、顧問契約を安定的に獲得できれば1,000万円を超えることも可能です。
税務顧問やIPO支援、事業再生など、専門分野に強みを持つことで報酬を大きく伸ばせます。
独立後は営業力と専門知識の両方が求められ、単に会計を処理するだけではなく、顧客の経営課題を解決する姿勢が重要です。
SNSやセミナーを活用して集客し、顧客満足度を高めることがリピーターにつながります。一方で、収入の安定性に欠ける点が最大の課題です。開業初期は固定費がかさむため、計画的な経営が求められます。
自らの裁量で働ける自由さと、結果をすべて自己責任で背負う厳しさが共存する世界です。自分の力でキャリアを築きたいという強い意志がある人にこそ向いています。
引用:
- 厚生労働省「令和5年中に勤務した給与所得者の平均給与(民間給与実態統計調査)」
- EY新日本有限責任監査法人(OpenWork)
- PwC Japan有限責任監査法人(OpenWork)
- アーク有限責任監査法人(OpenWork)
- 太陽有限責任監査法人(OpenWork)
- 公認会計士 年収情報(OpenWork)
公認会計士の年収が高い理由

公認会計士は数ある国家資格の中でも特に高収入が見込める職種です。では、なぜこれほどまでに年収が高いのでしょうか。
ここでは、その背景を多角的に解説します。以下の6つの要素が主な理由とされています。
- 専門性と資格難易度の高さ
- 社会的信頼と責任の重さ
- 昇進・昇格制度の明確さ
- 働き方の柔軟性と収益機会の多様性
- 経済・景気動向の影響を受けにくい点
- 海外・外資案件での報酬水準の高さ
①専門性と資格難易度の高さ
公認会計士は、税務や会計、監査の分野で高い専門性を持つ職業です。試験内容は非常に広範で、合格率は10%前後と難関に位置しています。
そのため、取得者の数が限られており、希少価値が高い人材として扱われます。専門性が高いほど、企業やクライアントからの信頼も厚く、報酬にも直結します。
さらに、会計士の知識は法律改正や国際基準の変更に対応する必要があり、常に最新情報を追う努力が欠かせません。その継続的な学習と知識更新が、専門家としての価値を維持する鍵になっています。
資格取得の難しさに加え、継続的なスキルアップが求められる点が、高年収の根拠といえるでしょう。
②社会的信頼と責任の重さ
公認会計士は、企業の財務情報を監査し、その正確性を社会に保証する専門家です。この役割は極めて重要で、1つの誤りが企業の信用や株主の判断に大きな影響を及ぼす可能性があります。
責任の重さに見合う形で高い報酬が設定されており、それが職業的信頼の証でもあります。また、会計士は「独立性」を重視する職業でもあります。
利害関係から離れ、公平かつ客観的な判断を下すために、高い倫理観と職業意識が不可欠です。この姿勢が社会からの信頼をさらに強化し、専門職としての価値を一層高めています。
社会的使命の大きさこそが、公認会計士の年収を支える背景といえるでしょう。
③昇進・昇格制度の明確さ
大手監査法人や会計事務所では、キャリアステップが明確に設計されています。アソシエイトからスタートし、シニア、マネージャー、シニアマネージャー、そしてパートナーへと昇進していく仕組みです。
それぞれの段階で役割と責任が変わり、成果に応じて年収も着実に上昇します。このような体系的な昇進制度があるため、努力と実績が報われやすく、長期的なキャリアビジョンを描きやすいのも特徴です。
特にパートナー職に到達すれば、年収は1,000万円を超えることが一般的で、業績次第では2,000万円以上を得ることも可能です。
実力主義の文化が浸透しているため、挑戦意欲のある人ほど報酬面で大きな成果を得やすい環境といえるでしょう。
④働き方の柔軟性と収益機会の多様性
公認会計士は、企業に勤める以外にも多様な働き方を選べます。独立して会計事務所を開業するほか、経営コンサルタントやM&Aアドバイザーとして活動するケースも少なくありません。
働き方の自由度が高く、自身のスキルを活かして複数の案件を同時に進めることで、収入を大きく伸ばすことができます。
また、専門性を生かしてセミナー講師や執筆活動を行う人もおり、知識そのものを価値として提供することも可能です。業務範囲が広がるほど、顧問料やプロジェクト報酬などの収益源が増えます。
自分のキャリアを主体的にデザインできることが、公認会計士の高年収を支える要因のひとつになっているのです。
⑤経済・景気動向の影響を受けにくい点
公認会計士の仕事は、景気の変動に左右されにくい安定した性質を持っています。企業が存続する限り、会計・税務・監査のニーズは常に存在し、不況時でも一定の需要が保たれます。
むしろ、経済が不安定な時期ほど、会計の透明性や財務リスク管理が重視されるため、会計士の価値は高まる傾向にあります。
さらに、法定監査などの業務は法律で義務付けられており、景気の影響を受けにくい業務領域です。そのため、雇用や収入の安定性が確保されやすく、長期的に安定したキャリアを築けます。
社会的需要が絶えないことが、公認会計士の報酬を支える強力な基盤となっています。
⑥海外・外資案件での報酬水準の高さ
グローバル化が進む現代において、国際基準(IFRS)や海外子会社の監査対応ができる公認会計士は特に高く評価されます。
外資系企業や海外クライアントを担当する場合、英語力や国際会計の知識が必須となり、その分報酬水準も上昇します。
国際案件を扱える人材は限られているため、希少価値が高く、高額報酬が支払われることが多いのです。
加えて、海外赴任やグローバルプロジェクトへの参加によって、手当や特別報酬が上乗せされるケースもあります。こうした案件では、年収1,500万円を超えることも珍しくありません。
語学力や国際的な感覚を磨くことで、国内だけでなく世界を舞台に活躍できる点も、公認会計士という職業の大きな魅力といえるでしょう。
公認会計士が年収を上げるための方法

就活生にとって、公認会計士という職業は「安定した高収入」のイメージが強いですが、実際にはキャリア形成やスキル次第で年収が大きく変わります。
ここでは、公認会計士が年収を高めるために実践すべき具体的な戦略を6つの観点から解説します。
- 転職によるキャリアアップ戦略
- マネジメントスキルとリーダーシップの強化
- 専門分野・コンサルティングスキルの習得
- 社外監査役・顧問などの副収入機会の活用
- 英語力・国際会計知識の向上
- 人脈形成とネットワーキングの重要性
①転職によるキャリアアップ戦略
年収を上げる最も現実的な方法は、転職によるキャリアアップです。監査法人から一般企業のCFOや経理部門の責任者に転職する場合、年収が1.5倍から2倍に上がることもあります。
特に、M&Aや国際会計基準(IFRS)の知識を持つ会計士は、外資系企業や上場企業から高く評価される傾向があります。
また、転職市場では「即戦力」としての経験値も重視されるため、若いうちから多様な業務に携わることが重要です。
さらに、転職を成功させるためには、業界の動向や求められるスキルを把握し、自身のキャリアを客観的に見直すことが欠かせません。
結果として、転職は単なる職場変更ではなく、キャリアの再設計によって生涯年収を大きく伸ばす有効な戦略となるでしょう。
②マネジメントスキルとリーダーシップの強化
組織内で昇進して年収を上げたい場合、マネジメントスキルの強化が必要不可欠です。会計士としての専門知識だけでは限界があり、チームをまとめ、メンバーを導ける力が求められます。
特に監査法人では、パートナー職に昇格するために、マネジメント能力やコミュニケーション力の高さが評価されます。
自分の成果を上げるだけでなく、チーム全体の生産性を向上させられる人材こそ、上位職への道が開けるのです。また、クライアントとの信頼関係を築く上でも、リーダーシップは欠かせません。
相手の課題を正しく理解し、最適な提案を導く姿勢は高い評価を得ます。管理職を目指すなら、技術者思考から経営的視点へのシフトが重要です。
将来的に独立や経営層を目指す際にも、このマネジメント経験が大きな財産となり、年収アップの可能性をさらに広げることができるでしょう。
③専門分野・コンサルティングスキルの習得
会計士の価値は専門性の深さと広さで決まります。税務や国際会計、M&A、IPO支援などの分野で専門知識を持つと、企業からの需要が高まり、単価も上がります。
加えて、コンサルティングスキルを身につけることで、単なる会計処理担当者から「経営の参謀」へと立場を変えることができます。
さらに、会計士としての専門知識を他分野と組み合わせることで、新たな価値を生み出すことも可能です。
たとえばITやデジタル化の知識を身につければ、DX支援コンサルタントとして活躍の場が広がります。
こうした高付加価値スキルを持つ会計士は、クライアントから直接依頼を受けられる立場になりやすく、独立後も安定した収入を得やすいでしょう。
専門性と戦略性を兼ね備えることが、長期的な収入向上の鍵になります。
④社外監査役・顧問などの副収入機会の活用
副業としての選択肢として、社外監査役や顧問業務を行う会計士も増えています。企業はガバナンスや内部統制を強化するため、経験豊富な会計士を登用する傾向が強まっています。
社外監査役の報酬は1件あたり年間数百万円規模であり、複数社と契約すれば、年収を大きく伸ばすことが可能です。また、経営顧問として企業の成長支援を行う形も人気があり、実績を積むほど報酬は上昇します。
ただし、副収入を得るためには、信頼関係と実績が欠かせません。若手のうちは地道な業務を通じて信頼を築き、業界での評価を高めることが重要です。
加えて、税理士や弁護士など他士業との連携を図ることで、顧問先の紹介や共同案件の機会も増えます。
長期的に見れば、こうした副業活動は単なる収入源ではなく、キャリアの幅を広げる重要なステップとなるでしょう。
⑤英語力・国際会計知識の向上
グローバル経済の中で、公認会計士が高収入を得るためには英語力と国際会計知識が欠かせません。外資系企業や海外子会社を担当する場合、英語での報告や監査対応が必須です。
特にIFRS(国際会計基準)対応の知識を持つ会計士は、国内外で需要が高く、海外赴任や国際プロジェクトのチャンスも増えます。
また、英語を通じてグローバルなビジネス文化を理解することは、単なる語学力の向上にとどまりません。
国際会議や多国籍チームでの協働を経験することで、視野が広がり、より高いレベルの仕事に挑戦できるようになります。
結果として、英語力はキャリアの選択肢を広げ、報酬の上限を引き上げる要素になります。学習コスト以上のリターンが見込める投資といえるでしょう。
⑥人脈形成とネットワーキングの重要性
会計士として長く活躍し、収入を安定的に増やすためには、人脈づくりが欠かせません。会計業務は信頼が基盤の職業であり、紹介や口コミによる案件獲得が多い業界です。
クライアントや同業者との関係を築くことで、新しい仕事の機会や転職情報が自然と入ってきます。特に独立を目指す場合、経営者層とのつながりは将来の顧客基盤を支える重要な財産です。
さらに、勉強会や業界イベントに積極的に参加することで、自分の知名度を高めることもできます。SNSやオンラインコミュニティを活用して専門的な発信を行うのも効果的です。
人脈を広げる努力はすぐに結果が出るものではありませんが、長期的には確実に大きなリターンをもたらします。
スキルや資格に加えて、人とのつながりを育てる姿勢こそが、高収入への最短ルートになるでしょう。
公認会計士になるまでのステップ

公認会計士として活躍するには、試験合格から実務経験まで段階的な努力が欠かせません。ここでは、大学生が目指す際に知っておくべき全体像を、試験内容から登録まで順を追って解説します。
- 公認会計士試験の概要を理解する
- 受験資格と必要条件を確認する
- 学習計画を立てて勉強を開始する
- 専門学校や通信講座を活用する
- 短答式試験と論文式試験に合格する
- 実務補習に参加して経験を積む
- 修了考査に合格して登録手続きを行う
- 公認会計士として実務に就く
①公認会計士試験の概要を理解する
公認会計士試験は、会計や監査の専門家としての基礎力を確認する国家試験です。出題範囲は会計学、監査論、企業法、租税法など多岐にわたります。
短答式試験では理論の正確さとスピード、論文式試験では論理的な思考と表現力が問われます。学問的な理解だけでなく、実際のビジネスの流れを意識した知識も必要です。
試験構成を早い段階で把握しておくことで、どの分野に重点を置くべきかが明確になります。特に初学者は、合格までのプロセスを全体的に理解することで不安が軽減されるでしょう。
まずは「何を、どれくらい学ぶのか」を整理し、長期的な視点で取り組むことが合格への第一歩です。
②受験資格と必要条件を確認する
公認会計士試験は、大学卒業を待たずに受験できます。学歴や年齢に制限がないため、大学在学中から挑戦する学生も増えています。ただし、試験範囲が広く難易度も高いため、早期の準備が成功の鍵です。
合格後には実務経験や補習所での研修、さらに修了考査の合格など複数のステップがあります。
これらを踏まえて、単に「資格を取る」ことではなく「会計士としてどう生きるか」を見据える姿勢が求められます。
将来的にどの分野で活躍したいかを意識しながら学習を進めると、目標が明確になり、モチベーションの維持にもつながるでしょう。
③学習計画を立てて勉強を開始する
公認会計士試験に合格するには、継続的で計画的な学習が欠かせません。まずは試験日から逆算し、1日の勉強時間や科目ごとの学習配分を設定しましょう。
大切なのは、無理のないペースで学び続けることです。最初から完璧を目指すよりも、理解を深めながら段階的にレベルアップしていく方が効果的です。
週単位での目標を設定し、進捗を可視化すると達成感を得やすくなります。苦手科目を放置せず、定期的に復習する習慣をつけることも重要です。
効率だけを重視せず、自分のリズムに合った計画を立てることで、長期的に安定した学習が続けられるでしょう。
④専門学校や通信講座を活用する
独学で合格を目指すことも可能ですが、効率を考えるなら専門学校や通信講座の利用が現実的です。講師による体系的な指導を受ければ、独学では理解しづらい論点もスムーズに習得できます。
さらに、模試やカリキュラムが整備されているため、自分の実力を客観的に把握しやすいのもメリットです。通信講座なら、大学の授業やアルバイトとの両立もしやすく、スキマ時間を活用して学習できます。
費用はかかりますが、情報の正確さや学習効率を考えると十分に価値がある投資といえるでしょう。自分に合ったスタイルを選ぶことで、学びの質が大きく変わります。
⑤短答式試験と論文式試験に合格する
短答式試験では、正確な知識とスピードが求められます。過去問を繰り返し解くことで、出題傾向を把握しながら解答力を磨いていきましょう。
一方、論文式試験では、知識をもとに自分の考えを論理的に展開する力が必要です。特に監査論や企業法では、事例に沿った思考力が問われます。
短答で基礎を固め、論文で応用するという流れを意識することが合格の近道です。勉強時間の配分にも注意し、短答対策と論文対策をバランスよく進めましょう。
どちらの試験も地道な努力の積み重ねが結果につながります。
⑥実務補習に参加して経験を積む
試験に合格した後は、実務補習所での研修に参加します。ここでは、会計事務所や企業での実務経験を通して、理論を現場で活かす力を養います。
講義で学んだ知識を実際の会計処理に結びつけることで、理解がより深まるでしょう。研修は複数年にわたり行われ、専門知識だけでなくチームワークや責任感も育まれます。
社会人としてのマナーやプロ意識を身につける絶好の機会です。この期間に得た実務経験は、今後のキャリア形成において大きな強みとなります。
実務補習を単なる義務ではなく、実践的な学びの場として積極的に活用してください。
⑦修了考査に合格して登録手続きを行う
修了考査は、公認会計士として登録するための最終試験です。これまでの実務経験と知識を総合的に問われるため、幅広い理解が必要です。
単なる暗記では対応できず、実際の業務を想定した判断力や分析力が求められます。合格するためには、過去の演習やケーススタディを通じて思考力を磨くことが効果的です。
試験勉強と並行して、これまでの経験を振り返り、自分の強みや課題を整理しておきましょう。修了考査を通じて得た知見は、今後の実務にも役立ちます。
合格後、日本公認会計士協会への登録を行えば、正式に会計士としての道が開かれます。
⑧公認会計士として実務に就く
登録後は、監査法人、一般企業、コンサルティング会社など、さまざまな職場で働けます。
監査法人では、大企業の監査や上場支援など責任の大きな業務に携わることができ、若いうちから実力を試される環境です。一方、企業の経理部門では経営の意思決定に関わるチャンスもあります。
経験を積めば、独立して自分の事務所を構える道も開かれます。公認会計士は、専門知識と実務経験を活かして長く活躍できる職業です。
働く場所や業務内容によってキャリアの形が大きく変わるため、自分の志向に合った働き方を選ぶことが大切でしょう。
公認会計士の仕事内容

公認会計士の仕事は、企業の会計や経営を支える専門職として幅広い分野にわたります。ここでは、主な6つの業務領域を紹介します。
就活生がそれぞれの仕事内容を理解することで、将来のキャリアをより具体的に描けるでしょう。
- 監査業務の内容と責任範囲
- 会計・税務コンサルティング業務
- M&A・企業再編支援業務
- IPO支援・内部統制アドバイザリー
- 一般企業での経理・財務業務
- 独立開業後の業務内容と案件獲得方法
①監査業務の内容と責任範囲
監査業務は、公認会計士の中心的な仕事であり、企業の財務情報が正確で信頼できるかを検証する重要な役割を担います。
目的は、投資家や取引先、金融機関などの利害関係者に対して、企業の財務状況を客観的に保証することにあります。具体的には、会計処理の妥当性を検討し、財務諸表の数値に不正や誤りがないかを調べます。
内部統制の運用状況や業務プロセス全体を確認することも多く、単なる数字合わせではなく、企業活動の信頼性そのものを支える仕事です。
特に上場企業の監査では、社会的責任が極めて大きく、倫理観と判断力が試されます。責任の重さから緊張感もありますが、企業の全体像を理解しながら経営を支えるやりがいのある職務です。
この業務を経験することで、会計基準の深い理解や分析力、リスク感知能力など、多方面に応用できるスキルが身につきます。結果として、将来は監査以外の分野でも活躍の幅が広がるでしょう。
②会計・税務コンサルティング業務
会計・税務コンサルティング業務は、企業の経営課題を数字の面から分析し、改善策を提案する仕事です。公認会計士は、財務戦略や税務計画の立案を通して、経営者の意思決定を支援します。
主な業務は、資金調達、コスト削減、グループ再編、国際税務など多岐にわたります。例えば、税務上のリスクを抑えつつ事業成長を促すようなスキームを設計するなど、実践的なアドバイスが求められます。
この仕事は、単に数字を扱うだけではなく、企業のビジネスモデルを理解する力が不可欠です。顧客の業界特性を把握し、経営者の課題に寄り添った提案を行うことで、信頼関係を築けます。
さらに、税法改正や国際基準への対応など、常に知識をアップデートする必要があります。知識とコミュニケーションの両面を磨くことで、クライアントの「右腕」として長期的に活躍できるでしょう。
③M&A・企業再編支援業務
M&A(企業の合併・買収)や企業再編支援は、企業が新しい成長を目指すための重要な戦略をサポートする業務です。
公認会計士は、財務デューデリジェンス(対象企業の価値やリスクを調査する業務)や、買収後の統合プロセス支援などを担当します。
具体的には、財務資料や契約書を分析して、潜在的なリスクや課題を洗い出します。その上で、買収価格やスキームの妥当性を判断し、経営陣の意思決定を支えます。
案件によっては、海外企業を対象とすることもあり、国際的な知識が必要になるケースもあります。
この分野では、数字だけでなく、企業文化や事業戦略、経営者の意図を読み取る洞察力が求められます。
企業成長の現場で経営を支えるダイナミックなキャリアを目指す人には非常に魅力的な領域です。
④IPO支援・内部統制アドバイザリー
IPO支援は、企業が株式上場を果たすために必要な会計・内部統制体制を整備する仕事です。公認会計士は、財務面の信頼性を高めるために上場審査基準を理解し、必要な改善提案を行います。
具体的には、会計処理の見直しや上場申請書類の作成支援、上場後を見据えた業務フローの設計などを担当します。
内部統制アドバイザリーでは、不正防止やリスクマネジメントの仕組みを整える役割を担います。
IPO支援は、経営者や証券会社、弁護士など多様な専門家と連携しながら進めるため、高い調整能力と対話力が必要です。また、上場企業になる過程を間近で支援できる点は、大きなやりがいでしょう。
企業が「社会的信用」を得るための基盤づくりを支えるこの仕事は、経営の根幹に関わる責任の大きい職務です。将来的に企業経営やファイナンスの分野で活躍したい人にとって、貴重な経験となります。
⑤一般企業での経理・財務業務
公認会計士が一般企業で経理・財務職として活躍するケースは年々増えています。監査法人で得た専門知識を活かし、企業内部から経営を支えるポジションとして働ける点が魅力です。
主な業務内容は、資金計画の立案、月次・年次決算、税務申告、資金調達のサポートなど多岐にわたります。自社の財務状況を把握し、経営判断の材料を提供する役割を果たします。
また、経営陣に近い立場で数字を分析し、戦略立案にも関わる機会が増えるため、単なる「数字の管理」ではなく「経営参謀」としての視点が必要です。
CFOなど経営層を目指すキャリアパスも開けるでしょう。一方で、監査と異なり自ら会計処理を行う立場になるため、責任はより直接的になります。
安定した組織で専門性を発揮したい人や、企業経営に関心のある人にとって理想的な働き方といえます。
⑥独立開業後の業務内容と案件獲得方法
独立した公認会計士は、自身の事務所を持ち、企業や個人の会計・税務を支援します。業務範囲は、決算支援、税務申告、資金繰りの改善、経営アドバイスなど非常に幅広いです。
独立の大きな魅力は、自分の得意分野を生かして自由に働ける点です。企業向けの顧問契約を中心に活動する人もいれば、スタートアップ支援や事業承継コンサルティングなど専門特化する人もいます。
最近では、クラウド会計やAIツールの普及により、少人数でも効率的な業務運営が可能になりました。場所や時間に縛られず、自分らしい働き方を実現できる環境が整いつつあります。
ただし、案件を安定的に得るためには、営業力と人脈構築が不可欠です。SNS発信やセミナー登壇などで認知を広げる努力が必要でしょう。
成功すれば、自分の理想とするキャリアと生活スタイルを両立できるやりがいのある道です。
公認会計士の仕事の魅力

公認会計士は数字を扱う仕事という印象を持たれがちですが、実際には企業経営や社会の信頼を支える重要な役割を担っています。
ここでは、就活生が特に気になる「専門性・キャリア・収入・将来性」など、6つの魅力をわかりやすく紹介します。
- 高い専門性と社会的信頼性
- 多様なキャリアパスの存在
- 安定した収入と将来性
- グローバルに活躍できるチャンス
- 経営者や企業との近い関係性
- スキルが他分野でも活かせる汎用性
①高い専門性と社会的信頼性
公認会計士は、企業の財務情報を正確に分析し、社会全体の信頼を支える専門家です。国家資格の中でも難易度が高く、合格までに長い学習期間と努力が必要になります。
その過程で得られる知識や分析力は、他の職業では身につけにくい強みとなるでしょう。資格取得後も、法改正や会計基準の変化に対応するため、継続的な学習が欠かせません。
こうした積み重ねが高い専門性を生み、社会的な信用を確かなものにします。経営者や金融機関など、重要な立場の人々から信頼を得ることも多く、ビジネスの現場で発言力を持てる点も大きな魅力です。
努力がそのまま評価につながる職業といえます。
②多様なキャリアパスの存在
公認会計士の資格を手にすると、監査法人でのキャリアにとどまらず、コンサルティングや税務、金融、経営企画など、幅広い分野で活躍できます。
たとえば、企業のM&A支援、スタートアップの財務アドバイザー、海外事業の監査など、専門知識を生かした選択肢が豊富です。近年は企業内会計士として経営戦略に関わる人も増えています。
数字を読み解くだけでなく、経営の意思決定を支えるスキルを持つ人材として重宝されるでしょう。キャリアが一つの方向に固定されないため、自分の興味や強みに合わせて柔軟に道を選べます。
変化の激しい時代でも、自分らしいキャリアを築ける職業です。
③安定した収入と将来性
公認会計士の平均年収はおおむね600〜1000万円程度で、年齢や経験によってさらに上昇します。20代で年収500万円台に達することも多く、努力が早い段階で報われやすい点が魅力です。
監査法人勤務時代は安定した給与体系が整っており、一定の経験を積んで独立すれば、顧客数や案件によって年収が2倍以上になることもあります。
また、AIや自動化の進展によっても、公認会計士の需要がなくなることはありません。会計判断やリスク評価には人の専門知識が不可欠だからです。
経済情勢に左右されにくく、長期的に安定して働ける点も大きな安心材料といえるでしょう。
④グローバルに活躍できるチャンス
会計の国際基準(IFRS)が普及するなかで、公認会計士には海外での活躍の場も広がっています。英語力を磨けば、国際監査業務や外資系企業への転職など、グローバルなキャリアを築くことができます。
また、日本企業の海外進出支援や、現地法人の会計管理に携わるチャンスも少なくありません。会計の専門知識は世界共通の言語といわれ、国境を越えて求められるスキルです。
実際、海外で活躍する日本人会計士も増えています。資格を活かして世界に挑戦したい人にとって、公認会計士は最適な選択肢でしょう。視野を広げることで、自分の市場価値も大きく高まります。
⑤経営者や企業との近い関係性
公認会計士は、単に数字を扱うだけでなく、経営者の良き相談相手として企業運営に深く関わります。財務諸表の監査や経営判断の助言を通じて、企業の課題解決を支援する存在です。
特に、経営者と直接やり取りする機会が多く、若手のうちから経営感覚を磨けます。信頼を積み重ねれば、企業の顧問や社外取締役として活躍する道も開かれるでしょう。
企業の成功を支える責任の重い立場ではありますが、その分やりがいも大きいです。自分の専門知識が経営判断に影響を与えるという実感を得られるのは、公認会計士ならではといえます。
⑥スキルが他分野でも活かせる汎用性
公認会計士が身につけるスキルは、会計業務にとどまりません。財務分析やリスク評価、論理的思考力は、経営企画やコンサルティング、金融業界などさまざまな分野で応用できます。
数字をもとに物事を整理し、課題を発見して改善策を提案する力は、どの業界でも重宝されるでしょう。また、プレゼンテーション能力やコミュニケーション力も高く評価されます。
監査法人を離れてもキャリアの選択肢が豊富で、転職市場でも強みを発揮できます。専門性と汎用性を兼ね備えた職業だからこそ、将来の変化に柔軟に対応できるのです。
長く価値を持ち続けるスキルを磨ける職業といえるでしょう。
公認会計士の仕事の大変さ

公認会計士は高収入で安定した職業として知られていますが、その裏では多くの努力と責任を背負っています。
資格取得までの長い勉強期間、繁忙期の激務、そして一つのミスが大きな影響を与える責任の重さなど、就活生が想像する以上のプレッシャーがある職種でしょう。
ここでは、公認会計士の仕事の大変さを具体的な視点から紹介します。
- 資格取得までの勉強負担
- 繁忙期の長時間労働
- ミスが許されない責任の重さ
- クライアント対応のプレッシャー
- チームマネジメントの難しさ
- キャリア維持のための継続的学習負担
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①資格取得までの勉強負担
公認会計士になるには、まず難関試験を突破しなければなりません。多くの人が3〜5年をかけて勉強しており、大学生活の多くを試験対策に費やします。
学ぶ範囲は会計・監査・税務・経営など幅広く、理解力や論理的思考力、継続力が求められます。特に大学の授業やアルバイトと両立するのは簡単ではなく、強い意志と計画性が必要です。
途中で挫折する人もいますが、合格後には専門職としての安定したキャリアと社会的信用を得られるでしょう。
効率的に学習を進めるには、通信講座や予備校をうまく活用し、自分に合った学習スタイルを確立することが大切です。焦らず地道に積み重ねていく姿勢こそが合格への近道です。
②繁忙期の長時間労働
公認会計士の業務は季節によって大きく波があります。特に3月決算の企業が多いため、年明けから春にかけては監査や決算対応に追われ、深夜残業が続くことも少なくありません。
提出期限が厳格に決まっているため、短期間で大量のデータを精査する集中力が必要です。一方で、繁忙期を乗り越えれば夏や秋には比較的ゆとりのある時期も訪れ、長期休暇を取ることもできます。
忙しい中でも健康管理を怠らず、効率よく仕事を進める工夫をすることが大切です。チーム内での分担やツールの活用により、無理なく乗り切ることができるでしょう。
季節ごとのリズムを理解しておくと、心身のバランスを保ちやすくなります。
③ミスが許されない責任の重さ
会計士の仕事では、扱う数字の一つひとつが企業の経営や株主の判断に直結します。そのため、小さな誤りでも信頼を失うおそれがあり、常に高い緊張感の中で業務を行う必要があります。
確認やレビューの体制を整えることはもちろん、自分の判断に自信を持てるよう知識を深める努力が欠かせません。ミスを防ぐためには、チームでの情報共有や二重チェックの習慣化が有効です。
また、慎重さばかりでなく、限られた時間の中で正確に仕事を進めるスピードも求められます。
責任の重さに押しつぶされそうになることもありますが、自分の仕事が社会や企業を支えているという誇りが、日々のモチベーションにつながるでしょう。
④クライアント対応のプレッシャー
公認会計士は、数字だけでなく人とも深く関わる職業です。クライアント企業の経営層と直接やり取りを行い、専門的な意見をわかりやすく伝える力が求められます。
時には厳しい質問や短い納期での依頼に直面することもありますが、冷静に対応する姿勢が信頼構築の鍵です。
専門用語を並べるだけではなく、相手の立場や理解度を意識して説明することで、円滑な関係を築けます。また、クライアントごとに業界特性や経営方針が異なるため、柔軟な対応力も必要です。
単に監査をこなすだけでなく、経営課題を共に考えるパートナーとしての姿勢を持つことで、感謝やリピートにつながるでしょう。誠実な対応を重ねることで、あなた自身の評価も自然と高まります。
⑤チームマネジメントの難しさ
公認会計士として経験を積むと、チームを率いる立場になることが増えます。後輩への指導や業務の割り振り、進捗管理、上司への報告など、多面的なマネジメント力が求められます。
特に繁忙期にはメンバーの負担が偏りがちで、モチベーションの低下やミスの増加を防ぐための調整が重要です。
リーダーは、チーム全体の雰囲気を読み取り、時に励まし、時に的確な指示を出さなければなりません。また、自分も現場での実務をこなしながらマネジメントを行うため、時間配分も難しいものです。
しかし、全員で協力して成果を出せたときの達成感は格別です。リーダーとしての経験は、将来のキャリアアップや独立にも大きく役立つでしょう。
⑥キャリア維持のための継続的学習負担
公認会計士の資格を取得しても、学びは終わりません。会計基準や税制は頻繁に改正されるため、常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。
実務の中で新しい知識を吸収することも多いですが、研修やセミナーへの参加、専門書の読解など、自己研鑽を続ける努力が欠かせません。
多忙な中でも学びを継続できる人ほど、信頼される専門家として成長していきます。特にグローバル化が進む現在では、英語や国際会計基準(IFRS)への理解も重要です。
こうした学習を続けることで、キャリアの幅が広がり、独立や海外での活躍といった可能性も見えてくるでしょう。継続的な努力こそが、公認会計士としての価値を高める最大の武器です。
公認会計士のキャリアと生涯年収の全体像を知っておこう!

公認会計士は、高い専門性と社会的信頼を背景に安定した収入を得られる職業です。
平均年収は他の士業に比べても高く、BIG4監査法人やコンサルティングファーム、一般企業、さらには独立開業など勤務先によって生涯年収は大きく変動します。
特に、専門スキルや英語力の向上、人脈形成、転職戦略などを駆使することで、年収アップのチャンスは広がります。
さらに、資格取得までの努力や責任の重さはあるものの、その分リターンも大きく、長期的に見て経済的安定とキャリアの自由度を両立できる点が魅力です。
つまり、公認会計士は「努力が確実に報われる」職業であり、生涯を通じて高い年収と成長を実現できる可能性を秘めています。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。