駅員の平均年収と仕事内容を徹底解説|企業別・職種別に比較
鉄道会社で働く駅員は、日々の安全運行を支える重要な存在です。早朝から深夜まで勤務することもあり、責任の重い職種として知られていますが、その分、安定した給与や充実した福利厚生も魅力です。
そこで本記事では、企業別・職種別の平均年収や仕事内容、手当の内訳まで詳しく解説します。これから鉄道業界を目指す方や、転職を検討している方はぜひ参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
駅員とは?

駅員とは、鉄道会社に所属し、駅での運行を支える大切な職種です。主な仕事は改札業務や切符の販売、乗客への案内、安全確認など多岐にわたります。
駅という多くの人が行き交う場所で、スムーズかつ安全な運行を保つことが使命といえるでしょう。
特に混雑時やトラブルが起きたときには、冷静な判断力と的確な対応が欠かせません。つまり、駅員は単に「改札に立つ人」ではなく、駅全体の運営を支える専門職です。
勤務はシフト制で、早朝や深夜の時間帯に及ぶこともあります。その分、公共交通を支える社会的な意義の高さとやりがいを実感できる仕事といえるでしょう。
近年では、駅のバリアフリー化や外国人観光客への対応など、サービスの幅も広がっています。駅員は交通の要を担い、人と社会をつなぐ安心の象徴といえる存在です。
駅員の平均年収はいくら?

ここでは、公的統計などをもとに駅員の平均年収や給与の特徴、昇給の流れをわかりやすく解説します。
駅員の平均年収はおおよそ400万円前後です。新卒の初任給は18〜22万円ほどで、勤続年数に応じて着実に昇給していきます。
30代では年収が450万円前後となり、40代で500万円を超える人も増えていきます。夜勤や早朝勤務などの手当が加算されるため、勤務形態によっては基本給よりも実際の手取り額が高くなる傾向です。
駅員の給与には基本給のほかに、夜勤手当、通勤手当、住宅手当、家族手当などが含まれています。とくに夜勤手当の割合が高く、勤務回数が多いほど収入に反映される仕組みです。
また、賞与(ボーナス)は年2回の支給が一般的で、年間で2〜4ヶ月分程度が支給されます。基本給だけではなく、これらの手当や賞与を含めた総支給額で比較することが大切です。
引用:
企業別に見る駅員の平均年収と特徴

就活生がよく調べる「駅員の年収」は、企業や部門・年次で大きく変わります。ここでは、主要鉄道会社を例に、駅員や現業職レベルでの相場感と企業別の特徴を整理しました。
働く場所や企業体質を意識することで、自分に合う志望先を選びやすくなるはずです。
- JR東日本
- JR西日本
- JR東海
- 東京メトロ
- 近畿日本鉄道(近鉄)
- 東武鉄道
- 小田急電鉄
- 名古屋鉄道(名鉄)
- 西武鉄道
- 阪急電鉄
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①JR東日本|国内最大規模の鉄道会社で安定した高水準の給与体系
JR東日本の有価証券報告書によれば、2024年3月期の平均年収は約725万円(平均年齢38.6歳)とされています。
これは管理職や技術職を含む全社員ベースの数値で、駅員や現業職ではこれよりもやや低くなる傾向があります。
同社の特徴は、給与水準が安定しており、勤続年数に応じた昇給や賞与制度がしっかり整っている点です。長期的に収入を伸ばしたい人にとって魅力があります。
一方で、首都圏勤務やシフト勤務、夜勤が多くなるため、生活リズムの管理が課題になることもあります。責任感を持ち、安定と成長を重視する人に適した環境です。
②JR西日本|地域密着と安定した働き方を両立できる企業
JR西日本の平均年収は約492万円とされており、福利厚生や手当制度が比較的充実しています。地域密着型の運営を掲げており、地元志向の社員が多いことが特徴です。
地方勤務や深夜シフトなど勤務形態の多様性が求められる一方で、社員同士の連携が強く、安定的に働ける雰囲気があります。
特に、長く地元で働きたい人や生活基盤を安定させたい人には好ましい職場でしょう。地域社会との関わりを持ちながら、腰を据えてキャリアを築きたい人に向いています。
③JR東海|新幹線運行を担う高収入・技術志向の企業
JR東海の平均年収は760万円前後とされ、鉄道業界でも高水準に位置しています。新幹線を中心とした運行を担うため、安全性と正確性が最も重視される環境です。
駅員も新幹線関連業務に関わることが多く、専門知識や高い判断力が求められます。研修制度が整っており、スキルを磨きながら昇進を目指すことができます。
高収入を目指す人や、技術・安全意識の高い職場で働きたい人に適した企業といえるでしょう。採用倍率は高いものの、その分やりがいも大きい職場です。
④東京メトロ|都市型鉄道で高利用率・高負荷環境
東京メトロの駅員平均年収は約460万円前後とされています。首都圏の中心を走るため、利用者数が多く、日々の業務は多忙です。
残業代や夜勤手当がしっかり支給される点が魅力で、勤務時間に応じた適切な報酬が期待できます。業務内容は運行管理、案内、トラブル対応など多岐にわたり、常に迅速で正確な判断が求められます。
忙しさの中で自分の力を試したい人、都市の中心で成長したい人に向いた職場といえるでしょう。
⑤近畿日本鉄道(近鉄)|私鉄大手で多様なキャリアが描ける
近鉄は関西最大規模の私鉄で、平均年収は500万〜600万円前後とされています。運行範囲が広く、駅員業務に加えて運行管理や観光列車対応など多様なキャリアパスがあります。
長期的に働く社員が多く、福利厚生や手当の充実度も高い水準です。地域に根ざした経営方針のもと、地元出身者の採用も多く、家庭との両立を支援する制度も整っています。
安定した環境で着実にキャリアを積みたい人におすすめの企業です。
⑥東武鉄道|関東広域をカバーする地域密着型企業
東武鉄道の給与水準は関東大手私鉄の平均に近く、およそ500万円前後と見られます。沿線が広く、地域ごとに特色の異なる駅業務を担当します。
業務は接客を中心に、安全確認や運行支援など幅広い内容を含みます。地域との関係性を重んじる社風で、地元イベントへの参加なども多く、人と関わることが好きな人に向いています。
安定と社会貢献を両立できる働き方ができるでしょう。
⑦小田急電鉄|都市近郊型の働きやすさと安定を重視
小田急電鉄の平均年収は500万円前後で、生活の利便性が高いエリアに勤務できる点が魅力です。シフト調整や休暇取得がしやすく、ワークライフバランスを保ちやすい職場環境が整っています。
また、接客スキルを生かして観光やイベント対応にも関わる機会があります。繁忙期には勤務時間が伸びることもありますが、働く人の声を反映した制度が進んでおり、安定した働き方を望む人に最適です。
⑧名古屋鉄道(名鉄)|地元密着と安定感を重視する企業
名鉄は中部地方を代表する私鉄で、平均年収は500万〜600万円台と推定されます。地元採用が多く、転勤リスクが低い点が大きな魅力です。
駅員業務は接客や安全管理が中心で、経験を積むと運行管理や教育担当などへステップアップできます。地域密着型の企業風土が強く、人間関係も穏やかな職場が多い傾向にあります。
安定した生活を送りたい人に向いた企業です。
⑨西武鉄道|観光対応や多様な業務でキャリアを広げられる
西武鉄道の駅員年収は450万〜500万円程度とされ、観光路線を多く抱える点が特徴です。
季節によって業務内容が変化し、観光客への案内業務やイベント運営に関わることもあります。
福利厚生が整っており、住宅手当や家族手当など生活面のサポートも充実しています。
観光業と公共交通の両方に関心がある人にとって、やりがいのある企業です。
⑩阪急電鉄|ブランド力と社員満足度の高い老舗私鉄
阪急電鉄は関西の老舗私鉄で、平均年収は400万円前後とされています。ブランドイメージと高い接客品質が特徴で、駅員は企業の「顔」として丁寧な応対が求められます。
昇進制度が明確で、長期的に働く人が多い点も特徴です。給与の伸びは緩やかですが、安定性や働きやすさを重視する人にとって魅力のある企業といえるでしょう。
引用:
- JR東日本 有価証券報告書・IR情報
- JR東日本 平均年収725万円(talentsquare)
- JR西日本 平均年収492万円(OpenWork)
- JR東海 平均年収760万円(OpenWork/有価証券報告書)
- 東京メトロ 駅員年収459〜471万円(OpenWork)
- 近鉄 年収傾向(OpenWork)
- 東武鉄道 平均年収594万円(OpenWork)
- 小田急電鉄 年齢別年収(OpenWork)
- 名鉄 年齢別年収(OpenWork)
- 西武鉄道 年収例500万円(OpenWork)
- 阪急電鉄 平均年収387万円(OpenWork)
職種別に比較!駅員・運転士・車掌の年収差

鉄道業界では、同じ会社に所属していても職種によって年収にかなり差が出ます。駅員・運転士・車掌・駅長・整備士・運行管理者など、それぞれの役割と責任が異なるからです。
ここでは主要な職種ごとの平均年収と特徴を、公的統計や企業データを基に比較・解説します。
- 運転士
- 車掌
- 駅長
- 整備士
- 運行管理者
①運転士
運転士の平均年収は500万〜600万円ほどで、駅員よりも高めの水準です。列車の安全運行を担うため、責任の重さに見合った待遇が与えられています。
運転士になるには、駅員などの現場経験を積み、社内試験や国家資格を取得しなければなりません。技術力と集中力が求められる一方で、運転中は単独行動が多く、黙々と仕事を進めたい人に適しています。
ダイヤ通りに列車を動かす緊張感はありますが、その分やりがいも大きいでしょう。特に新幹線や特急を担当する運転士は、さらに高い年収を得られる可能性があります。
②車掌
車掌の平均年収は450万〜550万円ほどで、駅員と運転士の中間に位置します。主な業務は列車の案内、安全確認、ドアの開閉操作などで、乗客の安全を直接守る重要な役割です。
列車遅延やトラブル発生時には迅速な判断力が求められ、精神的な強さも必要になります。接客面の比重が大きく、笑顔や丁寧な言葉遣いが評価されるでしょう。
車掌として経験を積んだ後、運転士へ昇進するルートもあり、キャリアの幅を広げやすい職種です。人とのやり取りが得意で、緊張感のある環境で働きたい人におすすめします。
③駅長
駅長の平均年収は700万〜900万円と高水準で、鉄道現場の管理職として大きな責任を担います。駅全体の運営管理、スタッフの育成、地域との連携など、幅広い業務を統括するポジションです。
これまでの現場経験を生かし、チームをまとめるリーダーシップが必要になります。駅の規模や乗降客数によって年収は変動し、主要駅ほど報酬が高い傾向にあります。
長年のキャリアを経て到達する職位のため、安定した地位と収入を得たい人にとって理想的な目標といえるでしょう。
④整備士
整備士の平均年収は400万〜500万円で、車両や設備の安全を裏側から支える技術職です。列車の定期点検や修理を行い、故障を未然に防ぐことが求められます。
勤務は夜間や休日を含むことも多いものの、手に職をつけられる安定性が魅力です。電気や機械の専門知識を持つ人は重宝され、資格手当で収入が上がる場合もあります。
現場での経験を積み、将来的には整備主任や管理職へとステップアップすることも可能です。技術志向が強く、ものづくりに興味がある人に向いた仕事でしょう。
⑤運行管理者
運行管理者の平均年収は500万〜600万円ほどで、列車の運行計画や安全管理を担う要職です。ダイヤ作成や運転士・車掌の勤務調整、トラブル発生時の対応など、全体を統括する立場にあります。
現場に出ることは少ないものの、高い判断力と冷静さが欠かせません。駅員や運転士としての経験を経て管理部門に進むケースが多く、鉄道業界を支える重要な裏方として活躍します。
安定した収入とワークライフバランスを両立したい人に向いている職種といえるでしょう。
引用:
- 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
- OpenWork「駅員の年収情報」
- OpenWork「東日本旅客鉄道(JR東日本)」
- OpenWork「西日本旅客鉄道(JR西日本)」
- OpenWork「東京地下鉄」
- OpenWork「東海旅客鉄道(JR東海)」
駅員の基本給・手当・残業代の内訳

駅員の給与は、基本給に加えて各種手当や残業代が重なって成り立っています。
求人票に記載された額だけで「高収入かどうか」を判断すると誤解しやすいため、どの要素が年収に影響を与えるかを知っておくことが肝心です。ここでは、駅員の収入構成を以下の視点で解説します。
- 基本給と給与テーブルの仕組み
- 各種手当(深夜・住宅・家族・通勤など)
- 残業代・休日出勤手当の支給実態
①基本給と給与テーブルの仕組み
駅員の基本給は、勤続年数・職位・役割などに応じた給与テーブルに基づいて決定されます。
多くの鉄道会社では、新卒の初任給が20万円前後という情報が見られ、そこから年次昇給や役職昇格で引き上げられるケースが一般的です。
社員数10人以上の企業では、運転士の平均年収がおよそ630万円程度とされており、一定の安定性が見込めます。
ただし、基本給の伸び率や昇格制度には各社の差があります。都市部を拠点とする大手鉄道会社では、昇給幅や役職手当が手厚く設計されていることが多いです。
給与体系が明確な企業ほど、将来設計を立てやすく安心して働けるでしょう。
②各種手当(深夜・住宅・家族・通勤など)
駅業務には深夜勤務がつきものです。深夜時間帯の勤務には深夜勤務手当が加算され、1日あたり数千円程度が支給されるケースもあります。
住宅手当や家族手当も支給されることが多く、扶養家族数や勤務場所によって金額が変動します。通勤手当は全額支給という会社が一般的ですが、上限が設けられている場合もあります。
これらの手当は勤務先の会社規模・地域・労働条件で大きく変わるため、手当込みで年収を計算する必要があります。基本給だけを見て「給与が低い」と結論づけないよう注意が必要です。
実際には、残業や深夜手当を含めると、手取り額が大幅に上がることも珍しくありません。
③残業代・休日出勤手当の支給実態
駅員はシフト制で働くため、残業や休日出勤が発生しやすい職場です。鉄道会社では労働時間管理が比較的厳格なところも多く、法定時間を超える労働には残業代が支払われる仕組みになっています。
残業代単価は基本給をベースにし、深夜時間帯には割増率が適用されます。
ただし、ダイヤの乱れ対応や事故対応、突発事項による勤務増などで、月ごとの残業時間が大きく変動することもあります。
休日出勤がある場合には振替休日制度や休日手当で調整されることが多いです。労務管理の透明性が高い企業を選ぶことで、働いた分が正当に評価される安心感を得られるでしょう。
引用:
駅員の仕事内容

駅員の仕事は、駅を安全で快適に利用できるよう支える大切な役割です。日々の運行を支えるため、改札・ホーム・案内・放送など、さまざまな業務を分担して行います。
ここでは、駅員が担当する主な仕事内容を順に見ていきましょう。
- 改札業務
- ホーム業務
- 案内業務
- 放送業務
- 安全管理業務
- 遺失物対応業務
- 切符販売・精算業務
- 駅構内清掃・美化業務
①改札業務
改札業務は駅員の代表的な仕事であり、乗客がスムーズに入出場できるよう支える役割を担っています。
自動改札機のトラブル対応や切符・定期券の確認、忘れ物の受け渡しなど、細やかな接客が求められます。混雑時には的確な判断と冷静な対応が欠かせません。
さらに、改札付近はトラブルが発生しやすい場所でもあります。機械の誤作動、切符の紛失、乗り越し精算など、短時間で適切に判断する力が問われます。
時には外国人観光客や高齢者など、異なる背景を持つ人々への配慮も必要です。そのため、改札業務はコミュニケーション能力と柔軟性を養う絶好の経験の場といえるでしょう。
駅員としての基本動作を身につけるための登竜門でもあります。
②ホーム業務
ホーム業務では、列車の安全な発着を支えることが最も重要です。乗客の乗降を確認し、ドアの開閉を補助しながら、列車が安全に発車できるよう注意を払います。
特に朝夕のラッシュ時にはホームが混雑し、転落や接触事故を防ぐための瞬時の判断が必要です。安全確認を怠ると重大な事故につながるため、常に緊張感を持って業務にあたる姿勢が欠かせません。
また、ホーム業務は観察力が問われる仕事でもあります。小さな異変を見逃さず、異常を発見した際には車掌や指令室と迅速に連携します。
加えて、体調を崩した乗客への応急対応や、列車遅延時の乗客案内など、臨機応変な対応も求められます。
単調に見える作業の中にも、安全と信頼を守る使命感があり、社会的責任を実感できるやりがいのある仕事です。
③案内業務
案内業務は、駅を訪れる人々が安心して目的地に向かえるよう支援する仕事です。乗り換えの方法、運行状況、観光案内、バリアフリー設備の場所など、質問の内容は多岐にわたります。
利用者の立場に立ち、わかりやすく説明する力が求められます。外国人観光客が多い駅では、英語や中国語などの語学力が大きな強みになるでしょう。
さらに、案内業務は「人と関わる力」を磨ける職種でもあります。相手の状況を瞬時に理解し、最適な提案をすることで信頼関係を築けます。
ときにはクレーム対応を行うこともありますが、冷静で誠実な対応が評価につながります。人に感謝される機会が多く、自身の成長を実感しやすいのも魅力のひとつです。
駅の“顔”として利用者の不安を解消する、やりがいのあるポジションです。
④放送業務
放送業務は、構内アナウンスを通じて乗客に正確な情報を伝える大切な仕事です。列車の到着や遅延、乗り換え案内、緊急時の避難誘導などを放送し、混乱を防ぎます。
短時間で状況を把握し、明瞭な言葉で伝えるスキルが必要です。声のトーンや話すスピードひとつで駅全体の雰囲気が変わるため、落ち着いた発声と正確な発音が求められます。
また、放送業務には責任感と判断力が不可欠です。マニュアルに沿って進めるだけでなく、突発的な事態にも柔軟に対応しなければなりません。
たとえば、列車の遅延が発生した際は、利用者が混乱しないよう丁寧な言葉で案内する必要があります。情報を通して安心を届ける放送業務は、駅の安全運行を陰で支える重要な役割です。
⑤安全管理業務
安全管理業務は、駅の安全を守る中心的な役割を担います。ホームや線路、構内設備の点検、不審物の確認、設備の破損チェックなどを行い、事故を未然に防ぎます。
安全管理は、駅運営の根幹を支える仕事といえるでしょう。夜間や悪天候時には特に警戒を強め、異常があれば迅速に報告します。
この業務では、慎重さと冷静さに加えて、状況判断力が必要です。たとえ小さな異変でも見逃さず、問題が起きる前に対処する姿勢が求められます。
定期的な安全点検や設備整備を通じて、乗客が安心して駅を利用できる環境を守ることが目的です。目立たない仕事ですが、駅員全体の信頼を支える縁の下の力持ちとして誇りを持てる職務です。
⑥遺失物対応業務
遺失物対応業務は、駅構内で拾われた落とし物を管理し、持ち主に返す仕事です。拾得物の内容を確認して記録を残し、警察や他駅との情報共有を行います。
中には財布やスマートフォンなど個人情報を含むものも多く、正確で丁寧な処理が必要です。遺失物の種類や数は日によって異なるため、柔軟な対応力が求められます。
また、この業務は利用者の感謝を直接受け取れる数少ない業務のひとつです。誠実で迅速な対応によって信頼を得ることができ、仕事の達成感を味わいやすいでしょう。
人の大切な持ち物を取り扱うため、細心の注意と責任感が欠かせません。丁寧な仕事を積み重ねることで、駅全体のサービス品質向上にも貢献できる業務です。
⑦切符販売・精算業務
切符販売・精算業務は、有人窓口や自動精算機で乗客をサポートする仕事です。乗り越し精算や特急券・定期券の発行、払い戻しなど、幅広い手続きを扱います。
正確な金銭管理が求められるため、注意深く作業を進める必要があります。特に混雑時にはスピードと正確さの両立が求められ、集中力が欠かせません。
さらに、料金体系や乗車区間制度を理解しておくことで、利用者からの質問にもスムーズに対応できます。初めは複雑に感じることもありますが、経験を重ねることで計算能力や応対力が向上します。
利用者に「ありがとう」と言われる瞬間が多く、やりがいを感じやすい業務です。事務処理と接客の両面で力を発揮できるポジションでしょう。
⑧駅構内清掃・美化業務
駅構内清掃・美化業務は、駅を清潔で快適に保つための仕事です。床やトイレ、ベンチ周り、ゴミ箱の清掃など、見えないところまで丁寧に手を入れます。
駅は多くの人が利用する公共の場であり、少しの汚れでも印象が変わります。清掃を徹底することで、利用者に安心感を与えることができるのです。
この業務では、継続的な努力と細やかな気配りが大切です。毎日の積み重ねが駅の美観を保ち、利用者の快適な移動を支えます。
朝の清掃で整った構内を見た瞬間、やりがいを感じる駅員も少なくありません。清潔な環境は駅全体の印象を向上させ、信頼される鉄道サービスの基盤となります。
駅員に求められる能力・スキル

駅員として働くうえで大切なのは、毎日の運行を安全で円滑に進めるための総合的な力です。接客や緊急対応など、幅広い業務を担うため、社会人としての基礎力と瞬時の判断力が求められます。
ここでは、駅員に必要とされる主な能力やスキルをわかりやすく紹介します。
- コミュニケーション能力と接客対応力
- 緊急時の判断力と行動力
- 体力・ストレス耐性
- 安全意識と責任感
- チームワークと協調性
- マルチタスク処理能力
①コミュニケーション能力と接客対応力
駅員の仕事は、利用者との関わりが中心です。切符の案内や乗り換えのサポート、トラブルの対応など、あらゆる場面で人と接する機会が多くあります。
そのため、相手の話を丁寧に聞き取り、正確で分かりやすい言葉で説明する力が欠かせません。特に高齢者や観光客など、事情が異なる利用者への対応では、思いやりと柔軟性が必要になります。
また、混雑時やクレーム対応では、感情的にならずに冷静に対応する力が求められます。小さな言葉遣いや表情の違いが、利用者の印象を大きく左右するからです。
経験を重ねることで、状況を素早く判断し、最適な対応を取れるようになります。利用者が安心して駅を利用できるよう、相手の立場に立って行動することが信頼を築く鍵といえるでしょう。
②緊急時の判断力と行動力
駅では、いつ何が起こるかわかりません。人身事故や急病人の発生、機械トラブルなど、想定外の事態に直面することも多いです。
その際に必要なのが、瞬時に状況を把握し、冷静に対応できる判断力と行動力です。例えば、救急要請のタイミングを誤ると被害が拡大する可能性があります。
駅員一人ひとりの判断が、乗客の安全を左右することを常に意識しなければなりません。
さらに、緊急対応ではチームとの連携も重要です。自分一人で解決できない場合は、速やかに周囲へ指示や連絡を行う必要があります。
平常時から訓練を重ね、緊急時の対応手順を体で覚えておくことで、焦らずに行動できるようになるでしょう。柔軟な発想と冷静な判断を兼ね備えた駅員こそ、現場で最も信頼される存在です。
③体力・ストレス耐性
駅員の仕事は、一日を通して立ちっぱなしの業務が多く、体力を必要とします。朝早くから深夜までのシフト勤務や、休日出勤が発生することもあり、体調管理の難しさを感じる人も少なくありません。
体をしっかり休め、バランスの取れた食事を意識することが、長く働くための基本です。
さらに、精神的なタフさも求められます。混雑時のプレッシャーや、クレーム対応、遅延対応など、ストレスがかかる場面が日常的にあります。
そのため、気持ちの切り替えが上手な人ほど、この仕事に向いているといえるでしょう。ストレス耐性を高めるには、趣味や運動などでリフレッシュする習慣を持つことも効果的です。
健康な心と体を維持できれば、いつでも安定した対応ができる駅員として信頼されるでしょう。
④安全意識と責任感
鉄道の運行において、最優先されるのは安全です。駅員の一つひとつの動作が、多くの乗客の命を守ることにつながっています。
ホーム点検や放送案内、列車出発時の確認など、一見単純に見える作業も安全の根幹を支える重要な役割です。だからこそ、どんなに忙しいときでも手を抜かず、確認を怠らない姿勢が求められます。
また、責任感の強さはミスを防ぐ力にもなります。たとえ小さな異変でも「これくらい大丈夫」と思わず、すぐに報告・対応する意識を持つことが大切です。
日常の業務を積み重ねることで、自然と危険を察知する感覚も磨かれていきます。自分の判断一つが安全を左右するという意識を持ち続けることが、駅員としての誇りを築く土台になるでしょう。
⑤チームワークと協調性
駅業務は、一人では成り立ちません。改札、ホーム、事務など、それぞれの持ち場で多くの職員が連携しながら動いています。
特にトラブル対応や遅延時には、情報共有のスピードが成果を大きく左右します。チームワークを重視し、相手の意見を尊重する姿勢が大切です。
協調性の高い人は、チーム全体を落ち着かせることができます。自分の仕事に集中するだけでなく、仲間の動きを見てサポートする姿勢が信頼につながります。
新人のうちは、先輩の行動をよく観察し、積極的に質問することが成長の近道です。仲間と協力しながら働くことで、現場の一体感が生まれ、利用者にも安心感を与えられるでしょう。
チームで成果を出せる人ほど、長く活躍できる駅員といえます。
⑥マルチタスク処理能力
駅員は、同時に複数の業務をこなす必要があります。改札での対応をしながら放送を行い、さらにホームの混雑状況を確認するなど、常に周囲への注意が欠かせません。
そのため、優先順位を素早く判断し、効率的に動くマルチタスク力が求められます。
この能力は、現場での経験によって磨かれていきます。業務を単なる作業としてこなすのではなく、「いま最も必要な行動は何か」を意識することで、判断の精度が高まります。
焦ってミスをするのではなく、冷静に順序立てて対応できる人ほど、チームからの信頼も厚くなります。
さまざまな業務を同時にこなす力は、駅員としての総合力を示す指標です。柔軟に動ける人材は、どの現場でも重宝されるでしょう。
駅員の仕事の魅力・やりがい

駅員の仕事には、日々の業務を通じて得られるやりがいや、多くの人々の生活を支える誇りがあります。給与やキャリアの安定性もあり、就職先としての魅力が高い職種といえるでしょう。
ここでは、駅員という仕事のやりがいについて、さまざまな角度からご紹介します。
- 社会インフラを支える誇り
- お客様とのふれあいによる喜び
- 安定した給与と福利厚生
- キャリアアップと昇進のチャンス
- 感謝される機会の多さ
- 地域貢献への実感
①社会インフラを支える誇り
駅員の仕事は、単なる接客や改札対応だけではありません。電車を安全かつ正確に運行させるために、多くの人が協力し合う社会インフラの最前線に立つ重要な職務です。
毎日数万人の移動を支えることは、社会のリズムを動かしているといっても過言ではありません。時刻通りの運行やトラブル対応など、細やかな判断力と責任感が求められます。
そうした中で、無事に一日を終えたときの達成感は大きく、「自分の働きが誰かの生活を支えている」と実感できます。
鉄道が止まれば社会全体に影響を与えるため、駅員の役割はまさに公共の信頼を預かる仕事です。表には出にくい存在ですが、社会の根幹を守る誇りを胸に働けることが最大の魅力でしょう。
②お客様とのふれあいによる喜び
駅員は日々、学生からビジネスマン、高齢者、外国人観光客まで、あらゆる層のお客様と接します。
迷っている人に道を案内したり、切符の購入を手伝ったりする中で、感謝の言葉をもらえることが多くあります。中には、自分を覚えてくれて笑顔で声をかけてくれる常連の方もいるでしょう。
ときにはクレームや厳しい言葉を受けることもありますが、冷静に対応することで人間としての成長を実感できます。
人の感情に寄り添いながら、相手の立場で考える姿勢が自然と身につくのもこの仕事の特徴です。毎日の出会いが刺激となり、人と関わることの深さや楽しさを学べる仕事といえるでしょう。
③安定した給与と福利厚生
駅員の仕事は、給与や待遇の安定性が高い点でも人気があります。多くの鉄道会社は上場企業や大手グループに属しており、景気の影響を受けにくい安定した経営基盤を持っています。
初任給は他業種と比較しても堅実で、年次ごとに昇給も期待できるでしょう。また、賞与や時間外手当、夜勤手当なども明確に支給されるため、頑張りがきちんと収入に反映される仕組みです。
さらに、住宅手当や交通費の全額支給、家族向けの福利厚生制度など、生活を支えるサポートが充実しています。育児や介護への理解も進んでおり、男女ともに長く働ける環境が整っています。
経済的な安定と職場の安心感を得ながら、社会に貢献できる職業として駅員は魅力的な選択肢といえるでしょう。
④キャリアアップと昇進のチャンス
駅員は、キャリアアップの機会が豊富にあります。入社当初は改札やホーム業務を担当しますが、経験を重ねることで助役や駅長など管理職への昇進が可能です。
その後、運行管理部門や営業企画、本社勤務など、現場を超えた幅広いキャリアを築く人もいます。
多くの鉄道会社では評価制度が整備されており、年功序列だけではなく、成果やリーダーシップを重視する傾向にあります。
日々の勤務態度やお客様対応の質が評価に直結するため、努力が見えやすく報われやすい環境です。さらに、社内研修や資格取得支援制度も充実しており、働きながらスキルアップを目指せます。
地道な経験を積み重ねれば、自分の手でキャリアを切り開くことができるのが駅員の大きな魅力です。
⑤感謝される機会の多さ
駅員の仕事は、人との関わりを通じて感謝される場面が多くあります。
落とし物を探して喜ばれたり、電車に間に合わなかったお客様を丁寧に案内して感謝されたりと、日々の小さな出来事がやりがいになります。
とくに災害やトラブル発生時に冷静な対応を見せることで、「助かりました」と直接声をかけてもらえる瞬間は大きな達成感を得られるでしょう。
お客様の安心や笑顔を守ることが、仕事そのものの意義となります。また、チームで支え合いながら働くため、同僚からの感謝や信頼を得られる場面も多くあります。
人の役に立つ喜びと、仲間との連帯感を同時に味わえる職場環境は、駅員ならではの魅力です。日常の積み重ねが、人との温かなつながりを築いていく仕事といえるでしょう。
⑥地域貢献への実感
駅員は、地域社会と密接に関わる存在です。通勤・通学の支援だけでなく、地域イベントやボランティア活動への協力などを通して、住民とのつながりを深めています。
とくに災害時や悪天候の際には、地域の安全を守るために迅速な対応が求められます。その姿勢が評価され、「この駅があってよかった」と感謝されることも珍しくありません。
長年同じエリアで勤務することで、顔なじみのお客様も増え、地域に根ざした信頼関係が築かれていきます。駅という場所は単なる交通拠点ではなく、地域の生活を支える大切な基盤です。
地元に愛着を持ち、地域の発展に貢献したいと考える人にとって、駅員の仕事は非常に意義深いものとなるでしょう。
駅員の仕事の大変な点

駅員の仕事には、普段見えない多くの苦労があります。勤務形態や精神・身体の負担、安全に関する重い責任など、入社前のイメージとは異なる現実に直面することも少なくありません。
就活生が見落としがちなポイントを正しく知ることで、職業選択の判断材料になります。ここでは、駅員として働く上で大変な点を詳しく紹介します。
- シフト勤務・夜勤による生活リズムの乱れ
- クレーム・トラブル対応の精神的負担
- 体力的なハードワーク
- 天候や事故による突発的対応
- 休日出勤・残業の多さ
- 安全管理に対する高い責任
①シフト勤務・夜勤による生活リズムの乱れ
駅員の勤務体制は、始発から終電、そして深夜の点検作業などを含むため、日中に限定された勤務ではありません。
そのため、シフトは早番・遅番・夜勤などが入り混じり、生活のリズムが一定になりにくいです。
夜勤明けには仮眠を取る時間が設けられていても、十分な休息を確保するのは難しく、疲労が蓄積しやすくなります。
また、夜勤後の回復が間に合わないまま次の勤務に入ることもあり、慢性的な睡眠不足に陥るリスクがあります。特に睡眠の質が落ちると、体調不良や注意力の低下を引き起こす要因にもなり得ます。
さらに、家族や友人との時間が合わず、私生活にも影響が出ることがあるでしょう。自己管理能力や健康への意識が欠かせない職業であるといえます。
②クレーム・トラブル対応の精神的負担
駅は多くの人が利用する公共の場であり、常にトラブルや不満が発生する可能性をはらんでいます。ダイヤの乱れや駅施設の不具合、乗客同士のトラブルなど、突発的な事案への対応は避けられません。
こうした状況で駅員が最初に矢面に立ち、乗客の怒りや不安に向き合うことになります。
感情的になっている相手に対して、冷静かつ的確に対応するスキルが求められます。ときには理不尽な言葉を受けることもあり、その精神的なストレスは計り知れません。
しかし、それらに対して丁寧に説明し、信頼を築いていく姿勢が、安全で快適な駅運営を支えているのです。
加えて、個々の判断で対応する場面が多く、経験や瞬発力も重要となります。精神的なタフさとともに、柔らかい物腰や共感力も求められるため、コミュニケーションに自信がある人に向いているでしょう。
③体力的なハードワーク
駅員の業務は、意外にも肉体的な負荷が大きいことで知られています。業務中は基本的に立ち仕事で、構内を頻繁に歩き回る場面が多く、一日の歩数が1万歩を超えることも珍しくありません。
ホームの巡回、改札での案内、駅施設の確認作業など、動きの止まる瞬間がほとんどないという日もあります。
さらに、車いす利用者や重い荷物を持つ方のサポートなど、力を使う対応も発生します。緊急時には迅速に現場へ駆けつけ、乗客の安全を守る動きも求められます。
天候が悪い日や気温が極端な日でも業務があるため、夏場の熱中症対策や冬場の防寒対策も重要です。
体力に自信があり、活動的に働きたい人には適している一方で、体力的な負担を避けたい人には厳しく感じる環境かもしれません。
④天候や事故による突発的対応
駅員の業務には、常に「予期せぬ出来事」が伴います。例えば、台風や大雪、落雷による設備障害などの自然災害は、列車の遅延や運休を引き起こし、多くの乗客対応を要します。
人身事故や車両トラブルなども突発的に発生し、迅速な判断と対応が求められる場面が数多くあります。
このような状況では、通常業務以上に緊張感を持って行動する必要があり、瞬時の決断力が問われます。
また、突発的な対応が増えることで、予定していた勤務時間が延びたり、急なシフト変更が入ることもあります。予測不可能な事態に対して柔軟に動けるかどうかは、適性の判断材料となるでしょう。
臨機応変な思考や切り替えの早さを持っている人にとっては、やりがいのある現場です。
⑤休日出勤・残業の多さ
鉄道は社会インフラの一部であるため、駅の運営は365日休みなく続きます。休日や年末年始、祝日でも通常通りの運行があり、そのぶん駅員の勤務も途切れることがありません。
特に大型連休や繁忙期には、出勤日が増えたり、勤務時間が延びることもあります。
急なトラブルが発生すれば、予定外の残業や早朝出勤が求められることもあるため、スケジュールの調整が難しい一面もあります。
とはいえ、代休や勤務ローテーションによって平日に休みを取れるメリットもあり、混雑を避けて余暇を楽しめるという利点もあります。
安定したライフスタイルを望む場合は、勤務体制を事前にしっかり確認しておくことが大切です。
⑥安全管理に対する高い責任
駅員は、駅構内や列車の運行に関わる多くの安全管理業務を担っています。ホームでの転落防止や乗降時の確認作業、異常時のアナウンス、設備の点検など、その一つ一つが利用者の命を守る行為に直結します。
また、安全確認のプロセスには細かいマニュアルがあり、それを確実に実行する責任感が不可欠です。状況によっては判断を求められる場面も多く、知識や経験に裏打ちされた対応力が問われます。
新人であっても責任の重さは変わらないため、常に高い意識を持って行動することが求められるのです。
その分、すべての乗客の安全を守っているという強い使命感と、社会的な意義を感じられるのも駅員の魅力の一つです。
責任感を持って仕事に取り組みたい人には、大きなやりがいを実感できる職業といえるでしょう。
駅員に向いている人の特徴

駅員という仕事には、日々多くの人と接しながら安全を守る大きな責任が伴います。自分の性格や特性がこの仕事に合っているか不安に思う就活生も少なくありません。
ここでは、駅員に向いている人の特徴を具体的に紹介し、自分に合っているかどうかの判断材料にしていただければと思います。
- 人と関わるのが好きな人
- 責任感が強く冷静に行動できる人
- チームワークを大切にできる人
- 体力に自信がある人
- ルールやマニュアルを守れる人
- 困っている人を助けたいと思える人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①人と関わるのが好きな人
駅員の仕事では、接客を中心とした業務が日常的に発生します。改札やホームでの案内、乗り換えの誘導、困っている乗客への対応など、さまざまな場面で人と関わる必要があります。
知らない人に話しかけられても戸惑わず、自然に会話ができる方は、この仕事において非常に適性があるといえるでしょう。
また、相手の話をしっかり聞き取り、丁寧に説明できるかどうかも重要です。駅構内では案内放送や他の音で騒がしいことが多く、はっきりとした口調や適切な距離感が求められます。
さらに、接客の中で感謝の言葉を直接受け取れる機会も多く、人と関わることが好きな人にとっては、大きなやりがいや満足感を得られる職場といえるでしょう。
②責任感が強く冷静に行動できる人
駅員は、安全と正確な運行を支える役割を担っており、その場その場で適切な判断を下すことが求められます。
たとえば、電車の遅延やホームでのトラブル、急病人への対応といったイレギュラーな状況においても、感情的にならず落ち着いて行動できるかどうかが問われます。
状況によっては、一瞬の判断ミスが大きな混乱や危険を引き起こす可能性もあります。
そうした環境でも、自分の役割をしっかり理解し、正しい手順で冷静に動ける人は、駅員として非常に信頼される存在です。
判断力や対応力は、経験を通じて磨かれていく部分もありますが、もともと慎重で責任感が強い性格の方には、非常に向いている仕事といえるでしょう。
③チームワークを大切にできる人
駅の運営は一人で完結するものではなく、改札係・ホーム係・駅長補佐など、さまざまな役割の人々が連携して成り立っています。
そのため、自分の持ち場に加え、周囲との情報共有や協力が欠かせません。たとえば、事故が発生した際には、すぐにチーム内で連携を取り、役割分担をしながら対応する必要があります。
また、交代勤務が基本のため、前のシフトの人からの引き継ぎや、次の人への申し送りも業務の一部です。
日々のやりとりを円滑に行い、互いに支え合える関係を築けるかどうかが、業務全体の質に直結します。
人との協調を自然に意識できる人ほど、駅の職場で信頼されやすく、円滑なチーム運営に貢献できるでしょう。
④体力に自信がある人
駅員の仕事は、思っている以上に体力を必要とします。駅構内は広く、ホームと改札を何度も往復することが日常的ですし、電車の運行に合わせて早朝や深夜の勤務もあります。
特に大都市圏では利用者数が多く、混雑する時間帯には動き回る量も自然と増えます。
また、立ちっぱなしでの業務が基本であるため、腰や足に負担がかかりやすく、継続して勤務するには体調管理が不可欠です。
体力に自信があり、生活リズムをある程度柔軟に調整できる人は、業務にスムーズに適応できるでしょう。
逆に、疲れが溜まりやすい体質の方や、不規則な生活が苦手な方は、あらかじめその点もよく検討することが大切です。
⑤ルールやマニュアルを守れる人
鉄道の現場では、乗客の安全が最優先であり、すべての業務が厳格なルールとマニュアルに基づいて運用されています。
たとえば、非常時の対応や点検業務など、細かく決められた手順を省略せず実施することが求められます。そのため、決まりごとを軽視せず、日々の業務の中で正確に守ることができる人に向いています。
また、緊急時には一貫した判断が必要となるため、独断で行動するよりも、マニュアルに従って冷静に動ける人ほど評価されやすい傾向にあります。
自分のやり方よりも組織全体の決まりを尊重できる人は、鉄道業界で安定して活躍できるでしょう。
⑥困っている人を助けたいと思える人
駅には、初めてその駅を利用する人、地理に不慣れな観光客、足元が不安定な高齢者など、さまざまな乗客が訪れます。
そういった方々の困りごとを見逃さず、自然と手を差し伸べられる姿勢がある人は、駅員にぴったりです。特に、外国人観光客など、言語の壁がある相手でも気後れせずに接することができる人は重宝されます。
さらに、単なる案内だけでなく、気持ちに寄り添った対応ができることも大切です。乗客の「ありがとう」という言葉は、駅員のモチベーションに直結する要素でもあります。
困っている人に気づき、自分から進んで行動できる人は、駅の現場で大きな存在感を発揮できるでしょう。
駅員に向いていない人の特徴
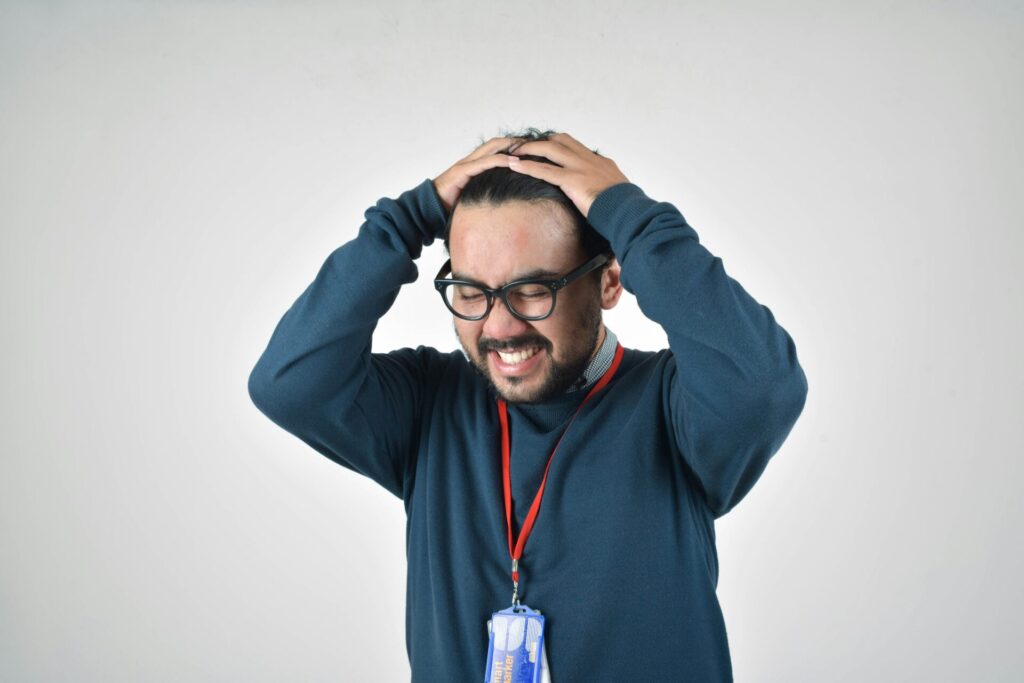
駅員という仕事は一見すると誰にでもできそうな印象がありますが、実際には向き・不向きがはっきりと分かれる職業です。
鉄道会社に就職した後に「想像と違った」と感じることを防ぐためにも、あらかじめ向いていない人の特徴を知っておくことが大切です。
ここでは、駅員という職業に適性がないとされる代表的な傾向について説明します。
- 夜勤や不規則勤務が苦手な人
- ストレスに弱い人
- 人とのコミュニケーションが苦手な人
- 柔軟な対応ができない人
- 集中力が続かない人
- 体力仕事を避けたい人
①夜勤や不規則勤務が苦手な人
駅員の勤務形態は、基本的にシフト制であり、早朝や深夜、さらには宿直勤務も発生します。とくに始発や終電の時間に合わせて業務が組まれるため、勤務時間は固定されていません。
安定した生活リズムを大切にしたい人にとっては、予想以上に負担になることがあるでしょう。
深夜勤務があると、体内時計の調整が難しくなり、睡眠の質や日常生活にも影響が出る可能性があります。仮眠が取れたとしても、十分に回復できるとは限りません。
また、休日も不定期になりやすいため、友人や家族と予定を合わせることが難しく、プライベートの充実度にも影響します。
こうした勤務形態に適応できないと、心身の疲労が蓄積しやすくなります。結果として業務に集中できず、ミスや事故につながる恐れも否定できません。
駅員の仕事では、生活のリズムに柔軟性が求められるため、規則正しいスケジュールで働きたい人には大きなハードルとなるでしょう。
②ストレスに弱い人
駅員の職場環境は、常に変化と緊張感が伴います。通勤ラッシュによる混雑、乗客同士のトラブル、天候や設備不良によるダイヤの乱れなど、日常的にさまざまな対応が求められます。
乗客からの理不尽なクレームや、突然の非常事態に対する判断も重要です。ときには感情をぶつけられることもあり、精神的に負荷がかかる場面は避けられません。
ストレスの蓄積により集中力が低下したり、仕事に対するモチベーションが下がってしまったりする可能性もあります。
また、鉄道業務は安全性が最優先されるため、どんな状況でも冷静に判断しなければなりません。緊張する場面でも落ち着いて対応できるかどうかが問われます。
ストレスに敏感で、不安定な状況下での行動に自信がない場合は、長く働き続けるのが難しく感じるかもしれません。
③人とのコミュニケーションが苦手な人
駅員は機械的な作業をこなすだけではなく、人と接する機会が非常に多い仕事です。
道に迷った乗客への案内や、トラブル発生時の状況説明、高齢者や子どもへのサポート、さらには訪日外国人への英語での対応など、場面に応じて丁寧なやりとりが求められます。
とくに混雑時やダイヤの乱れが発生したときには、乗客の不安や怒りが爆発しやすくなります。そんなときこそ、落ち着いて丁寧に説明し、信頼を得られるコミュニケーション力が重要です。
人と話すのが苦手だったり、相手の意図を汲み取ることが難しいと、仕事そのものに強いストレスを感じる可能性があります。
コミュニケーションに苦手意識がある人は、駅員という仕事が大きな負担になりかねません。
④柔軟な対応ができない人
駅員の仕事には、マニュアル通りに進まない業務が数多くあります。急な人身事故、急病人発生、強風や大雨による遅延、忘れ物の通報など、現場では予測不能な出来事が日々起きています。
その場の状況を素早く把握し、優先順位をつけて動く判断力が必要です。常に正解があるわけではないため、自分で最善策を考える力も求められるでしょう。
決められた通りに進めるのが得意な人や、想定外の事態に混乱しやすい人にとっては、強いプレッシャーを感じる場面が多くなります。
また、指示待ちの姿勢では現場が回らないこともあります。上司や先輩の指示を待っているうちに事態が悪化してしまうケースもあり、瞬発的な行動力が求められるのです。
柔軟な思考や対応に自信がない場合、駅員としての業務には大きな壁が立ちはだかるかもしれません。
⑤集中力が続かない人
駅員の業務には、安全確認、車掌への合図、アナウンス業務、時間調整、忘れ物対応など、注意力と正確性を求められる作業が数多くあります。
一つひとつはルーティンに見えても、その背後には緊張感が常に漂っています。わずかな気の緩みが重大なミスにつながるため、気を抜けない場面が続くのが特徴です。
たとえば、ホームでの安全確認では、乗客の足元や扉の開閉状況を瞬時に見極めなければなりません。通勤ラッシュでは状況が一秒ごとに変わるため、常に集中力を保つ必要があります。
単調な作業が続くと気が散りやすいタイプの人も、苦痛を感じやすいかもしれません。
⑥体力仕事を避けたい人
駅員の仕事はデスクワーク中心と思われがちですが、実際にはかなりの体力を必要とします。
ホームでの誘導、階段の昇降、重い荷物の運搬、落とし物の回収対応など、1日の中で何度も体を動かす場面があるのです。長時間立ちっぱなしの勤務も多く、下半身への負担も大きくなりがちです。
また、勤務時間が不規則なうえ、早朝や深夜の勤務が続くと、睡眠不足や疲労が溜まりやすくなります。仮眠時間が取れる場合でも、完全な休息にはなりにくいため、日々の体調管理が欠かせません。
さらに、繁忙期や災害時などには、通常以上の業務量が求められます。その際、疲労が蓄積しながらもミスをせず対応することが不可欠です。
体力に自信がない人や、体を動かす業務に抵抗がある人にとっては、駅員の仕事は想像以上に厳しい環境かもしれません。
駅員になるためのステップ
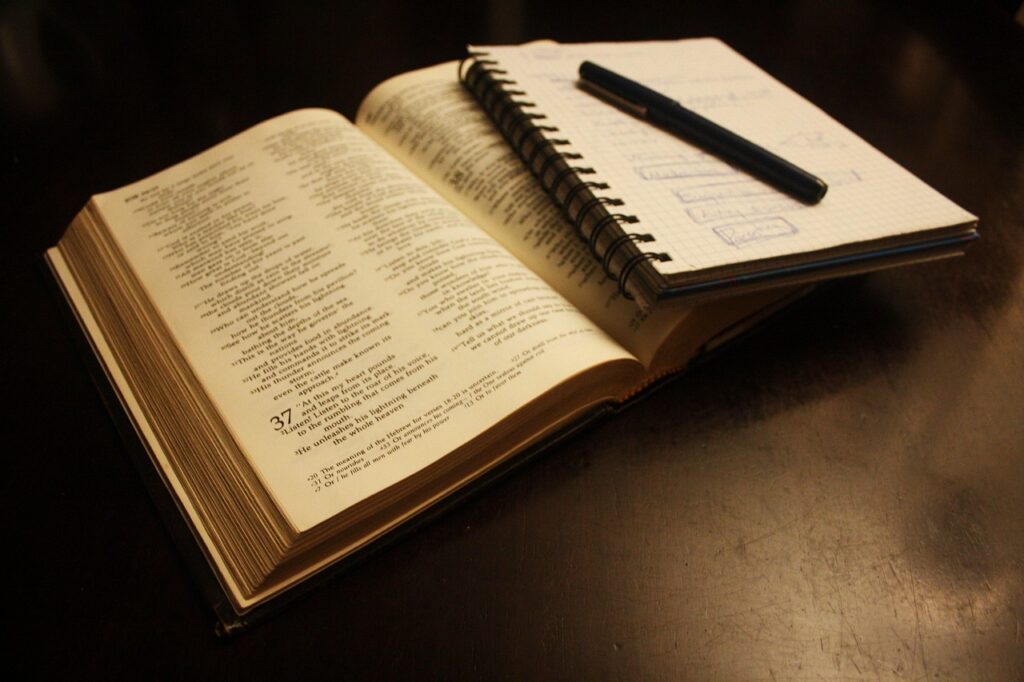
駅員になるには、ただ求人に応募すればよいというわけではありません。
鉄道業界についての理解から始まり、エントリーシートの作成、筆記試験、面接対策、そして研修を経て現場に出るまで、段階的に準備を進める必要があります。
ここでは、就活生が安心して選考に臨めるように、駅員になるまでの流れをわかりやすく解説します。
- 鉄道業界や企業の特徴を調べる
- 採用スケジュールを確認する
- エントリーシートを作成する
- 筆記試験・適性検査を受ける
- 面接対策を行う
- 内定後の研修を受けて現場に配属される
①鉄道業界や企業の特徴を調べる
鉄道業界には、JRグループや私鉄、地下鉄、第三セクターなど多くの企業があります。それぞれの会社には沿線の特性や経営方針、業務内容の違いがあり、働き方にも大きな差が出ます。
たとえばJR東日本のような大規模な企業では、駅員の担当範囲が細分化されている一方で、地方の中小私鉄では一人が複数業務を兼任することもあります。
また、勤務時間にも違いがあり、24時間体制のシフト勤務に対応できる体力や生活習慣の調整力も必要になるでしょう。さらに、年収や昇給制度、福利厚生の内容も企業ごとに異なります。
単に「鉄道が好き」という気持ちだけで選ぶのではなく、自分の将来像と照らし合わせながら企業研究を進めてください。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
②採用スケジュールを確認する
鉄道会社の採用スケジュールは企業によってばらつきがありますが、情報収集を怠ると、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性があります。
多くの大手鉄道会社は3月から6月にかけてエントリー受付や選考を実施しますが、エントリー開始は2月ごろから始まることも珍しくありません。
逆に、地方の鉄道会社や中小私鉄の場合は、夏や秋に採用活動を行うこともあります。
また、鉄道会社では説明会参加がエントリーの条件になっている場合や、インターン参加者に早期選考の案内が届くこともあるため、スケジュール全体を見渡して早めの動き出しが欠かせません。
自分が受けたい企業がどのような流れで選考を進めるのか、あらかじめ確認しておくことで、無駄のない準備ができるようになります。
③エントリーシートを作成する
駅員を目指すうえでのエントリーシートは、企業があなたの人物像や適性を初めて知る重要な材料です。
どの企業でも、誠実さや責任感、接客対応力といった資質が問われますが、内容が抽象的だと他の応募者と差別化できません。
たとえば「接客が好き」「人の役に立ちたい」という志望動機は多くの学生が使いがちですが、それをどのような経験から実感したのか、具体的なエピソードを交えて説明することが大切です。
大学でのアルバイト経験やサークル活動、ボランティアなどを通して、どのように人と関わり、工夫して行動したのかまで掘り下げると説得力が増します。
また、自己PRとの整合性にも注意が必要です。志望動機で「チームでの協力を大切にしている」と述べた場合、自己PRでは「協調性がある」だけでなく、それを証明するエピソードが求められます。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
④筆記試験・適性検査を受ける
鉄道会社の選考では、多くの場合、SPIや一般常識試験が課されます。それに加え、注意力や反応速度、判断力を測る独自の適性検査を行っている企業もあります。
駅員の仕事は安全が最優先であるため、ミスを防ぐ力や冷静な判断ができるかを測るための試験は避けて通れません。
適性検査では、同じ問題が連続して出題される「反復作業」や、短時間で多数の設問に答える「瞬発力系」のものなどもあります。
特にグループ討論では、積極性や協調性、話し合いの中で冷静に意見をまとめられるかなどが評価されるため、普段から人前で話す練習をしておくとよいでしょう。
筆記試験は単なる知識テストではなく、「現場で即戦力として働けるか」を見極める材料です。早めに対策を始め、反復練習を重ねることで、安心して本番に臨めるようになります。
⑤面接対策を行う
面接では、「駅員の仕事をどれだけ理解しているか」「大変な環境でも前向きに取り組めるか」が重要な評価軸になります。
志望動機や自己PRはもちろんのこと、夜勤やクレーム対応といった大変な業務にどう向き合うかも問われるでしょう。
「大学時代は朝から深夜まで活動するイベント運営に携わっていたため、時間管理と体調維持には常に気を配っていた」といった具体的な経験を交えると納得感が生まれます。
また、鉄道業界ではチームワークが欠かせません。遅延やトラブル時に連携して対応するため、「人と協力して成果を出した経験」や「意見が対立した場面での調整力」などをアピールするとよいでしょう。
さらに、笑顔や姿勢、声のトーンといった非言語の印象も評価されます。模擬面接を通じて、質問に対する受け答えの練習だけでなく、第一印象の磨き上げにも取り組んでください。
⑥内定後の研修を受けて現場に配属される
内定をもらった後、すぐに駅業務に就けるわけではありません。鉄道会社では入社後に研修期間が設けられ、接客スキルや安全管理の基礎をしっかり学ぶ機会が用意されています。
期間は数週間から数か月に及ぶことが一般的で、座学だけでなく実技指導も行われます。研修では、マニュアルに沿った対応方法だけでなく、想定外のトラブル時にどう判断するかといった応用力も問われます。
たとえば「電車が遅延した際、乗客へどう案内するか」「体調不良の乗客がいたらどう行動するか」といった実践的なケーススタディが含まれることもあります。
また、配属先によって必要なスキルが異なるため、習得内容にも若干の差が出ます。駅によっては外国語対応が必要になることもあるため、基本的な英会話を学ぶ研修が行われることもあるでしょう。
責任の重さを理解したうえで、学ぶ姿勢を持ち続けることが求められます。
駅員の年収に関して情報を集めよう!

駅員の年収は、企業や職種によって差があるものの、安定性と社会的意義の高さが魅力です。
特にJR各社や大手私鉄では、基本給に加えて手当や福利厚生が充実しており、長期的なキャリア形成がしやすい環境といえるでしょう。
駅員は改札や案内、安全管理など多岐にわたる業務を担当しますが、その分やりがいも大きく、地域社会に貢献できる仕事です。
もちろん夜勤やシフト勤務などの負担はありますが、それ以上に公共交通を支える誇りを感じられる点が魅力といえます。
鉄道業界への理解を深め、自分に合った企業や職種を見極めることが、理想のキャリアを築く第一歩となります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














