SPI数学の練習問題と出題傾向|高得点を狙う対策法を徹底解説
「SPIの数学問題が全然解けない…」「どんな問題が出るのか分からない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
SPI(適性検査)は多くの企業で導入されており、特に非言語(数学)分野は合否を大きく左右する重要パートです。短時間で正確に解く力を求められるため、しっかりとした対策が必要です。
本記事では、SPI数学の出題傾向から頻出分野(割合・速度算・損益算・推論など)、効率的な練習方法まで徹底解説します。
SPI数学を得点源に変えるヒントを、一緒に見ていきましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
SPI数学の練習問題で高得点を目指そう

SPI数学は就職試験で欠かせない重要な分野です。特に非言語領域にあたる数学問題は、論理的な思考力と計算力を同時に求められるため、多くの学生が苦手意識を抱きやすいでしょう。
しかし、そのまま放置すると他の受検者と大きな差がついてしまいかねません。なぜなら、SPI数学の出題範囲はある程度決まっており、繰り返し練習を行うことで得点源にできるからです。
具体的には、割合や比率、速度算、損益算など、日常生活とも関連する基礎的な問題が中心。これらをしっかり押さえれば効率よく得点を積み上げることができます。
また、制限時間内で複数の問題を解かなければならないため、正確さだけでなくスピードを意識した練習も欠かせません。
短期間で成果を出したい場合は、出題傾向に沿った問題演習を繰り返すことが最も効果的です。準備次第で大きな武器になるため、早めに取り組んで自信をつけてください。
SPI数学(非言語分野)とは?
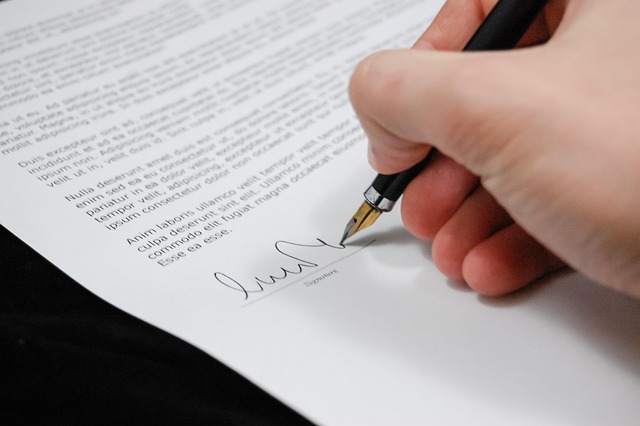
SPIの数学(非言語分野)は、就活の選考で多くの企業が取り入れている適性検査の中でも重要な位置を占めています。
数的推理や基礎的な計算を通して、論理的に考える力や短時間で正解にたどり着く力を確認されるものです。
出題範囲は四則演算や割合、損益計算、集合、確率など幅広く、大学受験で学んだ高度な知識よりも、日常生活や仕事に直結する実用的な題材が中心です。
特に損益や割合の問題は、営業や経営の場面でも役立つ考え方を問われているといえるでしょう。SPIの数学に苦手意識を持つ学生は少なくありませんが、出題形式に慣れるほど得点を伸ばしやすい分野です。
そのため、早い段階から練習問題を解いて形式に慣れ、自分の弱点を理解して取り組むことが効果的でしょう。苦手なまま放置すると他の受験者との差が広がってしまいかねません。
一方で、しっかり対策を重ねれば得点源に変えることもできます。SPI数学は「準備次第で逆転可能な科目」と意識して取り組んでください。
SPI数学の出題内容
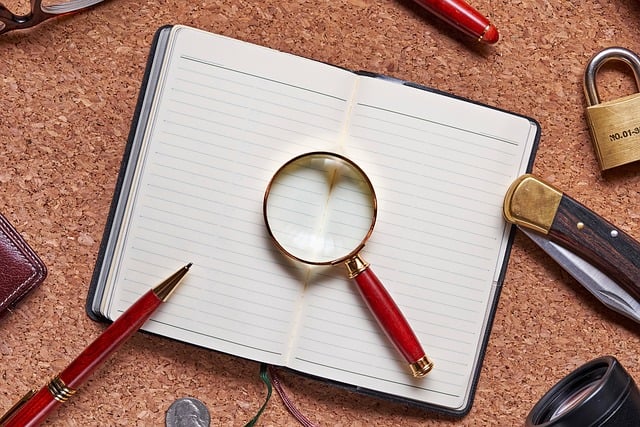
SPI数学は非言語分野にあたり、数の処理や論理的な思考力を確認するために幅広い問題が出題されるのです。
ここでは代表的な出題範囲を紹介し、どのような力が問われるのかを理解できるように解説します。
出題内容を知ることで効率的に対策を進められるでしょう。
- 割合・比率
- 速度算・通過算・流水算
- 損益算や代金精算
- 推論・順列・組み合わせ
- 集合やグラフ
- 濃度算や特殊算
- n進法などの応用
①割合・比率
割合や比率はSPI数学の中でも基本的な分野です。全体に対する部分の大きさを表す割合や、2つの量を比べる比率は日常生活でもよく使われるため、基礎知識の有無を確認するために出題されます。
典型的な問題は「売上が前年比で何%増加したか」や「男女比3:2のグループに人数が加わったときの比率」などです。一見単純ですが、条件を読み落とすと間違いやすいのが特徴。
正解するには全体と部分の関係を図や式で整理することが大切でしょう。計算の際は分数や小数を統一して扱うと混乱を防げます。
練習の段階では公式を暗記するだけでなく、なぜその式が成り立つのかを理解して解く習慣をつけてください。
安定して得点するには、速さと正確さを意識して繰り返し演習し、計算の型を体に染み込ませることが効果的です。
②速度算・通過算・流水算
速度算や通過算、流水算は移動や流れを扱う典型的な応用問題。速度算は「距離=速さ×時間」の公式をもとに列車や自動車の移動を計算する形式が中心になります。
通過算では列車が橋やトンネルを通過する時間を問うため、対象の長さを考慮する必要がああるのです。
流水算は川の流れに逆らう場合や流れに乗る場合を計算するため、静水時の速さと流速の合成を理解しておくことが欠かせません。
これらは公式を覚えるだけでなく、状況を図にしてイメージすることで解きやすくなります。特に制限時間内に正しく解くには、問題文の条件を整理する力が重要です。
同じパターンの問題を繰り返し解くことで、典型的な解法をすぐに思い出せるようになります。焦って計算ミスをしやすい分野なので、途中式を残す習慣を持つことも得点率を上げるポイントです。
③損益算や代金精算
損益算や代金精算は、ビジネスや日常の場面を題材にした問題です。損益算では「仕入れ値」「売値」「利益」などを扱い、利益率や損益分岐点を計算する問題が中心。
代金精算は「割り勘」や「おつり」を計算させる形式が多く、正確な計算力が問われます。身近なテーマで出題されるため簡単に見えますが、条件が複数あると計算が複雑になりやすいでしょう。
対策としては、与えられた数値を整理して表にまとめると計算がスムーズになります。割り算や小数のまま計算するよりも整数比に直すことでスピードと精度が高まるのです。
本番ではケアレスミスが失点に直結するため、練習から数字の扱いに注意を払いましょう。安定した得点源にするためには、典型問題を素早く正確に解ける習慣をつけることが効果的です。
④推論・順列・組み合わせ
推論や順列・組み合わせは、論理的に考える力を測るために出題されます。推論問題は「条件を満たすのは誰か」「正しい組み合わせはどれか」といった形式が多く、与えられた条件を整理する力が必要です。
順列や組み合わせは「並べ方」や「取り出し方」の数を求める問題で、場合の数の基本知識が問われます。公式が決まっているため、順列と組み合わせを見極められるかどうかが正解への鍵でしょう。
この分野は時間を使いすぎやすいため、条件を表や図に整理して効率よく解くことが大切です。慣れていないと難しく感じますが、パターンを理解して演習を重ねれば安定して得点できるようになります。
難問に惑わされず、典型的な問題を正確に解くことが得点アップにつながるのです。
⑤集合やグラフ
集合やグラフの問題は、情報を整理して読み取る力を測るために出題されます。集合ではベン図を使って「AかつB」「AまたはB」を整理する形式が中心です。
グラフ問題では、棒グラフや折れ線グラフ、円グラフから数値を読み取り、増減や割合を求める力が試されます。一見シンプルですが、条件とグラフの内容を正しく結びつけられないと誤答しやすい分野です。
正確に解くためには、条件を必ずグラフに反映させる習慣を持つことが大切。単位や割合を丁寧に扱うことで正答率も上がるでしょう。
普段からニュースや統計資料のグラフに目を通し、読み取る練習をしておくとSPI対策に直結します。練習を通じて正しい読み方を身につければ、安定した得点源にできるでしょう。
⑥濃度算や特殊算
濃度算や特殊算は応用的な出題範囲で、苦手に感じる人が多い分野です。濃度算は食塩水などの混合割合を扱い、濃度計算の式を正しく使えるかが問われます。
特殊算には「仕事算」「時計算」「年齢算」などがあり、状況を数式に落とし込む力が必要です。これらは一度理解すれば型で解ける問題が多いため、典型的なパターンを押さえることが最優先。
練習では問題文を図や表に整理し、そこから式を導く流れを徹底するのが効果的です。本番では難しい問題に時間をかけすぎないことも重要で、優先順位をつけて解く意識が高得点につながります。
苦手意識が強い場合は、まず基本問題を繰り返し練習して慣れることから始めてください。理解が深まれば、応用問題にも落ち着いて対応できるようになります。
⑦n進法などの応用
n進法などの応用問題は出題頻度は高くありませんが、得点差がつきやすい範囲です。n進法は10進法以外の表記方法を理解しているかを確認する問題で、慣れていないと混乱しやすいでしょう。
しかし基本の仕組みを理解すれば、規則性を活用して素早く解けます。応用問題には複数条件を同時に満たす計算や、複雑な数列問題などもあるでしょう。
焦って解くと間違えやすいため、落ち着いて手順を踏むことが大切です。学習段階では難しい問題に挑戦することで理解が深まり、基礎力の定着にもつながります。
練習で応用問題に触れておくと、本番でも冷静に対応できるでしょう。差をつけたい人にとっては狙い目の分野といえます。
SPI数学の苦手を克服する対策方法

SPIの数学は就活で避けて通れない試験であり、多くの学生が苦手意識を持つ分野です。しかし、正しい方法で学習すれば克服でき、得点源に変えることも可能でしょう。
ここでは代表的な対策方法を段階的に整理し、効率よく力を伸ばすための流れを紹介します。
- 問題を一通り解いて解説を理解する
- 問題のパターンを繰り返し練習する
- 苦手分野を特定して重点的に対策する
- 制限時間を意識して演習する
- 公式を理解して使いこなせるようにする
①問題を一通り解いて解説を理解する
SPI数学を克服する最初のステップは、実際に問題を解いてみることです。最初から正解を出そうとする必要はなく、むしろ解けない部分を見つけることが大事でしょう。
自分の弱点を把握することで効率的に学習できるからです。解いたあとは必ず解説を確認し、なぜその答えになるのかを理解してください。答えが合っていても、解法を説明できない状態では危険です。
もし解説を読んでも理解できない部分があれば、参考書や動画などを使って補いましょう。こうした取り組みを重ねることが、基礎力を固める第一歩になります。
②問題のパターンを繰り返し練習する
SPI数学は知識量よりも、出題パターンへの慣れが結果を左右します。そのため、典型的な問題形式を繰り返し解いて解法を体に覚え込ませることが必要です。
たとえば「損益計算」「速さ」「集合」などは定番の出題形式なので、繰り返し解けば自然に手が動くようになります。最初は時間をかけてもかまいませんが、慣れてきたらスピードを意識しましょう。
パターン練習を積むことで、初めて見る問題でも類似の方法を応用できるようになります。練習の中で自分のミスの傾向に気づける点も大きなメリットです。
最終的に得点を伸ばす近道は、この反復練習にあるといえるでしょう。
③苦手分野を特定して重点的に対策する
全分野を同じように学習するのは効率的ではありません。苦手を残したままでは本番で失点が増えてしまいます。そこで、自分の弱点を特定して重点的に練習することが必要です。
模試形式の問題集を解き、得点状況を確認すると弱点が明確になります。たとえば確率でつまずきやすいなら、その範囲を集中して取り組むと短期間で成果が出るでしょう。
反対に得意分野は基礎確認にとどめ、学習時間を節約してください。こうして弱点を克服すると、全体のバランスも整い、本番でも安定して得点できるようになります。
④制限時間を意識して演習する
SPI数学では正解率だけでなく、制限時間内でどれだけ解けるかも重要です。そのため、普段の練習から時間を意識して取り組む必要があります。
初めは時間を気にせず理解を優先して構いませんが、慣れてきたらタイマーを使い、本番を想定した演習をしてください。
時間を意識すると「どの問題を先に解くか」「どこで見切りをつけるか」といった判断力も養えます。SPIは全問正解を狙う試験ではなく、解ける問題を確実に得点することが大切です。
演習段階で時間感覚を身につけておけば、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。
⑤公式を理解して使いこなせるようにする
SPI数学で安定して得点するには、基本公式を正しく理解し、自在に使えるようになることが欠かせません。単なる暗記ではなく、なぜその公式が成り立つのかを理解しておくことが重要です。
たとえば割合や損益計算の公式は、意味を理解していれば少し応用された問題にも対応できます。逆に丸暗記だけでは、少し形が変わっただけで解けなくなってしまうでしょう。
理解に基づいて学習すれば、時間短縮にもつながり、より多くの問題に挑戦できます。公式を「覚えるもの」ではなく「考え方の道具」として使えるようになれば、大きな得点源になるはずです。
SPI数学の問題を解くコツ

SPI数学を安定して解くには、問題の種類ごとに適切な方法をとることが大切です。
ここでは文章問題や計算問題を効率的に処理するやり方、時間配分を意識した優先順位の決め方など、すぐに役立つコツを紹介します。
- 文章問題は要点を素早く整理する
- 計算問題は効率的に処理する
- 優先順位を決めて取り組む
- 与えられた条件を図や表に整理する
- 解答は簡潔にまとめる
①文章問題は要点を素早く整理する
SPI数学では文章問題が多く出題されますが、全文を丁寧に読もうとすると時間を大きく消費してしまいます。そのため、必要な条件や数値を抜き出し、要点を整理することが重要です。
例えば「仕入れ値=100円」「利益率=20%」といった形でメモを残せば、計算にすぐ移れるでしょう。要点を素早くまとめれば、制限時間内に解き切れる確率が高まります。
普段の練習から重要な数字や条件を印をつけて整理する習慣を持ってください。これを徹底することで読み飛ばしや誤解が減り、安定して得点を取れるようになるでしょう。
②計算問題は効率的に処理する
SPI数学では四則演算を中心とした計算問題が多いですが、すべてを丁寧に処理していては時間が足りません。そこで、途中式を工夫して計算を簡略化する力が求められます。
例えば分数や小数を整数に置き換えて計算する、倍数を利用して暗算で処理するなどの工夫が効果的です。電卓は使えないため、暗算力を鍛えることも大切でしょう。
練習では制限時間を設けて短時間で正確に答えを導く訓練をしてください。難しい問題に時間をかけるよりも、基本的な問題を確実に処理した方が全体の得点率は上がるでしょう。
効率を意識した計算処理が、SPI突破の必須スキルといえます。
③優先順位を決めて取り組む
SPIの数学問題は幅広い分野から出題されるため、すべてに同じ時間をかけると時間切れになる恐れがあります。そのため、問題に優先順位をつけることが大切です。
最初は得意な問題から解いて確実に得点を積み、その後に応用問題へ進む流れが効果的でしょう。
難易度の高い問題に固執すると全体の得点率が下がるため、「解けそうかどうかを数秒で判断する」意識を持つことが必要です。
練習段階から模擬試験で時間配分を試しておくと、本番でも落ち着いて対応できます。得点を最大化するには「全部解こうとしない」姿勢が逆に効率的なのです。
④与えられた条件を図や表に整理する
条件が多い問題や状況をイメージしにくい問題は、文章だけで処理しようとすると混乱しやすいものです。条件を図や表に書き出せば、問題がぐっと解きやすくなります。
例えば速度算では道のりを線分図に描き、集合問題ではベン図を使うと整理が容易です。図表化は答えを導く過程を明確にするため、ミスを減らす効果もあります。
特に推論や割合の問題では、数値を表に整理して関係を確認すると解答に近づきやすいでしょう。練習から図や表を使う習慣を身につけておけば、本番でも冷静に対応できます。
安定した正答率を維持するために、図表化は欠かせない工夫です。
⑤解答は簡潔にまとめる
SPI数学では途中の考え方ではなく、最終的な答えが評価されます。そのため、解答は簡潔にまとめることが大切です。
途中式にこだわりすぎると時間を無駄にするため、解答欄には必要な答えだけを明確に記入してください。
ただし、計算を雑に扱えば誤答につながるので、練習では丁寧に途中式を書き、本番では効率を意識するバランスが必要です。
解答が簡潔にまとまっていれば見直しもしやすく、時間が残った場合も確認がスムーズに進みます。答えをシンプルに記載する習慣をつけることで、多くの問題を時間内に処理できるでしょう。
結果として得点が安定し、自信を持って試験に臨めます。
SPI数学の練習問題例

SPI数学の力を高めるには、実際の練習問題を解くことが欠かせません。ここでは頻出分野から典型的な例題を紹介し、解答と解説をつけています。
解き方の流れを確認しながら取り組んでみてください。
①割合と比の問題
SPI数学では割合や比の問題は定番で、基礎力を確認する重要なテーマです。ここでは仕入れや利益率を扱う代表的な出題形式を紹介します。基準を意識する力を養う練習として取り組んでください。
| 【問題】 ある商品を1200円で仕入れ、利益率20%で販売しました。販売価格はいくらになりますか。 【解答】 1440円 |
【解説】
利益率は原価を基準に計算します。1200円×20%=240円が利益です。したがって販売価格=1200円+240円=1440円になります。
「基準が原価なのか売値なのか」を取り違えないよう注意しましょう。
②速度算の問題
速度算はSPIでよく出るテーマで、往復や追いかけ算などの応用が登場します。公式を覚えるだけでなく、状況を整理して考える力が必要です。ここでは往復に関する典型的な問題を確認しましょう。
| 【問題】 ある人が家から駅までを時速6kmで歩き、帰りは時速4kmで歩きました。 往復の平均速度は何km/hですか。 【解答】 4.8km/h |
【解説】
平均速度は「全体の距離÷全体の時間」で求めます。距離を片道12kmとすると、往路の時間は12÷6=2時間、復路の時間は12÷4=3時間、合計5時間です。
全体の距離は24kmなので、24÷5=4.8km/hとなります。単純に速さの平均を取るのではなく「時間を考慮する」点がポイントです。
③推論の問題
推論の問題は一見複雑ですが、条件を整理して矛盾を排除すれば解けます。焦らず順序立てて考える練習が必要です。ここでは典型的な嘘つき問題を例にします。
| 【問題】 A、B、Cの3人がいます。Aは「Bが嘘をついている」と言い、Bは「Cが嘘をついている」と言いました。実際に嘘をついているのは誰でしょうか。 【解答】 B |
【解説】
Aが正しいと仮定すると、Bが嘘をついていることになります。その場合、Bの発言「Cが嘘をついている」は偽なので、Cは正直者です。矛盾は生じません。よって嘘をついているのはBです。
このように「仮定して検証する」手順が推論問題を解く基本です。
④損益算の問題
損益算は商売に直結する考え方を問う分野で、利益率や割引を扱う典型問題が出るでしょう。ここでは割引を含むパターンを紹介します。
| 【問題】 原価2000円の商品を定価の25%引きで販売したところ、原価に対して10%の利益が出ました。定価はいくらですか。 【解答】 2880円 |
【解説】
原価2000円に対して10%の利益=200円なので、売値は2200円です。この売値は定価の75%(=100%−25%)にあたります。したがって定価=2200÷0.75=2880円となります。
「どの数値を基準にしているか」を確認しながら整理すると迷いません。
⑤集合の問題
集合の問題はベン図を描いて整理するとスムーズに解けます。条件を図に落とし込むことで重複や抜けを防げるでしょう。ここでは典型的な2集合の問題を示します。
| 【問題】 あるクラスで英語が得意な学生は20人、数学が得意な学生は15人います。そのうち両方が得意な学生は5人でした。 このとき、英語か数学のどちらかが得意な学生は何人いますか。 【解答】 30人 |
【解説】
和集合の公式を使います。英語または数学が得意な人数=20+15−5=30人です。重複部分を1回引くことを忘れないのがポイントです。集合問題では必ずベン図を描く習慣をつけましょう。
SPI数学の練習問題でつまずいたときの対応法

SPI数学の勉強を続けていると、思うように点数が伸びなかったり、途中でやる気をなくしたりすることもあります。解けない問題や時間不足、基礎力の弱さなど、悩みは人それぞれです。
ここでは代表的なつまずきと、その乗り越え方を紹介します。
- 解けない問題は解説を徹底的に確認する
- 時間不足は制限時間内で解く練習をする
- 基礎の理解が甘い場合は中学数学から復習する
- モチベーション低下時は模擬試験で実力を測る
- 学習方法を見直し効率的に取り組む
①解けない問題は解説を徹底的に確認する
解けなかった問題をそのままにすると、苦手意識だけが残ってしまいます。解説をしっかり読み、どの段階でつまずいたのかを明確にしましょう。多くの場合は公式の使い方や考え方が不足しています。
答えをただ覚えるのではなく、解説を見ながら途中式を再現してもう一度解き直すことが大切です。同じ問題を繰り返すことで理解が深まり、似た形式の問題にも対応できるようになるでしょう。
解説を活用する姿勢こそ安定した得点につながります。
②時間不足は制限時間内で解く練習をする
SPIでは知識があっても制限時間に間に合わなければ得点にはなりません。普段から時間を計り、本番と同じ条件で練習することが重要です。特に1問にこだわりすぎると他の問題を落とす原因になります。
目安として「1分以内で解けなければ次へ進む」と決めておくとよいでしょう。制限時間を意識した訓練を繰り返すことで、自然と優先順位を判断できる力が身につきます。
時間不足の悩みは、実戦形式を意識した練習で解消できるはずです。
③基礎の理解が甘い場合は中学数学から復習する
SPI数学の多くは中学から高校初期レベルの内容です。割合や分数、速さの計算などがあやふやだと、どれだけ演習しても応用問題は解けません。
もし解説を読んでも理解できない場合は、中学数学のテキストや基礎ドリルに戻るのが効果的です。特に割合・速さ・図形の基本は頻出分野で、ここが弱いと安定した点数は望めません。
焦らず基礎を固めることが、結局は効率のよい学習につながります。基礎力の補強はスコアアップの土台になるでしょう。
④モチベーション低下時は模擬試験で実力を測る
勉強を続けても成果が見えないと、やる気をなくしてしまうことがあります。そんなときは模擬試験を受けて、今の実力を数値で確認するのがおすすめです。
得点が伸びていれば自信につながり、課題が明らかになれば学習の方向性が定まります。模試は本番の環境を想定しているため、時間配分や解答順の工夫も身につくでしょう。
やる気が下がったと感じたら、模試で現状を可視化して小さな成長を確認してください。これが継続の力になるでしょう。
⑤学習方法を見直し効率的に取り組む
勉強しても成果が出ないときは、やり方そのものに問題がある可能性があります。解きっぱなしではなく、間違えた問題を振り返り、もう一度解き直すサイクルを作ることが重要です。
また、長時間まとめて勉強するよりも、毎日短時間で繰り返すほうが記憶に残りやすいでしょう。学習の量だけでなく質を意識すれば、少ない時間でも成果を感じられるはずです。
効率を意識した取り組みによって、つまずきを解消しスムーズに学習を進められるでしょう。
SPI数学対策におすすめの参考書・問題集
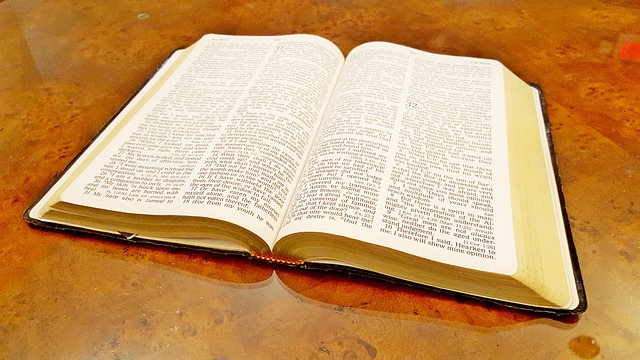
SPIの数学対策を効率よく進めるには、自分に合った参考書や問題集を選ぶことが大切です。市販の本は数多くありますが、学習の段階や目的によって適したものは変わるでしょう。
ここでは就活生に人気があり、実際の試験対策に役立つ定番書籍を紹介します。
- これが本当のSPI3だ!【2025年度版】
- 史上最強のSPI&テストセンター超実戦問題集
- 史上最強のSPI&テストセンター・WEBテスティング完全攻略
- ゼロからカンタンSPI3 【シリーズ】
①これが本当のSPI3だ!【2025年度版】
「これが本当のSPI3だ!」はSPI対策本の定番です。本番に近い形式の問題が多く収録され、解説も丁寧で理解しやすい構成になっています。
特に数学に苦手意識がある学生にとっては、基礎から応用まで段階的に取り組める安心感があるでしょう。最新版には直近の出題傾向が反映されているため、古い問題集より効率的に学べます。
ただし分量が多いため、すべてを一度に終えようとせず、まずは頻出分野から進めてください。計画的に使えば、SPI数学を得点源にできる可能性が高まります。
②史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集
この問題集は実戦的な内容が特徴で、本番レベルの問題が豊富にそろっています。そのため、基礎を終えた学生が仕上げ段階で使うと効果的でしょう。
制限時間を意識した練習に適しており、時間配分の感覚を磨けます。一方で、解説は簡潔なので初心者には少し難しく感じるかもしれません。基礎を固めた後に取り組むと実力を伸ばせます。
演習量を増やし、スピード感をつけたい人におすすめです。
③史上最強 WEBテスティング超実戦問題集
この参考書はSPIに加え、WEBテスティング形式に対応しています。複数の受検方式に対応する必要がある就活生にとって、1冊でWEBテスティングを徹底的に対策できるのは大きな強みです。
特に非言語分野の問題の解説が充実しており、出題パターンを網羅的に確認できるので安心感があります。
範囲を絞って計画的に取り組めば、効率よく活用できるでしょう。総合的に力をつけたい学生に適しています。
④SPI3の教科書 これさえあれば。
「SPI3の教科書 これさえあれば。」は、数学に苦手意識がある学生にとても適しています。基礎から体系的に学べる構成で、イラストや図解を使った解説が豊富なため、初めてでも理解しやすいでしょう。
専門用語や難解な表現をできるだけ避けて説明されているので、数的処理に不安がある人でも無理なく取り組めます。
ただし全体的に入門向けの難易度となっているため、この1冊だけで本番に挑むのは十分とは言えません。基礎を固めたあとには、応用的な問題集や実戦形式の演習に進むことが大切。
最初の一歩として学習の土台を築き、次のステップへとつなげられる一冊です。
SPI数学対策の総合ポイント

SPI数学は出題範囲が広く、割合や比率から応用的なn進法まで多様な問題が出ます。高得点を目指すには、まず練習問題を通して全体像をつかみ、出題パターンに慣れることが必要です。
次に、自分の苦手分野を特定し、繰り返し練習して克服することが効果的でしょう。また、時間制限があるため効率的に解くコツを身につけることも欠かせません。
さらに、参考書や問題集を活用して実戦的に取り組むと得点力が安定します。SPI数学は準備次第で大きな差がつく分野です。基礎を理解し、練習問題で実践力を養い、自信を持って試験に臨んでください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














