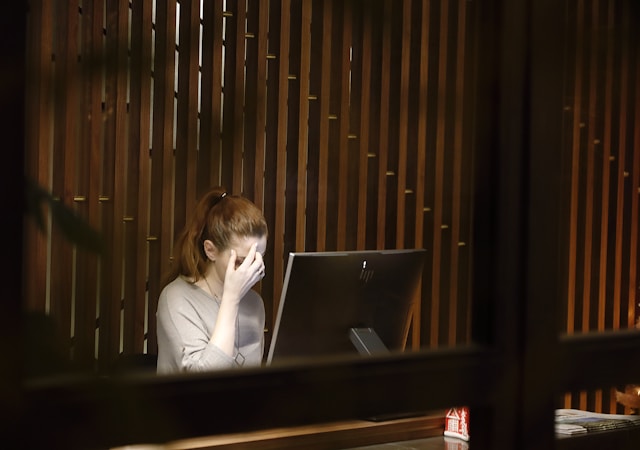既卒就活はなぜ厳しい?企業側の意図と内定を勝ち取る方法を解説
既卒での就活は難しいのかという不安を、卒業後も正社員を目指す人の多くが抱えています。新卒優先の文化が根強く、情報も少ない中で「どう動けばいいのか」と悩む方は少なくありません。
そこで本記事では、既卒就活が厳しいと言われる理由と、企業側がどう考えているのかを解説します。さらに、内定を勝ち取るための具体的な準備や戦略についても紹介します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
既卒とは?定義と新卒・第二新卒との違い

既卒とは、大学や専門学校などを卒業したものの、就職先がまだ決まっていない、または卒業後に就業経験がない人を指します。
新卒との大きな違いは「卒業時点で就職活動を終えているかどうか」、第二新卒との違いは「社会人経験の有無」でしょう。
企業は、在学中に就職先が決まらなかった理由や、卒業後の活動内容を重視するため、自己分析や経歴の整理がとても重要になります。
既卒であること自体は不利に見えやすいですが、社会人経験がない分、柔軟に育成できる人材として評価される場合もあります。
まずは自分の立場を正しく理解し、採用担当者が求める視点を踏まえた準備を整えることが、内定への近道といえるでしょう。
既卒就活は本当に厳しい?

大学在学中に就職活動がうまくいかず、既卒となった後に改めて就活を始める人は少なくありません。「既卒就活は厳しい」と耳にすると、不安を抱く学生も多いでしょう。
結論からいえば、新卒枠と比べてチャンスが限られ、選考基準が厳しくなる傾向があります。
ただし、企業が既卒者をすべて不利に扱っているわけではなく、新卒とは異なる強みを評価するケースも増えています。
ここでは、志望業界や職種の選び方、応募書類や面接対策、資格取得やスキル習得などの準備次第で、内定獲得の可能性を大きく高めることができることに注目してください。
重要なのは「既卒」という立場に引け目を感じるのではなく、これまでの経験や学びをどう伝え、採用側に納得感を与えるかです。
しっかり準備を整え、自分の強みを整理して挑むことで、既卒就活でも十分に成果を出せる環境は整っているといえるでしょう。
既卒就活が厳しいと言われる主な理由
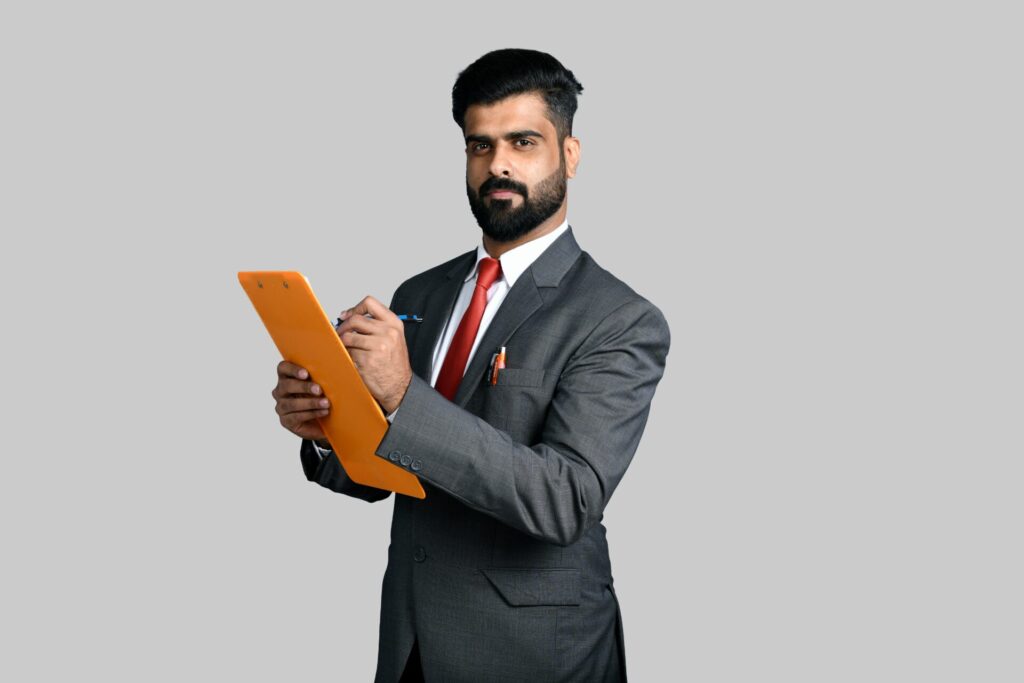
既卒就活が厳しい理由は、新卒採用が優先される日本特有の文化や企業側の枠の少なさ、空白期間の説明の難しさなど多岐にわたります。
ここでは、既卒就活が厳しい背景を一つずつ整理し、就活生が見落としがちなポイントや対策のヒントを紹介します。さらに学生目線で、実際にどのような準備や考え方が役立つかも触れていきます。
- 就職活動における新卒優先の文化
- 既卒者へのネガティブイメージ
- 企業側の既卒者採用枠の少なさ
- 即戦力が求められる中途採用では不利
- 空白期間の説明が難しい
- 実務経験やスキル不足
- 大学のキャリアセンターなど各種支援を活用しづらい
- 就職活動の情報量が少ない
- 年齢や社会経験の差による不利
- 志望動機や自己PRの作成が難しい
①就職活動における新卒優先の文化
日本では長年、新卒一括採用という仕組みが根付いており、企業は一度に多くの学生を採用して育成する方針を取ることが一般的です。
そのため既卒者は企業が用意する新卒採用枠から外れてしまうことが多く、応募先の選択肢が狭まりがちでしょう。
特に大企業ほどその傾向が強く、結果的に既卒者は求人情報の収集から選考対策まで多くの面で不利になりやすいです。
ただし中小企業や成長業界では既卒者を柔軟に採用するケースもあるので、志望先を広く設定し業界研究を深めておくことが突破口になります。
学生のうちから自分が興味ある業界を絞らずに探し、卒業後の動きをイメージしておくことがリスク回避にもつながるでしょう。
②既卒者へのネガティブイメージ
既卒者に対して「なぜ卒業後にすぐ就職しなかったのか」という疑問を持つ企業は少なくありません。これが先入観としてマイナス評価につながることがあります。
特に空白期間に何をしていたのか説明できない場合、採用担当者は自己管理能力や計画性に疑問を持つかもしれません。しかしインターンや資格取得など前向きな活動をアピールできれば評価は一転します。
準備段階で活動内容を整理し、自分の成長を具体的に伝える練習をしておくことが信頼回復の近道です。
学生の段階から「もし卒業後に活動が長引いたらどう説明するか」を意識し、今から行動記録をつけるだけでも後で役立つでしょう。
③企業側の既卒者採用枠の少なさ
企業は新卒枠と中途枠を明確に分けて採用活動を行うことが多く、既卒者向けの特別枠は限られています。
そのため求人票を見ても「新卒のみ」「社会人経験必須」といった条件が目立ち、応募できる企業が限られるのが現状です。しかし既卒歓迎の求人や通年採用を行う企業も増えつつあります。
業界や地域を広げて探し、転職サイトやエージェントを併用することで、自分に合う求人に出会える可能性が高まるでしょう。
学生目線では「卒業後もチャンスがある」という安心感を持ちつつ、今から複数の就活ルートを確保しておくことが重要です。
④即戦力が求められる中途採用では不利
中途採用では業務経験を持つ即戦力が求められることが多く、就業経験のない既卒者は不利になりがちです。特に専門スキルや実務経験が重視される職種では、書類選考で落とされることもあります。
ただしポテンシャル重視の企業や第二新卒枠を設けている企業なら、未経験からの挑戦を受け入れてもらえる場合があります。
志望職種の必要スキルを早めに調査し、オンライン講座やボランティアなどで経験を積んでおくと突破口になるでしょう。
学生時代にアルバイトやインターンを通じて業務の基礎を体験しておくことも、卒業後の就活を有利に進める助けになります。
⑤空白期間の説明が難しい
既卒就活においてもっとも大きなハードルのひとつが空白期間の説明です。採用担当者は「ブランクの理由」と「その期間に何を学んだか」を重視する傾向があります。
曖昧な答えや受け身な姿勢では不安を与えかねません。
しかし資格取得や語学勉強、ボランティアなど、前向きな活動をしていたのであれば、それを具体的な成果やエピソードとして説明することでプラス評価につながります。
事前にストーリーを整理し、面接練習で伝え方を磨いてください。学生時代から「空白を作らない」意識で、日々の活動を蓄積しておくことが後の安心材料になります。
⑥実務経験やスキル不足
既卒者は社会人経験がないことが多く、実務スキルやビジネスマナーに不安を抱かれることがあります。この点が中途採用候補との差になりやすく、内定獲得を難しくする一因でしょう。
ただし企業側も「素直さ」や「成長意欲」を評価する傾向があります。事前にインターンやアルバイトで業務を体験しておくと印象が大きく変わります。
さらに資格取得やポートフォリオ作成など、自分のスキルを見える形にすることで採用担当者への説得力が増すはずです。
学生のうちから職種に関連するスキルを少しずつ積み重ねておくことで、卒業後の不安を減らせます。
⑦大学のキャリアセンターなど各種支援を活用しづらい
既卒になると大学のキャリアセンターや就職課のサポートを受けにくくなるため、情報不足や孤独感に陥りやすいです。結果として自己流の就活になり、ミスマッチや選考落ちが増えることもあります。
しかし既卒者向けの就職エージェントや自治体のサポートを活用することで、この課題は解消できるでしょう。
専門アドバイザーから選考対策を受けることで視野が広がり、自分では気づけなかった強みを発見するチャンスも得られます。
学生のうちからキャリアセンターを積極的に使い、相談の仕方を覚えておくことも後に役立ちます。
「自分らしく働ける会社が、実はあなたのすぐそばにあるかもしれない」
就活を続ける中で、求人票を見て「これ、ちょっと興味あるかも」と思うことはあっても、なかなかピンとくる企業は少ないものです。そんなときに知ってほしいのが、一般のサイトには載っていない「非公開求人」。
①あなたの強みを見極め企業をマッチング
②ES添削から面接対策まですべて支援
③限定求人なので、競争率が低い
「ただ応募するだけじゃなく、自分にフィットする会社でスタートを切りたい」そんなあなたにぴったりのサービスです。まずは非公開求人に登録して、あなたらしい一歩を踏み出しましょう!
⑧就職活動の情報量が少ない
既卒者向けの求人情報は新卒や中途に比べて少なく、就活方法も明確なモデルがありません。そのため情報不足から誤った準備や自己流のアピールをしてしまうことがあります。
ただしSNSや専門サイト、既卒向けエージェントを活用することで情報格差を埋めることが可能です。既卒で内定を獲得した先輩の体験談を参考にすると、より現実的な対策が見えてくるでしょう。
行動量を増やしながら、情報を自分の中で整理することが大切です。学生時代から情報収集力を鍛え、複数のルートを持つことが卒業後の安心につながります。
⑨年齢や社会経験の差による不利
同じ既卒でも、年齢が上がるほど選考で不利になるケースがあります。これは企業が若手を育成するコストや適応力を考慮するためです。
ただし若さと柔軟性をアピールすることで印象を変えられる場合もあります。自分の年齢を不利と感じるよりも、むしろ経験値や視野の広さなどプラス面に転換して伝えることが重要です。
さらに職種選びを工夫することで、年齢のハンデを感じにくいフィールドを見つけてください。学生のうちに多様な経験を積み、自分の適応力や柔軟性を裏付けるエピソードを作っておくことが役立ちます。
⑩志望動機や自己PRの作成が難しい
既卒者は新卒時と比べて自分の立ち位置が変化しているため、志望動機や自己PRを作るのが難しくなりがちです。過去の挫折経験や空白期間をどのようにポジティブに伝えるかが成否を分けるでしょう。
ただし自己分析を深め、活動内容や強みを整理することで説得力のある文章が書けるようになります。
面接練習や模擬ESの添削を受けることで、自信を持って話せるようになり、採用担当者に前向きな印象を与えられるはずです。
学生時代から自分の強みや目標をノートなどに記録しておけば、卒業後の自己PR作成がスムーズに進むでしょう。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
既卒就活で内定獲得が難しい人の特徴

既卒就活で内定を得にくい人には共通する行動や考え方があります。これを知ることで、自分の弱点を早めに把握しやすくなり、より戦略的に動けるでしょう。
ここでは、その特徴を具体的に見ていきます。大学生のうちに知っておけば、卒業後のキャリア選択に役立つヒントにもなります。
- 既卒期間の空白を説明できない人
- 既卒になった理由が不明確な人
- 既卒であることをネガティブに捉えすぎている人
- 既卒ならではの強みや経験を言語化できていない人
- 新卒・中途どちらの枠で攻めるか戦略を決められていない人
- 既卒向けの求人・支援サービスを活用できていない人
- 年齢・時期の不利を過剰に意識してしまう人
①既卒期間の空白を説明できない人
既卒期間に空白があること自体は珍しいことではありませんが、その理由を明確にできないと採用担当者に疑問を抱かれやすくなります。
履歴の中に空白期間がある場合、その間の活動や目的が見えにくく、行動力や計画性に対する印象に影響を与えることがあります。
学生目線では「少し休んだだけ」という感覚でも、企業側からは情報不足に映り、判断材料が乏しいと捉えられがちです。
空白期間は経歴の中で特に注目されるため、既卒就活で不利になる一因になりやすい特徴といえます。
②既卒になった理由が不明確な人
既卒になった経緯をうまく説明できない場合、採用担当者に意思決定力や一貫性が不足していると見られる可能性があります。
背景があいまいだと、どのような目的や考えで行動してきたのかが伝わらず、将来の計画性にも不安を持たれることがあります。
学生からすると「色々事情があった」という感覚かもしれませんが、企業はその理由の裏にある価値観や判断基準を知りたいと思うものです。この不透明さが既卒就活の難しさにつながる特徴の一つです。
③既卒であることをネガティブに捉えすぎている人
既卒という立場に強いコンプレックスを持ちすぎると、自信のなさが書類や面接での態度に表れ、評価が下がりやすくなります。
学生目線では「既卒は不利」という情報が多く見えるため、自己評価を必要以上に低くしてしまいがちです。
こうした心理状態は発言や振る舞いに影響し、結果的に採用担当者にマイナスの印象を与えることがあります。既卒であること自体より、その受け止め方が選考に大きく影響するのが特徴です。
④既卒ならではの強みや経験を言語化できていない人
既卒期間に得た経験やスキルを整理できていない場合、企業側に自分の価値を伝えにくくなります。
アルバイトや課外活動、学習などさまざまな経験をしていても、それを具体的な成果やスキルとしてまとめられないと、単なる時間経過として見られがちです。
学生の段階では「いろいろやってきた」という実感があっても、企業は何をどれだけ身につけたかを知りたがります。このギャップが評価の低下につながる特徴となります。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
⑤新卒・中途どちらの枠で攻めるか戦略を決められていない人
新卒枠か中途枠か、どちらで応募するかを決められないまま就活を進めると、志望動機や自己PRに一貫性がなくなりやすいです。
企業は応募者の立ち位置やキャリアの方向性を確認し、その上で採用可否を判断します。
学生感覚では「とりあえず応募してから考える」という姿勢が自然かもしれませんが、企業側には計画性がないように映ることがあります。この曖昧さが、内定獲得を難しくする要因の一つです。
⑥既卒向けの求人・支援サービスを活用できていない人
既卒者向けの求人サイトや支援サービスを使っていない場合、情報不足や選択肢の偏りが起こりやすくなります。
企業によっては既卒や第二新卒を積極的に採用しているケースがあるため、こうした情報にアクセスしないことで機会を逃しやすい状況になります。
学生時代のようにキャリアセンターが情報を集めてくれる環境がないため、自分で情報網を持たない人ほど不利に立たされる傾向があります。これも既卒就活が難しいと感じられる特徴の一つです。
⑦年齢・時期の不利を過剰に意識してしまう人
年齢や就活時期の遅れを過剰に気にしすぎると、自信のなさや焦りが選考で伝わってしまいます。
学生目線では「卒業したらすぐに就職しないと不利」というイメージが強いため、自分を必要以上に追い込んでしまうことがあります。
この心理的な負担が、選考中の態度や回答内容に影響し、結果として評価を下げる要因になる場合があります。実際の不利さ以上に、自分の意識がマイナス効果を生んでしまうのが特徴です。
企業が既卒者を評価するポイント

就活で既卒という立場にあると、多くの学生が「企業はどう見ているのか」と不安を感じるでしょう。
実際には、既卒であること自体よりも、その背景や行動の一貫性、そして成長への姿勢が評価されることが多いです。
ここでは、企業が既卒者を評価するポイントを見ていくことで、自分の強みや課題を整理し、就職活動に活かすヒントを得てください。
学生目線で見れば、企業がどこを見ているかを理解するだけで、自分に必要な準備や行動の方向性が明確になり、安心感にもつながるでしょう。
- 既卒期間をどう過ごしたか
- 既卒になった理由を納得感のある形で説明できるか
- 既卒でも高い入社意欲・成長意欲を示せているか
- 空白期間を活かしたスキル習得や資格取得があるか
- 社会人経験や即戦力スキルを持っているか
- 既卒ならではの柔軟性・適応力を発揮できるか
- ネガティブ要素をプラスに変える自己PR力があるか
①既卒期間をどう過ごしたか
既卒期間の過ごし方は、企業が最も注目するポイントの1つです。時間の使い方から本人の主体性や責任感が見えるため、採用担当者はその期間の具体的な行動に目を向けます。
アルバイトやボランティア、インターンシップなど社会経験を積んでいれば、現場感覚や適応力として評価されることが多いですし、
自己分析や業界研究など将来を見据えた活動をしていれば、前向きさや成長への意欲が伝わります。
学生にとっては、この期間が単なる空白ではなく行動の履歴として見られていることを理解することが大切ですし、日々の活動の積み重ねがそのまま評価につながる点を意識しておくと良いでしょう。
②既卒になった理由を納得感のある形で説明できるか
企業は「なぜ既卒になったのか」という背景を知ることで、その人の価値観や判断力、そして物事への向き合い方を見ています。
理由が避けられない事情であっても、その後の行動や考え方に一貫性があり、誠実さが感じられれば信頼につながるでしょう。
説明の仕方ひとつで相手の受け取り方は大きく変わるため、企業はそこからその人の成長性や柔軟性も読み取ります。
学生視点では、この点が企業にとって人柄や将来性を測る重要な材料になっていると理解しておくことが大切で、単なる経緯の説明以上に、その後どう過ごしたかが評価のポイントになることを意識しておくと安心です。
③既卒でも高い入社意欲・成長意欲を示せているか
企業は、既卒者に対して「本当に働く意欲があるか」「成長する意欲があるか」という点を注視しています。
志望理由や価値観に明確な筋道があるかが、その人のモチベーションや将来性を判断する目安になるからです。
企業は、単に「働きたい」という言葉ではなく、どのような姿勢や考え方で仕事に臨もうとしているかを見ています。
学生から見れば、ここは自分の将来像や姿勢がそのまま評価される部分だと考えるとわかりやすく、日々の行動や考え方が企業にどのように映るかを意識することが求められるでしょう。
④空白期間を活かしたスキル習得や資格取得があるか
企業は、空白期間中にどんな活動をしていたかを細かく見ています。
資格取得やスキル習得など、具体的な成果があれば主体性や努力する姿勢が伝わりやすく、長期間のブランクがあってもプラス評価されることがあります。
企業はその内容や選んだ理由から、応募者がどのような視点でキャリアを考えているかも見ています。
学生にとっては、この期間が努力の証明として評価されることを理解しておくことがポイントであり、自分の活動がどんな意味を持つかを整理しておくことが将来の就活に役立つでしょう。
⑤社会人経験や即戦力スキルを持っているか
企業は、社会人経験や業務に役立つスキルを既に持っているかを重視します。こうした経験は早期に戦力化できる可能性を示すため、採用判断に大きな影響を与えます。
社会人経験がある場合、その経験値の深さや多様性が評価のポイントとなり、ない場合でも活動内容やスキルをどれだけ活かせるかを見ています。
学生視点から見ると、インターンや長期アルバイトなども将来的に評価される経験のひとつとなり得るため、自分の活動がどのような価値を持つかを理解しておくことが重要でしょう。
⑥既卒ならではの柔軟性・適応力を発揮できるか
企業は、多様な経験を持つ既卒者に対して柔軟な対応力や適応力を期待しています。新しい環境でもすぐに順応できる資質や行動の幅広さが評価され、変化に強い人材として見られることが多いです。
企業は過去の経歴から、その人が異なる環境でどう行動したか、何を吸収したかを見極めます。
学生としては、自分の経験が環境変化への強さを示せる点を理解しておくことが大切で、多角的な視点や幅広い経験が評価の後押しになることを知っておくと安心です。
⑦ネガティブ要素をプラスに変える自己PR力があるか
企業は、既卒という状況をどのように受け止め、どのように自分の強みに転換しているかを見ています。
過去の経験を前向きに語れる力は、信頼感や成長意欲の証とされ、特に困難を乗り越えた経験がある場合には評価の対象となりやすいです。
企業は単なる出来事ではなく、その人の物事の捉え方や変化の仕方を重視しています。
学生の立場からは、失敗や空白も評価の対象になりうると認識しておくことが重要で、自分の過去をどのように見せるかが企業評価に直結することを理解しておくと良いでしょう。
既卒者が就職するために準備すべきこと

既卒の就活は、新卒に比べて応募のチャンスや評価基準が変わるため、事前準備の質が大きな差を生みます。
限られた時間で効率的に成果を出すには、自己分析や企業研究だけでなく、面接・志望動機の対策や資格取得など多方面で整える必要があります。ここでは、具体的な準備項目を詳しく解説します。
これから就職活動に挑む大学生にとっても、卒業後の選択肢を見据えた準備は大きな武器となるでしょう。
- 自己分析の徹底
- 業界・企業研究の実施
- 既卒期間中の経験の整理
- 面接や志望動機の準備
- 就活に有利な資格・スキル習得
- 就活スケジュールの作成
- 就職活動の相談環境の整備
- 自己PR・志望動機の差別化
①自己分析の徹底
既卒での就活では、自分の強みや価値観を正確に把握することが内定への第一歩でしょう。
企業は新卒よりも「人柄や成長可能性」を重視する傾向があるため、自分の軸を持たないままでは説得力に欠けます。
過去の学業・アルバイト・ボランティア経験を振り返り、どんな場面で成果を出せたか整理してください。応募書類や面接で一貫したアピールが可能になります。
さらに、他者にヒアリングして客観的な評価を得るのも効果的です。学生時代からこの習慣を持っておくと、卒業後のキャリア選択にも役立ちます。
こうした準備により、企業に「入社後の活躍イメージ」を伝えやすくなり、結果的に内定獲得の可能性を高められるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②業界・企業研究の実施
既卒者は新卒と違い、応募の幅が広い一方で「なぜその業界・企業なのか」を厳しく問われやすいです。だからこそ、企業研究を深く行い、自分の希望条件と照らし合わせることが欠かせません。
業界の将来性や働き方、必要スキルなどを調べると、自分が活躍できる環境が見えてきます。OB・OG訪問やSNSなどを活用してリアルな声を収集するのも有効でしょう。
学生のうちから情報収集の習慣をつけておくと、将来既卒で就活することになっても落ち着いて対応できます。
こうした情報を基に志望動機を組み立てれば、採用担当者に「長く活躍してくれそう」という安心感を与えられます。結果として、応募の質が上がり、内定への道が近づきます。
③既卒期間中の経験の整理
既卒期間の過ごし方は企業が注目するポイントの一つです。空白期間があっても、どのように自己成長やスキル習得に取り組んだかを整理して伝えられれば、むしろプラスの評価につながります。
アルバイトや資格取得、ボランティアなどで得た経験を具体的にまとめ、成果や学びを明確にしておくことが大切です。「主体的に行動できる人材」という印象を与えられます。
無職期間がある場合でも、目標や取り組みを正直に説明してください。誠実さが伝わり、信頼感が増します。
大学生のうちにインターンや課外活動に積極的に挑戦しておくと、後に既卒となった場合にも説明しやすいでしょう。こうした準備が内定獲得の大きな後押しとなります。
④面接や志望動機の準備
面接や志望動機は、既卒就活の合否を左右する重要なポイントです。既卒であること自体は不利になりがちですが、理由や背景をポジティブに説明できれば印象を変えられます。
志望動機は「なぜその企業・職種なのか」「将来どのように貢献できるか」を具体的に示してください。
面接練習は、友人やキャリアセンター、オンライン面談などを活用すると客観的な改善点が見つかります。回答例を丸暗記するのではなく、自分の言葉で話すことが信頼感を高めるポイントです。
学生時代から模擬面接に慣れておくと、卒業後もスムーズに対策できるでしょう。こうした準備を丁寧に行うことで、不利を逆転するチャンスをつかめます。
⑤就活に有利な資格・スキル習得
既卒の就活で強みを作るには、資格やスキルの取得が有効です。業界で評価されやすい資格や実務に直結するスキルは、即戦力としての印象を高めます。
事務職ならMOSや簿記、IT系ならプログラミングや基本情報技術者などが挙げられるでしょう。学習中の段階でも履歴書に記載することで「努力している姿勢」を示せます。
資格学習は自信を持つきっかけにもなるため、面接での発言に説得力が増します。学生のうちから資格勉強に取り組むことで、卒業後すぐに就活へ生かせる点もメリットです。
スキル習得は短期的な武器だけでなく、長期的なキャリア形成にもつながるため意識して取り組んでください。
⑥就活スケジュールの作成
既卒就活は新卒と異なり、決まった採用スケジュールが存在しません。自分で計画的に動かなければチャンスを逃しやすくなります。
応募書類の準備、企業研究、面接対策などのステップを逆算してスケジュールを立てることが重要です。スケジュール管理ツールやカレンダーアプリを活用すれば、抜け漏れを防げるでしょう。
計画を立てる過程で自分の弱点や優先順位が明確になり、効率的に行動できます。学生時代から時間管理に慣れておくと、卒業後の就活でも落ち着いて対応できます。
こうした習慣は入社後の業務にも役立つため、企業からの評価も高まりやすくなります。
就活では、多くの企業にエントリーしますが、その際の自分がエントリーした選考管理に苦戦する就活生が非常に多いです。大学の授業もあるので、スケジュール管理が大変になりますよね。
そこで就活マガジン編集部では、忙しくても簡単にできる「選考管理シート」を無料配布しています!多くの企業選考の管理を楽に行い、内定獲得を目指しましょう!
⑦就職活動の相談環境の整備
孤独になりがちな既卒就活では、相談できる環境を持つことが重要です。
キャリアセンターやハローワーク、就職エージェント、オンラインコミュニティなどを活用すれば、客観的な助言や求人情報を得られます。
第三者の意見を取り入れることで、自分では気づけない改善点が見つかることもあるでしょう。
特にエージェントは非公開求人や書類添削、面接対策など総合的なサポートを受けられるため、有効活用する価値があります。
大学生のうちから相談相手を見つけておくと、卒業後も安心して就活に臨めます。相談環境を整えることで精神的な負担も減り、就活を長期的に続けやすくなります。
⑧自己PR・志望動機の差別化
既卒者は新卒に比べ、差別化の工夫が必要不可欠です。同じ志望動機やPRでは埋もれてしまうため、自分だけの経験や視点を際立たせることが大切でしょう。
アルバイトやインターンでの成果を具体的に数値で示す、独自の学習経験を語るなど、具体性を持たせると印象に残ります。
面接やエントリーシートに一貫性を持たせることで信頼感が増し、企業側も安心して採用できます。業界特有のニーズを研究し、自分のスキルや強みを紐づけることで説得力が高まるでしょう。
学生時代から自己分析や発信力を高めておけば、卒業後の差別化もしやすくなります。こうした差別化が内定への最短ルートとなります。
既卒者が内定を得るための方法

既卒者が内定を得るには、行動量と戦略性が大切です。採用担当者の目線に立ち、自分の強みを実際の行動で伝える工夫が欠かせません。
ここでは就活サイトやエージェントの活用、実務経験を踏まえた応募、幅広い業界への挑戦、面接でのアピール方法、そしてネット情報への向き合い方まで、実践的なポイントに絞って解説します。
行動のコツを知ることで、結果を早く出しやすくなるでしょう。
- 就活サイトを活用する
- エージェントやハローワークを利用する
- アルバイトやインターン経験から正社員を目指す
- 幅広い業界・職種へ応募する
- 面接で成果を具体的に伝える
- ネットの情報を鵜呑みにせず行動する
①就活サイトを活用する
就活サイトは、既卒者が求人を探すうえで最も直接的に活用できる手段です。まずは既卒・第二新卒向けの求人が多いサイトに登録し、毎日更新される求人に積極的に応募してください。
気になる企業にはスカウト機能やオファー機能を使い、短期間で面接に進めるよう調整することがポイントです。
また、応募した企業の採用ページや口コミをチェックし、面接前に企業研究を実践することが結果につながります。
待つだけではなく、毎日数件ずつ応募するような“行動習慣”をつけると好機を逃しにくくなります。
②エージェントやハローワークを利用する
エージェントやハローワークを実際に利用することで、求人探しが一気に効率的になります。
エージェントでは担当者と週1回の面談を設定し、履歴書添削や面接練習をその場で受けながら応募を進めると効果的です。
ハローワークでは、求人票を見ながらそのまま応募書類を提出したり、職業相談で条件交渉のコツを学んだりすることが可能です。
特に既卒の段階では、実際に窓口へ足を運び担当者に顔を覚えてもらうことが、選考を有利に進める近道になります。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
③アルバイトやインターン経験から正社員を目指す
既卒の場合、今働いているアルバイト先や過去のインターン経験を、積極的に正社員登用のきっかけに変える行動が重要です。
責任ある仕事を任せてもらえるよう自分から提案し、その成果を明確な数字や行動で示すことで、企業側も採用を検討しやすくなります。
また、在職中であっても他社に応募することをためらわず、並行して活動するのも実践的な方法です。現場での実績を面接で具体的に伝えることで、即戦力感を強くアピールできるでしょう。
④幅広い業界・職種へ応募する
既卒の就職活動では、実際に応募する数を増やすことが鍵となります。業界や職種にこだわり過ぎず、週に複数の分野へ応募し、面接の場数を踏むことで自分の強みを発見しやすくなります。
応募のたびに履歴書や職務経歴書を調整し、企業ごとの特性に合わせることも欠かせません。
面接の練習と同じように応募自体を実践的なトレーニングととらえることで、スピード感のある活動が可能になります。応募数が増えると同時に自己分析も深まり、志望先の方向性がより鮮明になるでしょう。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
⑤面接で成果を具体的に伝える
面接では、空白期間を説明するだけでなく、その期間に何をしてきたかを事実ベースで話すことが大切です。
例えばアルバイトで担当したプロジェクトや改善した業務の具体例を、数字や成果を添えて伝えると説得力が増します。
また、複数の企業の面接を連日受けることで、自分の話し方や回答の精度を高める実践訓練になります。
1社1社に全力を尽くしつつ、経験値を積んでいくイメージで進めると自信も自然とついてくるでしょう。面接後には振り返りを行い、次の面接で改善を重ねてください。
⑥ネットの情報を鵜呑みにせず行動する
ネットの情報は参考にはなりますが、それだけで判断すると行動が止まりやすくなります。
既卒採用に積極的な企業は実際に存在するため、気になる企業があれば説明会や個別面談に申し込み、現場の担当者に直接質問することが大切です。
応募企業が多いほど実体験としての情報が蓄積され、ネットの噂よりも正確な判断材料を持てるようになります。
特に面接や説明会で感じた印象やフィードバックは、自分自身の判断軸として強力な武器になります。行動を優先することで、自信を持って活動できるでしょう。
既卒者が狙うべき職種・業界

既卒者が就職活動で不安に感じやすいのは「自分に合う業界や職種が分からない」という点でしょう。実際には既卒でも活躍しやすい分野が複数あり、選択肢を知ることで将来の方向性を明確にできます。
ここでは既卒者が比較的採用されやすく、成長できる業界・職種を取り上げ、それぞれの特徴やポイントを詳しく解説します。
学生のうちから視野を広げておくと、自分に合う仕事を選びやすくなり、就活への不安も軽減できるでしょう。
- 営業職
- 接客・サービス業
- IT業界
- 工場勤務
- 介護職
- 公務員
- 社会人向けインターン参加可能な業界
- 専門職・資格職(看護師、保育士など)
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①営業職
営業職は既卒者でも応募しやすく、成果に応じて評価される環境が整っています。未経験でも研修制度がある企業が多く、実力次第でキャリアアップも目指せます。
特にコミュニケーション力や提案力を磨けば、自分の強みを活かしやすいでしょう。企業側も若手人材を育てたい意欲が強いため、潜在能力や前向きな姿勢が評価されやすいです。
さらに営業職は社会人基礎力を幅広く身につけられるため、将来的な転職やキャリアチェンジの際にも有利に働きます。
学生時代に培ったアルバイトやサークルでの経験を自己PRに活用できるのもポイントです。選考時には過去の経験だけでなく、なぜ営業に挑戦したいのかを明確に伝えてください。
②接客・サービス業
接客・サービス業は人と接する仕事が多く、既卒者が持つ柔軟性やコミュニケーション力が活かせます。ホテルや飲食、販売など幅広い分野があり、興味や適性に合わせて選べる点が魅力です。
経験が少なくても研修を通じてスキルを身につけやすく、現場での評価が次のステップにつながるでしょう。顧客対応の経験は他業種への転職にも役立つため、将来のキャリア形成に有利です。
さらに、接客を通して学べるチームワークや臨機応変な対応力は、どの業界でも重宝されるスキルです。学生時代にアルバイトで接客経験がある場合は、それを強調することで選考で好印象を与えられます。
応募時には笑顔や接客姿勢などの印象を意識してください。
③IT業界
IT業界は人材不足が続いており、既卒者でも挑戦しやすい分野です。未経験者向けの研修やスクールを活用すれば、プログラミングやネットワークの基礎を学べます。
システム運用やサポート業務から始めるとキャリアの幅を広げやすいでしょう。企業はスキル習得への意欲や論理的思考を重視する傾向があるため、学習姿勢が強いほど評価されやすいです。
将来的には専門性を高めることで年収やポジションの向上も期待できます。さらにIT業界は新しい知識に触れる機会が多く、学生時代からITに興味があった人にとってはやりがいを感じやすい職場です。
資格取得やプログラミング学習などを自主的に進めていると、面接でアピール材料になります。
④工場勤務
工場勤務は安定した需要があり、未経験から始めやすい職種です。製造ラインや品質管理などの仕事は、コツコツ取り組む姿勢や責任感が評価されます。
シフト制の企業も多く、生活リズムを整えやすいのも特徴です。資格取得支援制度がある職場も多く、スキルを積み上げてキャリアアップする道が開けます。
さらに、現場での改善提案や新しい取り組みに積極的に関わることで、早期の昇進や職務拡大も期待できるでしょう。
学生時代に培った体力や忍耐力、サークル活動などでの協調性をアピールすると好印象です。応募時には体力面やチームワークへの適性をアピールしてみてはいかがでしょうか。
⑤介護職
介護職は社会的ニーズが高く、既卒者でも歓迎されやすい業界です。人と接する力や思いやりが評価されるため、学歴や職歴に不安があっても挑戦しやすいでしょう。
多くの施設では資格取得支援制度があり、働きながら介護福祉士などの資格を取得できます。長く働くほど専門知識や経験が身につき、安定したキャリア形成が可能です。
さらに高齢化社会が進む中で、介護職は今後ますます重要になる分野であり、将来的な需要も見込めます。
学生時代にボランティアや地域活動に参加した経験がある人は、それを志望動機に活かせるでしょう。応募時にはなぜ介護職に興味を持ったのかを具体的に説明することが採用のカギになります。
⑥公務員
公務員は安定性が高く、既卒者も試験に合格すれば同じスタートラインに立てます。市役所や県庁、警察、消防など幅広い職種があり、興味や強みに応じて選べるのが特徴です。
試験対策には時間が必要ですが、計画的に学習すれば着実に力をつけられます。特に地域への貢献や公共性への理解を志望動機に盛り込むと、面接で好印象を与えやすいでしょう。
さらに公務員は長期的なキャリアを築きやすく、安定した生活基盤を得られる点も大きな魅力です。
学生時代からボランティアや自治体関連の活動に参加していれば、志望動機として説得力を持たせられます。長期的なキャリアを視野に入れる人には大きな魅力があります。
⑦社会人向けインターン参加可能な業界
社会人向けインターンは、既卒者が実務経験を積む貴重な機会です。短期間で複数の企業文化や仕事内容を体感でき、自分に合った職種を見極めやすくなります。
IT・ベンチャー企業や人材業界など、柔軟な働き方を提供する企業が多く、スキルアップにも直結します。さらにインターン経験を通じて業界の知識を深め、人脈を築くことも可能です。
学生時代にインターンやアルバイトで培ったスキルや経験を整理しておくと、応募の際にアピールしやすくなるでしょう。
選考時にはなぜその業界に挑戦したいのかを具体的に説明し、積極的に質問する姿勢を見せると印象が良くなります。結果的に内定につながるケースも少なくありません。
⑧専門職・資格職(看護師、保育士など)
専門職や資格職は、資格を持つことで安定した需要が見込める分野です。看護師や保育士などは人手不足が続いており、既卒でも経験を積みながらキャリア形成が可能でしょう。
資格をまだ持っていない場合でも、働きながら取得を目指せる制度が整っている職場もあります。自分の得意分野や興味に合わせて選ぶことで、長期的なキャリアを築きやすくなります。
さらに専門職は社会に直接貢献できる実感を得やすく、やりがいの大きさも魅力です。学生時代に学んだ専門知識やボランティア活動を活かして挑戦することもできます。
応募時には資格取得への意欲と将来のビジョンを具体的に示してください。
既卒就活を成功させるために今から準備しよう

既卒就活は「厳しい」と言われがちですが、ポイントを押さえた準備と戦略で大きく差をつけられます。
まず、既卒であることの定義や新卒・第二新卒との違いを理解し、企業側が重視する評価ポイントを把握しましょう。
そのうえで、空白期間や志望動機などネガティブに見られやすい要素を、自己分析や経験整理、スキル習得によってポジティブに変えることが大切です。
また、就活サイトやエージェント、幅広い業界への挑戦など、行動の幅を広げることで内定獲得の可能性が高まります。
既卒就活は確かに厳しい一面がありますが、自分の強みや経験を的確に伝える準備を整え、積極的に行動することが成功への近道です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。