内定健康診断書の提出完全ガイド|取得方法・期限・注意点を解説
「内定後に健康診断書を提出してください」と企業から案内されたものの、どこでどう準備すれば良いのか迷っていませんか?
就活を終えた安心感も束の間、健康診断書の取得や提出期限に対応しなければならず、不安になる学生も少なくありません。
そこで本記事では、健康診断書の取得方法や注意点を網羅的に解説しつつ、大学や病院での入手手順から提出時のマナー、結果による内定取消の可能性まで、押さえておくべきポイントを具体的にまとめました。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
内定先に提出する健康診断書とは?

就活で内定が決まったあと、多くの企業が健康診断書の提出を求めますが、健康診断書は、企業が内定者の健康状態を確認し、労働環境の安全を確保するための重要な書類です。
特に、安全性が重視される職種や長時間の業務が予想される職種では、健康状態が業務に影響しないかを確認する目的もあります。
また、提出期限が決まっていることも多く、事前に準備しておくとスムーズに入社手続きを進めやすくなるでしょう。
大学で受けた定期健康診断や病院での診断結果を利用できる場合もあり、余裕を持って準備しておくことが大切です。
内定後に健康診断書の提出が求められる理由

就活で内定が決まったあと、多くの企業が健康診断書の提出を求めています。入社予定者の健康状態を把握し、働く環境や業務内容に支障がないか確認するためです。
ここでは、企業が健康診断書を求める理由を3つに分けて説明します。
- 企業が内定後に健康診断書の提出を義務としているため
- 特定の職種や業界では健康診断書の提出が必須であるため
- 入社予定者の健康状態を確認するため
①企業が内定後に健康診断書の提出を義務としているため
企業は、労働安全衛生法などの法律に基づき、雇用前に健康診断を行う義務を負っている場合があります。そのため、内定者にも健康診断書の提出を求めることが多いです。
これにより企業は、入社後の健康トラブルを未然に防ぐ体制を整えられます。さらに、内定後に健康診断書を提出させることは、企業にとって採用後のリスクを減らすための重要なプロセスともいえるでしょう。
提出期限が明確に決められている場合が多く、期限を過ぎると入社手続きが遅れる可能性もあるため、早めに予約・受診・発行を進めておくと安心です。
②特定の職種や業界では健康診断書の提出が必須であるため
運輸・医療・製造業など一部の業界や職種では、安全管理や衛生管理の観点から、より詳しい健康診断書が必要とされています。
こうした業界は業務上のリスクが高く、心身の状態が業務遂行に直結するため、必ず健康診断書を求める傾向があります。
また、これらの業界では、法律や業界基準に基づいて検査項目が細かく定められていることが多く、通常より厳しい内容の検査を受ける必要があるケースもあるでしょう。
業種によっては、一般的な健康診断書に追加の検査結果が求められる場合もあるため、企業からの案内や提出書類の条件を事前にしっかり確認しておくことが重要です。
③入社予定者の健康状態を確認するため
企業は、内定者の健康状態を把握することで、業務内容や配置を適切に決めやすくなります。特に、長時間労働や体力を必要とする仕事では、健康状態を正しく把握することが重要です。
健康診断書は個人情報の扱いに注意して提出されますが、その目的は本人と企業双方にとって安全で快適な職場環境を整えることにあります。
さらに企業側にとっては、特定の業務に健康上の制約がないかを早めに知ることで、配置変更や業務内容の調整などを事前に行えるというメリットもあるでしょう。
事前に必要な検査や書類をそろえておくことで、提出時に慌てることなく入社手続きをスムーズに進められるはずです。
「健康診断書」と「健康診断証明書」の違い
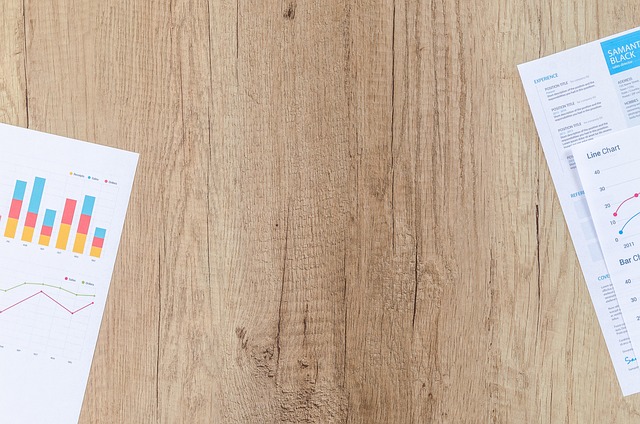
就活で内定が決まったあと、多くの企業から健康診断に関する書類提出を求められますが、「健康診断書」と「健康診断証明書」は似ているようで役割が異なります。
健康診断書は、医療機関で健康診断を受けた際に発行される公式な書類です。診断結果には身長・体重・血圧・視力などの基本検査から、胸部X線や血液検査まで幅広く記載されます。
企業がこの書類を求めるのは、入社予定者の健康状態をより詳しく把握し、職場での安全を確保するためです。
一方、健康診断証明書は大学などの保健管理センターが発行する簡易的な証明書です。診断書ほど細かい検査結果は載っていませんが、一定の健康診断を受けたことを示す書面として利用されます。
提出先によって必要な書類が異なる場合もありますので、指定内容を必ず確認してください。事前に企業が求めている書式や発行元を把握しておくと、提出時に慌てることなく、スムーズに手続きを進められるでしょう。
健康診断書の必要な検査項目

就活で企業に提出する健康診断書には、基本的な検査だけでなく職務適性を確認するための多様な項目が含まれます。
ここでは、主な検査項目を4つに分けて紹介し、どんな内容が重視されているのかを解説します。
- 既往歴や業務歴の確認項目
- 身長・体重・腹囲・視力・聴力の測定項目
- 胸部エックス線・喀痰検査などの画像診断項目
- 血圧・血液・尿・心電図などの生理学的検査項目
①既往歴や業務歴の確認項目
企業は、応募者の過去の病歴や業務歴を確認し、業務上の制限や配慮が必要かどうかを判断します。既往歴や業務歴の欄は、健康診断書の冒頭に記載されることが多く、入社後のトラブル防止に役立つでしょう。
この項目には、慢性的な疾患の有無や過去の手術歴、職務中に特別な配慮を要する事項などが含まれる場合があり、企業にとって採用後のリスクを減らすうえで重要な判断材料となります。
正確に記入することが求められ、虚偽の申告は後に問題を招く可能性があるため注意が必要です。
また、必要に応じて主治医の診断書や、補足資料を提出するよう求められることもあり、正確性と透明性が何より大切になります。
②身長・体重・腹囲・視力・聴力の測定項目
身長・体重・腹囲・視力・聴力といった基本測定は、職務に支障がないかを確認する基準になります。これらの測定値は、日常的な健康管理や体調変化を把握するうえでも重要です。
特に、視力や聴力は安全管理が必要な仕事で重視されることが多く、企業によっては一定の基準が設定される場合もあります。
さらに、測定結果は個々の健康維持や生活習慣改善の参考にもなるため、学生自身にとってもメリットがあるでしょう。
たとえば、腹囲の数値は生活習慣病リスクの把握につながり、体重の増減や視力の変化は早期の健康対策に役立ちます。
こうした基本測定の結果は、職場環境や仕事内容を決定する際の大切な資料となり、採用後の配置にも影響する場合があるため、慎重に扱うことが必要です。
③胸部エックス線・喀痰検査などの画像診断項目
胸部エックス線検査や喀痰検査は、呼吸器系疾患や感染症を早期に発見するために行われています。これらの検査は、集団で働く環境における安全確保に直結するのです。
特に、結核や慢性的な肺疾患などは、早期発見と予防が重要であり、健康診断書での結果確認が不可欠です。企業はこの結果を参考に、本人や職場全体への健康リスクを減らす取り組みを進めやすくなります。
また、画像診断は外見上ではわからない体の内部状態を把握するため、より精密な健康チェックが可能です。
こうした検査結果は、長期的な就業継続や安全配慮義務の履行にもつながるため、学生側も事前に指示された項目をしっかり確認し、受診漏れがないよう注意してください。
④血圧・血液・尿・心電図などの生理学的検査項目
血圧測定や血液・尿・心電図検査などは、生活習慣病や循環器系疾患の兆候を把握するために必要です。これらの項目は、特に長時間労働や体力を使う仕事で重要視されています。
生理学的検査は、個人の基礎的な健康状態をより具体的に数値化できるため、体調の変化を早期に発見しやすくなる利点があります。
血液検査では貧血や肝機能、腎機能など多方面にわたる健康状態を把握でき、尿検査は感染症や代謝異常を見つける手がかりになっています。
また、心電図検査は不整脈や心臓疾患の早期発見に役立ち、就業中の急な健康リスクを防ぐためにも欠かせません。
事前に健康状態を確認することで、入社後の体調悪化を防ぎ、働く環境の安全性を高められるでしょう。
大学で受けた健康診断書を取得する方法

就活で企業に提出する健康診断書は、大学で受けた定期健康診断の結果を活用できることがあります。
ここでは、大学で健康診断書を取得する3つの方法を紹介し、スムーズに準備するポイントを解説します。
- 大学の保健管理センターで発行する
- 大学の自動証明書発行機で取得する
- オンライン申請で取り寄せる
①大学の保健管理センターで発行する
大学の保健管理センターでは、在学生向けに健康診断書を発行しています。窓口で学生証や必要書類を提示するだけで手続きができ、費用も比較的安く済むのが特徴です。
発行には数日かかることもあり、就活で提出期限が決まっている場合は早めに申し込みをしておくことが大切になります。複数通が必要な場合は、同時に申請しておくと後の手間を減らせるでしょう。
また、保健管理センターでは過去の健康診断結果の保管状況によって、発行できる範囲が異なる場合があり、年度が変わっていると再検査が必要なこともあるため、事前に確認しておくと安心です。
必要に応じて電話やメールで問い合わせて、発行までの流れや所要日数を把握しておくとさらにスムーズに進められます。
②大学の自動証明書発行機で取得する
多くの大学には、自動証明書発行機が設置されており、健康診断書を簡単に取得できます。
学生証を使ってその場で申請し、数分で発行できるケースも多く、窓口よりもスピーディーに利用できるのが大きなメリットです。
ただし、発行機の利用可能時間や台数には限りがあり、特に昼休みや就活シーズンには混雑することが予想されるため、余裕を持って行動することが重要になります。
また、年度をまたいで発行する場合や、最新の健康診断結果が反映されるまでのタイムラグがある場合もあるため、事前に大学のホームページや掲示で発行開始日を確認するとよいでしょう。
加えて、印刷不良や紙詰まりなどのトラブルも稀に発生するため、急ぎの際は窓口発行との併用も検討してください。
③オンライン申請で取り寄せる
最近では、オンライン申請に対応している大学も増えており、スマートフォンやパソコンから簡単に手続きを進められます。
インターネット上で申請し、郵送か窓口受け取りを選べる場合が多く、忙しい就活時期でも移動せずに準備を整えられるのが魅力です。
特に、遠方での就職活動をしている学生にとっては、オンライン申請は時間と労力の節約につながります。
ただし、郵送を選んだ場合は到着までに日数がかかることがあるため、企業の提出期限から逆算して早めに申し込むことが欠かせません。
さらに、大学によってはオンライン申請の際に手数料が発生したり、申請内容に不備があると発行が遅れたりすることもあるため、入力内容を慎重に確認してください。
申請後に発行状況をオンラインで確認できるシステムを備えている大学もあるので、活用することで安心して準備を進められます。
大学以外で健康診断書を取得する方法

大学での健康診断書発行に間に合わない場合や、より詳細な検査が必要な場合は、大学以外の医療機関を利用する方法があります。
ここでは、3つの取得方法を紹介し、それぞれの特徴や注意点を説明しましょう。
- 病院・クリニックで取得する
- 自治体の保健センターで取得する
- 企業指定の医療機関で取得する
①病院・クリニックで取得する
一般の病院やクリニックでは、自費で健康診断を受けることができます。検査内容や料金は医療機関によって異なり、検査の所要時間や結果が出るまでの日数にも幅があります。
企業が指定する検査項目や書式がある場合は、予約の時点で必ず伝え、必要な内容が網羅されているかを確認することが重要です。
特に、心電図や血液検査、X線検査などは追加費用が発生することがあるため、料金体系を事前に把握しておくと安心でしょう。
また、繁忙期や健診シーズンには予約が取りにくくなるため、少なくとも提出期限の2〜3週間前には申し込みを済ませておくのがおすすめです。
発行までに時間がかかる場合もあるので、スケジュール全体を見越して計画的に動くことが大切になります。
②自治体の保健センターで取得する
自治体の保健センターでも、定期的に健康診断を実施しており、比較的安価で受けられる場合が多いです。学生でも利用しやすく、費用を抑えたい人には、特に適した選択肢といえます。
ただし、実施日や検査項目が限定されることが多く、たとえば、胸部エックス線や心電図などが含まれないこともあるため、提出先の要件と照らし合わせて利用する必要があるでしょう。
受診には事前の申し込みが必要な場合がほとんどで、自治体によっては抽選制になっていることもあります。
さらに、受診日から診断書発行まで時間がかかるケースもあるため、健康診断と発行手続きの両方のスケジュールを把握しておくことが求められるでしょう。
利用条件や必要書類をあらかじめ確認し、受付時間内に余裕を持って出向くことがスムーズな取得につながるはずです。
③企業指定の医療機関で取得する
企業が特定の医療機関を指定している場合は、その指示に従って受診する必要があります。
企業指定の医療機関では、提出先に合わせた検査内容や書式で健康診断書が発行されるため、提出時の不備や再提出のリスクを避けやすい利点があるでしょう。
さらに、企業の担当者が受診の予約を代行してくれる場合もあり、個別に調整する手間が省けることもありますが、指定医療機関は予約枠が限られていることが多く、希望日が取れない可能性もあるでしょう。
そのため、案内された予約方法や必要書類、持ち物、検査当日の注意点を事前にしっかり確認しておくことが不可欠です。
加えて、当日の遅刻や持ち物忘れがあると再予約が必要になることもあるため、前日までに準備を整えておくと安心でしょう。
健康診断書を準備する際の注意点

健康診断書は、内定先に提出する大切な書類です。発行までの期間や有効期限、提出形態などを正しく把握しておくことで、提出期限に遅れずスムーズに対応できます。
ここでは、注意点を4つに分けて解説しましょう。
- 発行にかかる期間と有効期限を把握しておく
- 原本提出とコピーの可否を調べておく
- 複数通の健康診断書を用意しておく
- 提出先ごとに必要な書類や添付物をチェックしておく
①発行にかかる期間と有効期限を把握しておく
健康診断書は、申請から発行までに数日から1週間、場合によってはそれ以上かかることがあります。
また、有効期限が3か月以内や6か月以内など企業によって指定されることも多く、期限を過ぎると再取得が必要です。
特に、就活シーズンは申し込みが集中して発行が遅くなる傾向があるため、提出日から逆算して余裕を持って申し込むことが欠かせません。
さらに、検査結果に時間がかかるケースや、郵送を利用する場合は配送日数も加味する必要があります。
スケジュールを全体的に見直し、健康診断を受ける時点から計画的に準備しておくと、期限に遅れず安心でしょう。
②原本提出とコピーの可否を調べておく
企業によっては、健康診断書の原本提出を求める場合と、コピーでもよい場合があります。
原本を提出すると手元に証明が残らず、後日別の企業に提出したいときや再確認が必要なときに不便になることがあるでしょう。
特に、複数の企業に応募している場合や、追加提出を求められる可能性がある場合には、必ずコピー提出が認められるか確認しておいてください。
コピー不可の場合でも、事前に複数通を用意しておくことで再発行の手間や時間を減らせます。
さらに、コピーをとる際は判読性が保たれているか、日付や検査項目がしっかり見えるかどうかもチェックしておくと安心です。
③複数通の健康診断書を用意しておく
複数の企業に提出する場合や、追加で求められる場合に備えて、最初から複数通の健康診断書を準備しておくことが有効です。
後から追加発行を依頼すると、再度検査費用がかかったり、手続きに時間を要したりすることが少なくありません。
特に、就活時期はスケジュールが詰まりがちで、再発行のために時間を割くことが難しい場合があります。そのため、申し込みの際に必要な部数を確認し、同時に複数通の発行を依頼しておくと安心です。
また、各通に署名や押印が必要な場合もあるため、細かい書式についても発行元に確認しておくとミスを防げます。
④提出先ごとに必要な書類や添付物をチェックしておく
案内や企業からのメール・書面をよく読み、必要な添付物や書式に不備がないか一つひとつ確認することが重要です。書類の不足や記載漏れがあると、再提出や手続き遅延につながりかねません。
提出先によっては、健康診断書そのもの以外に添え状や指定の封筒記載、さらには押印やサインなど追加書類が必要なことがあります。
郵送で提出する場合は、封入する書類や記載事項を事前にリストアップし、チェックしながら準備することでミスを防げます。
細かい準備を怠らないことが、全体の流れをスムーズにし、企業側への印象を良くする結果にもつながるでしょう。
健康診断書を郵送で提出する際のマナー

企業に健康診断書を郵送する際は、基本的なマナーを守ることが重要です。正しい方法で送付すれば、書類の紛失やトラブルを防ぎ、相手に良い印象を与えられるでしょう。
ここでは、6つのポイントに分けて説明します。
- 添え状を同封する
- クリアファイルに入れて郵送する
- 封筒に「健康診断書在中」と記載する
- 速達や簡易書留など追跡可能な方法で送付する
- 提出期限に余裕をもって郵送する
- 郵送後に到着確認の連絡を行う
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①添え状を同封する
健康診断書を郵送する際は、添え状を必ず同封してください。宛先や送付理由、提出書類の内容を簡潔に記載すると、受け取る側が確認しやすくなります。
手書きでもパソコン作成でも問題ありませんが、丁寧な文面に整えておくことが大切です。
添え状には日付や連絡先、担当者名なども忘れずに記載し、形式に沿って作成しておくとより丁寧な印象になります。
こうした細やかな配慮が、社会人としての基本マナーを示し、信頼感にもつながると覚えておきましょう。
②クリアファイルに入れて郵送する
健康診断書は折れや汚れを防ぐため、クリアファイルに入れてから封筒に入れることをおすすめします。
こうすることで、輸送中の衝撃や湿気から書類を守ることができ、相手にきれいな状態で届けられるでしょう。
書類の状態が良いまま届くことは、提出者の誠実さや細かい気配りを印象づけるポイントにもなります。
また、クリアファイルを使う際は、サイズが封筒に適しているか確認し、はみ出さないように調整するとさらに安心です。
③封筒に「健康診断書在中」と記載する
封筒の左下に「健康診断書在中」と赤字で記載すると、重要書類として扱ってもらいやすくなります。
特に、採用担当者が多くの書類を扱っている場合、記載があることで迅速かつ正確に仕分けされ、紛失するリスクを減らすのに効果的です。
記載する際は太めのペンを使う、スタンプを利用するなど、目立つように工夫すると良いでしょう。さらに、表面の宛名や住所、担当部署名を正確に書くこともトラブル防止につながります。
④速達や簡易書留など追跡可能な方法で送付する
郵送中のトラブルを避けるため、速達や簡易書留など追跡できる方法で送ると安心です。
追跡番号を控えておくことで、現在の配送状況や到着予定日を把握でき、提出期限に合わせて調整しやすくなります。
普通郵便よりも料金は高くなりますが、確実に届けるという信頼感を相手に与えることができるでしょう。特に、重要な書類の場合は、簡易書留やレターパックなど、配送記録が残る方法を選ぶのがおすすめです。
⑤提出期限に余裕をもって郵送する
郵送には、思わぬ遅延が発生することがあります。天候や交通事情、郵便局の繁忙期などにより配送日数が延びることもあるため、提出期限ぎりぎりにならないよう、数日前には発送してください。
早めに行動しておけば、書類の不備に気づいた場合でも修正や再発行が可能です。また、企業側から到着確認の連絡が来るまでに余裕があると、トラブル時の対応もしやすくなります。
こうした計画的な動きが、社会人としての信頼につながるでしょう。
⑥郵送後に到着確認の連絡を行う
郵送後は、企業の採用担当者に到着確認の連絡をしておくと安心です。電話やメールで「健康診断書を送付した旨」を伝えるだけで、相手の印象が良くなり、万一のトラブルにも早く対応できます。
連絡する際は、送付日や配送方法、追跡番号などを伝えるとよりスムーズです。到着確認を怠らないことで、提出者自身が書類管理に責任を持っていることを示せ、相手からの信頼度も高まります。
健康診断書の結果で内定が取り消されるケース
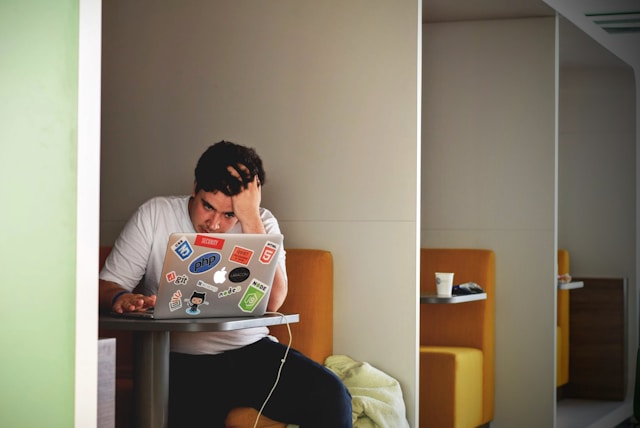
健康診断書の結果によっては、まれに内定が取り消されることがあります。どのような場合に取り消しの可能性があるかを知っておくことで、不安を減らし、適切な準備ができるでしょう。
ここでは、健康診断書の結果で内定が取り消されるケースを4つ紹介します。
- 就労困難と判断された場合
- 健康状態悪化の恐れがある場合
- 業務遂行に必要な健康条件を満たしていない場合
- 虚偽の健康情報を申告していたことが判明した場合
①就労困難と判断された場合
医師の診断により、業務の遂行が著しく難しいと判断された場合、内定が取り消されることがあります。企業は入社後の安全と本人の健康を守るため、このような判断を下すのです。
業務に支障が出る恐れがある場合には、早めに医師や企業に相談して対応策を確認しておくと安心でしょう。
また、診断書の内容によっては、特定の部署での勤務や勤務時間の調整など、柔軟な対応が可能な場合もあります。無理をせず、必要な情報を正確に伝えることで、内定取り消しのリスクを減らせるでしょう。
②健康状態悪化の恐れがある場合
業務に従事することで、健康状態が悪化する恐れがあると判断された場合も、内定取り消しにつながる可能性があるでしょう。
特に、重労働や特殊な環境での勤務が想定される場合、本人の安全確保が優先されます。必要な配慮や部署変更などが可能かどうか、事前に確認しておくことが大切です。
場合によっては、医師の診断書を追加提出し、現状の健康状態や勤務における留意点を企業に伝えることで、より柔軟な対応が得られることもあります。
自分自身の体調や持病に正直であることが、長期的なキャリア形成にもプラスに働くでしょう。
③業務遂行に必要な健康条件を満たしていない場合
一部の職種では、視力・聴力・体力など特定の健康条件が求められます。これらを満たしていない場合、企業は業務遂行が難しいと判断し、内定を取り消す場合があるでしょう。
募集要項や事前の案内で条件を確認し、不安があれば受診前に相談してください。
また、必要な条件を満たしていない場合でも、補助器具の利用や作業内容の変更など、適切なサポートを受けられる可能性があります。
採用担当者に正直に現状を説明することで、より良い解決策を一緒に考えてもらえることがあるかもしれません。
④虚偽の健康情報を申告していたことが判明した場合
健康診断書や事前申告で、虚偽の情報を提出していたことが発覚した場合、信用問題に発展し、内定が取り消される可能性が高くなります。
企業は誠実さを重視するため、正確な情報を伝えることが基本です。
虚偽が疑われるような記載は避け、事実を正直に伝えることが大切になるでしょう。特に、健康診断書は公的な書類であり、虚偽記載は法律的な問題にも発展する恐れもあります。
もし、申告漏れや誤記があった場合は、速やかに訂正や追加説明を行い、誠実な対応を示すことで信頼を回復できる可能性があるでしょう。
内定先に健康診断書を間に合わせるための対処法

内定先に健康診断書を期限までに提出できない場合は、早めの対応が欠かせません。
ここでは、提出が遅れそうなときに取るべき行動をまとめました。これらを知っておくことで、焦らず落ち着いて対処できるでしょう。
- 健康診断書の発行を急いでもらえる医療機関を探す
- 一時的に検査結果の写しや仮の健康診断書を提出する
- 健康診断書が間に合わない場合はすぐに企業へ連絡する
- メールや電話で提出遅延の理由と提出予定日を伝える
①健康診断書の発行を急いでもらえる医療機関を探す
医療機関によって、健康診断書の発行までの期間は異なります。提出期限が迫っているときは、発行を早めてもらえるかどうかを事前に確認し、事情を伝えたうえで予約するとよいでしょう。
迅速な対応をしてくれるところを選ぶことが大切です。さらに、発行のスピードだけでなく、検査内容が企業の指定に合っているかも確認してください。
検査項目が足りないと再発行が必要になり、かえって時間がかかる可能性があります。
複数の医療機関に問い合わせて比較し、最も条件に合う場所を選ぶことが、期限に間に合わせるための大きなポイントです。
②一時的に検査結果の写しや仮の健康診断書を提出する
どうしても正式な健康診断書が間に合わない場合は、検査結果の写しや仮の健康診断書を一時的に提出する方法があります。
多くの企業は後日正式な書類が届くことを理解してくれるため、正直に事情を説明することが信頼につながるでしょう。
さらに、提出する際には「正式な健康診断書は何日までに提出予定」と明確に伝えることが大切になります。仮の書類でも、必要な情報がそろっていれば、企業側は判断材料として使えることが多いです。
必ず写しや仮の診断書を提出したことを記録し、後日正式な書類と合わせて確認できるようにしておくと安心でしょう。
③健康診断書が間に合わない場合はすぐに企業へ連絡する
提出期限に間に合わないとわかった時点で、早めに企業へ連絡してください。連絡が遅れると誠意が伝わらず、信頼を損ねることもあります。
素早い報告は、今後のやり取りをスムーズにするためにも重要です。
また、連絡の際には「なぜ間に合わないのか」「いつまでに提出できるのか」を具体的に説明すると、企業側も安心して対応策を検討できるでしょう。
早めの相談によって、場合によっては提出期限を延長してもらえる可能性もあります。自己判断せず、誠実な態度で連絡することが信頼関係の構築につながるのです。
④メールや電話で提出遅延の理由と提出予定日を伝える
企業へ連絡する際は、提出が遅れる理由と提出予定日を具体的に伝えてください。メールや電話で誠実に説明することで、相手の理解が得やすくなります。
提出予定日をはっきり示すことは、先方の安心感にもつながるでしょう。加えて、連絡するタイミングや担当者名を控えておくと、後日のやり取りがスムーズになります。
特に、メールでは件名や本文を簡潔かつ丁寧に整えることが重要ですし、電話の場合は話す内容をメモにまとめてから連絡すると、より落ち着いて伝えられるでしょう。
こうした細かい配慮が、企業との信頼関係を強めることにもつながります。
健康診断を受ける際の服装や持ち物のポイント

内定後に受ける健康診断は、服装や持ち物を工夫することでスムーズに進められます。
ここでは、検査を円滑に受けるためのポイントを整理しました。
事前に知っておくと当日の不安が減り、落ち着いて臨めるでしょう。
- 検査を受けやすい服装を選ぶ
- 金属や装飾品を避ける
- 前日の食事・持ち物・受付時間などを確認しておく
①検査を受けやすい服装を選ぶ
健康診断では採血や測定、レントゲンなど多くの検査があります。そのため動きやすく、脱ぎ着しやすい服装を選ぶと検査がスムーズに進められるでしょう。
ワンピースや厚手の服は避け、上下分かれたシンプルな服が望ましいです。さらに、タイトすぎるパンツや長いブーツなども、検査時に着脱しづらいため避けるのが無難でしょう。
特に、レントゲン撮影の際には上半身を着替えることが多いため、インナーにも配慮するのを忘れないようにしてくださいね。
カーディガンやジャケットなど羽織りものを持参しておくと体温調整もしやすく、待ち時間にも快適に過ごせます。
このように服装に工夫することで、限られた時間内で多くの検査をスムーズに終えることができるでしょう。
②金属や装飾品を避ける
アクセサリーや金属製の小物は、レントゲンや測定機器に影響することがあります。時計やネックレス、ピアスなどは事前に外しておくか、持参しないようにしましょう。
こうした準備が、検査のやり直しを防ぎます。特に、心電図検査やMRI、エックス線撮影など、電気や放射線を使う検査では、金属が誤作動や画像の乱れの原因になるため注意が必要です。
金属を完全に外せない場合は、受付時にスタッフへ伝えておくと検査をスムーズに調整してくれます。
さらに、装飾の多い衣服やファスナーの大きい服も検査時には不便ですので、可能な限りシンプルな服装で臨むことが望ましいです。
③前日の食事・持ち物・受付時間などを確認しておく
血液検査や胃部の検査がある場合、前日の飲食に制限があることが多いです。案内書に従って食事や飲み物を控え、必要な書類や保険証、受診票などを忘れずに持っていきましょう。
受付時間も事前に確認し、余裕を持って到着してください。
さらに、検査によっては「前日の夜から絶食」「当日の朝は水だけ可」など細かな条件が指定される場合もあるため、必ず案内の指示をよく読んで準備しておくことが重要です。
また、必要に応じて筆記用具やメモ帳を持参し、当日の流れや注意事項を書き留めておくと安心でしょう。早めに到着することで問診票の記入時間も確保でき、落ち着いて検査に臨めます。
健康診断書に関するよくある質問

内定先に提出する健康診断書は、多くの就活生にとって不安や疑問の多い書類です。
ここでは、特に多く寄せられる質問をまとめました。あらかじめ確認しておくことで、手続きをスムーズに進められるでしょう。
- 健康診断書を紛失した場合の再発行方法は?
- 複数の企業に同じ健康診断書を提出しても良い?
- 海外の大学で受けた健康診断書を使える?
- 健康診断書に記載ミスがあった場合はどう訂正するのか?
①健康診断書を紛失した場合の再発行方法は?
健康診断書を紛失した場合は、まず診断を受けた医療機関や大学の保健センターに問い合わせてください。多くの場合は、本人確認書類と手数料が必要です。
再発行には日数がかかることもあるため、早めに連絡しておくと安心でしょう。
再発行の可否や手続き方法は機関によって異なり、書類の保管期限や電子データの有無によっても対応が変わることがあります。
また、複数通を一度に再発行してもらえるかどうかも確認しておくと、後の提出で困らずに済むでしょう。
②複数の企業に同じ健康診断書を提出しても良い?
同じ健康診断書を複数の企業に提出できるかは、各企業の方針によって異なります。原本提出が必要な企業も多いため、事前にコピーを取るか複数通を発行してもらうのがおすすめです。
特に、原本を回収する企業の場合、再発行の手間や追加費用がかかることがあるため、最初から複数通の取得を検討すると安心でしょう。さらに、提出先ごとの書式や指定項目の違いにも注意が必要です。
③海外の大学で受けた健康診断書を使える?
海外で受けた健康診断書も、内容が日本語または英語で記載されていれば認められる場合があります。ただし、企業によっては国内医療機関の診断書を求めることがあるため、必ず事前に確認してください。
場合によっては、翻訳証明や追加検査を求められることもあるため、余裕を持った準備が必要です。
提出先が定めるフォーマットや検査項目が、海外の診断書と一致しているかも確認しておくとスムーズでしょう。
④健康診断書に記載ミスがあった場合はどう訂正するのか?
記載内容に誤りがあった場合は、自分で修正せず発行元の機関に連絡してください。訂正印や正式な再発行が必要なことが多く、自己判断で書き換えると無効になる恐れがあります。
医療機関や大学によっては、再発行までに日数がかかる場合もあるため、早めに依頼しておくことが大切です。
さらに、提出期限が迫っている場合には、訂正依頼と同時に企業へ事情を伝えておくと信頼を損なわずに済むでしょう。
内定先に提出する健康診断書の重要ポイント

内定後に提出が求められる健康診断書は、就活生にとって採用確定の大切なステップです。
提出理由や必要な検査項目、大学や病院での取得方法、そして発行期間や有効期限などの注意点を理解しておくことで、スムーズな準備が可能になります。
さらに、郵送マナーや結果による内定取り消しのケース、提出が間に合わない場合の対処法まで知っておくことが安心につながるでしょう。
企業に提出する健康診断に関しての知識を早めに整理し、余裕をもって行動することが、トラブルを防ぎ内定先からの信頼を保つ最良の方法です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













