志望動機は何文字が正解?文字数の目安や文字数別の例文を紹介
「志望動機を書いてみたけれど、長すぎるのでは…?」「短すぎて伝わらないかも」と文字数に関して不安になる方は多いですよね。
実際は、志望動機の文字数には明確な目安があり、工夫次第で無理なく調整できます。
この記事では、履歴書やエントリーシートでの適切な文字数から、文字数ごとの構成のコツ、短すぎる・長すぎる場合の対処法まで丁寧に解説します。
ぜひこの記事を参考にして、自信を持って志望動機を書けるように一緒に整理していきましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
履歴書やESにおける志望動機の適切な文字数は何文字?

履歴書やエントリーシートの志望動機は、自分の熱意や適性を伝える大切な要素です。しかし、長すぎても短すぎても評価が下がる可能性があるでしょう。ここでは、ケースごとの目安を紹介します。
- 文字数が指定されている場合は9割以上を目安にする
- 文字数指定がない場合は200~400字を目安にする
- 履歴書は200字程度、ESは300~400字程度が目安である
- インターンでは200字前後、本選考では300字以上が目安である
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
①文字数が指定されている場合は9割以上を目安にする
文字数が指定されているときは、必ず9割以上を埋めることが基本。指定された文字数は、企業が応募者の思考力や表現力を確認するための基準だからです。
たとえば「300字以内」と指定されていれば、最低でも270字以上は必要でしょう。仮に200字程度しか書かなければ、熱意不足や準備不足と受け取られてしまう危険があります。
逆に、9割以上を満たすことで、与えられた課題に誠実に取り組む姿勢を示せるでしょう。もし、内容が不足していると感じる場合は、経験から得た学びや企業を志望する理由を掘り下げると自然にボリュームが増えます。
ルールを守ること自体が信頼につながり、最終的には選考での印象も良くなるのです。
②文字数指定がない場合は200~400字を目安にする
文字数が指定されていない場合は、200~400字を意識するのが安心です。この範囲なら、自分の経験と志望理由を無理なく整理できます。
200字程度であれば、意欲や結論を端的に伝えることができ、読む側も負担を感じにくいでしょう。
一方で400字程度なら、過去の経験や学びを具体的に盛り込みつつ将来像まで示せるので、説得力のある内容に仕上がります。
アルバイトや部活動の経験を例に挙げ、「そこで得た力を入社後どう活かしたいか」を加えると、適度なボリュームになるでしょう。
短すぎると自己PRとの差別化が難しく、長すぎると流し読みされる可能性が高いです。適度な文字数を意識することが、相手に伝わりやすい志望動機につながります。
③履歴書は200字程度、ESは300~400字程度が目安である
履歴書とエントリーシートでは、そもそも記入欄の大きさが違うため、求められる分量も変わります。履歴書の志望動機欄は小さな枠であることが多く、200字程度で簡潔にまとめるのが基本です。
ここでは「なぜその企業を選んだのか」を端的に表現することが重要でしょう。
一方で、エントリーシートは余裕のある欄が設けられているため、300~400字を使って経験や強み、将来の展望を詳しく書くことが期待されます。
同じ志望理由でも、履歴書用は短く整理し、ES用は内容を膨らませて補足すると良いでしょう。状況に応じて調整する姿勢が「文章力がある」「相手を意識している」と評価されやすくなります。
そのため、両者を区別して書き分けることが選考突破のポイントになるのです。
④インターンでは200字前後、本選考では300字以上が目安である
インターンと本選考でも、求められる文字数は大きく異なります。インターンでは200字前後を目安に、学びたい姿勢や企業に興味を持ったきっかけを端的にまとめることが大切です。
選考側は「どれだけ成長意欲があるか」を知りたいと考えています。本選考では、単に学びたいでは不十分で、企業への志望度や入社後にどう活躍するかが問われます。
そのため300字以上を使い、経験や強みを裏付けとして伝える必要があります。
たとえば「インターンでは学びの姿勢を中心に」「本選考では貢献できる具体的な方法を加える」といった書き分けが効果的です。
段階に応じて内容と文字数を調整することで、誠実さや柔軟性が伝わりやすくなり、結果として選考を有利に進められるでしょう。
志望動機を書く際には、文字数以外にも気を付けるべき点がたくさんあります。以下の記事では、自分で志望動機を書くときのコツやポイントを詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
志望動機の文字数を意識すべき理由

志望動機を書くときに文字数を意識することは、読み手に内容をしっかり伝えるために欠かせません。ここでは、文字数を意識すべき理由をわかりやすく解説します。
- 企業から文字数を指定されるケースが多いため
- 端的にまとめることで印象に残りやすいため
- 長すぎると流し読みされる可能性があるため
- 要約力や文章力をアピールできるため
①企業から文字数を指定されるケースが多いため
文字数を意識すべき大きな理由は、企業があらかじめ制限を設けていることが多いからです。「300字以内」と書かれていれば、最低でも270字以上は埋める必要があります。
逆に350字以上になれば、指示を守れない人だと見られてしまうでしょう。短すぎても「熱意が伝わらない」と受け取られるため、指定された範囲をきちんと満たすことが重要です。
もし、字数が足りないと感じたときは、エピソードの背景やそこから得た学びを加えると自然に増やせます。制限を守る姿勢は信頼にも直結し、結果として評価アップにつながるでしょう。
②端的にまとめることで印象に残りやすいため
要点を絞って簡潔に書くことは、採用担当者の記憶に残りやすくなるという大きな利点があります。長い説明よりも短く整理された文章の方が理解されやすく、読み手の頭に残るのです。
就活では数多くの学生が応募するため、一人ひとりの文章に割ける時間は限られています。その中で1つの理由に焦点を当て、経験や学びを具体的に述べれば強い印象を与えられるでしょう。
無駄を削ぎ落とした文章は「論理的に考えられる」「伝える力がある」と評価されやすく、さらに熱意も明確に伝わります。簡潔さは、就活において強い武器になるのです。
「私の書いた志望動機は端的にまとめられているかな…?」と不安に思う場合、完成した志望動機を添削してみるとよいですよ。以下の記事に、添削方法やセルフチェックの項目をまとめているのでぜひ参考にしてください。
③長すぎると流し読みされる可能性があるため
文字数が多すぎると、最後まできちんと読まれないまま流されてしまう危険が高まります。採用担当者は限られた時間で数十人分の書類に目を通すため、1人に長時間割くことは難しいのです。
その結果、志望動機の肝心な部分が伝わらないという残念な事態になりかねません。これを防ぐためには、200~400字を目安にコンパクトにまとめるのが安心でしょう。
特に、重要なエピソードや学びだけを残し、不要な部分は削除することで、伝えたいことが鮮明になります。適切な分量に調整できる力は「要点を整理できる人材」としての評価にもつながるはずです。
④要約力や文章力をアピールできるため
適切な文字数で仕上げた志望動機は、自分の要約力や文章力をアピールする手段にもなります。限られたスペースで経験や思いを整理し、相手に理解されやすい形で表現する力は社会に出ても役立つスキルです。
採用担当者が「この学生は取捨選択ができ、わかりやすく説明できる」と感じれば、評価は自然と高まるでしょう。
たとえば、部活動で培った力を一言でまとめ、企業の理念や価値観に結びつけて説明すれば、説得力が格段に増します。
与えられた制限を不便さではなく工夫の余地と捉えられるかどうかは、大きな差になるでしょう。適切な文字数を守ることで、自己PRとしての強みをより明確に示せるのです。
読みやすい志望動機を作るための構成

志望動機は長さよりも、読みやすく整理されていることが大切です。文章の流れを工夫すれば、採用担当者の印象に残りやすくなります。ここでは、効果的に伝えるための構成を紹介しましょう。
- 志望理由を端的に述べる
- 具体的なエピソードを盛り込む
- 入社後の展望で熱意を伝える
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
①志望理由を端的に述べる
最初に、志望理由をはっきり示すことが重要です。冒頭で結論を伝えると、採用担当者は内容を理解しやすくなります。
たとえば「企業理念に共感した」「成長できる環境に魅力を感じた」といった表現で始めると、文章全体の方向性が見えやすいでしょう。前置きを長く書くよりも、まず理由を一言で伝える方が効果的です。
その後に具体例や将来像を加えれば、より一貫した志望動機になります。冒頭で理由を明確にすることで読み手の集中力を引きつけ、最後までしっかり読んでもらえる確率も高まるでしょう。
②具体的なエピソードを盛り込む
次に、自分の経験を具体的に書くことで、説得力が大きく高まります。アルバイトやゼミ活動、サークル活動など身近な経験でも十分であり、特別な実績がなくても問題はありません。
大切なのは、そこで得た学びや力を志望理由とどう結びつけるかという点です。「接客の工夫を重ねた経験が、貴社の顧客志向の姿勢と重なった」と書けば、文章に厚みが増します。
抽象的な表現だけでは熱意が伝わりにくいため、数字や具体的なエピソードを交えると、よりリアリティが出て印象に残りやすいでしょう。
過去の経験を整理するためには、自己分析やマインドマップの作成が有効になります。以下の記事では、マインドマップの活用の仕方やメリットについて解説しているので、情報の整理がまだできていない人はぜひ参考にしてくださいね。
③入社後の展望で熱意を伝える
最後に、入社後にどう活躍したいかを語ることで、将来性や熱意を強く示せます。ただ働きたいと述べるだけでは意欲が伝わりにくいため、具体的な役割や中長期的な目標に触れることが効果的です。
たとえば「営業職として顧客との信頼関係を築き、将来はチームをまとめる存在になりたい」と書けば、意欲と成長意識が同時に伝わるでしょう。
入社後の展望を入れることで、短期的な志望動機にとどまらず、長期的に会社へ貢献したい姿勢も示せます。このように、未来を見据えた視点を加えることが、選考突破の大きなポイントです。
志望動機の文字数配分のコツ

志望動機は文字数によって表現の工夫が変わります。短い場合は要点を絞り、多い場合は具体的に広げる必要があります。ここでは、文字数ごとの構成のコツを紹介しています。
- 100字で伝える志望動機の構成
- 200字で伝える志望動機の構成
- 300字で伝える志望動機の構成
- 400字で伝える志望動機の構成
- 600字で伝える志望動機の構成
- 800字で伝える志望動機の構成
- 1,000字で伝える志望動機の構成
①100字で伝える志望動機の構成
100字程度の志望動機は、結論を端的に伝えることが最も大切です。理由は1つに絞り、短い文章の中で意欲や姿勢をはっきり示しましょう。
たとえば「挑戦する姿勢に共感し、自分の強みで貢献したい」とまとめれば十分に伝わります。複数の要素を盛り込むと焦点がぼやけ、逆に説得力が下がる可能性も。
短いからこそ選択と集中が必要で、焦点を明確にする力が評価されるでしょう。シンプルに要点を押さえることが、読み手の印象に残る近道です。
②200字で伝える志望動機の構成
200字では結論に加え、具体的な経験を1つ盛り込むと効果的です。冒頭で志望理由を簡潔に述べ、その後に体験や学びを補足すると説得力が増します。
たとえば「理念に共感した」と書いた後に「ゼミで培った分析力を活かしたい」と続ければ、理由と能力が自然につながるでしょう。
200字は短い分量のため、余計な説明を省き、主張と根拠を対応させることが重要です。あれもこれも書こうとせず、一番伝えたいポイントに絞ることで、簡潔さと具体性のバランスが整うでしょう。
③300字で伝える志望動機の構成
300字は、最もよく使われる分量であり、理由・経験・展望の3点を盛り込むのが理想です。
冒頭で志望理由をはっきり伝え、その後に具体的な経験を紹介し、最後に入社後の目標で締める流れにすると、一貫性が出て説得力が高まります。
たとえば「学園祭の運営で得た企画力を活かし、新規事業に挑戦したい」といった書き方です。適度な長さがあるため、エピソードを少し掘り下げつつも読みやすさを保てます。
情報量とわかりやすさの両立が、評価されるポイントでしょう。
④400字で伝える志望動機の構成
400字では、経験やエピソードをやや詳しく書けます。志望理由とエピソードを丁寧に述べ、最後に展望を加えると厚みのある志望動機になります。
たとえば「アルバイトで学んだ接客力」を具体的に説明し、それを志望理由に結びつければ説得力が高まります。ただし情報を詰め込みすぎると読みにくくなるため、必ず伝えたい要素を整理してください。
量が増える分、段落や接続詞を意識して流れを整えることも欠かせません。読み手に負担を与えない工夫が評価を左右します。
⑤600字で伝える志望動機の構成
600字では、複数の体験を組み合わせて伝えることが可能です。「ゼミの研究経験」と「ボランティアでの協働経験」を両方紹介し、それぞれを志望理由や入社後の展望につなげれば、説得力が増します。
長めの文章になるため、段落を意識し、読みやすさを確保することが欠かせません。焦点がぶれないよう、全てのエピソードを1つの志望理由に関連付ける必要があります。
量を活かして多面的に自分を表現しつつ、一貫性を持たせることが評価の決め手になるでしょう。
⑥800字で伝える志望動機の構成
800字は分量が多いため、深掘りされた内容が求められるケースが多いです。導入で志望理由を簡潔に示し、中盤で複数の体験や学びを丁寧に整理し、最後に入社後の展望で締める流れが適しています。
たとえば「留学での異文化経験」や「アルバイトでの実績」を組み合わせ、企業の求める人物像と結びつければ説得力が強まります。
長さがある分、冗長になりやすいため、必ず主題を一本に絞って展開することが大切です。文章全体の整理力や、構成力が問われる文字数といえるでしょう。
⑦1,000字で伝える志望動機の構成
1,000字の志望動機は長文のため、特に構成力と文章力が重視されます。序盤で志望理由を明確に述べ、中盤では複数の体験や学びを展開し、最後に将来の展望を語る流れが理想です。
大切なのは、全ての内容が志望理由にきちんとつながるよう、一貫性を持たせること。情報をただ多く詰め込むのではなく、整理して伝える力が評価されます。
段落分けや接続詞を工夫すれば、長文でも読みやすさを維持できます。論理性と熱意の両立が、この文字数では最も重要になるでしょう。
長文になればなるほど、構成力が問われます。こちらの記事では、志望動機の基本構成や気を付けるべきポイントについて詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
志望動機が指定文字数に届かないときの対処法

志望動機を書くときに、指定された文字数に届かず悩む人は少なくありません。無理に文章を増やすと不自然になりますが、工夫をすれば説得力を持たせながら自然に広げられます。
ここでは、その具体的な方法を紹介しましょう。
- 志望理由をさらに細分化して書く
- 数字や固有名詞を使って具体化する
- 入社後の展望を詳しく書く
- 自己分析を深めてエピソードを膨らませる
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
①志望理由をさらに細分化して書く
志望理由が大まかすぎると文字数が足りなくなり、説得力も弱まります。
もし、「成長できる環境に魅力を感じた」とだけ書くと抽象的で短くなりがちですが、「若手から責任ある仕事を任される制度がある点に惹かれた」「成果を出せば正当に評価される仕組みに魅力を感じた」と具体的に分けて書くと、自然に文章を広げられるでしょう。
このように志望理由を小さな要素に分解し、それぞれを丁寧に説明すれば内容に厚みが出て、文字数を増やしながらも一貫性を保つことができます。
②数字や固有名詞を使って具体化する
抽象的な表現に終始すると文字数が不足しやすいため、具体性を意識して加えることが大切です。
たとえば「アルバイトで接客を頑張った」では短すぎて伝わりませんが、「1日100人以上の顧客に対応し、その中で改善提案を3回行った」と書けば、経験の規模感や努力の度合いが明確に伝わります。
さらに「○○大学のゼミ活動で~」「○○社のイベントで~」と固有名詞を入れることでリアリティが増し、文章全体の厚みが出るでしょう。数字や名前を盛り込むことで、説得力と読みやすさを両立が可能です。
③入社後の展望を詳しく書く
志望動機が短くなる場合は、過去の経験だけで終わらせず、未来の展望を詳しく書き足すのが効果的です。
「営業として成果を上げたい」では文字数が不足しがちですが、「営業として成果を上げると同時に、将来的には後輩を育成し、チームをまとめる立場を担いたい」と付け加えると、一気に文章が広がります。
さらに「顧客から信頼される存在になりたい」「新規事業の立ち上げにも挑戦したい」など具体的な姿を示せば、自然に分量が増えるだけでなく、前向きな意欲や長期的なビジョンが伝わりやすくなるでしょう。
とはいえ、将来の展望をうまく描けない人も多いでしょう。以下の記事では、「入社後に何をしたいか」というテーマについて、考え方を詳しく説明しているため、気になる人は読んでみてくださいね。
④自己分析を深めてエピソードを膨らませる
自己分析が浅いと、志望動機は短くまとまりすぎてしまいます。
経験をただ並べるのではなく、「なぜその行動を取ったのか」「そこから何を学び、どのように成長したのか」まで掘り下げることで、自然に文字数を増やせるでしょう。
たとえば「サークルで企画を担当した」だけでは物足りませんが、「メンバーの意見をまとめる難しさを感じ、その中で相手の考えを尊重しながら調整する大切さを学んだ」と書けば、内容に厚みが出ます。
過程や気づきを補足することで、分量を増やしながら自己理解の深さをアピールできるでしょう。
志望動機が長すぎるときに文字数を削る要約術
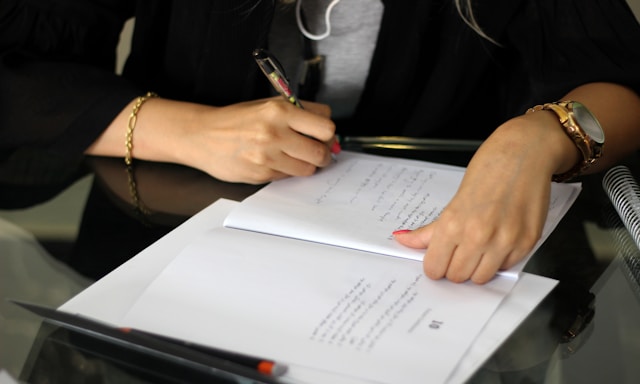
志望動機を書いていると、つい内容が長くなってしまうことがあります。そのまま提出すると読み手に負担をかけ、熱意が十分に伝わらない恐れもあるでしょう。
ここでは、削りすぎずに簡潔にまとめるための要約術を紹介します。
- 伝えたい主張を1つに絞る
- 冗長な表現をシンプルに言い換える
- なくても伝わる部分を削除する
- 副詞や接続詞を必要最小限に減らす
①伝えたい主張を1つに絞る
複数の経験や強みを盛り込みたくなる気持ちは理解できますが、欲張ると文章はどんどん長くなり、焦点が曖昧になります。
もし、「学業で培った分析力」「アルバイトで得た接客力」「サークルでの協調性」などをすべて入れると、主張が散らかってしまうでしょう。
そこで「チーム活動で培った調整力を活かしたい」と1点に絞れば、読み手は理解しやすくなります。さらに、その強みを裏付ける具体的なエピソードを1つ添えるだけで十分でしょう。
主張を1つに決めることが、冗長にならずに伝えるための第一歩です。
「そもそも自分の強みがわからない…」「自分の強みをどれか1つに絞りたい」という方には、以下の記事がおすすめです。強みを見つける方法や思いつかないときの対処法について詳しく説明していますよ。
②冗長な表現をシンプルに言い換える
長文化の原因の1つは、回りくどい表現を多用していることです。
たとえば「私は御社の理念に深く共感していると考えております」と書くよりも、「私は御社の理念に共感しています」と表現した方が短く、同時にすっきりと伝わります。
冗長な敬語や不要な修飾語を減らすだけで、数十字単位で圧縮できることも珍しくありません。要点を短い言葉で置き換えることで、文字数を減らすだけでなく、読みやすさも高まります。
特に「~であると考えております」「~していただきたいと考えております」などは「~と考えます」「~したいです」と言い換える習慣を持つと良いでしょう。
③なくても伝わる部分を削除する
「本当に」「実際に」「やはり」といった副詞は、なくても意味が通じる場合がほとんどです。これらを削るだけでも、文章はすっきりします。
また「私はこの経験からリーダーシップを学びました。その経験によってチームをまとめる力を得ました」というように、同じ内容を言い換えて繰り返す部分も省略可能です。
要点を一度しっかり述べたら、重ねて説明しなくても十分に伝わります。削るときは「この一文をなくしても意味が通じるか」を基準に判断してください。
不要な言葉を減らすことで、文章全体が引き締まり、相手に伝わる力も高まるでしょう。
④副詞や接続詞を必要最小限に減らす
副詞や接続詞を多用すると、文章がくどくなり、余計な文字数も増えてしまいます。「しかしながら」「そのために」「それによって」などを頻繁に使うと、読む側に負担をかけるでしょう。
接続詞は段落の切り替えなど必要な場面に限定して使用することが大切です。副詞についても「非常に」「とても」「かなり」といった強調語は多用せず、必要な場面に絞ってください。
こうした整理を行うだけでも、全体の文字数は大幅に削減できます。加えて、文章が簡潔になることで、内容がすっきりと伝わりやすくなるという効果も得られるでしょう。
志望動機を書くときの注意点

志望動機は文字数や内容の工夫だけでなく、書き方そのものにも気を配る必要があります。採用担当者が読みやすく、熱意を感じられる文章にするには細かな配慮が欠かせません。
ここでは、特に意識したい注意点を整理しました。
- 文字数指定がある場合は必ず守る
- 誤字脱字を避け正確な日本語で書く
- 一文を長くしすぎず60~80字以内に収める
- 小さな文字で詰め込みすぎないようにする
- 熱意が伝わる内容を意識する
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
①文字数指定がある場合は必ず守る
企業が志望動機に文字数を指定している場合、それを守ることは最低限のマナーです。
もし、「300字以内」と指定されているのに、200字程度しか書かなければ「やる気が足りない」と受け取られかねません。逆に、400字など超えてしまうと「指示を理解できない人」と判断されるリスクもあります。
文字数指定は、応募者の要約力や文章を整理する力を試すために設けられていることも多いです。
そのため、指定された範囲の9割以上を意識し、経験や学びを具体的に盛り込みながら書くと評価につながるでしょう。
②誤字脱字を避け正確な日本語で書く
どれだけ立派な内容を書いても、誤字や脱字があると一気に印象が悪くなります。「注意力が足りないのではないか」「業務でもミスをしやすいのでは」と不安を与えてしまうからです。
提出前には必ず時間を取って見直し、誤りがないか丁寧に確認してください。可能であればパソコンの校正機能を使ったり、友人や家族に読んでもらったりするとより安心です。
正確で整った日本語を使うことは、単なるマナーにとどまらず、応募者としての誠実さや信頼感を示す大切な要素になります。
③一文を長くしすぎず60~80字以内に収める
文章が長すぎると、どこで区切ればよいのかがわからなくなり、読み手が理解しづらくなります。特に、採用担当者は数多くの応募書類を短時間で目を通すため、わかりやすさが求められるのです。
1文は60~80字を目安にし、適度に句点で区切りましょう。たとえば「私はアルバイトで接客力を高めました。その経験を活かし、お客様との信頼関係を築きたいです」と短く切れば、スムーズに読み進められます。
逆に「私はアルバイト経験を通して接客力を高め、その経験を活かしてお客様との信頼関係を築き、会社に貢献したいです」と一文にまとめると、冗長で理解しにくくなるので注意が必要です。
④小さな文字で詰め込みすぎないようにする
履歴書やエントリーシートに書くとき、指定された枠に無理に詰め込もうと、小さな字でびっしり書いてしまう人がいます。
しかし、これでは採用担当者が読むときに負担が大きく、内容が頭に入ってこない可能性があります。余白を意識し、読みやすい字の大きさで整えて書くことが大切です。
見た目の印象は意外と評価に直結しやすいため、読みやすさを意識することは文章力と同じくらい重要です。余裕を持ったレイアウトで仕上げると、内容への信頼性も高まりやすいでしょう。
⑤熱意が伝わる内容を意識する
文字数や形式を守っていても、淡々とした内容では心を動かせません。志望動機で最も重要なのは、企業に対する熱意をしっかり伝えることです。
たとえば「御社の研修制度に魅力を感じました」と書くだけでは弱いため、「研修制度で学んだ知識を活かし、将来は新規事業に挑戦して貢献したい」と具体的に示すことで熱意が伝わります。
企業の理念や仕事内容を自分の経験や強みに結びつけて書くと、説得力も増すでしょう。採用担当者は「この人は本当に入りたいのか」を見ています。
気持ちを込めて表現することが、合否を分ける大きなポイントになるのです。
熱意が伝わる志望動機にするためには、まずその企業についてしっかり理解することが大切です。以下の記事では、企業研究のやり方や情報の集め方についてより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
【文字数別】履歴書・ESの志望動機例文

履歴書やエントリーシートの志望動機は、指定された文字数や状況によって書き方が大きく変わります。
ここでは、文字数ごとの例文を紹介し、実際のイメージをつかめるように解説しましょう。具体的には、以下のようなパターンがあります。
また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①100字の志望動機例文
ここでは、100字で簡潔にまとめた志望動機の例文を紹介します。短い文字数でも熱意を伝えるためには、志望理由を端的に表現し、具体性を持たせることが大切です。
| 私はテニス部の部長としてチームをまとめ、その中で相手の立場を理解し、全体をまとめる重要性を学びました。 御社の「協働」を重視する姿勢に共感し、私の経験を活かして仲間と成果を出したいと考え志望しました。 |
100字の志望動機では、学びと志望理由を短く結びつけることがポイント。自分の経験を一言で表現し、企業の特徴とリンクさせると効果的です。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
②200字の志望動機例文
ここでは、200字でまとめた志望動機の例文を紹介します。200字程度あれば、自分の経験や学びを具体的に盛り込みながら、企業への志望理由をわかりやすく伝えることができるでしょう。
| 私は、大学で地域イベントの企画運営で周りと協力しながら目標を達成する経験を積みました。 特に、地元の商店街と協働して新しい企画を形にしたとき、相手の意見を尊重しながら自分の考えを伝える難しさと周囲と協力し成果を出す楽しさを学びました。 御社はチームワークを大切にし、新しい挑戦を続けている点に魅力を感じています。私もその一員として貢献し、共に成長していきたいと考え志望しました。 |
200字の志望動機では、経験の具体性を出しながらも簡潔にまとめることが重要です。活動内容と企業の姿勢を結びつけると説得力が高まります。
③300字の志望動機例文
ここでは、300字でまとめた志望動機の例文を紹介します。300字程度あれば、自分の経験や強みをしっかり示しつつ、企業への志望理由を具体的に伝えることが可能です。
| 私は、大学で学園祭の運営委員として広報を担当し、来場者数を増やすためにSNSを活用した情報発信を行いました。 どのような内容なら多くの人に届くのかを考え、写真や動画を工夫して発信した結果、前年より来場者数を大幅に増やすことができました。 この経験から、相手の立場に立って考え、成果につながる行動を起こす力を身につけました。御社は挑戦的な姿勢を持ち、新しいアイデアを取り入れながら成長している点に強く魅力を感じています。 私は学んだ行動力と柔軟な発想を活かし、チームに貢献するとともに新しい価値を創り出す人材として成長していきたいと考えています。 |
300字の志望動機では、経験→学び→志望理由の流れを意識することが重要です。具体的な成果を入れることで説得力が増し、企業との接点が明確になります。
④400字の志望動機例文
ここでは、400字でまとめた志望動機の例文を紹介しています。400字あれば、自分の経験や強みを十分に説明しながら、企業の特徴や求める人材像と結びつけて具体的にアピールできます。
| 私は、大学でゼミ活動の一環として地域活性化プロジェクトに参加し、地元商店街と協力してイベントを企画しました。 来場者を増やすためにアンケートを実施し、学生や地域住民の意見を反映させたプログラムを提案した結果、前年より多くの参加者を集めることができました。 この経験から、相手のニーズを把握し、改善点を取り入れながら形にする力を養うことができたと思っています。 御社は、新しい価値を創出する姿勢を大切にしており、社会や顧客に寄り添いながらサービスを展開している点に強く共感しています。 私は、ゼミで培った企画力と調整力を活かし、御社の事業に貢献するとともに、仲間と協力しながら新しい挑戦に積極的に取り組んでいきたいです。 |
400字の志望動機では、経験から得た学びと企業への共感を丁寧につなげることが重要です。体験談を広げすぎず、企業との接点を明確にすることがポイントになります。
⑤600字の志望動機例文
ここでは、600字でまとめた志望動機の例文を紹介します。600字あれば、自分の体験をより丁寧に説明しつつ、学びや強みを企業の特徴と結びつけて伝えることができるでしょう。
| 私は、大学でゼミ活動として地域観光の活性化に取り組み、学生チームの一員としてイベントの企画と広報を担当しました。 観光客を増やすために地域の方々や行政機関にヒアリングを行い、意見を取り入れながら改善案をまとめ、SNSやポスターを通じて情報発信を行いました。 その結果、前年より参加者数を増やすことができ、地域の方からも感謝の言葉をいただけたのです。この経験から、相手の立場を理解し、課題を整理しながら成果に結びつける力を磨くことができました。 御社は人々の暮らしに寄り添ったサービスを提供し、新しい価値を創造し続けている点に強く惹かれています。 私は、ゼミ活動で培った企画力と協調性を活かし、御社の一員として社会に貢献するとともに、新しい挑戦に積極的に取り組んでいきたいと考えています。 |
600字の志望動機では、体験の経緯から学び、企業への共感までを丁寧に盛り込むことが大切です。段落を意識して整理することで、長文でも読みやすくなります。
⑥800字の志望動機例文
ここでは、800字を想定した志望動機の例文を紹介しています。800字クラスでは、経験や学びを段階的に深掘りし、志望理由を多角的に説明する必要があります。
ここでは、800字の志望動機の例文を提示しましょう。
| 私は、大学でサッカー部に所属し、キャプテンとしてチームをまとめてきました。 全国大会を目標に日々練習を重ねる中で、部員のモチベーションや役割の違いから意見が対立することも多く、当初は練習の方向性が定まらず成果が伸び悩む時期もありました。 私はこの状況を改善するため、まず一人ひとりと丁寧に対話し、各自が抱えている不満や提案、目標意識を把握しました。 また、部員の特性や役割を見極めて練習メニューを調整したり、練習後にミーティングを設けてその日の課題を振り返るなど、継続的に改善を重ねました。 こうした取り組みの結果、部の雰囲気は徐々に前向きなものへと変化し、メンバー同士が互いの意見を尊重し合える風土が育ちました。特に、部員が自主的に練習方法を提案したり、新しい戦術を積極的に試すなど、主体性を持って行動する姿勢が定着していきました。 その結果、チーム全体の結束力と競技力が高まり、大会では過去最高の成績を収めることができたのです。 この経験から、相手を尊重しながらチームを導くリーダーシップや、課題を整理し解決に導く問題解決力を実践的に培うことができたと感じています。 御社は挑戦を続ける企業文化を持ち、仲間と協力しながら新しい価値を生み出す姿勢に強く共感しています。 私は、大学時代にキャプテンとして培った「メンバー一人ひとりの意見を大切にしつつ、チーム全体を同じ方向へ導く力」「課題を整理し改善策を実行する力」を活かし、御社でも仲間と共に成果を創り出す存在になりたいと考えています。 入社後は、まず現場での経験を通じて御社の価値観や業務を深く理解し、その上で組織やお客様の課題解決に貢献できるよう努めたいと思います。そして、周囲と協働しながら新しい挑戦に積極的に取り組み、御社のさらなる発展に寄与できる人材へと成長していきたいと考えています。 |
800字の志望動機では、経験を複数段階に分けて深掘りし、説得力を持たせることが大切です。段落ごとに役割を決め、読みやすく整理するのが効果的でしょう。
⑦1,000字の志望動機例文
ここでは、1,000字を想定した志望動機の例文を紹介します。実際の選考で指定されることは多くありませんが、長文で求められるケースでは、自分の経験を体系的にまとめる力が試されるでしょう。
ここでは、1,000字の志望動機の例文を紹介します。
| 私は、大学でボランティアサークルに所属し、子ども向けの学習支援活動に力を入れてきました。 週に数回、地域の小学生を対象に国語や算数などの勉強を教えるだけでなく、勉強に苦手意識を持つ子どもたちが前向きに学べるよう、授業の進め方や声かけの仕方に工夫を重ねました。 その中で、単に知識を伝えるだけでなく、相手の状況や気持ちを理解し、寄り添う姿勢の大切さを強く実感しました。特に、学習に苦手意識を持っていた子どもが「できた!」と笑顔で喜ぶ瞬間に立ち会えたとき、自分自身も大きなやりがいと達成感を感じたのを今でも鮮明に覚えています。 また、メンバーと協力しながら活動を継続していく中で、計画を立てて行動する力や、課題に直面したときに柔軟に対応する力を身につけることができました。 その結果、より多くの子どもたちにきめ細やかな支援を提供することが可能となり、自分たちの活動が地域に与える影響の大きさを実感することもできました。こうした経験は、チームで課題を共有し、協力しながら解決に導く力を養う貴重な機会となりました。 御社は人に寄り添ったサービスを提供し、社会の課題解決に貢献している点に強く共感しています。 御社では、社会の多様なニーズを丁寧に汲み取り、単なるサービス提供にとどまらず、その先にある人々の生活の質の向上や持続可能な社会づくりに取り組んでいると伺っています。 そうした環境でこそ、私が培ってきた「相手に寄り添う姿勢」や「柔軟な対応力」「計画性」といった強みを発揮し、さらに成長できると考えています。 私はこれまでの経験を活かし、相手の立場を尊重しながら成果を出す人材として、御社の一員として成長していきたいと強く思っています。 入社後は、まず現場での実務経験を通して御社の価値観やサービスの特長を深く理解し、その上で課題発見力や改善提案力を磨いていきたいと考えています。そして、チームやお客様と信頼関係を築きながら、社会の課題解決に貢献できる新しい価値を創出する人材へと成長することを目指します。 |
1,000字の志望動機では、経験を段階的に詳しく書く必要があります。今回の例文のように、活動内容→学び→企業への共感→今後の展望の流れを意識すると書きやすくなるでしょう。
書き終わった志望動機は、一度誰かに見てもらうのも効果的です。本記事では、ES添削におすすめの依頼先を7つ紹介していますよ。また、利用するメリットや依頼メールの書き方なども解説しているので、ぜひ参考にしてください。
志望動機の文字数に関するよくある質問

志望動機を書くときに「短すぎるとどうか」「長すぎると不利なのか」「どう文字数を確認するのか」といった疑問を持つ人は多いでしょう。
ここでは、よくある質問に答えながら安心して準備できるよう解説します。
- 志望動機が短すぎると落ちる?
- 志望動機が長すぎると不利になる?
- 志望動機の文字数はパソコンでカウントすべき?
①志望動機が短すぎると落ちる?
志望動機が極端に短いと、熱意や考えの深さが十分に伝わらないおそれがあります。
もし、「御社に魅力を感じました」とだけ書かれていると、なぜそう思ったのか、どんな経験からそう考えたのかが見えてきません。
そのため、評価が低くなったり、準備不足と判断されたりする可能性があります。
ただし、必ずしも長ければ良いというわけではなく、200字程度であっても自分の体験や学びと志望理由をしっかり結びつけられていれば評価はされるでしょう。
重要なのは、限られた文字数の中でも伝えたいメッセージを整理し、具体的な根拠を添えて簡潔にまとめることです。短くても中身のある文章なら、十分に効果を発揮できるでしょう。
どうしても志望動機が短くなってしまう…と困っている方は以下の記事も参考にしてみてください。上手く書けない原因やおすすめの対処法を紹介していますよ。
②志望動機が長すぎると不利になる?
長すぎる志望動機は、採用担当者にとって読む負担が大きく、最後まできちんと目を通してもらえないこともあります。
特に、指定された文字数を超えてしまうと、「ルールを守れない人」と見なされ、マイナス評価につながる危険性があるかもしれません。
たとえば、600字以内と指示があるのに1,000字近く書いてしまえば、熱意があるどころか、要点をまとめる力がないと判断されかねません。
文字数が多くなりそうなときは、自分が一番伝えたい主張を1つに絞り、それを補強する具体例を簡潔に加えることで、すっきりとした文章に整えられます。
削ることは決して悪いことではなく、内容を磨き上げる作業でもあるのです。要点を押さえた志望動機の方が、相手の印象に残りやすくなります。
③志望動機の文字数はパソコンでカウントすべき?
文字数を正しく確認するには、手作業で数えるよりもパソコンの文字数カウント機能を使う方が確実です。
自分で数えると、空白や句読点をどう扱うか迷ったり、数え間違いをしてしまったりすることが少なくありません。
その結果、指定文字数を満たしていない、あるいは超過してしまうといったミスにつながります。ワードやGoogleドキュメントなどのツールを使えば、入力と同時に文字数が自動で表示されるため安心です。
特に、エントリーシートや履歴書は、提出前に正確な数字を確認することが欠かせません。余裕があれば、複数のツールでチェックして誤差がないか確認するとより安心でしょう。
こうした細かな配慮が、最終的な信頼感にもつながります。
志望動機の文字数を意識して成功につなげるポイント

志望動機を書くうえで文字数を意識することは、就活を成功させるための大切な要素です。
なぜなら、履歴書やエントリーシートでは200~400字程度が基本とされ、企業から指定があれば必ず守る必要があるから。
また、長すぎれば流し読みされやすく、短すぎれば熱意が伝わりません。適切な文字数の中で端的に理由を述べ、具体的なエピソードを加え、入社後の展望を示すことで、説得力のある内容に仕上げられます。
さらに、文字数が不足する場合はエピソードを細分化し、逆に長すぎる場合は主張を絞って簡潔にまとめることが効果的です。
志望動機は文章力や要約力を試される場でもあるため、文字数を意識しながら伝わりやすい形でまとめることが、採用担当者に好印象を与えるカギとなるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












