四則逆算のコツを徹底解説|基本法則・例題・時短テクニックを紹介
「四則逆算って、どこから手を付ければいいのか…」と感じたことはありませんか。制限時間に追われるとケアレスミスが増え、基本法則の理解が曖昧なまま手筋に頼るほど点数は安定しにくくなります。
しかし、交換・結合・分配の法則を軸に計算順序と検算の型を整えれば、複雑な式でも迷わず逆算できます。
また、分数化や通分、空欄を「□=」に直すなどの時短テクを押さえれば、正確さとスピードを両立できます。
この記事では、仕組みと制限時間の考え方から例題・解き方・時短術まで体系的に解説し、高得点獲得を後押ししますので、ぜひ学習の参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
四則逆算とは?
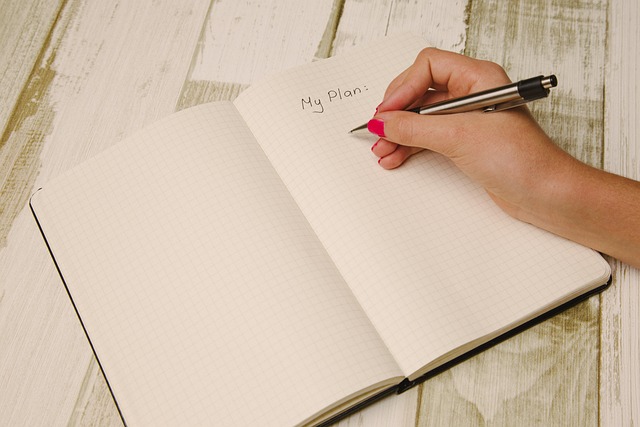
四則逆算は、足し算・引き算・掛け算・割り算を使い空欄の数を求める問題です。就活の適性検査や玉手箱で多く出題され、計算力だけでなく式を整理し順序を考える力も試されます。
そのため、公式を丸暗記するのではなく仕組みを理解し、練習を重ねることが重要です。正しい方法で取り組めば得点はアップも可能になるので、この形式の本質を掴むことが成功への第一歩となります。
四則逆算が難しく感じるのは、普段の計算が「順番に進める」のに対し、逆算は「結果から元の数をたどる」逆の思考が必要だからです。慣れていない人だと、制限時間内に解き終えられないこともあります。
しかし逆算には基本法則と順序があり、それを押さえれば解きやすくなります。掛け算や割り算の逆操作を使えば複雑な式も整理でき、練習を重ねれば本番でも力を発揮できるでしょう。
したがって、四則逆算を単なる計算問題と捉えず、「考え方を問う出題」として準備することが、内定に近づくための重要な対策になるのです。
四則逆算の制限時間

四則逆算は就活の適性検査やWebテストでよく出題される形式で、制限時間がある点が特徴です。多くの学生は「問題の内容は理解できるのに、時間内に解けない」と不安を感じやすいでしょう。
そのため、まずは制限時間の目安をつかむことが大切です。一般的には1問あたり30秒前後で処理することを求められる場合が多く、複数問を数分以内に解答する形式も少なくありません。
時間に追われると焦りが出て計算ミスも増えるため、冷静さを保つことが必要。そこで効果的なのは、制限時間を意識した練習です。
過去問や練習問題を実際の試験と同じペースで解くと、徐々に処理速度を高められるはず。また、難しい問題にこだわらず切り替える意識を持てば、限られた時間をより有効に活用できます。
制限時間を理解し、時間配分を意識した訓練を続けることが、高得点に近づくための最短ルートといえるでしょう。
四則逆算で押さえておきたい基本法則
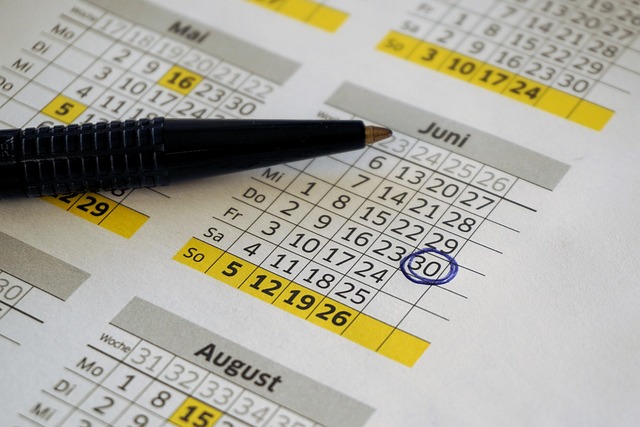
四則逆算を正しく解くには、まず基礎となる法則を理解しておくことが大切です。ここでは特に重要な3つを紹介します。知っているかどうかで計算の速さや正確さが大きく変わるでしょう。
- 交換の法則
- 結合の法則
- 分配の法則
①交換の法則
交換の法則とは、足し算や掛け算では数字の順番を入れ替えても結果が変わらないという性質です。例えば「3+5=8」と「5+3=8」は同じであり、「2×7=14」も「7×2=14」と一致します。
この性質を理解すると、解きやすい形に式を並べ替えることができ、逆算でも大きな助けになるでしょう。試験の場面では順序を工夫することで頭の負担を軽くできます。
例えば「25+□=97」であれば、「97−25」と考えればすぐに答えが出るのです。大きな数でも順序を変えて処理すれば計算が楽になり、結果的に時間を節約できます。
逆算に慣れていない学生は与えられた式をそのまま解こうとして時間を失いがちです。しかし交換の法則を活用すれば無駄な計算を減らせます。
その結果、制限時間内に多くの問題に挑めるようになり、高得点につながるでしょう。基礎的ですが、実践力を高めるうえで欠かせない知識です。
②結合の法則
結合の法則とは、足し算や掛け算でどのように数をまとめても答えが変わらないという性質です。
「(2+3)+4=9」と「2+(3+4)=9」、「(2×3)×4=24」と「2×(3×4)=24」はどちらも同じ結果になります。この法則を知っていると、複雑な式をシンプルにまとめ直すことが可能です。
例えば「□+5+8=20」という問題は「5+8=13」と先にまとめると「□+13=20」と簡単な形になります。そこから「20−13=7」とすぐに答えを出せるのです。
まとめる場所を工夫すれば、計算の手順を減らせるでしょう。長い式や複数の項を含む計算でも、この法則を意識することで効率的に整理できます。
特に試験本番のような緊張感がある場では、まとめ方を工夫する習慣が安定した得点に直結するのです。結合の法則は一見単純ですが、試験で確実に役立つテクニックといえます。
③分配の法則
分配の法則とは、「a×(b+c)=a×b+a×c」というように掛け算を足し算に分けられる性質です。例えば「2×(3+4)」は「2×3+2×4」と展開しても同じ14になります。
逆算の問題では式を整理しやすくする効果があるため、必ず身につけておきたい考え方です。
「(□+3)×5=40」という問題を例にすると、「□×5+3×5=40」と展開でき、そこから「□×5=25」と整理しやすくなります。最終的に「□=5」と答えにたどり着くのもスムーズでしょう。
展開の手順を意識するだけで、複雑に見える式も扱いやすくなります。逆算に苦手意識を持つ人の多くは、式を複雑なまま処理しようとして混乱しやすいです。
しかし分配の法則を取り入れると、式を見通しよく整理できます。他の法則と組み合わせれば応用の幅も広がり、制限時間内で正確に解く力を養えるでしょう。得点アップに直結する基礎力となります。
四則逆算の基本的な解き方
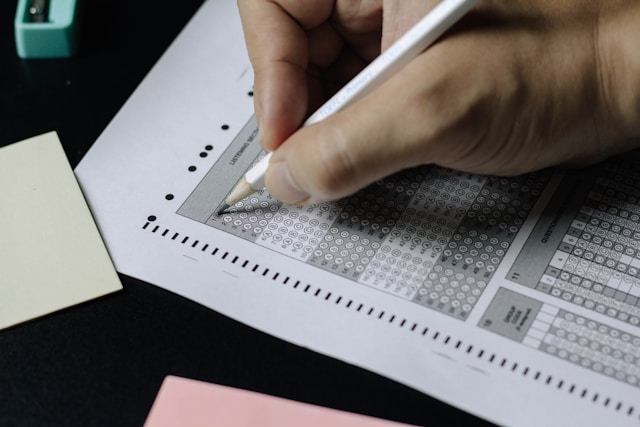
四則逆算は就活のWebテストでよく出題される形式で、通常の四則演算とは逆に結果からもとの数を推測して答えを導きます。
初めて取り組むと複雑に感じるかもしれませんが、基本の流れを押さえれば確実に解けるようになるでしょう。ここでは代表的な解き方を整理して解説します。
- 引き算を使って元の数を求める
- 割り算を使って元の数を求める
- カッコの計算を最初に処理する
- 掛け算・割り算を先に計算する
- 式を整理して逆算しやすくする
①引き算を使って元の数を求める
引き算は、式の最後が足し算で終わっているときに使うのです。たとえば「□+7=12」の場合、12から7を引けば答えの5が得られます。このように加算の逆を意識するだけで、迷わず解けるでしょう。
一度に式全体を処理しようとすると混乱しやすいので、部分ごとに逆算して整理すると落ち着いて進められるでしょう。また「□+7=5」のように結果が小さい場合は、5から7を引いて−2になります。
マイナスの扱いに慣れていないと正答率が下がりかねません。テストは制限時間が短いため、基本の引き算逆算を素早く処理できることが重要。
普段から暗算を使って簡単な計算を練習すると、処理速度が自然に高まるはずです。
②割り算を使って元の数を求める
掛け算で終わる式は、逆に割り算を使うのです。「□×4=20」であれば、20を4で割れば5が求められます。このように考え方はシンプルなので、慣れると安心して解答できるでしょう。
注意したいのは、小数や余りが出る場合です。「□×3=10」なら10÷3=3.333…となり、整数解は存在しません。このように答えが整数にならない問題もあるため、条件をきちんと確認してください。
符号付きの式も同様です。「−12÷4=−3」なども素早く処理できると強みになります。多くの受験者は割り算に時間を取られがちです。
九九や暗算を普段から繰り返しておくことで、スピードも精度も上がるでしょう。
③カッコの計算を最初に処理する
カッコがある場合は、必ず最初に計算する必要があるのです。「(□+3)×2=14」であれば、14を2で割って7にし、次に□+3=7を解いて答えが4になります。順序を誤ると正しい答えは出せません。
焦っているときほどカッコを見落としやすいので、常に「カッコから処理する」と意識してください。カッコの中が複雑でも、一つずつ分解すれば解けます。
慣れてくると「どこから逆算を始めるか」をすぐ判断できるようになり、安定した得点につながります。この意識を持つだけで、ミスの大半は防げるでしょう。
④掛け算・割り算を先に計算する
カッコがない場合でも、掛け算と割り算は足し算や引き算より優先されます。「□+6÷2=10」という問題なら、まず6÷2=3を計算して□+3=10と整理し、答えは7です。
ここで誤りやすいのは「10から6を引く」と考えてしまうケース。計算順序を正しく守れば、時間のロスを防げます。制限時間のあるテストでは、この基本の徹底が得点を左右するでしょう。
分数や小数が含まれていても同じです。「□×0.5+4=9」では、まず引き算をして□×0.5=5に整理し、次に割り算で答えが10と求められます。順序を守ることが速さと正確さの両立につながるでしょう。
⑤式を整理して逆算しやすくする
複雑な式は、整理してから逆算した方が効率的です。「(□+2)×3+4=19」なら、19から4を引いて15にし、15を3で割って5にし、最後に2を引いて答え3を導きます。
順序を工夫することでスムーズに進められるでしょう。最初に「どの順で逆算するか」をイメージしておくと、迷いなく解けます。
焦ると頭の中で整理せず進めてしまい、途中で混乱することが多いので注意してください。また、倍数や因数を見抜いて工夫すれば、さらに短時間で処理できます。
こうした工夫を積み重ねることで、本番でも安定して高得点を狙えるでしょう。
四則逆算を解くためのコツ

四則逆算は制限時間のある適性検査でよく出題されるため、効率よく正確に解く工夫が欠かせません。ここでは代表的な5つのコツを紹介します。これらを意識することで得点力の向上が期待できるでしょう。
- 空欄を「□=」の形にして整理する
- 小数と分数はどちらかに統一する
- 複数の分数は分母を揃えて計算する
- 割り算は分数に置き換えて処理する
- 計算後は必ず検算をする
①空欄を「□=」の形にして整理する
逆算問題では、空欄を「□=」の形に直すと式が見やすくなるのです。例えば「25+□=78」を「□=78−25」と書き換えることで、答えをすぐに導けます。
こうした整理を習慣化すると、複雑な式でも迷わず対応できるでしょう。就活の適性検査では焦りやすく、整理せずに計算を始めると誤答やミスにつながります。
最初の数秒を使って「□=」の形に整えるだけで、その後の計算がスムーズになり時間の節約にも役立つのです。短時間で正確に解くための基本的な方法といえます。
②小数と分数はどちらかに統一する
四則逆算では小数と分数が混ざると計算が煩雑になります。そのため必ずどちらかに統一してください。例えば「0.25」を「1/4」に変えると、割り算や掛け算が処理しやすくなります。
逆に分数を小数に変えると暗算に向く場合もあるでしょう。両方を混在させると途中で混乱しやすくなります。
問題演習の段階でどちらに変換するのが自分に合っているかを確認しておくと、本番で迷わず対応できます。この工夫が計算スピードを大きく左右するのです。
③複数の分数は分母を揃えて計算する
分数が複数出る場合は分母を揃えることが重要です。「1/2+1/3」は「3/6+2/6=5/6」と簡単に処理できます。分母を揃えないまま進めると式が複雑になり、時間を余計に使ってしまうでしょう。
適性検査では限られた時間内で正解することが求められます。分母を揃える習慣をつけることで、分数の計算にリズムが生まれ、安定感も増すでしょう。
分数問題が苦手な人こそ、この方法を徹底してください。
④割り算は分数に置き換えて処理する
割り算を分数に変えると計算が簡単になります。例えば「12÷3」を「12×1/3」と書き換えると掛け算に統一できるのです。逆算問題は掛け算と割り算が混ざることが多いため、掛け算に直すと効率的でしょう。
この方法を活用すると、複雑な式でも一定の流れで処理できます。また暗算でも解きやすくなるため、制限時間を意識する試験に適しているでしょう。
分数に置き換える発想を持つだけで、精度とスピードの両方が向上します。
⑤計算後は必ず検算をする
最後に欠かせないのが検算です。どんなに自信があっても焦りや不注意で間違えることはあります。検算を行えば誤答を防げるだけでなく、安心して次の問題に進めるでしょう。試験はスピード勝負ですが、誤答では得点になりません。
効率を考えるなら、検算はすべてに行う必要はありません。特に難しい問題や不安が残る問題に絞るだけでも効果的です。見直しの習慣を持つことで、安定した得点を確保できるようになります。
四則逆算を速く解くための時短のコツ

四則逆算は就活の適性検査で得点を伸ばすうえで重要な形式です。内容を理解していても時間切れになることが多いため、効率よく解く工夫が欠かせません。
ここでは短い制限時間の中で処理速度を上げる方法を紹介します。
- 出題されやすいパターンを暗記しておく
- 制限時間を意識して練習する
- 選択肢を先に確認してヒントを得る
- 迷う問題は飛ばして後回しにする
- 間違いをノートにまとめて復習する
①出題されやすいパターンを暗記しておく
四則逆算は、典型的なパターンを覚えておくことで格段に速く解けます。「□+7=12」「□×4=20」「(□+3)×2=14」といった形式はよく出題されるので、見た瞬間に手が動くようにしておくと安心でしょう。
毎回ゼロから手順を考えると時間が足りません。理解できるのに間に合わないという悩みは、暗記不足によって起こりがちです。ただし、単なる丸暗記ではなく仕組みを理解しながら覚えることが大切です。
構造を押さえておけば、多少変化した問題にも応用できます。典型的な問題を繰り返し解き、自分なりにパターンを整理してください。その積み重ねが本番でのスピード向上につながります。
②制限時間を意識して練習する
四則逆算で実力を出すには、実際の試験と同じ制限時間を意識して練習することが欠かせません。
1問あたり30秒程度しかかけられないことが多いため、普段から同じ感覚で取り組むと本番でも落ち着いて解けるでしょう。時間を計らずに解くと速さが鍛えられません。
逆に制限をかけると、最初は間違いが増えるかもしれませんが、正確さと速さを同時に身につけられます。机の上に時計を置いて問題を解くなど、環境を試験に近づける工夫をしてください。
解き終えた後は、どの部分に時間を使ったのか振り返ると効果的です。弱点を把握できれば重点的に克服でき、着実に力が伸びるでしょう。
③選択肢を先に確認してヒントを得る
四則逆算の問題は、選択肢を確認してから解き始めると効率が上がります。就活用のWebテストでは選択肢が提示されることが多いため、有効に活用してください。
選択肢が「2」「4」「6」「8」と並んでいれば、答えが整数に限られると分かります。小数や分数を考える必要がなくなるので、迷いが減るでしょう。
また、選択肢を代入して計算し、合うものを探す方法も時短になります。ただし、すべての選択肢を片っ端から試すのは時間の無駄です。候補を絞れるときに限定して使ってください。
適切に取り入れれば、短時間で正解にたどり着けるはずです。
④迷う問題は飛ばして後回しにする
解けそうにない問題に固執すると、時間を失ってしまいます。得点を伸ばすには、迷った問題は一度飛ばし、最後に余った時間で取り組むのが賢明です。
この戦略を取れば、解答できる問題数を増やせます。難問に時間を使うと簡単な問題を落とすことになりかねません。Webテストは相対評価の場合も多いため、効率よく得点を重ねることが重要でしょう。
飛ばす勇気を持つことで、冷静に試験に臨めます。時間配分を意識できれば、結果的に正答率も高まるでしょう。
⑤間違いをノートにまとめて復習する
速さを身につけるには、間違えた問題をノートにまとめて復習することが欠かせません。自分がどのようなミスをしやすいのか記録しておくと、同じ失敗を繰り返さなくなります。
「順序を間違えた」「カッコを処理し忘れた」「マイナスで混乱した」など、具体的な内容を書き残してください。弱点が一目で分かり、効率的に克服できます。
さらに、記録を見返すことで成長を実感でき、学習意欲も保てます。問題集を解くだけでは同じミスを続けやすいので、ノートにまとめる習慣をつけてください。
こうした取り組みが、最短で得点力を伸ばす近道になるでしょう。
【パターン別】四則逆算の例題
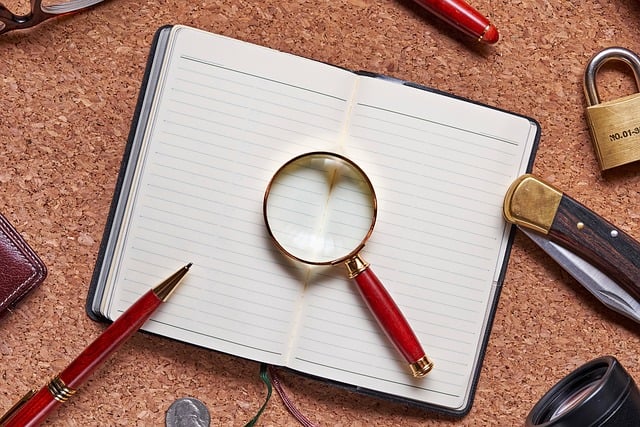
四則逆算は出題パターンを知っておくことで、初めて見る形式でも落ち着いて取り組めます。ここでは代表的な9種類を例題とともに紹介していきます。
実際に手を動かしながら理解することが、得点力を高める近道になるでしょう。
- 足し算
- 引き算
- 掛け算
- 割り算
- 四則混合(複合計算)
- カッコを含む計算
- 分数・小数を含む計算
- 空欄が複数ある計算
- 変数を含む計算(方程式型)
①足し算
足し算の逆算はもっとも基本的なパターンです。
大切なのは常に逆の操作を意識することです。足し算は引き算に変換するだけで迷わず解けます。慌てて暗算すると誤答することもあるため、落ち着いて処理しましょう。
| 例題:「□+25=78」 → 「78−25=53」 |
②引き算
引き算の逆算は「差と片方の数」からもう一方を求めます。符号の扱いに注意が必要です。負の数を含む場合は暗算だけで済ませず、途中式を書き出すとミスを防げます。
| 例題:「□−12=40」 → 「40+12=52」 |
③掛け算
掛け算の逆算は「積と一方の数」からもう一方を導きます。大きな数は「60÷6+12÷6」と分けて処理すると安定して解けるでしょう。複雑に見えても小さく区切れば安心です。
| 例題:「□×6=72」 → 「72÷6=12」 |
④割り算
割り算の逆算は「商と一方の数」からもう一方を求めます。重要なのは掛け算との対応を意識することです。割り算を掛け算に置き換える習慣を持つと、スピードが大きく上がります。
| 例題:「□÷5=9」 → 「9×5=45」 |
⑤四則混合(複合計算)
複合形式では順序を守ることが鍵です。まず「40÷4=10」と整理し、「□+3=10」から「□=7」を求めます。1つずつ丁寧に逆にたどると複雑な問題も解けるでしょう。
| 例題:「(□+3)×4=40」 |
⑥カッコを含む計算
カッコは計算の優先順位が最も高いため注意が必要です。掛け算を逆にして「18÷2=9」とし、「□+5=9」から「□=4」を導きます。式を書き出して確認すれば安心です。
| 例題:「(□+5)×2=18」 |
⑦ 分数・小数を含む計算
小数や分数は変換して扱うと解きやすくなります。0.25を1/4に直して「5÷1/4=20」と考えると直感的に理解できるはず。自分に合った処理方法を決めておきましょう。
| 例題:「□×0.25=5」 → 「5÷0.25=20」 |
⑧空欄が複数ある計算
空欄が2か所以上ある問題は順番に埋めることが基本です。仮に最初の□を3と置くと「(3×2)+□=15」→「6+□=15」→「□=9」と解けます。仮置きを活用すると冷静に進められるでしょう。
| 例題:「(□×2)+□=15」 |
⑨変数を含む計算(方程式型)
変数を含む形式は方程式の知識が役立ちます。未知数を孤立させる手順を意識すれば複雑な式も簡単に整理できます。方程式の基礎を復習しておくと効果的でしょう。
| 例題:「2□+4=10」 → 「2□=6」 → 「□=3」 |
四則逆算の対策方法

四則逆算は就活のWebテストでよく出題されますが、理解しているだけでは十分ではありません。高得点を取るには効率的な学習を続けることが欠かせないでしょう。
ここでは日々の取り組みから本番を意識した練習まで、効果的な方法を整理して紹介します。
- 毎日コツコツ練習問題を解く
- 制限時間を設定して解答スピードを鍛える
- よく出る問題パターンを重点的に練習する
- 模試やアプリを使って実戦感覚を養う
- 苦手な計算分野を重点的に克服する
①毎日コツコツ練習問題を解く
四則逆算は、一度に多く解くよりも毎日少しずつ取り組む方が効果的です。短時間でも継続することで計算の感覚が定着し、自然と速さも増していきます。
大切なのは、順序を間違えない習慣を身につけることです。毎日の練習で手順が体に染み込めば、本番でも焦らずに解けるでしょう。
反対に練習が途切れると、理解したつもりでも本番でミスを繰り返しかねません。問題集やアプリを使って1日10分ほど取り組むのがおすすめです。小さな積み重ねが大きな成果を生むことを意識してください。
②制限時間を設定して解答スピードを鍛える
実際の試験では1問に30秒程度しか使えません。そのため、普段の練習から制限時間を設けて取り組むことが必要です。時間を測らずに解いても、本番で役立つスピードは身につかないでしょう。
最初は焦って間違いが増えるかもしれませんが、経験を重ねれば精度も速さも改善します。どこで時間がかかったのかを振り返ると、弱点を明確にできるでしょう。
タイマーを使ったり、模試形式で一度に複数の問題を解いたりして、本番に近い環境で練習してください。そうすることで安定した得点力につながります。
③よく出る問題パターンを重点的に練習する
四則逆算には出題されやすい典型パターンがあります。これを重点的に練習しておくと、試験本番で迷う時間を減らせるでしょう。「□+7=12」「□×3=15」「(□+4)×2=18」といった形式は頻出です。
これらを見ただけで答えが浮かぶようにしておくと安心でしょう。ただし暗記だけに頼るのではなく、仕組みを理解することが大切です。
順序や法則を意識して練習すれば、形が少し変わっても対応できます。典型的な問題の習熟が全体のスピードアップにつながるのです。
④模試やアプリを使って実戦感覚を養う
個別の問題練習だけでは、本番特有の緊張感や時間配分の難しさに対応できません。模試や専用アプリを利用して、実戦形式の感覚を養ってください。
模試では限られた時間で複数の問題を解くため、集中力や切り替えの力を鍛えられます。アプリなら通学やすき間時間に取り組めるので、継続しやすいでしょう。
本番を意識した環境で練習することで、自分なりのペース配分や得点の取り方が見えてきます。それが安定した成績につながるはずです。
⑤苦手な計算分野を重点的に克服する
自分の弱点を把握し、そこを集中的に克服することも欠かせません。例えば「割り算に時間がかかる」「マイナスの計算で間違えやすい」といった癖を放置すると、試験での失点につながります。
練習でつまずいた箇所を記録し、原因を振り返ってください。そのうえで同じタイプの問題を繰り返すと、自信を持って取り組めるようになります。
苦手を減らすと全体の処理速度も自然に上がるのです。得意分野を伸ばすより、弱点を克服する方が得点に直結しやすいでしょう。安定して高得点を取るための重要な取り組みです。
四則逆算で高得点を狙うポイント
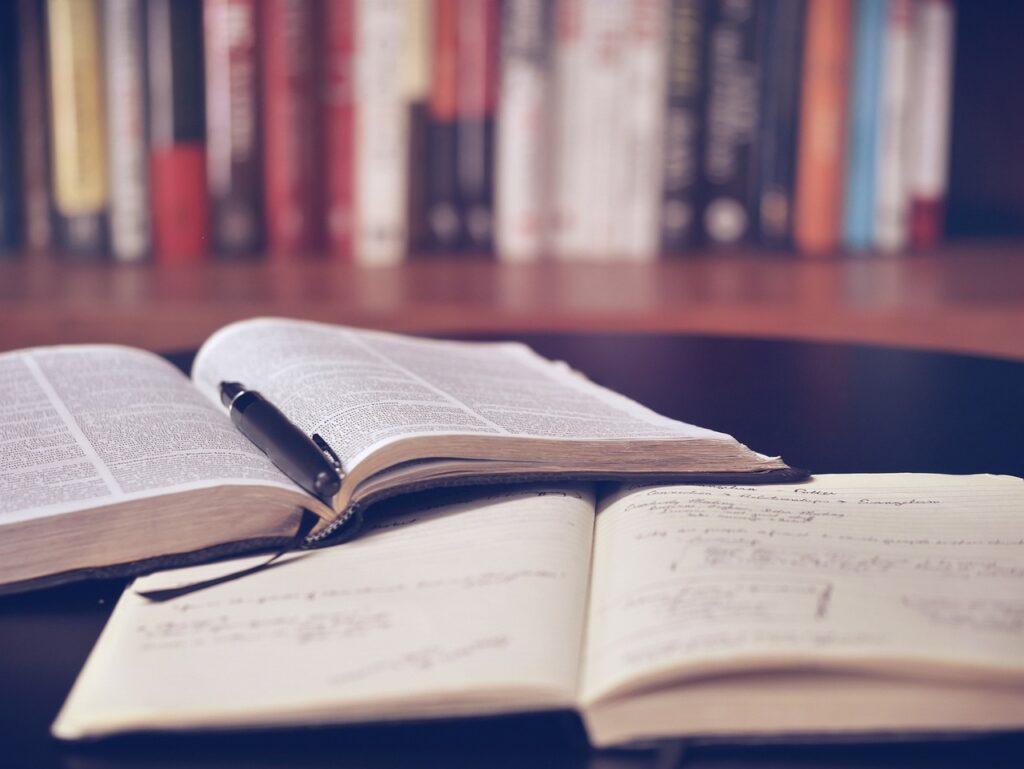
四則逆算で安定して点を取るには、やみくもに解くのではなく、取り組み方を工夫する必要があるのです。ここでは本番で役立つ5つの要点を紹介します。
今日からの練習に取り入れれば、短期間でも確実に実力が上がるでしょう。
- 正確さとスピードのバランスを意識する
- 計算の順序を徹底的に守る
- 難問よりも確実に解ける問題を優先する
- 時間配分をあらかじめ決めておく
- 最後まで諦めずに解き切る姿勢を持つ
①正確さとスピードのバランスを意識する
四則逆算は速さだけでも正確さだけでも得点は伸びません。両立させることで高得点につながります。なぜなら制限時間内に十分な問題数を解きつつ、ミスを減らさなければならないからです。
効果的なのは、式を「□=」の形に整理してから掛け算・割り算→足し算・引き算の順で処理する方法。これで手戻りが減ります。また、暗算にこだわりすぎないことも重要でしょう。
桁数が多いときはメモを活用し、検算では逆操作で素早く確認してください。練習時には1問ごとに時間と正誤を記録し、自分の解答スピードと精度を把握しておきましょう。
そうすれば本番では迷いが少なくなり、速さと正確さが自然に両立します。
②計算の順序を徹底的に守る
高得点を取るためには、計算の順序を必ず守ることが欠かせません。守らなければ速く解いても誤答が増えるだけです。
混合式では「掛け算・割り算が先、足し算・引き算が後」「カッコは最優先」というルールが絶対。おすすめは、式を見た瞬間に優先順位を印で示す習慣をつけることです。
例えば「□×3+12=48」なら「□×3=48−12→□=36÷3」と変形します。分数や小数が混ざる場合は先に形を統一しておくと順序ミスを防げるでしょう。
演習では似た式を並べて毎回同じ手順で処理できるか確認してください。手順が定着すれば、迷いなく答えにたどりつけるようになります。
順序を守ることはスピードを落とすどころか、判断を減らして効率を上げる効果があるでしょう。
③難問よりも確実に解ける問題を優先する
配点が同じなら、難問に時間をかけるより確実に解ける問題を積み上げた方が総合点は上がります。適性検査は問題数が多く、1問ごとの得点効率が重要だからです。
そこで事前に「見きわめの基準」を決めておくと安心。分数が多い複雑な式や空欄が2つ以上あるものは後回し、単純な式やカッコつきのものは先に解くといったルールを作りましょう。
実践的には最初の2分で全体を確認し、すぐに解ける問題に印を付けましょう。その後、易問→中問→やや難問の順に進め、最後に残った問題へ戻ります。
練習段階では難易度別にタグをつけ、標準レベルを高精度で仕上げることを意識してください。難問はボーナス、標準は落とさない。この戦略が高得点への近道です。
④時間配分をあらかじめ決めておく
高得点を目指すなら、時間配分を事前に決めておくことが不可欠です。場当たり的に解くと、序盤で時間を使いすぎて終盤に取りこぼすことになりかねません。
おすすめは「3段階配分」です。最初の2分で全体をざっと確認し、易問をチェック。次に本編で1問40〜60秒を目安に回収し、最後の2〜3分で見直しと保留問題に取り組みます。
練習ではキッチンタイマーやスマホを使い、このリズムを体に染み込ませてください。さらに「2手進めて見通しが立たなければ保留」といった打ち切り基準を作っておくと迷いません。
模試形式で記録を取り、自分に合う配分を探すと、本番で安定した得点につながるでしょう。
⑤最後まで諦めずに解き切る姿勢を持つ
終盤の1問を取れるかどうかで合否に影響する場合があります。同点が多い適性検査では特に差になりやすいでしょう。そこで必要なのは諦めない姿勢です。
解けないと感じたら深呼吸をして式を「□=」に直し、逆操作だけに集中してください。選択肢があるときは代入して消せるものから落としていくのも有効です。
見直しの際は「符号」「ゼロ」「分母」の3点を重点的に確認しましょう。これでケアレスミスを大幅に減らせます。
演習ではあえて残り1分からの解答練習を行い、焦りの中でも冷静に手を動かせるように備えてください。最後まで粘り強く取り組む姿勢は、そのまま評価にも直結します。
最後の1点まであきらめずに挑戦してください。
四則逆算の学習ポイント

四則逆算は就活のWebテストで頻出するため、正確さとスピードを両立した対策が欠かせません。
制限時間を意識しながら、法則の理解や基本的な解き方、さらにコツを活用することで得点力を高められます。
特に、出題されやすいパターンを暗記し、例題で実戦的な練習を積むことが重要です。また、苦手分野を克服しつつ、計算の順序を徹底して守れば安定した結果につながるでしょう。
結論として、日々の練習と工夫を積み重ねることこそが、四則逆算で高得点を狙うための最短ルートといえます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











