SPI勉強法を分野別に徹底解説!高得点のための実践対策ガイド
就活を控える人の多くがSPI(適性検査)の勉強法に悩むでしょう。限られた時間で得点を上げるためには、効率的に勉強する必要があります。
そこで本記事では、SPIの出題形式や頻出分野を押さえたうえで、実践的な勉強法を詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
SPIとは
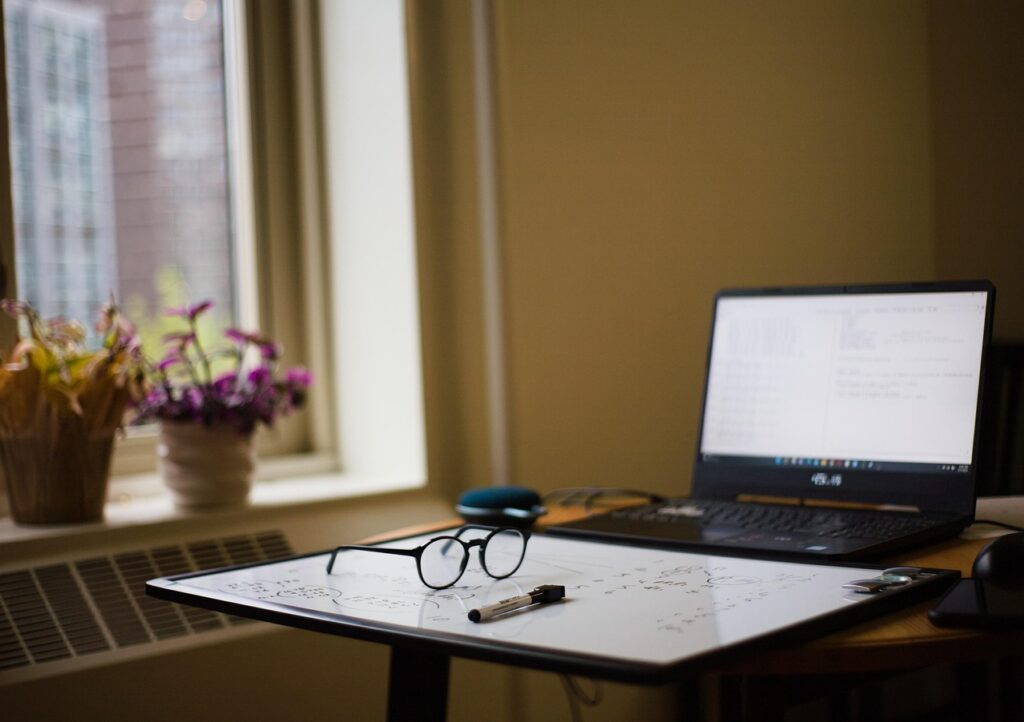
SPIとは、多くの企業が採用選考で利用する適性検査の一種で、主に言語分野と非言語分野から構成されています。就活生にとっては、書類選考を通過するための重要なステップの1つといえるでしょう。
SPIの内容を理解しておかないと、試験本番で実力を発揮できずに悔しい思いをするかもしれません。SPIは応募者の基礎的な学力や論理的思考力、性格の特徴などを測定することを目的としています。
企業側はこの情報をもとに、自社との相性や職種適性を判断しているのです。そのため、SPIで高得点を取ること自体がゴールではありませんが、事前の対策を怠ると不利になる可能性があります。
対策には、出題形式に慣れることや時間配分の練習が効果的です。まずはSPIの全体像を正しく理解し、効率よく準備を進めていきましょう。
SPIの対策開始時期
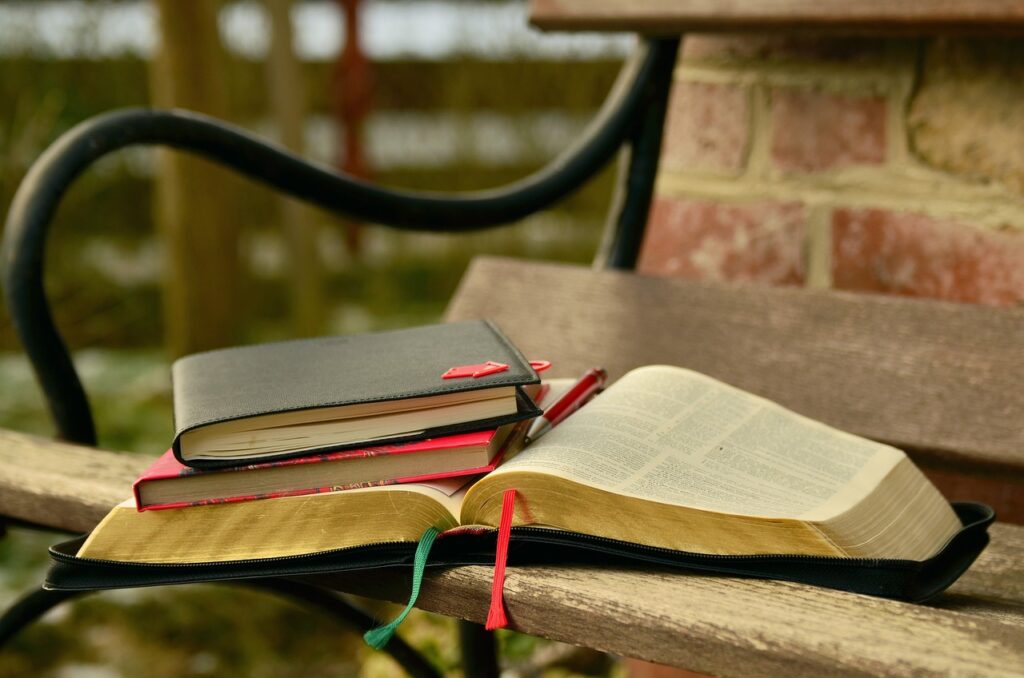
SPI対策を始めるタイミングに迷っている就活生は多いでしょう。「早く始めすぎると効率が悪そう……かといって、遅すぎると間に合わないのではないか」と不安になるかもしれません。
ここでは、就活の開始時期に応じた効果的なSPI対策の始め方を紹介します。
- インターンシップ時期から就活を始める場合
- 本選考開始時期から就活を始める場合
①インターンシップ時期から就活を始める場合
インターンシップに参加する予定がある人は、SPI対策を早めに始めておくと有利になります。近年では、夏のインターン選考にSPIを課す企業が増えており、6月ごろから準備に取りかかるのが理想的です。
最初は全体像を把握することを重視し、問題集を通して「どんな分野が出題されるのか」をつかむことが大切になります。特に非言語分野は慣れるまで時間がかかるため、じっくり取り組むと安心です。
また、時間配分を意識しながら問題を解く練習をすると、本番でも落ち着いて対応しやすくなるでしょう。
早めの対策は、他の選考準備や授業と無理なく並行して進められ、結果として精神的な余裕にもつながるはずです。
就活が本格化する前に基礎を固めておくことで、他の学生に一歩差をつけられるでしょう。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
②本選考開始時期から就活を始める場合
本選考から就活を始める場合は、短期間でSPIの基礎をしっかり身につけることが必要です。
たとえば、1月から本格的に対策を始めるとすれば、3月の選考本番までに効率よく勉強を進めることが求められます。
まずは、頻出問題を把握したうえで、1冊の問題集を選び、繰り返し解くことが基本となります。
限られた時間を有効に使うために、本番を想定して時間を計りながら問題演習を行うと、実践力がついていきます。
また、SPI対策アプリやオンライン模試を活用すれば、場所を選ばず対策できます。短期集中でも十分に点数アップは可能なので、焦らず計画的に学習を進めてください。
やるべきことに優先順位をつけ、時間を意識した対策を意識すると成果が出やすくなります。
SPIの対策時間

SPIの勉強を始めるときに、多くの就活生が迷うのが「どれくらいの時間をかければいいか」という点です。やみくもに長時間勉強しても効果は薄いため、効率的な取り組みが求められます。
ここでは、SPI対策にかけるべき時間の目安と、自分に合った学習ペースを紹介します。
一般的に、SPI対策に必要な勉強時間は、30〜50時間ほどです。この時間を目安に、言語・非言語・性格検査の各分野にまんべんなく取り組みましょう。ただし、数学に苦手意識がある方は、非言語分野に多めの時間を充てることをお勧めします。
たとえば、平日に1〜2時間、休日にやや長めの時間をとって、2〜4週間で計画的に取り組むのが現実的なスケジュールです。
毎日まとめて時間を取るのが難しい場合は、通学中やスキマ時間を活用して、アプリやWeb教材で対策を進めてみてください。
重要なのは、無理のないペースで継続することです。焦って詰め込むよりも、地道に力を積み上げていくほうが、本番での安定した得点力につながります。
SPIの勉強方法

SPI対策を始めるとき、「何から取り組めばいいのか」と迷う就活生は少なくありません。効率よく得点力を伸ばすためには、学習の順序や内容の選び方を工夫する必要があるのです。
ここでは、SPIの勉強を無理なく進めるための基本的な考え方と工夫を紹介します。
- 目的に応じて学習内容の優先順位を決める
- 分野ごとに勉強法を使い分ける
- 短時間でも継続できる学習習慣をつくる
- 本番までの逆算で学習スケジュールを立てる
- やる気を保つために目標スコアや進捗を可視化する
- 苦手分野は理解→練習→確認のサイクルで対策する
①目的に応じて学習内容の優先順位を決める
SPI対策を始めるにあたって、すべての分野を均等に勉強しようとすると効率が悪くなります。
特に、SPIには言語・非言語・性格検査など複数の領域があるため、「どこに力を入れるべきか」を最初に決めておくことが重要です。
まずは、志望企業で求められるSPIの出題形式や重視される分野を確認しましょう。頻出問題が多い非言語や言語分野から手をつけるのが基本となります。
限られた時間を有効に使うには、「何を優先するか」の判断が勉強の質を左右します。
②分野ごとに勉強法を使い分ける
SPIでは言語・非言語・性格検査など、各分野に応じた勉強スタイルを取ることが求められます。
たとえば、言語分野では日常的な読書や語彙の暗記、文章構成の理解が中心です。一方で、非言語分野は計算やグラフの読み取り、論理的な思考力が問われます。そのため、図や表を使って情報を整理する練習が効果的です。
性格検査に関しては、正解があるわけではないため、事前に設問の傾向を知っておくだけでも安心材料になります。
自分の苦手傾向に応じて、柔軟に対策を切り替えていきましょう。
③短時間でも継続できる学習習慣をつくる
毎日まとまった時間を確保するのが難しい就活生にとって、継続的な学習の仕組みづくりがカギとなります。
たとえば通学中にスマートフォンで語彙を確認したり、5分だけ計算問題を解くなど、日常のスキマ時間を活用することで、無理なく勉強のリズムが身につきます。
「たった10分でもやった」という積み重ねがモチベーションの維持につながり、結果的に長期間続けられる要因になるでしょう。
重要なのは、毎日机に向かうことではなく、毎日SPIに触れる習慣を保つことです。
④本番までの逆算で学習スケジュールを立てる
限られた準備期間で結果を出すには、試験日から逆算した学習スケジュールの設計が有効となります。
たとえば、2か月ある場合は「最初の3週間で基礎を固める」「その後2週間で応用問題をこなす」「残り3週間は模試形式で実戦力を高める」と段階的な進め方が効果的です。
こうした計画があれば、勉強の進捗が把握しやすく、焦りを感じにくくなります。漠然と勉強するのではなく、期間と目的を明確に区切ることが、着実なスキルアップにつながるでしょう。
⑤やる気を保つために目標スコアや進捗を可視化する
学習を継続するためには、モチベーションの維持が重要です。特に長期間の対策になると、「本当に伸びているのか」と不安になることもあります。
そんなときは、目標スコアや学習の進捗を記録して「見える化」することで、やる気を保ちやすくなるでしょう。
たとえば「模試で〇点を目指す」と数値目標を掲げたり、「今週は問題集の何ページまで終える」と進行具合をチェックするなど、自分で達成感を演出できる工夫が効果的です。
⑥苦手分野は理解→練習→確認のサイクルで対策する
苦手意識のある分野を避けてしまうと、いつまで経っても得点力は伸びません。まずは「なぜ苦手なのか」を知るために、解説を丁寧に読み、理解に努めましょう。
そのうえで、似た問題を繰り返し解くことで、知識を定着させます。時間をおいて再度解いてみる「確認ステップ」も忘れずに行ってくださいね。
このサイクルを何度か繰り返すことで、苦手分野の問題が徐々に克服できるはずです。
SPIの勉強の手順

SPIの対策は、正しい順序で取り組むことで効率的になります。
ここでは、就活生が無理なく実行できる6つのステップを紹介します。
- 志望企業のSPI出題形式を確認する
- 対策に使う問題集・アプリを選ぶ
- 1冊の問題集を計画的に1周する
- 間違えた問題を繰り返し解く
- 時間を計って実戦形式で練習する
- 模試を活用して本番に慣れる
①志望企業のSPI出題形式を確認する
はじめに、志望企業が「どのSPI形式を採用しているか」を調べましょう。SPIにはテストセンター・Webテスティング・ペーパーテストなど複数の形式があり、それぞれ出題傾向や環境が異なります。
誤った形式で対策してしまうと、本番で戸惑う原因になりかねません。企業の選考情報は、就活サイトや口コミで確認できます。
早めに形式を把握しておくと、無駄な学習を避けられ、時間を有効に使えるでしょう。
②対策に使う問題集・アプリを選ぶ
勉強には自分に合った教材を選ぶことが大切です。
市販の問題集はもちろん、最近はスマホで手軽に使える無料アプリも充実しています。
移動時間などのスキマ時間にはアプリ、じっくり取り組みたいときは紙の問題集、といった使い分けも効果的です。ただし、複数の教材に手を出すより、1つをやり切ることを優先してください。
選ぶ際は、出題範囲の網羅性や解説の分かりやすさを基準にすると良いでしょう。
③1冊の問題集を計画的に1周する
問題集を購入したら、まずは全体を1周して全体像をつかみましょう。
最初から正解を目指すよりも、問題の傾向や形式に慣れることを意識してください。
毎日少しずつでも進めれば、数週間で終えるのは難しくありません。全範囲を把握しておくことで、次のステップとなる復習や実戦練習にスムーズに進めます。まずは「解いてみる」姿勢が大切です。
④間違えた問題を繰り返し解く
1周終えたあとは、正解できなかった問題に集中して取り組みましょう。
「どこで間違えたのか」「なぜ解けなかったのか」を分析しながら復習することで、苦手分野を克服できます。
間違いノートを作って、同じミスを繰り返さないよう工夫すると効果的です。繰り返し解くことで理解が深まり、本番でも落ち着いて対応できるようになるでしょう。
⑤時間を計って実戦形式で練習する
SPIは時間制限のあるテストのため、時間配分に慣れておくことが欠かせません。
特に非言語分野では、考えるのに時間がかかる問題も多いため、タイムマネジメントが重要です。
本番と同じ時間を設定して練習することで、解答スピードと正確さのバランスを体感できます。早めに実戦形式に取り組めば、本番の焦りも減らせるでしょう。
⑥模試を活用して本番に慣れる
仕上げのステップとして模試を受けましょう。
模試は、今の実力を客観的に把握できる貴重な機会です。得意・不得意の把握だけでなく、試験本番の雰囲気に慣れることにもつながります。
受けたあとは、必ず解説を見て復習してください。1回の模試から得られる学びは多く、対策の最終確認にもぴったりです。余裕があれば複数回受けて、安定した力を身につけましょう。
【言語分野】SPI対策の勉強法

SPIの言語分野では、語彙力や読解力、文章の理解力など幅広い力が求められます。なんとなく解くクセがついているとミスが増え、点数も安定しないかもしれません。
ここでは、着実に得点を上げるための言語分野の勉強法を紹介します。
- 語彙・熟語は暗記対策で克服する
- 長文読解は設問先読みで対策する
- 文章力は日常読書で対策する
①語彙・熟語は暗記対策で克服する
語彙や熟語は、一度に覚えようとしても難しいものです。ただ、頻出の単語や表現をリスト化し、スキマ時間に繰り返して覚えるだけでも、着実に知識は増えていきます。
通学中や待ち時間にアプリや単語帳を使うと、無理なく続けられるでしょう。意味だけでなく、文脈の中でどう使うかまで理解しておくと、本番でも迷いません。
短時間でも毎日積み重ねることで、問題に出てきたときすぐに意味が思い出せるようになります。
②長文読解は設問先読みで対策する
長文読解では、文章全体を最初からじっくり読んでいると、途中で時間が足りなくなることがあるでしょう。そこで有効なのが「設問先読み」です。
まず設問を確認し、その内容に関わる情報を意識しながら本文を読むと、必要な部分を効率よく拾うことができます。
特に、要旨や言い換えを問う問題では、この方法が読み飛ばしやミスを防ぐのに役立つでしょう。読み方を少し変えるだけで、解くスピードと正確さが大きく変わります。
③文章力は日常読書で対策する
読解力や語彙力は、一夜漬けではなかなか伸びません。そのため、日常的に文章に触れることが効果的です。
新聞や小説、ビジネス書など、内容のある文章を読む習慣を持つと、語句の使い方や文章構造への理解が深まっていきます。
特に、論理的な構成に慣れておくと、SPIの設問にも自然と対応しやすくなるでしょう。
勉強というより、日々の生活の中で自然に取り入れてみてください。楽しみながら続けられる点も大きな利点です。
【非言語分野】SPI対策の勉強法

非言語分野はSPIの中でも難しく感じやすいパートですが、出題の特徴を理解し、ポイントを押さえた対策をすれば得点アップが狙えるでしょう。
ここでは、効率的に力をつけるための3つの対策法を紹介します。
- 頻出単元はパターン別演習で対策する
- 図や表は整理力の強化で対策する
- 時間管理は制限時間内演習で対策する
①頻出単元はパターン別演習で対策する
非言語では「割合」「速さ」「損益」など、よく出る問題のパターンがあります。これらは出題形式にある程度の傾向があるため、まずはパターンごとの練習を重ねることが効果的です。
典型的な問題から始め、徐々に応用へと進めると理解が深まるでしょう。間違えた問題は放置せず、原因を確認しながら解き直してください。
すべての範囲を一気にやろうとせず、頻出分野から集中して取り組むと、効率よく得点力が身につきます。
②図や表は整理力の強化で対策する
非言語では、図や表を見て数値を読み取りながら解く問題も多く出されます。対策として、図表の内容を紙に書き出して整理する習慣をつけるとよいでしょう。
情報の整理ができていないと、数字が多く混乱しやすいです。そのため、頭の中で処理しようとせず、目に見える形で並べることで思考がスムーズになります。
同じ形式の問題を繰り返し解いていけば、瞬時に構造を把握できるようになってきます。
③時間管理は制限時間内演習で対策する
非言語分野では、内容に加えて時間配分の難しさも大きな壁になります。解き方が分かっていても、時間が足りずに問題を残してしまうこともあるでしょう。
そのため、練習時から1問ごとに時間を設定し、解くスピードを意識してください。たとえば「1問1分以内」と決めて取り組むと、解答ペースがつかみやすくなります。
本番の制限時間を想定した演習を繰り返すことで、自然と集中力や判断力も高まっていくはずです。
【その他分野】SPI対策の勉強法
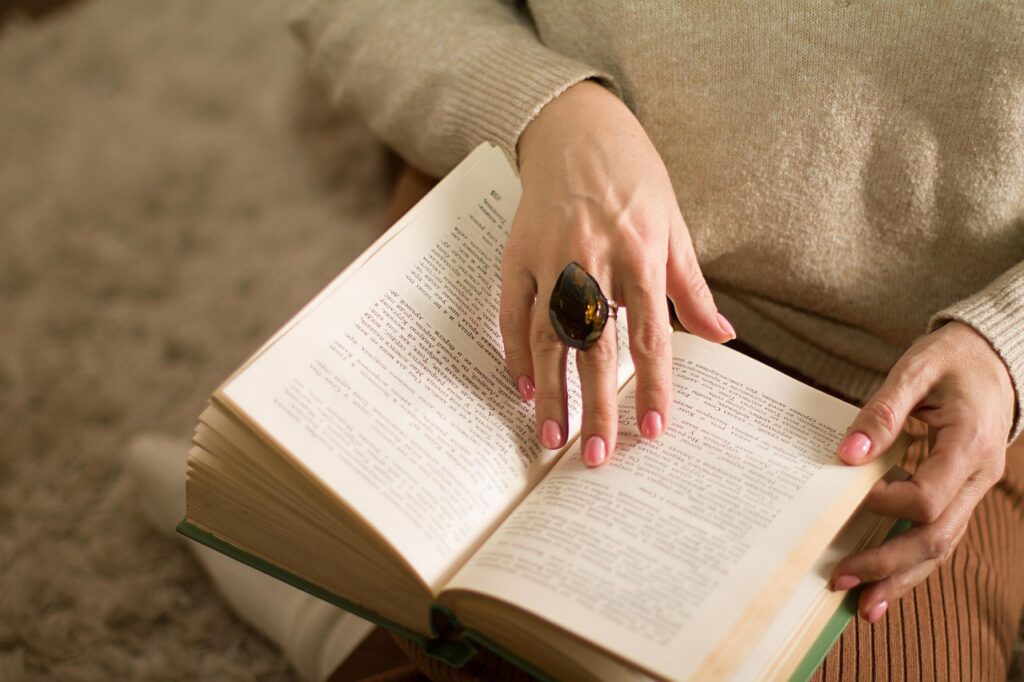
SPIには言語・非言語のほかにも、英語・構造的把握力・性格検査といった分野があります。後回しにしがちなこれらの科目も、企業によっては選考に大きく関わるため、早めの対策が重要です。
ここでは、それぞれの分野に合った勉強法を紹介します。
- 英語はTOEIC形式で対策する
- 構造的把握力は演習で対策する
- 性格検査は傾向理解で対策する
①英語はTOEIC形式で対策する
SPIの英語問題は、TOEICに似た形式で出題されるケースが多く、語彙や文法、読解力が問われます。そのため、TOEIC対策用の教材や問題集を使って学習すると効率的でしょう。
特に読解問題では、パターンに慣れておくと、解答スピードがぐっと上がります。英語が苦手な方は、まず単語や熟語の暗記から始めるのがおすすめです。
TOEIC対応のアプリなどを活用すれば、スキマ時間にも学習できるため、無理なく継続できるでしょう。
②構造的把握力は演習で対策する
構造的把握力は、文章や図表から情報を整理し、全体の構造を理解する力が問われる分野です。この分野は暗記では対応しづらく、問題を解きながら思考のコツをつかむ必要があります。
まずは、設問の意図や情報の関係性を意識して解くことが大切です。専用の問題集を繰り返すことで、設問のパターンや出題傾向がつかめてくるでしょう。
日頃から物事を論理的に考える習慣を意識することも、実践力につながります。
③性格検査は傾向理解で対策する
性格検査には正解・不正解はありませんが、回答に一貫性がなかったり、極端すぎる選択肢を選ぶと評価が下がる可能性があります。
対策としては、まず出題される質問の傾向を知っておくことが重要です。模擬問題に取り組むことで、自分の回答パターンを把握できるようになります。
また、「こう答えたほうが有利」と考えて作為的に答えると矛盾が生じやすくなるはず。素直かつ安定した回答を心がけることが、良い評価につながるでしょう。
SPI対策のコツ

SPIで高得点を目指すには、やみくもに問題を解くだけでは不十分です。限られた時間を有効に使うために、押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
- 設問ごとの時間配分を常に意識する
- 間違えた問題を分析して学びに変える
- 模試は本番環境を想定して取り組む
①設問ごとの時間配分を常に意識する
SPIでは、限られた時間の中で複数の設問を解き切る必要があります。特に非言語分野は思考に時間がかかるため、1問にかける時間を意識することが重要です。
難しい問題に時間をかけすぎると、後半の簡単な問題を落としてしまう可能性があります。対策としては、「この問題は30秒以内」「この形式は1分」といった自分なりの目安を決めて練習してください。
時間を区切って解くことで、無理のないリズムをつかみやすくなるでしょう。
②間違えた問題を分析して学びに変える
間違いは成長のチャンスです。ただ解説を読むだけで終わらせず、「なぜ間違えたのか」を考える習慣を持ちましょう。
計算ミス、設問の読み落とし、理解不足など、原因を具体的に把握することで同じミスを防げます。ノートにまとめておけば、後から見返すときの復習にも役立つはずです。
こうした積み重ねで、確実な得点力の向上につなげてください。
③模試は本番環境を想定して取り組む
模試は実力を確認するだけでなく、本番の雰囲気に慣れるための絶好の機会です。静かな場所で、決められた時間内に解くことで、集中力と時間感覚のトレーニングになります。
模試を受けたあとは、結果を分析し、弱点を見つけて対策を考えることが大切です。1回ごとの模試を丁寧に活用することで、着実に本番力が身につくでしょう。
SPIの勉強に役立つおすすめコンテンツ
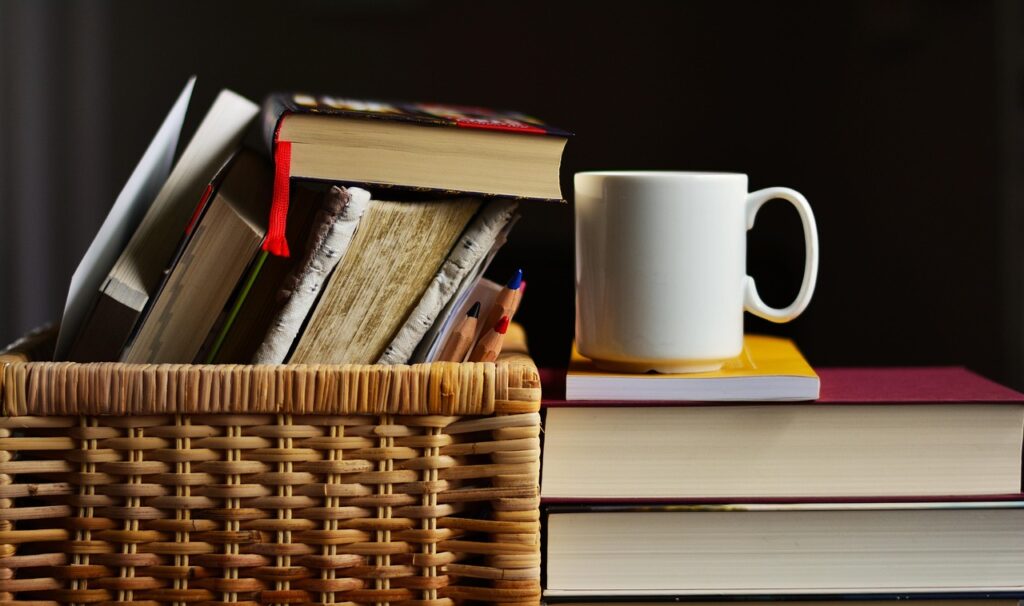
SPI対策では、自分に合った教材を選ぶことが成果につながるポイントです。勉強方法が合わないまま進めると、効果が出にくくなってしまうおそれもあります。
ここでは、書籍・アプリ・無料サイトの3つに分けて、それぞれの活用法を紹介します。
- 書籍は基礎から応用まで段階的に学べる
- アプリはスキマ時間に反復練習ができる
- 無料サイトは実践形式で模試対策ができる
①書籍は基礎から応用まで段階的に学べる
SPIの勉強では、まず市販の問題集や参考書を1冊用意するとよいでしょう。書籍の特徴は、内容が段階的に構成されているため、初学者でも安心して取り組める点にあります。
解説が丁寧なものを選べば、間違えた問題の理解もスムーズです。1冊を繰り返し使えば、知識が定着しやすくなるうえに、自分の進捗も確認しやすくなります。
取り組みやすい構成の本を選ぶことが、継続のカギとなるでしょう。
②アプリはスキマ時間に反復練習ができる
移動中や待ち時間などのスキマ時間も、SPI対策に活用できます。スマートフォン用の学習アプリを使えば、気軽に問題演習が可能です。
特に語彙や計算などの繰り返しが重要な内容は、アプリで効率的に学習できます。間違えた問題だけを復習する機能があるアプリを使えば、苦手の克服にも役立つでしょう。
時間がないと感じている方ほど、アプリ学習が効果を発揮するはずです。
③無料サイトは実践形式で模試対策ができる
SPIでは、実際の試験形式に慣れておくことも重要です。その点で、模擬試験ができる無料サイトは大きな味方になるでしょう。
制限時間つきで問題を解くことで、時間配分の感覚が自然と身につきます。
また、無料で何度も練習できるのは、コスト面でも安心です。まずは気軽に使えるサイトを試して、実践力を高めていきましょう。
合格を勝ち取るために必要なSPI勉強法とは

SPI対策を成功させるには、正しい勉強法を理解し、計画的に取り組むことが欠かせません。実際、就活の開始時期や目標に応じて、SPIの勉強法や対策の優先順位は変わってきます。
特に、言語・非言語・その他分野それぞれに合った方法で学習することが、効率よくスコアを伸ばすポイントです。また、勉強の手順や模試の活用、スキマ時間の使い方も成果を大きく左右します。
SPIの勉強法は決して1つではなく、自分に合ったスタイルを見つけて継続することが大切です。適切なタイミングで対策を始め、コツを押さえた勉強法を実践し、SPIを突破してくださいね。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










