推薦状の書き方完全ガイド|就活で役立つ例文・注意点・提出マナー
「推薦状って、どんな内容を書けばいいのかわからない……」
就活で提出を求められることもある推薦状は、基本的な流れやマナーを理解していないと、失礼になったり評価につながらなかったりする可能性があります。
そこで本記事では、推薦状の書き方や注意点、さらに提出時のマナーまでを詳しく解説します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
推薦状とは?

推薦状とは、第三者が応募者の人物像や能力を保証するために作成する文書です。
就職活動においては、大学の教授やゼミの指導教員、アルバイト先の上司などが書き手になることが多く、客観的な評価を採用担当者に伝えられる点が大きな特徴といえます。
自分でアピールするエントリーシートや履歴書と比べて、推薦状は信頼度が高いと受け取られるでしょう。そのため、推薦状の有無は選考結果に間接的に影響を与える可能性があります。
特に企業が応募者の人柄や協調性を重視している場合、推薦状は効果的な資料となるのです。
推薦状は必須の書類ではありませんが、提出することで他の学生との差別化につながるケースもあります。だからこそ、できるだけ早めに準備を整えておきましょう。
推薦状の種類

就職活動で推薦状は、自分を客観的に評価してもらえる重要な書類です。提出先によって内容や形式が異なるため、正しく理解しておくことが内定への近道となるでしょう。
ここでは代表的な推薦状の種類を取り上げ、それぞれの特徴や活用のポイントを解説します。
- 教授推薦状
- 自己推薦状
- 社員推薦状
①教授推薦状
教授推薦状は、大学の指導教員やゼミの教授が就活生の学業や研究活動、人柄を評価するものです。特に学業成績や研究実績が企業へのアピールにつながる学生にとって、大きな後押しとなります。
たとえば、学内での成績優秀者や研究活動に積極的だったことを具体的に記載してもらえると、書類選考で有利になる可能性があります。
一方で、教授との関わりが浅い場合は内容が表面的になりやすい点に注意が必要です。そのため、事前に面談を設けて自分の活動や強みを伝えておくことが欠かせません。
推薦を依頼する際は礼儀を守り、提出期限に余裕を持ってお願いしてください。こうした対応が教授との信頼関係を深めることにもつながります。
教授推薦状は努力や成果を裏付ける証明書となるため、学業や研究に自信のある学生にとっては非常に有効な手段です。
②自己推薦状
自己推薦状は、自分の言葉で強みや経験を伝える形式の推薦状です。エントリーシートや履歴書に書ききれない部分を補えるため、熱意や人柄を表現しやすいでしょう。
学業だけでなく、課外活動やアルバイト経験から培った力を強調できる点も魅力です。ただし、単なる自己PRで終わると推薦状の意味が薄れてしまいます。
客観的な事実に基づいて記述することが大切です。たとえば「アルバイトでリーダーを務め、売上を伸ばした」といった成果を示すエピソードを盛り込むと説得力が増します。
また、企業が推薦状に求めているのは「自社で活躍できるかどうか」という視点です。自分の強みを企業の求める人物像に結びつけて書くことが必要でしょう。
自己推薦状は自由度が高い分、構成力や文章力が問われます。そのため、書き上げた後に第三者へ確認してもらうと安心です。しっかり準備すれば、自分の魅力を伝える有力な武器になります。
③社員推薦状
社員推薦状は、志望先の企業に勤めるOB・OGや知人社員から推薦を受ける形式です。現場の視点から「この学生は自社に合う」と評価されるため、選考に大きな影響を与える場合があります。
特にOB・OG訪問を通じて信頼関係を築いている場合は、その関係性が推薦内容にも反映され、採用担当者に良い印象を与えるでしょう。ただし、推薦を依頼する際には注意が必要です。
唐突にお願いすると相手に負担をかけてしまい、逆効果になる恐れがあります。まずは自分の志望理由やこれまでの努力を丁寧に伝え、自然に依頼できる関係性を築いてください。
また、推薦状の内容が曖昧だと効果が薄まるため、自分の実績やアピールしたい点を事前に共有することが望ましいです。
社員推薦状は強力なアドバンテージになりますが、信頼関係と準備が伴わなければ形だけになりかねません。計画的に取り組むことで、選考を有利に進める大きな武器になるはずです。
就活で推薦状をもらうメリット

就職活動で推薦状は必須ではありませんが、提出することで他の学生との差がつきやすいです。特に企業が人柄や協調性を重視する場面では効果的に働くでしょう。
ここでは推薦状を活用する具体的な利点を整理し、選考を有利に進めるための視点を解説します。
- 推薦状があると選考通過率が高まる
- 推薦状によって早期内定が期待できる
- 教授や上司の信頼が評価に直結する
- 履歴書やエントリーシートの内容を補強できる
- 面接での回答に説得力を持たせられる
①推薦状があると選考通過率が高まる
推薦状を提出すると、書類選考を突破できる確率が上がる可能性があります。なぜなら、自分で書いたエントリーシートと違い、第三者の評価は客観性を持ち、採用担当者の判断を助けるからです。
特に教授やアルバイト先の上司からの推薦は、学業や実務の信頼性を示す強い材料になるです。
ただし、中身が薄い推薦状は逆効果になりかねません。表面的な褒め言葉ではなく、具体的なエピソードや数値を交えて書かれていることが重要です。
例えば「ゼミでリーダーを務め、チームをまとめて成果を出した」と記載があれば、採用担当者の印象に残りやすいでしょう。つまり、推薦状の価値は有無ではなく内容の質にあります。
誰に依頼するか、どのような内容を盛り込んでもらうかを考えることで、選考通過の確率を一段と高められるはずです。
②推薦状によって早期内定が期待できる
推薦状は内定獲得のスピードを速めることがあります。理由は、限られた選考期間で応募者の適性を判断する際、第三者の評価が安心材料となるからです。
特に人気のある企業や競争率が高い業界では、推薦状が差別化の要素となり、早期内定につながる場合もあるでしょう。
しかし、推薦状だけに頼るのは危険です。内容がどれほど優れていても、面接やエントリーシートの質が低ければ評価は下がります。
推薦状は補助的な位置付けにすぎません。したがって、推薦状を受け取った学生は自分の力を土台にしながら、追加の支えとして活用する意識が大切です。
そうすることで、評価を高めて早期内定の可能性を広げられるでしょう。
③教授や上司の信頼が評価に直結する
推薦状は、教授や上司の信頼が形になって伝わる文書です。大学教授やゼミの指導教員からの推薦は学業面での努力や姿勢を証明できますし、アルバイト先の上司からの推薦は実務能力や責任感を示せます。
こうした具体的な評価は、企業にとって応募者の将来性を判断する材料となるでしょう。ただし、推薦状は誰にでも気軽に依頼できるものではありません。
日頃から真面目に取り組む姿勢を見せて信頼を積み重ねていなければ、推薦者も心から推すことはできないはずです。つまり推薦状は、これまでの行動や努力が反映される結果といえます。
推薦者が安心して推薦できるよう、普段から成果を示すことが不可欠です。その結果、信頼のこもった推薦状は採用担当者に大きな安心感を与えるでしょう。
④履歴書やエントリーシートの内容を補強できる
推薦状は履歴書やエントリーシートを補強する役割を持ちます。自分の経験や強みを第三者が裏付けることで、内容に説得力が生まれるのです。
特に「文字だけでは伝えにくい」と感じる学生にとって、推薦状は有効な後押しとなるでしょう。ただし、履歴書と推薦状の内容に矛盾があると信頼を損ないます。
たとえば、推薦状で「協調性がある」と書かれているのに、履歴書には個人の成果ばかりを強調していると、一貫性に欠けると判断されるかもしれません。
こうした不一致を避けるために、推薦者と事前に自分の強調したいポイントを共有しておくことが欠かせません。また、推薦状は同じ内容を繰り返すよりも補足的な視点で書かれる方が効果的です。
履歴書の弱点を補うよう依頼できれば、応募書類全体の完成度が高まり、合格の可能性を一層引き上げられるでしょう。
⑤面接での回答に説得力を持たせられる
推薦状は面接の場でも活躍します。面接官が事前に推薦状を確認している場合、その内容に基づいて質問されることがあるからです。
その際に自分の回答が推薦状と一致していれば、話に信頼性が加わり、説得力が強まるでしょう。特に人柄や協調性に関する評価は、自分の言葉だけでは伝えきれない部分を補う効果があります。
一方で、推薦状に書かれた内容を把握していないと矛盾が生じかねません。例えば「リーダーシップがある」と記載されているのに、本人がその経験を語れなければ、評価を下げる要因となります。
そのため、推薦状を受け取ったら必ず内容を確認し、自分の言葉で説明できるよう準備しておく必要があります。推薦状を面接で生かすには、提出するだけでは不十分です。
受け答えとの一貫性を意識し、推薦者の評価と自分の言葉をつなげることで、面接官に強い印象を残せるでしょう。
推薦状を書くための下準備

推薦状は就職活動で信頼を高める大切な書類です。しかし、準備をせずに書き始めると内容が薄くなり、十分に力を発揮できません。
ここでは、推薦状を書く前に整えておきたい下準備を紹介します。計画的に進めれば、読み手に伝わる推薦状が仕上がるでしょう。
- 応募先企業の理念や求める人物像を調べる
- 自己分析で自分の強みを整理する
- 推薦状に使える具体的なエピソードを用意する
- 推薦者と被推薦者の関係性を確認する
- 推薦理由の根拠となる実績や評価を揃える
①応募先企業の理念や求める人物像を調べる
推薦状を書くうえでまず大切なのは、応募先の企業がどんな人材を求めているかを理解することです。企業理念や採用ページを調べれば、強調している人物像や働き方の特徴が見えてきます。
その情報を参考に推薦状を組み立てれば、読み手に「この学生は自社に合っている」と思ってもらいやすくなるでしょう。
たとえば「協調性を大切にする企業」であれば、仲間と協力して成果を出した経験を中心に書くと説得力が高まります。反対に調査を怠ると、せっかくの推薦状が的外れな内容になりかねません。
だからこそ、事前に企業の理念や評価基準を確認し、その軸に沿ったエピソードを選ぶ必要があります。企業に合わせた推薦状は「この学生なら安心して任せられる」という信頼を与える力を持つでしょう。
②自己分析で自分の強みを整理する
推薦状を説得力のある内容にするためには、自分自身の強みをしっかり整理しておく必要があります。
自己分析を通じて「リーダーシップ」「粘り強さ」「柔軟な発想」など、自分を表す言葉を明確にしてください。
強みが曖昧なままでは推薦者が書きにくくなり、推薦状の内容も弱いものになってしまいます。自分で整理して提示すれば、推薦者も安心して筆を進められるはずです。
例えば「挑戦心を持つ人材」を求める企業に応募するなら、研究で新しいテーマに積極的に取り組んだ経験を前面に出すと良いでしょう。
自己分析は単なる準備ではなく、推薦状全体の方向性を決める基盤です。時間をかけて丁寧に掘り下げることで、推薦状の質を一段と高められるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
③推薦状に使える具体的なエピソードを用意する
推薦状には必ず具体的なエピソードが必要です。「責任感がある」と書くだけでは弱いですが、「ゼミ発表で班をまとめ、チームを成功に導いた」といった事実が加われば印象は格段に強くなります。
数字や行動がわかるエピソードは、読み手にとって評価の根拠となり、推薦状の信頼性を支える柱になるのです。
ただしエピソードを多く盛り込みすぎると冗長になり、かえって伝わりにくくなります。1つか2つに絞り、端的に成果と役割を示すことが効果的です。
事前に準備したエピソードがあれば、推薦状は具体性を増し、読み手に「実際にこの学生は行動で示してきた」という印象を残せます。
④推薦者と被推薦者の関係性を確認する
推薦状の信頼性を支えるのは、推薦者と被推薦者の関係性です。たとえば「大学で2年間ゼミを担当した学生」「研究活動を継続的に指導した」などの記載があると、推薦の言葉に重みが出ます。
反対に関係性が不明確なままでは、本当に根拠のある評価なのか疑われることもあるでしょう。
推薦を依頼する前に、どのような関係をどのくらいの期間築いてきたのかを確認しておくことが重要です。推薦状の中で関係性が具体的に書かれていれば、評価と内容に一貫性が生まれます。
結果として、読み手に「この推薦には裏付けがある」と感じてもらえるでしょう。安心感を与えるためにも、日頃から信頼できる関係を築いておくことが前提となります。
⑤推薦理由の根拠となる実績や評価を揃える
推薦状に強い説得力を持たせるには、客観的な実績や評価を根拠として用意することが欠かせません。
「学業成績が学年上位10%」「研究成果を学会で発表した」などの情報は、読み手に具体的な裏付けを与えます。こうしたデータや成果が盛り込まれていると、推薦状の信頼度があがりやすいです。
推薦者に依頼する際は、自分の実績や評価を整理して渡しておくようにしましょう。具体的な成果を推薦者が把握できていれば、安心して文章に反映できます。
情報をしっかり整えてから依頼することで、推薦状の完成度は一段と上がり、結果として評価に直結する武器となるでしょう。
推薦状の書き方のポイント

推薦状は単なる形式的な文書ではなく、応募者の評価を左右する大切な書類です。採用担当者に信頼を持って読んでもらうためには、形式を守りつつ内容を具体的にする必要があります。
ここでは、作成時に必ず意識したいポイントを整理しました。
- 日付とタイトルを形式通りに書く
- 宛名と推薦対象者を正確に記載する
- 推薦者と被推薦者の関係性を具体的に書く
- 推薦理由や根拠を数字や成果で示す
- 結びの言葉で推薦の意思を明確にする
①日付とタイトルを形式通りに書く
推薦状を書くときは、まず形式を整えることが基本です。日付は作成日を明記し、タイトルには「推薦状」や「推薦書」といったシンプルで分かりやすい表現を使ってください。
逆に日付が抜けていたり、タイトルが曖昧だったりすると「準備不足ではないか」と受け取られる可能性があります。これは本人だけでなく、推薦者の印象にも影響するのです。
だからこそ、内容に入る前に形式を整えることが欠かせません。採用担当者は多くの書類を目にします。形式が乱れているとそれだけで悪目立ちしてしまうこともあるので注意しましょう。
基本を押さえて書き始めることで、内容にも集中して読んでもらえますよ。
②宛名と推薦対象者を正確に記載する
推薦状では宛名と対象者の記載ミスは絶対に避けるべきです。宛名は企業名や部署を正式名称で書き、対象者はフルネームで誤字なく記載しましょう。
どれほど内容が優れていても、この部分に誤りがあると信頼は失われてしまいます。特にありがちな間違いは、企業名の表記揺れや部署名の混同です。
さらに対象者の名前を略称で書いたり、字を間違えたりするのも大きなマイナスになります。推薦の正当性そのものが疑われかねません。
宛名と対象者を正しく記載することは、採用担当者への最低限の礼儀です。事前に正式名称を確認し、推薦者と対象者で情報を共有してから作成することでミスを防げるでしょう。
③推薦者と被推薦者の関係性を具体的に書く
推薦状で重要視されるのが、推薦者と被推薦者の関係性です。どの立場から推薦しているのかが明確であればあるほど、内容の信頼度は高まります。
教授なら学業面、上司なら実務や責任感といった観点から評価が期待されるでしょう。単に「ゼミの担当教員でした」と書くだけでは弱いです。
例えば「2年間ゼミを指導し、研究発表でリーダーとして班をまとめる姿を見てきました」と記載すれば、説得力が一気に高まります。採用担当者は推薦者の立場を通して応募者を理解するでしょう。
関係性を曖昧にせず、具体的な期間や状況を明示することが大切です。長期間にわたって見守ったという事実を伝えるだけでも、評価に厚みが増すでしょう。
④推薦理由や根拠を数字や成果で示す
推薦理由は、抽象的な評価ではなく、数字や成果を交えて説明すると説得力が大きく増します。
例えば「アルバイトで売上を前年比120%に伸ばした」「ゼミ研究で学会発表を経験した」といった具体例が有効です。根拠が曖昧だと「本当に評価できるのか」と疑問を持たれる恐れがあります。
逆に実績や数値が明示されていれば、採用担当者にとって信頼度の高い情報となるでしょう。さらに、推薦者自身が実際に見聞きしたエピソードを添えると効果的です。
推薦者の目を通じた具体的な経験が含まれることで、内容に厚みと現実味が加わります。こうした工夫が推薦状全体の質を高めるのです。
⑤結びの言葉で推薦の意思を明確にする
推薦状の最後は、推薦の意思をはっきりと伝える結びの言葉が必要です。「自信を持って推薦いたします」「貴社にとって有益な人材と確信しております」といった力強い表現を使うと効果が増します。
逆に曖昧な言葉で締めてしまうと、形式的に書かれた印象を与えかねません。どれほど理由を丁寧に書いても、最後の一文に力がなければ印象は弱くなってしまいます。
結びで推薦の強い意思を示すことによって、採用担当者に「信頼できる人物を紹介している」という安心感を与えられるでしょう。
推薦状の締めくくりは全体の評価を左右する部分ですので、ためらわずに明確に書くことが大切です。
推薦状の例文
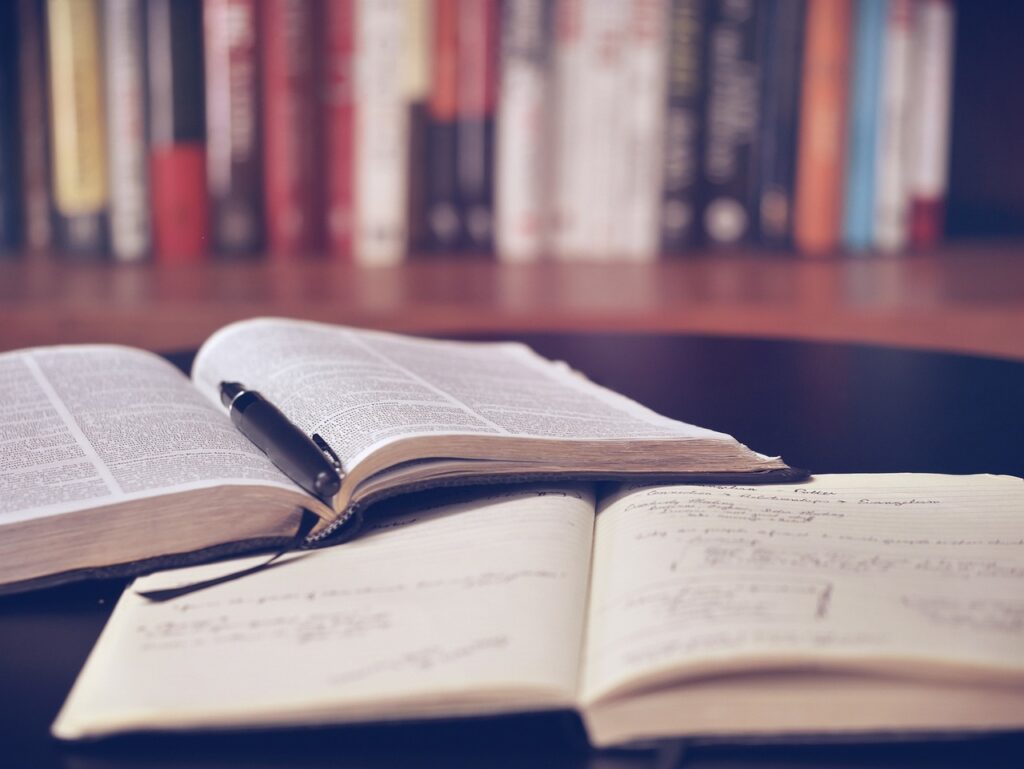
推薦状を書こうと思っても、どのように表現すれば良いのか迷う方は多いでしょう。
ここでは就活やインターンなど状況に応じた具体的な例文を紹介します。自分の立場や目的に合った書き方を参考にできるはずです。
- 就職活動に使う推薦状の例文
- インターンシップ応募用の推薦状の例文
- 学外活動やボランティア経験を評価する推薦状の例文
- 資格取得や研究活動を評価する推薦状の例文
- 内定後に提出する推薦状の例文
- 友人や知人を推薦する例文
①就職活動に使う推薦状の例文
ここでは、大学生活での経験をもとに就職活動で活用できる推薦状の例文を紹介します。日常的な活動や役割を具体的に示すことで、読み手に伝わりやすくなるでしょう。
| 私は〇〇さんを推薦いたします。〇〇さんは大学のゼミ活動において、常に前向きな姿勢で課題に取り組んでいました。 特にグループ研究の際にはリーダー役を務め、メンバーの意見を丁寧に聞きながら議論をまとめ、発表を成功に導いた実績があります。 その過程では協調性だけでなく責任感も発揮し、全員が納得する形で成果を出しました。またアルバイトでも接客を通して多くの人と関わり、柔軟に対応する力を身につけています。 こうした経験から、〇〇さんは貴社においても周囲と協力しながら成果を出せる人材であると確信しております。以上の理由により、私は自信をもって〇〇さんを推薦いたします。 |
この例文ではゼミ活動やアルバイトといった身近な経験をもとに具体的に評価をしています。自分で書く場合も、成果や役割を数字や事実で示すと信頼性が高まるでしょう。
②インターンシップ応募用の推薦状の例文
ここでは、大学生活での学びや課外活動を通じて成長した姿を伝える、インターンシップ応募向けの推薦状の例文を紹介します。
取り組みの過程や姿勢を強調することで評価につながりやすくなるでしょう。
| 私は〇〇さんを推薦いたします。〇〇さんは大学の授業や課外活動において、常に主体的に行動し周囲を引っ張ってきました。 特にゼミ活動では調査の中心を担い、難しいテーマに挑みながらも粘り強く調べ、最終発表を成功させた実績があります。 その過程で、仲間の意見を尊重しつつ自分の考えを的確に伝える姿勢が光っていました。 また、学園祭の運営に参加した際にはリーダー役を務め、限られた時間で計画を進め、協力者との信頼を築き上げた経験もあります。 これらの経験から、〇〇さんは御社のインターンシップでも責任を持って取り組み、周囲と協力しながら成果を生み出せる人材であると確信しているのです。自信をもって推薦いたします。 |
この例文ではゼミや学園祭といった身近な経験を組み合わせてアピールしています。インターン応募用では姿勢や協調性を強調するとより効果的です。
③学外活動やボランティア経験を評価する推薦状の例文
ここでは、学外活動やボランティア経験を通じて得た成長を伝える推薦状の例文を紹介します。
社会性や主体性を示すことで、企業の印象に残りやすいでしょう。
| 私は〇〇さんを推薦いたします。〇〇さんは大学在学中、地域の清掃活動や子ども向け学習支援ボランティアに積極的に参加してきました。 特に学習支援では、子ども一人ひとりの理解度に合わせて教え方を工夫し、信頼関係を築きながら学習意欲を引き出す姿勢が見られました。 また、地域清掃活動では仲間をまとめる役割を担い、定期的な参加を呼びかけることで活動の継続に大きく貢献したのです。 これらの経験を通して培った協調性や責任感は、社会で働くうえで大いに役立つと考えます。〇〇さんはどのような環境でも前向きに行動し成果を出せる人材であると確信しております。 以上の理由から、私は〇〇さんを自信を持って推薦いたします。 |
この例文では地域活動やボランティアの経験を具体的に記載し、社会性を強調しています。自分で書く際も、役割や成果を具体化すると説得力が高まるでしょう。
④資格取得や研究活動を評価する推薦状の例文
ここでは、資格取得や研究活動を通じて得た成果を評価する推薦状の例文を紹介します。
努力の積み重ねや探求心を示すことで、学習意欲や専門性の高さを伝えることができるでしょう。
| 私は〇〇さんを推薦いたします。〇〇さんは大学在学中に複数の資格を取得し、その過程で計画性と継続力を身につけてきました。 特にTOEICのスコア向上に向けて日々学習を重ね、短期間で目標を達成した姿勢は非常に印象的です。 また、ゼミでの研究活動においては独自の視点から課題を見つけ出し、資料を丁寧に分析しながら議論を深めることで周囲をリードしていました。 学会発表の際には冷静に質問へ対応し、研究内容を的確に伝える力を示したのです。こうした経験は、どのような環境でも粘り強く取り組み成果を出す力につながっています。 〇〇さんは専門性と実行力を兼ね備えた人材であり、強く推薦いたします。 |
この例文では資格取得と研究活動を結びつけて評価し、学習意欲と実行力を強調しています。同じテーマを書く際は成果を数字や具体的行動で示すことが効果的です。
⑤内定後に提出する推薦状の例文
ここでは、就職先が決まった後に提出する推薦状の例文を紹介します。内定後の推薦状は学生の人物像を補強し、安心して迎え入れてもらうために重要な役割を果たすのです。
| 私は〇〇さんを推薦いたします。〇〇さんは大学生活を通じて学業と課外活動を両立させ、常に前向きな姿勢で努力を続けてきました。 ゼミ活動では仲間と協力しながら研究を進め、成果をまとめ上げるリーダーシップを発揮。また、アルバイト経験では接客の場で顧客対応を学び、柔軟に対応する力と粘り強さを身につけました。 さらに、学内イベントでは企画から運営まで積極的に関わり、周囲を動かす行動力も示しています。これらの経験を通じて培った協調性と責任感は、社会人として働くうえで必ず活かせるでしょう。 〇〇さんが新しい環境でも力を発揮し、貴社に貢献できる人材であると確信しております。 |
この例文では内定後に安心感を与える内容を中心にまとめています。自分で書く際も、成果だけでなく人物としての信頼性を強調すると効果的です。
⑥友人や知人を推薦する例文
ここでは、友人や知人の人柄や努力を伝える推薦状の例文を紹介します。日常での関わりや行動を具体的に書くことで、信頼できる人物像を伝えやすくなります。
| 私は〇〇さんを推薦いたします。〇〇さんとは大学入学以来、勉学やサークル活動を通じて長く共に過ごしてきました。 特にゼミでは、常に責任感を持って課題に取り組み、仲間を支えながら発表の準備を進める姿が印象的です。 サークル活動でも、イベントの企画を中心となってまとめ上げ、参加者全員が楽しめる場を作り上げる努力を惜しまない姿勢を見せていました。 さらに日常生活においても、困っている人がいれば進んで声をかけ、誠実な対応を心がける人柄を持っています。 これらの経験を通じ、〇〇さんは協調性と行動力を兼ね備えた信頼できる人物です。私は自信を持って〇〇さんを推薦いたします。 |
この例文では学業とサークル活動の両面から人物像を描いています。友人を推薦する際は、身近なエピソードを簡潔にまとめることが効果的です。
推薦状を書くときの注意点

推薦状は就職活動で信頼性を高める重要な書類ですが、内容や表現を誤ると逆効果になる場合があります。
ここでは推薦状を書く際に押さえておきたい注意点をまとめました。細部まで丁寧に意識すれば、安心して読んでもらえる説得力のある文章に仕上げられるでしょう。
- 事実と異なる内容は絶対に書かない
- 実績や評価は具体的に表現する
- 内容は論理的で一貫性を持たせる
- 正しい敬語と日本語を使う
- 誤字脱字や体裁の不備をなくす
①事実と異なる内容は絶対に書かない
推薦状で最も避けるべきは、事実に反する記述です。虚偽の情報はすぐに見抜かれ、学生本人だけでなく推薦者の信頼まで失う恐れがあります。
例えば、実際には経験していない役職を強調したり、成果を誇張したりすると、面接で矛盾が生じてしまうのです。
採用担当者は履歴書や面接での発言と照らし合わせて確認するため、不自然な内容は必ず疑われるでしょう。だからこそ、等身大の強みを正しく伝えることが重要です。
誠実さを持って事実を記載した方が、結果的に「信頼できる人物」と評価される可能性が高くなります。
②実績や評価は具体的に表現する
推薦状を説得力のある内容にするには、抽象的な表現ではなく、具体的な実績や成果を示すことが必要です。「責任感がある」「努力家である」といった言葉だけでは印象が弱く、評価が伝わりません。
その代わりに「研究発表で最優秀賞を受賞した」「アルバイトで売上を前年比120%に伸ばした」など、事実を数字や結果で示すと説得力が増します。
推薦状は性格紹介の文ではなく、応募者の能力や努力を客観的に伝えるものです。具体的な成果を盛り込むことで、応募者の人物像がより鮮明に浮かび上がり、読み手の印象に残りやすいでしょう。
③内容は論理的で一貫性を持たせる
推薦状は一つの文章として論理的に構成することが求められます。冒頭で被推薦者の人物像を示し、中盤でエピソードや実績を加え、最後に推薦の意思を明確にすると、読みやすい流れになるでしょう。
順序が前後していたり、強調点が散漫だったりすると、採用担当者は混乱してしまいます。その結果「本当に理解して書かれているのか」と疑念を抱かれることもあるのです。
論理的に整った文章は、誠実さや信頼性を裏付ける効果があります。内容をまとめる際は「誰に」「何を」「なぜ推薦するのか」が一貫して伝わるかを常に意識してください。
④正しい敬語と日本語を使う
推薦状は公式な文書ですから、正しい敬語や日本語を使うことが欠かせません。「させていただく」の過剰使用や二重敬語など、不自然な表現は避けましょう。
文章全体は「です・ます調」で統一し、同じ語尾が続かないように工夫すると読みやすくなります。企業は推薦状を通じて、推薦者の人柄や配慮の姿勢も見ています。
言葉遣いに誤りがあると、それだけで信頼性を損なう恐れがあるのです。正しい日本語を心掛けることは、推薦状全体の完成度を高め、読み手に安心感を与える基本といえるでしょう。
⑤誤字脱字や体裁の不備をなくす
どれだけ内容が充実していても、誤字脱字や体裁の乱れがあると信頼性が低下します。細部への注意が欠けていると判断され、応募者にも悪影響が及ぶ可能性があります。
提出前には必ず数回読み直し、できれば第三者に確認を依頼してください。さらに、段落の分け方や余白の取り方を意識するだけで、見やすさが格段に向上します。
文章の中身だけでなく、形式面に注意を払うことは「丁寧に準備した」という印象を与える効果があります。体裁まで整えられた推薦状は、安心して読んでもらえる文書になるでしょう。
推薦状の提出方法

推薦状は書き方と同じくらい、提出の仕方も大切です。方法を間違えると内容が正しく評価されないことがあります。
ここでは代表的な提出方法と注意点を紹介し、安心して活用できるよう整理しました。
- 手渡し
- 郵送
- メール
①手渡し
手渡しはもっとも確実な方法です。面接や説明会などで担当者に直接渡せば、確実に届きます。特に大学推薦や教授を通した提出では、信頼性を高める手段になるでしょう。
ただし、渡すタイミングや方法を誤ると印象が悪くなります。面接の冒頭で慌てて出すと準備不足に見えるため、提出は受付時や終了時など落ち着いた場面を選んでください。
また、封筒に入れて封をした状態で渡すことが基本です。折りたたんだまま持参すると印象を下げます。渡す際に「こちら推薦状になります」と一言添えるだけで、丁寧さが伝わるでしょう。
②郵送
郵送は遠方の企業や事前提出が必要な場合に使われます。ただ、封筒の記載や方法を誤ると信頼を損ねる恐れがあります。宛名や住所を正確に書き、簡易書留や速達で送ると安心です。
推薦状だけを送るのは避け、送付状を添えてください。表には赤字で「推薦状在中」と記載すると、採用担当者が重要書類として扱いやすくなります。
さらに、発送後は到着日を確認することも大切です。企業によっては提出期限が厳格に決められている場合があるため、余裕を持って投函しておきましょう。
③メール
メール提出は近年増えている方法です。オンライン選考を行う企業では、PDFファイルでの提出を求められることが多いでしょう。すぐに届く点は大きな利点です。
注意点として、ファイル形式はPDFに統一してください。Wordや画像のまま送ると開けない場合があります。ファイル名は「推薦状_氏名.pdf」のように分かりやすく整えると良いでしょう。
本文には簡潔に挨拶と推薦状を添付した旨を書き、件名には「推薦状提出の件」と明記してください。送信後は必ず履歴を確認し、誤送信がないかをチェックしておくことが欠かせません。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
推薦状作成の最終的な考え方

推薦状は就職活動で信頼性を高める強力な書類です。種類やメリットを理解し、下準備を整えたうえで正しい書き方を実践すれば、選考の通過率や早期内定の可能性を高められるでしょう。
特に教授や上司の信頼を裏付ける記述や、数字を伴う成果を盛り込むことは説得力を増す重要な要素です。一方で、事実と異なる内容や誤字脱字は信用を損なう大きな落とし穴となります。
適切な形式を守り、エピソードや実績を正しく示した推薦状は、履歴書や面接内容を補強し、企業に好印象を与える結果につながるのです。
就活生にとって、推薦状の書き方を正しく理解して準備することは、内定を得るための有効な一歩といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














