国家公務員専門職とは?向いている人の特徴と適職判断の軸
「国家公務員専門職って、総合職や一般職とはどう違うんだろう…」と疑問に思っている人も少なくないはずです。
法律や経済、国際関係など、各々の専門性を活かして国家の重要な分野を支えるのが専門職の大きな役割です。安定性だけでなく、専門知識を社会のために役立てられる点にやりがいを感じる人も多いでしょう。
ただし、職種ごとに求められるスキルや働き方が異なるため、自分に向いているかどうかを見極めることが大切です。
本記事では、国家公務員専門職の特徴や種類、適職判断の軸について分かりやすく整理しています。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
国家公務員の3つの職種

国家公務員とは、国の行政機関に所属し、法律や制度の執行、政策の企画や実務を担う職員のことです。国の仕組みを支える役割を持ち、その働きは国民生活の基盤になっています。
国家公務員は大きく3つの職種に分かれ、それぞれ役割や求められる能力が異なります。ここでは国家総合職・一般職・専門職の特徴を整理して解説します。
- 国家総合職
- 国家一般職
- 国家専門職
① 国家総合職
国家総合職は、国家公務員の中でも政策立案に関わる中心的な役割を担います。各省庁に所属し、国の方向性を決める政策を企画・調整することが主な仕事です。
高度な知識だけでなく、論理的思考力や分析力、さらにチームを導くリーダーシップも必要とされます。
学生の多くは「自分に務まるのか」と不安に感じるかもしれませんが、採用後は研修や現場経験を通じて成長できる環境が整っています。
若手のうちから重要な案件を任されることもあり、責任の大きさと同時に大きなやりがいを得られるでしょう。幅広い分野を横断しながら国の課題に取り組みたい人に適した職種です。
② 国家一般職
国家一般職は、省庁や出先機関で実務を担い、政策を現場に反映させる役割があります。
具体的には行政文書の作成や各種手続きの管理、調査業務などを行い、国民生活を下支えしています。総合職ほどの政策立案力は必要とされませんが、正確に業務を進める力や協調性が重視されます。
就活生の中には「地味な仕事ではないか」と心配する人もいるでしょう。しかし、国の制度を動かす基盤を守る大切な役割です。
キャリア面では転勤が比較的少なく、安定した生活を送りやすいことも特徴です。専門性より幅広い事務業務に関わりたい人や、安定した働き方を求める人に合う職種でしょう。
③ 国家専門職
国家専門職は、税務・労働・外交・司法などの特定分野に特化して働く職種です。採用時点から専門分野に配属され、長期的にその領域でキャリアを積むことになります。
たとえば国税専門官は税務調査、労働基準監督官は労働環境の改善、外務省専門職員は外交交渉の支援といった業務に従事します。
就活生が見落としやすいのは、勤務地が全国に及ぶ可能性や試験制度が職種ごとに異なる点です。しかし、その分専門スキルを伸ばしやすく、社会に直接貢献している実感を得られる職種でもあります。
特定の分野に強い関心や適性を持ち、自分の力を深めたい人に適したキャリアだと言えるでしょう。
適職診断であなたにぴったりな職種を見つけよう!
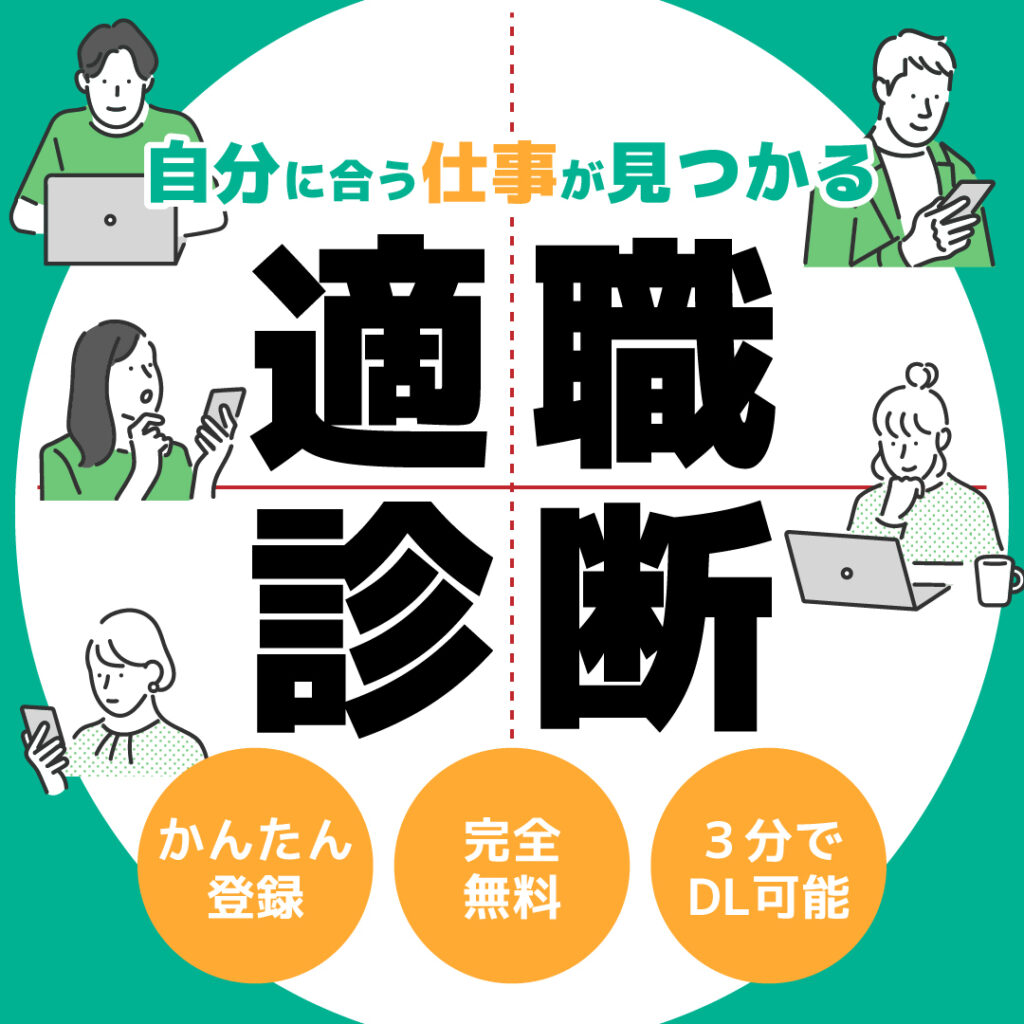
「なんとなく就活してるけど、自分に合う仕事が分からない…」
「選考に応募はしているけど、しっくりこない…」
そんな人にぴったりなのが、就活マガジンが用意している、LINEでできる適職診断です!1
0個の質問にスマホで答えるだけで、あなたの性格や価値観、向いている業界・職種が明確になります。
診断系のツールはパソコンで時間も取られる印象があると思いますが、すべてLINE上で完結するので、移動中やスキマ時間にもサクッと診断ができますよ!
就活に少しでも不安がある人は、まずは気軽に診断してみてください。
国家公務員専門職とは?

国家公務員専門職は、国家公務員の中でも特定の分野に特化して働く職種です。総合職や一般職と違い、専門知識を生かしながら長期的にキャリアを築けるのが特徴でしょう。
ここでは専門職の位置づけや他職種との違い、そして担う役割について解説します。
- 位置づけ
- 他職種との違い
- 担う役割
① 位置づけ
国家公務員専門職は、総合職・一般職と並ぶ3つの大きな職種の1つであり、特定の分野に精通した人材として採用されます。
総合職が政策立案、一般職が幅広い事務を担うのに対し、専門職は法律・税務・外交・労働など特化した業務を中心に行います。
「専門知識がなければ難しいのでは」と不安に思う学生も多いですが、採用後の研修や実務経験を通じて力をつけられるので心配はいりません。
専門職の位置づけを理解することは、自分の進路を考えるうえで重要です。国民生活を支える分野で責任を果たすため、社会的意義の大きな職種だと言えるでしょう。
② 他職種との違い
国家総合職は国全体の政策を立案し、国家一般職は各省庁や出先機関で多様な事務を担当します。これに対して専門職は、採用段階から分野が決まり、その領域に長く携わる点が大きな違いです。
例えば国税専門官は税務調査、労働基準監督官は職場環境の改善、外務省専門職員は外交交渉の補佐など、仕事内容が明確です。
この違いを理解しないまま志望すると、入職後に「想像していた内容と違う」と感じてしまうこともあるでしょう。
受験前に各職種の特徴を比較し、自分の希望や適性と合っているかを確認しておくことが大切です。
③ 担う役割
国家公務員専門職は、国民生活に直結する重要な分野で専門的な業務を遂行します。
税制の公平性を守る、労働者の安全を確保する、国際社会で日本の立場を支えるなど、社会に大きな影響を与える役割を担います。
単なる事務処理ではなく、法律や制度を正しく運用し国民の利益を守ることが求められます。就活生が意識すべきなのは、知識に加えて現場での対応力や冷静な判断力も重要だという点です。
実務を通じて役割を果たしながら専門性を深めることで、大きなやりがいを感じられるでしょう。使命感を持って挑戦することで、社会に貢献するやりがいのあるキャリアを築けます。
国家公務員専門職の働き方

国家公務員専門職は、総合職や一般職とは異なり、特定分野に特化して長期的に実務を担う職種です。
ここでは勤務地、給与水準、研修制度、キャリア形成の4つの観点から働き方を整理します。進路選びで見落としやすい点も多いため、事前に理解しておくことが重要でしょう。
- 勤務地
- 年収・給与水準
- 研修制度
- キャリア形成
① 勤務地
国家公務員専門職の勤務地は職種によって大きく異なります。国税専門官や労働基準監督官は全国の税務署や労働基準監督署に配属され、外務省専門職員は海外勤務の可能性もあります。
勤務地が幅広いため「どこに配属されるのか不安」と思う人もいるでしょう。ただし多くの場合、本人の希望や適性を考慮して決定されるため心配しすぎる必要はありません。
むしろさまざまな地域で経験を積める点は強みになります。勤務地の特徴を理解しておくことで、自分の生活スタイルや将来の計画と相性が合うかどうか判断しやすくなるでしょう。
② 年収・給与水準
専門職の給与は職種ごとに定められた給与表に基づいています。大卒の初任給は20万円前後で、勤続に応じて安定的に昇給し、モデルケースでは年収400万〜600万円ほどです。
総合職と比べると給与水準はやや低めですが、一般職よりは高いか同等であり、専門性に応じた手当が付くこともあります。
「給与が低いのでは」と心配する学生もいますが、昇給制度や福利厚生が整っているため安心です。
総合職は昇進が早く将来の給与が高くなる傾向がある一方、専門職は安定と専門性を両立できる点が魅力でしょう。
③ 研修制度
国家公務員専門職は研修制度が充実しています。採用直後は基礎を学ぶ初任者研修があり、その後も実務に即した専門研修や階層別研修が続きます。
「知識が足りないのでは」と不安に思う学生も少なくありませんが、こうした制度により着実に力を伸ばせます。
研修は一度で終わらず、キャリアの節目ごとに実施されるため、継続的にスキルを高められるのも特徴です。
また、同期や先輩との人脈を築ける機会にもなるため、学びと人間関係の両面で成長できるでしょう。安心して専門職の道を選べる理由の一つです。
④ キャリア形成
専門職は採用時から特定分野に配属され、その領域で長期的にキャリアを積みます。国税専門官なら調査官から管理職へ、外務省専門職員なら在外勤務を経て専門性を磨くといった形です。
「昇進の道は限られるのでは」と考える人もいますが、専門職独自の昇任ルートが整備されており、努力次第で管理職や専門分野の責任者を目指せます。
また、専門知識を活かし他の機関や国際的な場で活躍する道も開かれています。自分がどの分野で貢献したいのかを考え、その軸に沿ってキャリアを積み重ねることが大切でしょう。
安定と成長の両方を実現できる職種です。
国家公務員専門職の主な種類一覧

国家公務員専門職には多くの職種があり、それぞれが国の運営を支える重要な役割を担っています。
ここでは国家公務員の代表的な職種を取り上げて解説します。仕事内容や求められるスキルは大きく異なるため、自分の適性や興味に合わせて理解を深めることが必要でしょう。
- 国税専門官
- 財務専門官
- 労働基準監督官
- 裁判所事務官
- 法務教官
- 皇宮護衛官
- 外務省専門職員
- 食品衛生監視員
- 航空管制官
- 海上保安官
① 国税専門官
国税専門官は、税務署に勤務し、税務調査や納税指導を行います。国の財政を支える立場であるため、法律知識と分析力が求められるでしょう。
仕事の中心は税務調査で、正しい申告がなされているか確認し、不正があれば是正を指導します。
「数字が苦手」と感じる人には難しいかもしれませんが、研修が充実しているため安心してスキルを習得できます。
税務の知識は民間企業でも通用するため、将来のキャリア形成にも役立つのが特徴です。安定と専門性の両立が魅力といえるでしょう。
② 財務専門官
財務専門官は財務局や財務事務所で国の予算執行や金融監督に携わります。特に地域経済の健全性を保つために、中小企業への資金供給や金融機関の管理を担うことが多いです。
経済や金融に興味のある人に向いており、大学で経済学を学んだ人は知識を生かせるでしょう。
仕事内容が専門的で幅広いため、就活生の中には「自分に務まるのか」と不安を感じる人もいますが、段階的な研修やOJTによって成長を支えられる環境が整っています。
地域社会に根ざした公共サービスに関心のある人におすすめです。
③ 労働基準監督官
労働基準監督官は、労働基準法を守らせるために企業の労働環境を調査します。長時間労働や未払い賃金といった問題に取り組み、労働者の安全と健康を守る重要な役割です。
現場では強い指導を行うこともあり、法律知識と同時に調整力が必要でしょう。就活生の中には「対立が多く大変そう」と感じる人もいますが、その分社会的な使命感を強く感じられる仕事です。
働く人を守るやりがいを得たい人や、人々の生活に直結する分野で活躍したい人に向いています。
④ 裁判所事務官
裁判所事務官は裁判所で事務を担当し、裁判官や書記官を支えます。具体的には裁判資料の作成、事件記録の管理、訴訟関係者への対応などを行います。
法律を直接扱うため、法学部出身の学生には特に人気のある職種です。一見事務作業が中心と思われがちですが、裁判の円滑な進行を左右する責任の大きい仕事でもあります。
法律知識を深めつつ、公共の場で正義を支える役割を果たしたい人に向いているでしょう。
⑤ 法務教官
法務教官は少年院や刑務所で、非行や犯罪をした人の更生を支援する専門職です。教育的アプローチを通じて、社会復帰を助ける役割を担います。心理学や教育学の知識がある人は特に活かせるでしょう。
時には厳しい現場に直面することもありますが、人の成長を間近で支えられる点に大きなやりがいがあります。「人の役に立ちたい」という思いを強く持つ学生に適した仕事です。
⑥ 皇宮護衛官
皇宮護衛官は、皇室や宮殿の警備を行う特別な警察官です。天皇や皇族を守るという非常に重要で特殊な任務を担います。強い責任感と冷静な判断力が不可欠であり、体力も求められます。
仕事内容は一般的な公務員像とは異なり、「特殊な仕事に携わりたい」と考える人には大きな魅力となるでしょう。任務の性質上、厳しい訓練や規律もありますが、他にはない誇りを持って働けます。
⑦ 外務省専門職員
外務省専門職員は、外交業務を専門に担い、通訳や国際交渉の補佐などを行います。高い語学力が必須で、海外勤務も多く国際的に活躍できるのが特徴です。
「語学を生かして国際舞台で働きたい」と思う学生には理想的な職種でしょう。ただし語学力以外にも国際情勢への理解や柔軟な対応力が必要であり、ハードルが高いと感じる人も少なくありません。
それでも挑戦する価値のある魅力的な職種です。
⑧ 食品衛生監視員
食品衛生監視員は、輸入食品の検査や食品衛生に関する監督を行います。国民の健康を守る役割があり、理系分野の知識が特に活かせます。
食品検査や衛生管理は専門性が高いため、食品科学や生物学を学んだ人には向いているでしょう。食の安全を守る責任は重いですが、その分やりがいも大きいです。
生活に直結する分野で社会に貢献できる職種です。
⑨ 航空管制官
航空管制官は、飛行機の安全な離着陸や航行を指示する職種です。正確な判断と冷静さが求められ、緊張感の高い仕事ですが、多くの人命を支える重要な役割を果たします。
英語力や高度な集中力が必要で、「ミスが許されない」という点からも強い覚悟が必要です。厳しい条件をクリアした先には、大きな達成感と専門職ならではの誇りを得られるでしょう。
⑩ 海上保安官
海上保安官は、日本の海の安全を守る役割を担います。巡視船や航空機を用いて救難活動や密輸防止、海洋環境保全など多岐にわたる業務に従事します。
体力と精神力が不可欠であり、「海を守る仕事がしたい」と考える人には最適でしょう。危険な場面に直面することもありますが、その分だけ使命感を強く感じられる職種です。
国際的な協力の場に出ることもあり、グローバルな視点での活躍も可能です。
国家公務員専門職に向いている人の特徴

国家公務員専門職は幅広い職種があり、求められる人物像も多様です。しかし共通して重要なのは、職務への適性や性格的な強みです。
ここでは特に代表的な特徴を取り上げ、自分に合うかどうかを判断する助けになるポイントを解説します。
- 専門分野を突き詰められる人
- 責任感を持って行動できる人
- 安定した環境で長期的に働きたい人
- 冷静な判断力を持つ人
- 法令やルールを厳格に守れる人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
① 専門分野を突き詰められる人
国家公務員専門職は、特定の分野に特化して知識やスキルを活かす仕事です。国税専門官であれば税務、外務省専門職員なら語学や国際関係といったように、分野ごとに専門性が求められます。
表面的な知識ではなく、継続的に深掘りして学び続ける姿勢が不可欠です。就活生の中には「自分にそこまでの専門性があるか不安」と感じる人もいるでしょう。
しかし入省後は体系的な研修が整っており、現場で経験を積むことで知識を補えます。つまり大切なのは、最初から知識を完璧に備えることよりも、学び続ける姿勢を持てるかどうかです。
この点に共感できる人は専門職としての適性が高いといえるでしょう。
② 責任感を持って行動できる人
国家公務員専門職は、国民生活や社会の仕組みに直結する業務を担います。たとえば労働基準監督官は労働者の安全を守り、食品衛生監視員は国民の健康を支えます。
そのため一つの判断が大きな影響を及ぼす場合も少なくありません。プレッシャーを感じる人もいますが、裏を返せば責任を果たすことで強いやりがいを感じられる仕事です。
研修やマニュアルによる支援体制が整っているため、初めての段階でも無理なく職務を遂行できます。
責任を重荷と捉えるのではなく、「社会のために果たす役割」と前向きに考えられる人に向いているといえるでしょう。
③ 安定した環境で長期的に働きたい人
国家公務員専門職は、長期的に安定して働ける点も魅力のひとつです。給与や福利厚生が整っており、キャリア形成も制度的に支えられています。
就活生の中には「仕事が単調で飽きるのでは」と懸念する人もいますが、実際には配属先や業務内容の幅が広く、経験できる領域も多様です。さ
らに昇進や異動を通じてキャリアのステップアップが可能であり、安定性と成長の両方を実現できます。民間企業と比べても雇用が保証されているため、景気変動に左右されにくいのも強みです。
将来にわたり腰を据えて働きたい人にとって、専門職は理想的な選択肢といえるでしょう。
④ 冷静な判断力を持つ人
航空管制官や海上保安官のように、瞬時の判断が人命に関わる職種もあります。感情に流されず冷静に状況を把握し、最適な行動を選べる力が重要です。
緊張感のある職場は不安に感じる人もいますが、研修やシミュレーションを通じて判断力を養える仕組みが整っています。つまり最初から完璧な判断力を持つ必要はなく、成長の過程で力を磨けるのです。
冷静さは専門職全般に共通して求められる素養であり、地道に訓練を重ねられる人は適性が高いといえます。
自分の性格と照らし合わせ、落ち着いて物事を考えるのが得意な人には大きな強みになるでしょう。
⑤ 法令やルールを厳格に守れる人
国家公務員専門職は、法律や規則に基づいて職務を遂行することが基本です。国税専門官の調査や労働基準監督官の指導などは、すべて法令に裏打ちされた行為であり、恣意的な判断は許されません。
ルールを守ることが苦手な人にとっては厳しさを感じる場面もありますが、逆に「明確な基準があるからこそ迷わず動ける」と安心する人も多いです。
公正さと透明性を保つことが社会的信頼につながるため、ルールを遵守できる姿勢が大きな評価対象になります。規律を重んじ、筋道を立てて行動できる人は専門職として長く活躍できるでしょう。
国家公務員専門職の適職判断のポイント

国家公務員専門職を志望する際には、自分の性格や希望と照らし合わせて適性を見極めることが大切です。仕事内容や勤務地、求められるスキルの観点から整理しておくと、後悔のない選択につながります。
ここでは、国家公務員としての就職先を探す際、ポイントとなる観点について詳しく解説していきます。
- 仕事内容やキャリアパス
- 勤務地や働き方
- 求められるスキル
① 仕事内容やキャリアパス
国家公務員専門職は、特定分野の専門性を活かして職務を遂行するため、業務の幅は狭いものの深い知識と継続的な成長が求められます。
国税専門官なら税務調査、労働基準監督官なら労働環境の改善といったように、担当領域が明確である点が特徴です。
このため、自分がその分野に長く関わり続けたいと思えるかどうかが重要な判断軸になります。
就活生の中には「専門に縛られてキャリアが狭まるのでは」と不安に感じる人もいますが、実際には異動や研修で新しい業務に挑戦できる制度もあります。
つまりキャリアは一方向に固定されるわけではなく、自分の努力次第で広がりを持たせられるのです。こうした特徴を理解すれば、専門職での働き方をより前向きに考えられるでしょう。
② 勤務地や働き方
国家公務員専門職を選ぶうえで、勤務地や働き方は大きな判断材料となります。なぜなら、勤務地は全国規模で配属される可能性があり、さらに勤務時間も一律ではないからです。
例えば、国税専門官や食品衛生監視員は基本的に日中勤務中心ですが、繁忙期や緊急時には残業や休日出勤が求められることがあります。
一方、航空管制官や海上保安官、皇宮護衛官のように治安や安全を守る職種では、24時間体制のシフト勤務や夜勤が必要となり、体力面での適性も問われるでしょう。
また、外務省専門職員は海外勤務が中心であり、時差や異文化に合わせた働き方が求められる点が特徴です。
このように専門職は勤務地だけでなく勤務形態に大きな違いがあるため、勤務地の幅広さやシフト勤務の有無を理解し、自分がどのような働き方を望むのかをしっかり見極めることが大切です。
③ 求められるスキル
国家公務員専門職には、それぞれの職種に応じた専門スキルが求められます。語学力や法律知識、分析力など必要とされるスキルは多岐にわたり、就活生の不安要素になりがちです。
しかし最初から完璧に備えている必要はなく、入省後の研修や実務経験を通じて育成される仕組みが整っています。重要なのは「学び続ける姿勢」と「柔軟に吸収する力」です。
また、専門スキルだけでなく対人コミュニケーション能力や冷静な判断力など、共通して必要とされる力もあります。
自分の得意分野を伸ばしつつ不足を補う姿勢を持つことで、専門職での活躍が可能になります。
したがってスキルの有無を不安視するよりも、成長意欲があるかどうかを適職判断の基準にすることが有効です。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
国家公務員を志望する前に確認すべき注意点

国家公務員専門職を目指す際には、試験内容や仕事内容だけでなく、受験資格や倍率といった基本的な条件を理解しておくことが大切です。
知らないまま準備を進めると、受験できなかったり競争の厳しさに戸惑ったりする可能性があります。ここでは志望前に確認しておきたい3つの注意点を紹介します。
- 年齢制限や学歴制限の有無
- 併願の可否
- 倍率の高さ
① 年齢制限や学歴制限の有無
国家公務員専門職試験には、年齢や学歴の条件が設けられています。多くは大学卒業程度を対象としており、年齢は20代半ばまでが一般的です。
特に警察官や海上保安官、航空管制官など体力や判断力を重視する職種では、年齢上限がより厳格に決められています。
こうした条件を知らないまま勉強を始めると、受験資格がないと後から気づくことになりかねません。
受験案内を早めに確認し、自分の年齢や学歴が条件に合っているかをチェックしてから学習を始めると安心でしょう。
② 併願の可否
公務員試験は同時に複数の職種を受験できる場合がありますが、すべての試験で可能というわけではありません。
例えば国税専門官や労働基準監督官は総合職や一般職との併願が可能ですが、外務省専門職員など一部は併願が制限されています。
もし出願条件を見落とすと、せっかくの受験機会を逃してしまうこともあるでしょう。
効率的に挑戦するためには、試験日程や出願条件を照らし合わせて戦略的に計画を立てることが欠かせません。こうした工夫によって受験のチャンスを最大限に活かせます。
③ 倍率の高さ
国家公務員専門職試験は職種ごとに倍率が大きく異なります。国税専門官や労働基準監督官は採用人数が比較的多く、倍率も安定しています。
一方で外務省専門職員や航空管制官のような人気職種は採用枠が少なく、例年高倍率となるのが特徴です。この点を把握せずに受験すると、想定以上の競争に不安を感じてしまうかもしれません。
過去の実績や最新の採用状況を調べ、現実的な難易度を理解しておくことが大切です。倍率を踏まえて準備を進めれば、心構えを持ちながら効果的に学習計画を立てられるでしょう。
国家公務員専門職試験の選考フロー

国家公務員専門職試験は、筆記試験と人物評価を通じて適性を見極めるプロセスが特徴です。ここでは、筆記試験の範囲やその後の面接での評価基準、採用までの流れを説明していきます。
まず、6月から7月にかけて1次試験が実施され、専門分野ごとの学力と基礎能力が問われます。
続いて8月前後に2次試験として人物試験が行われ、面接や作文を通じて人柄や職務への適性が評価されます。最終合格発表は例年9月ごろに行われ、ここを突破してようやく採用選考へと進みます。
最終合格後には、採用面接(採用面談)が実施されます。この面接は実際の配属先を決める重要なプロセスであり、内定に直結します。
そのため受け身ではなく、主体的に自分の希望や適性を伝える姿勢が求められるでしょう。あらかじめ志望先の業務内容を調べ、自分の強みと結びつけて説明できるよう準備しておくことが大切です。
国家公務員専門職試験の難易度

国家公務員専門職試験は、受験者数が多い一方で求められる知識や適性が明確に定められており、合格のためには計画的な準備が必要です。
難易度を正しく理解することで、自分に合った勉強方法や受験戦略を立てやすくなるでしょう。
- 国家公務員専門職試験の合格難易度
- 国家公務員専門職試験の倍率
① 国家公務員専門職試験の合格難易度
国家公務員専門職試験は、職種ごとに求められる能力が異なり、それが合格の難易度に直結します。
たとえば国税専門官や労働基準監督官は法律や経済に関する幅広い知識が問われる一方、外務省専門職員は高度な外国語能力が不可欠です。
語学力は単に会話できるレベルではなく、外交文書の読解や交渉に対応できる水準が求められるため、十分な準備が欠かせません。
どの職種であっても専門的な学習と基礎的な教養の両立が必要であり、合格には計画的な対策が大きな鍵となるでしょう。
② 国家公務員専門職試験の倍率
国家公務員専門職試験の倍率は、近年ではおおむね、2〜3倍程度に落ち着いています。
もっとも、職種によっては変動が大きく、たとえば皇宮護衛官は採用人数が少ないため倍率が高くなりやすい傾向にあります。
一方で、航空管制官は責任の重さと専門性の高さから受験者の人気も高く、毎年注目を集めています。
志望先の倍率は年度ごとに変動するため、直近のデータを必ず確認しておくことが安心につながるでしょう。
国家公務員の専門職の理解を深めてから目指そう!

国家公務員は総合職・一般職・専門職の3つに分かれ、その中で専門職は特定分野に特化した知識と技能を生かせる点が特徴です。
勤務地や年収、キャリア形成など働き方も安定しており、国税専門官や労働基準監督官など多様な職種が存在します。
こうした国家公務員専門職は、責任感を持ち専門分野を突き詰めたい人に適しているでしょう。
受験にあたっては年齢制限や倍率の高さも確認が必要ですが、計画的な学習と自己分析を重ねれば合格は十分可能です。
結論として、国家公務員専門職は安定した環境で専門性を発揮したい就活生にとって大きな選択肢となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












