公務員の異動とは?決め方やルールを徹底解説
「公務員の異動ってどうやって決まるの?」
春になると異動のニュースが話題になりますが、その仕組みやルールについて詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。
本記事では、公務員の異動の基本から決め方の流れまでをわかりやすく解説します。
異動が頻繁に行われる理由や人事異動の基準、内示が出た後の動き方、さらには異動を拒否できるのかといった疑問まで取り上げます。
公務員として働くうえで避けて通れない「異動」について理解を深め、安心してキャリア形成に臨みましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員の異動とは

公務員の異動とは、職務や勤務地が変更されることを指します。
公務員というと、一般的には県庁や市役所の行政職や事務職の人々を想像しがちですが、実際には国家公務員や警察官、消防隊員、教員なども公務員に含まれます。
これらすべての公務員が異動の対象となり、それぞれの職業に応じた異動が行われます。
公務員の異動は、組織の運営や人員配置の最適化を目的として行われるもので、必ずしも同じ部署や地域に長期間留まるわけではありません。
異動の目的は、組織の運営や効率化を目指すものであり、どの職種であっても、自己の成長やスキル向上の一環として理解されています。
公務員としてのキャリアを考える際には、この異動の仕組みを理解しておくことが不可欠です。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
公務員の人事異動時期

公務員の人事異動は、一般的に4月を中心に行われます。この時期は新しい年度が始まるタイミングであり、異動が一斉に実施されることが多いです。多くの公務員は、4月に新しい部署や勤務地に配属されます。
ただし、異動が行われる時期は組織の状況によって異なる場合もあります。たとえば、年度途中に異動が行われることもあります。
また、公務員の異動には一定のサイクルがあります。一般的には、2年から4年のサイクルで異動が行われることが多いです。
公務員の仕事は幅広い知識とスキルを必要とするため、異動によって様々な経験を積むことが重要です。異動は、職員が多角的な能力を身につける機会でもあります。
このような異動のサイクルを理解しておくことは、キャリア計画を立てるうえで大切です。
適職診断であなたにぴったりな職種を見つけよう!
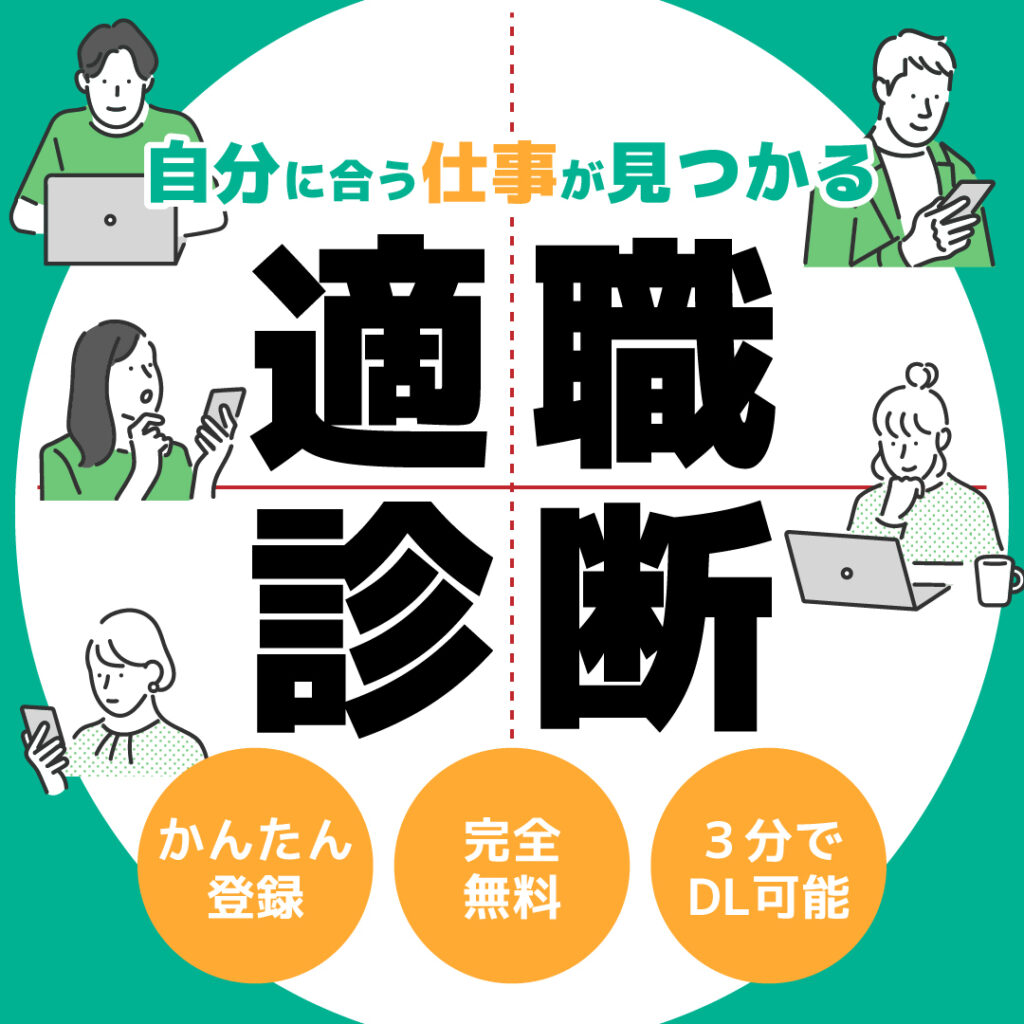
「なんとなく就活してるけど、自分に合う仕事が分からない…」
「選考に応募はしているけど、しっくりこない…」
そんな人にぴったりなのが、就活マガジンが用意している、LINEでできる適職診断です!1
0個の質問にスマホで答えるだけで、あなたの性格や価値観、向いている業界・職種が明確になります。
診断系のツールはパソコンで時間も取られる印象があると思いますが、すべてLINE上で完結するので、移動中やスキマ時間にもサクッと診断ができますよ!
就活に少しでも不安がある人は、まずは気軽に診断してみてください。
なぜ公務員の異動は頻繁に行われるのか?

公務員の異動が頻繁に行われる理由は、組織運営の効率化や職員の成長、法令や政策の変更に対応するためなど、さまざまな要因があるからです。
ここでは公務員の異動が頻繁に行われる主な理由を紹介します。
- 組織の運営効率を上げるため
- 職員の成長とキャリア形成を促進するため
- 法令や政策の変更に対応するため
- 特定の個人や団体との癒着防止のため
①組織の運営効率を上げるため
公務員の異動は、組織運営の効率化を目的としています。異動を定期的に行うことで、職員はさまざまな部署で経験を積むことができ、組織全体の機能が柔軟かつ効果的に運営されるようになります。
職員が異動することで、他の部署の業務にも対応できるようになり、組織全体のパフォーマンスが向上するのです。
②職員の成長とキャリア形成を促進するため
異動は、公務員の成長やキャリア形成を促進するための手段でもあります。異動先でさまざまな業務を経験することにより、公務員は幅広い知識とスキルを身につけることができます。
このようにして、キャリアの幅が広がり、組織の中でさまざまな役割を担えるようになるのです。異動によって得られる経験は、公務員の成長にとって欠かせないものとなります。
③法令や政策の変更に対応するため
異動は、法令や政策の変更に迅速に対応するためにも重要です。社会の情勢や政府の方針が変わることで、組織の運営に必要な人材が変わることがあります。
このような変化に適応するために、職員は異動を通じて新しい分野や業務に対応することが求められます。異動により、公務員は最新の法令や政策に基づいて業務を遂行できるようになります。
④特定の個人や団体との癒着防止のため
異動は、特定の個人や団体との癒着を防ぐためにも重要です。長期間同じ部署にいることで、外部との不適切な関係が生じる可能性があります。
異動を定期的に行うことで、このようなリスクを回避し、公務員が公平で中立的な立場を維持することができます。公務員としての職務において、不正や不公正を避けるためにも異動は必要不可欠な制度です。
公務員の人事異動が決まる流れ

公務員の人事異動は、民間企業の人事とは異なり、職員の階級や役職によって異動を決定する担当者が異なります。これにより、異動の決定過程やその流れが少し複雑になります。
異動がどのように決まるのか、また誰が決定するのかを理解することは、公務員として働く上で非常に重要です。
最初に決まるのは部長級や局長級の人事です。この段階では、「特別職」と呼ばれる市長や知事などの上級公務員が主導して異動を決定します。これにより、組織全体の重要なポストが配置されます。
次に、課長級の人事が決まります。ここでは、人事担当の部長や課長が異動を決定します。課長級の職員は、部署内で重要な役割を担うため、その適材適所が求められます。
最後に、係長級以下の人事が決定されます。この段階では、人事課長や人事係長が担当し、実務に携わる職員の異動を決定することが多いです。職員の業務を効率的に進めるための調整が行われます。
このように、公務員の人事異動は階級ごとに異なる担当者が決定し、組織の運営を支える重要なプロセスとなっています。
公務員の人事異動の決め方

公務員の人事異動は、組織の運営を効率的に行うための重要なプロセスです。その決定方法には、複数の要素が絡んでおり、部署の人数調整や組織の戦略、職員の適性などが考慮されます。
公務員としてどのように異動が決まるのか、その流れを理解することは、就活生にとって大切な知識となります。
- 部署の人数調整
- 組織の方針や戦略
- 上司や同僚とのバランス
- 若手職員の適性見極め
- 過去のパフォーマンスや実績
- 職員の個人的な事情
- 職員個人の希望
①部署の人数調整
異動の決定には、各部署の人数調整が重要な要素となります。組織は常に各部署の人数を調整し、業務が円滑に進むように配置を行います。
特に人手が不足している部署や、必要なスキルを持った人材を配置することで、組織の効率を最大化します。異動先の選定は、この調整によって影響を受けることが多いです。
②組織の方針や戦略
異動は、組織の方針や戦略にも基づいて決まります。例えば、特定の政策やプロジェクトを進めるために、必要なスキルや経験を持った職員が配置されます。
こうした戦略的な異動は、職員の成長にとっても大きなチャンスであり、組織の目標達成をサポートする役割を担います。
③上司や同僚とのバランス
職員の異動においては、上司や同僚とのバランスも考慮されます。チーム内での協力や職場の調和を保つために、過度に偏った異動が避けられます。
チームワークが重要な部署では、適切な人員配置が必要です。職員のスキルや性格も考慮され、円滑な業務運営を目指します。
④若手職員の適性見極め
若手職員には、その適性を見極めたうえで異動が行われます。職員の成長を促進するために、さまざまな業務を経験させることが求められます。
これにより、職員は新たなスキルを獲得し、より多くの業務に対応できるようになります。若手職員の異動は、組織内でのキャリア形成に重要な役割を果たします。
⑤過去のパフォーマンスや実績
職員の過去のパフォーマンスや実績は、異動の決定に大きな影響を与えます。優れた成果を上げている職員は、さらに成長できる部署に配属されることがあります。
一方で、業務に課題があった場合、その改善を目的とした異動が行われることもあります。
⑥職員の個人的な事情
職員の個人的な事情も考慮されます。育児や介護などの家庭の事情や健康状態など、職員の生活や状態に配慮し、適切な部署への異動が調整されることがあります。
ただし、すべての事情が異動に反映されるわけではなく、業務上の優先事項が重要視されます。
⑦職員個人の希望
異動を希望する場合、職員個人の希望も一定程度考慮されます。公務員には毎年、異動希望調査があり、この調査では、「異動を希望するか」「希望する部署」などが選択肢として提示されます。
しかし、すべての希望が反映されるわけではなく、最終的には組織のニーズや配置調整が優先されます。希望が通ることもありますが、最終的な決定は組織運営に基づいて行われます。
公務員の異動の内示はいつ? 異動が決まった後の動き方

公務員の異動に関して、内示がいつ行われるか、異動が決まった後にどう対応すべきかは重要なポイントです。
異動は通常、年度末や年度始めに行われますが、具体的な時期やその後の対応方法は組織によって異なります。異動が決まった後には、引越しや業務の引継ぎなど、さまざまな準備が必要です。
異動の内示は通常、数ヶ月前に行われます。これにより、職員は異動先が決まり、新しい部署での準備を始められます。
異動が決まった後は、引継ぎや新しい部署での準備をしっかりと進めることが求められます。新しい業務や環境に早く適応できるよう、計画的に準備を進めましょう。
公務員は異動を拒否することは可能か?

公務員には、基本的に異動を拒否する権利はありません。異動は公務員としての職務の一部とされており、組織の必要に応じて決定されます。
これは、職員個々の希望や都合に関係なく、組織の運営上必要な措置として行われるものです。
しかし、異動には例外もあります。例えば、家庭の事情や健康問題など、特別な事情がある場合には、異動の延期や調整が行われることがあります。
とはいえ、これらの例外的な対応はあくまで例外であり、すべての公務員に適用されるわけではありません。法律や規定に基づく正当な異動には、拒否できません。
また、異動先の職務が自分に合わないと感じる場合でも、その理由だけでは異動を拒否することは認められません。異動は公務員としてキャリアを積み、スキルや経験を広げるための機会でもあります。
異動に柔軟に対応し、新しい環境に適応していくことが、公務員としての成長に繋がります。
公務員の異動に関する重要なポイント

公務員の異動は、職務や勤務地の変更を指し、組織運営や職員の成長に大きな影響を与えます。異動は一般的に、年度の始まりや終了時に行われます。
異動が頻繁に行われる理由は、組織の効率化、職員のキャリア形成、法令や政策の変更対応、また癒着防止など、さまざまな要因によります。
異動の決定は、希望を考慮しつつも、人数調整や職員の適性、組織の方針などが優先されます。内示は通常、異動前に行われ、異動後は適応力が求められます。
また、公務員は異動を拒否する権利は基本的にないため、柔軟に対応することが求められます。公務員としてのキャリアの一環として、異動を理解し、適応することが大切です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












