就活で評価される得意なこと|自己PRに活かす方法とコツ
「面接で『あなたの得意なことは何ですか?』と聞かれると、どう答えればいいのか迷ってしまう…」
そんな就活生は多いものです。この質問は、あなたの強みや人柄を具体的に伝えられる絶好のテーマですが、漠然と話すだけでは自己PRにつながりません。
企業は質問を通して、あなたの能力や価値観、将来性を見極めています。
本記事では、就活で評価される「得意なこと」の見つけ方や効果的な伝え方、さらにそのまま使える回答例文まで詳しく解説します。
この記事を読めば、自分の強みを魅力的にアピールできるはずですよ。
自己PRをすぐに作れる便利アイテム
- 1自己PR自動作成ツール
- 最短3分!受かる自己PRを、AIが自動で作成
- 2ES自動作成ツール
- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
就活における「得意なこと」とは?

就活において「得意なこと」とは、あなたの強みや仕事との相性を知るために面接官が尋ねる質問です。
勉強・部活・アルバイト・趣味など、分野は自由ですが、大切なのは「その経験からどんな力が身についたのか」をエピソードとあわせて伝えること。
たとえば「料理が得意」とだけ話しても、面接官には伝わりづらいでしょう。「計画を立てて継続した結果、工夫する力が育った」など、背景があるとあなたの人柄や思考が見えやすくなります。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
「得意なこと」と「好きなこと」の違いを理解しよう

就活で「得意なこと」を聞かれた際、「好きなこと」との違いがよく分からず、悩んでしまう方も少なくありません。ですが、この違いを正しく理解することで、自己PRに説得力を持たせやすくなります。
「得意なこと」は、自分が成果を上げたり、他人に評価されたりした経験に基づくスキルや行動を指します。一方で、「好きなこと」は興味や関心が中心のテーマです。
もちろん、好きなことを通じて得意になった内容であれば問題ありません。ただし、単に「好き」という気持ちだけでは、具体的な強みとしては伝わりづらくなってしまいます。
たとえば、「旅行が好き」というだけではアピールとして弱くなりがちです。
しかし「旅行の計画を立てるのが得意で、友人からも頼りにされていた」など、行動や成果を交えて伝えれば、効果的なアピールになります。
ここでは、日常の中で自分が自然と努力し、周囲から評価された経験を思い出してみてください。それこそが、「得意なこと」の原石である可能性が高いでしょう。
面接で得意なことを質問される理由

就活の面接で「得意なこと」を尋ねられるのには、いくつかの明確な目的があります。
ここでは、面接官がこの質問をする理由を4つに分けて紹介しましょう。
- 就活生の人柄や価値観を知るため
- 業務への適性や能力を見極めるため
- 論理的思考力や説明力をチェックするため
- 緊張を和らげるために話しやすいテーマとして使われるため
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①就活生の人柄や価値観を知るため
面接官は、応募者がどのような人かを把握するために「得意なこと」を尋ねます。
チームワークを大切にする人は協調性に関するエピソードを話すでしょうし、前向きな人なら挑戦経験を話すことが多いでしょう。
つまり、得意なことを通して、価値観や性格が浮かび上がってくるのです。
一貫性があるエピソードを用意すれば、自己PRにもつなげやすくなります。
ただ得意だと話すだけでなく、「なぜそう感じるのか」「その背景には何があるのか」まで掘り下げておくと、説得力が増すでしょう。
②業務への適性や能力を見極めるため
企業側は、応募者の強みが職務に活かせるかを見極めようとしています。
事務職などであれば「几帳面さ」や「計画性」が活かせるでしょうし、営業職であれば「人と話すことが得意」という内容が評価されやすいです。
仮に仕事内容と直接関係がない強みであっても、「どう応用できるか」を説明できれば問題ありません。
自身の得意分野を職務にどう活かせるかを具体的に語れるよう、準備しておきましょう。
③論理的思考力や説明力をチェックするため
得意なことを通して、話の構成力や説明の分かりやすさを評価されることもあります。
話す順序がバラバラだったり、例が不明確だったりすると、論理性や伝達力に不安を感じさせてしまうかもしれません。
PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識して話せば、内容が明確になりやすく、面接官にも理解してもらいやすくなります。
自分の思考を整理しながら話すことが、結果的に好印象につながるはずです。
④緊張を和らげるために話しやすいテーマとして使われるため
面接の序盤では、緊張をほぐす目的で「得意なこと」のような話しやすい質問が使われることがあります。いきなり志望動機を問われるより、自分の得意分野について話すほうが、気持ちも落ち着くでしょう。
面接官はリラックスした状態で自然な受け答えを引き出そうとしているのです。ただし話しやすいとはいえ、準備せずに臨むのは避けたいところ。
自分らしさを伝えられる得意なことを1つ、しっかり用意しておくと安心です。
就活で使える得意なことの見つけ方

得意なことがわからず、エントリーシートや面接で悩んでいる就活生も多いでしょう。しかし、自分の日常や経験を見つめ直すだけでも、アピールできる強みは意外と身近にあるものです。
ここでは、自分に合った「得意なこと」の見つけ方を5つ紹介します。
- 学生時代の経験を振り返る
- 継続していることや習慣から探る
- 他人から褒められたことを思い出す
- 日常の中で自然にできていることを見つける
- 家族や友人に意見を聞いてみる
①学生時代の経験を振り返る
学生生活の中には、自分の強みを示すヒントが数多く隠れています。
たとえば、もし、ボランティア活動などで周囲よりも成果を出せた経験があれば、それが得意なことかもしれません。
「なぜそれがうまくいったのか」「どんな工夫をしたのか」といった点を深掘りすることで、表面的なエピソードにとどまらない説得力が生まれます。
具体的な成果や取り組み姿勢まで説明できると、企業側にもあなたの価値が伝わりやすくなるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②継続していることや習慣から探る
自分では当たり前に感じている日々の習慣も、実は立派な強みになることがあります。
たとえば、毎朝のランニングや日記の習慣、自炊を続けていることなどには、継続力や自己管理能力が表れるでしょう。
面接では、どれくらいの期間続けているのか、どんな工夫をしてきたかなどもあわせて伝えてみてください。日常の中で自然に続けている行動こそ、他人にはまねできないあなたの得意なことかもしれません。
③他人から褒められたことを思い出す
他人からの言葉は、自分では気づかない強みに気づかせてくれる手がかりになります。人から「説明がわかりやすいね」と言われた経験があれば、伝える力が得意なことといえるでしょう。
「気が利くね」とよく言われるなら、対人スキルが高い可能性があります。
何度も言われた内容や、異なる場面で同じように評価された経験があれば、それは立派なアピール材料です。
その言葉の背景にある行動を振り返ってみてください。
④日常の中で自然にできていることを見つける
自然とやってしまう行動の中にも、得意なことは隠れています。たとえば、予定の管理を無意識に引き受けている人は、計画性に優れているといえます。
整理整頓が習慣になっている人は、几帳面さという強みがあるでしょう。自分では「当たり前」と思っていることほど、他人から見ると価値のある行動です。
日常の行動を少し客観的に見直してみると、新たな強みに気づけるきっかけになります。
⑤家族や友人に意見を聞いてみる
自分ではなかなか気づけない強みも、周囲の人に聞いてみることで見つかる場合があります。
家族や友人、ゼミの仲間など、あなたのことをよく知っている人に「私の得意なことって何だと思う?」と率直に尋ねてみましょう。
複数の人から共通して出てくる意見があれば、それが客観的に見たあなたの強みです。自分自身の印象と照らし合わせることで、新たな発見があるかもしれません。
面接で得意なことを伝えるときのポイント

面接で「得意なこと」を聞かれたときは、単なる自己アピールではなく、企業にとって有益な情報として伝えることが大切です。
ここでは、あなたの魅力をより効果的に伝えるための5つのポイントを紹介します。
- 結論ファーストで簡潔に伝える
- 過去・現在・未来の流れで話す
- 得意なことを明確に話す
- 具体的なエピソードを交えて説明する
- 得意なことを仕事にどう活かせるか伝える
面接でどんな質問が飛んでくるのか分からず、不安を感じていませんか?とくに初めての一次面接では、想定外の質問に戸惑ってしまう方も少なくありません。
そんな方は、就活マガジン編集部が用意した「面接質問集100選」をダウンロードして、よく聞かれる質問を事前に確認して不安を解消しましょう。
また、孤独な面接対策が「不安」「疲れた」方はあなたの専属メンターにお悩み相談をしてみてください。
①結論ファーストで簡潔に伝える
面接の場では時間が限られているため、最初に話の結論を述べることが重要です。たとえば「私の得意なことは〇〇です」と冒頭で明確に伝えると、相手はその後の説明を理解しやすくなります。
逆に、理由や背景から話し始めると、要点が見えにくくなってしまうでしょう。最初にポイントを示し、そこから詳細を補足していく流れが効果的。
聞き手にとってわかりやすい構成を意識して話すことが好印象につながります。
②過去・現在・未来の流れで話す
得意なことをより魅力的に伝えるためには、「過去→現在→未来」の順で話すと自然な流れが生まれます。
「高校時代に始めた読書で文章力を鍛え、今ではゼミのレポートでも高評価をもらっています。将来はその力を仕事でも活かしていきたい」といったように、自分の成長と将来への意欲が伝わりやすくなるでしょう。
経験に基づいたストーリー性のある説明を意識してください。
③得意なことを明確に話す
「得意なこと」は抽象的ではなく、できるだけ具体的に伝える必要があります。
「コミュニケーションが得意」だけでは伝わりにくいため、「相手の話をじっくり聞いて、共感しながら会話するのが得意です」といったように、内容を明確に言葉で表すことが大切です。
身近な行動や経験から表現することで、聞き手にもイメージが伝わりやすくなるでしょう。
④具体的なエピソードを交えて説明する
得意なことの信頼性を高めるには、実際のエピソードが欠かせません。
たとえば「人前で話すのが得意」と伝えるだけでなく、「文化祭で司会を務め、緊張しながらも全体をまとめ上げた経験がある」といった具体例を加えることで説得力が生まれます。
話す際は、どんな場面で、どのような行動をとり、どんな結果につながったかを意識して伝えてみてください。
⑤得意なことを仕事にどう活かせるか伝える
面接官が注目するのは、あなたの得意なことが仕事にどう活かせるかです。
ただ「〇〇が得意です」と言うだけでなく、「そのスキルを活かして営業職でお客様との信頼関係を築いていきたい」といったように、具体的な活用イメージを示すと好印象を与えられるでしょう。
企業側の視点を意識しながら、仕事でどんな場面で活躍できるかを伝えてください。
就活で有効な「得意なこと」一覧

「得意なこと」は、あなたの人柄や能力を企業に伝える重要な材料になります。ここでは、ジャンル別に就活で活かせる得意なことの例を紹介しましょう。
自分に合いそうなものを探しながら、実体験と結びつけて考えてみてください。
- スポーツ系
- 知識・学習系
- アート・クリエイティブ系
- ITスキル系
- 対人スキル系
- 日常系
①スポーツ系
以下のような経験は、協調性や粘り強さの証明になります。部活動や趣味の運動を振り返ってみましょう。
- サッカー
- バスケットボール
- 野球
- 陸上競技(マラソン・リレーなど)
- バドミントン
- テニス
- 水泳
- 登山
- 武道(剣道・柔道など)
運動を通して身についた集中力や粘り強さ、協調性は、チームでの仕事にも活かせます。
たとえば「サッカー部で副キャプテンとして後輩指導をしていた」「マラソン大会で目標タイムを達成した」など、努力と結果を結びつけて伝えると説得力が増すでしょう。
運動経験は継続力の証明にもなるため、就活での強みとして効果的にアピールできます。
②知識・学習系
知的好奇心や地道な努力を示す内容は、企業からの評価も高くなります。以下のような項目が該当します。
- 英語(TOEIC・英検など)
- 数学・物理など理系科目
- 資格取得(簿記・FPなど)
- 歴史や地理の知識
- 時事問題に強い
- 読書習慣
- レポート作成が得意
- 物事を計画的に進められる
- 苦手なことにも粘り強く取り組める
資格取得や成績アップなど、自ら学び続ける姿勢はどの企業でも評価されやすいです。
たとえば「TOEICで200点アップ」「簿記2級合格のために毎日2時間勉強」など、成果とプロセスの両方を意識して伝えてみましょう。
学ぶ意欲と計画性は、どんな職種にも必要な要素であり、継続する姿勢も大きなアピール材料になります。
③アート・クリエイティブ系
創造性や表現力を発揮した経験がある方は、以下のような得意分野を活かせるでしょう。
- 絵画・イラスト
- デザイン制作
- 写真撮影
- 動画編集
- 音楽(演奏・作曲など)
- ダンス
- 文章・小説・詩の創作
- ハンドメイド
絵や音楽、動画制作など、表現力を活かせる分野も立派な得意なことです。
「イラストをSNSで発信してフォロワーが1万人に」「学園祭ポスターを担当して反響が大きかった」など、反応や結果を具体的に伝えると印象的でしょう。
発想力や構成力は、企画職や広報職などで特に重視されるため、自信があるなら積極的に伝えてみてください。
④ITスキル系
ITに関する知識やスキルを持っている方は、以下のような内容をアピールポイントにできます。
- プログラミング(Python、Javaなど)
- Web制作(HTML・CSS)
- データ分析(Excel・Googleスプレッドシート)
- ITパスポートなどの資格
- Adobe系ソフト(Illustrator、Photoshopなど)
- 動画編集ソフト(Premiere Proなど)
プログラミングやデザイン、動画編集などのスキルは、職種によっては大きなアピールポイントになります。
たとえば「Pythonで業務効率化ツールを自作」「Adobe系ソフトで学内プロジェクトの資料を作成」など、実績に触れながら語るのが効果的です。
ITスキルは実務でも即戦力として評価されやすく、習得のための姿勢そのものもアピール材料となります。
⑤対人スキル系
人との関わりの中で得たスキルや経験を活かしたい方に向いているジャンルです。
- 接客業の経験
- アルバイトでのクレーム対応
- プレゼン経験
- ディベート・スピーチ
- ファシリテーション(議論の調整役)
- リーダー経験(部長・班長など)
接客や部活のマネージャー経験などから得た対人スキルは、多くの職種で活かせます。
「飲食店でクレーム対応を任された」「ゼミ内の意見を調整して発表をまとめた」など、実践を通じたエピソードが重要です。
人と関わる能力は、チームで働く場面だけでなく、営業や顧客対応にも直結するため、具体的な行動や成果を伴って説明することがカギになります。
⑥日常系
一見アピールにならなさそうな日常の行動にも、継続力や計画性などが表れます。
- 早起き習慣
- 日記を毎日書く
- 掃除や片付けが得意
- 節約・家計管理
- 料理
- ガーデニングやDIY
趣味や習慣の中にも、アピールできる要素はあります。「毎朝5時に起きてランニング」「3年間毎日日記を継続」など、地道な継続力や計画性を伝えるきっかけになるでしょう。
普段の生活を見直すと、意外な強みに気づけるかもしれません。こうした身近な行動を丁寧に見つめ直すことで、自分でも意識していなかった価値が見えてくるでしょう。
就活で使える「得意なこと」の回答例文
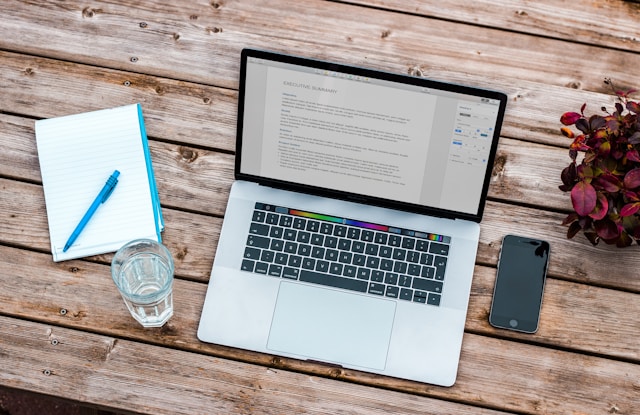
「得意なこと」と言われても、具体的にどう伝えればいいか悩む方は多いのではないでしょうか。ここでは、大学生活での経験や趣味・特技を活かした、実際に使える回答例文を紹介します。
自分の経験に近い例を探しながら、伝え方のヒントにしてみてください。
- サッカー経験を活かしたチーム貢献の例文
- 日々の料理習慣で培った継続力・几帳面さの例文
- アルバイトリーダーとして発揮したリーダーシップの例文
- カフェでの接客経験から得たコミュニケーション力の例文
- 学園祭準備で発揮した計画性の例文
- 苦手だった英語を克服した成長意欲の例文
- プログラミングを活かしたITスキルの例文
- 英語を使って留学生と協働した語学力の例文
- ディベート活動で培った対人スキルの例文
- ハンドメイド作品販売で発揮したクリエイティブ力の例文
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
①サッカー経験を活かしたチーム貢献の例文
ここでは、サッカー経験をもとに、チームでの役割を見つけながら目標達成に貢献したエピソードを紹介します。協調性や主体的な行動力をアピールしたい方におすすめです。
| 私の得意なことは「サッカー」です。大学ではサッカーサークルに所属し、プレーだけでなくチーム全体の活動を円滑に進める役割も担ってきました。 参加率の低下や練習内容のマンネリ化が課題だったため、私は自主的に練習日程を見直し、出欠確認や日程共有の仕組みを導入。 また、ポジションごとの課題を共有できるミーティングも定期的に行うよう提案しました。これによりメンバー同士の連携が強まり、練習への意欲も高まりました。 最終的には公式戦での勝利に繋がり、チームの一体感も大きくなったと感じています。この経験から、チームの中で自分の役割を見つけ、周囲と協力しながら目標に向かって行動する力を身につけました。 |
「サッカーが得意」と伝えるだけでは抽象的になりがちですが、プレー以外での工夫や貢献を具体的に盛り込むことで、主体性やチーム意識が伝わりやすくなります。
特に、課題を発見し改善策を提案・実行したエピソードがあると、周囲に良い影響を与えられる人物像として印象づけることができるでしょう。
②日々の料理習慣で培った継続力・几帳面さの例文
ここでは、毎日の料理という習慣を通じて継続力や几帳面さをアピールする例文を紹介します。地道な努力や丁寧な取り組みを強みにしたい方におすすめです。
| 私の得意なことは「料理」です。大学で一人暮らしを始めたことをきっかけに、平日は毎朝自炊をする習慣を2年以上続けています。 最初は手際が悪く、同じメニューでも味にばらつきがありましたが、調味料の分量や手順をノートに記録しながら工夫を重ねることで、次第に安定した味と効率的な段取りで調理できるようになりました。 毎日同じ時間に起きて作ることで生活リズムも整い、節約や健康管理にもつながっています。 この経験から、小さな改善を積み重ねる継続力と、正確さを意識して丁寧に取り組む几帳面さを養うことができました。仕事でもこうした姿勢を大切にしていきたいと考えています。 |
「料理」は身近なテーマだからこそ、継続年数や具体的な取り組みを明示すると強みに変わります。成果や工夫が伝わる表現を意識しましょう。
③アルバイトリーダーとして発揮したリーダーシップの例文
ここでは、アルバイト先でリーダーとしての役割を担った経験を通じて、リーダーシップをアピールする例文を紹介します。実践的なチームマネジメントの力を伝えたい方におすすめです。
| 私の得意なことは「人をまとめてチームで成果を上げられる」ことです。 大学2年から飲食店でアルバイトをしており、3年目には新人スタッフの指導やシフト管理などを任されるようになりました。当初はスタッフ間の連携不足やミスが多く、現場が混乱する場面も。 そこで私は、マニュアルをわかりやすく再整理し、共有ノートを活用して情報の見える化を図りました。また、シフト前に簡単なミーティングを行うことで、役割分担を明確にしました。 その結果、スタッフ同士の連携がスムーズになり、店舗全体の接客品質も向上したのです。この経験から、相手の立場に立って物事を整理し、チーム全体を動かす力を培うことができました。 |
リーダーシップを示す際は、課題→工夫→成果の流れを意識しましょう。身近な経験でも十分に伝えることができます。
④カフェでの接客経験から得たコミュニケーション力の例文
ここでは、カフェでのアルバイト経験を通じて、コミュニケーション力を身につけたエピソードを紹介します。人との関わりを通じて成長した経験をアピールしたい方におすすめです。
| 私の得意なことは「初対面の相手とも円滑にコミュニケーションを取れる」ことです。 大学1年からカフェで接客のアルバイトをしており、幅広い年齢層のお客様と接する中で、相手に合わせた言葉遣いや表情を意識するようになりました。 特に常連のお客様との会話では、名前を覚えたり好みのドリンクを把握することで、より丁寧なサービスを提供できるよう工夫してきました。 また、新人スタッフの教育も担当し、分かりやすく伝える力や、相手の反応を見ながら話す力も磨かれたと思います。 こうした経験を通じて、相手に安心感を与えながら、状況に応じた対応ができるコミュニケーション力を培うことができました。 |
コミュニケーション力を伝える際は、「相手との関わりの中でどう工夫したか」に焦点を当てると、印象に残るエピソードになります。
⑤学園祭準備で発揮した計画性の例文
ここでは、学園祭の企画運営に携わった経験を通して、計画性をアピールする例文を紹介します。限られた時間や資源の中でどう工夫したかを伝えたい方に適しています。
| 私の得意なことは「物事を計画的に進められる」ことです。大学の学園祭で模擬店の企画責任者を担当した際、限られた準備期間の中で効率よく作業を進める必要がありました。 そこで私は、全体のスケジュールを週ごとに細分化し、各担当者の役割と締め切りを明確にした進行表を作成。また、週に1回の進捗確認ミーティングを実施し、課題が出た場合にはすぐに対応できる体制を整えました。 その結果、準備は滞りなく進み、当日も混乱なく模擬店を運営することができたのです。この経験を通じて、目標から逆算して計画を立て、周囲と連携しながら実行する力を身につけました。 |
計画性を伝えるには「スケジュール管理」や「タスクの見える化」など、具体的な取り組みを示すことが大切です。準備から実行までの流れがわかると説得力が増します。
⑥苦手だったプレゼンを克服した成長意欲の例文
ここでは、もともと苦手だったプレゼンテーションに前向きに取り組み、克服した経験を通して成長意欲をアピールする例文を紹介します。苦手意識を乗り越えたプロセスを伝えたい方におすすめです。
| 私の得意なことは「苦手なことにも粘り強く取り組める」ことです。 もともと人前で話すことに強い苦手意識があり、大学入学当初のゼミ発表では緊張のあまり声が震え、内容がうまく伝わらなかったこともありました。 そこで私は、この苦手を克服しようと決意し、ゼミ外でもスピーチの練習を重ねたり、発表動画を見て話し方を研究したりするようにしました。 また、日々の授業でも積極的に発言することを心がけ、経験を重ねるうちに次第に自信がついていったのを覚えています。その結果、3年次には学外の発表会にも代表として参加できるまでに成長しました。 この経験から、苦手なことでも逃げずに取り組み、着実に成長できる力が自分の強みだと実感しています。 |
苦手なことをテーマにする場合は、「具体的なきっかけ」「取り組んだ内容」「成果」の流れを明確にすることで、説得力のある自己PRにつながります。
⑦プログラミングを活かしたITスキルの例文
ここでは、プログラミングの学習を通じて得たITスキルをアピールする例文を紹介します。自発的な学習や、スキルの実践経験を伝えたい方におすすめです。
| 私の得意なことは「プログラミング」です。大学1年のときに興味本位でプログラミングを学び始め、独学でHTMLやCSS、JavaScriptを習得しました。 2年次には友人のサークルの紹介で、イベント管理用のWebアプリを作る機会をいただき、タスク管理や参加者の登録フォームを備えたシステムを開発。 途中で思うように動かない部分も多くありましたが、エラーの原因を調べ、何度も修正を重ねながら完成までやり遂げました。 この経験を通じて、自分のスキルで人の役に立てる喜びと、粘り強く取り組む大切さを学びました。今後も技術を磨き続けながら、現場で活かしていきたいと考えています。 |
ITスキルのアピールでは「何を学んだか」だけでなく、「どう活かしたか」「誰に貢献したか」を明確にすることで説得力が高まります。
⑧英語を使って留学生と協働した語学力の例文
ここでは、英語を使って留学生とコミュニケーションをとりながら、共同でプロジェクトや活動に取り組んだ経験を紹介します。語学力とともに異文化理解や協調性を伝えたい方におすすめです。
| 私の得意なことは「英語」です。大学の国際交流プログラムに参加した際、留学生とのグループワークで地域の観光案内パンフレットを英語で制作するプロジェクトに取り組みました。 最初は言語の違いによる意見のすれ違いや進行の遅れもありましたが、私は率先して会話の橋渡し役を務め、相手の言葉を正確に理解できるよう何度も確認を取ったのをよく覚えています。 また、文化的な違いにも配慮しながら話し合いを進めた結果、全員が納得できる内容でパンフレットを完成させることができました。 この経験から、語学力だけでなく、相手の立場を尊重しながら協働する姿勢の大切さを学びました。 |
語学力をアピールする際は、点数よりも「実際にどのように使ったか」「誰とどう関わったか」を重視しましょう。異文化対応力も加えると効果的です。
⑨ディベート活動で培った対人スキルの例文
ここでは、ディベートを通じて培った論理的思考力や、相手との対話力を活かしたエピソードを紹介します。主張だけでなく、相手との信頼構築を重視してきた方におすすめです。
| 私の得意なことは「ディベート」です。大学のディベートサークルに所属し、週に一度の練習や大会に向けた準備を通して、相手の立場を理解しながら自分の意見を的確に伝える力を養いました。 議論では、感情的にならず、事実と論理に基づいて話すことを意識しました。 特に印象に残っているのは、全国大会で対戦相手の意見に納得しつつも、自分たちの立場を明確に示し、審査員から「冷静で相手を尊重した議論だった」と評価をいただいたことです。 この経験から、異なる意見を持つ相手とも建設的に話し合い、信頼関係を築く力を身につけることができました。 |
ディベートは「対立」ではなく「対話」を通じた理解力のアピールがポイントです。相手を尊重した言葉選びや、冷静な対応力を具体的に書きましょう。
⑩ハンドメイド作品販売で発揮したクリエイティブ力の例文
ここでは、自身のハンドメイド作品を制作・販売した経験を通じて、創造力や企画力、実行力をアピールする例文を紹介します。アイデアを形にする力を伝えたい方におすすめです。
| 私の得意なことは「ハンドメイド」です。大学1年の頃から趣味でアクセサリー作りを続けており、作った作品をハンドメイドマーケットアプリで販売するようになりました。 ターゲット層に合わせてデザインを工夫したり、季節ごとのテーマを取り入れたりすることで、フォロワー数も徐々に増加。 売れ筋商品を分析して改良を加えたり、写真の見せ方を変えたりと、試行錯誤を重ねながら継続してきました。 結果として、月に50点以上を売り上げるまでに成長し、自分のアイデアが誰かの手に届く喜びも感じられました。この経験を通して、企画から実行、改善までを一貫して行う力が身についたと実感しています。 |
クリエイティブ力を伝える際は、「何をどう工夫したか」「どんな成果が出たか」を具体的に記すと効果的です。数字やプロセスも忘れずに入れましょう。
面接で「得意なこと」を伝えるときのNG例

就活で「得意なこと」を伝えるときは、内容だけでなく伝え方にも注意が必要です。どんなに良い話でも、伝え方を誤ると評価されにくくなる可能性があるでしょう。
ここでは、採用担当者にマイナスな印象を与えてしまう避けたい例を紹介します。
- 自己PRにつながらない内容
- 抽象的すぎて伝わりづらい内容
- 役割や成果が他人任せの内容
- 自慢話に聞こえる内容
①自己PRにつながらない内容
得意なことを伝える目的は、自分の強みや人柄をアピールすることです。ただ「パズルが得意」「早起きが得意」といった趣味や日常の話題だけでは、採用担当者の印象には残りにくいでしょう。
仕事にどう活かせるかという視点が欠けていると、評価の対象になりにくくなります。
たとえば「計画的に物事を進めるのが得意で、学園祭ではスケジュール管理を徹底した結果、当日スムーズに進行できた」など、実際の経験に基づいた形で伝えると効果的でしょう。
自分の強みが仕事にどう活かせるかまで伝えることが大切です。
②抽象的すぎて伝わりづらい内容
「リーダーシップがある」「努力家だ」といった表現は、よくある一方で、具体性がないと説得力に欠けてしまいます。面接では、実際にどのような場面でそうした強みを発揮したのかが重要です。
たとえば「サークルの代表として全体をまとめ、イベントの動員目標を達成した」など、行動や成果を具体的に伝えると印象に残ります。
抽象的な言葉だけで終わらず、実体験を通じて証明することが説得力を高めるポイントです。数字や事実を交えて語ると、より納得感のある自己PRにつながるでしょう。
③役割や成果が他人任せの内容
チームでの活動を話す場合は、チーム全体の成果だけでなく、自分自身の関わり方をはっきり示すことが重要です。
「グループで成功した」「仲間に支えられた」といった内容だけでは、個人としての評価につながりにくくなります。
「自分が〇〇を提案して実行した結果、目標を達成できた」といったように、自分がどんな役割を果たしたのかを具体的に語りましょう。
主体性や行動力が伝わることで、採用担当者に「一緒に働きたい」と感じてもらえる可能性が高まります。
④自慢話に聞こえる内容
得意なことをアピールする際には、自信を持って話すことも大切ですが、過剰になると逆効果です。
「誰よりも優れていた」「他のメンバーよりも成果を出した」といった言い回しは、自慢話に聞こえてしまいかねません。評価されるのは、成果そのものよりも、その過程や姿勢です。
「メンバーと連携しながら自分の強みを活かして貢献した」といった表現であれば、協調性や謙虚さも伝わります。周囲への配慮がある言い方を心がけることで、より好印象を持たれるでしょう。
就活で得意なことをアピールする際の注意点

就活で「得意なこと」を聞かれたとき、単にスキルや趣味を伝えるだけでは不十分です。内容そのものに加えて、「どのように伝えるか」も重要な評価ポイントになります。
面接官に好印象を与えるためには、話す内容の一貫性や具体性、表現方法に気を配る必要があるでしょう。ここでは、特に気をつけたい4つの注意点を紹介します。
- 得意なことが「ない」と答えるのを避ける
- 一貫性のあるストーリーで伝える
- 一般的すぎて印象に残らない内容は控える
- 言葉選びに注意して伝える
①得意なことが「ない」と答えるのを避ける
面接で「得意なことはありません」と答えるのは、できるだけ避けたほうがよいでしょう。
特別なスキルがなくても、普段の生活やアルバイト、部活やゼミなどの活動を振り返ると、何かしらアピールできることが見つかるはずです。
たとえば「計画的に物事を進めるのが得意」といった内容も立派な強みになります。「ない」と言ってしまうと、自己理解が浅い、もしくは準備不足と判断されてしまいかねません。
自信がなくても、まずは自分の経験を振り返ってみてください。
②一貫性のあるストーリーで伝える
得意なことを伝えるときは、エピソードや志望動機と矛盾がないように注意が必要です。たとえば「協調性が強み」と言いながら、「個人プレーを重視する職種」を希望するのは一貫性に欠けてしまうでしょう。
一貫性のあるストーリーは、話の説得力を高めるだけでなく、あなたの価値観や将来のビジョンも明確に伝えることができます。
過去の経験、現在の行動、そして志望動機をつなげて話すことで、面接官に信頼感を与えられるでしょう。
③一般的すぎて印象に残らない内容は控える
「頑張るのが得意」「真面目に取り組める」といった表現は、抽象的すぎて記憶に残りづらい傾向があります。それだけでは他の就活生と差別化できず、面接官の印象に残らないかもしれません。
そうならないためにも、なるべく具体的なエピソードを交えるようにしましょう。たとえば「サークルで予算管理を任され、年間の支出を20%削減した」といった成果を加えると、説得力が高まります。
抽象的な言葉だけに頼らず、行動や結果で裏付けましょう。
④言葉選びに注意して伝える
得意なことを話す際、過度な自信を感じさせる表現は避けたほうが無難です。たとえば「完璧にこなせます」「誰にも負けません」といった言い方は、協調性や柔軟性が欠けている印象を与えるおそれがあります。
逆に「少しだけ得意です」といった控えめすぎる言い方も、自信のなさにつながる可能性も。
伝えるときは、「このような経験を通じて○○が得意になりました」「実際に△△と評価されたことがあります」といったように、具体的かつ謙虚な表現を意識してみてください。
面接で「得意なこと」を効果的に伝えるために

就活では「得意なこと」の伝え方が、自己PRの成否を大きく左右します。単にスキルを列挙するだけでは不十分で、選考を通して人柄や価値観、業務適性まで評価されていることを意識する必要があります。
そのため、「得意なこと」と「好きなこと」の違いを正しく理解し、具体的なエピソードを交えながら一貫性あるストーリーで伝えることが重要です。
また、就活で使える「得意なこと」は身近な習慣や経験の中にある場合が多く、自分の強みを見つけるには丁寧な自己分析が欠かせません。
さらに、避けるべきNG表現や伝え方の注意点を把握しておくことで、より説得力のあるアピールが実現できるでしょう。面接官に響く「得意なこと」の伝え方を磨くことが、内定獲得への近道です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











