面接で差がつく「人生で一番辛かったこと」の答え方と例文
「面接で『人生で一番辛かったことは何ですか?』と聞かれると、何を話せばいいのか迷ってしまう…」という就活生は少なくありません。
この質問は、あなたの困難への向き合い方や成長のプロセスを通じて、企業が人柄やストレス耐性を見極めるための重要なものです。
しかし、出来事を感情的に語るだけでは好印象にはつながりません。
本記事では、「人生で一番辛かったこと」を効果的に伝えるための選び方や構成、好印象を与えるポイント、さらにそのまま使える例文まで詳しく解説します。
この記事を読めば、自分の経験を前向きなストーリーとして面接で自信を持って話せるようになるはずですよ。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。
「人生で一番辛かったこと」は就活で頻出の質問

企業がこの質問をする理由は、あなたの価値観やストレス耐性、困難を乗り越える力を見極めたいからです。
だからこそ、「ただ辛かった話」ではなく、なぜ辛かったのか、どう向き合い、どのように乗り越えたのかまで伝えることが大切です。
回答を考える際は、過去の経験の中で「自分の考えや行動が問われた場面」「乗り越えようと工夫した出来事」を思い出してみてください。
その経験から何を学び、どう変化したのかを伝えることで、あなたの人柄や成長力が伝わるはずでしょう。
面接でよく聞かれる質問だからこそ、事前の準備が大切です。しっかり準備して、自分らしさが伝わる回答を用意しておきましょう。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
企業が「人生で一番辛かったこと」を聞く意図とは?

就活の面接で「人生で一番辛かったこと」を聞かれると、どう答えるべきか不安に感じる人も多いのではないでしょうか。ですが、この質問には企業側の明確な意図があります。
ここでは、面接官が何を見ているのかを4つの視点で解説しています。
- 困難をどう乗り越えるかを見るため
- 辛かった経験から何を学んだかを把握するため
- 何を「辛い」と感じるのかを知るため
- ストレス耐性を知るため
①困難をどう乗り越えるかを見るため
企業がこの質問を通じて確認したいのは、あなたが予期しないトラブルや困難な状況に直面したとき、どのような姿勢でそれに向き合い、どう解決しようと努力したかという点です。
仕事では常に想定通りに進むとは限らず、むしろ想定外の事態への対応力が求められます。たとえ些細な出来事であっても、自ら工夫しながら粘り強く取り組んだエピソードは高く評価されるでしょう。
問題から目をそらさず、一歩ずつ前進しようとする姿勢が伝わると、企業に安心感を与えられます。
②辛かった経験から何を学んだかを把握するため
企業は、辛い体験そのものよりも、その経験を通じて何を得たかに注目しています。
ただ大変だったという話にとどまらず、その経験によってどんな気づきを得て、考え方や行動にどう変化が生まれたのかが重要です。
そして、その学びを今後どのように仕事に活かしたいかまで語れると、成長意欲のある人物として評価されやすくなります。
自分の成長ストーリーを描くような意識で構成すると、説得力がぐっと増すでしょう。
③何を「辛い」と感じるのかを知るため
「辛さ」の感じ方は人それぞれであり、その違いには価値観や人生観が反映されます。
企業は、あなたがどのような場面を辛いと感じ、なぜそう感じたのかという背景を知ることで、あなたの感受性や人間性を見極めようとしています。
単なる感情表現だけで終わらず、その出来事があなたにとってどんな意味を持ち、どのような心理状態だったのかを具体的に伝えることで、より深い理解を得られるでしょう。
表面的な辛さではなく、自分なりの言葉で整理して説明することが大切です。
④ストレス耐性を知るため
働くうえで、ストレスはどうしても避けられません。
企業は、あなたがプレッシャーや人間関係、タスクの重圧といったストレス要因にどう向き合い、どう乗り越えてきたかを知ることで、採用後の活躍をイメージしようとしています。
辛い状況をどう受け止めたか、どんな工夫や思考の切り替えで乗り越えたかを丁寧に語ることで、柔軟性や回復力といった強みをアピールできるでしょう。
自分をどう整えるかというセルフマネジメント力も評価の対象になります。
「人生で一番辛かったこと」エピソードの選び方

エピソードの選び方次第で印象が大きく変わるため、事前の準備がとても重要です。
ここでは、効果的に伝わるエピソードを選ぶためのポイントを4つに分けて解説します。
- 辛かった出来事をリストアップする
- その経験から得たスキルや学びを抽出する
- ポジティブな視点に転換できるかを確認する
- 企業が求める人物像に合っているかを見極める
①辛かった出来事をリストアップする
まず最初に行いたいのは、自分の過去を振り返り、印象に残っている「辛かったこと」をできるだけ多く書き出すことです。
学校生活での挫折や、アルバイトでの苦労、部活動での人間関係の悩みなど、ジャンルに制限はありません。
大切なのは、自分の中で強く記憶に残っている出来事や、感情が大きく動いた場面を思い出すことです。
思い出せる限り数を出すことで、自分らしさがにじみ出るテーマや、一貫した傾向が見えてくるかもしれません。最初から完璧なエピソードを見つけようとせず、まずは「書き出す」ことを重視してください。
②その経験から得たスキルや学びを抽出する
どんなに印象的なエピソードでも、「その経験から何を得たのか」が明確でなければ説得力に欠けてしまいます。
単なる失敗談や苦労話で終わるのではなく、そのあと自分がどのように変化したのか、行動や考え方にどう影響があったのかを考えてみてください。
たとえば、リーダー経験から責任感を学んだ、あるいは人間関係の悩みを通じて傾聴力が身についたなど、具体的なスキルや成長の実感が伝わると評価されやすくなります。
その経験が「今の自分につながっている」と言えるかを意識しながら、エピソードを整理しておきましょう。
③ポジティブな視点に転換できるかを確認する
辛い出来事を語る際に注意したいのは、ネガティブな印象を残してしまわないことです。
どれほど大変だったとしても、「今では自分の成長の糧になっている」と前向きな視点に変換できているかが重要でしょう。
たとえば、「失敗して落ち込んだ」だけで終わらず、「その失敗を踏まえてこう行動した」というように、変化や改善のエピソードをセットで伝えてください。
感情だけを強調すると、共感は得られても評価にはつながりません。冷静な分析と前向きな姿勢を意識することで、聞き手に良い印象を与えられるはずです。
④企業が求める人物像に合っているかを見極める
どれほど感動的で完成度の高いエピソードでも、それが企業のニーズとずれていては効果的なアピールにはなりません。
企業ごとに重視する価値観や求める人物像は異なるため、事前に企業研究を行い、企業が大切にしているキーワードや行動指針を把握しておきましょう。
そして、自分のエピソードがその方向性と一致しているかを確認し、必要に応じて表現を調整することが大切です。
ほんの少し言い回しを変えるだけで、伝わり方がまったく違ってきます。エピソード選びは、企業とのマッチングを意識して行うと効果的です。
「人生で一番辛かったこと」の回答の構成

話の内容がどれほど良くても、構成が曖昧だと伝わりにくくなるため、話の流れを整理して質問に答えることが大切です。
ここでは、伝わりやすく魅力的なエピソードに仕上げるための5つのステップを紹介します。
- 辛かったことの概要を簡潔に述べる
- 辛さを数値などで客観的に伝える
- 乗り越えるために工夫した点を伝える
- 結果どうなったかを明確にする
- その経験から得たことを今後どう活かすかを伝える
①辛かったことの概要を簡潔に述べる
まずは、その出来事がいつ・どこで・どのように起きたのかを簡潔に伝えてください。
細かい背景よりも、「大学2年のゼミでリーダーを任された」「アルバイトでクレーム対応に苦戦した」など、聞き手がすぐに状況を想像できるようにまとめることが重要です。
詳細にこだわるよりも、ストーリーの軸を明確にする意識を持ちましょう。出だしが整理されていれば、聞き手は内容に集中しやすくなり、伝えたいポイントもしっかり届きます。
話の冒頭でつまずくと全体の印象に響くため、端的で分かりやすい導入を心がけてください。
②辛さを数値などで客観的に伝える
辛さを伝える際には、感情だけでなく、客観的な要素を交えて説明することが大切です。
「毎日深夜まで課題に取り組んだ」「3人中2人が辞めた中で1人で業務を回した」など、数字や具体的な状況を加えることで、聞き手がイメージしやすくなります。
主観だけに頼ると説得力に欠けてしまうため、なるべく事実に基づいた根拠を示しましょう。
また、第三者の視点でも納得できるような説明に仕上げることで、面接官に「その辛さは本当に大変だったのだ」と伝わりやすくなります。再現性のある表現を意識してください。
③乗り越えるために工夫した点を伝える
どんなに困難な状況であっても、それをどう乗り越えたかが最も重視されます。
「相談の頻度を増やした」「スケジュールを細かく立てて行動した」など、具体的な工夫や努力のプロセスを丁寧に伝えてください。行動の裏にある考え方や狙いをセットで語ると、説得力が高まります。
また、他人任せではなく、自ら状況を改善しようとした主体的な姿勢が評価されるでしょう。「あきらめずに改善策を模索した」というような粘り強さも、企業が注目するポイントです。
努力が結果にどうつながったのかも、できる限り明確にしましょう。
④結果どうなったかを明確にする
努力の結果として、どんな変化が起きたのかをわかりやすく伝えることが重要です。
「チーム全体の成果が向上した」「お客様から感謝の言葉をもらえた」など、目に見える結果があると話に説得力が増します。
たとえ大きな成功に至らなくても、「状況が改善した」「信頼関係が築けた」など、前向きな変化を具体的に表現しましょう。
また、他人からの評価や周囲の反応も付け加えることで、より客観性が高まります。結果の描写が弱いと、せっかくの努力が伝わりにくくなるため、成果を自信をもって語ってください。
⑤その経験から得たことを今後どう活かすかを伝える
話の締めくくりでは、辛かった経験をどのように自分の糧にし、今後にどう活かすかを伝えてください。
「計画性の重要性を実感した」「対人スキルを伸ばすきっかけになった」など、自分の成長を具体的に言語化できると良いでしょう。
そのうえで、志望する企業でどのように役立てたいかを結びつけると、面接官に強い印象を与えることができます。
過去の経験に終始せず、未来への意欲や前向きな姿勢を示すことが、評価につながることも。成長を継続できる人物として印象づけましょう。
「人生で一番辛かったこと」を伝える際のポイント

面接で「人生で一番辛かったこと」を聞かれた際は、ただ苦しかった出来事を語るのではなく、その経験から自分がどう成長したかを伝えることが大切です。
説得力のあるエピソードにするためには、以下のポイントを意識してください。
- 客観的にイメージできるように伝える
- 前向きな姿勢で取り組んだことを示す
- 成果や結果を数字や事実で示す
- 学びや成長を未来につなげて伝える
- 企業が求める人物像と関連づける
①客観的にイメージできるように伝える
抽象的な表現だけでは、相手に伝わりにくくなります。たとえば「部活が大変だった」では、どの程度大変だったのか、どのような状況だったのかが伝わりません。
一方で、「週6日、朝6時から3時間の練習を半年間続けた」「ケガをしたメンバーの代わりに2つのポジションを兼任した」などと具体的に述べることで、聞き手はその状況を明確に想像できます。
自分の体験を第三者にも分かりやすく伝えるには、数字や時間、場所などの情報を交えて、映像が浮かぶような説明を意識すると良いでしょう。
②前向きな姿勢で取り組んだことを示す
ただ「辛かった」と述べるだけでは、面接官の心に残ることは少ないでしょう。むしろ、その困難にどう向き合ったかが重要なポイントです。
「人間関係に悩んだが、自分から積極的に話しかけて少しずつ信頼を築いた」「連携が取れなかったチームに働きかけてミーティングを提案した」など、自分から行動を起こした姿勢を伝えることで、主体性や改善に向けた意欲が伝わります。
困難な場面で逃げずに取り組んだエピソードは、信頼性や実行力を評価されやすくするための大きな要素となるでしょう。
③成果や結果を数字や事実で示す
努力の成果を伝える際は、具体的な数字や事実を加えることで、説得力が格段に上がります。
たとえば「売上が20%向上した」「ゼミの出席率が60%から90%に改善した」「5人チームでの提案が採用された」といったように、誰が聞いても成果がわかる形にしましょう。
また、目に見える結果がない場合でも、「周囲から『変わったね』と声をかけてもらえた」「自分の提案がチーム内で採用された」など、行動が何かしらの変化を生んだことを伝えるのがポイントです。
主観的な表現だけでなく、客観的な評価を意識してください。
④学びや成長を未来につなげて伝える
どんなに素晴らしい経験であっても、それが今後にどう活きるのかが伝わらなければ、自己PRとしては弱くなります。
「継続する力を身につけたので、業務でも粘り強く取り組んで成果を出したい」「チーム全体を意識して行動する力を今後の協働にも活かしたい」といったように、自分の成長とそれを将来どう使っていくかを結びつけることで、面接官に将来性を感じてもらえるでしょう。
また、その学びが価値観や行動スタンスにどう結びついているのかも添えると、より深みのあるエピソードになります。
⑤企業が求める人物像と関連づける
最終的には、自分のエピソードが企業の求める人物像に合致していることを伝える必要があります。
もし、チームワークを重視する企業であれば、「チーム全体をまとめることに注力した経験」や「対話によって信頼関係を築いた話」が効果的です。
企業の理念や採用ページなどで求める人材像を確認し、自分のエピソードがその要素にどうつながるのかを明確にしておきましょう。
ただ語るだけではなく、聞き手である面接官の視点を意識し、「この人ならうちの会社で活躍してくれそうだ」と思ってもらえるような構成を意識してください。
面接で好印象を与える「人生で一番辛かったこと」の例文

「人生で一番辛かったこと」と言われても、どんな内容を話せばよいか悩む就活生は多いものです。ここでは、面接官に好印象を与える具体的なエピソード例文を10パターン紹介します。
自身の経験に近いものを参考にしながら、自分らしい回答を組み立てていきましょう。
- アルバイトのトラブル対応を乗り越えた例文
- 受験勉強での挫折と復活の例文
- 部活動でのリーダーとしての苦労と成長の例文
- 文化祭・体育祭など学校行事の責任と達成の例文
- 兄弟との比較で自信を持てなかった経験を伝える例文
- サークルでの人間関係の悩みと改善の例文
- インターンでの失敗と改善の例文
- 初めての一人暮らしでの困難を乗り越えた例文
- 人前で話すことが苦手だった自分の克服体験の例文
- 長期目標に向けて継続した努力の経験を伝える例文
面接でどんな質問が飛んでくるのか分からず、不安を感じていませんか?とくに初めての一次面接では、想定外の質問に戸惑ってしまう方も少なくありません。
そんな方は、就活マガジン編集部が用意した「面接質問集100選」をダウンロードして、よく聞かれる質問を事前に確認して不安を解消しましょう。
また、孤独な面接対策が「不安」「疲れた」方はあなたの専属メンターにお悩み相談をしてみてください。
①アルバイトのトラブル対応を乗り越えた例文
ここでは、アルバイト先でのトラブルをきっかけに、自分なりに考えて行動し、状況を改善した経験を例文として紹介します。責任感や行動力をアピールしたい人におすすめです。
| 私は大学2年のとき、飲食店のホールスタッフとしてアルバイトをした経験があります。ある日、予約のダブルブッキングが発生し、お客様同士のクレームが同時に起きてしまいました。 責任者が不在の中、私はすぐに他のスタッフと連携し、空いている席へのご案内やドリンクのサービスを提案して、お客様の不満を和らげようと行動しました。 それでも不安が残ったため、後日改めて店舗のマネージャーと話し合い、予約管理のルールを見直すよう提案したのです。 結果的に、予約確認のフローが改善され、同様のトラブルは起きなくなりました。この経験を通じて、トラブルが起きたときこそ冷静に判断し、主体的に動くことの大切さを学びました。 |
この例文では、トラブル対応だけでなく「その後どう行動したか」までを明確に伝えることで主体性をアピールしています。自分がどんな役割を果たしたかを具体的に書くことがポイントです。
②受験勉強での挫折と復活の例文
ここでは、大学受験において思うような結果が出せずに挫折しながらも、努力を継続して乗り越えた経験を紹介します。継続力や目標への姿勢を伝えたいときに有効です。
| 高校3年生のとき、第一志望だった大学の推薦入試に落ちてしまい、大きなショックを受けた経験があります。それまで順調に成績を上げてきたこともあり、自信を失い、数日間は勉強の手がつかない状態でした。 しかし、このままでは終われないという思いから、一般入試に向けて気持ちを切り替え、今まで以上に計画的に学習に取り組むことにしたのです。 特に苦手だった英語は、毎日音読と復習を欠かさず続けた結果、模試の偏差値が10以上上がりました。 最終的には第二志望の大学に合格し、失敗から学んだ「継続する力」の大切さを実感しました。この経験は、目標に対して粘り強く取り組む自信につながっています。 |
この例文では、落ち込んだ状態からどうやって立ち直ったかを明確に描くことで、継続力や行動力を印象づけています。復活の過程を丁寧に描くのがポイントです。
③部活動でのリーダーとしての苦労と成長の例文
ここでは、部活動の中でリーダーを任され、メンバーとの意見の違いや役割の重さに悩みながらも、成長につなげたエピソードを紹介します。責任感やチームワーク力を伝えたい方に適したエピソードです。
| 大学のバドミントンサークルで副代表を務めた際、練習方針を巡ってメンバーの間に対立が生まれ、運営がうまくいかなくなった時期がありました。 私は当初、自分の意見を通そうとしてしまい、かえって状況を悪化させてしまいました。しかし、何が問題なのかを冷静に見直し、一人ひとりと対話を重ねる中で、相手の考えに耳を傾ける姿勢の大切さを実感。 その結果、練習内容をみんなで話し合って決める形に変更し、徐々にサークルの雰囲気が改善されました。 リーダーとは引っ張るだけでなく、支えることも大事だと気づいたこの経験は、今後チームで働く上でも活かせると考えています。 |
この例文は、リーダーとしての「失敗」と「改善」の流れが明確で共感を呼びやすくなっています。自分の役割と変化を具体的に伝えることが成功のコツです。
④文化祭・体育祭など学校行事の責任と達成の例文
ここでは、大学の学園祭で実行委員を務め、大きなプレッシャーと向き合いながら成功に導いた経験を紹介します。計画力やリーダーシップをアピールしたい方におすすめです。
| 大学2年生のとき、学園祭のステージ企画を担当する実行委員になった経験があります。出演者のスケジュール調整や会場設営の責任を任され、準備の初期段階から大きなプレッシャーを感じていました。 特に、開催1週間前に主要出演者がキャンセルを申し出たときは、頭が真っ白になりましたが、すぐに代替案を考え、他のサークルに出演交渉を行いました。 短期間で調整を終えたことで、無事にプログラムを成立させることができたのです。本番当日は観客の笑顔を見て、努力が報われたと実感しました。 この経験を通じて、トラブルが起きても冷静に行動する力や、目標に向かって粘り強く取り組む大切さを学びました。 |
この例文では、行事運営の中で直面した具体的な問題と、それにどう対応したかを描いています。準備や当日の行動も含めて、過程を丁寧に伝えることがポイントです。
⑤兄弟との比較で自信を持てなかった経験を伝える例文
ここでは、兄弟と比べられることへのコンプレックスを乗り越え、自分らしさを見つけていった経験を紹介します。自分の成長過程や内面の変化を伝えたい方に適したテーマです。
| 私には2歳上の兄がいて、昔から成績や運動などあらゆる面で優れており、家族や親戚から比較されることが多くありました。 特に高校時代は、兄と同じ進学校に通っていたため、常に「兄のようにできないのか」と言われ、自信を失うことも多かったです。 しかし、大学に入って環境が変わったことで、他人と比べるのではなく、自分が何を大切にしたいかを考えるようになりました。 ゼミ活動では自分の意見を積極的に発言し、企画にも主体的に関わった結果、先生からも評価されるようになり、自信がついてきました。 この経験から、他人と比べるよりも、自分のペースで前に進むことの大切さを学べたと思います。 |
この例文では「比較されて苦しんだ過去」から「自分らしさを見つけた現在」への変化が丁寧に描かれています。内面的な成長を伝えるには、気持ちの変化を具体的に言語化しましょう。
⑥サークルでの人間関係の悩みと改善の例文
ここでは、大学のサークル活動において人間関係の不和に悩みながらも、対話を重ねて関係を改善した経験を紹介します。対人スキルや協調性を伝えたい方におすすめです。
| 大学のダンスサークルに所属していた際、練習方針を巡って同学年のメンバーと意見が合わず、ギスギスした雰囲気が続いていました。 当初は自分の主張を通そうとしがちでしたが、練習の成果が出ない状況が続いたことで「このままではいけない」と感じ、思い切って相手に話しかけ、互いの考えを冷静に伝え合う場を設けることにしたのです。 対話を重ねる中で、相手にも熱意があることに気づき、共通の目標を再確認できたことで関係が徐々に改善され、最終的には学園祭の舞台で成功を収めることができました。 この経験から、対立を恐れずに向き合い、歩み寄る姿勢の大切さを学びました。 |
この例文では、感情的な対立からどう建設的な対話へつなげたかが明確に描かれています。人間関係のテーマでは、「変化のきっかけ」と「行動の具体性」が重要です。
⑦インターンでの失敗と改善の例文
ここでは、インターンシップ中に経験した失敗をきっかけに、反省と改善を重ねて成長につなげたエピソードを紹介します。責任感や課題解決力を伝えたい方におすすめです。
| 大学3年生の夏、IT企業での1か月間のインターンに参加した際、チームで新サービスの企画を任されたことがあります。 私はアイデア出しや発表準備の中心を担いましたが、他のメンバーとの役割分担があいまいなまま進めてしまい、最終プレゼン直前に全体の構成がバラバラであることが発覚しました。 自分の責任を痛感し、その場で全員に謝罪し、徹夜で構成を再調整。発表当日はなんとか形にすることができました。 その後は必ずタスクを可視化し、情報共有を徹底するよう心がけました。この経験から、チームで動く際には「全体を見る意識」と「早めの共有」が欠かせないと学びました。 |
この例文では、失敗からどう立て直したかを具体的に示し、責任感や改善力をアピールしています。失敗経験を書く際は、最後に「得た学び」を必ず入れましょう。
⑧初めての一人暮らしでの困難を乗り越えた例文
ここでは、実家を離れて初めて一人暮らしを始めた際に直面した、不安や孤独をどう乗り越えたのかという経験を紹介します。自立心や問題解決力を伝えたい方におすすめです。
| 大学進学を機に地元を離れ、初めての一人暮らしを始めた当初、生活リズムや食事の管理、人との関わりのなさに強い不安を感じていました。 特に、慣れない環境の中で体調を崩したときは、誰にも頼れないことに孤独感が増し、「戻りたい」と思うほど辛く感じていたのを覚えています。 しかし、それを機に生活リズムを見直し、近所のスーパーでの買い物や、大学のサークル活動への参加を積極的に行うようにしました。 次第に地域や大学の人とのつながりができ、自分の居場所を感じられるようになったのです。この経験から、自ら行動することで環境は変えられるという自信を得ることができました。 |
この例文では、初期の辛さから自分の力で改善へ向かった流れを丁寧に描いています。身近なテーマでも、行動と気づきを具体的に書くことで説得力が生まれます。
⑨人前で話すことが苦手だった自分の克服体験の例文
ここでは、人前で話すことへの苦手意識を克服するために努力した経験を紹介します。自己成長や挑戦をテーマにしたい方に適したエピソードです。
| 私はもともと人前で話すことが極端に苦手で、教室での発表や自己紹介の場面でも声が震えてしまうほどでした。 大学1年のプレゼン課題でうまく話せず、グループに迷惑をかけた経験をきっかけに、このままではいけないと感じるようになったのです。 そこで、2年生からはスピーチ系のサークルに入り、毎週の練習を通して場数を踏むように心がけました。 最初は緊張で言葉に詰まることもありましたが、少しずつ周囲の反応を見ながら話せるようになり、最終的には学内のプレゼン大会にも出場するまでに成長できました。 この経験を通じて、苦手意識は努力で乗り越えられることを実感しています。 |
この例文では、苦手なことへの挑戦と成長の過程が具体的に描かれています。変化のきっかけと継続した行動をセットで語ると説得力が増します。
⑩長期目標に向けて継続した努力の経験を伝える例文
ここでは、長期間にわたって目標に取り組み続けた努力の過程と、それによって得た成長を描いたエピソードを紹介します。継続力や自己管理能力を伝えたい方におすすめです。
| 私は大学入学と同時に、英語のスピーキング力を伸ばすことを目標に掲げました。 将来、海外の企業とも関わる仕事がしたいという想いから、TOEICのスコアアップと実践的な会話力の習得を目指しました。最初はうまく話せない自分に落ち込み、勉強をやめたくなったことも。 しかし、「1日15分でも続ける」を自分に課し、毎日英語日記やオンライン英会話に取り組みました。 1年半後、TOEICでは200点以上スコアが伸び、英語でのディスカッションにも積極的に参加できるようになったのです。 この経験を通じて、小さな努力を積み重ねることの大切さと、それが自信に変わることを実感しました。 |
この例文では、目標達成に向けた地道な努力の継続と成果を具体的に伝えています。継続テーマでは「習慣化」と「成果の見える化」を意識して書くと効果的です。
面接で「人生で一番辛かったこと」を話すときのNG例
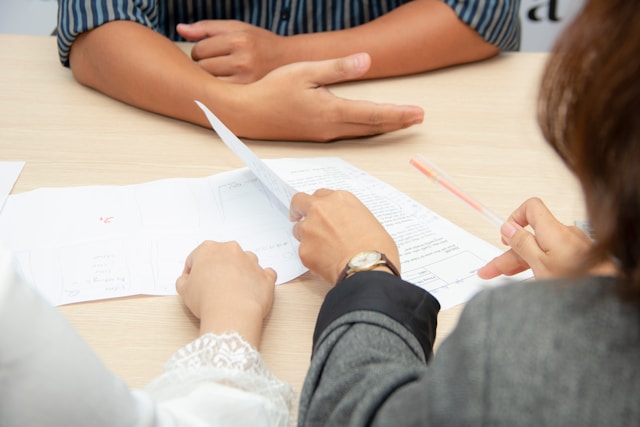
就職活動では、話し方や内容によってはマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。たとえ実際に辛かった経験でも、伝え方を間違えると評価を下げかねません。
ここでは、避けるべきNG例を紹介します。
- 愚痴や他者批判に聞こえる内容を話す
- 身内の不幸などプライベートすぎる内容を伝える
- 嘘や盛ったエピソードを話す
- 同情を引くような話し方をする
- 克服できていない経験を話す
①愚痴や他者批判に聞こえる内容を話す
誰かの言動が原因でつらい思いをした場合でも、その相手を責めるような表現は避けたほうがよいでしょう。
「上司が理不尽だった」「先輩が非協力的だった」などの言い方は、受け手にネガティブな印象を与えてしまいます。
面接では、相手の落ち度ではなく、その状況に自分がどう対応したか、どんな工夫や行動を取ったかに焦点を当てることが大切です。
問題が起きたときに人のせいにせず、自分なりに前向きに取り組んだ姿勢を見せることで、信頼や共感を得やすくなるでしょう。
②身内の不幸などプライベートすぎる内容を伝える
家庭内の問題や身近な人の不幸といった、非常にプライベートな内容は、面接の場にそぐわないテーマです。聞く側が反応に困ったり、面接全体の雰囲気が沈んでしまったりする恐れがあります。
また、そうした話題は仕事に直結しにくく、あなたの人柄や価値観を判断する材料としても適していません。
代わりに、大学生活やアルバイト、サークル活動など、比較的客観的に共有できる経験の中から題材を選ぶと、面接官にも受け入れられやすくなるはずです。
③嘘や盛ったエピソードを話す
「印象に残るような話をしたい」「他の人より目立ちたい」と思うあまり、実際の経験を誇張したり、まったく異なる話を作ってしまったりするのは絶対に避けてください。
面接では突っ込んだ質問が続くこともあるため、細部で矛盾が生じればすぐに信頼を損ないます。嘘がばれるリスクを背負うよりも、自分の言葉でリアルな体験を丁寧に語るほうが、はるかに好印象です。
自信がなくても構いません。あなたらしいエピソードで、等身大の魅力を伝えることが、最終的には評価につながります。
④同情を引くような話し方をする
辛い経験を語る際に感情がこもるのは自然なことですが、話し方によっては「同情してほしい」という印象を与えてしまうことがあります。
「あの頃は本当に苦しかった」「誰も助けてくれなかった」といった表現ばかりでは、聞き手が気まずさを感じたり、あなたの成長を見出せなかったりする可能性があるでしょう。
重要なのは、困難にどう向き合い、そこから何を学んだかを伝えることです。自分の経験を前向きに捉え直し、今につながっていることをアピールすれば、より好意的に受け取られるでしょう。
⑤克服できていない経験を話す
面接で話す内容としては、すでに自分なりの結論や変化がある経験を選ぶことが望ましいです。
現在も引きずっているような問題や、どう向き合うべきかが定まっていない話題を出すと、「この人はまだ自己理解が浅いのでは」と思われてしまうかもしれません。
もちろん、完全な成功体験である必要はありませんが、「その後どう変われたか」「何を意識するようになったか」といった視点を盛り込むと、前向きな印象を与えやすくなります。
面接は成長や可能性をアピールする場であることを忘れないようにしてください。
面接で「人生で一番辛かったこと」を伝える際の注意点

面接で辛かったエピソードを話すときは、内容や伝え方に注意が必要です。正直に伝えることは大切ですが、話し方によってはマイナスの印象を与えるおそれもあります。
以下の5つのポイントに気をつけると、より説得力のある伝え方ができるでしょう。
- 苦労話だけで終わらせないようにする
- 辛さの程度が極端になりすぎないようにする
- 感情だけに頼った説明にならないようにする
- 構成が支離滅裂にならないようにする
- 企業にネガティブな印象を与えないようにする
①苦労話だけで終わらせないようにする
ただ「大変だった」「辛かった」と伝えるだけでは、面接官に努力や成長が伝わらず、印象に残りにくくなります。
大切なのは、その状況にどう向き合い、自分でどのように乗り越えようとしたのかを具体的に語ることです。
たとえば「アルバイトでトラブルが続いたが、周囲と協力して対応した」「サークルで孤立していたが、信頼関係を築く努力をした」など、自分の行動や工夫を含めて伝えることで、前向きな姿勢や問題解決力をアピールできます。
面接官が知りたいのは経験の内容以上に、その経験からどう変わったか、何を学んだかです。
②辛さの程度が極端になりすぎないようにする
あまりにも重すぎる話や深刻な体験は、面接官がどうリアクションしていいか分からず、場の空気が重くなるリスクがあります。
たとえば家庭内の複雑な事情や心の病に関する話題などは、慎重に扱う必要があるでしょう。
もちろん嘘をつく必要はありませんが、就活の場では、仕事や人間関係、学業など「日常的に起こり得る困難」に絞ったほうが適切です。
そうしたエピソードであれば、聞き手も共感しやすく、自分との距離を感じさせません。伝えたい内容が極端に重い場合は、言葉や切り口を工夫して、できるだけ前向きに伝えるよう意識しましょう。
③感情だけに頼った説明にならないようにする
「本当に悔しかった」「当時は悲しくて仕方なかった」など、感情を強調するだけの話し方は、聞き手に伝わりにくいことがあります。
共感を得るためには、何が起きて、どのように自分が対応したのかという具体的な状況を示すことが必要。感情は補足的な要素として扱い、その背景や行動、結果をしっかり語ることが大切です。
たとえば「努力が報われなかったことが悔しかったが、自分の行動を見直して別のアプローチを取った」といったように、経験のなかで自らがどう動いたかを軸に構成すると、より説得力のある内容になります。
④構成が支離滅裂にならないようにする
せっかく良いエピソードを選んでも、話の流れがバラバラだと、内容が伝わりにくくなる可能性があります。
時系列が前後したり、言いたいことが整理されていなかったりすると、聞き手は混乱してしまうことも。そこで役立つのが、PREP法(Point→Reason→Example→Point)です。
この流れに沿って話を組み立てれば、自然と論理的で分かりやすい内容になります。また、話す前に紙に書き出して整理しておくと、面接当日もスムーズに説明できるようになるでしょう。
自分の話を客観的に構造化しておくことが、伝える力を高める第一歩です。
⑤企業にネガティブな印象を与えないようにする
「人生で一番辛かったこと」はセンシティブな話題でもあるため、話し方を間違えると相手に重苦しい印象を与えてしまうおそれがあります。
暗い表情や悲しそうなトーンで話すと、相手の気持ちも沈んでしまい、面接の流れが悪くなることも。
同じエピソードでも「この経験を通して、自分の弱さを認められるようになった」「今ではその経験が強みになっている」といった前向きな表現に変換することで、聞き手も安心して話に耳を傾けやすくなります。
相手の立場を意識した話し方が、就活では非常に重要です。
「人生で一番辛かったこと」がない場合の対処法

面接で「人生で一番辛かったこと」を聞かれたとき、具体的な経験が思い浮かばず不安に感じる方もいるでしょう。ですが、無理にエピソードを作る必要はありません。
自分の経験や価値観を見つめ直すことで、伝えられる材料は見つかるはずです。ここでは、困難な経験がないと感じている人に向けた対処法を紹介します。
- 自己分析を通じて「小さな困難」を探す
- 過去の挑戦や努力からエピソードを見つける
- これからの挑戦を「未来形エピソード」として準備する
- 困難を感じにくい自分の特徴を強みに変換する
①自己分析を通じて「小さな困難」を探す
人生のなかで誰しもが直面する「ちょっとした困難」は、立派なエピソードになります。
大きな試練でなくても、「苦手なことに向き合った」「不得意分野にチャレンジした」など、自分なりに壁を感じた出来事があれば、それで十分です。
人前で話すのが苦手だったけれど、プレゼンに挑戦したというような経験も、立派な題材になります。
自己分析を通して自分の価値観や行動パターンを振り返れば、小さな努力や変化の積み重ねが見えてくるでしょう。大切なのは、困難の大小ではなく、それに対する自分の姿勢や向き合い方です。
②過去の挑戦や努力からエピソードを見つける
明確に「辛い」と感じた記憶がない場合でも、何かに真剣に取り組んだ経験を丁寧に振り返ってみてください。そこには、自然と困難や乗り越えた壁が含まれているもの。
たとえば、部活動でポジション争いを経験した、アルバイトでトラブル対応を任された、ゼミで資料作成に苦労したなど、工夫や努力を要した場面はきっとあったはずです。
自分にとっての挑戦とは何だったのかを見つめ直し、そこにどんな工夫や気づきがあったかを言葉にしていきましょう。
「どれだけ苦しかったか」ではなく「どう行動したか」を丁寧に伝えることで、十分な説得力を持たせることができます。
③これからの挑戦を「未来形エピソード」として準備する
過去にこれといった困難が思い浮かばない場合は、これから取り組もうとしている挑戦をテーマにする方法もあります。
たとえば「TOEICで800点を目指して毎日勉強している」「未経験の分野で長期インターンに参加する予定がある」など、具体的な目標や計画を語ることで、主体性や向上心を十分にアピールが可能です。
重要なのは、これからどんな困難が予想され、それに対してどのような姿勢で臨もうとしているかを明確にすること。
未来形で語る場合でも、思いや覚悟が伝われば、面接官の印象に残る内容になります。過去の実績にとらわれすぎず、前向きな意欲を表現しましょう。
④困難を感じにくい自分の特徴を強みに変換する
「人生で一番辛かったことが思い浮かばない」と感じる背景には、実はポジティブな特性が隠れている場合があります。
物事を前向きに受け止められる性格だったり、どんな環境にも柔軟に対応できたりする人は、強いストレスを感じにくい傾向があるでしょう。
そうした性格や思考の特性は、社会人になってからも大きな強みになります。無理にドラマチックな話を作ろうとするのではなく、「自分は困難を困難と感じすぎないタイプです。
その分、冷静に物事を判断し、前に進める強さがあります」と自然体で伝えることが大切です。自分らしさを肯定的に捉え、自信を持って表現してください。
「人生で一番辛かったこと」に関するよくある質問

質問をされたとき、どこまで話してよいのか、内容の深さや感情表現の程度に悩む人は多いでしょう。ここでは、よくある5つの質問に対して、就活生が安心して答えられるようなヒントを紹介します。
- 「辛かったこと」と「苦労したこと」は同じ?
- どこまで詳しく話せばいい?
- 面接で泣いてしまいそうな内容でも話していい?
- エピソードが複数ある場合はどうする?
- 緊張してうまく話せないときはどうすればいい?
①「辛かったこと」と「苦労したこと」は同じ?
「苦労したこと」と「辛かったこと」は混同されがちですが、実は少し意味合いが異なります。
「苦労したこと」は物理的・時間的な努力や工夫を要した経験が中心であるのに対し、「辛かったこと」は気持ちの面での負担や精神的なストレスが強調される傾向があるでしょう。
ただし、企業が本当に知りたいのは、その困難に対してどんな考えを持ち、どう乗り越えたのかという点です。
どちらの表現を使っても問題はありませんが、エピソードを通じて自分の成長や変化が伝わるようにすることが大切。自分の経験のどの部分に重点を置くかを意識すると、話しやすくなります。
②どこまで詳しく話せばいい?
エピソードの話し方には、簡潔さと具体性のバランスが求められます。詳細すぎると時間がかかり、抽象的すぎると伝わりません。
基本は「背景→課題→行動→結果」という構成で整理し、自分がどんな判断をし、どんな行動をしたかを中心に述べると効果的です。
また、数字やエピソードの具体的な描写を交えることで、聞き手が状況をイメージしやすくなります。
ただし、細部にこだわりすぎて本筋がぼやけないよう注意が必要です。面接時間を考慮して、伝えるべきポイントを優先順位をつけて組み立てることを意識しましょう。
③面接で泣いてしまいそうな内容でも話していい?
涙が出てしまうようなエピソードは、それだけ思い入れが強く、心を動かされた経験であるともいえます。
そうした話をすること自体は問題ありませんが、冷静に話す準備ができているかどうかが重要です。感情的になりすぎると、話の流れが乱れて伝わらなくなってしまう可能性があります。
事前に何度も練習を行い、感情をコントロールできる状態で本番に臨むようにしてください。穏やかなトーンで丁寧に話せば、誠実さや本気度が伝わり、かえって好印象になることもあります。
無理に感情を抑える必要はありませんが、伝えたいポイントがぶれないように心がけましょう。
④エピソードが複数ある場合はどうする?
複数のエピソードが思い浮かんだ場合は、それぞれを比較し、最も効果的なものを選ぶことが大切です。
ポイントは、企業が求める人物像と照らし合わせて、自分の経験がどれだけマッチしているかを見極めること。
たとえば、チームワークを重視する会社であれば、集団での取り組みや人との関わりが強調されたエピソードが適しています。
また、自分自身が最も成長を感じられた出来事を選ぶと、話す際に自然と熱量が伝わるはずです。迷ったときは、それぞれのエピソードを紙に書き出し、整理してから比較するのも有効な手段でしょう。
⑤緊張してうまく話せないときはどうすればいい?
面接で緊張してしまうのは、多くの人にとって自然なこと。大切なのは、緊張を無理に克服しようとせず、それでも自分の考えを伝えようとする姿勢です。
うまく話せなくても、誠実に向き合っている様子が伝われば、面接官の印象が悪くなることはありません。事前によくある質問に対する答えを用意し、繰り返し練習することで、少しずつ自信もついてきます。
話し方を丸暗記するのではなく、自分の言葉で説明できるようになると、多少言葉が詰まっても落ち着いて対応できるでしょう。完璧を目指すより、自分らしく話すことを意識して臨んでください。
面接での「人生で一番辛かったこと」の伝え方を理解しておこう!

「人生で一番辛かったこと」は、就活で定番の質問です。その意図や答え方を理解し、適切なエピソードを選んで準備することが、面接での印象アップにつながります。
具体的には、企業の求める人物像と自分の経験を重ね合わせ、前向きな姿勢で乗り越えた実例を示すことがポイントです。さらに、話す際の構成や表現の仕方、避けるべきNG例なども意識しましょう。
もし強いエピソードが思い浮かばない場合でも、小さな困難や未来の挑戦を軸に話を組み立てることで、十分に自分の強みを伝えることは可能です。
「辛かったこと」は単なる過去の出来事ではなく、成長の証としての伝え方が求められます。面接官に「この人と働きたい」と思ってもらえるよう、しっかり準備してください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













