公務員の適性試験とは?内容と対策|適性検査との違いも解説
「公務員の適性試験って、どんな内容が出るんだろう…」と不安に感じる方は多いですよね。
適性試験は知識を問う筆記試験とは異なり、計算力や判断力、注意力など職務遂行に必要な基礎能力を測る重要な選考ステップです。出題形式や評価方法を理解せずに挑むと、本来の力を発揮できないこともあります。
そこで本記事では、公務員の適性試験の概要や出題傾向、効果的な対策方法を解説し、突破に向けた学習ポイントやおすすめ問題集もあわせて紹介します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員の適性試験とは

公務員試験における適性試験とは、知識ではなく注意力や処理能力、正確な思考力などを評価するためのものです。内容は計算や図形把握など多岐にわたります。
業務遂行に必要な基礎能力を測るため、多くの自治体で導入されているのです。なかには基礎能力試験と並んで重視される場合もあり、無視できません。
軽視されがちですが、適性試験で足切りになるケースもあります。全体の得点が高くても、基準点に満たなければ不合格となるリスクが伴うのです。
合格を目指すなら、形式に慣れましょう。模試や過去問を繰り返し解くことで、効率的に処理する力を養い、得点力の向上を期待できます。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
公務員の適性試験と適性検査の違い

公務員試験では、「適性試験」と「適性検査」という似た名称が使われますが、それぞれ目的や内容、評価方法が異なります。
混同すると誤った対策をしてしまうおそれがあるため、正確な違いを知っておくことが大切です。ここでは、それぞれの観点から違いを分かりやすく解説します。
- 目的
- 出題形式
- 試験内容
- 評価方法と扱われ方
①目的
適性試験と適性検査は、どちらも受験者の特性を把握するために行われますが、測定対象には明確な違いがあります。
適性試験は、注意力や反応の速さ、計算力など、公務に必要なスキルを短時間で発揮できるかどうかを判断するものです。
一方の適性検査には、性格傾向や価値観、人との関わり方などを通じて、組織との相性や対人能力を見極める目的があります。
混同したまま対策を進めると、重要な準備を忘れてしまう恐れがあります。目的を理解し、正しく備えることが重要です。
②出題形式
適性試験と適性検査では、出題形式も大きく異なります。
適性試験は、マークシート方式の選択問題が中心です。時間制限の中で、正確かつ素早く解ける能力が求められます。数字や図形を扱う問題が多く、反応速度や集中力、空間認識力などが試されるのです。
一方、適性検査はアンケート形式が基本です。「あなたは新しい環境にすぐ慣れるタイプですか?」など、性格や考え方に関する質問に対して、自分の感覚で回答します。選択肢は、「当てはまる」「どちらともいえない」「当てはまらない」などが一般的です。
どちらも対策の方向性が異なるため、形式に慣れておくことが重要。
特に適性試験では時間配分がカギとなるため、模擬問題で練習を積んでおくと安心でしょう。
③試験内容
適性試験は、処理能力や視覚判断、空間認識、集中力など、業務に直結する能力を確認するための問題が中心です。
具体的には、「同じ数字の並びを見つける」「回転させた図形を正しく選ぶ」「単純な計算をすばやく繰り返す」など、シンプルながらミスしやすい問題が出題されます。スピードと正確さのバランスが問われるため、事前に問題傾向に慣れておくことが大切です。
適性検査は、それとは異なり、性格傾向を測定する内容が中心。「はい・いいえ」で答える形式が多く、判断に迷わず、自分に正直に答えることが求められます。
特に注意したいのは、矛盾する回答や極端に偏った答えを選んでしまうと、一貫性がないと判断され、評価が下がる可能性がある点です。正解・不正解はないとはいえ、落ち着いて一貫性のある受け答えができるよう意識してください。
④評価方法と扱われ方
適性試験と適性検査では、評価の仕組みと選考での扱い方も異なるのです。
まず、適性試験は数値として得点化されます。基準点に達しない場合には、足切りの対象となるケースもあるため、他の筆記試験と同様に対策が必要です。
一方、適性検査は点数化されることはほとんどなく、人事担当者が受験者の人物像を把握するための参考資料として使われます。
面接や論文と組み合わせた総合評価の一部にすぎませんが、組織の求める人材像とあまりにかけ離れているとマイナス評価を受けることもあるでしょう。
このように、評価方法を正しく理解しないままでは、どちらかを軽視してしまうおそれがあります。両方に適切な対策をしておくことが、公務員試験を突破するための基本です。
公務員の適性試験の主な出題内容
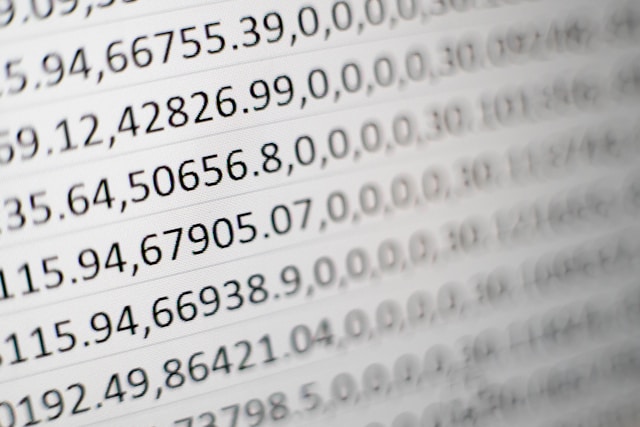
公務員の適性試験では、一般的な学力試験とは異なる形式の問題が出題されます。ここで問われるのは、知識の多さではなく、短時間で正確に情報を処理する力です。
職務に直結する事務処理能力を測るために設定されており、その内容や形式を理解しておくことが合格への近道となります。ここでは、主な出題形式とその特徴について解説します。
- 計算問題
- 分類問題
- 照合問題
- 置換問題
- 図形把握問題
- 複合問題
①計算問題
計算問題は、足し算・引き算・掛け算・割り算など、基本的な四則演算が中心です。高校数学のような複雑な知識は、基本的に求められません。
ただし、短時間で正確に処理する力が求められるため、計算そのものに慣れる練習が必要です。特に暗算力の向上が得点力を支えるカギになります。
ケアレスミスの防止には、桁数の確認や符号の見直しが効果的です。いきなりスピードを意識するのではなく、まずは正確に解く練習から始めましょう。
毎日の学習に計算ドリルやアプリを取り入れることで、処理能力の定着が図れます。計算問題でリズムをつかめると、その後の設問にも良い影響が期待できるでしょう。
②分類問題
分類問題では、与えられた情報を決められたルールに沿って整理する力が求められます。判断力と処理速度の両方が試される分野です。
出題形式には、数字や文字の性質に基づくもの、記号の法則を見抜くものなどがあります。一見シンプルでも、見極めに時間がかかることがあります。
確実に解くには、まず出題文を丁寧に読み、基準を見出す必要があります。どの視点で分類されているかを意識しながら、冷静に取り組むことが肝心です。
練習段階で多様なルールに触れておけば、初見の問題にも柔軟に対応できます。図形や画数、偶奇など、分類の切り口を広げておくと効果的です。
③照合問題
照合問題は、複数の情報を見比べて一致・不一致を判定する形式の問題です。数字や記号、文章の違いを瞬時に見抜く力が試されます。
見た目は単純でも、わずかな違いを探す作業には高い集中力が必要です。特に似た並びの中での微妙な違いを見逃さない観察眼が問われます。
効果的な対策としては、丁寧な照らし合わせを重ねて精度を高めることが基本です。慣れてきたら、徐々に処理スピードを意識していきましょう。
視線移動の練習を取り入れると、ミスの予防にもつながります。本番では深呼吸を挟みつつ、短時間でも集中の質を保つことが重要です。
④置換問題
置換問題とは、特定のルールに従って文字や記号を別のものへ変換する形式の問題です。たとえば、アルファベットと数字の対応などが代表例といえます。
他にも、漢字の部首を入れ替えたり、一定の法則で文字をずらしたりと、出題のパターンには幅があります。まずは基本的なルールに慣れることが大切です。
ルールが複雑な場合や途中で変化する場合には、混乱しやすくなります。こうした問題では、正確な読解と冷静な処理力が求められるでしょう。
練習では「図解」や「書き換え」を活用すると理解が深まります。本番では、丁寧さと時間管理の両立を意識しながら取り組むことが得点につながります。
⑤図形把握問題
図形把握問題では、展開図や鏡像、回転、対称性など、空間的な認識力が求められます。視覚情報を頭の中で処理する感覚が重要です。
苦手意識を持つ人も多く見られますが、理由の一つに「空間認識の訓練機会が少ない」という学校教育の影響が挙げられます。
まずは、図形を実際に描いてみる、折って確かめるなど、視覚と手を使った確認を習慣にすることが、理解を深める第一歩となるでしょう。
選択肢を照らし合わせる際には、全体ではなく部分的に注目する方法も効果的です。反復練習を通じて、形の動きを自然にイメージできる力を育ててください。
⑥複合問題
複合問題とは、計算・分類・照合など複数の出題形式が1問に組み込まれた応用的な問題です。処理手順の理解と柔軟な思考が求められます。
この形式は、最初のミスが連鎖して影響を及ぼす点が特徴です。慎重に手順を追いながら、情報を順序立てて扱う姿勢が重要となります。
問題を整理する際は、難しそうに見えても単純な作業の組み合わせにすぎないことを意識しましょう。全体の構造を把握すれば、解きやすさが変わってきます。
対策としては、単独形式の練習から始めて段階的に複合型へ移行するのが効果的です。優先順位を意識する習慣も、本番での冷静さにつながります。
公務員の適性試験で押さえるべき対策ポイント

公務員の適性試験では、限られた時間の中で正確かつスピーディーに解答する力が求められます。
ただし、やみくもに勉強しても成果にはつながりにくいため、試験の特徴を理解したうえで、自分に合った方法で対策を進めることが重要です。
ここでは、公務員の適性試験で押さえるべき具体的な対策ポイントを5つに分けて紹介します。
- 出題傾向を把握して効率よく学習する
- 計算や分類問題は繰り返し練習する
- 時間配分を意識して模試を活用する
- ミスを減らすためのチェック力を養う
- 本番を想定した環境で練習する
①出題傾向を把握して効率よく学習する
適性試験は職種や試験の種類によって出題内容が異なります。たとえば事務職では数字や図形を扱う問題が多く、警察官や消防官では反応速度や注意力が問われやすい傾向があるでしょう。
そのため、まずは志望先の過去問を確認して、どんな問題が出るのかを知ることが大切です。傾向を把握しておけば、必要な分野に集中して対策できるので、効率よく学習を進められます。
試験の構成や頻出テーマを理解していれば、初見の問題にも落ち着いて対応しやすくなるでしょう。
問題集をすべてこなそうとするのではなく、自分の志望先に合わせて「出やすい問題」に絞って対策を立てることが合格への近道です。
②計算や分類問題は繰り返し練習する
適性試験では、数字の計算や記号の分類など、比較的シンプルな問題が多く出題されます。内容自体は難しくないものの、制限時間があるためスピードと正確さが求められるのです。
このタイプの問題は、回数を重ねて練習することで確実に解答スピードが上がります。たとえば、毎日10分でもよいので、一定の量を反復練習してみてください。
慣れることで、感覚的に素早く処理できるようになります。また、よく出るパターンを意識しながら解いていくと、問題の構造を自然と理解できるようになるでしょう。
繰り返すうちに、どんな問題でも迷わず取り組めるようになるはずです。
③時間配分を意識して模試を活用する
時間配分は、適性試験における大きなカギ。1問にかけられる時間が短いため、焦ってしまうとミスにつながりやすくなります。そこで役立つのが模擬試験や時間を測っての過去問演習です。
タイマーを使って実際の制限時間を体感しておくと、本番でも焦らず対応しやすくなります。特に、どの問題に時間がかかるかを把握することで、自分に合ったペース配分をつかめるでしょう。
さらに、模試後には必ず振り返りを行い、間違えた原因や時間が足りなかった理由を分析してください。これを繰り返すことで、試験本番でもより冷静に対応できるようになります。
④ミスを減らすためのチェック力を養う
スピードが求められる一方で、正確さも非常に重要です。慌てて解答してしまうと、思い込みや読み飛ばしといったミスが発生しやすくなります。これを防ぐには、確認する習慣をつけることが効果的です。
たとえば、マークミスや設問の読み間違いといった単純なミスでも、点数を大きく落とす原因になりかねません。問題文をしっかり読んでから答えることを意識し、余裕があれば見直しの時間も設けてください。
また、自分がどんなミスをしやすいかを知ることも重要です。間違えた問題を記録しておくことで、同じ失敗を繰り返さずに済むでしょう。正確さを意識するだけで、総合的な得点力は着実に向上します。
⑤本番を想定した環境で練習する
どれだけ練習を重ねても、本番に緊張してしまうと実力を出し切れません。そのため、普段から本番と似た環境で勉強することが効果的です。
たとえば、静かな部屋でタイマーを使って問題を解くことで、試験本番の空気感を再現できます。机や椅子の高さ、使う筆記具などにもこだわると、当日の違和感を減らせるでしょう。
また、試験当日のスケジュールや移動時間も事前にシミュレーションしておくと、心に余裕が生まれます。服装や持ち物の準備も含めて「本番の一日」を意識して練習してください。
こうした積み重ねが、当日の不安をやわらげ、落ち着いて試験に臨む力につながっていきます。
公務員の適性試験の注意点

公務員の適性試験では、学力以外に注意力や性格の傾向が見られます。筆記試験とは違った準備が必要なうえ、ちょっとした油断が大きなミスにつながることもあるのです。
ここでは、適性試験を受ける際に特に注意したいポイントを整理しました。
- マークミスや記入漏れをしないようにする
- 足切り点を下回らないように得点を意識する
- 試験形式や時間の違いを事前に確認しておくようにする
- 練習不足で焦らないように十分に準備しておく
- 時間配分を誤らないように時間感覚を身につける
- 問題文を読み間違えないようにする
①マークミスや記入漏れをしないようにする
適性試験では、内容以前にマークシートのミスが大きな減点につながります。たとえば、番号を1つずらして塗ってしまったり、マークが薄すぎて読み取られなかったりする場合です。
こうした形式上のミスは、どれだけ内容が正しくても得点になりません。このような失敗を防ぐには、練習の段階から本番を意識した記入を習慣づけることが大切です。
市販の問題集や模試でも、シャープペンシルや鉛筆を使って正確にマークする練習をしておくと安心でしょう。
また、回答が終わったあとに一気に見直すのではなく、問題を解いたその都度マークを確認する癖をつけると、記入漏れやずれを早めに発見しやすくなります。
②足切り点を下回らないように得点を意識する
公務員試験では、適性試験が「参考程度」と思われがちですが、実際には足切りの基準が設けられている場合があります。
他の試験で高得点を取っていても、適性試験の得点が一定ラインを下回ると不合格になることも珍しくありません。
こうした仕組みに気づかないまま適性試験を軽視してしまうと、せっかくの努力が水の泡となってしまいます。
対策としては、最低限の点数を確保できるよう、苦手な問題形式を把握し、反復練習を重ねることが有効です。
出題傾向は自治体ごとに異なりますが、共通するパターンもあるため、過去問や類似問題を使って効率的に取り組みましょう。
③試験形式や時間の違いを事前に確認しておくようにする
適性試験は、受験する自治体や機関によって出題形式や所要時間が異なります。数分で終わるものもあれば、20分以上集中を要するものもあるため、思い込みで準備を進めるのは危険です。
対策の第一歩は、受験する自治体や機関の試験要項をよく読むこと。そこで試験形式が明示されていれば、それに合わせた練習を重ねる必要があります。
形式が不明な場合は、幅広いパターンの問題を解いて対応力を高めておくと良いでしょう。試験時間が短い場合は素早い判断力が、長い場合は集中力の持続が求められます。
自分が苦手とする形式を早めに見極めておくことも大切です。
④練習不足で焦らないように十分に準備しておく
適性試験は、単なる感覚や直感で乗り切れるものではありません。とくに図形や空間把握、数的処理のような問題は、慣れていないと時間ばかりかかってしまいます。
練習不足のまま試験に臨むと、思うように解けず焦ってしまい、本来の力が発揮できません。そうならないためには、日頃から少しずつ問題に取り組み、問題の形式と解き方に慣れておくことが効果的です。
また、時間を計りながら解く練習をすることで、実戦感覚も身につきます。完璧に仕上げる必要はありませんが、「この形式なら落ち着いて取り組める」という自信を持てる状態で試験日を迎えましょう。
⑤時間配分を誤らないように時間感覚を身につける
適性試験では、限られた時間内に多くの問題を解かなければなりません。1問ごとにじっくり考えていると、最後まで到達できずに時間切れになってしまうおそれがあるのです。
とくに注意したいのは、難問に時間をかけすぎて他の問題を解く余裕がなくなることです。試験中は時間を確認しながら、1問に何秒使えるかを意識しましょう。
事前の練習で「感覚的な時間配分」を身につけておくと、当日も落ち着いて対処しやすくなります。
時計を持参して、試験の開始時刻と終了時刻から逆算する癖をつけておくと、焦らずにペースを保つことができます。
⑥問題文を読み間違えないようにする
緊張していると、ちょっとした読み間違えで正しい答えを導き出せなくなることがあります。
特に「正しくないものを選べ」といった否定表現を含む設問では、うっかり逆の答えを選んでしまうことも少なくありません。
主語や述語、否定語などの要素をしっかり意識して、焦らずに問題文を読み進めましょう。内容を正しく理解したうえで答えを導くことが、安定した得点に直結します。
普段の練習でも、問題文を「早く読む」だけでなく「正確に読む」習慣をつけることがポイントです。焦りそうな場面こそ、ひと呼吸おいて確実に読み取る意識を持ってください。
公務員の適性試験対策におすすめの問題集

公務員の適性試験では、限られた時間の中で正確に問題を処理する力が求められます。そのため、対策には問題集をうまく活用することが効果的です。
出題傾向に合わせて練習を積み重ねれば、自信を持って試験に臨めるようになるでしょう。ここでは、就活生におすすめの問題集を紹介します。
- 高卒程度公務員 完全攻略問題集 2024年度版
- 公務員試験 適性試験対策 やればやるほど伸びるトレーニング
- スイスイとける事務能力検査
①高卒程度公務員 完全攻略問題集 2024年度版
この問題集は、公務員試験の初学者にも取り組みやすい構成で、基礎から応用へと段階的に理解を深められるよう設計されています。
高卒程度の出題範囲に対応し、数的処理や文章理解の基礎固めに最適です。過去の傾向を反映した問題を通じて、効率よく実力を養えます。
各問題には丁寧な解説が付属し、解き方まで徹底解説。間違えた原因を根本から理解でき、着実に得点力を伸ばせる点が魅力となっています。
単元ごとの確認テストで理解度を定期的に測定できるため、本試験を意識した計画的な学習にも活用しやすい一冊です。
商品はこちら:https://amzn.asia/d/1oX4et1
②公務員試験 適性試験対策 やればやるほど伸びるトレーニング
この問題集は、反復学習を重視しており、繰り返し解くことで自然と力がついていく構成になっています。問題の難易度が段階的に設定されているため、基礎が不安な方でも無理なく取り組めるでしょう。
計算・図形・分類など、適性試験で頻出の形式を網羅しており、幅広い力をバランスよく身につけることができます。
また、実際の試験を想定した時間設定や設問数で構成された模擬問題も含まれており、時間配分のトレーニングにも適しています。
本番に近い緊張感の中で練習を重ねることで、集中力やスピード感も養えるでしょう。問題数も豊富なので、自分の苦手分野を重点的に繰り返したい場合にも対応できます。
着実に得点力を上げたい人にとって、心強い一冊といえるでしょう。
商品はこちら:https://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/110555
③スイスイとける事務能力検査
この問題集は、特に事務系の公務員を目指す人に特化しており、実務で求められる基本的な能力を鍛えるのに適しているでしょう。
数字や文字の照合、分類、記号の置き換えなど、スピードと正確性の両方が求められる問題を数多く取り上げています。反復練習によって、業務に必要な基礎力が自然と身についていくでしょう。
また、各問題の出題意図や解答のポイントが簡潔にまとめられているため、復習しやすく効率的です。
実際の職場で行われる作業に近い内容が多いため、試験対策だけでなく、業務への適応力向上にもつながる内容になっています。スキマ時間に少しずつ進められるよう、短めの演習単位で構成されているのも特徴です。
忙しい学生や社会人受験者にとって、継続しやすい教材といえるでしょう。
商品はこちら:https://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/110769
公務員の適性試験を突破するために大切なこと

公務員の適性試験を受けるには、出題内容や試験形式、さらには適性検査との違いを正しく理解することが欠かせません。
なぜなら、出題される問題の種類や評価方法が多様であり、単なる学力だけでは対応しきれないからです。試験では計算や図形、照合といった複数の分野が出題されるため、対策の幅も広がります。
効率よく学ぶには出題傾向の把握や問題集の活用が有効ですし、本番を見据えた模試での練習も必要不可欠です。また、試験当日の注意点を押さえておくことで、ミスを最小限に抑えることができるでしょう。
公務員適性試験の結果は、事前の準備次第で大きく変わります。正しい知識と綿密な対策で、自信を持って本番に臨んでください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











