就活の座談会後はお礼メール必須?書き方と例文を解説
「座談会に参加したけど、終わったあとってメールすべきなのかな…?」
就活中に企業と直接話せる貴重な機会として注目されている座談会。社員のリアルな声を聞ける反面、その後の対応に迷う方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、座談会参加後のメールを送るべき理由から書き方のステップ、シーン別の例文まで、丁寧に解説していきます。
就活中のメール対応はこれだけでOK!
- ◎メールが最短3分で書けるテンプレシート
- 「このメールで失礼じゃないかな…」と悩みがちな場面でも、コピペするだけで安心してメールを送れる
座談会後にお礼メールは送るべき

結論から述べると、企業の座談会に参加した後は、お礼メールを送るべきです。
お礼を伝えることで、感謝の気持ちを表すだけでなく、企業側に「礼儀正しい」「志望度が高い」といった良い印象を与えられるからです。
企業の担当者は多くの学生と接していますが、その後に丁寧なフォローを行う学生は意外と少ないのが現実です。だからこそ、お礼メールを送るだけで他の学生と差をつけることができます。
さらに、メールの内容に工夫を加えれば、自分の印象を強く残したり、次の選考ステップにつなげるきっかけにもなります。
お礼メールを送らなかったからといって必ず不利になるわけではありませんが、送ることで得られるメリットは大きいため、迷わず実践するのがおすすめです。
就活における座談会とは

就活における「座談会」とは、企業の社員と学生が少人数で交流できる、カジュアルなイベントのことです。
説明会や面接と異なり、リラックスした雰囲気の中で実施されるため、社員の本音やリアルな職場の様子を聞ける貴重な場といえるでしょう。
1人では知り得ない情報や、企業の公式サイトには載っていない実情を知ることができるため、企業理解を深める上で大きなヒントになります。
ただ話を聞いて終わるのではなく、自分から質問する姿勢が大切です。企業側も学生の人柄や熱意を自然な形で見ています。
選考とは関係ないと考えて油断してしまうと、思わぬところで評価を下げる原因になりかねません。座談会の目的をしっかり意識して参加すれば、今後の選考にもプラスに働くはずです。
座談会のお礼メールに書くべき内容

座談会後に送るお礼メールは、「ありがとうございました」だけで終わらせるのではなく、感謝・学び・意欲を伝える構成にすることが大切です。内容を工夫することで、印象に残るメールになります。
ここでは、座談会後のメールに書くべき内容を5つ紹介します。
- 参加への感謝の気持ち
- 座談会で印象に残った話題や学び
- 自分の志望度や選考への意欲
- 今後の抱負や具体的な行動
- 会社や担当者への配慮
① 参加への感謝の気持ち
メールの冒頭では、座談会に参加させてもらったことへの感謝をしっかり伝えましょう。たとえば「お忙しいなか、お時間をいただきありがとうございました」と書くと、礼儀正しさが伝わります。
そこに「貴重なお話を伺えて、大変参考になりました」と続けると、内容をきちんと受け止めたことが自然に伝わるでしょう。
とくに、感謝の言葉は定型的な一文で終えるのではなく、どのように役立ったのか、自分にどう響いたのかを添えることで、心のこもった文章になります。
また、表面的な言葉遣いにならないように注意し、自分の言葉で気持ちを表現することが大切です。最初の一文で好印象を与えることが、その後の文章全体にもプラスに働きます。
② 座談会で印象に残った話題や学び
感謝のあとは、座談会で心に残った話題や印象に残った学びについて具体的に記述すると、内容への理解度や姿勢が伝わります。
たとえば「〇〇さんの“失敗から得た経験”という話に感銘を受けました」と書くだけでなく、なぜそう感じたのか、自分の経験とどう重なったのかも述べると、文章に深みが出るでしょう。
企業側は学生がどれほど真剣に話を聞いていたか、どのように受け止めたかを見ています。そのため、単なる事実の羅列や要約ではなく、自分なりの視点を加えることが重要です。
また、学んだことを今後どう活かしたいかも示すと、成長意欲や主体性も伝わります。一方的な感想にとどまらず、自分の考えとリンクさせて表現しましょう。
③ 自分の志望度や選考への意欲
お礼メールでは、企業の志望度や選考に対する意欲を伝えるようにしましょう。
意欲を伝えずに感謝だけで終えてしまうと、相手にとっては他の多くのメールと区別がつかなくなり、印象が薄れてしまう可能性があるためです。
大切なのは、意欲を伝える際に「なぜそう思ったのか」を一文添えることです。企業理念・文化・仕事内容・社員の姿勢など、何に惹かれたのかを具体的に述べるとよいでしょう。
具体的には「〇〇の取り組みに共感し、御社への志望度がさらに高まりました」「今後の選考にも積極的に参加したいと考えております」といった文章です。
志望動機の簡潔な補足として、メール全体に説得力を持たせる意識で書いてみてください。
④ 今後の抱負や具体的な行動
意欲を示すだけでなく、それに基づいた今後の行動計画や目標を言葉にすることで、信頼感や行動力をアピールできます。
「今回の座談会で得た気づきをもとに、自己分析を深めたいと思います」や「志望動機を見直す良い機会になりました」といった文があると、前向きな姿勢が伝わるでしょう。
さらに、「次回の説明会にも参加したい」「インターン応募を検討しています」など、具体的な予定や希望を添えると、行動につながる意欲がより明確になります。
この部分では、単に感想を述べるだけでなく、自分が次に何をするのかを宣言するようなイメージで構成すると良いでしょう。メールを読んだ相手にも、今後の接点を持ちやすい印象を残せます。
⑤ 会社や担当者への配慮
メールの締めくくりには、企業や担当者への気配りを添えるようにしましょう。
たとえば「暑い日が続いておりますので、どうぞご自愛ください」や「業務ご多忙のなか貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」といった一文です。
結びの言葉では「今後のご活躍をお祈りいたします」「またご連絡の機会がありましたら幸いです」なども活用できます。
ただし、あまりにも形式的で堅苦しい表現ばかりになると、かえって冷たく感じられてしまうこともあるため、自分の言葉で、シンプルかつ自然な表現を心がけましょう。
座談会のお礼メールの書き方ステップ
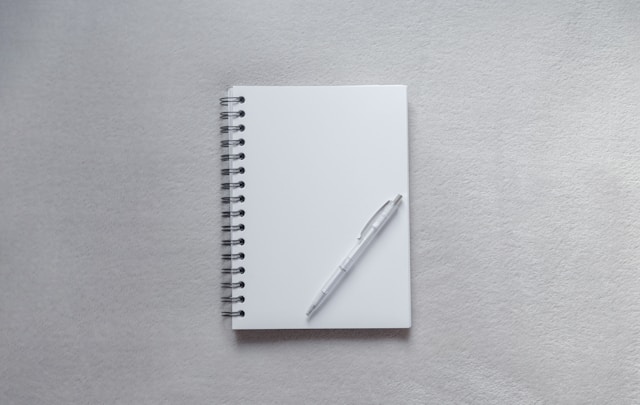
座談会後にお礼メールを送ると、企業に良い印象を残すことができます。ただ気持ちを伝えるだけでなく、マナーを意識した構成や表現も重要です。
ここでは、お礼メールを書く際に押さえておきたい6つのステップを紹介します。
- 宛先のメールアドレスを正確に入力する
- 件名は「○○座談会のお礼(氏名)」など簡潔にまとめる
- 宛名は「○○部 ○○様」と役職・氏名を正しく書く
- 本文は構成を意識して簡潔に書く
- 結びの言葉で丁寧に締めくくる
- 署名には大学名・学部・氏名・連絡先を明記する
① 宛先のメールアドレスを正確に入力する
お礼メールを送るときに、まず確認すべきなのが宛先のメールアドレスです。どれほど丁寧な文章でも、アドレスが間違っていれば相手には届きません。
特にスマートフォンでの入力は打ち間違いが起きやすいため、慎重にチェックしてください。送信前には、入力したアドレスが正しいかどうか再確認しましょう。
不安があれば、自分宛てにテストメールを送ってみるのもおすすめです。加えて、コピー&ペーストで入力した場合も、末尾に不要なスペースが入っていないか確認すると安心でしょう。
また、複数の担当者にメールを送る場合は、CCやBCCの使い方にも注意が必要です。
宛先の設定ミスによる情報漏洩や誤送信は、マナー以前の信頼問題になります。最初の入力段階から丁寧に対応しましょう。
② 件名は「○○座談会のお礼(氏名)」など簡潔にまとめる
件名は、メールを開くかどうかを左右する重要な部分です。
採用担当者は日々多くのメールを受け取っているため、「○月○日○○座談会のお礼(氏名)」のように、誰からの、どのようなメールかが一目で伝わる件名にしましょう。
「お世話になっております」や「こんにちは」などの汎用的な件名は避けてください。具体性が欠けると見落とされる可能性もあります。
送信時に自分で見てもわかりやすいか、確認するクセをつけると良いでしょう。また、件名を長くしすぎるとスマホなどで途中で切れてしまうため、伝えたい情報を簡潔にまとめることが大切です。
フォーマルな表現を意識しながら、配慮のある件名を工夫してください。
③ 宛名は「○○部 ○○様」と役職・氏名を正しく書く
メールの冒頭に書く宛名は、社会人としての基本的なマナーのひとつです。
わからない場合は「人事部 採用ご担当者様」でも構いませんが、座談会でお話しした社員の名前が分かっている場合は、可能な限り正しく記載しましょう。
たとえば「営業部 第二課 田中様」のように、部署名と氏名を丁寧に書くことで、相手への敬意が伝わります。また、漢字の表記間違いや、氏名の誤認にも気をつけるべきです。
]名刺や配布資料などを見返して、正確性を確認してください。敬称の重複にも注意しましょう。「〇〇様へ」や「〇〇さん様」などは誤りです。
「様」は一度だけ使用し、「〇〇部 〇〇様」と書くだけで十分丁寧です。こうした細かい部分に気を配る姿勢が、信頼につながります。
④ 本文は構成を意識して簡潔に書く
本文では、まず座談会に参加できたことへの感謝を述べるのが基本です。次に、印象に残った話題や具体的な学びに触れ、それをどのように活かしたいと感じたのかを簡潔に書くと良いでしょう。
たとえば「〇〇様の現場での体験談から、仕事への責任感を強く感じました」などの一文を加えると、内容が深まります。
さらに「御社で働きたいという気持ちがより一層強まりました」といった選考への意欲も添えておくと効果的です。
文章の長さは、短すぎると事務的に見えますし、長すぎると読みづらくなってしまいます。目安としては300〜400字程度を意識しましょう。
⑤ 結びの言葉で丁寧に締めくくる
本文の締めくくりには、感謝や今後の関係性に対する前向きな姿勢を示す結びを添えましょう。
たとえば、「今後とも何卒よろしくお願いいたします」や「今後の選考でもどうぞよろしくお願いいたします」といった表現です。
また、季節の挨拶や相手の健康を気遣う一文を加えると、さらに好印象を与えます。「季節の変わり目ですので、ご自愛くださいませ」といった表現もよいでしょう。
自然体で気遣いを表現できると、社会人らしい文章になります。
⑥ 署名には大学名・学部・氏名・連絡先を明記する
メールの最後には署名を付け、自分の基本情報をしっかり明記しましょう。内容としては「大学名・学部・学年・氏名・電話番号・メールアドレス」が基本です。
選考の案内や連絡を受ける際にも、この情報が役立ちます。署名は簡単なようでいて、誤字や情報漏れが起こりやすい箇所です。
送信前には必ず見直し、特に電話番号やアドレスに間違いがないかを確認してください。内容が正しくても連絡が取れなければ意味がありません。
また、メールソフトやアプリに署名テンプレートを登録しておけば、毎回手入力する手間が省けてミスも防げます。社会人になってからも使える習慣なので慣れておきましょう。
座談会のお礼メールの例文

座談会のあとは感謝の気持ちを伝えたいと思っていても、どのように言葉にすればいいか迷うこともありますよね。
ここでは、実際の場面を想定したお礼メールの例文を紹介します。
- 座談会で学びを得た場合の例文
- 本選考への意欲を強調した例文
- 志望動機を再確認したい場合の例文
- 社員との会話が印象に残った場合の例文
- カジュアルな雰囲気の座談会向け例文
- 業界研究を深められた場合の例文
- 複数社員と話せたことに感謝する例文
また、ビジネスメールがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジン編集部が作成したメール自動作成シートを試してみてください!
ビジネスマナーを押さえたメールが【名前・大学名】などの簡単な基本情報を入れるだけで出来上がります。
「面接の日程調整・辞退・リスケ」など、就活で起きうるシーン全てに対応しており、企業からのメールへの返信も作成できるので、早く楽に質の高いメールの作成ができますよ。
①座談会で学びを得た場合の例文
座談会で得た気づきを具体的に共有しながら、学んだ内容を今後に生かす姿勢を示す例文です。感謝→学び→活用→締め、の順で構成しつつ、文量を適切にまとめて読みやすさにも配慮しましょう。
《例文》
| 件名:〇月〇日開催 座談会のお礼(〇〇大学〇〇) 株式会社〇〇 人事部 〇〇様 昨日は学生向け座談会にお招きいただき、誠にありがとうございました。〇〇様が語られた「入社後の失敗を共有する文化」が特に印象的で、挑戦を後押しする御社の風土を深く理解できました。 私は研究室でも後輩の挑戦を支える役割を担っており、この経験を生かしながら御社でも積極的に新しい課題に取り組みたいと考えております。 今後の選考機会がございましたら、ぜひご指導ください。取り急ぎ御礼申し上げます。末筆ながら、〇〇様の益々のご活躍をお祈りいたします。 〇〇大学〇〇学部 氏名:〇〇〇〇 電話番号:080-XXXX-XXXX メールアドレス:xxxx@example.com |
上記の【メールは自動作成シート】で作成したものです
《解説》
感謝のあとで学びを具体化し、自分の経験と結び付けると説得力が増します。締めくくりでは次の選考への意欲を短く添え、前向きな印象で終えるよう意識してください。
②本選考への意欲を強調した例文
本選考に向けた強い意欲を伝える例文です。座談会を通じて得た学びを起点に、将来像や企業への魅力を具体的に伝える構成が効果的です。
《例文》
| 件名:〇月〇日開催 座談会のお礼(〇〇大学〇〇) 株式会社〇〇 人事部 〇〇様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。 昨日は学生向け座談会にご招待いただき、誠にありがとうございました。 〇〇様が語られていた「入社後の失敗を共有する文化」が特に印象的で、挑戦を歓迎する御社の風土を深く理解することができました。 私は研究室で後輩のサポート役を担っており、挑戦を支える姿勢を大切にしてきました。 この経験を生かし、御社でも積極的に新しい課題に取り組んでいきたいと考えております。 今後の選考機会がございましたら、ぜひご指導いただけますと幸いです。 取り急ぎ御礼を申し上げますとともに、〇〇様のますますのご活躍をお祈り申し上げます。 〇〇大学〇〇学部 氏名:〇〇〇〇 電話番号:080-XXXX-XXXX メールアドレス:xxxx@example.com |
上記の【メールは自動作成シート】で作成したものです
《解説》
企業に対する具体的な共感ポイントを挙げたうえで、自分の経験と結び付けて意欲を伝えると効果的です。抽象的な熱意ではなく、行動に裏打ちされた姿勢を見せることが大切でしょう。
③志望動機を再確認したい場合の例文
座談会を通じて、もともと持っていた志望動機を再認識したケースでは、その動機がさらに強まった理由を具体的に伝えると説得力が増します。
《例文》
| 件名:〇月〇日開催 座談会のお礼(〇〇大学〇〇) 株式会社〇〇 人事部 〇〇様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。 昨日は貴重な座談会にご招待いただき、誠にありがとうございました。 〇〇様のお話の中で、若手のうちから責任ある仕事に挑戦できる環境があると伺い、御社で働くイメージがより明確になりました。 私はゼミ活動でイベント企画の責任者を務めた経験があり、周囲を巻き込む調整力や計画力には自信があります。 座談会を通じて、御社で自分の力をさらに試してみたいという思いが一層強まりました。 今後の選考にもぜひ参加させていただきたく、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 〇〇大学〇〇学部 氏名:〇〇〇〇 電話番号:080-XXXX-XXXX メールアドレス:xxxx@example.com |
上記の【メールは自動作成シート】で作成したものです
《解説》
志望動機を「再確認した理由」と「自分の原体験」に結び付けて書くと、より深みのある内容になります。体験とリンクさせることでオリジナリティも伝えられるでしょう。
④社員との会話が印象に残った場合の例文
座談会で社員との会話が心に残った場合は、その具体的なエピソードと自分の感想を交えてお礼メールに反映させることで、印象的な内容に仕上がります。
《例文》
| 件名:〇月〇日座談会のお礼(〇〇大学〇〇) 株式会社〇〇 人事部 〇〇様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。 昨日はお忙しい中、座談会の機会をいただき誠にありがとうございました。 〇〇様がお話しされていた「新入社員のうちから裁量を持って働ける」という点が、特に印象に残っております。 大学のサークル活動でリーダーを任された際、自分で考えて動くことの難しさとやりがいを実感した経験があり、御社の風土に大きな魅力を感じました。 実際に現場で働かれている方から直接お話を伺えたことで、企業理解がより一層深まりました。 その結果、御社で働きたいという思いが一段と強まりました。 今後の選考にも、ぜひ参加させていただきたく存じます。 引き続き、何卒よろしくお願いいたします。 〇〇大学〇〇学部 氏名:〇〇〇〇 電話番号:080-XXXX-XXXX メールアドレス:xxxx@example.com |
《解説》
会話の中で印象に残った内容を明確にし、自分の体験とリンクさせて伝えるのがポイントです。「なぜ心に残ったのか」を補足すると説得力が増します。
⑤カジュアルな雰囲気の座談会向け例文
カジュアルな雰囲気の座談会では、形式にとらわれすぎず、感謝の気持ちや親しみを込めた文面が好印象につながります。自然体で丁寧な言葉遣いを意識しましょう。
《例文》
| 件名:〇月〇日座談会のお礼(〇〇大学〇〇) 株式会社〇〇 人事部 〇〇様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。 昨日は学生向け座談会にご招待いただき、誠にありがとうございました。 終始なごやかな雰囲気で、緊張せずにリラックスして参加することができました。 特に、〇〇様が話されていた「入社前のギャップ」についてのエピソードは、笑いも交えてお話しくださったおかげでとても印象に残っております。 そのお話を通じて、企業選びにおいて大切にしたいポイントを改めて考えるきっかけにもなりました。 実際に社員の方と直接お話しできたことで、御社の魅力をより身近に感じました。 今後の選考にもぜひ参加させていただきたく存じます。 本当にありがとうございました。 〇〇大学〇〇学部 氏名:〇〇〇〇 電話番号:080-XXXX-XXXX メールアドレス:xxxx@example.com |
《解説》
カジュアルな座談会では、丁寧さを保ちつつもややフランクな表現を取り入れると好印象です。自然な言葉選びと共感を意識して書くのがコツ。
⑥業界研究を深められた場合の例文
座談会で業界理解が深まった場合は、学んだ内容とともに今後の行動意欲を伝えると、主体性がある印象を与えることができます。
《例文》
| 件名:〇月〇日座談会のお礼(〇〇大学〇〇) 株式会社〇〇 人事部 〇〇様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。 昨日は貴重な座談会の機会をいただき、誠にありがとうございました。 〇〇様のお話を通じて、御社が業界内で果たしている役割や今後の展望について深く理解することができ、大変有意義な時間となりました。 これまで業界研究に自信が持てず悩んでいたのですが、現場の視点からリアルなお話を伺えたことで、自分の理解に自信を持てるようになりました。 特に「変化に強い企業づくり」というお考えに強く共感し、これからの企業選びの軸にもなりそうです。 今回の学びをもとに、今後の選考に向けてさらに理解を深めてまいります。 このたびは本当にありがとうございました。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。 〇〇大学〇〇学部 氏名:〇〇〇〇 電話番号:080-XXXX-XXXX メールアドレス:xxxx@example.com |
《解説》
業界理解が深まったことを感謝とともに伝える際は、印象に残ったキーワードや考え方を具体的に書くと説得力が増します。自分の変化や今後の行動にも触れましょう。
⑦複数社員と話せたことに感謝する例文
複数の社員と直接話すことができた座談会では、異なる視点や価値観に触れたことへの感謝を具体的に伝えると、真剣さと誠実さが伝わります。
《例文》
| 件名:〇月〇日座談会のお礼(〇〇大学〇〇) 株式会社〇〇 人事部 〇〇様 お世話になっております。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。 昨日は学生向け座談会に参加させていただき、誠にありがとうございました。 複数の社員の方々と直接お話を伺うことができ、非常に貴重な機会となりました。 同じ会社の中でも多様な価値観や働き方があることを知り、大変刺激を受けました。 特に〇〇部の〇〇様が語っておられた「失敗を恐れず行動する姿勢」には強く共感し、自分もより前向きに挑戦する姿勢を大切にしていきたいと感じました。 それぞれの立場や視点からのお話を通じて、御社で働くイメージがより具体的に描けるようになりました。 今後の選考にもぜひ参加させていただきたく、何卒よろしくお願いいたします。 〇〇大学〇〇学部 氏名:〇〇〇〇 電話番号:080-XXXX-XXXX メールアドレス:xxxx@example.com |
《解説》
複数人との会話で得た気づきや印象に残った話題を具体的に挙げると、内容に厚みが出ます。個別の名前やエピソードを入れるとより誠実な印象になるでしょう。
座談会のお礼メールの注意点

座談会後にお礼メールを送る際は、ただ送ればいいというものではありません。いくつかのポイントに気をつけるだけで、相手に与える印象が大きく変わります。
ここでは、お礼メールを送る際の注意点を5つ紹介します。
- メールは24時間以内に送信する
- 件名・宛名・署名に誤字脱字がないか確認する
- 定型文のコピペだけにならないよう注意する
- ネガティブな内容は避ける
- 長文になりすぎないよう簡潔にまとめる
① メールは24時間以内に送信する
お礼メールはできるだけ早く送るのが基本です。可能であれば座談会の当日中、遅くとも24時間以内に送信しましょう。
時間が経つにつれ相手の記憶も薄れてしまい、せっかくの感謝の気持ちが伝わりにくくなる可能性があります。
また、スピーディーな対応は「マナーがある」「行動が早い」といった好印象を与えやすく、ビジネスの現場でも大切な資質と見なされてしまうでしょう。
文面の表現に悩んだ場合でも、あまり時間をかけすぎず、自分の言葉で丁寧にまとめて送ることを意識しましょう。メールを送るタイミングも評価の一部と考えて行動するのがポイントです。
② 件名・宛名・署名に誤字脱字がないか確認する
どれだけ内容のある文章を書いたとしても、件名や宛名、署名に誤字や脱字があれば、受け取る側の印象は一気に下がってしまいます。
特に相手の名前や会社名を間違えるのは失礼にあたるため、注意が必要です。送信前には必ず、氏名や役職名、メールアドレスなどを一文字ずつ確認しましょう。
読み間違いや変換ミスが起こりやすいため、読み返す際には音読するのも有効です。署名も同様に大切です。大学名や学部名、連絡先に誤りがあると、企業側が再度連絡を取ろうとした際に支障が出ます。
文面の中身以上に、こうした基本的な項目の正確さが信頼を生みます。初歩的な部分こそ、丁寧に見直してください。
③ 定型文のコピペだけにならないよう注意する
インターネットには多くのお礼メールのテンプレートが掲載されていますが、それをそのままコピーしてしまうと、あなたらしさがまったく伝わりません。
企業の担当者は多数のメールを受け取っており、テンプレート文はすぐに見抜かれてしまいます。テンプレートを参考にすること自体は問題ありません。
ただし、印象に残った具体的なエピソードや自分の感想をしっかり盛り込むことで、自分の言葉としての信ぴょう性や誠意が伝わるメールになります。
たとえば「〇〇さんのお話に感銘を受けました」と書く場合は、どんな話だったのか、なぜ心に残ったのかを一文でも添えるだけで、印象は大きく変わります。
コピペではなく「自分の声」で伝えることを意識しましょう。
④ ネガティブな内容は避ける
お礼メールでは前向きな内容に徹することが鉄則です。
たとえ座談会で疑問に感じた点や納得できなかった点があったとしても、それをそのままメールに書いてしまうと、読む側に違和感や負担を与えてしまうおそれがあります。
たとえば「〇〇の話はよく理解できませんでした」「少し話が難しかったです」といった表現は、たとえ正直な感想であっても、お礼の場にはふさわしくありません。
意図せずネガティブな印象を与えることもあります。質問したい内容がある場合は、別の機会を使って丁寧に問い合わせましょう。
お礼メールはあくまで感謝と前向きな姿勢を伝えるものであり、指摘や改善要求を含める場ではないことを意識してください。
⑤ 長文になりすぎないよう簡潔にまとめる
感謝・学び・意欲など、伝えたいことが多くなりがちなお礼メールですが、相手の時間を考えると簡潔にまとめることがとても大切です。
目安としては全体で300〜400字程度に抑えると、負担なく読んでもらえる内容になります。伝えたい内容をすべて詰め込もうとすると、文が長くなり読みづらくなってしまいます。
段落ごとに要点を整理し、無駄な修飾語を減らすことで、文章はよりスッキリと伝わるのです。また、1文1文の長さにも注意してください。読点が多く続く長文は、相手の理解を妨げます。
読み返しながらテンポの良い文章に整えることで、全体の印象も大きく向上します。読みやすさも就活のマナーの一部と考えましょう。
お礼メールで座談会での印象をプラスに変えよう!

就活における座談会は、企業と学生が直接交流できる貴重な場です。そこで得た学びや気づきを丁寧に伝える「お礼メール」は、他の学生と差をつけるチャンスでもあります。
本文の構成や件名、署名など細かい点にも気を配れば、誠実さや志望度が自然と伝わるでしょう。座談会後の行動次第で、あなたの印象は大きく変わります。
実際、メールを通じて企業側に良い印象を残したいと考える学生は多く、正しい書き方やマナーを知ることが重要です。
メール1通に気持ちを込めて、次のステップへつなげてください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









