内定取り消しの主な理由は?正しい対処法と撤回を求める方法
この記事では、内定取り消しの理由を解説しています。
実際に内定取り消しをされてしまった場合の違法性の有無や実際の対処法も紹介していますよ。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
内定取り消しになった場合は落ち着いて行動しよう

突然「内定取り消し」の連絡を受けると、大きな不安や焦りに襲われるでしょう。しかし、感情的に反応する前に、まずは冷静さを取り戻すことが大切です。
落ち着いて状況を把握すれば、今後の対応も判断しやすくなるでしょう。ここでは、内定取り消しを告げられたときに、まず取るべき姿勢について解説します。
就職活動の終盤、ようやく得た内定が取り消されるとなると、心に大きなショックを受けるのは当然です。しかし、その場で感情的に反応してしまうと、思わぬ不利益を招くおそれがあります。
たとえば、怒りのまま企業へ連絡をしたり、SNSに投稿してしまったりすると、冷静な交渉のチャンスを失ってしまうかもしれません。
まずは深呼吸をして気持ちを落ち着け、自分が置かれている状況を客観的に整理することが必要です。内定取り消しには企業側の都合だけでなく、法的に問題のあるケースも含まれています。
事実を正しく把握すれば、適切な対応策が見えてくるはずです。焦って行動するのではなく、一度立ち止まり、落ち着いて次の一手を考える姿勢が、将来を守る第一歩になるでしょう。
内定取り消しは違法?

就職活動の中でようやく勝ち取った内定が、突然取り消されると知ったとき、不安や疑問が一気に押し寄せるでしょう。
とくに、「内定取り消しは法律的に問題ないのか?」という点は、多くの就活生が気になるところです。
ここでは、企業の内定取り消しが違法と判断されるケースと、正当な理由がある場合の違いについて説明します。
内定取り消しは、状況によっては違法とされることがあります。一般に、企業が内定を出した時点で労働契約が成立しているとみなされ、その契約を一方的に取り消すには合理的な理由が必要です。
たとえば、応募者が経歴を偽っていたり、重大な犯罪歴が明らかになったり、健康上の重大な問題が発覚した場合などは、内定を出した前提が崩れるため、企業に正当性が認められる可能性があります。
一方で、業績悪化や人員調整といった企業都合による内定取り消しは、原則として違法と判断されることが多いです。
このような場合には、労働基準監督署や弁護士に相談することで、損害賠償請求が認められることもあるでしょう。
企業の都合によって一方的に内定を取り消されたときには、泣き寝入りせず、まず自分の状況を冷静に整理してください。その上で、信頼できる相談窓口に助けを求めることが重要です。
内定取り消しになる主な理由
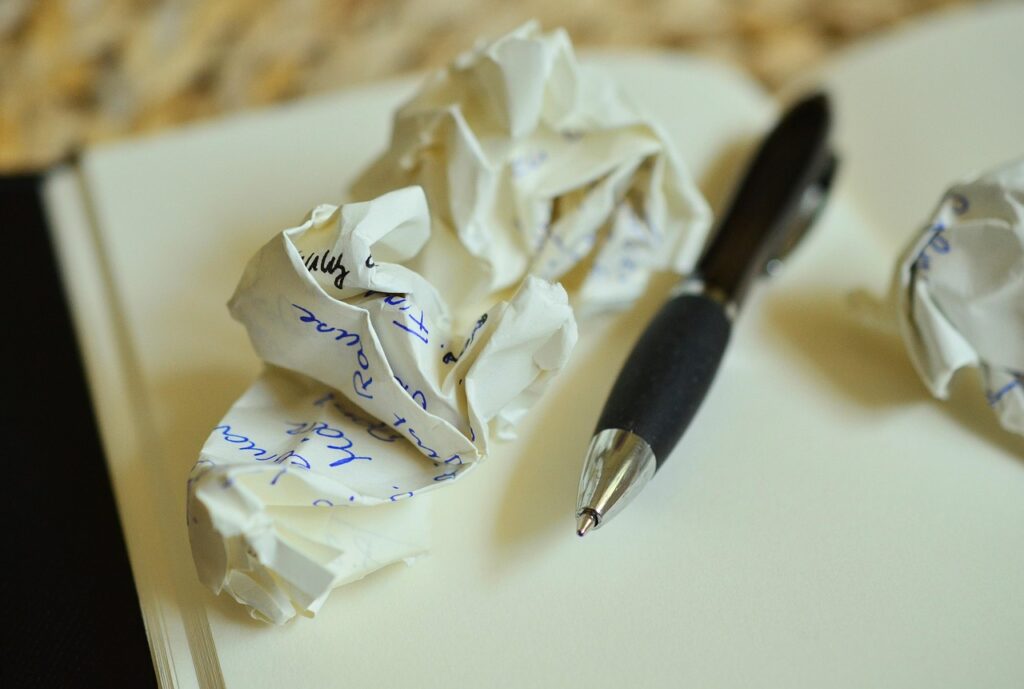
内定が取り消される背景には、学生側に原因がある場合と、企業側の都合によるものがあります。ここでは代表的な理由を整理し、それぞれのケースでどのようなことに注意すべきかを解説します。
なかには回避できるものもあるため、あらかじめ把握しておくと安心です。
- 卒業できない・単位不足だから
- 健康状態の悪化や怪我により働けないと判断されたから
- 経歴詐称や応募書類の虚偽記載が発覚したから
- SNSでの不適切な投稿など素行に問題があったから
- 必要な資格が取得できていなかったから
- 犯罪行為や違法行為が明らかになったから
- 企業の経営悪化や採用計画の変更があったから
- 採用枠の見直しで他の候補者を優先する判断がされたから
- 業務内容の変更により求められる人材像が変わったから
- 新規プロジェクトの中止により採用ニーズがなくなったから
① 卒業できない・単位不足だから
大学を卒業できなければ、正社員として入社する資格を満たせません。内定は卒業を前提として出されているため、単位不足が判明した時点で取り消される可能性があります。
特に卒業見込みで進行している採用では、最終学年での単位未修得が大きなリスクです。普段から履修状況を定期的に確認し、卒業要件を常に意識して学業に取り組むことが欠かせません。
内定が出たからといって気を抜くのではなく、最後まで計画的に単位を取得する努力が必要でしょう。
② 健康状態の悪化や怪我により働けないと判断されたから
企業は、内定者が入社後に継続的に働けることを前提に採用しています。
そのため、健康診断の結果が著しく悪かったり、大きな怪我をして業務遂行が困難だと判断された場合、内定取り消しに至ることもあるのです。
もちろん体調不良は不可抗力ですが、体調の変化に気づいた時点で早めに通院するなど、自己管理が求められます。また、体調が理由である場合は、企業に正確な情報を伝えることが大切です。
相談次第では配慮を受けられる可能性もあるため、一人で抱え込まないようにしましょう。
③ 経歴詐称や応募書類の虚偽記載が発覚したから
就活においては、自分をよく見せたいという気持ちから、経歴を少し盛ってしまうという誘惑があるかもしれません。
しかし、意図的な虚偽記載や事実と異なる情報は、発覚した時点で企業の信頼を著しく損ねます。たとえ小さな内容でも、信頼を前提にした内定では信用失墜が致命的です。
提出書類やエントリーシートは、必ず正確な情報を記入し、事実に基づいた内容で自己PRを構成しましょう。不明点があれば大学のキャリアセンターなどで確認することもおすすめです。
④ SNSでの不適切な投稿など素行に問題があったから
SNSは就活生にとって身近なツールですが、そこに書いた内容は思った以上に多くの人に見られています。
過去の投稿が企業関係者の目に留まり、炎上や社会的問題を起こすようなものであれば、企業イメージを損なうとして内定取り消しの対象になり得ます。
特に公序良俗に反する内容や、差別的・暴力的な発言は避けるべきです。アカウントの公開範囲を見直し、投稿内容を整理するなど、社会人としてふさわしい情報発信を心がけてください。
⑤ 必要な資格が取得できていなかったから
職種によっては、内定条件として資格取得が必須とされていることがあります。たとえば教員免許や薬剤師資格などが代表的です。
企業側は、入社時点でその資格を保有していることを前提に採用しているため、取得できなかった場合には内定を取り消されるリスクが高まります。
資格試験の勉強は就活と並行して行う必要があるため、計画的なスケジュール管理が欠かせません。不安な点がある場合は、早めに担当者に相談しておくとよいでしょう。
⑥ 犯罪行為や違法行為が明らかになったから
刑事事件への関与や、法令に違反する行為が明るみに出た場合、企業の信用問題に発展する可能性があるため、内定取り消しはほぼ避けられません。
たとえ事件として扱われなくても、社会通念上問題があると判断される行動が判明した場合も同様です。
内定後も「学生だから許される」といった油断はせず、社会の一員としての自覚を持って行動しましょう。トラブルに巻き込まれた場合には、早めに大学や信頼できる第三者に相談することが望ましいです。
⑦ 企業の経営悪化や採用計画の変更があったから
企業の経営が急速に悪化したり、予期せぬ業績不振が続いた場合、採用計画の見直しによって内定を取り消されるケースがあります。こうした事情は学生側では予測できず、防ぎようがありません。
ニュースなどで志望企業の業績情報を把握しておくと、多少の備えにはなりますが、実際に取り消しになった場合は迅速に気持ちを切り替えることも大切です。
再就活や他の選択肢に向けた行動を早めに始めることで、精神的なダメージも最小限に抑えられるでしょう。
⑧ 採用枠の見直しで他の候補者を優先する判断がされたから
採用方針が変更された結果、他の候補者を優先するために内定が取り消されることがあります。企業側の都合ではありますが、対応が一方的すぎると不当解雇とみなされる可能性も。
そのため、取り消しの理由が不明確だったり説明に納得できなかったりする場合は、大学のキャリアセンターや労働相談機関など第三者に相談してみましょう。
感情的に反応するのではなく、事実確認と適切な対応を冷静に行うことが重要です。
⑨ 業務内容の変更により求められる人材像が変わったから
企業の組織変更や戦略転換により、採用時点では必要だった人材像が変わることがあります。
その影響で、これまでの内定者が想定していたポジションに適さないと判断され、内定を取り消される場合も考えられるでしょう。
個人としての責任ではないものの、予期せぬ変化に戸惑うこともあります。このようなケースでは、ポジティブに捉え直して、今後のキャリアを再設計するチャンスとする前向きな考え方が大切です。
⑩ 新規プロジェクトの中止により採用ニーズがなくなったから
特定のプロジェクトに合わせて行われた採用の場合、その計画が途中で中止となれば、内定が不要になることがあります。
企業側の経営判断であるため、学生に非はないものの、急な変更に戸惑うのは当然です。
こうした場合でも、補償措置や説明責任が企業に求められることがあります。もし納得できない点があるなら、大学や第三者機関への相談を検討し、事実関係を丁寧に確認して対応してください。
内定取り消しになった場合の対処法

内定が取り消されたときは、驚きや不安で冷静に動けなくなるかもしれません。しかし、状況に応じた適切な対応を知っていれば、今後の選択肢を広げることができるでしょう。
ここでは、内定取り消しに直面した際に考えるべき行動を紹介します。
- 企業に内定取り消しの理由を口頭で確認する
- 内定通知など証拠となる書類やメールを保管する
- 大学のキャリアセンターに相談する
- 労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する
- 就活を継続する場合の準備を始める
- 第三者に同席してもらい企業と話すことを検討する
①企業に内定取り消しの理由を口頭で確認する
突然内定を取り消された場合、まず企業に理由を確認してください。納得できる説明があれば対応もしやすくなりますし、不当な理由であれば異議を申し立てるきっかけになります。
曖昧な返答や説明を避けようとする態度が見られる場合は、話の内容を記録し、後の行動に備えることが大切です。早い段階で理由を明確にしておくことで、その後の対応がスムーズに進むでしょう。
②内定通知など証拠となる書類やメールを保管する
企業とのやり取りを示す書類やメールは、今後の相談や交渉で役立ちます。特に、内定通知や内定承諾の連絡などは、契約成立を裏付ける証拠になる場合があります。
削除せず、わかりやすい形で保存しておきましょう。紙の書類だけでなく、メールやメッセージのスクリーンショットも有効です。いざというときに備えて、しっかり整理しておくと安心でしょう。
③大学のキャリアセンターに相談する
悩んだときには、大学のキャリアセンターに相談するのが効果的です。専門のスタッフが、就職に関するアドバイスや企業対応の方法を教えてくれます。
過去に似たようなケースを扱った経験があることも多く、実例をもとにした具体的な支援が期待できるでしょう。
必要に応じて大学から企業へ連絡を入れることもあり、一人で悩むより心強いサポートになるはずです。
④労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する
企業の対応が不適切だと感じたら、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談しましょう。これらの機関では、労働問題の専門知識を持つ担当者が無料で相談に乗ってくれます。
違法性の有無や適切な対応策など、自分では気づかない視点からアドバイスがもらえるはずです。証拠がそろっていれば、より具体的な助言が受けられます。
少しでも迷ったら、まずは一度連絡してみてください。
⑤就活を継続する場合の準備を始める
内定取り消しは大きなショックですが、早めに気持ちを切り替えて、次の就職活動に向けて準備を進めましょう。求人の情報収集や自己分析を見直すことで、新たな視点が得られるかもしれません。
すでに一度内定を得た経験があることは、自信につながる要素です。気持ちを落ち着けて、前向きに動き出すことが、次のチャンスを引き寄せる近道になるでしょう。
⑥第三者に同席してもらい企業と話すことを検討する
企業と話をする際は、一人で臨むよりも、第三者に同席してもらうことで冷静な対応がしやすくなります。
大学の職員や保護者、信頼できる友人などに立ち会ってもらえば、相手の言動にも抑止力が働きやすくなります。発言内容の記録も取りやすくなり、後のトラブル防止にも役立つでしょう。
不安なときほど、一人で抱え込まずに助けを求めてください。
内定取り消しを撤回してもらう方法

内定取り消しの中には、法的に問題があるケースも見られます。すぐにあきらめるのではなく、まずは取り消しの妥当性を見極めましょう。
ここでは、内定取り消しに納得できない場合にとるべき対応を、順を追って解説します。
- 企業に内定取り消しの理由を文書で請求する
- 内定通知やオファーレターを証拠として提示する
- 弁護士など法律の専門家に相談して対策を練る
- 企業に対して法的措置も視野に入れて交渉する
- 内定取り消しが無効と認められる可能性があるか確認する
① 企業に内定取り消しの理由を文書で請求する
企業から突然内定を取り消されたとき、まず行うべきことは「理由の明示を求めること」です。口頭での説明は記録に残りづらく、後で話が食い違う原因にもなりかねません。
文書で明確な理由を出してもらうことで、撤回交渉や法的手続きに進む際の重要な判断材料になります。
仮に企業側が理由を曖昧にしようとした場合でも、文書で求めることで責任ある対応を促す効果が期待できるでしょう。あわせて、日付や担当者名なども控えておくとより安心です。
② 内定通知やオファーレターを証拠として提示する
企業からの内定通知書やオファーレター、または確認メールは、内定の成立を示す有力な証拠です。これらの文書があることで、正式な採用契約があったと判断されることもあります。
保存はデータ形式と紙媒体の両方が理想的で、やりとりの履歴も含めて保管しておきましょう。
加えて、LINEやチャットツールでのやりとりがあればスクリーンショットを取っておくなど、証拠は多いに越したことはありません。こうした記録があるかないかで、対応の選択肢が大きく変わります。
③ 弁護士など法律の専門家に相談して対策を練る
内定取り消しが不当かどうかを自分で判断するのは難しいことが多いため、法律の専門家に相談することが大切です。
労働問題に詳しい弁護士であれば、就職内定の法的な扱いや、企業との交渉方法について的確なアドバイスをしてくれます。
初回相談は無料という事務所もありますし、大学のキャリアセンター経由で紹介を受けることも可能です。
一人で抱え込まず、客観的な視点からのサポートを得ることで、より冷静かつ的確に対応を進めることができるでしょう。
④ 企業に対して法的措置も視野に入れて交渉する
企業側との話し合いで解決が見込めない場合は、法的措置を検討する段階に入ります。
交渉の場で証拠をもとに主張することはもちろん、状況によっては内容証明郵便を送ったり、労働審判や民事訴訟などを起こすという選択も出てきます。
ただし、これらの手段には時間と労力がかかるため、感情的にならず、現実的な解決方法かどうかも専門家と相談しながら進めることが大切です。
自分の権利を守るための一手段として、選択肢に加えておきましょう。
⑤ 内定取り消しが無効と認められる可能性があるか確認する
すべての内定取り消しが違法となるわけではありません。企業側に合理的で客観的な理由がある場合、その取り消しは正当とされることもあります。
逆に、抽象的な表現や根拠のない理由での取り消しは、不当と見なされる可能性が高いです。どちらに該当するかを冷静に判断するには、法律の専門家の意見が不可欠。
早まって判断を下さず、証拠と照らし合わせながら、慎重に検討を重ねることが納得のいく解決につながります。
内定取り消しが確定した場合の考え方

内定が取り消されたときは、大きなショックを受けるかもしれません。ただ、その出来事をどう受け止めるかで、今後の選択や行動は大きく変わってきます。
ここでは、内定取り消しが確定したあとに、前向きに考えるための視点を紹介します。
- 内定取り消しは自分の全てを否定するものではないと認識する
- 今後のキャリアを冷静に再設計する
- 働き方や業界選びを見直す機会にする
- 自己分析を深めて次の選考に活かす
- 一度立ち止まって視野を広げる時間と捉える
①内定取り消しは自分の全てを否定するものではないと認識する
内定取り消しは自分の全てを否定するものではないと認識する内定を取り消された事実に直面すると、多くの人が「自分は否定された」と感じるかもしれません。
しかし、これは必ずしも個人の価値を否定するものではありません。企業の事情や方針変更が理由である場合も多く、本人の努力やスキルに問題がないケースもあります。
たとえば採用人数の削減やプロジェクトの中止といった要因であれば、本人の資質とは無関係です。
このようなときこそ、感情的にならずに「なぜ起きたのか」を客観的に整理し、自分の価値を見失わないよう心がけましょう。自信を保ちつつ、前向きな行動につなげてください。
②今後のキャリアを冷静に再設計する
今後のキャリアを冷静に再設計する突然の内定取り消しは、将来の不安を強くする出来事です。しかし、それを「軌道修正のチャンス」と捉えることができれば、新たな可能性も見えてきます。
内定先の業種や職種に固執せず、自分が本当にやりたいことや向いていることを改めて考えるよい機会です。
自分のキャリアビジョンに照らして、必要な経験やスキルは何かを見直し、より納得感のある就職活動にシフトしましょう。焦らず、自分のペースで設計し直すことが大切です。
③働き方や業界選びを見直す機会にする
働き方や業界選びを見直す機会にする内定をもらった企業の選定基準が「世間の評価」や「知名度」だけに偏っていなかったか、一度振り返ってみてください。
今回の出来事をきっかけに、自分が求める働き方や職場環境について再認識できるかもしれません。
たとえば、ワークライフバランスを重視したいのか、裁量の大きい仕事がしたいのか、チームワークが合う職場が理想なのかなど、今後の選択軸を明確にするチャンスです。
企業選びにおいて重視するポイントを再設定することで、納得のいくキャリア選択ができるようになるでしょう。
④自己分析を深めて次の選考に活かす
自己分析を深めて次の選考に活かす内定を得たという実績がある以上、自分には評価される強みがあるはずです。
取り消しという結果にだけ注目せず、それまでの過程を振り返って、どのような要素が企業に評価されたのかを考えてみてください。
また、反省点や改善できる点があれば、次の選考に向けてブラッシュアップすることも可能です。
過去の応募書類や面接でのやりとりを見返すことで、自己理解を深め、より自信を持って次に臨む準備ができます。前回の経験を生かすことで、より確実な内定獲得につなげられるはずです。
⑤ 一度立ち止まって視野を広げる時間と捉える
一度立ち止まって視野を広げる時間と捉える立て続けの就職活動で疲れていた場合、内定取り消しという出来事が、結果的に「休息と見直し」のタイミングになることもあります。
短期留学やインターン、アルバイトを通じて社会経験を積むなど、新たなアプローチを模索してみるのも有効です。
また、スキルアップのために資格取得や講座受講に挑戦することも、将来の可能性を広げる手段になります。
無理に今すぐ結果を求めるのではなく、「今できること」に目を向けて行動することで、未来への道が開けてくるでしょう。
内定獲得後に気をつけたいこと
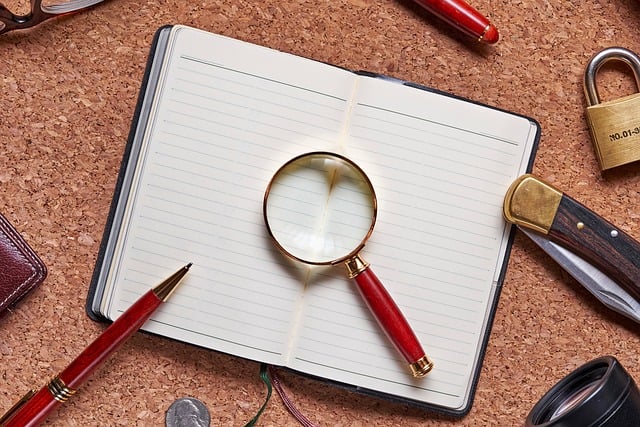
内定をもらったあとも、就職活動は完全に終わりではありません。内定が取り消される事態を避けるには、入社までの行動に注意を払うことが大切です。
ここでは、内定後に意識しておきたい5つのポイントを紹介します。
- SNSでの投稿やオンラインの言動に注意する
- 企業からの連絡には迅速に対応する
- 生活習慣を整え、体調管理に気を付ける
- 単位取得と卒業要件の管理を徹底する
- 内定者研修や書類提出に適切に対応する
① SNSでの投稿やオンラインの言動に注意する
SNSは内定後も企業に見られている可能性があります。不適切な発言や過激な投稿があれば、社会人としての資質を疑われ、内定に影響するかもしれません。
たとえば差別的な発言や、アルバイト先での迷惑行為を撮影・投稿するような行動は、炎上のリスクだけでなく、企業からの信頼を大きく損ねる結果につながります。
過去の投稿を見直し、問題があれば削除することも一つの手段です。公開範囲の設定を見直すとともに、今後の投稿内容にも十分注意を払いましょう。
② 企業からの連絡には迅速に対応する
内定後は企業とやり取りする機会が増えます。返信が遅かったり、連絡を放置したりすると、誠意に欠けると判断されかねません。
メールや電話はこまめに確認し、内容を理解したうえで早めに返答してください。また、返信の言葉遣いやフォーマットにも注意し、社会人としてのマナーを意識することが重要です。
連絡の遅れが続くと、企業側から「内定辞退の意思があるのでは」と誤解される可能性もあります。小さなことのように見えても、信頼関係を築くうえで重要なポイントです。
③ 生活習慣を整え、体調管理に気を付ける
健康状態によっては、企業側が業務に支障が出ると判断し、内定を取り消す可能性もあります。特に入社直前に入院や長期療養が必要な状態になると、スムーズな配属が難しくなるおそれも。
生活が不規則になりやすい時期ですが、睡眠や食事に気を配り、体調を崩さないよう努めましょう。また、持病がある場合は必要な治療を継続し、入社に向けて健康を維持する努力が求められます。
適度な運動やストレスケアも含め、日々の生活管理を大切にしてください。
④ 単位取得と卒業要件の管理を徹底する
卒業できなければ、内定は自動的に無効になることがあるのです。特に4年次後期で必要単位が不足していた場合、修正が効かず留年になるリスクが高まります。
シラバスや履修要件を改めて確認し、卒業に必要な条件を明確に把握しておきましょう。卒業論文や最終試験のスケジュール管理も怠らないようにし、余裕を持って取り組むことが大切です。
万が一のトラブルを防ぐため、学内の教務課やゼミの担当教員とも密に連絡を取り、進捗状況を共有しておくと安心でしょう。
⑤ 内定者研修や書類提出に適切に対応する
企業によっては、内定後に研修や書類の提出を指示される場合があります。期日を守らない、内容が不十分といった対応が続くと、企業の印象を損ねるおそれがあります。
指定された提出物には正確に対応し、期日に余裕をもって取り組んでください。研修がオンラインで行われる場合は、通信環境や準備物の確認も重要です。
積極的に参加する姿勢を見せることで、企業側に対して良い印象を残すことができます。与えられた機会をきちんとこなすことは、社会人としての第一歩でもあるでしょう。
内定取り消しの理由を理解し、適切に備えよう

内定取り消しは誰にでも起こりうる現実であり、その理由には法的、個人的、企業側の都合などさまざまな要素があります。だからこそ、もしものときには落ち着いて行動することが重要です。
まず、内定取り消しの背景には単位不足や経歴詐称といった本人に起因するものから、企業の経営悪化といった外部要因まで幅広い理由があると知っておきましょう。
そして、その対応方法を事前に理解しておくことで、いざというときも冷静に対処できます。さらに、内定取り消しが違法と判断されるケースもあるため、適切な対策を取れば撤回の可能性もあるのです。
内定獲得後も気を抜かず、SNSの使い方や体調管理などにも配慮することで、安定したスタートが切れるでしょう。事実を知り、備えることが未来の安心につながります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










