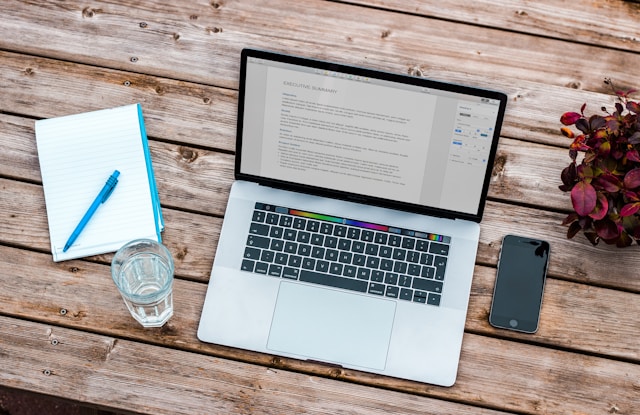テストセンターでは電卓持ち込み禁止!紙での計算の工夫や練習方法まで徹底解説
テストセンターでの適性検査を控えた就活生の皆さん、電卓を持っていっていいのか迷っていませんか?
SPIなど非言語問題では複雑な計算も多く、電卓があれば安心だと考える方も多いでしょう。しかし、テストセンターでは電卓の持ち込みが禁止されています。
この記事では、テストセンターでの電卓持ち込み禁止の理由や、電卓なしで効率よく計算するコツ、さらには電卓以外の持ち込み禁止品や必要な持ち物まで詳しく解説します。
テストセンター対策に悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考にして万全の準備を整えてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
【結論】テストセンターでは電卓持ち込み禁止

テストセンターでは、受験者の純粋な計算能力を評価するため、電卓の持ち込みは認められていません。
これは、企業は応募者の実力を正確に把握しなけばならず、電卓を使用すると、本来の能力が正しく評価できなくなる可能性があるためです。
最悪の場合、不正行為とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
①電卓の代わりに会場で貰う計算用紙と鉛筆で計算する
テストセンターでは、電卓の代わりに計算用紙と鉛筆が提供され、これらを使用して計算を行います。
通常、計算用紙は試験開始時に配布され、鉛筆も会場で用意されていることが大半ですが、施設によっては自身の筆記用具の持参が許可される許可される場合もあります。
計算用紙は余白も含めて自由に使用できるので、言語のメモをする場所と、非言語の計算をする場所など、事前にルールを決めておくと上手に活用できるでしょう。
②Webテスティング形式の場合は電卓の使用も可能
一方、自宅などで受験するWebテスティング形式の場合は、電卓の使用が許可されています。
Webテスティングでは、コンピューターの電卓機能や手持ちの電卓を利用できることが多くなります。
しかし、電卓が使えるからといってすべての計算を電卓に頼るのではなく、簡単な計算は頭の中で行い、複雑な計算のみ電卓を使用するようにして、効率的な使い方を心がけましょう。
電卓以外でテストセンターに持ち込み禁止のもの

テストセンターでは、電卓だけでなく多くのアイテムが持ち込み禁止となっています。これは試験の公平性を確保し、受験者の真の能力を正確に評価するためです。
誤って持ち込み禁止のものを持参すると、不正行為と判断される可能性があるので、試験会場に到着したら、これらの物品は必ずロッカーに預けるようにしましょう。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①スマートフォン
スマートフォンは、インターネット接続や計算機能を使った不正を防ぐため、テストセンターでの持ち込みが厳格に禁止されています。
また、試験中にスマートフォンの通知音が鳴ると、他の受験者の集中を妨げる恐れがあります。スマートフォンは必ず電源を切り、ロッカーに保管してから試験室に入るようにしましょう。
うっかり持ち込んでしまうと、試験が中断される可能性があるので、十分な注意が必要です。
②腕時計
腕時計は、高性能時計を使った不正を防ぐため、テストセンターでは持ち込みが許可されていません。
通常のアナログ時計であっても持ち込みは認められません。試験時間の管理は、会場に設置された時計や試験システムの画面で行うことができます。
時計を外し忘れて試験室に入ると、不正行為と見なされる可能性があります。
③筆記用具
テストセンターでは、カンニングを防ぐため、個人の筆記用具の持ち込みも禁止されています。
試験に必要な筆記用具は、会場側が提供します。通常、鉛筆やシャープペンシル、消しゴムが用意されていますよ。
自分のお気に入りの筆記用具を使いたい気持ちは理解できますが、ルールの遵守が重要です。
④電子辞書
電子辞書も、保存された情報の不正利用を防ぐため、テストセンターへの持ち込みが禁止されているアイテムの一つです。
SPIなど適性検査では、基本的に高度な語彙力を必要とするような問題は出題されません。そのため、電子辞書がなくても十分に対応できるはずです。
もし語彙力に不安がある場合は、事前に学習を重ねておきましょう。電子辞書を持ち込もうとすると、不正行為と判断される可能性があるので注意が必要です。
テストセンターに持っていく持ち物

テストセンターでの受験に必要な持ち物は、意外にも少数です。多くのアイテムが持ち込み禁止となっているため、持参するものは厳選されています。
しかし、必須の持ち物を忘れると試験を受けられなくなる可能性があるので、細心の注意をしてください。
①身分証
身分証は、テストセンター受験において最も重要な持ち物の一つで、本人確認に使用されるため、必ず顔写真付きの有効な身分証明書を用意する必要があります。
適切な身分証としては、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、学生証(プラスチックカード型に限る)などが挙げられます。
身分証は必ず原本を持参し、コピーは認められません。また、有効期限が切れていないか事前のチェックも大切です。
身分証を忘れると受験できなくなるので、前日のうちに準備しておくことをお勧めします。
②受験票
受験票は、テストセンターの予約情報を証明する重要な文書です。通常、テストセンター予約時に表示される「受験予約完了画面」を印刷したものを受験票として使用します。
予約完了画面を印刷し忘れた場合は、「テストセンター受験予約内容の確認メール」を印刷して代用も可能ですよ。
どうしても印刷できない状況では、テストセンターID、カナ氏名、検査名、会場名、日程、タームをA4用紙に手書きで記入したものでも代用できる場合があります。
受験票は忘れずに持参し、スムーズな受付を心がけましょう。
テストセンターの試験内容

テストセンターでは、就活生の総合的な能力を評価するために複数の試験が実施されます。
基礎的な学力から思考力、そして性格特性まで幅広い測定を目的としており、各試験には独自の特徴があり、それぞれに適した準備が必要です。
以下では、テストセンターで一般的に行われる4つの主要な試験内容について詳細に解説しますよ。
①言語問題
言語問題は、受験者の言語運用能力を多角的に評価する試験で、出題内容は多岐にわたり、語彙の理解度、文法知識、読解力などが総合的に問われます。
具体的には、同義語や反義語の選択、適切な言葉の用法、文章の論理的構成、長文の要旨把握などが含まれます。
この試験では、日常的な言語感覚だけでなく、ビジネス場面で求められる高度な言語スキルも評価対象ですよ。
対策としては、質の高い文章を日頃から読む習慣をつけることや、語彙力を増強するための学習をしましょう。
②非言語問題
非言語問題は、数学的思考力と論理的推論能力を測定する試験で、出題範囲は広く、基本的な算術から、データ分析、図形の性質理解まで多様です。
典型的な問題としては、数列の規則性発見、確率計算、グラフや表の解釈などがあります。
この試験では、単なる計算力だけでなく、問題の本質を素早く把握し、効率的に解決する能力が求められますよ。
準備には、基礎的な数学の復習に加え、様々なタイプの問題に触れ、解法のパターンの習得が重要です。
③構造把握
構造把握試験は、複雑な情報を整理し、本質を見抜く力を評価します。主に、文章や図表から重要な情報を抽出し、その関係性を理解する問題が出題されます。
この能力は、ビジネス環境で直面する複雑な課題を分析し、効果的な解決策を見出すのに不可欠だと言えるでしょう。
対策としては、新聞記事やビジネスレポートなどを読み、要点を素早く把握する練習が有効です。また、情報を視覚化して整理する技術を身につけることも重要です。
④性格検査
性格検査は、受験者の行動傾向や価値観を探る試験です。多くの場合、日常生活や仕事に関する質問に対し、自身の考えや行動を選択する形式で行われます。
この検査には正解はなく、企業の求める人材像との適合性を判断するツールとして使用されますよ。回答の一貫性が重視されるため、自分自身をよく理解し、誠実に答えることが大切です。
事前準備としては、自己分析を深め、自分の強みや弱み、価値観を明確にしておくことが役立ちます。
また、志望企業の企業理念や求める人材像を研究しておくことも有効な戦略ですよ。
テストセンターで電卓なしで速く計算するコツ

テストセンターでは電卓の使用が禁止されているため、迅速かつ正確な計算能力が不可欠です。
ここでは、電卓を使わずに効率的に計算するためのテクニックを紹介します。
①掛け算の方法を工夫する
掛け算は、テストセンターの非言語問題で頻出する計算タイプの一つです。通常の筆算では時間がかかりすぎるため、効率的な計算技術の習得をしましょう。
ここでは比較的よく登場する、3、5、9、11の乗算に関する迅速な計算法を紹介します。
1.三算術(3の掛け算)
三算術は、3を掛ける計算を迅速に行うための手法です。
例えば、35×3を計算する場合、まず35を2倍して70を作り、そこに元の数35を足す方法が有効です。つまり、35×3 = (35×2) + 35 = 70 + 35 = 105となりますよ。
この方法により、3の掛け算を足し算に変換でき、計算が簡略化されます。
大きな数字にも適用可能なので、習得しておくと便利です。繰り返し練習して、この手法に慣れましょう。
2.五算術(5の掛け算)
五算術は、5を掛ける計算を迅速に行うための手法です。
例えば、24×5を計算する場合、まず24を10倍して240を作り、その半分を取る方法が有効ですよ。つまり、24×5 = (24×10) ÷ 2 = 240 ÷ 2 = 120となります。
この方法により、5の掛け算を10倍して半分にする操作に変換でき、計算が簡略化されるのです。10倍は容易なので、実質的には2で割るだけの計算ですね。
3.九算術(9の掛け算)
九算術は、9を掛ける計算を迅速に行うための手法です。
例えば、37×9を計算する場合、まず37を10倍して370を作り、そこから元の数37を引く方法が有効ですよ。つまり、37×9 = (37×10) – 37 = 370 – 37 = 333となります。
この方法により、9の掛け算を10倍して1つ分引く操作に変換でき、計算が簡略化されるのです。9の掛け算は意外と頻出するので、この手法を習得しておくと大幅な時間短縮につながるでしょう。
4.十一算術(11の掛け算)
十一算術は、11を掛ける計算を迅速に行うための手法です。
例えば、45×11を計算する場合、4と5の間に4+5=9を入れますよ。つまり、45×11 = 495となります。この手法は2桁の数字に特に効果的です。
3桁以上の場合は若干複雑になりますが、同様の原理で計算可能です。11の掛け算はそれほど頻出しませんが、この手法を知っておくと、出題された際に迅速に解答でき流でしょう。
②頻出問題の解き方のコツを知っておく
テストセンターの非言語問題では、特定のパターンが繰り返し出題されます。
これらの問題タイプに対する効果的な解法を事前に理解しておくことで、試験当日の解答効率と精度を大きく改善できます。
ここでは、順列・組み合わせ、割引計算、仕事算、比率計算、論理的推論の5つの代表的な問題タイプについて、それぞれの攻略法を解説します。
1.順列・組み合わせ
順列・組み合わせの問題では、基本公式の正確な理解が鍵です。順列の公式は「nPr = n!/(n-r)!」、組み合わせの公式は「nCr = n!/(r!(n-r)!)」と表されます。
問題文から必要な情報を迅速に抽出し、適切な公式に当てはめる練習が重要ですよ。また、円順列や重複を含む場合など、応用問題にも注意を払う必要があります。
問題を解く際は、まず「順番が関係するか(順列)」「順番が関係ないか(組み合わせ)」を判断しましょう。
2.料金の割引問題
料金の割引問題では、割引率や税率の計算が頻出します。基本的な計算手順として、「割引後価格 = 原価 × (1 – 割引率)」を覚えておくと便利です。
また、複数回の割引が適用される場合は、個別に計算を行う必要がありますよ。
例えば、20%オフの後に10%オフの場合、「0.8 × 0.9 = 0.72」となり、合計28%オフになります。
3.仕事算
仕事算の問題では、「仕事量 = 能力 × 時間」の基本公式を覚えておくことが重要です。複数の人や機械が同時に稼働する場合は、それぞれの能力を合計して計算します。
例えば、AさんとBさんが同時に作業する場合、「1/(Aの能力) + 1/(Bの能力) = 作業時間」の式で解決できますよ。
また、作業途中で人が交代する場合は、各段階の作業量を個別に算出し、最終的に合計するアプローチが有効です。
4.割合の計算
割合の計算問題では、「部分 ÷ 全体 = 割合」の基本公式を覚えておくことが重要です。また、比較する際は、単位の統一を忘れないようにしましょう。
増加率や減少率を求める問題も頻出しますが、これらは「(変化後 – 変化前) ÷ 変化前」で算出できます。
パーセントを小数に、小数をパーセントに素早く変換できるようにしておくことも大切です。
5.推論
推論問題では、論理的思考力が試されます。解く際のコツは、与えられた情報を整理し、図や表を使って視覚化することです。
例えば、「AさんはBさんより背が高い」「BさんはCさんより背が高い」という情報があれば、A > B > Cと図式化しますよ。
また、「すべて」「少なくとも1つ」といった限定表現に注意を払い、正確な情報の解釈が重要です。
推論問題は時間がかかりがちなので、素早く情報を整理する練習を重ねておくことが大切です。
電卓がなくても非言語が解けるようになる練習法

テストセンターでは電卓の使用が禁止されているため、非言語問題を効率的に解くには特別な準備が必要です。
しかし、適切な訓練を積めば、電卓なしでも十分に対応できる力が身につきます。ここでは、電卓を使わずに非言語問題を解くための効果的な練習方法を3つご紹介します。
①解き方を覚えてしまう
非言語問題には、特定の解法パターンが存在するため、これらの解き方を事前に習得しておくことで、電卓がなくても効率的に問題を処理できます。
例えば、比率問題では「部分/全体」の基本的な考え方を理解しておくと、多様な問題に対応できるようになり、また、速度に関する問題では「距離/時間」の基本概念の活用が重要です。
解法を学ぶ際は、単なる暗記ではなく、その方法が適用できる理由の理解をしましょう。
②問題集を繰り返しとき問題に慣れる
非言語問題に習熟するには、実際に多くの問題を解く経験が不可欠です。テストセンター対策用の問題集を活用し、繰り返し演習すれば、問題パターンの認識能力と解答スピードが向上しますよ。
初めは時間をかけてじっくり取り組み、徐々に時間制限を設けて解くようにしましょう。同じ問題を複数回解くのも効果的です。
2回目以降は解法を思い出しながら素早く答えを出すことで、本番での対応力が養われます。また、誤答した問題は特に注意して復習し、同じミスを繰り返さないよう心がけましょう。
③よく使う公式を覚えておく
非言語問題では、特定の公式を適用する場面が多々あるため、事前に記憶しておくことで、電卓なしでも迅速に計算を行えます。
例えば、面積や体積の公式、ピタゴラスの定理、円周率など、頻出する公式をリストアップし、暗記しておきましょう。
公式を覚える際は、単に数式を丸暗記するのではなく、その公式がどのような状況で適用されるのかの理解が大切です。
また、公式の暗記だけでなく、実際の問題で使用する練習も行いましょう。これにより、試験本番で適切な公式を迅速に選択し、適用できます。
【Webテスト】使用する電卓の選び方のポイント

Webテストでは電卓の使用が許可されていますが、電卓の選び方によって、テストの効率性や精度が大きく左右されます。
ここでは、Webテストで活用する電卓を選ぶ際の4つの重要なポイントを解説します。
①自分の手にあった電卓を選ぶ
Webテストで使用する電卓は、手に馴染む電卓を使うことで、操作がよりスムーズになり、計算ミスのリスクを低減できるでしょう。
理想的な電卓のサイズは、手のひらでちょうど覆える程度とされています。過度に大きいと操作に時間を要し、逆に小さすぎるとボタンの押し間違いが増える可能性があります。
電卓を購入する際は、実際に手に取って操作感を確認することが賢明な選択と言えるでしょう。
②計算機能のみのシンプルな電卓を選ぶ
Webテストにおいては、多機能な電卓よりも、基本的な計算機能に特化したシンプルな電卓を選ぶことをお勧めします。
関数電卓や科学電卓は機能が豊富ですが、操作が複雑になり、かえって時間を浪費してしまう可能性があります。
Webテストで主に必要とされる計算は、四則演算と比率計算ですよ。これらの機能を備えたシンプルな電卓を選ぶことで、操作に迷うことなく迅速に計算を行えます。
また、シンプルな電卓は比較的安価なので、テスト専用として新たに購入しましょう。
③押しやすいボタンの電卓を選ぶ
Webテストでは制限時間内に多くの計算をこなす必要があるため、押しやすいボタンを持つ電卓を選ぶことが重要です。
ボタンの大きさ、配置、触感を吟味し、自分にとって最も操作しやすいものを選びましょう。特に、頻繁に使用する数字キーや基本演算のキーは押しやすさが重要です。
また、ボタンの反応が良く、軽いタッチで確実に入力できる電卓を選ぶことで、計算速度を向上させられるため、実際に店頭で触って操作感を確かめてからの購入をお勧めします。
④スマホの電卓で十分な場合は買わなくてもいい
Webテストでは、スマートフォンの電卓アプリの利用も可能です。スマートフォンの標準電卓アプリは基本的な計算機能を備えており、多くの場合これで事足ります。
日頃からスマートフォンの電卓を使い慣れている場合は、新たに電卓を購入する必要はないでしょう。
ただし、スマートフォンを使用する際は、バッテリー切れや予期せぬ通知に注意が必要です。
テスト中はスマートフォンを機内モードにして、集中力を維持するための対策を講じておくことが大切です。
【Webテスト】電卓を効率よく使うコツ

Webテストでは電卓の使用が許可されていますが、単に電卓を使えばよいわけではありません。電卓の効果的な活用で、より多くの問題を迅速に解答し、高得点獲得につながります。
ここでは、Webテストで電卓を効率的に使いこなすための2つの重要なコツを紹介します。
①事前に電卓の操作方法に慣れておく
Webテストで電卓を効果的に使いこなすには、事前に電卓の操作に十分習熟しておくことが不可欠です。テスト中に操作に戸惑えば、貴重な時間を浪費してしまいます。
日常的に問題演習の際に電卓を使用し、キーの配置や各種機能を熟知しておきましょう。特に、四則演算や百分率計算など、頻出する操作は瞬時に行えるよう事前練習が重要です。
また、電卓の高度な機能を理解し、効率的な計算テクニックを習得しておくことで、より迅速かつ正確に問題を解決できます。
②暗算の方が速い場合は電卓をムリに使わない
電卓が使用可能だからといって、全ての計算を機械に頼る必要はありません。単純な計算や、頭の中で素早く処理できる場合は、電卓を使わずに暗算で解答する方が効率的です。
例えば、10や100との乗除算、簡単な加減算などは、暗算の方が迅速に処理できることがあります。
電卓使用と暗算のどちらが適しているかを瞬時に判断し、状況に応じて最適な方法を選択する判断力を磨くことで、テスト全体の解答速度が大幅に向上するでしょう。
テストセンターでの電卓持ち込みについてよくある質問

テストセンターにおける電卓の持ち込みに関しては、多くの就活生が不安や疑問を抱いています。ここでは、頻繁に寄せられる質問とその回答を解説します。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①テストセンターに電卓を持っていくとバレる?
テストセンターに電卓を持ち込むことは、ほぼ確実に発覚します。テストセンターでは、受験者の所持品チェックが厳格に実施されます。
受付時に私物をロッカーに預けるよう指示があり、試験室には最小限の必需品しか持ち込めません。電卓を隠匿しようとしても、金属探知機などの機器で検出されてしまいます。
万一、試験中に電卓の使用が発見された場合、不正行為として即座に退場処分となる可能性があります。
このようなリスクを避けるためにも、電卓の持ち込みは絶対に避けるべきです。
②監視型のwebテストでも電卓は使える?
監視型Webテストでは、通常の自宅受験型とは異なり、電卓使用に制限が設けられる場合があります。
カメラを通じて受験者の行動が監視されるため、電卓の使用が不正行為と判断されるリスクがあります。
ただし、テストの種類や実施企業によってルールが異なることがあるため、事前に電卓使用可否の確認をしましょう。
電卓が使用できない場合は、暗算能力の向上や、筆算の速度アップをして、代替策を講じる必要があります。テスト形式に応じた適切な準備を心がけましょう。
テストセンターには電卓持ち込み禁止だが対策法はある!

テストセンターでの電卓持ち込みは禁止されており、会場で配布される計算用紙と鉛筆を使用して計算を行う必要があります。
また、電卓以外にもスマートフォンや腕時計、私物の筆記用具なども持ち込み禁止なので、テストセンターで高得点を取るためには、掛け算の工夫や頻出問題の解き方のコツを押さえ、電卓なしでも速く正確に計算する能力を身にけましょう。
テストセンターは就活の重要な関門の一つですが、適切な対策を行えば必ず乗り越えられます。自信を持ってテストに臨んでください!
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。