診療情報管理士の年収と仕事内容を徹底解説|初任給・ボーナスも紹介
医療の現場を“裏から支える専門職”として注目されている診療情報管理士は、医療データの管理や分析を通じて病院経営や医療の質向上に貢献する重要な存在です。
この記事では、診療情報管理士の年収・初任給・ボーナスなどの収入事情から、具体的な仕事内容、勤務先別の特徴、求められるスキル、将来性まで徹底解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
診療情報管理士とは?

診療情報管理士とは、医療現場で発生する多くの診療データを整理し、病院経営や医療の質を高める専門職です。
医師や看護師のように直接患者と関わることは少ないものの、医療チームの一員として欠かせない存在といえるでしょう。
カルテの確認や診療情報の分類、統計資料の作成などを通じて、医療機関の運営を支えます。診療情報管理士の主な役割は、医療情報の「正確さ」と「活用のしやすさ」を高めることにあります。
近年では電子カルテの普及や医療DXの推進により、診療情報管理士の需要が増えています。正確な情報処理能力に加えて、ITスキルや分析力も求められる時代です。
医療の裏側を支えるプロフェッショナルとして、今後も安定したキャリアを築ける職種といえます。
診療情報管理士の平均年収

診療情報管理士の全国平均年収はおおよそ 440万円前後 とされています。厚生労働省の統計や求人サイトの公開データをもとに算出された数字で、医療職の中では中堅クラスの水準に位置します。
ただし、年収は勤務先の規模や地域、勤続年数によって大きく異なります。たとえば国立病院や大規模総合病院では平均を上回る傾向があり、経験を積むほど昇給幅も広がります。
一方で、小規模クリニックや地方医療機関では、初任給が低めに設定されるケースも少なくありません。また、資格取得後にスキルを高めることで昇給チャンスが増えるのも特徴です。
統計分析や医療DXに関する知識を持つ人材は、近年特に評価が高まっています。給与だけでなく、働き方や将来性の面でも安定性のある職種といえるでしょう。
引用:
診療情報管理士のボーナス・賞与

ここでは、診療情報管理士のボーナス(賞与)について詳しく解説します。支給額や時期、評価基準は勤務先によって異なりますが、全体的な傾向を理解することで、就職や転職の参考になるでしょう。
- 診療情報管理士の平均ボーナス支給額
- 賞与の支給時期と回数
- 評価基準と昇給の仕組み
①診療情報管理士の平均ボーナス支給額
診療情報管理士のボーナスは、年2回支給されることが多く、合計で月給の約4か月分が目安とされています。平均的な支給額は70万〜80万円前後で、医療職の中でも安定した水準といえるでしょう。
ただし、ボーナス額は勤務先の規模や経営状況、勤続年数などによって変わります。
大規模病院や公的医療機関では支給率が高い傾向にありますが、クリニックなどの小規模施設ではやや低めになる場合もあります。
新人のうちは支給額が抑えられることもあるため、就職活動の際には「支給実績」を確認しておくと安心です。
安定した収入を得たい場合は、病院の規模や経営体制、賞与の算定基準を事前に調べておくことをおすすめします。
②賞与の支給時期と回数
多くの医療機関では、賞与は「夏」と「冬」の年2回支給が一般的です。支給時期は6〜7月と12〜1月頃が中心で、病院の会計年度や決算期により前後する場合もあります。
一部の施設では年1回の支給、または決算賞与として追加支給されるケースもあります。なお、支給タイミングが変更されたり見直されたりすることもあるため、就業規則を確認しておくことが大切です。
支給回数や時期は病院ごとに異なるため、面接時に「賞与の支給実績」を質問しておくと、入職後のギャップを減らせるでしょう。
③評価基準と昇給の仕組み
診療情報管理士の賞与や昇給は、勤務年数やスキル、資格、成果などの複数の要素で決まります。主な評価基準としては以下のような項目があります。
- 勤続年数・経験年数:勤務期間が長くなるほど昇給率が上がりやすい
- 役職・責任範囲:管理職やリーダー職に就くと加算が大きくなる
- 業務成果・改善実績:業務効率化やミスの少なさが評価に反映される
- 資格・スキル:医療情報技師などの資格保有がプラス評価につながる
評価制度が明確な医療機関では、昇給・賞与の基準がわかりやすく、長期的なキャリア形成がしやすい傾向があります。
透明性の高い評価制度がある職場を選ぶことが、モチベーション維持にもつながるでしょう。
引用:
診療情報管理士の仕事内容
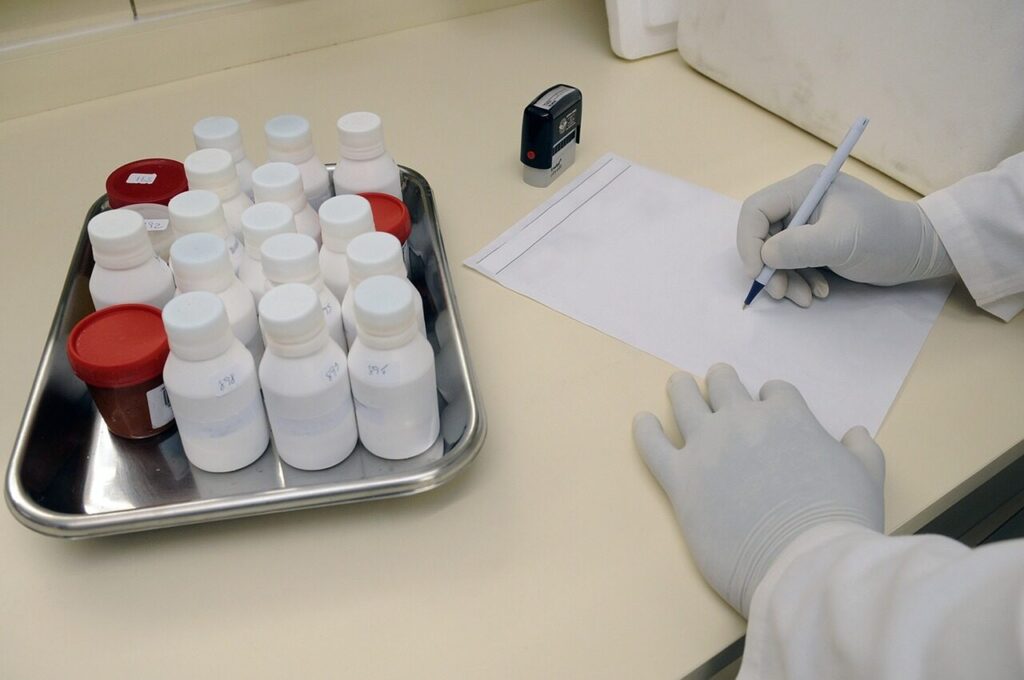
診療情報管理士は、医療現場で「データと情報の専門家」として活躍する職種です。診療記録やカルテの管理をはじめ、医療の質向上や経営支援にも関わる重要な役割を担います。
ここでは、主な6つの業務内容を詳しく紹介します。
- 診療記録の管理業務
- カルテ内容の確認・点検業務
- 病名分類(コーディング)業務
- データ入力・統計資料作成業務
- 医療情報の分析と経営支援業務
- 医療チームとの連携・情報共有業務
①診療記録の管理業務
診療情報管理士の中心となる仕事は、診療記録を正確かつ効率的に管理することです。病院では毎日、多くの患者の診療情報が発生しますが、これを適切に保存・整理しなければ、必要なときに活用できません。
診療情報管理士は紙カルテや電子カルテの内容を体系的に整理し、医療スタッフがすぐに情報を取り出せる環境を整えます。
これにより、診療の流れがスムーズになり、医療ミスの防止や迅速な意思決定にもつながります。また、個人情報保護の観点からセキュリティ対策も欠かせません。
法令遵守を意識しながら、安全で信頼できる情報管理体制を築くことが求められます。データの整備は、医療の質と病院の信頼性を守る基盤といえるでしょう。
②カルテ内容の確認・点検業務
カルテ内容の確認や点検は、医療の精度と信頼性を保つための大切な仕事です。カルテは医師の診療内容を記録する公式な文書であり、その正確性が診療報酬請求や病院経営にも直結します。
診療情報管理士はカルテの記載内容に誤りがないか、必要事項が抜けていないかを丁寧に確認します。たとえば、治療日や処置内容、病名などの記録に不整合がある場合は、医師に確認を行い修正を促します。
このような点検を通じて、データの品質向上が図られ、診療報酬の請求漏れ防止にもつながります。
さらに、カルテを精査する過程で医師や看護師と連携する機会が多く、チーム全体の情報共有体制も強化されます。
正確なカルテは医療の信頼を支える“証拠”であり、その維持に診療情報管理士の存在が欠かせません。
③病名分類(コーディング)業務
病名分類(コーディング)業務は、診療情報管理士が持つ専門的な知識と分析力が試される仕事です。患者の診断内容をICD-10などの国際基準に基づいてコード化し、統一された形式で記録します。
この作業により、全国の医療機関でデータを比較・分析することが可能になり、医療の質向上や政策立案にも役立ちます。
単なる事務作業に見えますが、病名や治療内容を正確に理解しなければ正しいコードを付与できません。そのため、医学知識や判断力が求められます。
さらに、診療報酬の算定においてもコーディングの精度は非常に重要です。誤った分類は病院の収益に影響することもあるため、細心の注意が必要です。
正確なコーディングを行うことで、医療データの信頼性を高め、病院経営にも大きく貢献できるでしょう。
④データ入力・統計資料作成業務
診療情報管理士は、日々の診療データを正確に入力し、それをもとに統計資料を作成します。データ入力は単なる事務処理ではなく、後の分析や報告に直結する重要な工程です。
収集した情報を分析し、病院全体の動向を把握することで、感染症対策や治療成績の改善にも役立ちます。
たとえば、手術件数の推移や平均在院日数を分析すれば、効率的な病床管理や人員配置の最適化にもつながります。また、厚生労働省や自治体への報告資料を作成する際にも、この統計データが活用されます。
診療情報管理士のデータ処理能力は、医療の透明性を高めると同時に、経営戦略にも欠かせない要素です。正確で信頼できる資料を作ることが、病院全体の意思決定を支える基盤となるでしょう。
⑤医療情報の分析と経営支援業務
医療情報の分析と経営支援は、診療情報管理士の中でも特に専門性が高い分野です。蓄積された医療データを活用し、病院経営の課題を見つけ出して改善策を提案します。
たとえば、診療科ごとの収益性や患者数の変化を分析し、効率化のための施策を検討することがあります。
医療の現場に関する深い理解と経営視点の両方が求められるため、単なる事務職ではなく「医療経営のパートナー」としての役割を果たす立場です。
また、データをもとにした提案が評価されれば、経営会議などで発言する機会も増え、キャリアアップの道も広がります。
今後、病院経営のデジタル化が進む中で、この分析力を持つ診療情報管理士の需要は一層高まるでしょう。
⑥医療チームとの連携・情報共有業務
診療情報管理士は、医師や看護師、薬剤師、事務スタッフなど多職種との橋渡し役として、医療チーム内で重要な役割を果たします。
医療情報を正確に共有することは、治療方針の統一や患者安全の確保に直結します。特に、電子カルテの運用や医療データベースの管理に関しては、診療情報管理士が中心となって調整することが多いです。
人と情報をつなぐ存在として、チーム医療の質を高め、患者により良い医療を届けるための重要な役割を担っているのです。
診療情報管理士の勤務先

診療情報管理士は、医療データを扱う専門職として多様な職場で活躍しています。勤務先によって業務内容や求められるスキル、働き方が大きく異なるのが特徴です。
ここでは代表的な6つの勤務先について詳しく見ていきましょう。
- 大学病院
- 総合病院
- 地域医療機関
- 診療所・クリニック
- 医療関連企業
- 公的機関・自治体
①大学病院
大学病院は高度な医療を提供するだけでなく、教育・研究の拠点でもあります。そのため、診療情報管理士は多岐にわたるデータを扱うことになります。
複数の診療科が連携して研究を行うため、診療情報の整理や統計処理、学術論文用データの抽出など、専門的な分析業務も多いです。
また、最新医療の導入が早いことから、新しい電子カルテシステムや分析ツールへの対応力も求められます。医療現場の最前線で専門性を磨ける環境であり、将来のキャリアアップを目指す人にも適しています。
医師や研究者と協働しながら、医療の質向上と研究支援の両面で貢献できるのが大学病院で働く魅力でしょう。
②総合病院
総合病院では、幅広い診療科をカバーしながら地域の中核医療を担っています。診療情報管理士は患者数の多さに対応し、効率的な情報処理を行う能力が求められます。
カルテの整理、診療報酬の確認、病名コーディング、統計資料の作成など、日々の業務は多岐にわたります。大規模病院ではチーム体制で業務を分担するため、協調性も欠かせません。
また、経営分析や医療の質評価(QI活動)など、データを活用した改善提案の機会も多いでしょう。現場での実務経験を積みながら、管理職や専門リーダーを目指す人にも適した環境です。
多様な症例に触れられるため、実践的なスキルを高めたい人には理想的な職場といえます。
③地域医療機関
地域医療機関では、地域住民の健康を支える役割が中心です。診療情報管理士は、限られた人員の中で幅広い業務を担当します。
カルテ管理やデータ分析だけでなく、医療連携の調整や行政への報告書作成なども行うことがあります。大規模病院に比べて1人あたりの担当範囲が広いため、マルチタスク力と臨機応変な対応力が必要です。
その一方で、患者や地域との距離が近く、自分の仕事が直接医療の現場に貢献している実感を得やすいのも魅力です。
地域包括ケアが進むなかで、医療・介護・行政をつなぐ“情報の橋渡し役”としての存在価値が高まっています。地域に根ざした働き方を希望する人には向いている勤務先でしょう。
④診療所・クリニック
診療所やクリニックでは、診療情報管理士が事務的な役割も兼ねるケースが多いです。患者数が比較的少ないため、カルテ管理やレセプト業務、予約システムの管理などを一手に担うことがあります。
小規模な医療機関では、現場の流れを理解したうえで柔軟に動ける力が求められます。電子カルテの運用やデータ集計を通して、医師や看護師の業務効率化を支援することが主なミッションです。
また、患者対応の機会も多く、コミュニケーション力も重要なスキルとなります。組織の一員というよりも「医療チームの中心的存在」として動くことができるため、やりがいを感じやすい職場です。
小規模だからこそ、自分の工夫や努力が結果に直結しやすい環境といえるでしょう。
⑤医療関連企業
診療情報管理士の活躍の場は、病院にとどまりません。医療関連企業でも、データを扱う専門知識が重宝されています。
たとえば、医療システム開発会社では電子カルテや統計ソフトの開発・導入支援に携わることがあります。製薬会社では、治験データの整理や医療統計の分析を担当するケースもあります。
また、コンサルティング会社では、病院経営の改善提案を行う際に医療データを分析し、戦略立案をサポートします。
現場経験を生かして企業側から医療を支える仕事ができるため、キャリアの幅を広げたい人に適しています。医療知識とビジネス感覚の両方を磨ける、成長性の高いフィールドです。
⑥公的機関・自治体
公的機関や自治体では、医療統計や地域医療計画の策定に診療情報管理士の専門知識が活かされます。
具体的には、地域ごとの疾病データを分析し、医療資源の配置や予防医療政策に反映させる業務などがあります。データの信頼性を確保するため、情報の精査や報告書作成にも慎重さが求められます。
公的機関ではチームよりも個人での分析作業が多く、正確さと粘り強さが重要です。安定した環境で働ける一方で、社会全体の医療体制づくりに貢献できるというやりがいもあります。
民間とは異なり、地域医療の未来をデータから支える使命感を持って働けるのが魅力です。公共性の高い分野で専門性を発揮したい人に向いた勤務先といえるでしょう。
診療情報管理士になるためのステップ

診療情報管理士を目指すには、資格取得までにいくつかの段階を踏む必要があります。高校卒業後の進路選びから資格取得、そして就職までの流れを理解しておくことが大切です。
ここでは、診療情報管理士になるための6つのステップを順を追って説明します。
- 進学先を選択する
- 専門学校や大学で学ぶ
- 必要な単位を取得する
- 認定試験を受験する
- 資格を取得する
- 医療機関などに就職する
①進学先を選択する
診療情報管理士を目指す最初のステップは、適切な進学先を選ぶことです。主に専門学校と大学の2つの選択肢があります。専門学校は実践的なスキル習得に重きを置いており、短期間で資格取得を目指せます。
一方、大学では医療情報や統計、経営などを幅広く学べるため、将来のキャリアの幅が広がるでしょう。どちらを選ぶかは、自分の学びたい内容や将来の働き方を考えて決めることが大切です。
オープンキャンパスや卒業生の進路実績を確認し、学校ごとの特徴を理解して選択するとよいでしょう。自分に合った進学先を選ぶことが、資格取得への第一歩となります。
②専門学校や大学で学ぶ
進学先を決めたら、診療情報管理士として必要な知識を学びます。専門学校では2〜3年間、医療情報システムやコーディング実習、カルテ管理など実務に直結する授業が中心です。
大学ではこれに加え、医療統計や情報セキュリティ、経営学などの理論的な科目も学びます。いずれの学校でも、医療現場を理解するための病院実習が行われるのが一般的です。
現場での経験を通じて、データ管理だけでなく医療チームとの連携や倫理観の大切さも学べます。授業で得た知識を実際の業務と結びつけることで、実践力が身につくでしょう。
努力を積み重ねることで、資格試験に必要な基礎が確実に固まります。
③必要な単位を取得する
診療情報管理士認定試験を受けるには、指定された科目の単位を修得する必要があります。これらの科目は「診療情報管理学」「医療制度論」「統計学」「疾病分類」など幅広い分野にわたります。
単位を取得するためには、講義だけでなく、実習・レポート・試験など多様な評価が行われます。特に医療統計や病名分類は難易度が高く、しっかりとした理解が求められる分野です。
授業の復習や過去問題の活用など、計画的に学習を進めることが合格への近道となります。
また、グループワークを通じて他の学生と意見交換を行うことで、現場で役立つコミュニケーション能力も身につくでしょう。地道な努力が将来の実力につながります。
④認定試験を受験する
必要な単位を取得したら、いよいよ診療情報管理士認定試験を受験します。この試験は公益社団法人 日本病院会が実施しており、年に1回開催されます。
出題範囲は幅広く、医療制度やコーディング、統計、倫理など、学んだ知識を総合的に問われます。合格率はおおむね60〜70%前後で、事前の十分な準備が欠かせません。
特に過去問を活用した演習は効果的で、出題傾向をつかむことができます。また、模擬試験を受けて時間配分を確認しておくのも重要です。
焦らず基礎を固め、理解を深めることで合格の可能性は高まります。しっかりと計画を立てて勉強を進めてください。
⑤資格を取得する
認定試験に合格すると、正式に「診療情報管理士」として認定されます。この資格は全国共通のものであり、医療現場で広く通用します。
資格取得後は、医療情報の専門家として病院やクリニック、企業などで働くことができます。とはいえ、資格はゴールではなくスタートです。
医療制度やデータ管理の技術は常に進化しているため、資格取得後も研修や勉強会に参加して知識を更新する姿勢が求められます。
継続的にスキルアップすることで、管理職や経営支援など、より専門性の高い仕事にも挑戦できるでしょう。資格取得は、医療業界で長く活躍するための重要なステップといえます。
⑥医療機関などに就職する
資格を取得したあとは、医療機関や関連企業への就職活動を行います。主な就職先は病院や診療所ですが、最近では製薬会社や医療IT企業、公的機関などへの就職も増えています。
就職活動では、履歴書や面接で「なぜ診療情報管理士を目指したのか」「どのように医療現場に貢献したいのか」を明確に伝えることが大切です。
学生時代の実習経験や資格取得の努力を具体的に話すと印象が良いでしょう。働き始めてからも、医療スタッフとの連携力や問題解決力を発揮し、現場で信頼される存在になることが求められます。
就職はゴールではなく、新たなスタートラインです。常に成長意欲を持ち、医療に貢献できるプロフェッショナルを目指してください。
診療情報管理士に求められるスキル・能力

診療情報管理士は、医療現場で「情報の専門家」として活躍する職種です。そのためには、専門知識だけでなく、分析力や人間的な柔軟性も求められます。
ここでは、診療情報管理士として活躍するために必要な6つのスキルと能力を紹介します。
- 医療知識と診療報酬制度の理解力
- 情報処理・データ分析スキル
- 正確性と注意力
- 倫理観と守秘義務意識
- チームワークとコミュニケーション能力
- 継続的な学習意欲と向上心
①医療知識と診療報酬制度の理解力
診療情報管理士にとって、医学的知識と診療報酬制度への理解は欠かせません。医療データを正確に扱うためには、病気の基礎知識や治療の流れを理解しておく必要があります。
たとえば、病名の分類や手術の内容を正しく把握できなければ、コーディングミスが発生し、診療報酬の算定に影響を及ぼす可能性があります。
また、診療報酬制度は法改正や制度変更が頻繁に行われるため、常に最新の情報を学び続ける姿勢も大切です。
医療知識と制度理解の両方を持つことで、医師や看護師からの信頼を得られ、的確なデータ管理や報酬請求のサポートができるでしょう。正確な知識は、医療の質と経営の安定を支える基礎となります。
②情報処理・データ分析スキル
医療現場では、膨大な量のデータを扱います。その中から有益な情報を抽出し、活用できる形に整理するのが診療情報管理士の重要な役割です。
電子カルテや医療統計ソフトを使いこなす情報処理スキルはもちろん、エクセルやSQLなどの分析ツールを扱える力も求められます。
データの傾向を読み取り、経営改善や医療の質向上に活かすことができれば、組織全体の価値向上にもつながるでしょう。さらに、分析結果を分かりやすく報告・提案するプレゼンテーション力も重要です。
単に数字を扱うのではなく、そこから「何を読み取るか」を考える力が、専門職としての大きな強みになります。データを価値ある情報に変える力が、診療情報管理士の真価といえるでしょう。
③正確性と注意力
診療情報管理士の仕事では、わずかな入力ミスが大きな影響を及ぼすことがあります。カルテの誤記や病名の分類ミスがあれば、診療報酬の請求金額や医療統計の結果に誤差が生じてしまいます。
そのため、常に正確さを意識し、細部まで丁寧に確認する姿勢が求められます。また、複数の診療科や医師のデータを扱うため、似たような項目や略語に惑わされない冷静さも必要です。
さらに、期限がある業務でも焦らず、手順を守って作業を進める慎重さが信頼につながります。正確性と注意力を兼ね備えた人ほど、医療現場で重宝される存在です。
細やかな確認作業を怠らず、データの品質を保つことこそが、診療情報管理士の責務といえるでしょう。
④倫理観と守秘義務意識
診療情報管理士は、患者の個人情報を日常的に扱う職種です。そのため、高い倫理観と強い守秘義務意識が求められます。
診療記録や検査結果には機微な内容が含まれており、わずかな情報漏えいが患者の信頼を失う原因となります。
法的には個人情報保護法や医療法に基づく管理が義務づけられており、規定を理解したうえでの慎重な取り扱いが必要です。
加えて、デジタル化が進む現代では、システムの不正アクセスや操作ミスへの対策も重要です。情報を守ることは医療従事者としての最低限の責任であり、その意識が組織全体の信頼にもつながります。
どんな状況でも情報を軽視せず、常に「患者の立場」を意識して行動できる姿勢が求められるでしょう。
⑤チームワークとコミュニケーション能力
診療情報管理士は、医師・看護師・事務スタッフ・経営者など多職種と関わりながら仕事を進めます。正確なデータを共有し、効率的に業務を行うためには円滑なコミュニケーションが不可欠です。
たとえば、カルテ内容の確認や病名分類の修正依頼を行う際には、相手の立場を理解し、根拠を明確に伝える力が必要です。
チーム医療が重視される現代では、単なる裏方ではなく、組織全体を支える「調整役」としての役割も期待されます。
また、意見の食い違いが生じた場合でも冷静に対話を続け、最善の解決策を導く柔軟さが大切です。信頼関係を築くことで、チーム全体の連携が深まり、結果として医療の質向上にも貢献できるでしょう。
⑥継続的な学習意欲と向上心
医療業界は制度改正や技術革新が早く、診療情報管理士も常に最新の知識を更新し続ける必要があります。
新しい電子カルテシステムの導入や病名分類ルールの変更など、学びを止めてしまうと業務に支障が出ることもあります。
そのため、定期的に研修やセミナーに参加し、専門誌や学会で最新情報を収集する姿勢が大切です。また、自ら課題を見つけ、スキルアップを目指す向上心も欠かせません。
学び続けることで、自分の成長だけでなく、職場全体の知識レベル向上にも貢献できます。医療情報の世界は進化し続けており、成長意欲を持ち続ける人ほど長く活躍できるでしょう。
継続的な努力が、専門職としての信頼とキャリアの広がりを生み出します。
診療情報管理士に向いている人の特徴

診療情報管理士は、医療データを扱う専門職であり、正確さや慎重さが求められる仕事です。人によって向き不向きがありますが、一定の性格傾向や考え方を持つ人がこの職種で活躍しやすい傾向があります。
ここでは、診療情報管理士に向いている人の6つの特徴を紹介します。
- 細かい作業が得意な人
- 医療やデータに興味がある人
- 責任感が強く慎重に行動できる人
- 他職種と円滑に連携できる人
- ルールや手順を守るのが得意な人
- 新しい技術に柔軟に対応できる人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①細かい作業が得意な人
診療情報管理士の仕事は、カルテの点検や病名の分類、データ入力など、細かい作業が多くあります。そのため、コツコツと地道に作業を進めることが苦にならない人に向いています。
ひとつひとつのデータを丁寧に扱う姿勢が求められるため、集中力や几帳面さが強みになります。ミスを防ぐための確認作業を怠らず、正確性を保てる人はこの職業に適しています。
反対に、注意が散漫になりやすい人や大まかな処理で済ませてしまうタイプの人には少し難しいかもしれません。
小さな誤りが大きな影響を与える仕事だからこそ、細かい作業を楽しめる人ほど信頼される存在になれるでしょう。
②医療やデータに興味がある人
医療の知識とデータ分析の両方に関心を持てる人は、診療情報管理士に向いています。病気の分類や医療制度、統計データなど、多くの情報を扱うため、知的好奇心を持って学び続けられることが大切です。
たとえば、医療データから患者の傾向を分析し、経営改善につなげるといった業務もあるため、単なる事務仕事にとどまらないやりがいがあります。
また、データの裏にある「医療の現場の動き」を理解しようとする姿勢も求められます。医療分野に興味がある人にとって、知識と分析力の両方を活かせる魅力的な職業といえるでしょう。
③責任感が強く慎重に行動できる人
診療情報管理士の業務では、扱う情報のすべてが患者の命や医療の信頼に関わります。そのため、責任感が強く、慎重に物事を進められる人に向いています。
わずかなデータ入力ミスや病名の誤分類が、診療報酬の計算や治療方針に影響を与えることもあります。ミスを恐れて動けないのではなく、「確実に確認してから進める」姿勢が大切です。
責任を持って行動できる人ほど、現場で信頼されやすくなります。また、複数の業務を同時にこなす場面も多いため、優先順位を考えながら冷静に対応できる力も必要です。
慎重さと冷静さを兼ね備えた人こそ、診療情報管理士に最適といえるでしょう。
④他職種と円滑に連携できる人
診療情報管理士は、医師・看護師・薬剤師・事務職員など多職種と連携しながら仕事を進めます。したがって、円滑なコミュニケーションを取れる人が活躍しやすいです。
たとえば、カルテの記載内容に不明点がある場合、相手に丁寧に確認を取る必要があります。その際、専門的な内容を理解しつつ、相手を尊重した伝え方ができるかが重要です。
また、チーム医療では他者との協力が欠かせません。自分の仕事だけでなく、チーム全体の動きを意識して行動できる人は重宝されます。
人との関係を大切にし、柔軟に対応できる人こそ、信頼される診療情報管理士として成長できるでしょう。
⑤ルールや手順を守るのが得意な人
診療情報管理士の業務では、法令やガイドラインに基づいて情報を扱うため、ルールを正しく理解し、順序を守って行動できる人が向いています。
特に個人情報の取り扱いに関しては、厳密な規定が存在するため、曖昧な判断を避ける慎重さが必要です。
たとえば、カルテの閲覧やデータの持ち出しには明確なルールがあり、これを徹底することが信頼につながります。また、手順通りに作業を進めることで、ミスの防止や業務の効率化も実現できます。
マニュアルを守ることを苦にせず、正確に遂行できる人は、医療現場でも高く評価されるでしょう。ルールを守ることが、結果的に患者と組織を守ることにつながります。
⑥新しい技術に柔軟に対応できる人
医療現場では、電子カルテやAI分析ツールなど、デジタル技術が急速に進化しています。そのため、新しいシステムや技術に対して柔軟に対応できる人が求められます。
診療情報管理士は、こうしたツールを活用してデータの効率的な管理や分析を行う役割を担うため、変化を前向きに受け入れる姿勢が大切です。
また、未知のシステムに対しても、自ら学びながら使いこなす積極性があると強みになります。医療情報の世界は常に進化しており、学び続ける意欲を持つ人ほど長く活躍できるでしょう。
新しい知識を吸収し、現場で活かすことができる柔軟さこそ、これからの診療情報管理士に不可欠な資質です。
診療情報管理士の将来性

診療情報管理士は、今後ますます重要性が高まる職種です。医療データのデジタル化やAIの発展、医療制度の変化により、専門知識を持つ人材へのニーズは拡大しています。
ここでは、診療情報管理士の将来性を示す6つの観点から、その可能性を詳しく見ていきましょう。
- 医療DX・電子カルテ普及による需要拡大
- 医療データ活用の進展と新たな役割
- 少子高齢化と医療体制変化への対応
- 医療経営・品質管理での重要性の高まり
- AIやデータサイエンスとの融合による発展
- 国際標準化とグローバル人材への期待
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①医療DX・電子カルテ普及による需要拡大
近年、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、医療現場のデジタル化が急速に進んでいます。
電子カルテの導入率も年々上昇しており、データを正確に管理・活用できる人材として診療情報管理士の需要が高まっています。
電子カルテを用いた診療情報の整理や、データ入力の品質管理、システム運用の補助など、役割の幅は広がる一方です。
さらに、医療機関同士でデータ連携が進むなか、情報の標準化やセキュリティ管理に精通した人材が求められています。今後も医療DXの進展に合わせて、診療情報管理士の活躍の場は拡大していくでしょう。
②医療データ活用の進展と新たな役割
医療データの利活用が進む現代では、診療情報管理士が果たす役割がこれまで以上に重要になっています。診療情報は単なる記録ではなく、分析を通じて医療の質向上や経営改善に役立てることが可能です。
たとえば、疾病統計の作成や医療の成果分析、行政報告の作成など、データを社会全体で活かす流れが進んでいます。
その中で、データの信頼性を確保し、正確な情報を提供できる専門職が不可欠です。今後は、研究支援や医療ビッグデータの解析にも携わる機会が増え、より戦略的な視点を持つ人材として期待されます。
診療情報管理士は「医療データを社会に還元する役割」を担う存在へと進化していくでしょう。
③少子高齢化と医療体制変化への対応
日本は世界でも有数の少子高齢社会であり、医療需要は増加の一途をたどっています。その一方で、医療従事者の負担軽減や効率的な医療提供体制の構築が課題となっています。
診療情報管理士は、限られた人員でも質の高い医療を維持するために欠かせない存在です。医療データを分析して現場の課題を可視化し、経営面・運営面の改善につなげることが期待されています。
また、地域医療連携の推進や在宅医療のデータ管理など、新たな領域でも活躍の場が広がっています。
高齢化が進む社会において、医療情報の整備と活用は不可欠であり、診療情報管理士の価値は今後さらに高まるでしょう。
④医療経営・品質管理での重要性の高まり
診療情報管理士は、医療経営や品質管理の分野でも欠かせない人材になりつつあります。診療報酬の適正化や経営データの分析を通じて、病院経営の健全化に貢献できる点が評価されています。
特にDPC(診断群分類)制度や診療報酬請求に関わるデータ分析は、病院の収益構造を左右する重要な業務です。
また、医療の質を測定する指標(QI:Quality Indicator)の作成にも携わることがあり、医療安全や患者満足度の向上にも寄与しています。
経営と医療の両側面を理解できる専門職として、今後さらに組織内での存在感が増していくでしょう。データに基づく医療経営を支えるキーパーソンとしての活躍が期待されます。
⑤AIやデータサイエンスとの融合による発展
AI(人工知能)やデータサイエンスの発展により、診療情報管理士の業務は新たな段階へ進化しています。
AIによる自動コーディングや画像診断支援が進む一方で、データの品質を保証し、結果を正しく解釈できる人材の重要性が増しています。
診療情報管理士は、AIを「使う側」だけでなく「活かす側」として、データの意味づけや運用方針の決定に関わる役割を担うことが求められます。
また、データサイエンスの知識を身につければ、医療研究や経営戦略の立案にも携わることが可能です。
AI時代においても、人間による判断と倫理的な視点を持つ診療情報管理士の存在は不可欠であり、将来的にさらに発展していく分野といえるでしょう。
⑥国際標準化とグローバル人材への期待
医療データの国際的な標準化が進む中、診療情報管理士にはグローバルな視点も求められています。
ICD(国際疾病分類)やHL7などの国際規格に対応した情報管理が必要となり、海外とのデータ共有や国際比較研究にも関わる機会が増えています。
こうした流れの中で、英語でのデータ読解力や異文化コミュニケーション能力を持つ人材は貴重です。
また、海外の医療制度や情報技術を学ぶことで、日本の医療情報管理に新しい視点を取り入れることもできます。
将来的には、国際医療機関やグローバル企業で活躍する診療情報管理士も増えるでしょう。世界基準で通用するスキルを磨くことが、次世代のキャリア形成につながります。
診療情報管理士のキャリアについて詳しくなろう

診療情報管理士は、医療データの専門家として、安定した年収と将来性を兼ね備えた職種です。平均年収は勤続年数や勤務先によって差がありますが、医療業界全体で需要が高まりつつあります。
特に、電子カルテの普及や医療DXの推進により、データ分析・情報管理のスキルを持つ人材の価値は今後さらに上昇するでしょう。
実際の仕事内容は、カルテの点検やコーディング、統計資料作成など多岐にわたり、正確性と分析力が重視されます。
また、資格取得を通じて専門性を磨き、大学病院や企業などさまざまな職場で活躍できるのも魅力です。医療知識とITスキルを兼ね備えた診療情報管理士は、将来の医療を支える重要な存在といえます。
安定した収入と成長の両方を求める方にとって、非常に有望なキャリアでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














